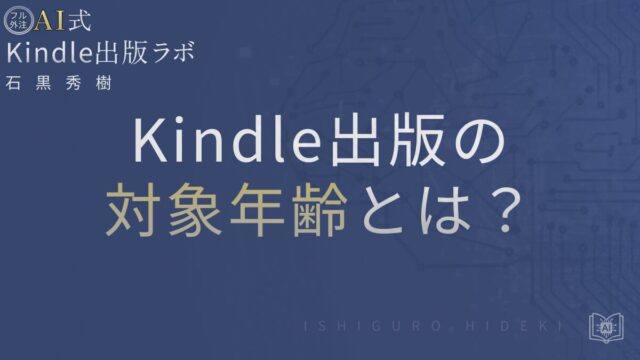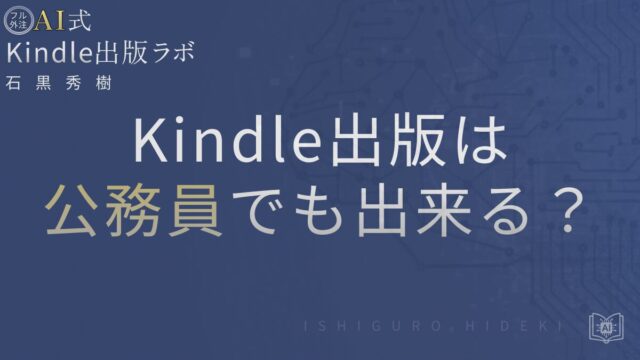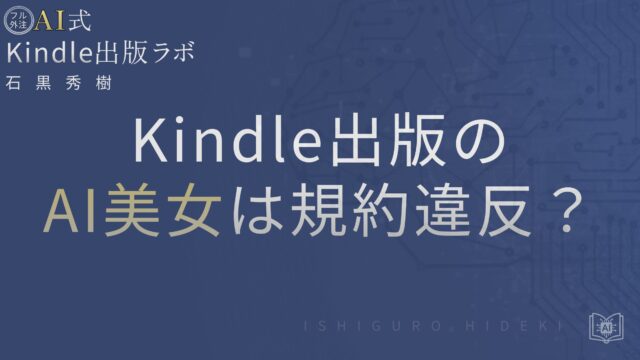KDPアカウント閉鎖・停止とは?復活手順と注意点を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を続けていると、「突然アカウントが閉鎖された」「KDPにログインできなくなった」という相談を目にすることがあります。
実際、KDP(Kindle Direct Publishing)はAmazonのシステムと直結しているため、**一度停止されると復旧が難しいケースもある**のが現実です。
ただし、焦って新しいアカウントを作るのは危険です。
まずは「閉鎖」「停止」「解約」の違いを正しく理解し、自分のケースがどこに該当するのかを整理することが、復活への第一歩になります。
この記事では、KDPアカウントが閉鎖・停止された場合の基本的な考え方と、復活できる可能性、そして最初に確認すべき重要なポイントをわかりやすく解説します。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
KDPアカウント「閉鎖・停止」と復活可否の基本を理解する
目次
KDPアカウントに関するトラブルは、「閉鎖」「停止」「解約」など、似ているようで意味が異なる言葉が多いため混乱しやすいです。
それぞれの違いと対応の方向性を理解しておくことで、復活の可否を正しく判断できるようになります。
KDPアカウント閉鎖・停止・解約の違いを整理(KDPアカウント管理の基本)
まず、「閉鎖」「停止」「解約」はKDP上では別の意味を持ちます。
「閉鎖(Termination)」は、Amazon側が規約違反や不正を理由にアカウントを完全に無効化する措置です。再開の可能性は低く、サポートへの対応次第になります。
「停止(Suspension)」は、一時的に出版や収益化機能を止めている状態を指します。多くの場合、コンテンツ修正や説明を行えば再開のチャンスがあります。
一方で「解約(Closure)」は、著者自身がKDPアカウントを閉じる操作をしたケースです。自分の意思で閉じた場合も、再開にはサポート対応が必要となります。
この3つを混同すると、対応を誤ってしまうことがあります。メール文面にどの表現が使われているかを丁寧に確認しましょう。
KDPアカウントそのものの仕組みや基本から整理したい方は、『Kindle出版のKDPアカウント作成とは?登録手順と注意点を徹底解説』もあわせて読んでおくと、今回の閉鎖・停止との違いがより理解しやすくなります。
自分の希望で閉鎖したKDPアカウントは復活できるのか(サポート案内と現実)
自分の意思で「KDPアカウントを閉鎖」した場合、**原則として自分で再開操作を行うことはできません**。
KDPのシステムでは、一度閉鎖したアカウントはデータ削除処理が始まり、内部的に復旧が難しい設計になっています。
ただし、Amazon公式ヘルプにもあるように、「誤って閉鎖した」「事情が変わった」場合は、**KDPサポートに依頼することで復活できた事例もあります**。
私自身もサポートに問い合わせた経験がありますが、英文対応を求められることもあるため、内容を簡潔にまとめ、閉鎖理由を正直に伝えることが大切です。
コンテンツ違反などでKDPアカウント停止・閉鎖になった場合の復活可能性
KDPアカウントがAmazon側によって停止・閉鎖される主な原因は、コンテンツポリシー違反や著作権侵害、過度なAI生成物の登録などです。
この場合、即時の復活は難しいものの、公式サポートへの「改善計画書」の提出で再審査を受けられるケースがあります。
改善計画書では、違反点の理解・再発防止策・今後の改善方針を具体的に説明する必要があります。
公式では詳細なフォーマットは公開されていませんが、誠実な対応を行えば、部分的に出版権限が戻る場合もあります。
ただし、**同じ違反を繰り返すと完全閉鎖になる可能性が高い**ため、内容の再確認とチェック体制の見直しが欠かせません。
「アカウント閉鎖」「解約」と書かれていた場合にまず確認すべきポイント
アカウントに関する通知を受け取ったときは、まずメールの送信元と文面を正確に確認しましょう。
Amazon公式から届く場合は「@amazon.com」または「@kdp.amazon.com」ドメインが使われています。見慣れないアドレスからの連絡は詐称メールの可能性もあります。
次に、メールに「アカウントの閉鎖」「今後のアクセス制限」といった具体的な文言が含まれているかをチェックします。
「閉鎖(termination)」と書かれている場合は、原則として再開困難です。
「停止(suspension)」なら改善対応の余地があるため、すぐにサポートへ連絡し、原因と解決策を確認しましょう。
文面が曖昧な場合は、自分で判断せず、KDP公式の問い合わせフォームから原文を添付して確認を求めるのが安全です。
KDPアカウントが停止・ブロックされた直後に確認すべきこと
KDPアカウントが突然ブロックされると、動揺してしまうのは当然です。
しかし、ここで慌てて動くと、取り返しのつかない状況になることがあります。
まず最初に行うべきことは、「何が起こったのか」を正確に把握することです。
KDPは通知を通じて理由や状況を説明してくれる場合が多く、そこに今後の対応のヒントが隠れています。
以下では、通知メールの確認方法から、原因の特定、そして絶対にやってはいけない対応までを順に解説します。
KDPからの通知メールを読む:停止理由・コンテンツガイドライン違反の確認
KDPアカウントが停止されたとき、最初にすべきことは「通知メールを落ち着いて読むこと」です。
Amazonはアカウントの状態に関する重要な情報を、登録メールアドレス宛に送信します。
このメールには「アカウント停止(Account Suspension)」「アカウント閉鎖(Account Termination)」などの表現が記載されていることがあります。
文面の中には「該当する書籍」「違反内容」「今後の対応方法」などが示されている場合もあり、内容を正確に理解することが重要です。
メールが英語で届く場合も多いため、内容を翻訳して読み解くことも必要です。
Google翻訳などで全体を訳しつつ、特に “violated our content guidelines” や “your account has been terminated” といった部分に注目しましょう。
これらの文言がある場合、ガイドライン違反が原因の可能性が高いです。
もしメールが見つからない場合は、迷惑メールフォルダも確認してください。
また、KDPアカウントにログインできる場合は「KDPヘルプ」や「お問い合わせ履歴」から同内容の通知を確認できることもあります。
「一時ブロック」「アカウント停止」「閉鎖通知」それぞれの文面の違いと意味
通知メールには複数のパターンがあり、文面によって意味が異なります。
ここを誤解すると、対応を誤って復活のチャンスを逃してしまうこともあります。
「一時ブロック(Temporary Hold)」は、一部の機能(出版や収益受け取り)が一時的に制限されている状態です。
この段階であれば、内容の修正や改善計画書の提出によって復旧するケースが多く見られます。
「アカウント停止(Account Suspension)」は、より深刻な状態です。
出版機能が全面的に止まり、過去の売上振込も保留される場合があります。
ただし、まだ完全に閉鎖ではないため、誠実な対応で再開に至った例も少なくありません。
一方、「アカウント閉鎖(Account Termination)」の文言がある場合は、状況はさらに厳しくなります。
この通知が届いた時点で、基本的にはアカウントの再開は難しいと考えた方がよいでしょう。
ただし、サポートとのやり取りの中で、誤認や改善計画の提示をきっかけに再審査が行われた事例も報告されていますが、対応方針はケースごとに異なります(公式ヘルプ要確認)。完全に諦める前に、まずはKDPサポートに事実関係を確認しましょう。
Kindle出版のどの本が原因かを特定するためのチェック手順
KDPアカウントの停止には、1冊の書籍が原因となっているケースが多いです。
そのため、どの本が対象なのかを突き止めることが復活への第一歩になります。
通知メールにタイトルが記載されていない場合でも、次の方法で確認できます。
1. KDPにログインできる場合は、管理画面の「本棚」から「ブロック中」や「非公開」などの表示を探します。
2. 最近アップロードした本、または内容を大幅に修正した本を中心に確認します。
3. KDPガイドラインに照らして、表現・メタデータ・表紙などに問題がないかを見直します。
特に、著作権の扱いや画像の出典、AI生成物の扱いは誤解されやすいポイントです。
「自分で作ったから大丈夫」と思っていても、素材サイトの規約違反が原因になることもあります。
公式のコンテンツガイドラインをもう一度確認し、曖昧な部分はKDPサポートに問い合わせるのが確実です。
焦って新規KDPアカウントを作らないほうがよい理由
アカウントが停止されると、「新しいアカウントを作れば解決するのでは?」と考える人もいます。
しかし、これは最も避けるべき対応です。
KDPの利用規約では、**同一人物が複数のアカウントを作ることは明確に禁止**されています。
強制閉鎖された後に新規アカウントを作ると、システム側で自動検知され、すぐに削除対象となることがあります。
実際、私がサポート担当者から聞いた話でも、「新規アカウントを開設したことで再開がさらに難しくなった」ケースは珍しくありません。
Amazonは登録情報、銀行口座、端末情報などを紐づけて管理しており、名義を変えてもリスクが残ります。
復活を目指すなら、必ず既存アカウントのサポート対応を優先しましょう。
再開が難しい場合も、丁寧なやり取りを重ねることで「将来的な再登録の可否」についてアドバイスをもらえることがあります。
焦らず、一つひとつの手順を正確に進めることが、遠回りのようで最も確実な道です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
KDPアカウントの復活を目指す具体的な手順
アカウント停止・ブロックが起きた場合でも、状況によっては復活できるケースがあります。
ただし、KDPは自動システムで処理される部分が多く、「誠実な対応」と「正しい手順」を踏まないと、逆に再審査のチャンスを失ってしまうこともあります。
ここでは、KDPサポートとのやり取りから改善計画書の提出まで、実務的な流れを具体的に解説します。
通知メールへの返信とKDPサポートフォームからの問い合わせ方法
まず最初に行うべきは、KDPから届いた「通知メール」への返信です。
このメールには多くの場合、「ご質問や異議がある場合はこちらに返信してください」といった案内が記載されています。
返信する際は感情的な言葉を避け、簡潔かつ礼儀正しい文面を意識しましょう。
英語メールの場合でも、翻訳ツールを使いながら誠実に対応すれば問題ありません。
返信の基本構成は「お詫び・原因の理解・改善方針」の3点です。
たとえば「誤ってガイドラインに抵触した可能性があることを理解しました。今後は再発防止に努めます」といった文面で、姿勢を示すことが大切です。
もし返信先が明示されていない場合や、メールが届かない場合は、KDP公式サイトの「お問い合わせフォーム」から直接連絡しましょう。
その際、「アカウント停止に関する問い合わせ」「既存アカウントの確認」を選び、登録メールアドレス・ASIN(書籍ID)などを添えるとスムーズです。
KDPが求める「改善計画書」とは?構成・書き方の基本
アカウント停止の原因がコンテンツポリシー違反などの場合、KDPは著者に「改善計画(Plan of Action)」の提出を求めることがあります。
この文書は、Amazonが再審査を行う際の重要な判断材料になります。
テンプレートは公式に存在しませんが、一般的には以下の3構成でまとめると効果的です。
1. **問題の認識**:どの行為・表現がガイドラインに抵触したのかを自分の言葉で説明する。
2. **原因の分析**:なぜそれが起きたのか、チェック体制や知識不足など具体的に述べる。
3. **再発防止策**:今後どのように改善するか(再チェック、外部監修、削除など)を明確に書く。
たとえば「第三者の画像を使用してしまった」「タイトルに誤解を招く表現があった」といった場合、それをどう修正し、今後どう防ぐかを具体的に書くことが重要です。
形式的な謝罪文ではなく、根拠をもった説明をすることで、再審査の信頼性が高まります。
コンテンツ修正・出版停止など、復活に向けて著者側が取るべき対応
KDPが問題視するのは「著者がガイドラインを理解しているかどうか」です。
そのため、改善計画書の提出だけでなく、実際にコンテンツを修正する姿勢を見せることも重要です。
たとえば、タイトル・表紙・本文・メタデータのいずれかに問題がある場合は、すぐに修正版を作成し、再アップロードを控えたうえで内容を確認します。
KDPの公式ガイドラインやヘルプページの「コンテンツポリシー」に沿って、該当箇所を丁寧に修正しましょう。
また、複数の書籍を同時に公開している場合は、特定の1冊だけでなく、**全書籍を対象に自己チェックを行う**ことが推奨されます。
Amazonはアカウント全体の健全性を判断するため、1冊でも違反が残ると復活が難しくなることがあります。
修正後は、「修正が完了したこと」「再発防止の取り組み」をKDPサポートに報告しましょう。
スクリーンショットや修正後の概要を添えると、審査がスムーズになることがあります。
メールの回数・タイミング・言語(日本語/英語)の実務的なコツ
問い合わせメールは、**短期間に何度も送らないことが鉄則**です。
Amazonのシステムでは、複数メールが届くと「スパム扱い」される可能性があるため、1回の送信内容を丁寧にまとめることが重要です。
一般的には、返信がない場合でも「3〜5営業日」ほどは待ちましょう。
この期間を空けても返答がない場合に、改めて状況確認のメールを1通だけ送るのが適切です。
言語については、KDPサポートの多くが英語対応です。
日本語で送っても自動翻訳で処理されますが、正確性を重視するなら、**英語+日本語の併記**が望ましいです。
たとえば、冒頭に英語で要約を書き、その下に日本語で補足する形です。
「This is a follow-up regarding my suspended account.(停止アカウントに関する確認です)」のように短い英文でも十分伝わります。
最後に、KDPとのやり取りはすべて記録しておきましょう。
メールの日時・担当者名・返信内容を保存しておくことで、万が一の再審査時にも信頼性を証明できます。
焦らず、誠実に対応を積み重ねることが、復活への最短ルートです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
自分で閉鎖・解約したKDPアカウントを再開したいとき
自分の意思でKDPアカウントを閉鎖したあと、「もう一度出版を再開したい」と思うケースは少なくありません。
ただし、KDPのシステムはAmazonアカウント全体と連動しており、一度閉鎖すると簡単に再開できる仕組みではありません。
焦らずに、まず「閉鎖」と「解約」の違い、そして再開できる可能性の有無を整理することが大切です。
そもそも自分の意思でアカウントを完全に削除したい場合の正式な流れについては、『Kindle出版のKDPアカウント削除とは?正しい手順と注意点を徹底解説』で手順と注意点を詳しく解説しています。
Kindle出版のKDPアカウント解約ルールと「元に戻せない」ケース
KDPの「アカウント閉鎖(Closure)」は、著者が自らの意思でアカウントを終了させる操作を指します。
閉鎖を行うと、登録していた書籍は販売停止・非公開となり、レポートや印税に関する情報も通常の画面からは閲覧できなくなります(具体的な保持期間や内部データの扱いは公式ヘルプ要確認)。
一度閉鎖したアカウントは、基本的に自分で再開することはできません。
これは、KDPがAmazonのシステム上で「削除済みアカウント」として管理されるためで、再開には内部の再承認が必要になるためです。
実際、閉鎖操作をしてから数日以内であれば、Amazon側にまだデータが残っていることもあります。
この場合は、KDPサポートに「誤って閉鎖した」と連絡することで復旧できた事例もあります。
しかし、閉鎖後しばらく経っている場合や、複数回の出版停止・ポリシー違反の履歴がある場合は、再開が難しくなる傾向があります。
公式ヘルプにも「アカウントを再開できない場合がある」と明記されています。
閉鎖済みKDPアカウントの再開をKDPサポートに依頼する流れ
閉鎖済みのアカウントを再開するには、KDPサポートへの依頼が唯一の方法です。
まず、KDP公式サイト([https://kdp.amazon.co.jp/)の最下部にある「お問い合わせ」リンクからフォームにアクセスします。](https://kdp.amazon.co.jp/)の最下部にある「お問い合わせ」リンクからフォームにアクセスします。)
問い合わせカテゴリでは「アカウントと登録情報」→「アカウントの閉鎖/再開について」を選択してください。
英語でのやり取りになることもありますが、最初は日本語で送って問題ありません。
メッセージ内容には、以下の項目を具体的に書くとスムーズです。
* アカウントを閉鎖した日付(おおよそでもOK)
* 閉鎖理由(例:一時的に活動を休止した、誤操作など)
* 再開したい理由(例:新しい書籍を出版したい)
* 登録時のメールアドレスと氏名
返信は通常2〜5営業日ほどで届きます。
再開可能な場合は、手順の案内が届き、本人確認や銀行口座情報の再設定を求められることがあります。
ただし、再開が認められない場合は「新しいアカウント作成を検討してください」といった案内が来る場合もあります。
その際は、同一メールアドレスや口座の扱いに注意が必要です。
同じメールアドレス・銀行口座で再登録するときの注意点
KDPでは、**原則として同一人物が複数のアカウントを持つことは禁止**されています。
そのため、閉鎖したアカウントと同じメールアドレス・口座情報を使って新規登録を行うと、システム側で自動的に関連付けられてしまう場合があります。
公式には、「閉鎖済みアカウントと同じ情報を使用する場合、事前にKDPサポートへ連絡すること」が推奨されています。
事前確認なしで登録してしまうと、「重複アカウント」としてブロック対象になる可能性があります。
安全に再登録したい場合は、まずKDPサポートに「以前のアカウントが閉鎖済みであること」を伝えたうえで、
再利用してよいか確認を取りましょう。
実際の運用上、Amazonのデータベースには過去の登録情報が長期間保存されているため、
名前や銀行口座、端末情報などで同一人物と認識されるケースが多いです。
そのため、やむを得ず新規アカウントを作成する場合は、**必ず旧アカウントの閉鎖完了を確認し、KDPサポートの承認を得てから**行うのが安全です。
この手順を踏むことで、アカウント重複によるリスクを防ぎ、安心して再スタートを切ることができます。
「新しいKDPアカウントを作ればいい」は危険?やってはいけない対応
KDPアカウントが停止されたあと、「新しいアカウントを作り直せばいいのでは」と考える人は少なくありません。
しかし、これは最もリスクの高い行動のひとつです。
Amazonのシステムはアカウント情報を非常に厳格に管理しており、再登録や複数運用は規約違反に該当する可能性があります。
結果として、すべてのアカウントが永久停止になることもあるため、安易に新規登録するのは避けましょう。
アカウント閉鎖後に無断でKDPアカウントを再登録するリスク
KDPでは、同一人物による複数アカウントの作成を禁止しています。
アカウントが閉鎖または停止された場合、別のメールアドレスを使って再登録しても、Amazon側で個人情報や銀行口座、IPアドレス、デバイスなどを照合して同一人物と判断されることがあります。
その結果、新しいアカウントも数日で停止されることが多く、再審査のチャンスすら失う恐れがあります。
一度停止・閉鎖された場合は、必ずKDPサポートに事情を説明して対応を仰ぐことが重要です。
再開の可能性が低い場合でも、将来的な再登録の可否を確認することで、無用なリスクを避けることができます。
家族名義・別人名義でのKindle出版アカウント作成が疑われるケース
「自分ではなく家族名義で登録すれば大丈夫」と考える人もいますが、これは非常に危険です。
Amazonはシステム上で名義以外にも多くの情報を紐づけており、名義だけを変えても「関連アカウント」として検出されることがあります。
たとえば、同一の銀行口座や税務情報、パソコン、インターネット回線(IPアドレス)を使ってログインした場合、それだけで本人と判断されるケースもあります。
これはKDPのセキュリティが非常に高精度であるためで、「家族だから」「別の端末だから」といった説明では通用しません。
もし誤って同じ環境からログインしてしまった場合でも、すぐにサポートに事情を伝えれば対応してもらえる可能性があります。
隠して運用するよりも、正直に説明する方が結果的に信頼回復につながります。
複数KDPアカウント運用に関する規約と、永久停止リスクへの注意喚起
KDPの規約では、同一個人による複数アカウント運用は原則認められておらず、特別な事情がある場合のみ事前の許可が必要とされています(公式ヘルプ要確認)。
これは、印税の不正受け取りや販売データの分散などを防ぐためのルールです。
複数アカウントを使って出版を続けると、一時的に運用できたとしても、Amazonの審査システムが自動検出し、ある日突然すべてのアカウントが同時に閉鎖されることがあります。
この場合、過去の印税も支払われず、データも復旧できません。
アカウント停止後にできる最善策は「再登録」ではなく「正規ルートでの問い合わせ」です。
KDPサポートに状況を丁寧に伝え、再開が難しい場合は、新規登録の可否を正式に確認しましょう。
経験上、誠実に対応する著者には「一定期間後に再申請できる」と案内されることもあります。
遠回りに見えても、このルートが最も安全で確実です。
KDPアカウント閉鎖・停止を防ぐための予防策(Kindle出版の安全運用)
KDPアカウントの閉鎖・停止は、ほとんどの場合「意図せずルールに触れていた」ことが原因です。
Amazonの審査システムは自動検出が中心で、悪意がなくても機械的に検知されることがあります。
そのため、トラブルを未然に防ぐには、KDP公式ガイドラインを理解し、日常の運用を慎重に行うことが何よりの対策です。
ここでは、実際に停止経験を持つ著者の事例も踏まえて、注意すべきポイントを整理します。
コンテンツガイドラインと禁止コンテンツ:KDP公式ルールの押さえどころ
KDP公式ガイドラインでは、禁止コンテンツや不適切な出版形式について明確に定められています。
代表的なものとして、「著作権を侵害する作品」「誤情報や誤解を招くタイトル」「他者の商標を含む書名」などがあります。
また、成人向けコンテンツに関しては特に審査が厳しく、Amazon.co.jpでは明確な区分や制限が設けられています。
たとえ創作の一部であっても、露骨な表現や読者に不快感を与える要素があると、即時削除やアカウント審査の対象となることがあります。
「表現の自由」と「販売プラットフォームの基準」は別問題です。
出版する際は、自分の創作意図だけでなく、Amazonの販売ポリシーに照らして安全かどうかを確認することが大切です。
私自身、過去にタイトルの一部に誤解を招くキーワードを含めてしまい、販売停止になったことがあります。
公式ヘルプを読み返して修正したところ、再承認まで1週間かかりました。
ほんの一語でもシステムが反応することがあるため、慎重すぎるくらいでちょうどいいです。
著作権侵害・盗用・AI生成コンテンツ利用でトラブルになりやすいパターン
著作権侵害は、KDPで最も多い停止理由のひとつです。
他サイトの文章や画像、既存書籍の一部を流用した場合はもちろん、引用の範囲を超える加工も危険です。
近年はAI生成コンテンツに関する規約も強化されています。
KDPではAIを使用すること自体は禁止されていませんが、AI生成コンテンツに関する開示方法や取り扱いは公式の最新ガイドラインに従う必要があります(公式ヘルプ要確認)。
また、他人の作品を学習したAIが作ったテキストや画像を無断利用するのも著作権侵害にあたる可能性があります。
AIを使う場合は、生成プロセスの記録を残し、必要に応じて「AI生成を一部利用」と開示しておくと安全です。
AIの出力をそのまま載せるのではなく、編集者としての自分の意図や構成を加えることで、オリジナリティを保つこともできます。
実際にKDPで出版する著者の多くは、AIを「補助的な道具」として使っており、それが最もトラブルを避けやすい運用です。
レビュー操作・ランキング操作など運用面のNG行為を避ける
KDPアカウントの停止理由として意外と多いのが、「販売促進のための不正行為」とみなされるケースです。
たとえば、自分や知人が複数アカウントからレビューを投稿する、報酬を渡してレビュー依頼をする、同一端末から繰り返し購入・閲覧を行うなどが該当します。
Amazonは不正レビューを非常に厳しく監視しており、AIによる検知も年々精度が上がっています。
「一度だけだから大丈夫」と思っても、ログやIP情報が一致すると即座に自動フラグが立つことがあります。
また、SNSでの「レビュー交換」や「互助グループ」も注意が必要です。
一見自然な交流に見えても、Amazon側から見ると「組織的レビュー操作」と判断される可能性があります。
安全にレビューを増やすには、読者との信頼を積み重ねるしかありません。
誠実に書籍の内容を改善し、読者が自発的にレビューしたくなるような品質を目指すことが、最も確実な方法です。
アカウント情報・税務情報・支払い情報の不備で停止されないためのチェックリスト
最後に意外と見落とされがちなのが、アカウント情報や税務情報の不備です。
KDPでは本人確認や税務書類が正しく登録されていない場合、印税の支払いが保留されるだけでなく、最悪アカウント停止になることもあります。
とくに、銀行口座名義の表記ミス、税務インタビュー(TIN情報)の未更新、住所の記載漏れなどは頻発するトラブルです。
登録時は細かい部分を見逃さず、定期的に「アカウント設定」ページを確認するようにしましょう。
また、法人化している場合や海外収益がある場合は、源泉徴収率や税区分が異なるため、税務インタビューの再提出が必要になることがあります。
もし変更があった場合は、速やかに再登録しておくと安心です。
アカウント情報の整合性は、KDP運用の信頼そのものです。
どんなに良い作品を出しても、登録情報に不備があるだけでアカウントが保留されることもあるため、日常的なチェックを習慣にしましょう。
実例から学ぶ:KDPアカウント停止から復活した・できなかったケース
KDPアカウントの停止・閉鎖は、著者にとって大きなダメージです。
しかし、実際には「復活できたケース」も一定数存在します。
一方で、誠実に対応しても再開が難しいケースもあります。
ここでは、実際の体験談や事例をもとに、何が分かれ道になったのかを解説します。
初回のコンテンツ違反からKDPアカウントが復活したケースの流れ
最も多い復活パターンは、「初回の違反」で、意図せずルールに触れていたケースです。
たとえば、タイトルやキーワードの設定で誤解を招く表現をしてしまった場合や、無料素材サイトの画像を使った際にライセンス表記が抜けていたなどが該当します。
このような場合、Amazonから届くメールには「コンテンツポリシー違反」や「知的財産の問題」と書かれています。
返信の際には、該当箇所の修正点を具体的に説明し、「今後同様のミスを防ぐ対策」を添えることが重要です。
実際、私が関わった著者の中でも、「すぐに修正版を提出して謝罪文を添えた」ことで、約1週間で再開された事例がありました。
KDPは「悪意ある違反」よりも、「誠実な改善姿勢」を重視する傾向があります。
ただし、Amazonの判断基準は明確に公開されていないため、同じケースでも結果が異なることはあります。
そのため、復活を急ぐよりも、丁寧で誠意ある対応を心がけましょう。
改善計画書を出してもKDPアカウント復旧が難しかったケースの共通点
一方、改善報告を出しても復旧できなかったケースには、いくつかの共通点があります。
まず挙げられるのが、過去に複数回の警告を受けていた場合です。
KDPでは警告履歴もすべて記録されており、同じような違反が繰り返されると「改善の見込みがない」と判断されやすくなります。
また、改善計画書の内容が抽象的だったり、具体的な再発防止策が書かれていない場合も審査を通過しにくいです。
単に「気をつけます」と書くだけでは、Amazon側に「根本的な理解が不足している」と見なされることがあります。
改善計画書は「何を」「どう変えたか」を具体的に書くことが鍵です。
たとえば「画像素材をすべて自作に変更」「引用箇所を明記」「第三者に事前確認してから出版」など、再発防止のための行動が明確になっていることが望まれます。
さらに、AI生成コンテンツを利用していた場合などは、「AI利用の開示」「著作権チェックの手順」を記載しておくと効果的です。
アカウント復活後に再び停止されないための再発防止策
ようやくアカウントが復活しても、気を抜くと再び停止されることがあります。
特に危険なのは、復旧後すぐに大量の新作をアップロードする行為です。
審査中は一時的にAmazonのシステムが警戒モードになっていることがあり、再検出されるリスクが高まります。
復旧直後は、まず過去の出版データをすべて見直し、ガイドライン違反がないか再確認しましょう。
そのうえで、1〜2冊ずつ慎重に公開するのがおすすめです。
また、KDPアカウントはAmazon全体のアカウントと紐づいているため、他サービス(Audible、Amazonアソシエイトなど)での違反も影響する可能性があります。
出版以外の活動も含めて、ポリシーに沿った安全な運用を意識しましょう。
「復活」はゴールではなく再スタートです。
再び信頼を積み上げていく意識が、長く安心して出版活動を続けるための最大の予防策になります。
まとめ|KDPアカウント閉鎖・復活で迷ったときの判断軸
KDPアカウントの停止は突然訪れるものですが、冷静に対応すれば道は残されています。
焦って行動するよりも、「現状を正確に把握し、次に何をすべきか」を見極めることが大切です。
ここでは、判断を誤らないための基本的な考え方を整理します。
「復活の余地があるケース」と「新しい道を考えるべきケース」の見極め方
Amazonからの通知文の内容で、おおよその方向性を判断できます。
「修正すれば再公開可能」と記載がある場合は、まだ復活の余地があります。
一方で、「重大なポリシー違反」「今後の利用はできません」といった表現がある場合は、再開の可能性は低いです。
このような場合、サポートに丁寧に事情を説明したうえで、再登録の可否を正式に確認することをおすすめします。
判断に迷うときは、他の著者の事例を調べるのも有効です。
ただし、ネット上の体験談は古い情報もあるため、必ずKDP公式ヘルプも参照しましょう。
KDPアカウントの復活が難しい場合や、別の出版ルートも検討したいと感じたときは、『自費出版と商業出版の違いとは?費用・流通・契約を初心者向けに徹底解説』を参考にしながら、次の一歩を考えてみるのもおすすめです。
Kindle出版を長く続けるために守るべき最低限のKDPルール
KDPを長く続けていくには、「知識」よりも「意識」が大切です。
特に守るべき基本ルールは次の3つです。
1. 他者の著作物を使わない(引用は出典を明記)
2. 誤情報・誇大表現を避け、正確な内容を届ける
3. アカウント情報や税務情報を常に最新に保つ
特別なテクニックよりも、誠実な運用が最大の防御策です。
KDPは一度信頼を失うと回復に時間がかかるため、日常の小さな確認を習慣化しておきましょう。
KDPアカウントを安全に守りながら収益面もしっかり押さえておきたい方は、『Kindle Unlimitedの著者収入とは?仕組みとKDPセレクトを徹底解説』もあわせて確認しておくと、運用ルールと稼ぎ方をセットでイメージしやすくなります。
不安なときに確認したい公式ヘルプ・コミュニティ・専門家への相談先
KDPの仕組みや規約は随時更新されており、自己判断で動くと誤解を招くこともあります。
不安を感じたら、まず公式サポートまたはヘルプページで最新情報を確認しましょう。
特に参考になるのは以下の3つです。
* [KDPヘルプセンター(公式)](https://kdp.amazon.co.jp/help)
* Amazon著者コミュニティ(実例や質問の共有あり)
* 出版サポート経験者・専門コンサルタント(有料相談もあり)
自分で抱え込むよりも、信頼できる情報源に早めにアクセスすることが解決への近道です。
焦らず一歩ずつ、丁寧に確認しながら進めていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。