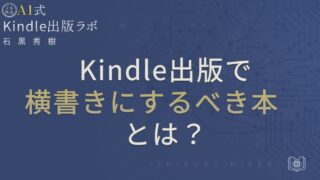Kindle出版で何を書く?初心者がテーマを決める4ステップを徹底解説
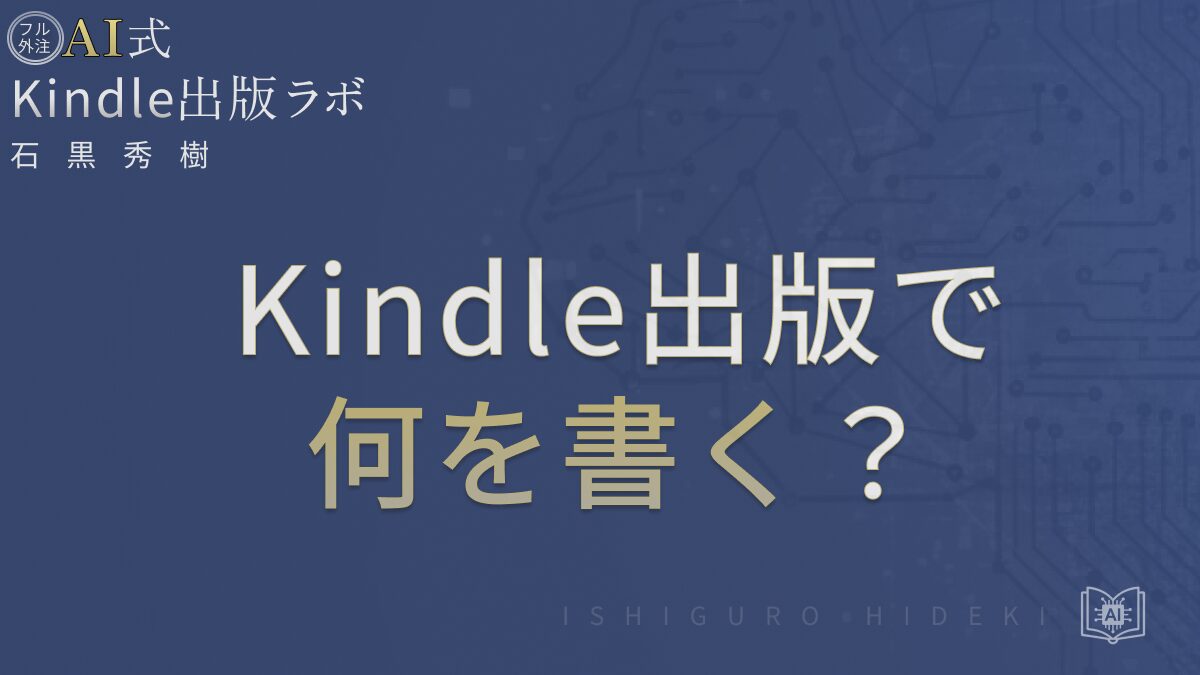
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの人が最初にぶつかる壁が「何を書くか」というテーマ選びです。
テーマが決まらないまま執筆を始めると、途中で方向性を見失ったり、最後まで書き切れないケースが非常に多いです。
この記事では、Kindle出版の成功を左右する「題材の選び方」を、初心者にもわかりやすく整理します。
単に思いつきを書くのではなく、読者に求められるテーマを見つける考え方と、電子書籍ならではのポイントを具体的に解説します。
▶ 人気ジャンルや成功事例を参考にしたい方はこちらからチェックできます:
出版ジャンル・成功事例 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「何を書くか」がKindle出版で最重要なのか
目次
Kindle出版では、内容の質やデザイン以上に「テーマ設定」が成否を分けます。
どんなに文章が上手でも、読者の求めていない内容では読まれません。
ここでは、読者視点の重要性と、よくある「自分中心」の落とし穴について解説します。
読者のニーズに応えると出版成功の確率が上がる理由
Kindle出版で売れる本の多くは、「自分が書きたいこと」よりも「読者が知りたいこと」を起点にしています。
読者は常に“悩み”や“疑問”の答えを探しています。
たとえば「副業を始めたい」「英語を勉強したい」など、行動のきっかけには明確な目的があります。
その目的を理解し、そこにあなたの経験を重ねることで、読者に刺さるテーマが見えてきます。
経験上、タイトルや内容よりも「最初の読者設定」が的確な本は、レビューの評価も安定しやすいです。
読者の悩みを解決できる構成にすることが、リピート読者を生む第一歩です。
「自分が書きたいこと」だけでは通用しない背景
多くの初心者が最初に陥るのが、「自分の好きなテーマ」をそのまま書くことです。
もちろん熱意は大切ですが、Kindle出版は「趣味日記」ではありません。
読者にとって価値がある内容でなければ、検索にもレビューにもつながりません。
たとえば、「留学体験」を書きたい場合でも、単なる思い出話ではなく、「これから留学する人に役立つ実用的な内容」に変換する必要があります。
この変換こそが、Kindle出版における企画力です。
私自身も最初の一冊で「好きなジャンル」を優先した結果、ダウンロード数が伸びずに悩みました。
後から読者アンケートを取り、「どんな内容が知りたかったか」を分析して、ようやく次の本で手応えを得られました。
つまり、“読者の目的”と“自分の経験”の交わる地点を探すことが成功の鍵なのです。
電子書籍(Kindle本)を中心に考えるべき理由
Kindle出版は、紙の本と違い、スマホやタブレットで読まれることが前提です。
そのため、内容のボリュームよりも「読後の満足感」が重要視されます。
電子書籍では、短くてもテーマが明確であれば十分に評価されます。
また、出版後に内容を修正・更新できる点も特徴です。
実際、私も出版後に読者のフィードバックを受けて、加筆・修正を行ったことでレビューが改善した経験があります。
つまり、電子書籍では「完璧に書き切る」よりも、「読者の反応を見て改善する」柔軟さが求められます。
ペーパーバック(紙の本)はページ数や印刷レイアウトなど制約が多いため、最初の一冊は電子版から始めるのが現実的です。
このように、Kindle出版では“テーマの明確さ”と“柔軟な改善姿勢”が結果につながります。
Kindle出版で「何を書くか」を決める4ステップ
Kindle出版で最初にやるべきことは、書くテーマを明確にすることです。
思いつきで書き始めると途中で迷子になり、最後まで形にならないことが多いです。
ここでは、私自身が実際にKindle本を出版する中でたどり着いた「題材を決める4ステップ」を紹介します。
“読者に届くテーマ”を見つけるための実践的な流れを意識して、順を追って進めてみてください。
ステップ1:ターゲット読者を具体化する(誰が困っているか)
まず最初に考えるべきは「誰のために書くか」です。
ここがぼんやりしていると、どんなに内容を頑張っても伝わりません。
たとえば「副業に挑戦したい20代」「仕事に悩む30代女性」など、具体的な人物像を1人思い浮かべてください。
その人がどんな状況にいて、どんな悩みを抱えているのかを想像することが大切です。
実際、私も最初の本ではターゲットを「会社員」と広く設定しすぎて、結局誰にも響かない内容になってしまいました。
次に出したときは「副業に興味はあるけど時間がない人」と具体化したところ、レビュー数が倍になりました。
読者像が明確になるほど、タイトル・導入・本文の軸がぶれなくなるので、最初に時間をかけてここを決めましょう。
ステップ2:読者が抱える困りごと・疑問を洗い出す
次に、ターゲットが「どんなことで困っているか」を書き出します。
リサーチ方法はシンプルで、AmazonやGoogleでそのテーマを検索してみることです。
レビュー欄やQ&Aには、リアルな読者の悩みが詰まっています。
また、SNSやnoteの記事コメントなども貴重な情報源です。
私も毎回このステップを丁寧に行っています。
実際に読者が使う言葉を拾うことで、タイトルや本文の表現が自然になり、検索に強くなります。
ここで重要なのは、「自分の推測」ではなく「読者の言葉」をベースにすることです。
「〜したい」「〜が不安」「〜の方法が知りたい」などの具体的なフレーズを集めておくと、構成づくりが一気に楽になります。
ステップ3:自分の経験・知識と読者ニーズを掛け合わせて題材を定義する
読者の悩みが見えてきたら、次はそれに対して「自分が何を提供できるか」を考えます。
ここが“あなたにしか書けない本”になるポイントです。
たとえば、「英語が苦手でもTOEIC700点を取れた体験」や「子育てしながら副業で月5万円を稼いだ方法」など。
特別な実績でなくても、実際に乗り越えた経験や工夫は十分価値があります。
注意点として、単なる成功談ではなく、「読者が再現できる方法」に変換することが大切です。
これは多くの初心者が見落とす部分です。
「うまくいった」ではなく、「どうやってうまくいったのか」を具体的に説明することで、信頼が生まれます。
私も以前、「失敗から学んだポイント」を正直に書いたことで、想定以上に共感の声をもらいました。
“経験を抽象化し、読者が実践できる形にする”、これがテーマ定義の肝です。
ステップ4:1冊に絞る「テーマ」「ベネフィット」「構成軸」の決定
最後のステップは、テーマを1冊分に絞ることです。
あれも書きたい、これも入れたいと思う気持ちは分かりますが、Kindle出版では「狭く深く」が基本です。
1冊で複数テーマを扱うと、読者が迷いやすくなります。
テーマを1つに決めたら、そのテーマで読者が得られる結果(ベネフィット)を一行で書き出してください。
たとえば「30代からでもブログで収益を得られるようになる」「副業を始める最初の3ステップがわかる」といった具体的な成果です。
それを軸に、「問題提起→原因→解決策→まとめ」というシンプルな構成を作ると、読者も読みやすくなります。
KDPの公式ガイドラインでは構成形式に制限はありませんが、実務上はこの流れが最も自然で評価されやすいです。
ペーパーバックにする場合は、ページ数の要件(最小24ページ)に注意しながら、電子版と同じ構成を基本にしましょう。
この4ステップを丁寧に行えば、テーマに迷う時間が激減します。
より具体的な題材の洗い出し方については、『Kindle出版のテーマ選びとは?初心者でも売れる題材の見つけ方を徹底解説』で詳しく解説しています。
実際に出版してみると、「何を書くか」より「どう伝えるか」が次の課題になるはずです。
それは、正しいテーマ選びができた証拠でもあります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
実際に使える題材探しと目次作成のコツ
テーマが決まったら、次のステップは「どう構成するか」です。
題材探しと目次設計は、Kindle出版で最も時間がかかる部分ですが、ここを丁寧に整えることで執筆が驚くほどスムーズになります。
特に、既存の発信内容を再構成して出版につなげる方法と、読者に伝わりやすい目次テンプレートの活用がポイントです。
既発信ブログ・Noteから再編集してKindle出版する方法
すでにブログやNoteなどで情報発信をしている場合、それは大きな財産です。
一から書き起こすよりも、既存の記事をもとに再編集することで短期間で出版できます。
ただし、そのままコピペするのはNGです。
ブログ等の既出記事を流用する場合は、そのままの再掲ではなく、追補・再編集・体系化で付加価値を加えてください。
品質が低い寄せ集めや公的情報の羅列は不承認の可能性があります(公式ヘルプ要確認)。
私も以前、ブログ記事をそのまままとめた原稿を提出したところ、審査で「重複コンテンツの可能性あり」と表示され、修正を求められた経験があります。
再編集のコツは、テーマを1冊の流れに合わせて再構成すること。
たとえば、5本の記事を「導入→課題→解決策→事例→まとめ」の流れに並び替えるだけでも、一気に“本”として読める形になります。
また、文体を統一することも重要です。
ブログでは口語調でもOKですが、電子書籍では読者が長時間読むため、文末の表現を整えるだけで印象が変わります。
再編集後は、実際にKindleリーダーでプレビューしてレイアウトを確認しましょう。
見出しや改行のズレは、読みやすさに直結します。
ブログと電子書籍を組み合わせる全体の流れは、『ブログ×Kindle出版の正しい活用法とは?集客と信頼を両立する再編集術を徹底解説』でステップごとに整理しています。
目次テンプレートを使って「何を書くか」を形にする
題材が定まっても、構成がぼんやりしていると書き出せません。
そこでおすすめなのが、目次テンプレートを活用する方法です。
多くのKindle著者が採用している基本構成は次のようなものです。
「第1章:現状の悩み」
「第2章:なぜその問題が起きるのか」
「第3章:解決策の全体像」
「第4章:具体的な手順・方法」
「第5章:実践後の変化・まとめ」
このテンプレートに沿って、自分のテーマを当てはめてみると、自然と全体像が見えてきます。
私自身もこの型をベースに、各章で「読者の疑問に答える質問」を意識して書いています。
「どうすればいいの?」「なぜそうなるの?」といった問いを想定すると、説明の流れが明確になります。
また、章ごとに小見出し(H3)を3〜4個入れると、電子書籍でも読み飛ばしやすくなります。
Kindleリーダーでは目次が自動生成されるため、読者が求める部分にすぐアクセスできる構成が好まれます。
公式ガイドでは特にテンプレートは指定されていませんが、実務上は「読者が検索で抱える疑問を順番に解決する構成」が最も効果的です。
具体的な章立てや目次の作り方は、『Kindle出版の構成とは?章立てと目次の作り方を徹底解説』をあわせて確認しておくと安心です。
テーマが広すぎると読み手が離れる理由とその対策
初心者が最もやりがちなのが、テーマを広げすぎることです。
「副業の始め方」と書き出しても、途中で「節約」「マインド」「マーケティング」と方向が散らかると、読者が混乱します。
読者は1冊で“具体的な1つの悩み”を解決したいと思っています。
広すぎるテーマは、結果的に「どれも浅い」と感じさせてしまうのです。
私も初期の本でこれをやってしまい、レビューに「内容が薄い」と書かれたことがあります。
その後、テーマを「時間がない会社員でもできる副業3選」に絞り直したところ、KDPレポートでは主にKENP既読ページ(Kindle Edition Normalized Pages)が確認できます。
章の絞り込みで『読まれ方』の傾向を把握しました。
対策としては、1冊で扱うテーマを1つにし、それ以外の内容は次作に回すことです。
KDPでは何冊でも出版できるため、「シリーズ化」して少しずつ展開する方が結果的に読まれやすくなります。
また、テーマを絞るとタイトルも明確になり、Amazonの検索結果でクリック率が上がる傾向があります。
最終的に、「誰が・どんな悩みを・どう解決できるか」を1行で説明できる状態が理想です。
そこまで整理できていれば、構成もブレず、読者満足度の高い本に仕上がります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
注意すべき表現と出版時のルール確認
Kindle出版では、文章や内容の自由度が高い一方で、Amazonのガイドラインに違反すると販売停止になるリスクもあります。
とくに、表現の適切さと著作権の扱いは初心者が見落としがちな部分です。
この章では、KDP(Kindle Direct Publishing)の日本向け規約に沿って、注意すべきポイントを具体的に整理します。
KDPで特に注意したいNG表現の具体例については、『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』を事前に確認しておくと安全です。
過度に刺激的・性的な内容の扱い(KDPの日本向けガイドライン)
KDPの日本向けガイドラインでは、暴力的・過度に刺激的・性的な表現を含むコンテンツには制限があります。
刺激の強い表現は審査で制限・非表示等の対応になる場合があります。
該当の可否と基準は最新の『コンテンツガイドライン(日本向け)』をご確認ください(公式ヘルプ要確認)。
この点は米国版KDPとの違いの一つで、日本では特にコンテンツ基準が厳しく運用されています。
私の周りでも、自己啓発書の中に比喩として刺激的な表現を入れた結果、「読者に不快感を与える可能性がある」として一時的に販売停止になった例があります。
つまり、表現が直接的かどうかではなく、「読者がどう受け取るか」まで考慮する必要があります。
文章中の比喩や描写に迷った場合は、Amazon公式の「コンテンツガイドライン(日本版)」を確認しましょう。
実務上、ぼかした表現や抽象的な説明に置き換えることで、多くの場合は問題を回避できます。
また、AIを用いた場合は、著作権や品質の最終責任が著者にあります。
開示や申告が必要な運用は変更される可能性があるため、提出時の入力項目と最新ヘルプを必ず確認してください(公式ヘルプ要確認)。
著作権・目次構成・リライト再構築の落とし穴
もうひとつ注意すべきなのが、他人の著作物を引用または再構成する際の扱いです。
KDPでは、著作権侵害の疑いがあるコンテンツを検出すると、自動的に「審査保留」または「販売停止」の対象となります。
特にAIリライトやまとめ記事をそのまま電子書籍化するのは非常にリスクが高いです。
公式では「著作権で保護された素材の無断使用は禁止」と明記されていますが、実務上は引用範囲や出典の明記で曖昧になる部分もあります。
私の経験では、ネット記事を参考に執筆した際、元記事と構成が似すぎて指摘を受けたことがありました。
文章を自分の言葉に置き換えるだけでなく、「独自の視点」や「体験談」を加えることが安全です。
また、目次構成を他書から参考にする場合も、丸ごと模倣するのではなく、問題提起の順序や章の粒度を変えるなどの工夫をしましょう。
審査基準は詳細非公開で、機械的チェックと人手の確認が組み合わさると考えられます。
判断基準は公開情報と実務の範囲で把握し、迷う場合はサポートへ問い合わせましょう。
そのため、公式ガイドラインを読んだうえで、最終判断は“自分が著者として責任を持てるかどうか”を基準にすると良いです。
もし不明点があれば、KDPの「コンテンツ品質チーム」への問い合わせフォームから確認できます。
まとめ:読者起点で「何を書くか」を先に決める習慣
Kindle出版を成功させる最大のコツは、常に「読者起点」で考えることです。
テーマ選びも構成も、すべては「どんな読者のどんな悩みを解決できるか」を中心に組み立てるのが基本です。
そのうえで、ガイドラインと著作権を守りながら、自分らしい視点や経験を活かすことで、安心して長く読まれる作品になります。
私自身も、最初は書くテーマに迷い、規約違反を恐れて慎重になりすぎた時期がありました。
しかし、KDP公式の情報をしっかり確認し、他の著者の事例を参考にしたことで、安心して出版できるようになりました。
Kindle出版は、正しい手順を踏めば誰でも挑戦できます。
最後にもう一度だけ強調します。
「自分が書きたいこと」より、「読者が知りたいこと」から始める。
この考え方が、出版の成功と継続のどちらにもつながります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。