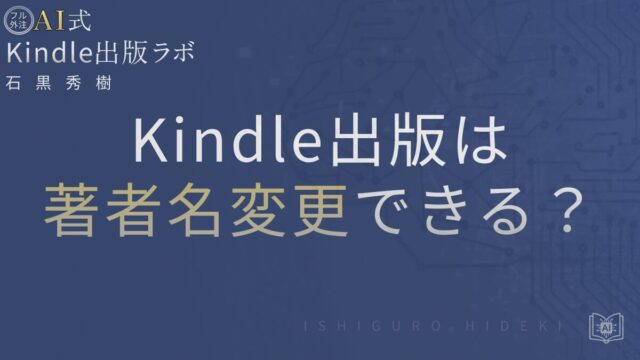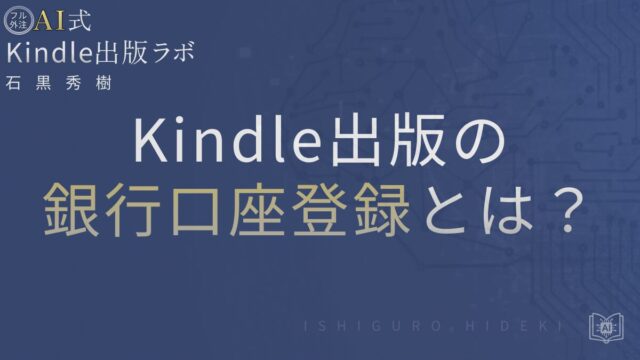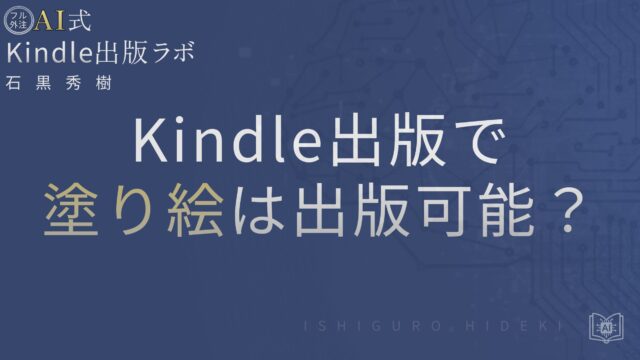Kindle出版はバレる?ペンネームで安全に副業する方法を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めたいけれど、「ペンネームで出しても本名がバレるのでは?」と不安を感じていませんか。
特に副業で活動している人や、会社・家族に知られたくない人にとっては、個人情報の扱いは大きな関心事です。
この記事では、KDP(Kindle Direct Publishing)の仕組みに基づいて、ペンネーム出版でも安全に活動できる理由と注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
私自身も最初は「本名がどこかに表示されるのでは?」と不安でしたが、実際に複数冊出版してみると、正しい知識と設定を理解しておけば問題なく運用できることが分かりました。
Kindle出版で本名がどこまで扱われるのか不安な場合は、『 Kindle出版で本名は公開される?ペンネームで匿名出版する方法を徹底解説 』も参考になります。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版はバレる?ペンネームでも安全に出版するための基礎知識
目次
Kindle出版では、著者名(ペンネーム)は自由に設定でき、基本的に読者側に本名が表示されることはありません。
ただし、Amazonのシステム上で入力する「氏名・住所・税情報」などの個人情報は、Amazon側で管理されています。これは本人確認や印税の支払いに必要な内部データであり、外部には公開されません。
この仕組みを正しく理解しておけば、「本名がバレるのでは?」という不安の多くは、実は思い込みに近いことが分かります。
「Kindle出版 バレる」と検索する人が抱える不安とは
「Kindle出版 バレる」と検索する人の多くは、次のような不安を抱えています。
・ペンネームで出版しても、どこかに本名が出るのでは?
・KDPの登録住所や口座情報が、他人に見られるのでは?
・会社や家族に副業がバレてしまうのでは?
これらはすべて、「どこまでが公開情報なのか」「Amazonがどう個人情報を扱っているのか」を知らないことが原因です。
実際には、KDPでは「販売ページに表示される情報」と「Amazon内部で保持される情報」は明確に区別されています。
読者が見られるのは著者名(ペンネーム)と書籍情報のみで、住所や本名は開示されません。
ペンネームで出版しても本名は公開されない理由
KDPで出版する際、書籍ページに表示される著者名は、出版者が自由に入力できる「表示用の名前」です。
Amazon側は本人確認のために本名・住所・税情報を登録させますが、それは**内部処理専用**であり、販売ページに紐づくわけではありません。
そのため、ペンネームを設定していれば、Amazon.co.jpの販売ページ上に本名が出ることはありません。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
・原稿ファイル(WordやPDF)に作者名を自動挿入している
・表紙デザインに本名を入れてしまっている
・奥付(書籍の最後のページ)に本名を記載している
これらは**KDPの設定ではなく、ファイル制作時のミス**によって本名が露出するパターンです。
特にWordで作成した原稿をそのまま使う場合、「プロパティ情報(作成者)」にも注意しましょう。ファイル情報に本名が残っていると、まれに検証用データとして残ることがあります。
ペンネーム出版の全体像をさらに深く知りたい方は、『 Kindle出版は匿名でも可能?ペンネーム出版の仕組みと注意点を徹底解説 』もあわせて確認すると安心です。
KDPで公開される情報と非公開情報の違い
KDPでは、読者から見える「公開情報」と、Amazonの内部だけで管理される「非公開情報」が明確に分かれています。
**公開情報(販売ページに表示される)**
・著者名(ペンネーム)
・タイトル・説明文・カテゴリ
・出版社名(設定した場合)
**非公開情報(Amazonが管理)**
・本名(アカウント登録名)
・住所・電話番号
・銀行口座・税情報
このうち、非公開情報はAmazonの審査や印税支払いのために必要なもので、一般の読者や他の著者には一切見えません。
ただし、公式ガイドライン上で「虚偽の情報登録」は禁止されています。つまり、印税の受け取りや税務処理の段階では、正しい本名・住所を登録する必要があります。
ペンネームを使う場合でも、KDPの登録情報は“本名ベース”、販売ページは“ペンネームベース”と分けて考えるのが正しい運用です。
実務上の補足として、出版後に「著者ページ(Amazon Author Central)」を設定することで、複数の本を同じペンネームでまとめることも可能です。
この設定をしておくと、読者から見たときに一貫した作家ブランドとして表示され、本名を出さずに活動を続けることができます。
Amazonはプライバシー保護の観点から、著者の個人情報を販売ページ上に出さない仕組みを採用しており、安心してペンネーム出版を行うことが可能です。
ペンネームでKindle出版する際の設定方法と注意点
Kindle出版をペンネームで行う場合、最も重要なのは「どの情報が公開され、どの情報が非公開か」を理解することです。
KDP(Kindle Direct Publishing)では、アカウント情報と出版情報が別々に扱われます。
つまり、登録者本人の本名や住所はAmazon内部で管理され、販売ページには表示されない仕組みになっています。
ただし、設定を誤ると本名がファイル内や奥付に残ってしまうケースもあるため、慎重に確認する必要があります。
ここでは、ペンネーム出版の基本設定と注意点を具体的に見ていきましょう。
KDPアカウント登録時に入力する氏名・住所の扱い
KDPアカウントを作成する際、最初に求められる「氏名」「住所」「銀行口座情報」は、Amazonが本人確認や印税の支払いに利用するものです。
この情報は販売ページや読者側には公開されません。
たとえば、Amazonの書籍ページには「著者名(Author)」としてペンネームが表示されますが、KDPアカウントで登録した本名は内部データとしてのみ扱われます。
ここで注意すべきなのは、アカウント登録名をペンネームにしてはいけないという点です。
公式ガイドラインでも「税務・支払い情報は法的な本人名義で登録すること」と定められています。
実際、税務処理や印税振込時に本人確認が行われるため、偽名や架空名義で登録するとアカウント停止のリスクがあります。
したがって、KDPアカウントは「本名で登録」、書籍ページは「ペンネームで表示」という2層構造で運用するのが正しい方法です。
また、登録住所については、Amazonから紙の通知や郵送物が届くことはほとんどありません。
ただし、税務関連でフォーム送信などが必要な場合もあるため、現住所を正確に入力しておくことが大切です。
著者名(ペンネーム)の設定手順と変更の可否
ペンネームの設定は、KDPの「本の詳細」ページで行います。
「著者名」欄に入力した名前が、Amazonの販売ページで表示される名前になります。
日本語・英語・記号を含む名前も使用できますが、商標登録された名称や他人の名義を模倣するものはガイドライン違反となるため避けましょう。
著者名は出版後でも変更できますが、反映までに数日かかる場合があります。
また、既に販売中の書籍の著者名を変更すると、新しい著者として扱われるケースもあるため、シリーズものを出す場合は最初に統一ルールを決めておくのがおすすめです。
私自身も初期に2つのペンネームを使い分けた結果、Amazon上で別の著者ページに分かれてしまい、後で統合に手間がかかりました。
ペンネームは最初に決めて一貫して使う。これが長期的なブランディングの基本です。
もし著者ページを統一したい場合は、「Amazon Author Central」で管理が可能です。
複数の本を同じペンネームで登録すれば、読者が一目であなたの他の作品も見つけやすくなります。
出版社名(レーベル)を個人で設定する場合のポイント
KDPでは「出版社名(レーベル名)」を自由に設定できます。
個人出版の場合でも、この欄に好きな名前を入力することで、自分の出版ブランドを作ることができます。
たとえば「○○Books」や「△△Publishing」などの形式が一般的です。
ただし、ここで設定した名前は販売ページに公開されるため、実在する出版社名や他者の商号に似た名称は避けましょう。
また、法人登録がなくても設定可能ですが、Amazonはこの情報を「表記上のブランド」として扱うだけで、法的な出版社として認定するわけではありません。
そのため、「出版社名=ブランディング要素」と割り切り、実際の運営は個人の責任で行うことを理解しておきましょう。
なお、出版社名を設定しなくても出版自体は可能です。
空欄のままにすると、自動的に著者名(ペンネーム)が販売ページの表示に使われます。
私の経験では、個人でシリーズ展開をする場合にのみレーベル名を付けると、統一感が出て読者の印象も良くなりました。
このように、ペンネーム出版を安全に行うためには、KDPアカウントの「本名管理」と出版情報の「表示名設定」をきちんと分けて理解することが大切です。
設定を正しく行えば、匿名性を保ちながら信頼性のある著者活動を続けることができます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
会社・家族に「バレる」ケースと対策
Kindle出版を副業として行うとき、多くの人が心配するのが「会社や家族にバレるのでは?」という点です。
実際のところ、KDPはペンネームで出版できるため、一般的な検索やAmazon上では個人情報が公開されません。
ただし、税金の処理や入金の方法によっては、思わぬ形で周囲に知られる可能性があります。
この章では、バレる典型的なケースと、それを防ぐための実務的な対策を整理していきます。
勤務先との兼ね合いが心配な方は、『 Kindle出版は副業禁止の会社でもできる?就業規則と税金の注意点を徹底解説 』で必要なポイントを押さえておきましょう。
副業としてKindle出版する際に気をつけたい税金の仕組み
Kindle出版で得た印税は、原則として「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
どちらに分類されるかは、継続性や規模によって税務署の判断が異なりますが、一般的に副業レベルであれば雑所得に該当することが多いです。
「KDPからの支払い通貨・支払主体はマーケットや受取口座により異なります。『外国所得』扱いになるかは取引実態で判断(公式ヘルプ要確認)。」
「W-8BENの提出が関係するのは、米国マーケットで売上が生じる場合の源泉軽減時です。Amazon.co.jpのみの販売では前提が異なるため、必要性は公式ヘルプ要確認。」
これはオンラインで行え、日本在住の個人であればほとんど自動的に処理されます。
ただし、確定申告の際には日本円換算した収入額を申告しなければなりません。
ここで注意したいのが、「会社員でも確定申告が必要なケースがある」という点です。
たとえば、副業収入が20万円を超えた場合は確定申告が義務になります。
少額でも、年間を通して継続的に印税が発生する場合は、帳簿や収支の記録を残しておくと安心です。
印税と確定申告の基準を詳しく知りたい場合は、『 Kindle出版の印税は確定申告が必要?20万円ルールと副業対策を徹底解説 』もチェックしてみてください。
住民税から会社にバレるのを防ぐには「普通徴収」設定
会社員の場合、最も多い「バレる」きっかけは住民税の通知です。
副業で収入があると、その分の住民税が増えます。
自治体はそれを「特別徴収(=給与から天引き)」として会社に通知するため、金額の差で副業が発覚することがあります。
これを防ぐには、確定申告の際に「住民税は自分で納付(普通徴収)」を選択するのが有効です。
申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の欄で、「自分で納付」を選べば、自治体から直接自宅に納付書が届くようになります。
ただし、「普通徴収の可否や取り扱いは自治体運用で差があります。希望しても特別徴収へ振替される場合があるため、事前確認が安全です。」
また、確定申告をe-Taxで行う場合でも、住民税の選択項目を忘れずチェックしておきましょう。
ここを見落とすと、自動的に「特別徴収」となり、会社に通知されてしまいます。
報酬受取口座の名義・入金通知など実務上の注意点
「KDPの印税は原則月次で支払われ、通貨は口座や販売国により異なります。支払時期や通貨の詳細は最新の公式ヘルプ要確認。」
日本国内の銀行を登録しておけば自動的に円換算されて入金されますが、口座名義はKDPアカウントと同一人物(本名)でなければならない点に注意が必要です。
ペンネーム名義の口座を使うことはできません。
また、家族と共有している口座に振り込まれると、通帳や入金通知で気づかれることがあります。
プライバシーを保ちたい場合は、個人専用の口座を用意するのが安心です。
副業管理用の口座を1つ作っておくと、確定申告時の収支確認もスムーズになります。
さらに、KDPから送られてくる「支払い明細メール」も意外と盲点です。
家族と共用のメールアドレスを使用していると、通知メールで出版活動が知られる可能性があります。
KDP専用のメールアドレスを作成しておくのも一つの対策です。
このように、税金・住民税・口座管理の3つを正しく理解しておくことで、「バレる」リスクは大幅に減らせます。
特に確定申告と住民税の処理を丁寧に行うことで、ペンネーム出版でも安心して活動を続けることができます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
ペーパーバック出版(紙の本)の場合に注意すべき点
電子書籍と違い、ペーパーバック出版では「実際に印刷される」という性質上、個人情報が表示されるリスクが少し高くなります。
KDPで設定を誤ると、知らないうちに本名や住所が奥付(おくづけ)部分に記載されてしまうこともあります。
紙の出版では、公開情報の扱いが電子書籍よりも厳密に確認が必要です。
ここでは、ペーパーバック特有の注意点と、匿名出版を安全に行うための設定方法を解説します。
奥付や表紙裏に個人情報が記載される可能性
ペーパーバックを出版する際、注意すべきなのが「奥付(おくづけ)」の扱いです。
奥付とは、本の最後のページなどに記載される「著者名」「出版日」「発行者」などの情報部分のことです。
日本の商業出版では法律上、責任の所在を明確にする目的でこれらの情報を明示するのが一般的ですが、KDPではそれが義務ではありません。
ただし、「紙・電子とも内頁に何を印字するかは基本的に原稿データ次第です。登録名が自動印字される仕様は通常ありません。奥付やメタデータの自記載に注意。」
特にWordファイルやPDFをそのままアップロードした際、ファイルのプロパティ情報(作成者名)に本名が残っているケースもあります。
これは意外と多い落とし穴で、「ファイル情報の中に本名が埋め込まれている」ことに気づかず出版してしまう人も少なくありません。
実際に私も初回出版時に、PDFのメタデータを確認していなかったため、作成者名が本名になっていたことに後から気づきました。
公開ページには影響しませんでしたが、印刷データとして残る可能性もあるため、事前に「プロパティ」や「ファイル情報の作成者欄」を確認・修正しておくことをおすすめします。
また、ペーパーバックでは「出版日」や「出版社名(レーベル名)」を自由に記載できます。
ここに本名や住所を入れる必要はありません。
Amazonも個人出版においては、特定商取引法の表記を求めていないため、安心してペンネームやブランド名を使用できます。
紙の出版で本名が出ないようにする設定と工夫
ペーパーバックで本名を出さずに出版するには、いくつかの設定ポイントがあります。
まず、著者名の設定は電子書籍と同様に「本の詳細」ページでペンネームを入力します。
この名前が表紙や販売ページに表示されるので、出版前に誤りがないか必ず確認しましょう。
次に重要なのが、KDPでアップロードする原稿データの確認です。
WordやPDFファイルの「ドキュメント情報」には、作成者や会社名が残っていることがあります。
この部分を「ペンネーム」または空欄に変更してからアップロードすれば、奥付に本名が表示されることを防げます。
また、表紙デザインに「著者名(ペンネーム)」を記載する際は、テンプレート内に自動で入る文字と重複しないように注意しましょう。
KDPのプレビュー機能を使えば、印刷プレビューで実際の仕上がりを確認できます。
出版ボタンを押す前に、「表紙」「奥付」「ファイル情報」すべてを自分の目でチェックするのが確実です。
さらに、KDPの「出版社名(レーベル)」設定を活用しておくのもおすすめです。
ここをブランディング名にしておくと、販売ページでも「○○Books」などの表記が使われ、本名を隠したまま出版活動を継続できます。
この方法は個人クリエイターにも広く使われています。
ペーパーバック出版は、電子書籍に比べて確認項目が多くなりますが、一度設定を理解してしまえば安心して運用できます。
出版物としての体裁を整えながらも、匿名性を保ちたい方は、事前チェックを徹底することで安全な出版が可能です。
安全にKindle出版を続けるための実践的な対策
Kindle出版を長く続けていくには、作品を出すだけでなく「安全に活動を継続できる環境づくり」も欠かせません。
特にペンネームで活動している場合、Amazon上やSNSで不用意に個人情報が結びつくと、匿名性が損なわれるリスクがあります。
ここでは、出版後の確認作業やSNS運用で気をつけたいポイントを整理し、最後にKDPの規約上の注意点についても触れます。
著者ページ(Amazon Author Central)での表示確認
書籍を出版したら、まず確認しておきたいのがAmazonの著者ページです。
KDPで出版すると、自動的に著者名(ペンネーム)ごとにページが生成されることがあります。
このページにはプロフィール文や著書一覧が表示されるため、意図しない情報が公開されていないかチェックすることが重要です。
Author Centralにログインすれば、自分の著者ページを編集できます。
ここで入力できるのは「著者紹介文」「写真」「SNSリンク」などですが、個人情報に直結する内容は避けましょう。
特に、SNSリンクを掲載する場合は、ペンネーム用アカウントを利用することをおすすめします。
また、複数のペンネームを使っている場合は、著者ページが分かれてしまうことがあります。
この場合、KDPサポートに依頼すれば同一アカウント内のページを統合できるケースもあります。
ただし、作品のジャンルが大きく異なる場合(たとえばビジネス書と詩集など)は、あえて分けたほうがブランド管理しやすいこともあります。
出版後に個人情報を特定されないためのSNS運用の工夫
出版をきっかけにSNSを活用する人も多いですが、匿名で活動する場合は「日常投稿の積み重ね」が特定につながることがあります。
たとえば、勤務地や居住地、家族構成、日常の写真などを投稿していると、ペンネームと現実の自分が結びつくリスクが高まります。
対策としては、次の3点を意識するだけでも安全性がぐっと高まります。
1つ目は、出版専用アカウントを作ること。
仕事や私生活の投稿と切り分けることで、情報の混線を防げます。
2つ目は、SNS名・アイコン・ヘッダー画像などを一貫した世界観で統一することです。
ペンネームの印象を確立でき、信頼性も高まります。
3つ目は、DM(ダイレクトメッセージ)やコメント欄でのやり取りに注意することです。
Amazonの著者名とSNS名が一致している場合、やり取り内容から個人情報が推測されるケースもあります。
特に、初期の読者や同業者との交流では、距離感を保ちながら発信しましょう。
KDPガイドラインで禁止されている行為と注意点(公式ヘルプ要確認)
KDPでは、著者の安全を守るためにもさまざまなガイドラインが定められています。
中でも注意すべきなのが、「誤解を招く著者情報」「他人の作品の転載」「レビュー操作」に関する禁止事項です。
たとえば、実在の著者名や有名人名に似せたペンネームを使うのは、商標や肖像の問題につながるおそれがあります。
また、他者のレビューに報酬を提供したり、自作自演のレビューを投稿したりする行為も規約違反です。
これらが発覚すると、アカウント停止や出版停止の対象となることがあります。
さらに、KDPはAI生成コンテンツに関しても一定のガイドラインを設けています。
AIを使って生成した文章や画像を使用する場合は、著作権や出典の扱いに注意が必要です。
公式ヘルプページには最新の規約が記載されているため、出版前に必ず確認しておきましょう。
安全に出版を続けるためには、「公開情報の管理」と「ルールの理解」が不可欠です。
特にペンネーム出版では、自分の情報を守る意識がそのまま信用につながります。
まとめ:ペンネーム出版はリスクを理解すれば安全に続けられる
ペンネームでのKindle出版は、基本設定と税務・情報管理を正しく行えば、十分に安全に続けられます。
匿名でありながらも、誠実な発信や作品づくりを心がけることで、読者からの信頼も自然と育っていきます。
重要なのは、「誰にも知られないように隠す」ことではなく、「安心して活動を続けられる形を自分で設計する」ことです。
アカウント情報・SNS運用・ガイドラインの理解をバランスよく保つことで、ペンネーム出版は長期的に安定した活動へとつながります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。