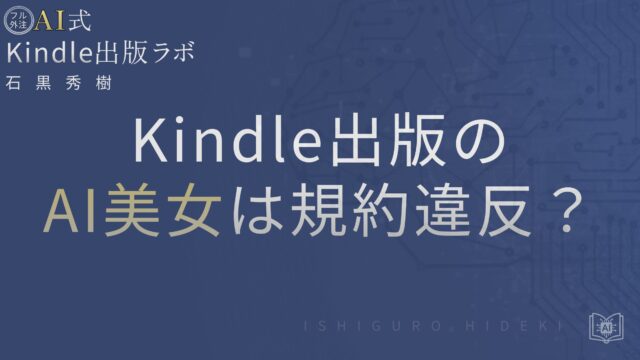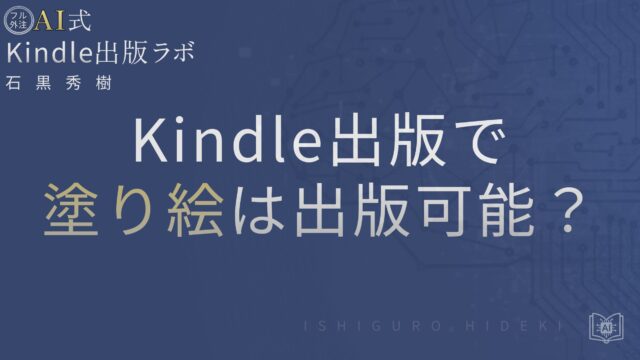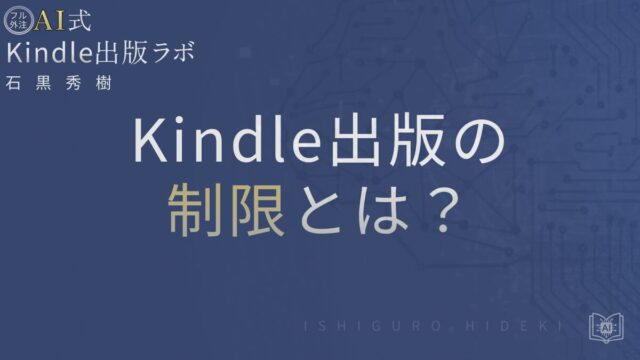Kindle出版のブロックとは?原因と解除手順を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を進めていると、「ブロック」「配信停止」「審査保留」といった言葉を目にして戸惑う方も多いのではないでしょうか。
突然メールで通知が届くと、「アカウントが停止されたのでは?」と不安になりますが、実際は段階的な処理であり、すぐに出版停止やアカウント削除になるわけではありません。
この記事では、Kindle出版における「ブロック通知」の意味と、確認すべきポイントを初心者にもわかりやすく解説します。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の「ブロック」とは?通知の意味と範囲【Amazon.co.jp前提】
目次
- 1 Kindle出版の「ブロック」とは?通知の意味と範囲【Amazon.co.jp前提】
- 1.1 ブロック・配信停止・審査保留の違い(用語整理)
- 1.2 通知メール(ダッシュボード警告)の読み方:確認すべき3点
- 1.3 メタデータ不一致:タイトル・キーワード・カテゴリの整合性
- 1.4 著作権・引用・画像素材の権利証跡不足(出典と許諾)
- 1.5 表紙・本文の内容差/過度な宣伝・誘導表現の扱い
- 1.6 フォーマット不備:可読性・レイアウト・プレビュー未確認
- 1.7 修正前のバックアップと差分メモ作成(エビデンス化)
- 1.8 本文・表紙・説明文の再点検チェックリスト(Kindle出版 ブロック 解除)
- 1.9 Kindle Previewer確認と再提出のポイント(公式ヘルプ要確認)
- 1.10 初回出版でブロックされた場合の進め方(Kindle出版 審査)
- 1.11 複数回ブロック時の影響と連絡方法(アカウント方針は要確認)
- 1.12 ペーパーバックの審査留保と奥付表記の注意点(補足)
- 1.13 出版前チェックリストのテンプレ(メタデータ/権利/プレビュー)
- 1.14 権利証跡の保管方法と再審査時の説明テンプレ
- 1.15 AI生成物の開示方針と表現の抽象化(公式ヘルプ要確認)
- 2 まとめ:原因特定→適正化→再提出で再発を防ぐ
KDP(Kindle Direct Publishing)での「ブロック」とは、Amazonのシステムまたは審査チームが出版物に問題を検知した際に、**一時的に配信や販売を停止する措置**のことです。
原因はさまざまですが、主にコンテンツ内容・メタデータ・著作権関連など、AmazonのポリシーやKDPガイドラインに抵触した場合に発生します。
ブロックは「罰」ではなく、修正・再提出の機会を与えるための措置です。
実際、筆者の経験でも、表紙画像の解像度不足やカテゴリ設定の不一致など、軽微な理由で一時的に配信停止となったケースがありました。
修正後の再申請で数日以内に復旧することも珍しくありません。
つまり、通知を受け取った時点で慌てず、内容を冷静に確認することが第一歩です。
そのためにも、まず「ブロック」と「配信停止」「審査保留」の違いを正しく理解しておくことが大切です。
ブロックや配信停止の意味を押さえたうえで、審査全体の流れも整理しておきたい場合は『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』もあわせて読んでおくと状況を把握しやすくなります。
ブロック・配信停止・審査保留の違い(用語整理)
これら3つの用語は似ていますが、意味が異なります。
* **ブロック(Block)**:販売や公開が一時的に停止。内容修正後に再申請可能。
* **「配信停止(Unpublish)は通常、著者側の操作で公開を取り下げた状態を指します。ポリシー違反等でAmazon側が販売を止める場合は『販売停止/抑止』など別扱いになることがあります(用語は公式表記を優先)。」
* **審査保留(Under Review)**:新規または再提出時に、Amazonチームが内容確認中の状態。
特に注意したいのは、「ブロック」と「配信停止」の違いです。
前者は再提出で回復できる一時的措置、後者は販売自体を取り下げた状態を指します。
筆者の体感としても、ブロック通知は一種の「警告段階」であり、再提出が受理されれば通常通り販売が再開されます。
反対に、ガイドライン違反を放置したまま放置すると、アカウント全体に影響が及ぶリスクもあります。
通知メール(ダッシュボード警告)の読み方:確認すべき3点
「KDPからの連絡は登録メールに届きます。品質関連はダッシュボードの品質通知や該当タイトルに表示される警告でも確認できます(公式ヘルプ要確認)。」内容を理解せずに削除してしまうと、対応が遅れる原因になります。
確認すべき主な3点は以下の通りです。
1. **対象タイトル**:どの書籍がブロックされたのか。シリーズ展開している場合は特に要確認。
2. **理由(Reason)**:ガイドライン違反・フォーマット不備・メタデータ不一致など、通知文内に英語で簡潔に記載されます。
3. **対応方法**:修正指示や再提出手順が具体的に書かれていることもあります。
たとえば、「Metadata mismatch」と記載されていれば、タイトル・サブタイトル・説明文・表紙の整合性をチェックしましょう。
また、「Offensive content detected」のような文言がある場合は、表現の修正が求められている可能性があります(※具体的な表現内容は控えます)。
通知メールは必ず保管し、対応履歴をメモしておくことが重要です。
Amazonサポートに問い合わせる際も、このメール内容があるとやり取りがスムーズになります。
また、まれに「自動翻訳では意味が取りにくい」通知文もあります。
その場合は、KDP公式ヘルプの該当項目を確認するか、英語原文をそのままサポート窓口に引用して問い合わせるとよいでしょう。
ブロック通知は怖いものではありません。
「何が問題だったのか」を読み取り、修正して再提出すれば、ほとんどの場合は復旧が可能です。
Kindle出版でブロックされる原因の多くは、明確な「違反」ではなく、“Amazon側の審査基準に合致していない”だけのケースです。
特に初めて出版する場合、KDPガイドラインの細かな表現ルールやデータ設定の整合性に気づきにくく、知らないうちに引っかかることがあります。
ここでは、実際の出版現場でもよく見られるブロック要因と、その一次判断のポイントを整理していきます。
メタデータ不一致:タイトル・キーワード・カテゴリの整合性
ブロックの最も多い原因が、**メタデータ不一致**です。
メタデータとは、タイトル・サブタイトル・シリーズ名・著者名・キーワード・説明文・カテゴリなど、本の「登録情報」を指します。
これらが表紙や本文と一致していない場合、KDPの自動審査によりブロックや審査保留となることがあります。
たとえば、表紙では「〇〇完全ガイド」となっているのに、タイトル欄では「〇〇入門」として登録していると、内容不一致と判断されやすいです。
また、キーワードに過剰な宣伝語(例:「最強」「稼げる」「公式」など)を含めると、検索スパム扱いになる可能性もあります。
タイトル・表紙・説明文は“ワンセット”で整合性を取ること。
これが、ブロックを防ぐうえでの第一歩です。
カテゴリ選定についても、内容と関連性の低いものを設定すると「誤分類」と見なされる場合があります。
メタデータ不一致だけでなく、そもそものNG行為を押さえておきたい方は『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』で全体のルールを一度整理しておくと安心です。
特にランキング目的で人気カテゴリに登録する行為は避けましょう。
著作権・引用・画像素材の権利証跡不足(出典と許諾)
次に多いのが、著作権関連の問題です。
KDPでは、使用素材の出典やライセンス証明が不十分な場合、ブロック対象となることがあります。
たとえば、フリー素材サイトから画像をダウンロードした場合でも、**商用利用可能か/クレジット表記が必要か**を確認していないとNGになることがあります。
引用についても、「出典を明示しているからOK」と思われがちですが、引用量や目的によっては著作権侵害と判断されることがあります。
他作品の文章や画像を扱うことが多い場合は、出版前に『Kindle出版の引用ルールとは?著作権とKDP審査を徹底解説』で権利まわりの基本を押さえておくとブロックリスクを下げられます。
筆者の経験では、引用ルールを守っていても、AI自動検出の段階で誤検知されるケースが稀にあります。
その際は、Amazonからの通知メールに対して、出典元やライセンスURLを添えて再説明すれば解除されることが多いです。
素材の出典・利用許可・ライセンスURLは、出版前に必ずメモして保管しておくこと。
再審査の際に提出できる「証跡」があるだけで、対応スピードが格段に上がります。
表紙・本文の内容差/過度な宣伝・誘導表現の扱い
KDPでは、「表紙と本文の内容が一致していない」場合もブロックの対象になります。
たとえば、表紙に「完全攻略」と書いてあるのに、本文では一部しか解説していない場合などです。
また、「外部サイトへの過度な誘導や購入体験を損なう誘導は制限・拒否の対象になることがあります。必要な参照は宣伝色を抑え、説明文や本文での過度な誘導は避けましょう(公式ヘルプ要確認)。」
実際に出版経験者の間でも、「本文に自己紹介ページでSNSを載せたらブロックされた」という声は少なくありません。
Amazonとしては、購入者を外部へ誘導する行為を「販売目的の逸脱」とみなすためです。
自己紹介や活動紹介はOKですが、外部へのリンクや明確な誘導は避けること。
もし外部リソースを紹介したい場合は、「参考資料として検索できる名称のみ記載」するのが安全です。
フォーマット不備:可読性・レイアウト・プレビュー未確認
最後に見落としがちな原因が、**フォーマット不備**です。
改行やインデントが乱れていたり、画像サイズが極端に小さい・大きいなど、読者の閲覧体験を損なう状態のまま出版すると、品質面でブロック対象になることがあります。
KDPでは、本文データのチェックに「Kindle Previewer(無料ツール)」を利用できます。
これを使わずに公開してしまうと、スマホやタブレットで崩れたまま販売ページに並んでしまうことも。
また、目次リンクが機能していない、余白が不均一といった軽微な問題も「再提出対象」とされることがあります。
筆者も最初の出版時、改行位置がずれて再提出になった経験があります。
ほんの数行のずれでも、読者からクレームが入る可能性を考慮して、KDP側が慎重にチェックしているのです。
出版前には必ずKindle Previewerで全デバイス表示を確認する。
「読みにくい」と判断されない限り、ブロックされることはほぼありません。
このように、ブロックの原因はほとんどが「知っていれば防げるもの」です。
ひとつずつ丁寧に確認していけば、KDPの審査は決して怖いものではありません。
ブロック通知を受けたあとに重要なのは、焦らず順を追って対応することです。
KDPでは、一度ブロックされた書籍でも、内容を修正して再提出すれば再公開されるケースが多くあります。
ここでは、「解除」までの流れを3段階に整理し、具体的な手順と注意点を解説します。
修正前のバックアップと差分メモ作成(エビデンス化)
まず最初に行うべきは、「現状のバックアップ」と「修正点の整理」です。
KDPに再提出すると、前回のデータが上書きされるため、**修正前の状態を必ず保存**しておきましょう。
Wordやテキストエディタの場合は、日付を含めた別名で保存しておくのが安心です。
また、通知メールで指摘された箇所が明確な場合は、その部分を抜粋してメモに残しておきます。
どの章・どの画像・どの文言を修正したかが分かるように、「修正前/修正後」を対比して整理しておくと、次回以降のトラブル防止にも役立ちます。
筆者の経験では、ブロックが解除されたあとに再審査対象となるケースでも、この差分メモを見返すことで原因の再発を防げました。
修正前データは「保険」、差分メモは「次への指針」。
KDP運営側からの問い合わせに対応する際も、どのように修正したかを説明できるようにしておくと信頼度が高まります。
本文・表紙・説明文の再点検チェックリスト(Kindle出版 ブロック 解除)
修正を行う際は、まず以下の観点で「3点セット」を見直してください。
1. **本文**:
・表現に誤解を招く表現や過度な誇張がないか。
・引用や画像素材に出典・権利表記があるか。
・章立てや目次のリンクが正しく動作しているか。
2. **表紙**:
・タイトル・著者名・シリーズ名がKDP登録情報と一致しているか。
・推奨解像度(2560×1600px以上)を満たしているか。
・過激・誤認・商標を含むデザインになっていないか。
3. **商品説明(メタデータ)**:
・タイトル・サブタイトル・著者名が表紙と完全一致しているか。
・説明文に外部リンクや販売誘導表現が含まれていないか。
・キーワードに誇張的・過剰なワードが含まれていないか。
「公式ではOK」と書かれていても、審査AIが誤検知することがあります。
そのため、「ギリギリ大丈夫」ではなく「誰が見ても安全」と判断できる状態を目指すことがポイントです。
再点検の段階で第三者に読んでもらうのも有効です。客観的な視点で確認することで、見落としを減らせます。
Kindle Previewer確認と再提出のポイント(公式ヘルプ要確認)
修正を終えたら、最後に**Kindle Previewer**でプレビュー確認を行いましょう。
KDPの審査では、読者視点での可読性やデザイン崩れもチェック対象です。
特に、スマートフォン表示で行間や画像が崩れていないかを確認してください。
Kindle Previewerでは、「Fire端末」「Kindleアプリ」「タブレット」など複数の端末表示を再現できます。
プレビューをすべて確認してから「再提出」ボタンを押すのが基本です。
また、再提出の際は、KDPの入力欄で**「更新内容」**を簡潔に記載するとスムーズです(例:「タイトル・本文表現修正」など)。
再提出=再審査です。
内容が完全に修正されていれば、数時間〜数日で配信が再開されるケースが多いです。
ただし、違反度が高い場合や繰り返し修正が必要な場合は、審査に数日〜1週間かかることもあります。
その場合は、KDPサポートに英語で簡潔に問い合わせると早期対応につながる場合があります。
解除までのプロセスは時間がかかることもありますが、手順を踏めば必ず改善できます。
焦らず、一つひとつ確認しながら進めることが再発防止にもつながります。
ブロックが発生したときの対応は、状況によって異なります。
初回の出版でのブロックと、複数回の再発ではAmazon側の対応も変わるため、それぞれに合った進め方を知っておくことが大切です。
ここでは、経験者の視点から「実際にどう行動すれば解除に近づくか」を整理し、最後にペーパーバック特有の注意点にも触れます。
初回出版でブロックされた場合の進め方(Kindle出版 審査)
初めての出版でブロック通知が届いた場合、多くは「設定や整合性のミス」が原因です。
タイトル・表紙・説明文の不一致や、キーワードの誇張表現などが代表的です。
焦って削除・再登録を繰り返すよりも、まずは**通知メールの内容を丁寧に確認**することから始めましょう。
メールの英語文には、ブロック理由のキーワード(例:”Metadata mismatch”、”Content guideline”など)が含まれています。
意味が分かりにくい場合は、KDP公式ヘルプの該当項目で翻訳内容を確認しましょう。
多くのケースでは、問題箇所を修正して再提出するだけで解除されます。
筆者の体感でも、**初回出版のブロックは「警告」的な意味合いが強く、再提出で復旧することがほとんど**です。
ただし、修正後も同じファイルをそのまま再提出するのは避けましょう。
内部データに古い設定が残っていると、再びブロックされることがあります。
WordやEPUBの本文データを再保存し直してからアップロードするのが確実です。
初回は「学びのタイミング」と捉え、慌てず再提出。
一度審査を通す経験が、次回以降の出版をスムーズにします。
複数回ブロック時の影響と連絡方法(アカウント方針は要確認)
ブロックが複数回発生した場合、KDPアカウント全体の信頼性に影響する可能性があります。
特に、同じ原因で繰り返しブロックされると、システム上「再審査対象アカウント」として監視対象になることがあります。
このようなときは、Amazon側からの自動メールだけでなく、**サポートフォームから直接連絡する**のが効果的です。
KDPダッシュボード右上の「ヘルプ」→「お問い合わせ」→「書籍の審査・配信に関する問題」からアクセスし、状況を英語で簡潔に伝えましょう。
(例)
“Hello, I received a block notice multiple times. I have fixed the issue and would like to confirm if there are any remaining problems.”
強調しておきたいのは、**問い合わせの目的を「抗議」ではなく「確認依頼」として伝えること**です。
Amazonはユーザーの態度も評価の一部として見ています。
筆者の経験でも、丁寧な英語での問い合わせは返信率が高く、数日で解除されたケースが多くあります。
同じ原因を繰り返さないことが最大の防御策。
再発時は、第三者チェック(他の出版者や校正者)を入れると効果的です。
ペーパーバックの審査留保と奥付表記の注意点(補足)
「ペーパーバックではKDPが自動で本名や住所を奥付に挿入するわけではありません。奥付は内製データの記載次第です。著者名やレーベル名の表記はプレビューで必ず確認し、不要な個人情報を自分で入れないようにしましょう。」
KDP日本版では、電子書籍のように完全匿名で出版できますが、ペーパーバックの場合は印刷物としての法的要件を満たすため、**奥付欄に「発行者名(著者名)」が明記**されます。
この部分にペンネームを使用したい場合は、著者名をKDP上の「出版者名」として登録することで対応できます。
ただし、出版国や流通経路によってはAmazon側が自動で「Publisher」欄を生成する場合があり、完全には制御できないこともあります。
そのため、ペーパーバックの奥付情報は必ずプレビューで確認し、問題があればKDPサポートに修正依頼を出しましょう。
また、紙の本ではページ数や印刷品質の基準もあるため、審査時間が電子書籍より長くなる傾向があります。
再提出の際は、2〜5営業日程度の余裕を見ておくと安心です。
ペーパーバックはデザイン性や信頼感を高めやすい一方で、データ整合や表示名の扱いに注意が必要です。
初回は電子書籍で経験を積んでから、紙版へ展開するのが現実的な流れです。
ブロックを避けるためには、「出版後に直す」よりも「出版前に防ぐ」意識が大切です。
特に、KDPでは審査が自動化されているため、形式面の不備やメタデータの食い違いでもブロック対象になることがあります。
ここでは、出版前に確認すべきチェック項目と、運用面での再発防止策をまとめます。
出版前チェックリストのテンプレ(メタデータ/権利/プレビュー)
出版前の最終チェックは、**3つの柱**で整理すると漏れが少なくなります。
1. **メタデータの整合性**
・タイトル、サブタイトル、著者名、シリーズ名が本文・表紙と一致しているか。
・キーワードが誤解を招く表現(例:「公式」「非公開」など)を含んでいないか。
・カテゴリ設定が書籍内容と整合しているか(フィクション/ノンフィクションの混在に注意)。
2. **権利・引用の確認**
・引用部分に出典を明記しているか。
・フリー素材の画像やフォントを使用している場合、商用利用可の明記があるか。
・外部作品に依存しすぎていないか(“解説書”形式でも原作引用量が多いと審査対象)。
3. **プレビュー確認**
・Kindle PreviewerまたはKDPオンラインプレビューでレイアウト崩れがないか。
・見出しや目次リンクが正常に動作するか。
・文字化けや余白のズレがないか。
この3点をテンプレート化して出版前にチェックするだけで、ブロックリスクを7〜8割減らせる印象があります。
筆者も最初のうちは「とりあえず出してみよう」で公開してブロックを受けた経験がありますが、上記をルール化してからは再審査にかかることがなくなりました。
権利証跡の保管方法と再審査時の説明テンプレ
素材や文章に関する**権利証跡(エビデンス)**を残しておくことは、再審査時に非常に重要です。
Amazonから「証明を求められる」ケースは稀ですが、特に画像・音楽・引用を扱う書籍では対応が求められることがあります。
保管方法としては以下が実用的です。
* 使用した素材サイトのURLと利用規約のスクリーンショット
* 自作の場合は制作日とファイル名を含めた保存フォルダ
* AI生成の場合はプロンプト履歴の保存
再審査依頼時は、次のような簡潔な説明を添えると伝わりやすいです。
(例)
“This image was created by myself using original illustration software. No third-party materials were used.”
または
“This photo was obtained from [素材サイト名], which allows commercial use.”
英語での説明が推奨されますが、翻訳ツールでシンプルにしても問題ありません。
「証拠を持っている」という事実自体が、アカウントの信頼度につながります。
AI生成物の開示方針と表現の抽象化(公式ヘルプ要確認)
AIツールを使って制作した文章・画像を含む場合は、**「AI生成コンテンツ」である旨を開示する**ことが推奨されています。
「AI生成物の取り扱いは透明性の観点から注意喚起が続いています。開示方法や申告の要否は変更され得るため、最新の公式ヘルプで必ず確認してください(公式ヘルプ要確認)。」
たとえば、ChatGPTや画像生成ツールを使用した場合は、著作権に抵触しないことを確認したうえで、本文や紹介文で「AIサポートを活用しています」と明記しておくと安心です。
ただし、単にツールで構成を補助した程度であれば、明記義務まではありません。
一方で、AI生成文章をそのまま掲載する場合は、**人間による編集・監修を経ていることを明示**しておくのが理想です。
表現が直接的すぎるとガイドライン抵触の可能性があるため、内容は「抽象的な説明」にとどめておくと良いでしょう。
(例)
「AIツールの提案をもとに、著者自身の言葉で編集しています。」
AIは便利な一方で、生成元不明な素材や著作権侵害リスクもあります。
そのため、「使用経緯の記録」+「人の手による最終確認」を習慣にしておくことがブロック回避の鍵です。
まとめ:原因特定→適正化→再提出で再発を防ぐ
KDPのブロック対応で大切なのは、感情的にならずに「原因→修正→再提出」を冷静に進めることです。
どんなブロックにも理由があります。
メタデータの整合性、著作権、内容の誤認防止、この3つを中心に点検すれば、ほとんどのケースは改善可能です。
実際、筆者がサポートしてきたケースの多くも、原因を突き止めて適切に修正するだけで再公開されています。
ブロックは「失敗」ではなく、「出版品質を整えるチャンス」です。
焦らず、ひとつずつ手順を踏むことで、アカウントの信頼性を高め、今後の出版活動を安定させることができます。
KDP側がどのような観点でコンテンツをチェックしているかを知りたい場合は『KDPのコンテンツガイドライン違反とは?審査落ちを防ぐチェックポイントを徹底解説』を確認し、この記事のチェックリストとあわせて運用ルールに落とし込むのがおすすめです。
最後に、疑問点が残る場合は必ずKDP公式ヘルプで最新情報を確認しましょう。
規約や審査方針は定期的に更新されるため、「以前は通った」ではなく「今どうか」を見る姿勢が重要です。
出版は継続の積み重ねです。
1冊ずつ改善を重ねることで、確実にブロックのない安定した出版運用ができるようになります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。