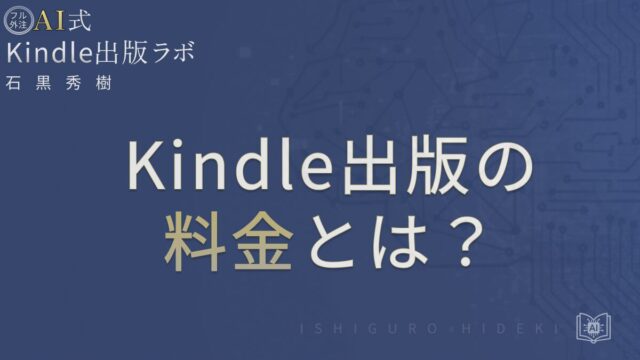Kindle出版の収益はどう決まる?印税と既読の仕組みを徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で本当に収益は出るのか。
まず一番気になるのは、ここだと思います。
私自身、初めてKDPの管理画面を開いたときは、印税率や既読カウントの仕組みがわからず、数字が合わないように感じてモヤモヤした経験があります。
その後、公式ヘルプと実際のレポートを照らし合わせながら出版を続ける中で、「意外とシンプルで、正しく積み上げれば成果は出る」という結論に至りました。
この記事では、初心者の方がつまずきやすいポイントを避けつつ、**収益の仕組みをやさしく整理**しています。
曖昧なまま進めると、価格設定やKDPセレクトの選択で迷いやすくなるため、最初に道筋を理解しておきましょう。
▶ 印税収入を伸ばしたい・収益化の仕組みを作りたい方はこちらからチェックできます:
印税・収益化 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で収益は本当に出る?結論と仕組みを初心者向けに解説
目次
Kindle出版で収益が出るかどうかは、多くの方が最初に抱く疑問です。
結論から言うと、**仕組みを理解し、継続して改善すれば収益化は可能**です。
「出せば勝手に稼げる」という世界ではありませんが、仕組みが比較的わかりやすく、改善の余地も多い分野です。
私は最初の3冊でようやくレポートの数字が安定し始め、「こういう動きなんだな」と掴めました。
最初は不安でも、理解が進むほど自分のコントロール感が増していきます。
Kindle出版そのものの流れや基本構造を一度整理しておきたい方は、『Kindle出版とは?初心者が無料で始める電子書籍の基本と仕組みを徹底解説』もあわせて読んでおくと、全体像がつかみやすくなります。
Kindle出版の収益源は「印税+既読」の2本柱
Kindle出版の収益は、大きく分けて以下の2つです。
1. 電子書籍の販売による印税
2. Kindle Unlimitedで読まれた分(既読)
まず、販売印税は**70%または35%**のどちらかです。
日本向けの場合、70%の適用には価格帯などの条件があります(最新条件は必ず公式ヘルプを確認してください)。
次に、KDPセレクトに登録するとKindle Unlimitedの対象となり、読まれたページ数に応じて収益が加算されます。
この「既読」は月ごとに単価が変動します。
私も初期は「ページ単価はいくら?」と固定値を探してしまいましたが、実際は毎月変わる仕組みです。
「売れない=収益ゼロ」ではなく、内容が読まれれば既読で積み上がるというのは、地味ですが継続型の強みです。
結論:正しい仕組み理解と継続で収益化は可能
結論として、**正しい仕組み理解+継続**が収益化のカギです。
印税率・価格設定・KDPセレクトの選択、この3つを誤解したまま進めると損をしやすいです。
例えば、印税70%を選んだつもりが、価格帯の条件を外れていたり、設定変更のタイミングによって適用されていなかったり……。
私も最初は「なぜこの数字?」と困惑したことがありますが、レポート画面や公式ガイドをこまめに確認することで解消しました。
“理解して→検証して→改善する”流れを繰り返すほど、収益は安定します。
これはブログやYouTubeなど、他のコンテンツ発信でも同じですね。
副業として人気が高い理由と、誤解されやすい点
Kindle出版が副業として注目される理由は、初期コストの低さと、ストック型の資産になる点です。
作った本が長期間読まれる可能性があるのは大きな魅力です。
ただし、「1冊ですぐに高収益」という期待は持たない方が健全です。
上位表示や既読を積み上げるには、最低でも数冊の経験と改善が必要なケースが多いです。
「AIで丸投げすれば稼げる」と誤解されることがありますが、品質チェックは必須ですし、内容が薄いとレビューや既読に響きます。
実務では、**AI=作業効率化の補助**という位置づけの方が結果的に安定します。
初心者の方は、「まず1冊出してみて、数字で学ぶ」くらいの姿勢で進めるのがおすすめです。
実際、私も最初の作品よりも、3冊目以降で世界が一気にクリアになりました。
KDP(Kindle出版)で収益が発生する仕組み|印税と既読の基本
Kindle出版では、大きく2つの仕組みで収益が発生します。
ひとつは本が購入されたときの「販売ロイヤリティ」、もうひとつは読み放題サービスで読まれたページ数に応じた「既読分(Kindle Unlimited)」です。
この章では、まずは基礎を押さえましょう。
私も最初は「印税=販売だけ」だと思っていましたが、既読が積み上がることで安定感が出てくると実感しました。
販売ロイヤリティの種類(70%/35%)と違い
販売ロイヤリティは、**70%プラン**か**35%プラン**の2種類です。
これは出版時に選べる設定で、どちらを選ぶかで収益性が大きく変わります。
70%の方が高いからお得、と思いがちですが、条件があるため必ずしも全作品に最適とは限りません。
また、日本のKDPではロイヤリティ計算の基準が“税抜き価格”である点に注意が必要です。
ここを誤解して売上予測を立てると、「思った数字と違う…」という初心者あるあるが起きます。
私自身、最初の頃は税込で計算して少しズレを感じた経験があります。
70%と35%ロイヤリティの具体的な違いや適用条件を詳しく押さえたい場合は、『Kindle出版のロイヤリティとは?70%と35%の違いと条件を徹底解説』でチェックしておくと、価格戦略が立てやすくなります。
70%ロイヤリティの条件(価格帯など|公式ヘルプ要確認)
70%適用は価格帯・対象地域・配信コスト条件など複合要件です。該当外は自動で35%になる場合があります(最新条件は公式ヘルプ要確認)。
条件は変更される可能性があるため、必ず最新の公式ヘルプで確認してください。
特に初心者が見落としやすいのは、
* 価格帯
* 配信地域
* 配信コスト
この3点です。
条件を満たさないと、自動的に35%になるケースもあるため、出版前に一度チェックしておくと安心です。
実務的な感覚としては、最初は無理に70%にこだわらず、価格検証の柔軟性を持つ方が進めやすいこともあります。
KDPセレクトとKindle Unlimited既読の仕組み
KDPセレクトに登録すると、Kindle Unlimited(読み放題)の対象になります。
この登録は任意ですが、既読による収益を得たい場合は必要になります。
読み放題で読まれた分は、ページ数に応じた収益として計上されます。
最初は「読み放題だと収益が減るのでは?」と心配する人も多いですが、実際には**長期的に読まれるコンテンツ**ほど既読が安定しやすい傾向があります。
ただし、セレクトに登録するとAmazon独占配信となるため、他のプラットフォームでの販売はできません。
公式では自由に選べるとされていますが、実務では作品性や戦略によって向き不向きがあります。
既読換算(KENP)と分配方式の概要(月次変動)
Kindle Unlimitedで読まれたページ数は、「KENP(Kindle Edition Normalized Pages)」という指標で換算されます。
簡単に言うと、Amazonが定める基準でページ数に変換する仕組みです。
そして、KENPに応じて分配される収益は月ごとに変動します。
「1ページ=◯円」と決め打ちしている方もいますが、月次で変わるため固定値として扱わない方が安全です。
私の経験では、「先月より単価がやや上がった/下がった」という動きは珍しくありません。
そのため、予測は目安としてとらえ、レポートをこまめに確認して慣れていくのが現実的です。
なお、公式ダッシュボードで既読推移をチェックできるため、数字と照らし合わせながら対策できるのがKDPの強みです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle出版の収益はどうやって決まる?計算式と重要ポイント
販売ロイヤリティは、〈70%:税抜リスト価格−配信コスト〉×70%、〈35%:税抜リスト価格×35%〉が基本です。既読はKENP×月次単価で算出します(詳細は公式ヘルプ要確認)。
式にするとシンプルですが、実際にレポート画面で数字を追うと「この金額は何?」と最初は戸惑いやすいです。
私も最初の2〜3冊目までは、計算表を作ってダッシュボードと突き合わせていました。
慣れると自然と理解できるので、「今はよくわからない…」と不安になる必要はありません。
ロイヤリティ計算の基本(日本は「税抜き価格」ベース)
Kindle出版のロイヤリティ計算は、**税抜き価格が基準**です。
ここは初心者が混乱しやすいポイントで、「税込で70%じゃないの?」と私も最初は勘違いしていました。
具体的には、
販売価格(税抜) × ロイヤリティ率(70% or 35%)
という形で計算されます。
例えば、税込価格が500円だとすると、税抜価格は約455円です。
この455円に対して70%または35%が適用されます。
販売価格が同じでも、税抜計算を意識できているかで収益予測の精度が変わります。
正確な税率は時期により変わるため、国税庁やAmazonの設定に従って判断してください。
実際のロイヤリティ計算をステップごとに確認したい方は、『Kindle出版の報酬とは?ロイヤリティ計算と稼ぎ方を徹底解説』を見ながら手元で計算してみると、数字のイメージが一気にクリアになります。
既読ロジックとレポート画面の見方|初心者のつまずきポイント
Kindle Unlimitedの既読収益は、**月ごとに変動する単価**で計算されます。
「1ページ=◯円」という固定の考え方は誤解で、毎月公式発表があります。
レポート画面では、
* 既読ページ数(KENP)
* 推定ロイヤリティ
が確認できます。
最初の頃は、「推定額が毎日少し変わる」「確定額が翌月にズレ込む」などの動きに戸惑う方が多いです。
私も初月は「数字が減ってる?」と驚きましたが、月次締めを理解してから落ち着きました。
推定は月中に変動し、確定は翌月に反映されます。確定時期の細目は国・期間で異なるため公式ヘルプ要確認。
という流れを覚えておくと安心です。
手数料や源泉徴収の概要(日本在住向け)
Kindle出版の収益は、税や手数料の考え方も押さえておく必要があります。
日本在住の場合、Amazon.co.jpの売上は日本の所得として扱われます。
分類は、
* 雑所得
* 事業所得
どちらになるかは状況によるため、個別判断が必要です。
確定申告で迷う方が多い部分なので、早めに税務署や税理士に確認しておくと安心です。
また、米国ストアで売上がある場合は、**源泉徴収や租税条約**の手続きが関わることがあります。
この記事では日本向け出版を前提にしていますが、海外分が発生した場合は公式サポートの案内や税務情報ページを必ず参照してください。
「税金はよくわからなくて不安…」という声も多いですが、最初は難しく感じて当然です。
収益が出始めた段階で学べば間に合うので、一歩ずつ進めていきましょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版で収益を伸ばすための3つの戦略
Kindle出版で収益を伸ばすためには、やみくもに冊数を増やすより、戦略的に制作と運用を進めることが大切です。
私自身、最初は勢いで数冊出しましたが、**戦略を意識してから収益の伸び方が変わった**実感があります。
テーマ選び、価格設定、KDPセレクトの使い方。
この3つを押さえるだけでも、継続読まれる本になりやすく、既読も伸びやすくなります。
①ジャンル選定|需要×継続読まれるテーマ
ジャンル選定は、収益を左右する最重要ポイントです。
市場の需要があり、読み続けられるテーマかどうかを意識しましょう。
具体的には、
* 課題解決系(例:生活改善・お金・学習)
* スキル学習(例:副業、文章術、ツール活用)
* ニッチだけど検索ニーズがある領域
などが長期的に安定しやすいです。
「書きたいことを書く」だけだと、読者ニーズとずれてしまい、既読が伸びにくくなります。
私もはじめは好きなテーマで出しましたが、**読者の検索意図を軸に企画した本の方が数字が安定**しました。
“自分の強み×読者の困りごと”の交点を探すと方向性が定まりやすいです。
読者の検索意図に合わせてタイトルやキーワードを設計し、商品ページからのクリック率を高めたい場合は、『Kindle出版のSEOとは?タイトルとキーワード設計を徹底解説』で検索対策の基本も押さえておくと効果的です。
②価格設定戦略|低価格から検証、70%帯の活用
価格設定は、最初はやや難しく感じるかもしれません。
いきなり高価格にするより、**まずは手に取られやすい価格帯**で読者の反応を確かめるほうが現実的です。
Kindleでは、300〜500円台でスタートして、評価や既読の伸びを見て調整する方も多いです。
もちろんテーマやボリュームによりますが、初期は「まず読まれる環境を作る」ことが重要です。
その上で、条件を満たすなら70%ロイヤリティ帯をうまく活用すると収益効率が良くなります。
ただし、公式の条件に該当しない場合は無理に狙わず、柔軟に進めましょう。
価格は後から変更できます。
「最初から完璧に決めよう」と力みすぎないことも大切です。
③KDPセレクト戦略|登録するか迷った時の判断軸
KDPセレクトに登録するかどうかは、作品の性質と収益モデルで判断します。
セレクトに登録すると、Kindle Unlimitedで読まれる可能性が生まれ、既読収益が期待できます。
一方で、Amazon独占配信になるため、他サイトでは販売できません。
私の体感では、**最初の数冊はセレクトを活用し、読者データを集める**ほうが学びが早いです。
ただし、他サービスで既にファンがいる場合や、カラー多めのノウハウ本などは別戦略の方が向くこともあります。
つまり、「絶対にセレクトが正解」というより、作品ごとに適切な判断が必要です。
迷ったら、
* 読まれる導線を強化したい → セレクト
* マルチ配信で広く露出したい → 非セレクト
というシンプルな判断軸で良いと思います。
実例で理解|Kindle出版の収益イメージ(販売+既読)
Kindle出版の仕組みはわかったものの、「結局どれくらい収益が出るの?」という疑問は残りますよね。
ここでは、実際の動きに近い形で、販売と既読のモデル例をやさしく整理します。
もちろん、細かな数値は公式の仕様に基づき、月ごとに変動する部分もあります。
そのため、ここでは考え方の理解を目的にしています。
私自身、最初は“目安のイメージ”を掴んでから、レポートを確認する習慣をつけたことで数字が理解しやすくなりました。
販売による収益モデル例(公式仕様ベースで説明)
販売収益は、**税抜価格×ロイヤリティ率**で算出されます。
例えば、税込価格500円の電子書籍を考えてみましょう。
500円(税込) → 約455円(税抜)
この455円に対し、70%または35%のロイヤリティが適用されます。
* 70%の場合:455円 × 0.7 ≒ 318円
* 35%の場合:455円 × 0.35 ≒ 159円
配信コストは70%ロイヤリティ選択時のみ差し引かれ、主にファイルサイズに依存します(画像多い・固定レイアウトは影響大)。公式ヘルプ要確認。
初心者さんが混乱しやすいのは、「500円の70%=350円ではない」という点です。 Amazon.co.jpでは“税抜価格”が基準になるため、電卓を叩くときは必ず意識してくださいね。
出版初期は、1冊あたりの利益ばかり気になるかもしれませんが、実務では
* タイトルの需要
* カテゴリ選択
* 表紙・説明文
などの要素も大きく影響します。
既読による収益モデル例|短期と長期の違い
次に、Kindle Unlimitedで読まれた場合のイメージです。
既読は「KENP(規格化ページ)×月ごとに変動する単価」で計算されます。
たとえば、あなたの本が150ページ相当だったとして、1人が全部読めば150KENPです。
仮に月の単価が1KENP=約0.5円なら、150ページ読みきられると約75円になります。
もちろん、これはあくまでイメージです。 既読単価は毎月変動するため、固定値ではありません(公式発表を必ず確認してください)。
短期で一気に読まれる本は初速が出やすく、
長期でじわじわ読まれる本はストック型の収益になります。
私の経験では、専門性の高いテーマは長期型、エッセイ系は口コミで短期に伸びるケースもありました。
「出した月だけ数字を見て判断しない」という視点も大切です。
初心者が勘違いしやすい「ページ=○円」固定思考に注意
よく聞く誤解が、「1ページ=○円」と覚えてしまうことです。
SNSや動画で固定値のように言われることがありますが、これは避けたい考え方です。
実際には、
* 月の基金総額
* 全体の既読ページ数
で単価が変わります。
そのため、1ページいくらと断定するより、
「ページが読まれるほど収益になる」
と理解しておく方が現実的です。
地味ですが、レポートを毎月確認する習慣が、数字感覚を育てます。
私も最初のころは「単価が微妙に違う?」と不安になりましたが、毎月の変動が普通だとわかってから気持ちがラクになりました。
固定値を期待すると予測が外れやすく、誤解や焦りにつながります。
丁寧にレポートを見て、少しずつ肌感を育てていきましょう。
Kindle出版で収益が伸びない理由と改善チェックリスト
Kindle出版で「出したのに思ったほど伸びない…」と感じるときは、原因がどこかに潜んでいます。
私自身、初期の作品では数字が伸びず、原因をひとつずつ洗い出しながら改善しました。
焦らず、確認ポイントを押さえながら進めれば、少しずつ数字は変わっていきます。
収益が伸びないときは、テーマ・タイトル・構成・読了率・レポート分析の5点を見直すと突破口が見えることが多いです。
一緒に要点を整理していきましょう。
よくある原因:テーマ選定/タイトル/読了率
収益が伸びないとき、まず見返してほしいのが**テーマ選定**です。
需要が小さすぎる、競合が強すぎて埋もれる、検索意図から外れている。
この3つのどれかに当てはまると、読まれにくくなります。
「自分が書きたいテーマ」だけで進めると、読者ニーズとズレやすいです。
特に初心者さんは、**読者の悩みを解決する切り口**を軸にテーマを選ぶと成果が出やすいです。
私もテーマ選びを見直しただけで、数字が一気に動いたことがありました。
次に、**タイトル設計**です。
タイトルは検索・クリックのきっかけです。
抽象的すぎる、メリットが伝わらない、キーワードが入っていない。
こうした点があると、表示されてもクリック率が下がります。
読んだあとどう変われるのかを一言で示すと、興味を引きやすいです。
そして、意外と見落とされやすいのが**読了率**です。
最初だけ読まれて途中で離脱されると、既読が伸びず、評価も上がりません。
* 導入が長い
* 回りくどい説明
* 実例や図解が少ない
こうした点を改善すると、読了率が上がりやすくなります。 「最初の数ページで価値が伝わる構成」を意識すると結果が変わります。
改善策:検索意図に寄せた構成とレポート分析
改善の基本は、**検索意図に沿った構成**にすることです。
読者が知りたい順に情報を並べ、余計な脱線を避けるだけで、読了率が大きく変わります。
初心者さんが陥りがちなのは、
「全部書かないと…」
と意気込んで情報を詰め込みすぎること。
実務上は、必要な情報を整理して、**読みやすさと理解しやすさを優先**するほうが結果的に支持されます。
次に、**レポート分析**です。
KDPのダッシュボードは情報の宝庫です。
* 日ごとの閲覧数
* 既読推移
* 販売タイミング
* プロモーション効果
特に既読推移は、改善ポイントを見つけるヒントになります。
私も最初は数字の揺れに不安になりましたが、定期的にチェックしながら調整する習慣がつくと、改善スピードが上がりました。
「感覚ではなく、数字で判断」という意識が、結果を安定させます。
この段階では、無理にすべて改善しようとせず、ひとつずつクリアしていけば大丈夫です。
出版は“積み上げ型”の取り組みなので、焦らなくても大丈夫。
数字を味方につけて、少しずつ育てていきましょう。
Kindle出版の確定申告と税金の基礎(日本向け)
Kindle出版で収益が出てきたら、忘れてはいけないのが税金です。
「副業だから関係ない」「少額なら大丈夫」と思われがちですが、収益が出た以上は適切な処理が必要です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、ポイントだけ押さえれば安心して進められます。
私も初期は「経費って何?」「どこまで申告するべき?」と悩みましたが、少しずつ理解を深めることでスムーズになりました。
収益区分の基本(雑所得/事業所得|状況で異なる)
Kindle出版で得た収益は、**雑所得**か**事業所得**として扱われます。
どちらになるかは、収益規模・継続性・業務としての実態などにより異なります。
一般的に、
* 副業段階で規模が小さい:雑所得として扱うケースが多い
* 継続的で事業性がある:事業所得として扱う可能性がある
というイメージです。
ただし、どちらに該当するかは個々の状況次第なので、税務署や税理士に確認するのが安心です。
私も「どちらに該当するのだろう?」と迷った際、税務署に質問して明確にできました。
“収益が少額でも、条件次第では申告が必要”という点は意外と見落とされやすいです。
また、経費の計上可否も所得区分によって扱いが変わるため、早めに理解しておくと後で慌てません。
参考例として、Kindle出版で必要になり得る経費には、以下があります:
* 表紙制作費
* 執筆用ツール代
* 外注費
* 調査目的の書籍代 など
経費については領収書をしっかり保管しておきましょう。
海外ストア収益がある場合の補足(源泉徴収|一言)
日本向け出版が中心の場合でも、海外ストアで購入された場合には、**源泉徴収**や**租税条約**などの税務手続きが関わることがあります。
具体的には、米国ストアで収益が発生すると、条件によって米国側で源泉徴収される可能性があります。
そのため、海外売上がある場合は税務インタビューでW-8BEN等を提出し、租税条約の適用可否を確認してください(公式ヘルプ要確認)。
私自身、海外読者が想定外に増えた際に「いつの間にか源泉徴収されている…?」と気づいたことがあり、早めに税務設定を整える重要性を実感しました。
もし海外売上が発生したら、必ずKDPの税務情報ページと税務署の案内を確認しておくと安心です。
特に米国とのやり取りは制度が変わる可能性もあるため、定期的なチェックをおすすめします。
以上が、Kindle出版の税金まわりの基本です。
最初は「難しそう」と感じるかもしれませんが、ひとつずつ理解していけば必ず対応できます。
収益が伸びてきたタイミングで税務の専門家に相談するのも、よくある選択肢です。
初心者が安全に始めるためのQ&A
Kindle出版は誰でも挑戦できますが、最初に押さえるべき安全ポイントがあります。
「知らなかった…」で後から手戻りになると、心理的にも疲れてしまいます。
私自身、最初はページ数や規約まわりで戸惑ったので、これから始める方には最短ルートで理解してほしいと思っています。
KDP公式仕様の確認ポイント(規約・ガイドライン)
まず、必ずチェックしたいのがKDP公式の利用規約とコンテンツガイドラインです。
「とりあえず出してみる」で進めてしまうと、修正依頼や公開停止につながることがあります。
特に確認したい部分は以下です。
* 他者のコンテンツを引用する場合のルール
* 誤解を招く表現や誇張表現の禁止
* 読者体験を損なう商品設計(極端に短い内容など)
公式では明確に書かれていても、実際の運用では「グレーに見える行為」がSNS上で広まることがあります。
ただ、“一時的にできてしまう”ことと“長期的に安全”は全く別です。
私も最初は「みんなやってるから大丈夫なのかな?」と思いましたが、長期運用を考えるなら公式に沿うほうが安心です。
迷ったら公式ヘルプを確認し、必要に応じてサポートへ問い合わせると良いです。
AI活用の注意点|文章品質とチェック体制
AIは執筆の心強い味方ですが、万能ではありません。
文章全体をAIに任せると「情報の正確性」「文脈の自然さ」が崩れることがあります。
たとえば、
* 実体験が含まれず、薄い内容になる
* 古い情報を引用してしまう
* 曖昧な表現が残り、信頼性が下がる
といったリスクがあります。
AIを使う際は、
* 内容の事実確認
* 自分の感想や経験を追加
* 読み手の役に立つ図解や補足を入れる
というチェック体制を持つことが重要です。
私も最初は「AIが言ってるから正しいだろう」と思い込み、修正に時間がかかったことがあります。
今では「下書き→自分で編集→第三者視点で見直し」という流れにして精度を高めています。
AIはあくまで補助。
最終的な品質は、自分の目で確かめることが大切です。
まとめ|Kindle出版の収益は「仕組み理解+継続」で伸びる
Kindle出版は、仕組みを理解し、地道に改善を続ければ確実に伸ばせる分野です。
いきなり大きく稼ぐ必要はありません。
まずは仕組みを理解し、1冊、また1冊と積み重ねるだけで、経験値が大きく変わります。
特に、
* 読者ニーズに沿うテーマ設定
* 読みやすさを意識した構成
* PDCAと分析の積み重ね
この3つが成果を左右します。
途中で不安になることがあっても大丈夫です。
ほとんどの人が同じ段階を通ります。
継続し、改善し続ける。
それがKindle出版の最大の強みであり、成長の道です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。