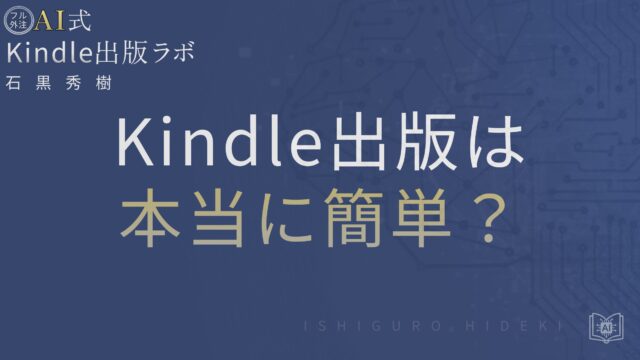Kindle出版の費用は本当に無料?必要コストと節約術を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版は「無料でできる」とよく言われます。
たしかに、私が初めてKDPで電子書籍を出したときも、前払いの料金はありませんでした。
しかし、実際に出版してみると、**“完全に何もかからない”という意味ではない**と気づきました。
印税の仕組みや配信コスト(データ転送費)を理解していないと、「思ったより手元に残らない」と感じる場面が出てきます。
この記事では、Kindle出版の費用が本当に無料なのかを、初めて挑戦する方にもわかりやすく解説します。
実体験にもとづき、初心者がつまずきやすいポイントもしっかり押さえています。
Kindle出版そのものの全体像やメリット・デメリットもまとめて押さえておきたい方は、先に『Kindle出版とは?初心者が無料で始める電子書籍の基本と仕組みを徹底解説』を読んでおくと、本記事の「費用」の話もスムーズに理解しやすくなります。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の費用は本当に無料?初心者がまず知るべきポイント
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
Kindle出版は、Amazonが提供する電子書籍のセルフ出版サービスです。
結論から言うと、**前払い費用は基本0円で出版できます**。
とはいえ、無料で編集やデザインをサポートしてくれるサービスではありません。
そのため、出版後の仕組みやデータ容量の考え方を知っておくことで、結果として大きく損をしにくくなります。
Kindle出版は基本0円で始められる(前払い費用なし)
KDPでは、アカウント作成や本の登録、出版自体に料金はかかりません。
いわゆる「出版手数料」は不要で、ここが副業として始めやすい理由です。
私も最初は不安で、念のためクレジットカード情報の入力がないか確認しましたが、登録時点では求められませんでした。
ただし、無料といっても、原稿作成ソフトや画像編集ツールを自前で用意する必要があります。
Wordやデザインツールを持っていない場合は、無料ツールを使う人が多いです。
(例:GoogleドキュメントやCanvaなど)
「無料=費用ゼロ」ではなく、印税計算と配信コストの仕組みを理解する
前払いが無料だからといって、出版後の費用が一切ないわけではありません。
実際には、売上が発生した時点でロイヤリティと配信コストの差し引きがあります。
KDPのロイヤリティは35%/70%の選択制です。70%は対象マーケットでの配信、定められた価格帯の設定、配信コスト差し引き等の条件を満たす必要があります(詳細は公式ヘルプ要確認)。
ここを理解せずに「70%だから儲かる」と思うと、後で差異に驚くことになります。
また、70%ロイヤリティを選択した場合、**ファイル容量に応じたデリバリー(配信)コスト**が発生します。
画像が多い本や、写真集形式の作品を作ると、知らないうちにコストがかさむことがあります。
私自身、最初の出版時に画像圧縮を忘れ、思ったより手残りが減った経験があります。
対策として、画像は圧縮し、不要な装飾は避けるのが安全です。
Amazon.co.jp向けKDPの前提と、米国向け補足(必要時のみ)
この記事は、日本のAmazon.co.jp向けに出版する前提で解説しています。
日本の出版者にとって、KDPの仕様は米国と大きく変わりませんが、税務上の手続きが異なる場合があります。
販売先が海外(例:Amazon.com)にも広がると、源泉徴収や税務フォームが関係する場合がありますが、まずは**日本市場が中心**と考えて問題ありません。
海外販売を扱う場合は、KDP公式の税務ガイドを確認してください。
私自身も、日本向けの1冊目が安定してから海外販売に広げました。
まずは国内で流れをつかむのが安心です。
Kindle出版にかかる費用の内訳と考え方
Kindle出版の費用は、前払いがない代わりに「売れた後に引かれる費用」と「必要に応じて自分で投資する費用」に大きく分かれます。
初心者の方は、まずこの構造を理解することが大切です。
私も最初は「完全無料で放置でOK」と誤解していましたが、実際はうまく投資と節約のバランスを取らないと、結果が出にくくなります。
ただ、最初から高額投資をする必要はありません。
まずは小さく始めて、売れ始めたら必要な部分に資金を回す、という考え方が現実的です。
電子書籍出版で必ず発生する「販売後の費用(配信コスト・ロイヤリティ)」
Kindle出版では、出版する時点でお金はかかりません。
販売後にはロイヤリティは常時差し引かれますが、配信コストは70%ロイヤリティ選択時のみ発生します(公式ヘルプ要確認)。
ロイヤリティは35%または70%の選択制で、70%を選ぶには価格帯や販売条件があります(公式ヘルプ要確認)。
初心者の方は、この部分を曖昧なまま出版しがちです。
「70%=儲かる」と短絡的に判断せず、条件を確認してから選びましょう。
また、配信コストはファイル容量で変動します。
特に画像を多用した書籍は、容量が増えやすく、結果的に手取りが少なくなることがあります。
私も写真が多いコンテンツを最初に出版した際、画像圧縮を怠って手残りが大きく減った経験があります。
画像はWeb最適化設定で軽くし、必要以上にページを増やしすぎないのがポイントです。
これは公式ページにも書かれている内容ですが、実務では「軽量化で印税が増えた」という実感が湧きます。
任意で発生する費用:表紙デザイン・校正・編集・画像素材など
Kindle出版で必須費用はありませんが、クオリティを上げたい場合は外部サービスに費用を払うことがあります。
多くの方が投資するのは、表紙デザイン、文章の校正、EPUB変換、画像素材などです。
表紙は読者のクリック率に直結するため、初心者が一番悩むポイントかもしれません。
私も初期は自作でしたが、後からデザインを改善したところ、明らかに閲覧数が伸びました。
ただし、はじめての出版では高額投資を避けて問題ありません。
無料ツール(例:Canva)でも十分クオリティを出せますし、文章の校正もAIで一次チェックし、最小限の外注に絞る方も多いです。
外注費の相場と「必要な部分だけ外注」する考え方
外注費の相場は、表紙1,000〜10,000円、文章校正数千円〜数万円程度が多いです(クラウドソーシング相場)。
とはいえ、全てを外注する必要はありません。
初心者には「大事なところだけ外注」するミニマム戦略をおすすめしています。
具体的には、表紙だけ外注し、原稿は自分で書き、校正はAIで一次チェック+気になる箇所だけ人に依頼、という流れです。
実務的にも効果的で、いきなりフル外注しても費用だけかかり、文章の方向性が定まらないことがあります。
最初の1冊は学びが大きいので、自作と外注のバランスを試しながら進めましょう。
紙(ペーパーバック)の場合:印刷コストは売上から差し引き(前払いは不要)
ペーパーバックでも前払いは不要です。印刷コストは1冊ごとのページ数・インク種などに応じて変動し、販売価格から差し引かれます(公式ヘルプ要確認)。
ただし、電子書籍よりも印刷コストが固定で必要になるため、価格設計が重要です。
初心者の方は、まず電子書籍だけでスタートし、需要が見えたタイミングで紙版を追加するのが現実的です。
私自身、最初の1冊は電子のみで様子を見て、反応が良かったため紙版も出しました。
印刷見本が届いた時の感動はありますので、タイミングを見て挑戦するのも楽しいですよ。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle出版の配信コスト(デリバリー)とロイヤリティの仕組み
Kindle出版では、売れた後に利益が入りますが、その前に「ロイヤリティと配信コスト」が差し引かれます。
これを理解していないと、「思ったより手元に残らなかった」という声が必ず出ます。
売上からどのようにロイヤリティが計算され、既読分の収益が加算されていくかを数字ベースで把握したい方は、『Kindle出版の収益はどう決まる?印税と既読の仕組みを徹底解説』もあわせてチェックしておくと、「費用」と「収益」のバランスを立体的にイメージしやすくなります。
私も最初の1冊目は、ロイヤリティの違いを深く理解しておらず、数字の差に驚いた記憶があります。
KDPは仕組みがシンプルに見えて、実務では細かなルールの差が結果に影響します。
できるだけ難しい話はかみ砕きますので、安心して読み進めてくださいね。
35%と70%ロイヤリティの違いと、選択条件(公式ヘルプ要確認)
Kindle出版の収益は、販売価格からロイヤリティ(印税率)をかけて受け取ります。
ロイヤリティには「35%」と「70%」があります。
70%を選べるのは、Amazonの条件を満たしたときのみです。
たとえば、日本向けの場合、価格帯や販売地域設定などが条件になります(詳細は公式ヘルプ参照)。
初心者がやりがちな誤解は、「70%=常に最適」という判断です。
実際には、70%のときだけ配信コストが差し引かれるため、画像が多い本や容量の大きい本では、思ったより手取りが減るケースがあります。
私も最初は「70%固定でいいじゃん」と思っていましたが、容量によっては35%のほうが結果的に得な場合もありました。
出版前に、ジャンルやページ構成に応じて判断しましょう。
配信コスト(デリバリー料)の仕組みと、容量を抑える工夫
70%ロイヤリティを選択した場合、ファイル容量に応じた**配信コスト(デリバリー料)**が差し引かれます。
これは、本を読者の端末へ届けるためのデータ転送費です。
配信コストは、画像・挿絵・余分な装飾が多いほど高くなります。
いわゆる「写真が多い作品」や「リッチなレイアウト」の本は慎重に作る必要があります。
私も写真を多用したハウツー本を作ったとき、この配信コストが想定より高く、利益率が低くなった経験があります。
その後、画像を最適化し、必要最低限の解像度に調整したところ、利益が改善しました。
Web用に圧縮する、Canvaで軽量設定を使う、不要な画像は削るなど、容量を抑える工夫がおすすめです。
公式ヘルプにもファイル最適化の推奨があります。
KDPセレクト加入の有無と収益への影響
KDPセレクトはAmazon独占配信のオプションです。加入作品はKindle Unlimited等で読まれたページ数に応じ、月ごとの基金(KDP Select Global Fund)按分で収益が発生します(販売価格のロイヤリティとは別枠)。
経験上、初心者の方はKDPセレクトを活用するほうが収益化しやすい傾向があります。
ただし、独占配信となるため、他サービスで販売したい場合は慎重に判断が必要です。
また、KDPセレクトに加入することで、プロモーション機能(無料キャンペーンなど)が使えるため、最初は認知を広げやすくなります。
私も1冊目はKDPセレクトで公開し、Kindle Unlimitedの閲覧が初期の売上を支えてくれました。
ただし、ジャンルによっては独占にしない戦略が効果的な場合もあります。
出版スタイルに応じて検討し、迷ったら1冊目は試してみるのが良いでしょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
無料でKindle出版する場合の進め方とチェックポイント
Kindle出版は、最初からお金をかけなくても十分にスタートできます。
実際、私自身も1冊目は完全無料で出版し、改善を重ねながら読者に届けました。
ただ、無料=手間がゼロという意味ではありません。
ツール選びやデータの扱い方を理解し、必要な工程を丁寧にこなすことで、無料でも十分魅力的な本になります。
ここでは「無料で出版する流れ」と、チェックすべきポイントを紹介します。
これを押さえておくと、無駄なコストをかけずに品質を高められます。
出版の流れ全体や、アカウント設定・審査でつまずかないためのチェックポイントを事前に整理しておきたい場合は、『Kindle出版の準備とは?審査落ちを防ぐ手順とチェックポイントを徹底解説』を読みながら進めると、ムダな出費ややり直しを減らしやすくなります。
無料で出版するためのツール例(執筆・EPUB変換・画像圧縮)
まずは、無料で使えるツールをうまく活用しましょう。
KDPは、Word原稿やEPUB形式に対応していますが、初心者なら以下のツールで十分です。
執筆:Googleドキュメント、Notion、Word Online
EPUB変換:KDP公式ツール(Kindle Create)、Googleドキュメント→Word→KDPアップロード
画像作成/編集:Canva(無料版)、Photopea
画像圧縮:TinyPNG、Squoosh
特にKindle Createは初心者にも扱いやすく、表紙テンプレートや目次作成も簡単です。
私も初期はKindle Create一本で仕上げていました。
有料ツールは便利ですが、最初の1冊は「無料ツールで学んで、必要性を感じたら投資する」のが安全です。
最初から有料ツールを揃えるより、まずは書き始めることを優先しましょう。
画像や挿絵が多い場合の注意点とファイル軽量化のコツ
画像や挿絵を使う本では、データ容量が増えやすくなります。
70%ロイヤリティを選ぶ場合、容量が大きいと配信コストが増えるため、結果的に手取りが減る点に注意です。
特に、写真集や図解が多い冊子では、画像サイズをそのまま使うとかなり重くなります。
私は過去に、画像を圧縮せずにアップロードしてしまい、配信コストがかさみました。
画像は「書籍用」の最適化が必要です。
ポイントは以下です。
・端末表示に十分な解像度まで適正化する(推奨値や画像仕様は公式ヘルプ要確認)
・Web最適化したJPEG/PNGを使う
・ファイルはTinyPNGなどで圧縮
・カラーよりグレースケールのほうが軽いケースも
公式ガイドでも容量最適化が推奨されているため、出版前にチェックしましょう。
見た目と容量のバランスを取りながら制作すると、印税の実入りが変わります。
リリース後の改善でコストを最適化する方法
Kindle出版の良いところは、出版後に更新・改善できる点です。
無料で始めてから、読者の反応を見て必要箇所だけ投資するのが、リスクを抑えた進め方です。
たとえば、
・表紙をより魅力的なものに差し替える
・章立てや見出しを調整して読みやすくする
・レビューを元に加筆・修正する
・画像圧縮して配信コストを調整する
私は、出版から1ヶ月後に表紙を改善し、クリック率が上がったことがあります。
出版して終わりではなく、改善を重ねることで安定した収益につながります。
「まず出す → 読者の声を見る → 必要な部分だけ改善」
このサイクルを回すと、無料出版でもクオリティを高められます。
最後に、無理に広告をかけたり、高額な外注に頼ったりする必要はありません。
最初はミニマムで試し、反応が取れた部分にだけ費用をかける。
これがKindle出版で長く続けるための王道パターンです。
Kindle出版の費用シミュレーションと注意点
Kindle出版で「お金をかけるかどうか」は、出版の段階と目的によって変わります。
最初から完璧を目指すより、スモールスタートで検証しながら必要箇所に投資する方が、結果的にリスクが小さく済みます。
ここでは、無料で始める場合の考え方から、売れ始めた後の投資判断まで、具体的にシミュレーションしていきます。
私自身、1冊目は完全無料でテスト出版し、反応を見てから改善しました。その経験を踏まえて解説していきますね。
初心者向け:0円出版シナリオ(最低限の構成で出す)
最初の1冊は、無料で出してみるのがもっとも現実的です。
執筆ツール、表紙作成ツール、EPUB作成ツール、すべて無料で揃います。
たとえば、以下の形が典型的です。
・執筆:Googleドキュメント
・表紙:Canva無料テンプレート
・EPUB変換:Kindle Create
・校正:自分+AIチェック
この構成なら、0円で出版できます。
いわゆる「最低限の構成」ですが、情報整理と読みやすいレイアウトさえ意識すれば、十分に読者の役に立つ本になります。
私が0円出版をしたときも、まずはシンプルに出し、読者の反応やレビュー内容を見て、必要箇所を改善しました。 最初は“高品質”より“リリースと改善”を優先する姿勢が大切です。
売れ始めたら強化:デザイン改善・校正依頼・広告検討
本が売れ始めたら、次のステップとして投資を検討します。
いきなり大きな費用をかける必要はなく、少しずつ強化すれば大丈夫です。
たとえば、以下の順番がスムーズです。
・表紙だけプロに依頼(数千円〜)
・気になる章だけ有償校正に出す
・読者の質問を踏まえて加筆修正
・レビューが増えてから広告検討
多くの出版者が経験するのですが、表紙を改善すると閲覧数や購入率が上がることがあります。
私も表紙を差し替えたあと、ランキングに入ったことがあり、「見た目の重要性」を実感しました。
広告も有効ですが、まずは本の質を上げることが優先です。
広告だけ先に打ってしまうと、レビューがつかず費用がもったいなくなる場合があります。
赤字リスクを避けるための判断基準(自己投資の優先順位)
Kindle出版はローリスクですが、投資の順番を間違えると効率が悪くなります。
最初から高額な外注や広告に頼るのはおすすめしません。
以下の優先順位を意識すると、安全に進められます。
1. 自力で出版(0円)
2. 読者の反応を確認
3. 最小限の外注で改善
4. 安定した動きが出てから広告
ポイントは、「実際の数字と読者の声を見てから投資判断する」ことです。
「みんな有料ツールを使っているから」という理由で初期投資すると、継続できなくなることがあります。
また、売上が伸びるまでに時間がかかるケースも普通にあります。
だからこそ、持続できる範囲でステップアップすることが大切です。
もし迷ったときは、先に小さな改善(表紙・序文の書き直しなど)を優先しましょう。
読者の第一印象に関わる部分から着手すると、成果が出やすいです。
長期的に続けるなら、無理のない投資と改善のサイクルが鍵になります。
「まず出す → 反応をみる → 必要箇所だけ投資する」という流れさえ守れば、赤字リスクはかなり抑えられます。
費用面だけでなく、集客・制作負荷・規約まわりなども含めてリスクを横断的に押さえておきたい方は、『Kindle出版のデメリットとは?初心者が失敗しやすい注意点を徹底解説』もあわせて読んでおくと、「どこにお金と時間をかけるか」の判断がしやすくなります。
Kindle出版の費用を抑えるための実例・テンプレート集
Kindle出版では、費用をかけすぎずに成果を出すための“型”があります。
すべてを手作りしつつ、必要な部分だけ外注することで、リスクを抑えながら改善できます。
ここでは、費用をおさえたい方に向けて、ジャンルごとの最小コスト戦略と、初心者向けテンプレート、そして実際に低コストで成功した例をご紹介します。
「独学でいけるか不安…」という方も、このセクションを使えば道筋が見えやすくなるはずです。
ジャンル別:費用を最小化しやすい出版スタイル例
ジャンルによって、制作コストのかかりやすさが変わります。
たとえば、画像が少ないジャンルはコストをかけずに出版しやすいです。
以下は、低コストで始めやすいジャンルです。
* 実体験ベースのノウハウ本
* 仕事や生活のTips集
* エッセイ、人生経験談
* まとめ系、学びのシェア
* 簡易ワークブック
これらは文字中心なので、画像や図表が少なくても成立します。
私もはじめは「仕事術のエッセイ」でデビューしましたが、文章構成と読みやすい見出しに集中すれば十分読まれます。
逆に、高解像度画像をたくさん使う写真集やイラスト集は、配信コストや制作負担が増えます。
最初はテキスト主体のジャンルで慣れてから挑戦するのがおすすめです。
「文章8割+見やすい構造+タイトルの精度」で勝負すると、無駄な費用を使わずに読者に届きます。
ミニマム構成テンプレート(軽量原稿+シンプル表紙)
ここでは、費用ゼロで仕上げるためのテンプレートをご紹介します。
これだけ守れば“必要十分な1冊”になります。
**文章構成テンプレ(例)**
1. 課題提示
2. 体験談と失敗例
3. 解決ステップ
4. 具体例・チェックリスト
5. まとめ・次の行動提案
**制作ツール**
* 執筆:Googleドキュメント
* 表紙:Canva無料テンプレ
* EPUB:Kindle Create
この構成で作れば、シンプルでも誠実で読みやすい本になります。
私もこのテンプレをベースにし、初版をリリースした後に追加修正して育てました。
表紙は、写真を無理に選ばなくてもOKです。
文字中心のミニマルデザインは、かえって“誠実さ”が出ます。
気負わず“最初の1冊”を形にすることが、長く続けられる秘訣です。
実例:低コスト出版→後改善で売上が伸びたケース
私の例をひとつ紹介します。
最初の出版時、費用はほぼ0円でした。
必要だったのは、GoogleドキュメントとCanvaだけです。
出版後、読者からのレビューを参考に、以下を改善しました。
* 表紙のフォントを変更
* 目次の構成を整理
* 改行・余白を調整し読みやすさを改善
* 冒頭に導入ストーリーを追加
これだけの調整で購入率が上がり、ランキングに入る日も増えました。
「最初から完璧」は目指さず、「必要になったら整える」という感覚が大切だと実感した瞬間です。
出版は作って終わりではなく、育てていくものです。
改善できる自由度が高いのがKDPの良いところですね。
【まとめ】Kindle出版の費用はゼロで始めて、必要箇所だけ投資する
Kindle出版は、初期費用ゼロで始められる珍しいビジネスです。
まずはミニマムで1冊出し、反応を見て必要な部分だけ投資しましょう。
いきなり高額な外注や広告を使うのではなく、数字と読者の声を見ながらコツコツ育てていく。
その積み重ねが、長く収益が続く本を作るコツです。
「まず出す。そして育てる。」
この姿勢を持てば、リスクを抑えながら成果を出せます。
今日から、あなたの1冊に向けて準備を始めてみませんか。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。