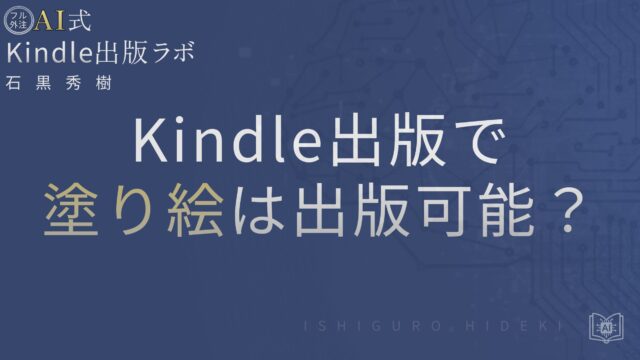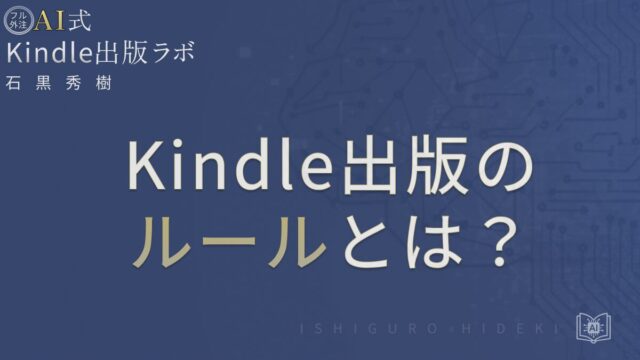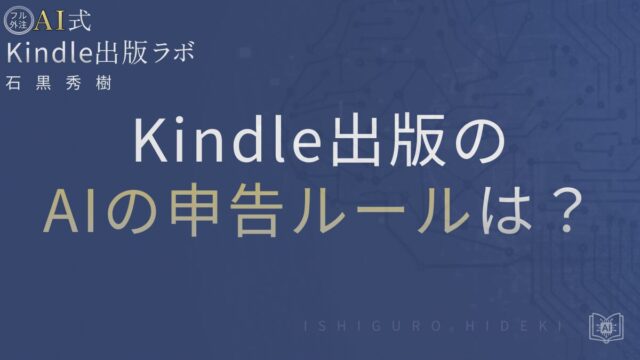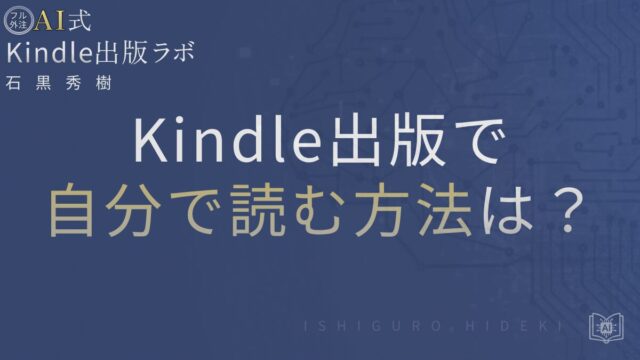Kindle出版のKDPアカウント複数とは?禁止理由と正しい管理方法を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの人が一度は「ジャンルごとにアカウントを分けた方が管理しやすいのでは?」と考えます。
しかし、KDP(Kindle Direct Publishing)では、同一人物による複数アカウントの作成は禁止されています。
知らずに複数作ってしまうと、最悪の場合アカウント停止につながることもあります。
この記事では、KDPアカウント複数の基本ルールと、誤解されやすいポイント、そして安全な管理方法をわかりやすく解説します。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
KDPアカウントを複数作るのはOK?Kindle出版の正しいルールを解説
目次
KDPアカウントは、Amazonが運営する電子書籍出版の管理システムです。
電子書籍の原稿登録から販売、印税の受け取りまで、すべてこのアカウントを通じて行われます。
そのため、KDPアカウントは「出版者本人の身元確認」と「支払い管理」を兼ねる重要な契約単位です。
Amazonの公式ヘルプでも明記されていますが、原則として一人につき一つのKDPアカウントしか持てません。
複数のアカウントを作ると、重複登録としてシステムが検知することがあり、停止や支払い保留などのトラブルにつながる可能性があります。
これからKDPアカウントを新規作成する段階の方は『Kindle出版のKDPアカウント作成とは?登録手順と注意点を徹底解説』を先に読んでおくと、基本設定で迷いにくくなります。
アカウント停止の流れや復活までの具体的なステップを先に押さえておきたい方は『Kindle出版のアカウント停止とは?原因と復活までの流れを徹底解説』もあわせて読んでみてください。
KDPアカウント複数とは?仕組みと基本ルール
「KDPアカウントを複数持つ」とは、同じ人物が別のメールアドレスや情報でKDPを新規登録することを指します。
たとえば、「ペンネームを変えたい」「別のジャンルを分けたい」といった理由で新しく作りたくなる人は多いのですが、これは規約上NGです。
KDPのシステム上、個人情報・銀行口座・税務情報などは一貫して本人名義で管理されるため、複数開設は重複と判断されるおそれがあります。
一方、KDP内では1つのアカウント内で複数の著者名(ペンネーム)を使い分けることが可能です。
つまり「アカウントを増やす」のではなく、「著者名を増やす」のが正しい運用です。
この違いを理解せずにアカウントを分けようとすると、後で統合や削除の手間が発生します。
同一人物による複数アカウントが禁止されている理由
複数アカウントが禁止されている最大の理由は、「支払い・税務・コンテンツ権利の一元管理」にあります。
KDPでは、印税支払いの口座・税務情報・本人確認をすべて1対1で紐づけています。
もし複数のアカウントを作成すると、著作権や支払い情報の重複、レポートの分散などが発生し、システム上のトラブルを引き起こしかねません。
また、悪用防止の観点もあります。
一部の利用者が複数アカウントを使ってレビュー操作や販売履歴の偽装を行うケースが過去にあったため、現在は非常に厳しく管理されています。
公式としては「明確な理由があり、事前にAmazonの承認を得た場合のみ例外が認められる」とされていますが、個人レベルではその対象になりません。
経験上、複数開設が発覚した場合、まずメールによる確認が入り、状況によっては一方が閉鎖されるケースもあります。
「後から統合すればいい」と考えて作るのは避けましょう。
KDP全体の禁止事項やガイドラインの全体像を整理しておきたい場合は『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』をチェックしておくと安心です。
よくある誤解:「買い物用Amazonアカウント」との違い
ここで多いのが、「買い物用のAmazonアカウントとは別だから、KDPをもう一つ作ってもいいのでは?」という誤解です。
Amazonの買い物アカウントとKDPのアカウントは、確かにシステム上は別のサービスとして管理されています。
しかし、KDPにログインする際には、Amazonの認証基盤を使うため、同一人物が複数登録すると重複と見なされることがあります。
つまり、買い物用と出版用のメールアドレスを分けること自体は問題ありませんが、「出版者としての本人」が複数のKDPアカウントを持つこと自体が規約違反になる、という点が混同されやすいのです。
実務上は、買い物・読書用のAmazonアカウントと、出版専用アカウントを1つだけ使い分ける形が最も安全です。
もし誤って複数登録してしまった場合は、削除ではなく統合申請を行うようにしましょう。
複数アカウントを作ってしまった場合の対処法
KDPでは、同一人物による複数アカウントは原則禁止です。
しかし、意図せず二重登録してしまうケースは少なくありません。
たとえば「別のメールで登録したら新しいアカウントになっていた」など、初期設定の段階で気づかないこともあります。
焦って削除を進める前に、まずはAmazon公式のサポートに連絡し、アカウント統合を依頼するのが最も安全な方法です。
削除を先に行うとデータの復元が難しくなるため、手順を確認してから動きましょう。
アカウント統合の手順と申請時の注意点(公式対応)
KDPのアカウント統合は、カスタマーサポートに英語または日本語で問い合わせを行う形になります。
公式ヘルプにも記載がありますが、「統合希望」と伝え、対象となる2つのアカウントの登録メールアドレス・出版状況・入金情報を明記して依頼します。
確認後、サポート側で本人確認が行われ、問題なければ統合作業が進められます。
なお、統合には数日〜1週間程度かかる場合があり、その間は売上レポートの反映が一時的に停止することもあります。
また、統合対象が本人名義であることが前提です。
異なる個人や法人のアカウントを1つにまとめることはできません。
実務上のポイントとして、問い合わせ時には出版中の書籍URLを添えるとスムーズに対応されやすい印象があります。
削除ではなく統合が推奨される理由と失敗例
「いらない方のアカウントを削除すればいい」と考える人は多いですが、これは危険です。
削除を実行すると、これまでの出版データ・販売履歴・税務情報が完全に消え、復元ができません。
その結果、印税支払いの履歴が不明瞭になったり、出版中の書籍が販売停止になるケースもあります。
一方で統合であれば、既存データをできる限り保持しながら、1つのアカウントにまとめることができます。
過去に私の知人が削除で対応したところ、「Author Central」と「KDP」が別紐づけのまま残り、修正に数週間かかったことがありました。
このようなリスクを避けるためにも、KDPアカウントは削除ではなく統合で解決するのが基本です。
統合時に引き継げないデータ・再設定が必要な項目
統合を行っても、すべてのデータが自動的に移行されるわけではありません。
印税レポートや広告データ(Amazon Ads)は別システムで管理されているため、過去分の閲覧ができなくなることがあります。
また、支払い方法・税務情報・A+コンテンツなど、一部の設定は統合後に再登録が必要です。
この点は公式にも明記されていますが、実務上は「税務情報(TINやマイナンバー関連)」の再入力で時間がかかる人が多い印象です。
統合前に、重要なデータはエクスポートして保存しておくと安心です。
特に販売レポートや広告履歴は、再確認できなくなる前に控えを取っておきましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
ジャンルを分けたいときの正しい方法:ペンネームと著者ページ管理
複数ジャンルを出版したい場合でも、アカウントを増やす必要はありません。
KDPでは、1つのアカウントの中でペンネームを複数設定し、それぞれ独立した著者ページ(Author Central)を作ることができます。
つまり、アカウントを分けなくても、作品ごとに“別の顔”を持たせることが可能です。
この方法を理解しておくと、規約に抵触することなくジャンルの幅を広げられます。
1つのKDPアカウントで複数名義を使う方法
KDPでは、書籍ごとに「著者名(Author)」を自由に設定できます。
この著者名がそのままAmazon上に表示される名前=ペンネームになります。
たとえば、実用書では本名、フィクションでは別名義という形で分けることも可能です。
この設定は出版画面で行えるため、ジャンル別に名義を変えたい場合も、アカウントを増やす必要はありません。
実務上の注意として、著者名が同一アカウントに複数ある場合でも、印税はすべて1つのアカウントに集約されます。
収益の分配や確定申告はアカウント単位で行われる点を忘れないようにしましょう。
ペンネームを増やしてジャンルごとにブランドを分けたい方は『KDPで複数ペンネームは使える?安全運用の仕組みと注意点を徹底解説』も参考にしてみてください。
ペンネーム設定と著者ページ(Author Central)の使い分け
著者ページ(Author Central)は、ペンネームごとに作成できます。
これにより、異なるジャンルの本をそれぞれ独立したブランドとして見せることができます。
たとえば、ペンネームAでは教育書、ペンネームBではエッセイというように、読者層を分けて見せることができます。
ただし、Author Centralを複数作る際は、各ペンネームで出版済みの書籍が1冊以上必要です。
また、プロフィールや写真などを変えても、KDPのアカウント情報(支払い・税務)は共通です。
この仕組みを理解せずに「別人のように見せたい」と思っても、システム的には同一人物の管理下にあります。
ここを混同すると、KDPのポリシーに抵触するおそれがありますので注意してください。
法人名義・家族名義を分けたい場合のルールと注意点
個人事業として出版を始めたあと、法人化したい、または家族の名義で別ジャンルを出したい、というケースもあります。
この場合は、法人名義で新たにアカウントを開設することが認められています。
ただし、同一人物が個人と法人の両方を運用することはNGです。
法人化する際は、既存の個人アカウントを閉鎖して法人名義に移行するか、正式に統合を依頼する形になります。
また、家族がそれぞれ自分の名義で出版すること自体は問題ありませんが、口座や端末を共用していると、システムが「同一人物」と誤認するリスクがあります。
住所・銀行情報・デバイスの紐づけには十分注意し、別管理を徹底しましょう。
この点は実務上でもよく誤解される部分なので、トラブルを避けたい方は必ず公式ヘルプで最新のガイドラインを確認しておくことをおすすめします。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
アカウント停止を防ぐための実務チェックリスト
KDPの運用で最も怖いトラブルが、突然のアカウント停止です。
意図せず規約に触れてしまったり、複数アカウントと誤認されることで停止されるケースも少なくありません。
ここでは、日常的に気をつけたいポイントを整理しながら、実務的なチェック項目をまとめます。
「知らなかった」では済まない部分も多いため、定期的な確認を習慣化しておくことが大切です。
複数アカウントと誤認されやすいケース
実際に多いのが、「複数アカウントを作るつもりはなかったのに、システムに重複と判断された」というパターンです。
たとえば、同じパソコンで別のAmazonアカウントにサインインしたままKDPにアクセスすると、同一端末から複数アカウントを利用しているように見なされることがあります。
また、家族と同じWi-Fi環境でそれぞれKDPを運用している場合も、IPアドレスが共通のため注意が必要です。
私自身も、過去にサポートから「アカウントの関連性が確認されました」という通知を受けた経験があります。
事情を説明して問題は解決しましたが、“意図していなくても”同一人物と見なされることがあるという点は覚えておくべきです。
住所・銀行口座・端末の共通利用によるリスク
KDPでは、住所・銀行口座・端末情報などをもとに本人確認を行っています。
そのため、複数アカウントでこれらの情報が一致すると、自動的に関連性が検出されることがあります。
たとえば、夫婦や家族で同じ住所・口座を使っている場合、Amazonのシステム上は「1人が複数運用している」と認識されやすい仕組みです。
口座の共用や、同じスマートフォン・PCで複数アカウントにログインする行為も避けたほうが安全です。
経験的には、法人化したあとに個人口座を残したまま出版を続け、支払いの名義不一致で一時保留になった例もあります。
運用上のミスを防ぐために、出版専用の端末や銀行口座を1つに統一しておくと安心です。
規約違反を避けるための安全な運用ポイント
まず大前提として、KDPの利用規約は英語版を含めて頻繁に更新されています。
特に「コンテンツポリシー」や「アカウント運用ルール」は、出版ジャンルや市場動向に合わせて細かく改訂されることがあります。
日本版のKDPヘルプページを定期的に確認し、古いブログ記事などの情報を鵜呑みにしないようにしましょう。
運用面では、以下の3点を守るだけでもリスクを大幅に減らせます。
1. ログインは常に公式サイト(kdp.amazon.co.jp)から行うこと。
2. 他人の名義・口座・端末を共有しないこと。
3. メールで届く警告や本人確認リクエストには必ず期限内に対応すること。
これらは一見当たり前のようですが、忙しいときに後回しにしがちな部分です。
安全な運用は「守りの積み重ね」です。
少しでも不安がある場合は、サポートへ事前に相談しておくのが確実です。
まとめ:KDPアカウントは一人一つ、名義はペンネームで柔軟に管理を
KDPでは、アカウントを分けずともペンネームで自由に名義を使い分けることができます。
それでも「新しいアカウントを作ったほうが整理しやすそう」と感じる人は少なくありません。
しかし、実務的にも規約上も、アカウントは1人1つが原則です。
トラブルを避けるためには、ジャンルや名義を工夫して1つのアカウントを安全に運用することが最善策です。
出版活動を長く続けたいなら、アカウント管理をルールに沿って行うことが何よりの基礎になります。
公式ヘルプで最新ルールを定期的に確認する習慣を
Amazonは定期的にKDPのポリシーを更新しています。
特に近年はAI生成コンテンツや翻訳出版など、新しいジャンルの扱いが追加されています。
そのため、過去に問題なかった内容でも、今後は制限対象になることもあります。
私自身も、以前書いた記事の一文を修正しただけで審査が長引いた経験があります。
このように、ルール変更は予告なく行われることがあるため、公式ヘルプの「最新情報」ページを月1回程度チェックするのが理想です。
更新履歴を確認しておくと、知らないうちに規約違反になるリスクを減らせます。
もし米国で売上がある場合の補足
基本的に本記事はAmazon.co.jp(日本)での出版を前提としていますが、もし米国や他国のストアで売上が発生している場合は、税務処理が異なります。
米国では「源泉徴収(Withholding Tax)」の制度があり、W-8BENフォームの提出が必要になることがあります。
日本居住者であっても、米国源泉税の還付を受けるには正確な申告が求められます。
この点は国際税務の範囲になるため、税理士やAmazonの公式ヘルプで最新情報を確認するのが確実です。
出版自体は同じアカウントで管理できますが、支払い条件や通貨の扱いが異なるため注意してください。
安全に運用するためには、「わからない部分をそのままにしない」ことが一番のリスク対策です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。