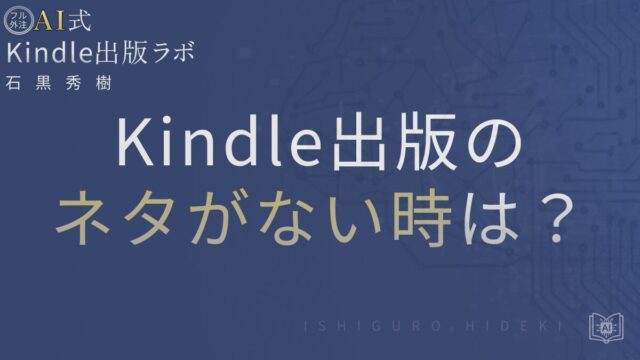Kindleで絵本を自費出版する方法とは?固定レイアウトから印税まで徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
絵本を自分の手で出版したいと思ったことはありませんか。
今では、出版社を通さなくてもAmazon Kindleを使えば個人で絵本を自費出版できます。
とはいえ、一般的な文章中心の電子書籍とは異なり、絵本ではレイアウトや画像サイズなど注意すべき点が多いのも事実です。
本記事では、初心者の方でも迷わず進められるように、絵本出版に適したKindle形式からKDP登録までの流れを丁寧に解説します。
▶ 人気ジャンルや成功事例を参考にしたい方はこちらからチェックできます:
出版ジャンル・成功事例 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で絵本を自費出版する基本の流れ
目次
- 1 Kindle出版で絵本を自費出版する基本の流れ
- 1.1 絵本出版に向くKindle形式とは?固定レイアウトの説明
- 1.2 絵本データを準備する:イラスト・ページ構成・サイズのポイント
- 1.3 KDPへの登録と出版手順:Amazon.co.jpでの電子絵本アップロード方法
- 1.4 ターゲット年齢・ジャンル・キーワードの選定方法
- 1.5 定価の決め方と印税率(35%/70%)の適用条件
- 1.6 表紙とプレビューがカギ:レビューを獲得する仕掛け
- 1.7 ファイルサイズ・画像解像度・固定レイアウトの落とし穴
- 1.8 KDP規約で注意:子ども向けカテゴリ・著作権・説明文のポイント
- 1.9 紙版(ペーパーバック)併売を考える際の補足事項
- 1.10 わたしの出版体験:最初の1冊で気づいた改善点
- 1.11 既読ページ数を伸ばすストーリー設計とシリーズ展開の可能性
- 2 まとめ:絵本をKindleで長く読まれる一冊に育てるために
絵本のKindle出版は、テキスト主体の電子書籍とは制作工程が少し異なります。
特にページごとのデザイン構成や画像の扱い方に気を配る必要があります。
ここでは、出版の全体像と、最初に知っておくべき基礎知識を整理します。
絵本出版に向くKindle形式とは?固定レイアウトの説明
Kindle出版で絵本を作る場合、もっとも重要なのが「固定レイアウト(Fixed Layout)」という形式を選ぶことです。
これは、ページの配置や画像の位置を固定したまま表示する方法で、絵本や写真集、漫画などに適しています。
通常のKindle本で採用される「リフロー型」は、文字サイズや行間が読者側で自由に変えられる仕様です。
小説やエッセイなどの文章主体なら便利ですが、絵や文字の配置がずれるため、絵本には向きません。
固定レイアウトを選ぶことで、作者が意図したページ構成をそのまま保てます。
ただし、固定レイアウトではデータ容量が大きくなりやすいため、KDPの容量上限(650MB)を超えないよう注意が必要です。
また、制作時はKindle Createなどの公式ツールを使うと、ページの中央揃えやトリミングのズレを防ぎやすくなります。
絵本づくりの基本的な制作手順は『 Kindle出版で絵本を出す方法とは?固定レイアウト制作と登録手順を徹底解説 』でも整理しています。
絵本データを準備する:イラスト・ページ構成・サイズのポイント
次に、出版前のデータ準備です。
絵本制作では、最初に全ページの構成を決めておくことが成功の鍵になります。
1ページあたりのサイズは、KDP推奨の比率に合わせるのが安心です。
たとえば、横長の絵本なら「2560×1600px」、縦長なら「1600×2560px」が目安です。
これを統一しておかないと、ページごとの余白が不揃いになり、印象が崩れてしまいます。
また、「電子書籍ではdpiよりピクセル寸法が重要です。端末比に合わせ長辺2,560px以上を目安に、圧縮で容量最適化(公式推奨値はヘルプ要確認)。」
経験上、スマートフォンで閲覧する読者が多いため、軽量かつ見やすい設定にすると表示が安定します。
テキストをイラストの上に配置する際は、フォントサイズや行間にも注意が必要です。
特に白背景に淡い文字色を使うと、端末によっては読みづらくなることがあります。
試しにプレビュー機能でスマホ・タブレット両方を確認しておくと安心です。
KDPへの登録と出版手順:Amazon.co.jpでの電子絵本アップロード方法
データが完成したら、いよいよKDP(Kindle Direct Publishing)で出版手続きを行います。
手順は大きく分けて3ステップです。
1. **KDPアカウントの作成**:Amazonアカウントでログインし、著者情報・支払い情報を登録します。
2. **書籍情報の入力**:タイトル、著者名、説明文(販売ページに表示されるあらすじ)を設定します。
ここでは、絵本の対象年齢やテーマを簡潔に書くと読者に伝わりやすくなります。
3. **ファイルのアップロード**:完成した固定レイアウトのEPUBファイルをアップロードし、プレビューでレイアウトを確認します。
この段階でページのズレ・余白・フォント崩れをチェックしておくことが重要です。
公式プレビューでは端末ごとの表示確認ができるため、必ず確認しましょう。
価格設定や印税率の選択もここで行いますが、初めての方は70%印税の条件(価格帯や地域)を満たしているかを公式ヘルプで確認してください。
出版ボタンを押すと、通常72時間以内に審査が完了し、Amazon.co.jp上に公開されます。
ページ比率の基準は『 Kindle出版の絵本サイズとは?最適比率と設定方法を徹底解説 』を参照すると統一しやすくなります
なお、実際に出版してみると、表紙画像のサイズや説明文の改行など、細かな修正が必要になることがあります。
公開後もKDPの「本棚」から再編集できるので、慌てず丁寧に確認するとよいでしょう。
Kindle絵本出版では、「作って終わり」ではなく、どのように届けるかが大切です。
どんなに良い内容でも、検索に引っかからなければ読者の目に触れません。
ここでは、絵本を見つけてもらうための設計と販売戦略を具体的に解説します。
ターゲット年齢・ジャンル・キーワードの選定方法
まず、絵本づくりの出発点は「誰に読んでもらいたいか」を明確にすることです。
たとえば「3〜5歳向けの動物絵本」や「小学生向けの道徳絵本」のように、年齢層やテーマを具体的に設定します。
これがあいまいだと、内容も販売ページもぼやけてしまい、検索にも弱くなります。
「カテゴリーの選択・表示は仕様変更があり得ます。現在の選択数や表示は属性・キーワード連動を含むため、最新仕様を公式ヘルプ要確認。」
たとえば「Children’s Picture Books」と「Animals」など、内容に最も近い項目を選びましょう。
後から変更も可能ですが、初期設定で適切なジャンルを選ぶことで、関連検索に表示されやすくなります。
年齢層の設定は『 Kindle出版の対象年齢とは?設定方法と注意点を徹底解説【Amazon.co.jp版】 』もあわせて確認しておくと安全です。
次にキーワード設定です。
Amazonの検索欄で「絵本 動物」「子ども 本」などと入力し、候補に出てくる語句を確認すると、実際に読者が検索しているワードを把握できます。
これらをタイトルや説明文に自然に盛り込むのがポイントです。
経験上、タイトルに1〜2語だけ主要キーワードを入れると、クリック率が上がりやすい傾向があります。
ただし、過剰に詰め込みすぎると不自然になるため、読みやすさを優先しましょう。
定価の決め方と印税率(35%/70%)の適用条件
価格設定は、多くの初心者が迷う部分です。
Kindleでは、印税率が「35%」と「70%」の2種類あり、販売価格によって自動的に切り替わります。
「日本(Amazon.co.jp)で70%を適用するには、税込250〜1,250円の価格帯に加え、KDPセレクト登録が前提です。配信コスト控除やその他条件もあるため最新の公式ヘルプ要確認。」
また、KDPセレクトに登録し、Amazon.co.jpを含む対象国で販売することも条件の一つです。
これを満たさない場合、自動的に35%の印税率になります。
絵本の場合、ページ数が多いほどデータ容量も大きくなり、制作に時間がかかります。
しかし、価格を高く設定しすぎると購買率が下がりやすくなるため、最初は400〜600円前後の価格帯が無難です。
実際に出版してみると、「内容より価格で購入をためらう読者」が一定数いることに気づきます。
最初は低価格で読者層を広げ、レビューが増えてから価格を調整するのも戦略のひとつです。
表紙とプレビューがカギ:レビューを獲得する仕掛け
読者が購入を決めるまでに、最も影響を与えるのが表紙とプレビュー画像です。
検索結果一覧で最初に目に入るのが表紙だからです。
表紙デザインでは、縮小表示でも文字や絵がはっきり見えるように作るのが基本です。
細かい線や淡い色合いは、サムネイルになると埋もれてしまうことがあります。
タイトルは太めのフォントで中央寄せにすると、全体が安定して見えます。
また、「プレビューは固定ページ数ではなく、作品の一部が割合ベースで表示されます(範囲や抽出は変更あり・公式ヘルプ要確認)。冒頭に魅力を集中させる設計が有効。」
そのため、冒頭の構成に一番力を入れましょう。
たとえば、物語のテーマがすぐ伝わる1ページ目や、印象に残るイラストを配置すると読者の離脱を防げます。
レビューを増やすコツとして、巻末に「読んでくれてありがとう」といった感謝のメッセージを添えるのも効果的です。
強制ではなく、自然にレビュー投稿を促すスタイルが好印象につながります。
このように、検索に強く、読者に愛される絵本を作るには、「誰に」「いくらで」「どんな見せ方で」届けるかを意識することが大切です。
それが結果的に、印税や販売継続率にもつながっていきます。
絵本のKindle出版は自由度が高い一方で、初めての方が見落としやすいルールや仕様も多くあります。
特にファイル形式・KDP規約・著作権は、知らずに進めると審査で差し戻されることもあるため、注意が必要です。
ここでは、よくある失敗や規約上の落とし穴を、実務経験を交えながら解説します。
ファイルサイズ・画像解像度・固定レイアウトの落とし穴
絵本を制作する際に最も多いトラブルが「ファイルサイズの超過」です。
KDPの上限は650MBですが、絵や写真が多い絵本では意外とすぐに達してしまいます。
高解像度の画像をそのまま使うと、プレビューで動作が重くなり、アップロード時にエラーが出ることもあります。
経験上、画像解像度は150〜300dpiを目安に調整するのがおすすめです。
特にスマートフォンで読まれることを前提にすれば、200dpi前後でも十分きれいに見えます。
JPEG形式で軽量化しておくと、出版時のトラブルを防げます。
もうひとつ注意したいのが「固定レイアウト」の扱いです。
固定レイアウトはページ構成を崩さずに表示できる反面、リフロー型(文字中心)とは仕様が異なります。
たとえば、フォントの埋め込みが正しくできていないと、一部の端末で文字化けするケースがあります。
KDP公式の「Kindle Previewer」を使うと、端末ごとの表示崩れを事前に確認できます。
見落としがちなのは、端末によっては「横スクロール表示」になる場合がある点です。
この現象は、見開き設定を解除すると改善されることがあります。
KDP規約で注意:子ども向けカテゴリ・著作権・説明文のポイント
次に、KDPの規約面で特に注意したいのが「子ども向け作品の扱い」です。
子ども向け絵本は審査がやや厳しく、内容やキーワードに問題があると非公開になることがあります。
たとえば、教育目的を装った広告やリンク誘導、過度な宣伝文句などはNGです。
また、登場キャラクターやイラスト素材を使用する場合は、著作権の確認が必須です。
フリー素材でも「商用利用可」と明記されていないものは避けましょう。
KDPでは著作権侵害が疑われた時点で販売停止になることがあり、再審査には時間がかかります。
説明文(商品ページ)にも注意が必要です。
公式ルールでは、価格やキャンペーン情報、他サイトへの誘導を含めてはいけません。
また、対象年齢や内容を正直に記載することが信頼につながります。
私の経験では、説明文に「この絵本は〜歳のお子さま向けです」と一言入れるだけでも購入率が上がりました。
シンプルですが、読者に安心感を与える要素です。
紙版(ペーパーバック)併売を考える際の補足事項
最後に、電子書籍とあわせてペーパーバック(紙の本)を併売したい場合の注意点です。
「ペーパーバック印税は『販売価格×60% − 印刷コスト』が基本式です。原価を踏まえ価格設定を。」電子版よりも利益率は低くなります。
ただし、ギフト用途や読み聞かせ向けに紙版を希望する読者も一定数いるため、ブランディングには効果的です。
紙版を作成する際は、KDP専用の「印刷コスト計算ツール」でページ数とカラー設定を事前に確認しておきましょう。
特にフルカラー印刷では原価が上がるため、価格設定を慎重に行う必要があります。
もう一点、電子書籍と紙版は内容・タイトル・著者名を完全一致させることが重要です。
これが異なると、Amazon上で同一作品として統合されず、レビューが別々に表示されてしまいます。
登録時にASINの統合をリクエストできるため、後からでも修正可能です。
まとめると、KDPで絵本を出版する際は「ファイル構成」「規約」「形式」の3点を丁寧に確認することが、長く販売を続けるための基本です。
出版後の修正も可能ですが、初回で正確に設定しておく方が後の手間を減らせます。
絵本をKindleで自費出版する人の中には、「思ったより読まれない」「印税がほとんど入らない」と感じる方も少なくありません。
しかし、実際に売れ続ける絵本には、いくつか共通したポイントがあります。
ここでは、実際の体験と他の著者の成功例をもとに、印税を伸ばすためのコツを解説します。
わたしの出版体験:最初の1冊で気づいた改善点
私が初めて絵本をKDPで出版したとき、最初の売上はほぼゼロでした。
理由は明確で、ターゲットを曖昧にしたまま制作していたからです。
当時は「誰でも読めるように」と考えていましたが、結果的に誰にも刺さらない内容になってしまいました。
そこで次に意識したのが「読む人を明確にイメージすること」です。
たとえば「3歳児が寝る前に読む」「ママが読み聞かせに使う」など、具体的なシーンを想定しました。
それに合わせてページ数を短くし、リズム感のある文に変更したところ、読まれる数が徐々に伸びていきました。
もう一つの改善点は、表紙とタイトルを見直すことです。
最初の作品では、抽象的なタイトルを使ってしまい検索に引っかかりませんでした。
「やさしいどうぶつの絵本」や「はじめての色あそび」など、わかりやすく温かみのある言葉を入れることでクリック率が明らかに変わりました。
このように、作品内容そのものだけでなく「見つけてもらう工夫」が印税アップには欠かせません。
KDPのダッシュボードで日ごとのページ読了数を確認し、改善を繰り返すことが大切です。
既読ページ数を伸ばすストーリー設計とシリーズ展開の可能性
KDPの印税収益は、「Kindle Unlimited」での既読ページ数によっても大きく変わります。
つまり、「最後まで読まれる絵本」を作ることが重要です。
短くてもストーリーに流れがあり、読後にもう一度開きたくなる構成が理想です。
たとえば、「季節ごとの絵本」や「キャラクターシリーズ」を展開する方法も効果的です。
同じ登場キャラクターを使えば、読者が続きに興味を持ちやすくなります。
また、シリーズタイトルに「Vol.1」「春編」などの表記を入れると、Amazon内での関連性も高まりやすくなります。
経験上、1冊ごとにテーマを絞ると、読者が求めるシーンでヒットしやすくなります。
「夜寝る前」「親子で読む」「数を数える」など、明確な目的をもった作品は長く売れ続けます。
ストーリーの最後に「次回作の予告」や「登場キャラの紹介ページ」を入れるのもおすすめです。
これにより、リピーターが増えやすくなり、結果的に既読ページ数と印税が安定して伸びていきます。
まとめ:絵本をKindleで長く読まれる一冊に育てるために
絵本出版で継続的に印税を得るためには、「内容」「見せ方」「継続性」の3つが鍵になります。
まずはターゲットを明確にし、わかりやすいタイトルと表紙で届けたい層に届くように工夫しましょう。
そのうえで、ストーリーや世界観に一貫性を持たせ、シリーズ化を意識することが長期的な読者づくりにつながります。
一度出版して終わりではなく、「作品を育てる」という視点で改善を重ねることが成功の近道です。
最後に、出版後のレビューや読者の反応を分析し、改善を重ねることを忘れないでください。
小さな工夫の積み重ねが、やがてAmazonランキングに反映され、印税アップへとつながります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。