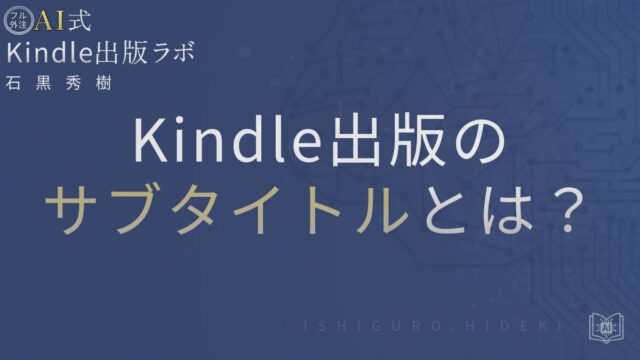Kindle出版の値段はどう決める?70%印税と価格設定を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版をしようとしたとき、多くの人が最初につまずくのが「値段をいくらに設定すればいいのか」という悩みです。
価格によって印税率だけでなく、読者の購入意欲や検索での露出にも影響が出るため、なんとなくで決めてしまうのはリスクがあります。
この記事では、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の公式仕様を前提にしつつ、私自身が何度も出版・価格調整を行ってきた経験も踏まえて、「どう考えて設定すべきか」を整理して解説します。
特に初心者の方にありがちな「70%印税がいつでも選べると思ってしまう」「最初から高く設定して読まれなくなる」という落とし穴も避けられるよう構成しています。
最後まで読めば、価格に迷う状態から抜け出し、根拠を持って設定できるようになります。
▶ 出版の戦略設計や販売の仕組みを学びたい方はこちらからチェックできます:
販売戦略・集客 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で値段に迷う人が知るべき結論とこの記事の全体像
目次
Kindle出版の価格は「適当に決めても何とかなるもの」ではなく、公式ルールを理解したうえで、自分の出版目的に合わせて戦略的に決める必要があります。
価格の基本ルールをまとめて確認したい場合は『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版の価格設定とは?70%印税と最適価格の決め方を徹底解説』が役立ちます。
さらに、印税率(70%か35%か)は価格帯とKDPセレクト登録によって変わるため、条件を知らないまま設定すると損をする可能性があります。
この記事では、まずこの「価格で結果が変わる現実」を理解してもらうことから始め、そのうえでロイヤリティ制度→価格帯→目的別戦略という流れで整理していきます。
価格設定に迷っている方は、まず「何が自分の収益や読者の反応を左右するのか」を知るところから始めましょう。
Kindle出版は「価格戦略」で印税と露出が大きく変わる
Kindle本は価格の設定によって、印税の受け取り額だけでなく、読者の購入判断やランキングでの露出にも大きな差が生まれます。
たとえば、500円程度の本がクリックされやすいジャンルもあれば、内容によっては1,000円以上でも売れるケースもあります。
私自身、同じ内容量でも価格を300円→550円→800円とテストしたことで「売れやすい価格帯の感触」が変わることを実感しました。
つまり、価格は「ただの数字」ではなく「読者が価値を感じる指標」でもあるということです。
そのため、本記事では感覚ではなく「制度」と「戦略」の両面から整理していきます。
検索キーワード「Kindle出版 値段」の本当の悩みは何か
「Kindle出版 値段」で検索する人の多くは、「いくらにすれば売れるのか」「70%印税はどうすれば適用されるのか」「相場ってあるのか」といった不安や疑問を抱えています。
特に初心者の方ほど「正解があるなら知りたい」と考えがちですが、実際には「公式ルールの範囲内で目的に応じた設定」をする必要があります。
また、値段は後から変更できますが、「最初の価格で印象が決まり、レビュー数にも影響する」ことを知らずに損をしてしまう人もいます。
このような悩みを解消するために、次の章からはロイヤリティ制度と価格の関係を丁寧に整理していきます。
Kindle出版の価格設定に影響するロイヤリティ(70%と35%)
印税率の仕組みを詳しく理解したい場合は『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版のロイヤリティとは?70%印税の条件と配信コストを徹底解説』で確認できます。
Kindle出版では、価格をいくらにするかを考える前に、「印税率(ロイヤリティ)」の仕組みを理解することが欠かせません。
AmazonのKDPでは、電子書籍の印税は「70%」か「35%」のどちらかになりますが、これは自分で自由に選べるわけではなく、条件によって自動的に決まります。
ここを理解しておかないと、「70%を選んだつもりが35%になっていた」というケースが実際によくあります。
また、私自身も初期のころは70%を適用できる条件を見落としていて「思ったより収益が低い」と感じた経験があります。
まずは70%印税の条件から見ていきましょう。
日本のKDPで70%印税を選べる条件(KDPセレクト登録と価格帯)
日本のAmazon.co.jpで70%印税を適用するには、主に次の2つの条件を満たす必要があります。
1.KDPセレクトへの登録が必要(日本・ブラジル・メキシコ・インドの場合)
2.価格が指定の範囲(日本円でおおむね250円〜1,250円)に入っていること
この条件を知らずに価格を極端に低くしたり、高すぎる価格をつけてしまうと、70%印税を適用できなくなります。
特に日本マーケットで出版する場合、「70%印税はKDPセレクト先行販売が前提」という点を理解しておくことが重要です。
KDPセレクトは90日間のAmazon独占配信プログラムです。KUの閲読収益が加算されます(公式ヘルプ要確認)。
この条件に抵抗がある人もいますが、初心者の方はまず70%印税を取りやすい環境を整えるためにもセレクト登録を前提にするケースが多いです。
¥1,251以上は70%の対象外となり35%になります(税抜基準・公式ヘルプ要確認)。
35%印税になるケースと価格設定の自由度
70%の条件を満たさない場合、自動的に35%印税になります。
たとえば、以下のような場合が該当します。
・KDPセレクトに登録していない
・価格が99円〜249円または1,251円以上
・一部の対象外地域でのみ販売している
35%印税でも出版は可能であり、最初から低価格で拡散を狙う戦略もあり得ます。
ただし、35%の価格帯は自由度が高い代わりに収益率が低くなるため、販売部数をある程度見込める人や、フリーミアム的な導線設計がある人向けといえます。
印税率の選択は「どちらが得か」ではなく「自分の出版目的と価格戦略に合っているか」で判断することがポイントです。
印税計算の基本と「実際の受け取り額」の考え方
印税は「希望小売価格 × 印税率」というシンプルな計算で算出されます。
例:500円 × 70% → 350円が受け取り額(税・為替などは別途考慮)
ここで注意すべきなのは、70%印税の場合のみ「配信コスト(配信データ量に応じた手数料)」が差し引かれる点です。
文章中心の本であれば配信コストはわずかですが、画像が多い本では印税に影響することもあります。
また、アメリカなど海外での販売がある場合は為替レートによって日本円での受取額が変動します(国内出版を前提とする場合は補足程度で問題ありません)。
印税の仕組みを理解しておくことで、単に「高くすれば儲かる」ではなく、「読者に選ばれる価格帯の中で最大化を目指す」という視点で価格戦略を立てやすくなります。
このように、ロイヤリティ構造を理解することは、今後の価格設定やシリーズ展開を考えるうえでの土台となります。
次の章では、実際に設定できる価格帯や、市場でよく採用される価格レンジについて整理していきます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle出版で設定できる価格帯と「よくある価格の範囲」
ここでは、Kindle出版で実際に設定できる価格帯や、市場でよく採用される価格の傾向について整理します。
前の章で印税率の仕組みを理解したことで、「どの範囲で価格を決められるか」という視点が持ちやすくなっているはずです。
ここを理解しておくと、戦略的な価格設定だけでなく、「なぜその価格がよく使われるのか」も納得できるようになります。
公式で認められている価格帯(日本円での最低価格〜上限価格)
AmazonのKDPでは、電子書籍の価格を日本円で「99円〜20,000円」の範囲で設定できます。
この範囲外の価格はシステム上入力できないため、まずはこの上下限を前提として考える必要があります。
ただし、99円に設定するケースはごく一部で、セールやキャンペーン的な目的で使われることが多い印象です。
一方で、10,000円を超えるような価格帯も技術系・教材系など一部ジャンルでは存在しますが、初心者向けコンテンツや一般読者向けノウハウ系では現実的ではありません。
特に「最初の1冊」や「集客を兼ねた出版」の場合は、自由に設定できるとはいえ、「読者が心理的に受け入れやすいレンジ内」で決めることが重要です。
この範囲を理解したうえで、次に印税率の観点で価格帯を整理します。
70%印税対象となる価格帯の具体例(¥250〜¥1,250)
日本向けのKDPにおいて、KDPセレクト登録済みの電子書籍が70%印税を適用される70%印税の対象価格帯は¥250〜¥1,250(税抜)です。最新の範囲は公式ヘルプ要確認。
この範囲外、たとえば200円以下や1,500円以上にすると、自動的に35%印税となってしまいます。
ここを理解しておくと、「例えば価格を700円と設定した場合は70%印税対象になるが、1,300円にすると35%に落ちてしまう」といった判断がしやすくなります。
私の経験では、最初から1,250円ぎりぎりを狙うより、500〜800円の間で調整した方がレビュー獲得や読者数の増加につながりやすいことが多いです。
この章の目的は「どの価格帯なら選択肢に入るか」を理解することなので、ここまでを整理できた時点で戦略に応じた調整がしやすくなります。
市場で多い価格帯と「500円前後が選ばれる理由」
実際のKindleストアでは、ノウハウ系・実用書系の個人出版で多く見られる価格帯は「300〜800円」の範囲です。
特に500円前後がよく選ばれるのは、以下のような理由があります。
・ワンコイン感覚で手を出しやすい心理的ライン
・ランキング上位でもこの価格帯が多く、読者の期待値に合う
・1,000円未満であれば返品率が低いことが多い
・70%印税の条件にも収まりやすい
私の場合も、300円で出した本と550円で出した本を比較すると、550円のほうが「きちんと作られた本」という印象を持たれやすく、結果的に購入率も高まりました。
もちろん、すべての本が500円前後であるべきという話ではなく、「読者が価格と内容を照らして納得できるかどうか」が重要です。
絶対的な「相場」に合わせるのではなく、自分のコンテンツ価値が市場のどこに位置するかを判断することが大切です。
この理解をもとに、次の章では「目的に合わせた価格戦略」について掘り下げていきます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版の価格をどう決めるか:目的別のおすすめ戦略
ここからは、「公式価格帯の中でどう戦略的に価格を設定するか」という視点で整理していきます。
価格に正解はありませんが、目的によって適切なレンジは変わります。
私自身も「読者を増やしたい時期」と「収益を安定させたい時期」では価格設定を変えていました。
まずは出版する目的をはっきりさせ、その目的に合わせた価格にすることが大切です。
「読者獲得を優先」する場合の低価格(リード獲得型)
「まずは読者を増やしたい」「レビューを集めたい」という段階では、低価格戦略が有効です。
特に、300円~500円程度に設定しておくと、いわゆる“ワンコイン感覚”で購入されやすく、クリック率も高くなります。
実際に私が初めて出版した本も、最初は350円で設定し、レビューが増えてから価格を見直しました。
ただし、安すぎると「内容が薄いのでは?」と思われることもあります。
目的が読者獲得であっても「低価格=安売り」ではなく「取りやすく、信頼を得るための価格」と考えると失敗しにくくなります。
また、シリーズ展開やメルマガ誘導など、次のステップにつなげる導線がある場合は、この戦略が特に効果的です。
「収益を取りに行く」場合の中価格〜継続販売型
「収益をしっかり取りたい」「単品で売れるコンテンツとして成立させたい」という場合は、500円〜800円程度がひとつの目安になります。
この価格帯は70%印税が適用されるうえ、内容に対して適正な価値があると判断されやすく、リピーター読者の信頼も得やすくなります。
たとえば、750円で70%印税の場合、1冊あたり約525円が収益になるため、販売数がそこまで多くなくとも利益を確保できます。
私の経験でも、内容がしっかりしている本ほど、500円台より600円~800円の範囲のほうが「想定読者の満足度」と「販売数」がバランスよく安定する傾向がありました。
この戦略を採用する場合は、価格に見合う価値(ボリュームや専門性など)を伝えるタイトルや説明文の工夫も重要です。
シリーズ出版で「1冊目だけ低価格」にする方法
シリーズ前提で出版する場合は、「1冊目だけ低価格」「2冊目以降を適正価格」という二段構えの戦略が効果的です。
最初の1冊を300円〜400円程度に設定することで読者に入り口としての安心感を与え、続編や関連テーマの本に繋げやすくなります。
この方法は、いわゆる“体験版+本編”という構造にも似ており、読者との信頼関係をつくりながら単価の高い本へステップアップさせる形です。
実際に私が行ったケースでも、1冊目を350円、2冊目を680円、3冊目を780円と段階的に設定することで、シリーズ全体の売れ行きが安定しました。
注意点として、最初の本も「安いから買われる」のではなく「内容がしっかりしているから次も買われる」という前提を忘れないことが大切です。
このように、価格は「一度決めたら終わり」ではなく、出版目的・読者の反応・シリーズ展開によって柔軟に調整することが大切です。
次の章では、価格設定の実際の入力方法や変更時の注意点について見ていきます。
KDPの価格設定手順と変更時の注意点
ここまでで「価格はどう考えるべきか」という戦略的な視点を整理できました。
次は、実際にKDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)で価格を入力する方法と、変更時に注意すべきポイントを解説します。
初心者の方からよく受ける質問として、「どこで価格を設定するのか分からない」「価格を変えたのに反映されない」というものが多くあります。
また、プロモーション機能やKindle Unlimited(読み放題)との関係も価格によって影響を受けるため、ここでまとめて理解しておくと後のトラブルを防げます。
KDP本棚での「権利と価格設定」入力手順
Kindle本の価格は、KDP本棚から該当するタイトルを選び、編集画面の「権利と価格設定(Pricing)」タブで入力します。
基本的な流れは以下の通りです。
1.KDP本棚で対象タイトルの右側にある「…」から「編集」を選択
2.「権利と価格設定」タブを開く
3.「ロイヤリティプラン(35%または70%)」を選択
4.「希望小売価格(日本円など)」を入力
5.他地域への価格は自動換算または手動設定が可能
6.内容を確認して「保存して公開」をクリック
このとき、70%印税を選択するためには「価格が規定範囲内であること」と「KDPセレクトに登録していること」が前提となります。
セレクト登録をしていない場合、70%の選択肢は表示されず、自動的に35%のみ選べる状態になります。
慣れてくると5分程度で設定できますが、最初はロイヤリティの表記や換算価格に戸惑う人も多いです。
入稿後の確認作業については『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説』が補足になります。
価格変更後の反映タイミングと時間差に関する注意
価格を変更して公開ボタンを押すと、通常は数時間~24時間程度で反映されます。
ただし、Amazon.co.jpだけでなく、他のマーケットにも同時に反映される関係でタイムラグが発生するケースがあります。
特に深夜帯や週末など、反映までに時間がかかるタイミングもあるため、「すぐに変わらない=失敗」と焦らないことが大切です。
私の経験では、価格変更直後に何度も更新を押すよりも、1日程度は様子を見るほうが確実です。
また、一時的に旧価格と新価格が混在して表示されることもあり得ますが、最終的には自動的に新価格に統一されます。
反映待ちの段階でSNSなどに「価格変更されました」と告知してしまうと、「まだ変わっていない」という問い合わせにつながりやすいため注意してください。
価格に応じたプロモーションやKindle Unlimitedとの関係
KDPセレクトに登録している場合、価格帯によって利用できるプロモーション機能が変わります。
特にKindle Countdown DealsはAmazon.com/.co.ukのみで実施可能です。Amazon.co.jpでは利用不可です。
無料キャンペーンは各90日間につき最大5日まで利用可能です(公式ヘルプ要確認)。
また、Kindle Unlimited対象の場合、価格による印税収益に加えて、読み放題ページ数(KENP:ページ換算)による収益も得られます。
そのため、低価格でもKU読み放題でページ単位の収益が積み上がるケースもあります。
一方で、KUを利用しない単品販売型の戦略では、価格の妥当性が売上を左右しやすいため、プロモーション戦略と価格設定をセットで考えることが重要です。
「価格が高すぎて読み放題中心にシフトされてしまう」「低価格のまま値上げのタイミングを逃す」といった失敗もあるため、販売状況を見ながら適宜再設定していく意識が大切です。
ここまでで「価格設定の手順」と「変更時の注意点」「プロモーションとの関係」まで理解できました。
次の章では、設定時に陥りやすい失敗や注意すべき落とし穴について解説します。
「Kindle出版の値段」で失敗しやすい3つの落とし穴
ここでは、Kindle出版で価格を設定する際に、多くの初心者が陥ってしまう代表的な失敗を3つに絞って解説します。
どれも「知らなかった」「なんとなくで決めてしまった」ことで損をするケースです。
私自身も初期の出版でいくつか経験し、「もっと早く気づいていれば…」と思ったポイントばかりです。
これから価格を決める人は、あらかじめこうした落とし穴を理解して避けるだけで、スタート時点から損失を防げます。
70%印税の条件を満たさずに損をするケース
最も多い失敗が、「70%印税を適用したつもりが、実際には35%になっていた」というケースです。
原因はシンプルで、「KDPセレクトに登録していなかった」「価格が250円未満または1,250円以上だった」など、条件を正しく理解していないことによります。
たとえば、「安くして読者を集めたい」と思って200円に設定してしまうと、それだけで印税率が35%になります。
同じ300円でも、70%印税なら1冊あたり210円、35%印税なら105円と、販売数が同じでも収益がほぼ半減します。
「印税率は自由に選べる」と思い込んでいる人もいますが、実際は価格とセレクト登録が大きく関係しています。
この点を理解せずに出版すると、後から設定を変えたくてもレビューや販売履歴の関係で動きにくくなってしまいます。
相場だけを見て自分の本に合わない価格をつけるリスク
「他の著者が500円だから自分も500円にしておけばいいだろう」という考え方も危険です。
なぜなら、ジャンル・読者の習慣・情報の専門性・ブランド力・表紙のクオリティなどによって、適正価格は大きく変わるからです。
たとえば、実用系でも「入門書」と「専門性の高い解説書」では、読者が期待する価格レンジが異なります。
また、レビュー件数が多い著者は高めの価格でも売れやすく、新規著者は同じ価格帯でも「初めてだから少し迷う」読者が増えがちです。
相場は“参考値”であって“正解”ではありません。むしろ自分の読者がどんな価格で安心して買えるかを考えるほうが重要です。
「売れている価格帯」を見ることは大切ですが、それを鵜吞みにすると「読者ニーズとのミスマッチ」に気づきにくくなります。
「高すぎる=売れない」だけでなく「安すぎる=品質を疑われる」問題
価格設定の初心者がよく思い込むのが、「安ければ買われるだろう」という思考です。
しかし、実際には「安すぎる本」は「内容が薄いのでは?」「雑に作られていそう」と疑われる可能性があります。
私自身、300円で出していた本より、550円に調整したあとで購入率が上がったケースがありました。
読者は価格だけではなく、価格とタイトル・レビュー数・説明文との“バランス”を見て判断します。
また、価格が安すぎると「読み放題で読めばいいか」と判断されやすく、収益性が落ちる場合もあります。
一方で高すぎる価格を設定すると「購入前に比較される確率」が高まり、カートに入れられても購入決定まで至らないケースが増えます。
結局のところ、「売れる価格帯」は読者の期待と本の価値が一致したときに成立します。
そのため、「安さで勝負する」のではなく、「内容に合った価格を自信を持って提示する」ことが長期的な出版戦略につながります。
次の章では、電子書籍とペーパーバック(紙)で価格の考え方がどう異なるのかも補足します。
電子書籍とペーパーバックで価格設定の考え方は異なるのか(補足)
Kindle出版の中心は電子書籍ですが、最近はペーパーバックも手軽に出版できるようになり、価格設定をどう考えるか悩む方も増えています。
ここでは、電子書籍を基本としつつ、ペーパーバック(紙)との考え方の違いを補足します。
「どちらを先に出すべきか」「紙では価格をどう設定するべきか」といった判断にも役立つ視点です。
ペーパーバック印税は印刷コスト控除後に50%または60%(日本の場合)
ペーパーバックの印税率は、電子書籍とは仕組みが異なります。
日本のAmazon.co.jpの場合、希望小売価格が1,000円未満なら50%、1,000円以上なら60%が印税率になります(ただし、印刷コストが控除された後の金額が対象)。
ここで注意すべきなのは、電子書籍のように「価格 × 印税率」で単純に計算できない点です。
たとえば、1,200円のペーパーバックで印刷コストが300円かかった場合、
(1,200円 − 300円)×60%=540円が印税額となります。
電子書籍よりも製造原価が発生するため「高めの価格でないと収益が取りにくい」のが特徴です。
そのため、ペーパーバックの価格は電子書籍より高めに設定されることが多く、1,000円〜2,000円台が中心になります。
電子書籍を基準に収益性・出版ステップを比較する
まず電子書籍のみで出版し、その後ペーパーバックを追加する流れは非常に一般的です。
電子書籍は印刷コストがないため、500円前後でも70%印税を得られるケースが多く、「売れた数 × 印税」がそのまま収益につながりやすい構造です。
一方、ペーパーバックは「手に取る価値」「物理的な所有感」「信頼性」を評価されることが多く、セミナー講師や専門家プロフィールとの相性が良いです。
電子書籍は収益性とスピード重視、ペーパーバックは信用性と付加価値重視という役割分担で考えると判断しやすくなります。
私自身も最初は電子書籍のみで販売し、評価が安定してからペーパーバック版を追加することで「紙が欲しかった」という読者の声に応え収益を広げられた経験があります。
どちらが正解というよりは「段階戦略」として使い分ける意識が大切です。
まとめ:Kindle出版の値段は「公式条件+目的別戦略」で決める
Kindle出版の価格設定は「いくらが正解か」ではなく、「どんな目的で、どの印税条件を踏まえて、どの市場に合わせるか」によって決まります。
まずは「価格帯と印税率の仕組み」を理解し、そのうえで「読者獲得型」「収益型」「シリーズ導線型」などの目的別に戦略を立てることが大切です。
特に、70%印税の条件を満たさずに出版してしまうと、販売が伸びたあとに損をしていたことに気づくケースが多いので注意が必要です。
また、「安いから買われる」「高いから売れない」という単純な話ではなく、価格は「内容への期待値」「レビュー数」「著者の信頼性」と組み合わせて考える必要があります。
価格は一度決めたら終わりではなく、「読者の反応」「レビュー」「販売数」を見ながら少しずつ調整していく改善型プロセスです。
最適な価格は一発で決めるものではなく、試行と検証を通じて見つけていくものです。
この記事の内容を参考にしながら、あなたの出版目的に合った価格設定を行い、継続的に見直しながらブラッシュアップしていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。