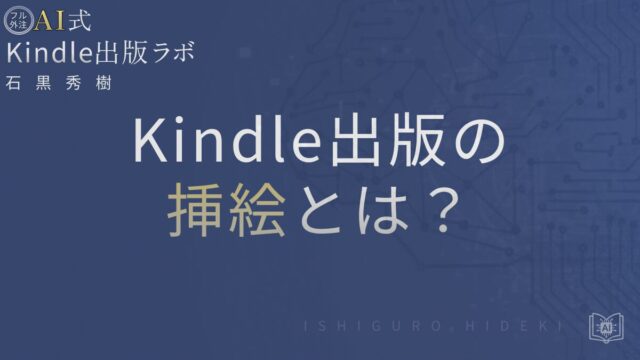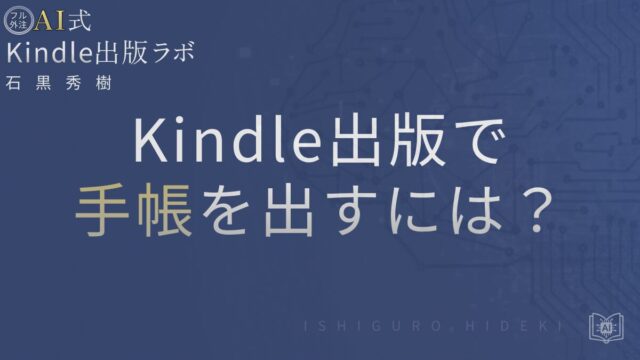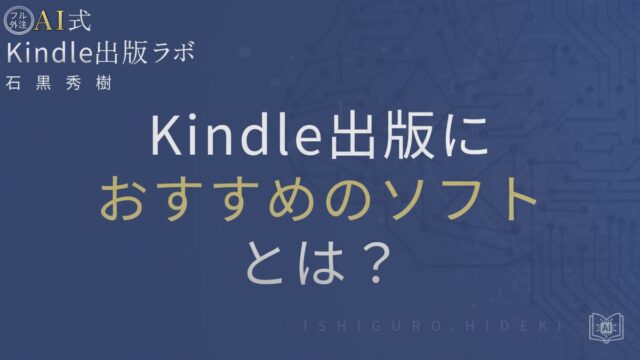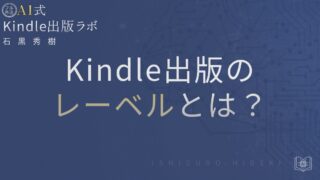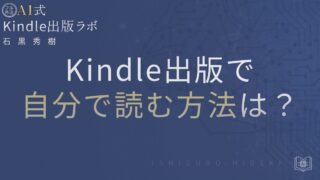GoogleドキュメントでKindle出版する方法とは?無料でできる手順と注意点を徹底解説

のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
「GoogleドキュメントでKindle出版できるの?」
この疑問は、初めて電子書籍を出そうとする人が最初に抱くものです。
実際、Wordを持っていなくても、Googleドキュメントを使えば無料で原稿を書き、KDP(Kindle Direct Publishing)に入稿することが可能です。
この記事では、クラウド執筆の利点から実際の入稿可否、そして初心者がつまづきやすい制度面まで、最新の日本向けKDP仕様に沿って解説します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「GoogleドキュメントでKindle出版」が注目されているのか
目次
Googleドキュメントは、無料で使えるクラウド型の文章作成ツールです。
パソコン・スマホ・タブレットのどれからでもアクセスでき、データが自動保存されるのが大きな強みです。
この「手軽さ」と「クラウド環境」が、Kindle出版を目指す個人著者の間で注目を集めています。
特に近年は、在宅での副業やスモールビジネスの一環として出版する人が増え、Wordを購入せずに済む方法として選ばれています。
クラウド執筆のメリットとWord不要の背景
Googleドキュメントの最大の利点は、「どこでも書ける」ことと「自動保存」です。
電車の中やカフェでもスマホで続きが書けるため、思いついたアイデアをすぐ形にできます。
Wordのようにファイル保存のトラブルを気にする必要がなく、共同編集も簡単です。
また、Kindle出版ではWord形式(.docx)やEPUB形式が主に推奨されていますが、Googleドキュメントはそのまま.docx形式に変換可能です。
つまり、Wordがなくても原稿をKDP対応形式に書き出せるのです。
一方で、Googleドキュメントの書式機能はWordに比べてやや制限があり、表組みや段組みを多用する本には不向きです。
しかし、文章中心のビジネス書やエッセイであれば十分対応できます。
検索キーワード「Kindle出版 Googleドキュメント」から読み取る著者の本音
実際に「Kindle出版 Googleドキュメント」で検索する人の多くは、Wordを持っていない、または使い慣れていない層です。
無料で完結できる方法を探しており、「Googleドキュメントだけで出版できる?」という実務的な答えを求めています。
もう一つの本音は、「できれば追加ツールを使わず、最短で出版したい」というものです。
Kindle CreateやEPUB変換ツールの存在は知っていても、操作が複雑だと感じている人が多い印象です。
そのため検索上位の記事では、「Googleドキュメントで原稿を作成→.docxで出力→KDPへアップロード」というシンプルな手順を示した構成が多く、読者の実用ニーズに即しています。
日本向けKDPで“Googleドキュメント→出版”が可能か?制度・仕様の確認
結論から言うと、Googleドキュメントで作成した原稿をKindle出版に使うことは可能です。
ただし、「Googleドキュメントのまま」直接アップロードすることはできません。
一度、Word形式(.docx)やEPUBに書き出してからKDPに入稿する必要があります。
KDPの日本版ガイドラインでは、日本語書籍のPDF入稿は推奨されていません。
フロー型の日本語電子書籍ではPDF入稿は非推奨です。docxやEPUBが推奨形式で、PDFは再現性に課題があります(固定レイアウト等は公式ヘルプ要確認)。
そのため、Googleドキュメントで作成した原稿は必ず.docxやEPUB形式でダウンロードして使いましょう。
実務的には、「見出しスタイル」「改ページ」「画像の挿入位置」をKDPプレビューで確認するのが重要です。
公式の仕様上は対応していても、実際のKindle端末では余白や改行の見え方が異なることがあります。
なお、ペーパーバック出版を検討する場合は、ページ数や余白設定が必要となり、PDF入稿が基本です。
この場合はGoogleドキュメントのままでは対応しにくいため、WordやCanvaなど別ツールの併用をおすすめします。
このように、Googleドキュメントを活用したKindle出版は、コストを抑えつつスピーディーに実現できる方法です。
しかし、仕組みや仕様を正しく理解しておくことで、後から修正に追われるリスクを防げます。
対応しているファイル形式やPDF入稿の注意点を全体像から押さえたい方は、『Kindle出版のデータ形式とは?対応ファイルとアップロード手順を徹底解説』もあわせて読んでおくと安心です。
Googleドキュメントから電子書籍(Kindle本)を出す基本ステップ
Googleドキュメントを使ったKindle出版の流れは、大きく3つのステップに分かれます。
まず原稿を書き、次にWord形式(.docx)で保存し、最後にKDP(Kindle Direct Publishing)にアップロードするだけです。
これらを順番に進めることで、Wordを使わずに電子書籍を完成させることができます。
ただし、それぞれの段階で注意すべきポイントがいくつかあります。
原稿を書く:Googleドキュメントでの書き出し準備
最初のステップは、原稿をGoogleドキュメントで執筆することです。
Wordと同様に見出し、段落、箇条書き、画像の挿入などが可能なので、使い慣れれば十分に出版用の原稿を作れます。
特に重要なのが、「見出しスタイル」を正しく設定することです。
「見出し1」「見出し2」を使って章立てを作っておくと、後で自動目次を生成できるため、Kindle本の読みやすさが格段に上がります。
手動で太字にするだけでは目次として認識されない点に注意しましょう。
もう一つのポイントは、改ページを明示することです。
改ページを挿入しておかないと、KDP側でページ区切りがずれてしまうことがあります。
これはプレビュー時に多くの初心者が戸惑う部分なので、執筆段階で意識しておくと安心です。
また、画像を使う場合は解像度に気をつけましょう。
Googleドキュメント上ではきれいに見えても、Kindle端末ではぼやけることがあります。
目安として、短辺で1000ピクセル以上ある画像を用意すると安全です。
.docx形式でダウンロード:GoogleドキュメントからWord形式へ変換
原稿が完成したら、次はKDPが受け付ける形式に変換します。
Googleドキュメントのメニューから「ファイル」→「ダウンロード」→「Microsoft Word(.docx)」を選びます。
これでKDPにアップできるWordファイルが生成されます。
この手順は非常にシンプルですが、ここで気をつけたいのは「余白・段落の崩れ」です。
GoogleドキュメントとWordでは行間の処理や余白の解釈が微妙に異なるため、変換後にレイアウトが崩れることがあります。
実務的には、一度Wordで開いて軽く整えるか、KDPのオンラインプレビューで直接確認するのがおすすめです。
また、ダウンロード時にファイル名を半角英数字にしておくと、アップロード時のエラーを防げます。
これは意外と見落とされがちな小さなポイントです。
アップロード:日本のKindle Direct Publishing(KDP)へ入稿する流れ
最後に、KDPの管理画面で新しい電子書籍を作成します。
Amazonアカウントでログインし、「新しいタイトルを追加」をクリックします。
タイトルや著者名、説明文を入力した後、「電子書籍のコンテンツ」欄で先ほど保存した.docxファイルをアップロードします。
アップロード後はKDPのオンラインプレビューで確認できます。必要に応じてデスクトップ版Kindle Previewerでも再現性を確認してください。
ここでレイアウトの確認を必ず行ってください。
特に目次リンクや改ページ、画像の位置はずれやすいため、事前確認が不可欠です。
プレビューで崩れを見つけた場合は、Googleドキュメントで修正→再ダウンロード→再アップロードの流れで調整します。
少し面倒に感じるかもしれませんが、このひと手間で読者の体験が大きく変わります。
また、KDPの審査は通常72時間以内に完了します。
この間にAmazonの自動チェックが行われ、内容や表記に問題がなければ公開されます。
一度公開した後でも、Wordファイルを差し替えることで更新が可能です。
「後で直せる」と思っておくと、初回出版の心理的ハードルが下がります。
この3ステップを覚えておけば、Googleドキュメントだけで電子書籍をスムーズに出版できます。
最初は不安でも、慣れると1冊を数時間で形にできるようになります。
「Wordを持っていないから無理」と思っていた人でも、無料ツールだけで十分対応できるのがこの方法の強みです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
目次・見出し・レイアウトでつまづきやすいポイントと対策
Kindle出版では、見た目の整え方が出版の成否を左右します。
Googleドキュメントで書いた原稿も、KDPにアップロードすると見出しが飛んだり、目次が動かなくなったり、画像や余白がずれたりと、細かいトラブルが起こることがあります。
ここでは、よくあるつまづきとその解決策を、実際の出版経験をもとに整理します。
目次リンクが機能しない原因とGoogleドキュメント側の設定方法
Googleドキュメントで「目次がうまく動かない」という相談は非常に多いです。
最大の原因は、“見出しスタイルを正しく設定していない”ことにあります。
「太字+大きな文字」にしても、それは単なる装飾であり、KDP側では目次として認識されません。
必ず「見出し1」「見出し2」などの段階見出しを使いましょう。
この設定を行うと、KDP側が自動的に目次を生成し、Kindle端末でもリンクが機能します。
また、目次を文中に挿入したい場合は、「挿入」→「目次」からリンク付き目次を選びます。
ただし、Googleドキュメント内で機能しても、KDPでは反映されない場合があります。
このときは、Kindle Previewerでリンクが動作しているかを確認してください。
私の経験では、ドキュメントの途中に画像を多く入れていると、リンク位置がずれるケースもありました。
章タイトル直前に改行を入れすぎないようにするだけでも、表示が安定します。
論理目次の具体的な作り方や、KDP上での確認手順については、『Kindle出版の目次とは?論理目次の作り方と確認方法を徹底解説』でより詳しく解説しています。
画像挿入・改ページ・余白崩れの対処法(Kindleプレビューで要確認)
KDPでは、紙のようなレイアウト再現は期待できません。
Kindle端末は画面サイズが異なるため、余白や段組みはデバイスによって自動調整されます。
このため、「見た目を固定したい」という発想をいったん手放すことが重要です。
画像を挿入する際は、「テキストの折り返し」を使わず、センター配置を基本にします。
折り返しを設定すると、画面サイズの違いで画像が飛んだり、本文に重なったりすることがあります。
画像サイズはできるだけ小さめ(幅600〜1000ピクセル程度)にし、圧縮しておくと読み込みも早くなります。
改ページは「Ctrl+Enter」で明示的に入れるのが安全です。
余白や改ページをスペースで調整すると、端末ごとに崩れる原因になります。
また、Kindle Previewer(KDP公式ツール)で実際の表示を確認することを忘れないでください。
ブラウザ上のプレビューよりも正確で、タブレット・スマホ・Kindle端末の表示を再現できます。
経験上、ここで崩れを見つけて直すことが、読者レビューのトラブル防止につながります。
レイアウト崩れを防ぐ具体的な設定方法や、プレビュー確認のチェックポイントを体系的に知りたい場合は、『Kindle出版のレイアウトとは?崩れない作り方とプレビュー確認の徹底解説』も参考にしてみてください。
フォント・縦書き・和文特有レイアウトの注意点(公式ヘルプ要確認)
日本語書籍特有の悩みとして、フォントや縦書きレイアウトの問題があります。
KDPの電子書籍は基本的に横書き・可変レイアウトで表示されるため、縦書きやフォント固定は非推奨です。
縦書きや特殊な書体を使いたい場合、Kindle Createや固定レイアウト(Fixed Layout)形式が必要になります。
ただし、日本語版のKDPでは固定レイアウト書籍の審査が厳しく、対応しないジャンルもあります。
公式ヘルプを事前に確認することをおすすめします。
また、Googleドキュメント上で使用できるフォントの多くは、Kindle端末では再現されません。
標準的な「Noto Sans」や「Arial」「Times New Roman」などの汎用フォントにしておくと、安全です。
特殊文字や絵文字も環境によっては欠落します。
特に見出しに記号を入れると、目次生成がエラーになることがあるので注意しましょう。
和文は英語よりも行間が広くなりやすく、全体が間延びして見えることがあります。
この場合、Googleドキュメント上で1.15倍〜1.3倍程度の行間に調整しておくと、Kindle端末でも読みやすく表示されます。
細部まで整えることより、「端末で読んだときの自然さ」を意識するのがコツです。
これらの対策を意識することで、GoogleドキュメントでもKDPに適したレイアウトを作れます。
一見細かい話ですが、この整え方が「素人感のないKindle本」を作る分かれ目になります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
実践:Googleドキュメント活用+KDPで出版した事例/成功のコツ
Googleドキュメントを活用したKindle出版は、いまや個人著者の定番手法になりつつあります。
ここでは、実際にGoogleドキュメントだけで電子書籍を出版した初心者の事例と、効率的に複数冊を出すための仕組みづくりを紹介します。
どちらも「無料ツールでここまでできるのか」と驚くほど実践的な内容です。
初心者著者がGoogleドキュメントで出版したケース紹介
私が支援した著者の中には、パソコン操作に慣れていない60代の方もいました。
その方は、長年の経験をまとめたビジネスエッセイをGoogleドキュメントで執筆し、初めてKindle出版に挑戦しました。
特別なツールを使わず、Googleドキュメントで文章を書き上げ、Word形式で書き出してKDPにアップロード。
それだけで1冊目の電子書籍をリリースできました。
最初は「目次が消えた」「改ページがずれた」と何度かやり直しましたが、プレビューを見ながら修正するうちに自然とコツを掴んでいました。
結果的に、出版から1か月以内にAmazonランキングのカテゴリー1位を獲得。
レビューでも「読みやすい」「構成がわかりやすい」と好評でした。
このケースで印象的だったのは、Googleドキュメントのシンプルさが作業の継続を支えたという点です。
執筆に集中でき、余計な操作に時間を取られないため、完成まで迷わず進められたとのことでした。
「書くこと」に集中したい初心者ほど、Googleドキュメントとの相性は良いと感じます。
量産を可能にする「テンプレート+外注」の仕組みと活用法
1冊出して慣れてくると、「次は複数冊を出したい」と考える人が多いです。
そのときに役立つのが、テンプレート化と外注化の組み合わせです。
テンプレートとは、見出し構成・目次形式・書式設定をあらかじめ整えた「原稿のひな形」です。
Googleドキュメントなら1度作っておけば、共有リンクで誰でもコピーして使えます。
この仕組みを整えておくと、2冊目以降の執筆スピードが一気に上がります。
たとえば、タイトル・導入・章立ての構成を決めたフォーマットを1つ用意し、リサーチ担当やライターに執筆を依頼する。
Googleドキュメントは複数人で同時編集が可能なので、進行管理が非常に楽になります。
私はこの方法で、執筆・校正・装丁デザイナーをそれぞれ分業し、毎月2冊ペースの出版を実現できました。
注意点として、著作権やKDPのコンテンツポリシーを理解したうえで外注することが重要です。
特に文章生成AIや外部ライターを活用する場合、出典の明記やオリジナリティの確保を怠ると、審査でリジェクトされる可能性があります。
KDPでは「AI生成コンテンツ」を明示する項目も追加されているため、公式ヘルプを都度確認しましょう。
テンプレート+外注の仕組みは、一度整えると長く使えます。
自分の得意テーマをシリーズ化すれば、ブランドとしての信頼性も高まり、継続的な収益につながります。
Googleドキュメントの共有・複製機能を活かせば、費用をかけずに“出版チーム”を組むことも可能です。
このように、Googleドキュメントは「一人で完結できるツール」であると同時に、「複数人で量産を仕組み化できるツール」でもあります。
初めての1冊はシンプルに、2冊目以降はテンプレートと分業で効率化する。
この流れを意識するだけで、継続的なKindle出版がぐっと現実的になります。
料金・出版形式・ペーパーバック対応の補足(電子書籍が前提)
Kindle出版は基本的に無料で始められます。
ただし、電子書籍とペーパーバックではコスト構造が異なります。
ここでは、日本版KDP(Amazon.co.jp)を前提に、出版費用と印税の仕組み、そして紙書籍への対応について整理します。
電子書籍出版時にかかるコストと収益構造(日本版KDP)
KDPで電子書籍を出版する際、初期費用や手数料は一切かかりません。
登録・アップロード・販売ページ作成まですべて無料で行えます。
唯一発生するのは、売れたときにAmazonのシステムが自動で差し引く「販売手数料(配信コスト)」のみです。
印税(ロイヤリティ)には35%と70%の2つの選択肢があります。
日本では、価格を250円〜1,250円に設定した場合に70%ロイヤリティが適用され、それ以外の価格帯では35%となります。
70%ロイヤリティは「税抜価格」を基準に計算し、さらに配信コスト(デリバリー費)が差し引かれます。具体額は価格・容量・税率により変動します(公式ヘルプ要確認)。
ただし、70%ロイヤリティを選ぶ場合は配信コストとして「1MBあたり約1円」が差し引かれるため、画像や装飾を多く使う書籍では収益がわずかに下がることもあります。
私の経験上、文字主体の本(実用書・エッセイなど)であれば1MB前後に収まり、配信コストは数円程度です。
逆に、写真集やイラスト中心の書籍では10MBを超えることもあり、配信コストの影響が無視できません。
その場合は35%ロイヤリティで販売価格を上げるか、画像圧縮ツールを使ってデータ容量を減らす工夫が必要です。
なお、KDPセレクトでは主にKindle Unlimitedの閲読分配と、無料キャンペーン等の販促機能を利用できます。Kindleオーナーライブラリーは現行では対象外です。
ただし、独占配信(他社販売禁止)という条件があるため、他の電子書店で販売したい場合は注意が必要です。
公式ガイドラインでは「90日間の独占契約期間」と明記されています。
実際に複数プラットフォームで販売したい場合は、通常のKDP出版を選択しておくのが無難です。
電子書籍は基本的に在庫を持たないため、印刷費や倉庫保管費がかからず、リスクゼロで販売できます。
この点が、個人著者がGoogleドキュメントを活用して出版する最大のメリットとも言えます。
ペーパーバック(紙書籍)でGoogleドキュメント→出版する場合の一言補足
KDPでは電子書籍に加え、ペーパーバック(紙の本)の出版も可能です。
ただし、ペーパーバック本文はPDF推奨ですが、DOCX入稿も可能でKDP側で変換されます。いずれの場合も裁ち落とし・余白など印刷要件の適合が必要です。
一度、PDF形式で書き出し、印刷対応のレイアウトを整える必要があります。
ペーパーバックはページ数・余白・フォントサイズなどの物理的な制約が多く、KDPの審査基準も電子書籍より厳しめです。
特に日本語書籍の場合、24ページ以上ないと出版できない点に注意してください。
また、カバー(表紙)は背幅を含めたサイズで作成する必要があるため、Amazonのテンプレートを利用すると安全です。
私の経験では、Googleドキュメントで執筆した原稿をWordに変換し、Word上で余白やノンブル(ページ番号)を整えてからPDF化するのがもっともスムーズでした。
Wordを使わない場合は、Canvaなどのデザインツールで整える方法もあります。
ただし、画像の解像度が足りないと印刷時にぼやけることがあるため、300dpi以上を目安に準備しましょう。
電子書籍の出版が慣れてから、ペーパーバックに挑戦するのが理想的です。
最初から両方を同時に進めると、校正やプレビュー確認に時間がかかりすぎてしまいます。
Googleドキュメントでの執筆経験を積んでから、紙書籍のレイアウトにステップアップするのがおすすめです。
こうした知識を押さえておけば、電子と紙の両方をバランスよく使い分けられます。
最初は電子書籍から始め、後からペーパーバックを追加する流れが、個人出版ではもっとも効率的です。
ペーパーバック化の具体的な条件や入稿手順を一通り確認したい方は、『Kindle出版で紙の本を出すには?ペーパーバックの条件と手順を徹底解説』を先に読んでおくと、電子書籍との違いがよりクリアになります。
まとめ:Googleドキュメントを使ったKindle出版をスムーズに進めるために
Googleドキュメントは、無料で使えて操作も直感的なため、初めてKindle出版に挑戦する人にとって最適なツールです。
Wordを持っていなくても、原稿の執筆から入稿まで一通り完結できるのが最大の魅力です。
ただし、KDPの仕様を理解せずに進めると、レイアウト崩れや目次エラーなどのトラブルに遭遇しがちです。
最後に、この記事で押さえておくべきポイントと、次に進むための具体的な行動を整理しておきましょう。
本記事で押さえるべき「3つの要点」
まず1つ目の要点は、Googleドキュメントの「見出しスタイル」を正しく使うことです。
章立てを「見出し1」「見出し2」で統一すれば、KDPが自動で目次を作成し、リンクも正しく動作します。
太字やフォントサイズ変更だけで構成を作ると、見出し認識されずに崩れる原因になります。
2つ目は、原稿を書き終えたら必ず「.docx形式」でダウンロードすることです。
PDFで入稿してもエラーになったり、日本語レイアウトが正しく反映されなかったりします。
この形式で保存すれば、KDPのプレビュー機能でもスムーズに確認できます。
3つ目は、Kindle Previewerで必ず最終チェックを行うことです。
プレビューを怠ると、章タイトルが飛んでいたり、画像がずれていたりすることに気づかず公開してしまうケースがあります。
実際にKindle端末でどう見えるかを確認し、必要に応じて修正を重ねましょう。
この3点を守るだけで、出版トラブルの多くは防げます。
次のステップとしてやるべきこと
ここまで読んだ方は、もうKindle出版の準備が整っています。
次のステップは「1冊を実際に完成させてみる」ことです。
書籍内容が短くても構いません。
5,000〜10,000文字程度の短いテーマを選び、まずは出稿から販売までの流れを一度体験してみましょう。
出版の工程を一通り経験しておくことで、次からは作業効率が格段に上がります。
慣れてきたら、テンプレート化や外注化に進むのもおすすめです。
Googleドキュメントなら共有機能があるため、ライターや校正者と同時に作業ができます。
これを活かすことで、1人でも複数冊を効率よくリリースできます。
最後に、KDPの仕様やガイドラインは定期的に更新される点も忘れないでください。
Amazonの公式ヘルプを定期的にチェックし、最新ルールを踏まえて出版を続けることが信頼と継続収益につながります。
「Googleドキュメント × KDP出版」を理解しておけば、コストをかけずに自分の知識を形にし、長く残る資産として発信することができます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。