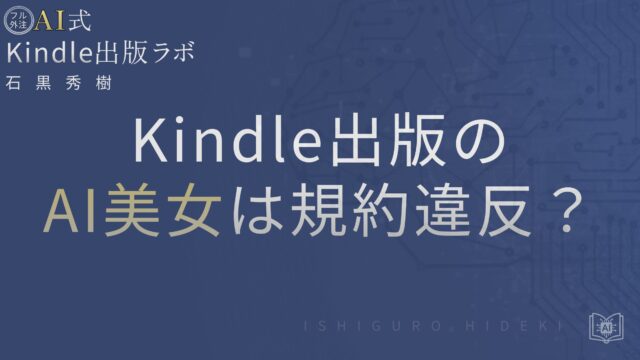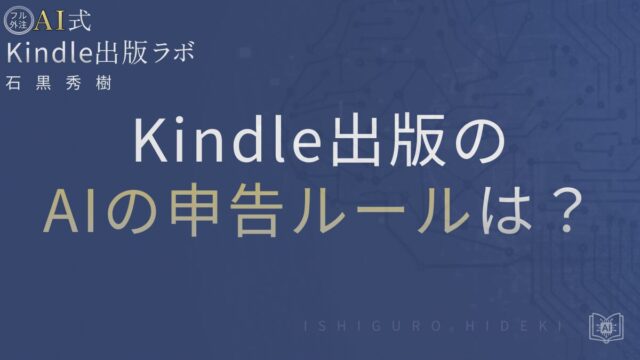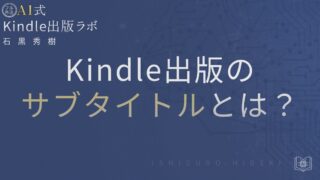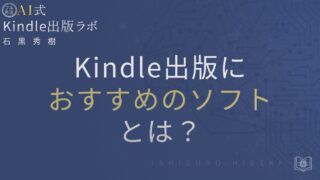Kindle出版の制限とは?審査で止まらないための最新ガイド
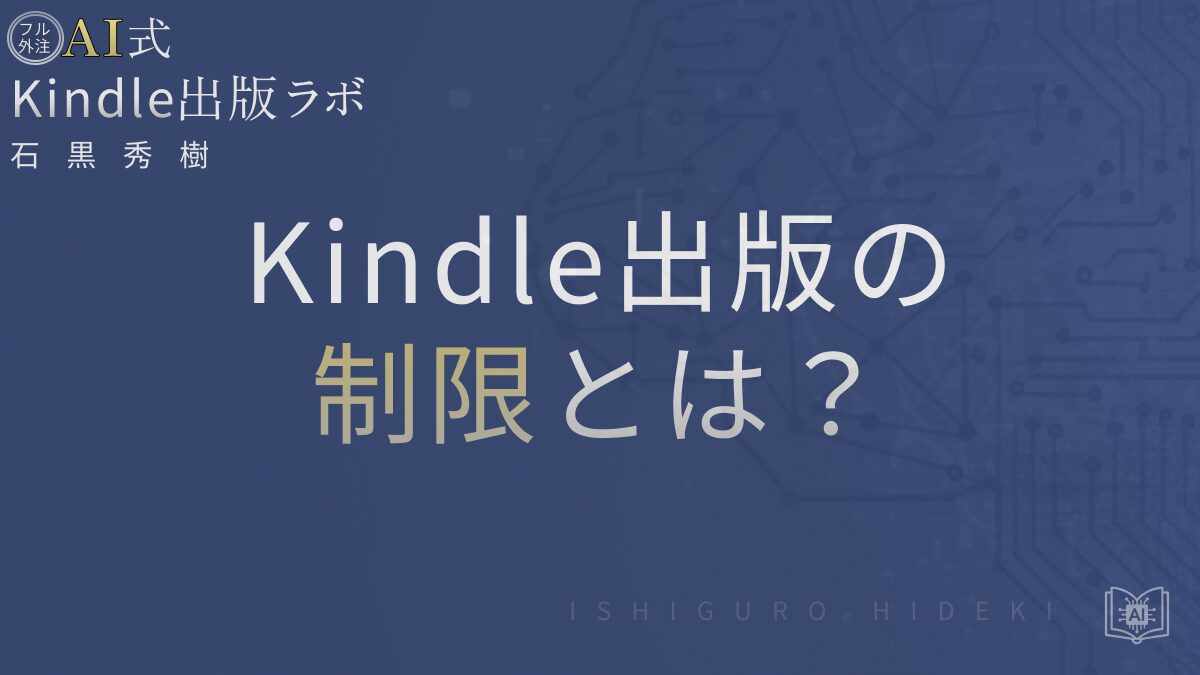
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようとしたとき、「どこまでがOKで、どこからがNGなのか?」と不安に感じた方は多いと思います。
特に初めての出版では、KDPの“制限”に触れてしまい、審査で止まったり、最悪の場合は販売停止になることもあります。
この記事では、Kindle出版における制限の基本をわかりやすく整理し、どのような点に注意すればスムーズに出版できるのかを具体的に解説します。
公式ヘルプの内容を踏まえつつ、実際に出版してきた中で感じた「現場での差」や「ありがちな勘違い」も交えてお伝えします。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版における「制限」とは?初心者がまず知るべき基本
目次
- 1 Kindle出版における「制限」とは?初心者がまず知るべき基本
- 1.1 KDPの「制限」はどこにある?内容・形式・運用の3分類
- 1.2 制限を理解しておくべき理由:リジェクトや販売停止を防ぐために
- 1.3 Amazon.co.jpと他国KDPの仕様違い(補足)
- 1.4 公序良俗・著作権・誤解を招く宣伝表現の制限
- 1.5 スピリチュアル・心理・宗教系ジャンルの抽象化ルール
- 1.6 教育・啓発目的として扱う際のポイント(公式ヘルプ要確認)
- 1.7 タイトル欄とサブタイトル欄の区別と禁止パターン
- 1.8 キーワード乱用・誇張表現のNG例と修正方法
- 1.9 著者名・シリーズ名・出版社欄に関する登録制限
- 1.10 1日に出版できる冊数制限と背景(スパム対策)
- 1.11 短期間での大量出版がリジェクトされる理由
- 1.12 再審査・更新時の注意点と対応フロー
- 1.13 最小ページ数と印刷対応フォーマットの基本
- 1.14 電子書籍とのメタデータ統一と差分の管理
- 1.15 よくあるリジェクト理由とその改善例
- 1.16 再提出で通過するためのチェックリスト
- 1.17 実際に出版者が経験した「グレーゾーン」の事例
- 1.18 公式ヘルプの最新情報を定期確認する
- 1.19 審査前チェックで“落ちる要素”を見抜く
- 1.20 不確実な箇所は安全側で調整する判断軸
- 2 まとめ:制限を理解すれば、Kindle出版はもっと自由になる
Kindle出版(KDP)における「制限」とは、Amazonが安全で信頼できるコンテンツを提供するために設けているルールや基準のことです。
これは主に「内容」「メタデータ(登録情報)」「出版運用」の3つの領域に分かれます。
どれも曖昧なまま進めると、知らずにリジェクト(審査落ち)されることがあるため、最初にしっかり把握しておくことが大切です。
KDPの「制限」はどこにある?内容・形式・運用の3分類
KDPで設けられている制限は、大きく分けて次の3つのカテゴリに分類できます。
1つ目は「内容面の制限」です。
これは、公序良俗や著作権、誤解を招く表現などに関するもので、Amazonが最も厳しくチェックしている部分です。
2つ目は「メタデータの制限」です。
タイトル・サブタイトル・著者名・キーワードなど、商品情報に関わる項目は、ユーザーを誤認させないよう細かいルールが定められています。
3つ目は「運用上の制限」です。
出版ペースや冊数、審査時の対応方法など、KDPの運営システムに関連するものが該当します。
これらの制限は、それぞれ目的が異なりますが、共通して「読者に対して誠実であること」が根底にあります。
特に最近ではAI生成コンテンツの増加に伴い、自動的に検知・制限されるケースも見られます。
制限を理解しておくべき理由:リジェクトや販売停止を防ぐために
制限を理解しておく最大の理由は、出版停止やリジェクトを未然に防ぐためです。
公式では「KDPコンテンツガイドライン」に沿うよう求められていますが、実際の審査ではAI判定+人による確認が行われるため、微妙な表現や構成でストップがかかることもあります。
特に注意したいのは、「意図せず誤解される構成」です。
たとえば、タイトルと内容の整合性が取れていない場合や、説明欄で煽るような表現を使っていると、読者を誤認させると判断されやすいです。
また、一度リジェクトされると再提出に時間がかかるため、事前に制限を理解しておくことが、最短で出版するための近道になります。
実際に筆者も初期の頃、キーワードを多く入れすぎてタイトルが拒否されたことがあります。
公式ルールを読んでも曖昧な部分が多いのですが、審査担当者の裁量が入るため、「安全側」で判断するのが鉄則です。
KDP全体の規約やメタデータ制限を整理して確認したい場合は『Kindle出版の規約とは?審査通過のポイントと違反回避を徹底解説』もあわせて読んでおくと、リジェクトを事前に避けやすくなります。
Amazon.co.jpと他国KDPの仕様違い(補足)
KDPは世界共通のプラットフォームですが、実際にはAmazon.co.jp(日本)独自の運用が存在します。
たとえば、成人向けコンテンツや医療・健康関連の表現は、日本ではより慎重に審査される傾向があります。
同じ原稿でも、米国では販売できても日本ではリジェクトされることがあるのです。
また、日本語コンテンツの場合、誤字脱字や翻訳調の文章が多いと品質審査に引っかかる場合があります。
英語圏よりも「読みやすさ」「正確さ」が重視される点も覚えておくと良いでしょう。
海外の情報を参考にするのは有効ですが、最終的にはAmazon.co.jpのヘルプページやガイドラインを基準に判断することをおすすめします。
Kindle出版の審査では、最も多くリジェクトが発生するのが「内容面の制限」です。
ジャンルや表現が広がるほど、どこまでがOKでどこからがNGか判断が難しくなります。
特に初めての方は、「自分の本がどの制限に触れる可能性があるか」を理解しておくことが大切です。
ここでは、内容面で注意すべきポイントを実例とともに解説します。
公序良俗・著作権・誤解を招く宣伝表現の制限
KDPでは、公序良俗に反する内容や他人の権利を侵害する表現は禁止されています。
例えば、暴力や差別、性的描写などが過度なものはリジェクト対象になります。
ただし、社会問題を題材にした作品や心理描写の一部として登場する場合などは、「教育的・文芸的意図が明確であること」が判断基準となります。
著作権に関しては、歌詞や引用、写真素材などが特に注意が必要です。
「引用元を明記すれば大丈夫」と思われがちですが、商用利用が許可されていない素材を使うと出版後に取り下げの可能性があります。
特に、画像をAIで生成した場合でも、学習元のデータや著作権表記に関する規約違反があれば審査で止まるケースがあります。
また、宣伝文やタイトルにも制限があります。
「ベストセラー」「売上No.1」「驚異の効果」など、根拠を示せない宣伝表現はNGです。
このあたりはAmazonのレビュー・広告ポリシーにも共通しており、誇張表現を避けて事実ベースで説明することが信頼につながります。
実際、筆者も過去に「短期間で収益化」などの文言を使った際に、リジェクトを受けた経験があります。
「断定的」「保証的」な表現は特に厳しく見られるため、「〜の事例もある」「〜の方法を紹介」といった中立的な表現にするのが安全です。
公序良俗や著作権まわりの具体的なNG例は『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』で一覧化しているので、出版前に一度チェックしておくと安心です。
スピリチュアル・心理・宗教系ジャンルの抽象化ルール
スピリチュアルや心理、宗教に関するテーマは、Amazonが特に慎重に審査する領域です。
内容によっては、KDPガイドラインに抵触する場合があります。
具体的には、「特定の宗教・信仰への勧誘」や「特定の思想・団体の批判」「医療行為に関する断定的効果の主張」はリジェクト対象です。
これらは信仰や健康に関わるセンシティブな領域であり、誤解を招く恐れがあるためです。
このジャンルで出版する場合は、「体験談」や「個人の気づき」として表現することが安全です。
たとえば、「宇宙の法則で願いが叶う」と断定するのではなく、「私の場合はこの考え方で前向きになれた」といった形です。
また、スピリチュアル系の挿絵やシンボルなども、特定宗教の象徴に似ている場合は注意が必要です。
意図せず関連づけられてしまうこともあるため、できるだけ抽象的なビジュアルを使うのが無難です。
教育・啓発目的として扱う際のポイント(公式ヘルプ要確認)
スピリチュアル・心理・健康分野などのテーマでも、教育・啓発目的であれば出版できる場合があります。
ただし、KDPの審査では「教育的意図」が明確に伝わらないと判断されるとリジェクトされることがあります。
教育・啓発の枠で扱う場合は、「理論の紹介」「研究結果の引用」「一般的知識の解説」など、客観的情報をベースに構成するのがポイントです。
たとえば、「自律神経を整える呼吸法」などを紹介する場合、実体験だけでなく「医療行為ではない」「自己管理を目的とした方法」という注釈を添えると安全です。
公式ヘルプでも、健康・心理・宗教に関する内容は“読者を誤解させないよう注意する”と明記されています。
また、Amazon側で内容を再分類されることもあるため、出版後にジャンル変更されても慌てず対応しましょう。
実務上は、タイトル・説明文・キーワードで「教育・実用・エッセイ」など中立的な枠組みに整えると審査がスムーズです。
このように、KDPの内容面の制限はやや曖昧に見えますが、「読者を誤導しない」「社会的に中立である」という視点で判断すれば、多くの問題は防げます。
Kindle出版では、内容だけでなく「タイトルや著者名などの登録情報(=メタデータ)」にも明確な制限があります。
この部分での違反は、意図せずともリジェクトの原因になることが多く、見落とされがちなポイントです。
ここでは、メタデータの制限をわかりやすく整理し、スムーズに審査を通すための注意点をまとめます。
タイトル欄とサブタイトル欄の区別と禁止パターン
まず最も基本的なルールは、「タイトル欄とサブタイトル欄を明確に区別すること」です。
タイトルは作品名そのものを指し、サブタイトルはその内容を補足・説明するために使われます。
たとえば「夢を叶えるノート」がタイトルで、「毎日3分で自分を変える習慣法」がサブタイトル、という形です。
よくある失敗は、タイトル欄にサブタイトルや宣伝文句を詰め込んでしまうケースです。
たとえば、「夢を叶えるノート:誰でも簡単に成功できる!Amazonランキング1位」などは明確にNGです。
「タイトルの過度な記号・装飾や、ランキング・保証などの誤解を招く表現は避けましょう(具体条件は公式ヘルプ要確認)。」
これは読者を誤解させないためのルールであり、審査でも最初にチェックされる部分です。
実務上は、タイトルとサブタイトルを「文脈でつながるように」設計するのがコツです。
たとえば、「心を整える日記」+「書くだけで気持ちが軽くなる習慣」など、自然に補足する形が理想です。
筆者の経験でも、タイトルの順序や区切り方を少し変えただけで審査がスムーズに通ることがありました。
キーワード乱用・誇張表現のNG例と修正方法
Kindle出版では、SEO目的でキーワードを入れすぎると逆効果になることがあります。
タイトルや説明文に同じ言葉を繰り返すと、スパム行為と判断されることがあるため注意が必要です。
たとえば、「Kindle出版 Kindle出版 Kindle出版で副業」などは、明確なNGパターンです。
また、「絶対稼げる」「最短で成功」「奇跡の方法」など、誇張や保証を含む表現も制限されています。
これらはAmazonの広告ポリシーにも抵触するため、審査で止まるリスクが高いです。
修正する際は、キーワードを自然な文脈に溶け込ませるのがポイントです。
たとえば、「Kindle出版で収益化するためのステップ」というように、説明的な形で1回だけ含めると安全です。
また、タイトルだけでなく「説明文」「キーワード欄」でもバランスを意識することが重要です。
強調よりも「読者にとって意味のある言葉」を優先することで、結果的にSEO効果も安定します。
筆者の経験では、タイトルよりも説明欄にキーワードを1〜2回入れる方が効果的でした。
タイトルは「作品の顔」であり、過度な最適化よりも“信頼感”を重視する方が長期的にはプラスに働きます。
著者名・シリーズ名・出版社欄に関する登録制限
著者名やシリーズ名にも制限があります。
KDPでは、「実在しない人物・有名人・企業名を名乗ること」を禁止しています。
たとえば、「Amazon公式」や「◯◯研究所」といった紛らわしい表記はNGです。
また、筆名を使う場合でも、他の著者やブランドと混同されるような名前は避けるべきです。
シリーズ名については、Amazonの検索や分類に影響するため、統一感が大切です。
シリーズ名に特典や宣伝文句(例:「完全版」「保存版」「豪華特典つき」)を入れるとリジェクト対象になります。
筆者も過去に「シリーズ第1巻(無料特典つき)」と入れて審査で止められたことがあります。
その際は、特典内容をタイトルから外し、本文の冒頭で案内する形に変更して通過しました。
出版社欄については、個人出版の場合、空欄でも問題ありません。
任意で屋号やブランド名を登録できますが、商標登録されていない名称を使うと警告が出る場合があります。
安全策としては、自分の活動名(例:「Awairo Works」「Yumi Books」など)を統一的に使うのがおすすめです。
メタデータは、見落とされがちですが「Amazon上での信頼性を左右する部分」です。
読者から見たときに「この本は誠実そう」と感じてもらえるように設計することが、出版の第一歩になります。
KDPでの出版活動を継続するうえで、意外と見落とされがちなのが「運用上の制限」です。
ここでは、出版可能冊数や審査ルール、再審査の際の注意点など、実務に直結する最新仕様を整理します。
特に2023年以降はスパム対策が強化され、出版ペースに関する制限が厳しくなっているため、注意が必要です。
1日に出版できる冊数制限と背景(スパム対策)
KDPでは、2023年後半から「1日に出版できる冊数が最大3冊まで」という制限が導入されています。
これは、AI生成コンテンツの急増により、内容の薄い本が大量に投稿されるケースが増えたことが背景にあります。
Amazonとしては、読者体験の質を守るため、1アカウントあたりの出版ペースを制限する措置を取っています。
この制限は、「現在は1日の出版上限が設けられています(一般に3冊が目安)。地域・時期で運用が変わる可能性があるため、最新の公式情報を確認してください。」
一見、AIで効率的に出版する人には不便な仕様に思えますが、長期的には品質維持のための重要なルールといえます。
筆者の経験でも、1日に2冊までを安定的に登録し、翌日に3冊目以降を回すことで問題なく出版できています。
「まとめてアップロード」ではなく「少しずつ丁寧に登録する」方が、結果的に審査もスムーズに進みます。
短期間での大量出版がリジェクトされる理由
短期間で多数の本を公開すると、Amazonの自動審査システムによりスパムアカウントと判断されることがあります。
特に、ジャンルやタイトル構成が似ている作品を連続して登録すると、AI検出システムが「同一内容の複製」と誤認する場合があります。
この仕組みは完全自動ではなく、人の再チェックが入ることもありますが、一度警告を受けると出版ペースを戻すまで時間がかかります。
公式ガイドラインでは「同一または非常に類似したコンテンツの繰り返し投稿は禁止」とされており、これはAI書籍にも適用されます。
また、短期間で数十冊を出すと「内容精査なしにAI生成されたもの」と判断されやすく、最悪の場合はアカウント停止のリスクもあります。
特に、タイトルや説明文がパターン化しているとスパム認定されやすいため、構成・言葉選びを少しずつ変える工夫が必要です。
筆者自身、過去に似たテーマのエッセイを短期間で5冊出した際、うち2冊が審査保留になりました。
その後、表紙と説明文を変更して再提出したところ、無事に承認されています。
この経験からも、スピードよりも「1冊ごとの完成度」を意識することが大切だと感じます。
アカウントや本がブロックされた場合の具体的な原因と復旧の流れは『Kindle出版のブロックとは?原因と解除手順を徹底解説』で詳しく解説しているので、万が一の備えとして押さえておくと安心です。
再審査・更新時の注意点と対応フロー
一度出版した本でも、表紙や内容を更新した際には再審査が行われます。
ここで注意したいのは、更新時の審査基準が初回よりも厳しくなる傾向がある点です。
たとえば、表紙デザインを差し替えた際に文字サイズやイメージが誤認を招くものと判断されると、再承認までに時間がかかることがあります。
また、説明文やタイトルを変更する場合も、内容の整合性が取れていないと再審査で止まるケースがあります。
再審査が行われた場合の基本フローは次のとおりです。
1. 更新後、自動的にKDP側で審査が開始される。
2. 通常は24〜72時間以内に結果が通知される。
3. 修正が必要な場合は「出版不可」として理由がメールで届く。
この通知を確認し、該当箇所を修正して再申請すれば、再審査を通過できます。
なお、更新を繰り返しすぎるとシステムに「頻繁な変更」として記録され、審査が遅くなることがあります。
実務上は、内容更新は「1作品につき月1〜2回まで」にとどめ、まとめて修正するのが安全です。
また、Amazon側でガイドラインが更新されるタイミングでは、以前は通っていた内容が一時的にリジェクトされる場合もあります。
このようなときは慌てず、公式ヘルプやコミュニティフォーラムで最新情報を確認するのが確実です。
KDPの運用制限は、一見面倒に感じますが、「信頼性を守りながら継続的に出版するためのルール」です。
焦らず、品質を優先する姿勢こそが長く読まれる著者への第一歩です。
ペーパーバック出版は、電子書籍よりも自由度が高い一方で、印刷という工程が入る分だけ制約も多くなります。
ページ数やサイズ、本文フォーマットなど、Amazonの印刷基準を守らなければ出版が止まってしまうこともあります。
ここでは、ペーパーバックの制作で注意すべき「ページ数」「体裁」「電子書籍との整合性」について詳しく解説します。
最小ページ数と印刷対応フォーマットの基本
KDPのペーパーバックでは、最小ページ数が24ページと定められています。
このページ数を下回ると、印刷工程に対応できないため出版できません。
一方で、上限は約828ページまでですが、用紙の種類やインク量によって実際の上限は変わります。
ページ数は「本文のみ」でカウントされ、奥付や目次も含まれます。
ただし、表紙・裏表紙はページ数に含まれません。
この点を勘違いして「表紙込みで24ページ」としてしまい、リジェクトされるケースがよくあります。
本文データは、PDF形式でアップロードする必要があります。
推奨サイズは「A5」または「6×9インチ(15.24×22.86cm)」が一般的です。
このサイズは日本語の縦書きでもレイアウトしやすく、エッセイ・小説・実用書いずれにも対応しやすい規格です。
また、フォントサイズや余白の設定も印刷時の仕上がりに直結します。
特に文字が端に寄りすぎると「裁ち落とし(印刷の際に切り落とされる部分)」にかかることがあるため、内側に広めのマージンを取るのが安全です。
筆者の経験では、本文の余白は上下25mm・左右20mmほど確保すると見栄えが安定しました。
KDP公式でもテンプレートを提供しているので、それを基準に調整すると失敗が少ないです。
もうひとつ注意すべきなのは「グレースケール印刷」です。
カラー印刷を選ぶこともできますが、費用が高くなるうえ、白黒のデータでも自動的にカラー扱いになることがあります。
イラストや写真が少ない場合は、本文はグレースケールで出力する設定にしておくとコストを抑えられます。
電子書籍とのメタデータ統一と差分の管理
ペーパーバックを出版する際は、電子書籍版との整合性を保つことが重要です。
KDPでは、同じ内容・同じ著者による作品は「同一タイトル」として統一登録するのが原則です。
この統一が取れていないと、Amazon上で別作品として扱われてしまい、レビューやランキングが分散します。
タイトル・サブタイトル・著者名・シリーズ名などは、電子版と完全に一致させましょう。
ただし、「改訂版」「完全版」などの表記を追加する場合は、実際に内容が大幅に更新されていることが条件です。
形式的な修正だけで「新装版」として登録すると、誤解を招く恐れがあるため避けるべきです。
説明文やキーワードについては、電子書籍とペーパーバックで微調整しても問題ありません。
印刷版ではページ数やサイズの情報を加えると親切です。
また、電子書籍でリンクを使用していた箇所は、印刷版ではリンクが機能しないため、URLを明記するか削除するようにしましょう。
実務上の注意点として、「ペーパーバックでは出版設定中に『無料のKDP提供ISBN』を割り当てるか、独自ISBNを入力します。割り当ては公開前に行います。」
そのため、外部で取得したISBNを使う場合は、事前に「独自ISBNを使用する」に設定変更しておく必要があります。
設定を誤ると、後から修正できず再登録が必要になることがあります。
ペーパーバック出版は電子書籍より手間がかかりますが、物理的な本として手に取れる喜びは大きいものです。
電子版と一貫性を保ちつつ、印刷仕様の制限を正しく理解して丁寧に設計することが、スムーズな審査と品質維持の鍵になります。
Kindle出版の審査は、基本的には自動チェックと人による目視確認の二段階で行われます。
スムーズに通過する作品もあれば、ちょっとした表現や設定ミスでリジェクト(差し戻し)になるケースも少なくありません。
ここでは、筆者自身や他の著者が経験した実例をもとに、審査で止まりやすいポイントと回避のコツを解説します。
審査基準の流れや承認までのステップをより詳しく知りたい方は『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』でチェックポイントをまとめて確認してみてください。
よくあるリジェクト理由とその改善例
KDPでよく見られるリジェクト理由は、大きく分けて次の3つです。
「内容ポリシー違反」「メタデータ不一致」「ファイル不備(形式エラー)」です。
それぞれに共通しているのは、意図せずルールを外れてしまう“うっかりミス”が多いということです。
まず「内容ポリシー違反」。
これは本文に誤解を招く表現や極端な主張が含まれる場合に発生します。
たとえば「必ず成功する」「100%治る」などの断定的な表現や、特定の個人・団体を暗に批判するような書き方は、教育・啓発目的であってもリジェクトされることがあります。
修正例としては、「成功の確率を高める方法」「症状が軽くなった体験談」など、主観的で柔らかい表現に変えるのが有効です。
次に「メタデータ不一致」。
これはタイトル・著者名・表紙の文字が登録情報と一致していない場合に起こります。
たとえば、表紙に「第1巻」とあるのに登録名が「シリーズ1」になっていたり、著者名にスペースが入っていたりすると審査で止まります。
KDPではシステムが細かく照合しているため、ちょっとした違いでもリジェクト対象になります。
最後は「ファイル不備」。
本文データのレイアウト崩れ、余分なページ、目次のリンク切れなどが原因です。
特にWordやCanvaから直接アップロードする場合、改ページが正しく反映されずにページずれを起こすことがあります。
修正する際は、一度「プレビューツール」で見え方を確認し、ページ送りや目次リンクを確実にチェックしましょう。
再提出で通過するためのチェックリスト
リジェクトされた場合でも、焦る必要はありません。
ほとんどのケースは、修正すれば再提出で通過します。
以下のチェックリストを使うと、再申請の際に見落としを防げます。
✅ タイトル・サブタイトル・著者名が登録内容と完全一致しているか
✅ 本文に「誤解を招く断定表現」が含まれていないか
✅ 外部リンク(SNS・URL)はAmazonポリシーに違反していないか
✅ 表紙に「特典」「ランキング」「無料」などの宣伝語がないか
✅ プレビューツールで体裁・改ページが正常に表示されているか
このチェックを行うだけでも、再審査での通過率は大幅に上がります。
筆者の場合、初回でリジェクトされた作品も、このリストを基に修正して再提出したところ、翌日には無事承認されました。
KDPの審査は「完璧さ」よりも「ルールの理解と整合性」が重視される印象です。
また、修正理由を明記して再提出する際に「修正内容の要約(50〜100字程度)」をコメント欄に書いておくと、審査担当者に意図が伝わりやすくなります。
これは公式ルールでは明記されていませんが、実務上とても効果があります。
実際に出版者が経験した「グレーゾーン」の事例
KDPでは、明確にNGとは書かれていないものの、判断が微妙な「グレーゾーン」も存在します。
たとえば「自己啓発書とスピリチュアルの境界」や「健康法と医療アドバイスの違い」などが代表的です。
これらは表現の仕方によっては教育・体験談として認められることもあれば、根拠のない助言とみなされることもあります。
筆者が実際に経験したケースでは、スピリチュアル寄りの内容(引き寄せ体験談)を出版した際、「医療的効果を示唆している」と指摘され、再提出を求められました。
修正後は「科学的根拠」ではなく「個人的な気づき・感想」として書き換えたことで、無事に承認されています。
また、AI生成画像を表紙に使った場合も、著作権の帰属が不明確なまま提出すると審査で止まります。
この場合、「使用素材の権利関係とライセンス条件を満たすことが最重要です。必要に応じて出典や権利表示を適切に行いましょう(公式ヘルプ要確認)。」
こうしたグレーゾーンの多くは「悪意ではなく、表現の誤解」が原因です。
疑わしい箇所は、「これは読者に誤解を与えないか?」という視点で読み直すのが一番確実です。
審査は一見厳しそうに見えますが、KDPの目的は著者を排除することではありません。
むしろ、ルールを理解して誠実に修正する姿勢を示すことが、信頼される著者への近道です。
KDPのガイドラインを守りながら出版を進めるには、「制限を避ける」よりも「理解して上手に回避する」意識が大切です。
一見ややこしく見えるルールも、実務では3つの基本を押さえるだけで安定した出版ができます。
ここでは、筆者の経験をもとに、審査でつまずかないための3つの実践ポイントを紹介します。
公式ヘルプの最新情報を定期確認する
KDPのガイドラインは年に数回、細かく更新されます。
特にAI生成コンテンツ、著作権、成人向け表現などの分野では、ここ1〜2年で大きくルールが変わりました。
そのため、「数か月前に通った内容でも、今はリジェクトされる」こともあります。
筆者も以前、同じ形式で出していたエッセイシリーズのうち1冊だけが突然保留になり、原因を調べたところ、「タイトル欄での強調記号の使用がNG」に変わっていたことがわかりました。
このように、些細な変更でも審査結果が変わることがあるため、出版前には必ずKDP公式ヘルプを再確認する習慣をつけておきましょう。
特に「コンテンツガイドライン」「メタデータ」「出版ポリシー」の3項目は要チェックです。
審査前チェックで“落ちる要素”を見抜く
出版登録前の最終確認を怠ると、リジェクトや販売停止のリスクが高まります。
チェックすべきポイントは、内容・表紙・メタデータの3つです。
まず、内容面では誤字脱字よりも「読者を誤解させる表現」が重要です。
「効果がある」「治る」など断定的な言葉は教育的文脈であっても避け、体験談や主観表現にとどめると安全です。
表紙では、強調的な言葉(例:「最強」「完全版」「No.1」など)は審査で止まりやすい傾向があります。
一方、読者の行動を具体的にイメージさせる文言(例:「30日で変わる」「読んで気づく」など)は問題ありません。
また、メタデータ(タイトル・著者名・サブタイトル)は登録内容と完全一致しているか確認しましょう。
表紙の表記と異なると、自動でリジェクトされるケースが多いです。
このように「何を見られるか」を理解しておくと、審査がぐっとスムーズになります。
筆者は出版前に5分ほどかけて「KDPプレビューツール」と「目視確認」を併用するようにしてから、リジェクト率がほぼゼロになりました。
不確実な箇所は安全側で調整する判断軸
KDPのルールには、明文化されていない“グレーゾーン”も多く存在します。
たとえば、スピリチュアル系や心理ジャンルの「表現の強さ」、AI生成素材の扱いなどです。
このような場合は、「少し控えめにする」「出典を明記する」など、常に安全側で調整するのが基本です。
筆者の経験では、「これくらいなら大丈夫だろう」と出した作品が、説明文の一文だけで止まったことがあります。
逆に、迷った箇所を修正して出した作品は問題なく通過しました。
つまり、迷ったら「出す前に整える」が鉄則です。
「KDPではAI生成コンテンツの申告項目があります。該当する場合は必ず申告してください(詳細は公式ヘルプ要確認)。」
Kindle出版は、ルールを恐れるより「信頼を得るための基準」として向き合うのがポイントです。
この考え方を持つだけで、リジェクトを避けながら自由度の高い創作ができるようになります。
まとめ:制限を理解すれば、Kindle出版はもっと自由になる
KDPの制限は、著者を縛るためのものではなく、読者と著者の信頼を守るためにあります。
最初はルールが多く感じるかもしれませんが、慣れてくると「安全に自由を広げるコツ」が見えてきます。
たとえば、過剰な表現を避けつつ、体験や想いを言葉に変えることで、読者により深く届く本にできます。
また、KDPの規約を理解しておけば、出版停止やリジェクトを避け、継続的に作品を出し続けることが可能です。
筆者も最初の数冊は審査に時間がかかりましたが、ルールを理解してからは1〜2日でスムーズに出版できるようになりました。
「制限の理解=自由の幅を広げること」。
これを意識して取り組めば、Kindle出版は想像以上に柔軟でクリエイティブな世界になります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。