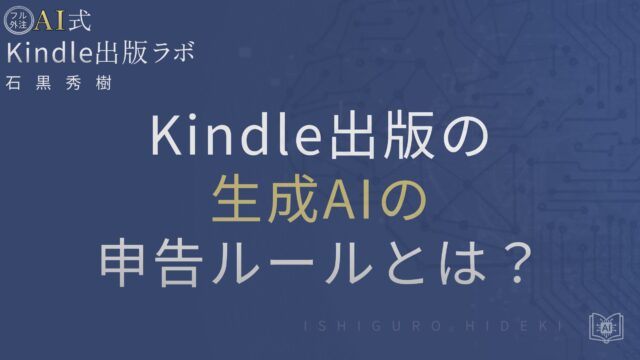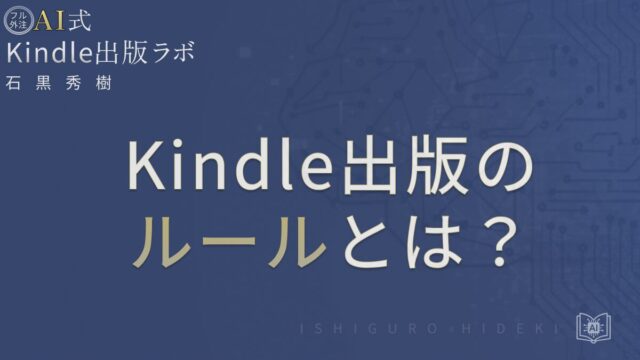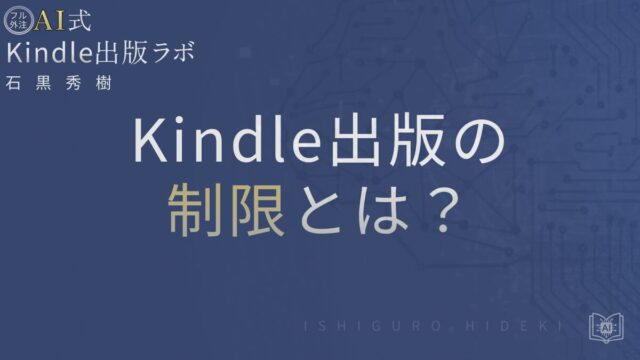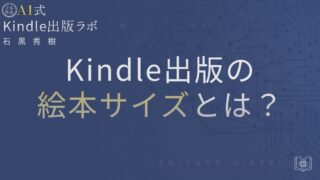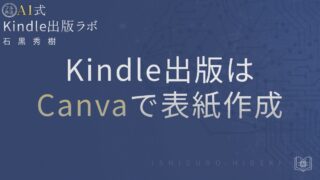公務員でもできる?Kindle出版の許可・副業ルールを徹底解説
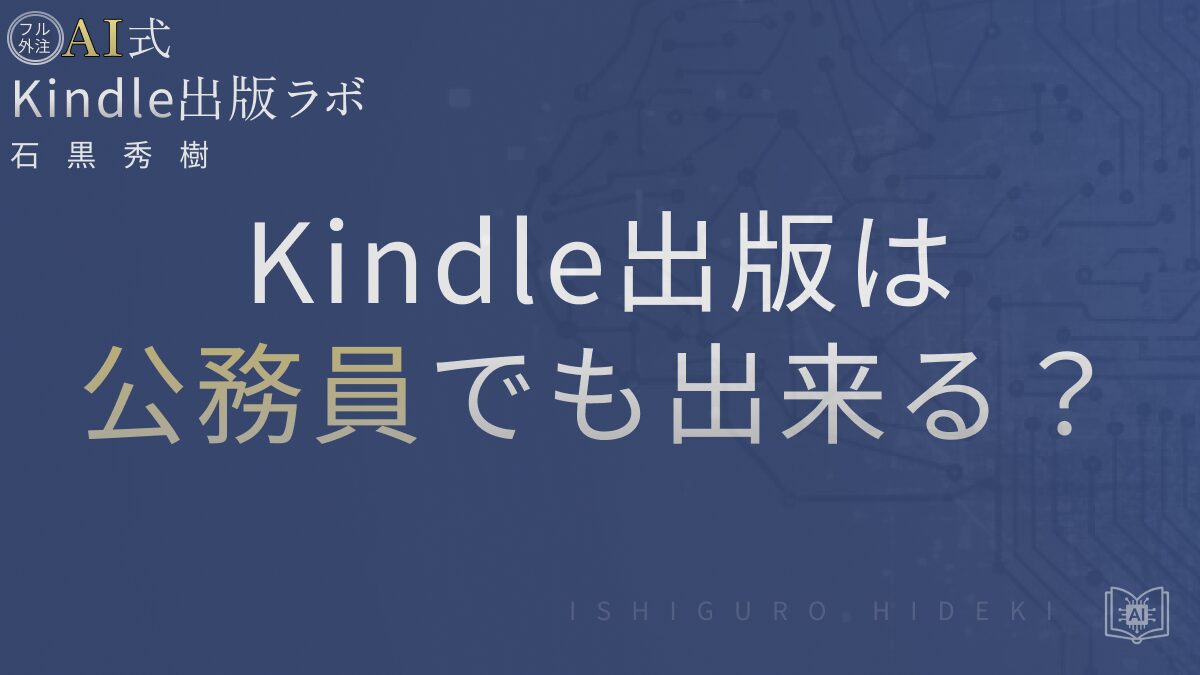
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
「公務員でもKindle出版をしていいの?」
この疑問は、実際に私の周囲の公務員の方々からもよく聞かれます。
結論から言うと、公務員でもKindle出版は可能です。ただし「必ず所属の許可を取る」ことが前提です。
この記事では、公務員がKindleで電子書籍を出版する際に知っておくべき基本ルールを、実務の感覚も交えてわかりやすく整理します。
「匿名ならバレないのでは?」という誤解や、実際の許可の判断基準、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の仕組みまで、初心者でも安心して理解できるように解説していきます。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
公務員でもKindle出版はできる?まず知っておくべき基本ルール
目次
公務員がKindle出版をする際に一番大切なのは、「法律的に禁止されているわけではないが、所属の許可が必要」という点を正しく理解することです。
実際、地方公務員法や国家公務員法では「営利企業への従事」や「兼業」を原則として禁止しています。
ただし、執筆や出版のように「創作的な活動」であれば、申請すれば許可が下りるケースも多くあります。
とはいえ、どんなテーマでもOKというわけではありません。職務と関係する内容や、職場の信用を損なうような内容は許可されない可能性があります。
この章では、まず「Kindle出版とは何か」から始めて、公務員が特に気をつけるべきルールを具体的に見ていきます。
Kindle出版とは?電子書籍を個人で販売できる仕組み
Kindle出版とは、Amazonが提供している「Kindle ダイレクト・パブリッシング(KDP)」というサービスを使い、誰でも自分の書籍を電子書籍として販売できる仕組みです。
個人でも法人でも、無料で登録でき、原稿をアップロードして表紙を設定すれば、公開までの目安は通常24〜72時間です。
審査状況や修正指示により前後します(公式ヘルプ要確認)。
売上に応じて印税(ロイヤリティ)を受け取ることができ、電子書籍は在庫管理や発送の手間がないのが大きな特徴です。
印税率は35%または70%で、価格や販売国によって異なります。
日本のKDPで70%ロイヤリティを選ぶには、指定の価格帯に設定し、消費税控除後の価格に配信コスト(ファイルサイズ連動)を差し引いた額が対象になります。
価格帯や条件は変わることがあるため、最新の公式ヘルプ要確認。
※正確な条件はKDP公式ヘルプで最新情報を確認してください。
このように、KDPは副業や個人発信の手段として人気ですが、公務員の場合は「兼業」に該当する可能性があるため、慎重に進める必要があります。
具体的な入稿画面とチェック手順は『Kindle出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説』で図解しています。
公務員の「副業禁止」ルールとKindle出版の関係
公務員は、法律上「職務専念義務」や「信用失墜行為の禁止」が課せられています。
そのため、勤務時間外でも利益を得る活動(=営利活動)を行う場合、原則として許可が必要になります。
KDPによるKindle出版は、自動的に印税が発生する仕組みであるため、「営利目的の活動」とみなされることが多いです。
たとえ1冊しか売れていなくても、システム上は“販売”として扱われるため、無許可で行うと「兼業」に該当する可能性があります。
ただし、勤務時間外に行い、職務と関係ない一般的なエッセイや趣味の内容であれば、許可が得られるケースもあります。
実際の判断は所属や自治体によって異なるため、迷ったら必ず人事課や上司に確認しましょう。
兼業・副業の許可が必要になるケースとは
「どこからが副業扱いになるのか」が一番悩ましいポイントです。
一般的には、以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、許可申請が必要になります。
1. 印税などの金銭的な報酬を受け取る場合。
2. 勤務時間内や職務上の設備を利用して執筆する場合。
3. 職務と直接関係する内容を出版する場合。
特に注意したいのは「報酬の有無」です。
「利益を目的としていない」と本人が思っていても、KDP上で販売している時点で営利活動に見なされることがあります。
また、勤務時間中に構想を練ったり、職場PCを使って執筆していた場合も、実務上は「職務の一部」と判断されることがあります。
公式の許可を取っておくことが、自分を守る一番の方法です。
匿名で出版しても問題ない?誤解されやすいポイント
「匿名ならバレないし、問題ないのでは?」という声もよく聞きます。
しかしこれは大きな誤解です。
公務員が守るべきルールは「誰が書いたか」ではなく、「その行為が兼業に該当するかどうか」で判断されます。
つまり、ペンネームや別名で出版しても、実質的に兼業に当たる場合は許可が必要です。
また、匿名であっても内容が特定の職務や内部情報に関わる場合、「守秘義務違反」や「信用失墜行為」に該当するおそれがあります。
実務でも問題視されやすい論点です。
所属の服務規程・通達・事例集で判断基準を事前確認してください(公式ヘルプ要確認)。
匿名出版を完全に否定するものではありませんが、「匿名=自由」ではないことを理解しておくことが大切です。
実名・匿名にかかわらず、出版前に所属のルールを確認し、万一のトラブルを避けましょう。
公務員がKindle出版を始める前に確認すべきこと
Kindle出版は誰でも簡単に始められる反面、公務員の場合は「やっていいかどうか」の確認を怠ると、後で思わぬトラブルにつながることがあります。
ここでは、出版を始める前に必ず確認しておくべきポイントと、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の基本ルール、印税の扱い、そして“安全な範囲”で創作を続けるコツを解説します。
私自身も最初にこの部分を理解しておくことで、安心して出版活動を続けることができました。
所属先に確認すべき3つの項目(兼業・守秘義務・信用失墜行為)
まず最初に確認すべきは、あなたの勤務先が定める「兼業」「守秘義務」「信用失墜行為」の3つです。
どれも法律だけでなく、各自治体や省庁ごとに定められた服務規程で詳細が決まっています。
たとえば、執筆や講演などの創作活動は原則として申請すれば許可される場合が多いですが、勤務内容と関係のあるテーマの場合は慎重に判断されます。
特に気をつけたいのは「信用失墜行為」。
これは“職務に関係のない内容でも、公務員としての信頼を損なうおそれがある行為”を指します。
たとえば、過激な主張や誤情報に見える発言がSNSで拡散された場合も該当する可能性があります。
守秘義務に関しても、職場で知った情報をもとに執筆すると違反となるおそれがあります。
実際、実体験をもとに書く際に「具体的な部署名や人物をぼかす」だけでは足りないこともあります。
判断に迷うときは、必ず事前に人事課などの担当窓口に相談しましょう。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の基本ルール
KDPはAmazonが提供する、誰でも電子書籍を出版できる仕組みです。
登録料は無料で、WordやPDFなどの原稿データをアップロードするだけで出版できます。
表紙や本文のフォーマットも自動変換機能があり、プログラミング知識は不要です。
ただし、KDPにはいくつかの重要なルールがあります。
たとえば、他人の著作物を無断で利用することは禁止されていますし、特定の人物や団体を誹謗中傷する内容も公開できません。
また、成人向けや刺激の強い表現についても厳しい基準が設けられています。
KDPのコンテンツガイドラインは頻繁に更新されるため、出版前には必ず公式ヘルプを確認してください。
実務的には、軽い日記エッセイやノウハウ系、専門知識のまとめなどは比較的スムーズに通過します。
一方で、「境界線が曖昧なジャンル」は公開に時間がかかる場合もあるので注意が必要です。
提出フォーマットの選び方・変換のコツは『Kindle出版のEPUB形式とは?作り方と注意点を徹底解説』を参照してください。
KDPの収益(印税・ロイヤリティ)に関する正しい理解
Kindle出版では、本が売れると印税(ロイヤリティ)という形で収益を得られます。
これは自動的に計算され、毎月Amazonから指定口座に振り込まれる仕組みです。
印税率は35%または70%で、販売価格によって変わります。
日本のAmazon.co.jpでは、250円〜1250円の範囲で価格設定をすると70%のロイヤリティが適用される仕組みです。
ただし、これは「販売価格−配送料(Kindle配信コスト)」に対しての70%です。
実際の振込額は、少し少なくなる点に注意してください。
ここで重要なのは、たとえ1冊でも売れれば「所得が発生する」という点です。
公務員の場合、無申告のままにすると“副収入隠し”と見なされる可能性があります。
年度末の確定申告や職場への収入報告の扱いは、必ず確認しておきましょう。
私の周囲でも、「たいした額じゃないから」と放置してトラブルになった例を何度も見ています。
印税は原則『雑所得または事業所得』です。
給与所得者の『20万円以下の所得の所得税申告不要』の特例はありますが、住民税の申告や所属への報告が必要な場合があります。
最寄りの税務署・所属規程を必ず確認(公式ヘルプ要確認)。
職務や勤務時間と関係しない「私的創作活動」の範囲とは
公務員でも、勤務時間外に自宅で創作活動を行うこと自体は問題ありません。
ここでいう「私的創作活動」とは、職務と無関係なテーマで、かつ職務時間・職場設備を使わない活動を指します。
たとえば、趣味としてエッセイや旅行記を書く、自己啓発本をまとめる、音楽やイラストの経験をまとめるといったケースは、許可が得られやすい傾向にあります。
ただし、「教育行政に関わる職員が教育制度を批評する本を出す」「警察官が事件対応の裏側を書く」など、職務と関係するテーマは注意が必要です。
本人の意図がどうであれ、読者から見ると“職務上の立場を利用している”と誤解されるおそれがあります。
実務的には、「勤務と切り離された活動であること」「信頼を損なわない内容であること」の2点を明確にしておくと、許可がスムーズに下りやすいです。
最後にもう一度強調すると、公務員のKindle出版は「禁止」ではなく、「条件付きで可能」です。
安心して出版を進めるためにも、必ず所属先と相談し、ルールを理解したうえで行動するようにしましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
安全に出版するための手順と注意点
公務員がKindle出版を進めるうえで最も重要なのは、「問題のない形で、安心して続けられる体制を作ること」です。
手順を踏まずに出版してしまうと、後で許可や税務の面でトラブルになることがあります。
ここでは、実際の申請の流れから、執筆テーマの選び方、Amazonのガイドライン、印税の税務処理まで、安全に出版を行うための実務的なステップを解説します。
許可取得後に迷いやすい実務フローは『Kindle出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説』が最短ルートです。
出版許可を得るための一般的な流れと相談先
最初のステップは、必ず所属の人事担当または総務課に相談することです。
口頭での確認ではなく、できるだけ書面やメールで記録を残しておくと安心です。
実際の申請では、執筆内容や収益の見込みを簡潔にまとめた「兼業許可申請書」または「副業届」の提出を求められるケースが多いです。
このとき、「趣味としての創作活動」か「営利目的の活動」かを明確にしておくことが大切です。
特に印税収入が発生する場合は、たとえ少額でも“営利活動”に分類される傾向があります。
職場によっては、出版後に報告書の提出を求められる場合もあります。
私の経験では、最初の段階で「事前相談」をしておくと、書類提出がスムーズに進みました。
黙って出版して後から発覚するより、最初に相談したほうが圧倒的に安心です。
執筆テーマの注意点:職務情報・内部情報を使わない
執筆テーマを決める際は、「職務に関係しない内容」であることを徹底してください。
たとえば、業務上知り得た情報や、内部の手続き、職員の実名などを使うのは守秘義務違反にあたる可能性があります。
たとえ匿名化していても、「職場の状況が特定できる描写」があれば問題視されることもあります。
一見 harmless に見える体験談でも、読み手の立場では“内部告発的”に受け取られる場合があるのです。
また、過激な意見表明や特定の団体・個人を批判するような内容も、「信用失墜行為」として懲戒の対象になるおそれがあります。
安全なテーマの例としては、趣味や生活の工夫、教育や福祉などの一般的な知識、地域活動の経験談などがあります。
執筆にあたっては、「誰が読んでも公務員としての信用を損なわない内容」を意識することがポイントです。
KDPコンテンツガイドラインで禁止されている内容(概要)
AmazonのKDPでは、出版できる内容にも一定のルールが定められています。
主な禁止項目は次のとおりです。
* 著作権で保護された他者の作品を無断で使用する行為
* 虚偽情報や誤解を招く表現
* 過度に刺激的または不適切な内容
* 誹謗中傷や差別的な表現
* スパム的なコンテンツ(短い本の量産や同内容の繰り返しなど)
これらはKDPの「コンテンツガイドライン」で公開されています。
Amazon側の審査で違反と判断されると、公開が差し止められたり、アカウント停止になることもあります。
公式では明確な基準が示されていない項目もあり、実際には「境界線があいまいなケース」が多いです。
たとえば、「教育的な意図がある作品」でも、表現が過度だと審査で止まる場合があります。
そのため、少しでも不安がある場合は公式ガイドラインを参照し、可能なら第三者にチェックを依頼すると良いでしょう。
確定申告・税金の扱い方(印税収入の申告方法)
Kindle出版で得た印税収入は、金額にかかわらず「所得」として扱われます。
基本的には「雑所得」または「事業所得」に分類され、年度末に確定申告が必要です。
会社員や公務員の副収入が20万円以下なら申告不要と誤解されがちですが、これは給与所得者限定のルールであり、公務員の場合は勤務先への報告義務が別途あります。
また、住民税の申告も必要になるため、「税務署に申告していない=勤務先に収入が伝わらない」とは限りません。
実務的には、印税明細(KDPの支払いレポート)を保存しておき、税務署または所属の経理担当に相談すると確実です。
私の知る限り、印税額が小さくても、報告しておいたほうが後々トラブルになりません。
税金面での不備は、出版よりもはるかに大きな問題になる可能性があります。
特に、自治体や省庁では「兼業・副業に関する年次確認」が行われる場合もあるので注意しましょう。
最後にもう一度まとめると、公務員がKindle出版を安全に行うには、「許可」「内容」「税務」の3点をきちんと整えることが不可欠です。
手続きに時間がかかっても、リスクを回避しながら進めたほうが、長く安心して出版活動を続けられます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
公務員がKindle出版で成功している事例とポイント
公務員であっても、しっかりルールを守りながらKindle出版で成果を出している人は少なくありません。
私がこれまで見てきた中でも、「地道に積み上げるタイプ」「専門性を活かすタイプ」「趣味を共有するタイプ」に分かれる傾向があります。
ここでは、実際の成功事例に見られる傾向と、テーマ選び・著作権の注意点を具体的に整理します。
読んでいただければ、どんな形なら安全かつ継続的に活動できるかがイメージしやすくなるはずです。
実名・匿名どちらで活動しているかの傾向
公務員のKindle著者は、ほとんどが匿名またはペンネームで活動しています。
実名で出している人もいますが、その場合は必ず所属の許可を得たうえで、職務と関係しない分野(たとえば趣味・教育・自己啓発など)に限定しています。
匿名の利点は、身元が特定されにくいことではなく、「職務との関係を切り分けやすい」点にあります。
読者から見ても“個人としての表現”に感じやすいため、誤解を避けやすいのです。
ただし、匿名であっても兼業にあたる活動は許可が必要です。
Amazonの著者ページやKDPの登録情報には本名や銀行口座情報を入力するため、内部的には匿名ではありません。
実際、私の知人でも「匿名だから大丈夫」と思って始め、あとから勤務先に指摘されたケースがありました。
「匿名=自由」ではなく、あくまで表現上の選択として考えるのが安全です。
出版テーマ別:安全で継続しやすいジャンルの例
公務員が安心して取り組めるテーマは、「個人の経験や趣味に基づく一般的な内容」です。
具体的には、次のようなジャンルが人気でリスクも低めです。
* **生活改善・時間管理・習慣化**:日常での工夫をまとめた実用系。
* **教育・子育て・キャリア形成**:自身の学びを客観的に書く形なら安全。
* **地域活動やボランティア体験**:公的活動の延長でも、内部情報を避ければOK。
* **趣味・旅行・読書エッセイ**:公務と関係がなく、読者も共感しやすい。
* **スキル系ノウハウ**:文章術、Excel活用、資格勉強などは根強い需要があります。
逆に避けたほうがいいのは、職務に関連する政策批評や行政の内部実態を連想させる内容です。
たとえ問題意識から書いたとしても、読者に「公務員としての立場で発言している」と見なされるおそれがあります。
私が見てきた中では、「小さく始めて反応を見ながら継続する」人ほど長続きしています。
KDPは更新や改訂が容易なので、最初から完璧を狙わず、一冊ずつ積み上げる意識が大切です。
著作権・引用ルールで注意すべきポイント
出版経験の少ない方がよくつまずくのが、この「著作権と引用」の扱いです。
Kindle出版では、著作権侵害や無断転載があると即時非公開になることもあります。
特に、画像・歌詞・地図・ニュース記事などを使う場合は注意が必要です。
たとえば、ネット上で「フリー素材」と書かれていても、商用利用が禁止されているケースがあります。
KDPは販売目的での公開となるため、商用利用可の素材を明示的に選ぶことが基本です。
引用については、「出典を明示し、本文よりも短く、引用部分が主張の補助として使われている」ことが原則です。
これは日本の著作権法に基づくもので、Amazon独自のルールではありません。
実務的には、章の終わりに「出典一覧」や「参考文献」をまとめておくとトラブルを防ぎやすいです。
私も過去に引用ルールを確認せずに審査で止まった経験がありますが、その際は出典を明記して再提出したところ、無事に公開されました。
要するに、「自分が書いたもの以外は必ず権利者を確認する」ことが、安全出版の第一歩です。
ペーパーバック(紙書籍)出版は可能?電子書籍との違い
Kindle出版というと電子書籍のイメージが強いですが、KDPでは「ペーパーバック(紙書籍)」も発行できます。
Amazon.co.jpでも近年、紙版を同時に出す著者が増えており、読者層によっては紙の需要も依然として根強いです。
ただし、公務員の立場で出版する場合は、電子書籍と同じく兼業許可・内容確認が必要になります。
ここでは、ペーパーバック出版に関する基本情報と、電子書籍との違いを整理しておきましょう。
紙出版に必要な最低ページ数と注意点(補足)
KDPのペーパーバックでは、最低ページ数が決まっています。
一般的には **24ページ以上** でないと紙書籍として登録できません。
この制限は印刷上の都合によるもので、ページ数が少なすぎると製本できないためです。
また、電子書籍とは異なり、カバー(表紙・背表紙・裏表紙)も自分で用意する必要があります。
Amazonの提供する「カバーデザイナー」を使えば、テンプレートをもとに簡単に作成できますが、印刷用データは解像度や寸法の指定が厳しく、初めての方にはややハードルが高いと感じるかもしれません。
さらに、印刷版では校正の重要性が増します。
電子書籍なら公開後も修正できますが、紙書籍はデータ修正後に再審査と印刷設定が必要になるため、誤字脱字のチェックは念入りに行いましょう。
私も初めてペーパーバックを出した際、余白設定のズレで印刷が左右非対称になり、再入稿に手間がかかった経験があります。
デザインの整合性や余白設定は、最終確認時にしっかりチェックすることをおすすめします。
電子書籍との費用・手間の違いを理解して選ぶ
電子書籍とペーパーバックの最大の違いは、「印刷コストがかかるかどうか」です。
電子書籍は無料で出版できますが、ペーパーバックは印刷コストが販売価格に含まれるため、著者が得られる印税(ロイヤリティ)は少し低くなります。
印刷コストはページ数・白黒/カラー印刷・紙サイズによって変動します。
もう一つの違いは「審査と反映スピード」です。
電子書籍は最短24時間で販売開始できますが、紙書籍は印刷データのチェックが入るため、反映まで数日かかることがあります。
公務員として出版する場合は、電子版の手軽さから始めるのが現実的です。
ペーパーバックはKDPの無料ISBNを選べば取得できます。
既存ISBNの持ち込みも可です。後から紙版を追加する運用でも問題ありません。
出版目的が「読者への信頼感アップ」や「贈呈用の冊子づくり」であれば、ペーパーバックは効果的です。
ただし、収益目的で考えるなら、印刷コストや在庫管理を伴わない電子書籍のほうが効率的です。
実際、私も最初は電子書籍のみで出し、反応を見てから紙版を追加しました。
結果として、電子書籍で認知を広げてから紙版を出す流れが一番スムーズでした。
最初の1冊は電子書籍から、次のステップとして紙書籍へ。
これが公務員にとっても負担の少ない安全な始め方です。
まとめ:公務員のKindle出版は「許可確認+ルール遵守」が最重要
ここまで、公務員がKindle出版を行う際のルールや注意点を整理してきました。
一番大切なのは、「出版そのものは禁止ではない」ことを理解し、所属の許可を得たうえで正しく進めることです。
Kindle出版は、執筆の自由度が高く、初期費用もほとんどかかりません。
ただし、内容や活動の仕方を誤ると、服務規程違反とみなされるリスクがあります。
特に気をつけたいのは以下の3点です。
1. **所属への事前確認**:兼業許可や守秘義務の範囲を明確に。
2. **内容の適正**:職務関連・誹謗中傷・内部情報の使用は避ける。
3. **税務処理**:印税収入は雑所得または事業所得として申告。
これらを押さえておけば、公務員でも安心して出版活動を続けられます。
実際、KDPでの執筆をきっかけに、専門知識を体系化したり、キャリアの棚卸しができたという声も多く聞きます。
「小さく始めて、コツコツ育てる」——それがKindle出版の魅力です。
最初の一歩を踏み出すと、想像以上に世界が広がります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。