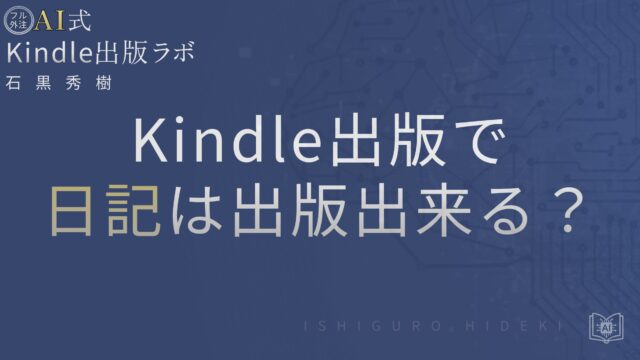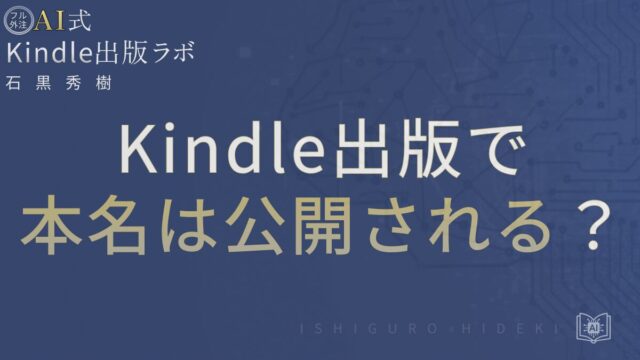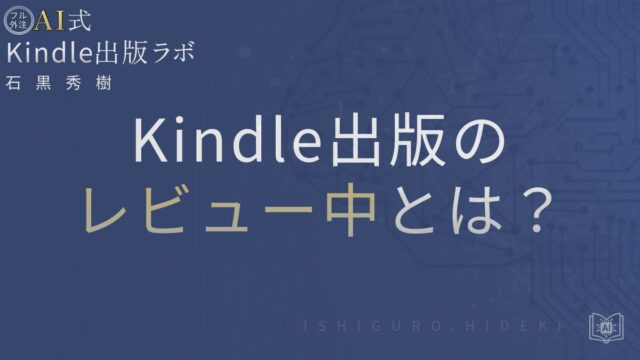自費出版の奥付とは?意味・書き方・注意点を徹底解説【電子書籍対応】
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
自費出版をはじめて行うとき、多くの人がつまずくのが「奥付(おくづけ)」です。
本の最後にある小さな欄ですが、実は作品の信頼性や責任の所在を示す重要な部分です。
この記事では、奥付の基本的な意味から商業出版との違い、電子書籍での扱いまでをわかりやすく解説します。
初心者でも迷わないように、実務上の注意点も交えながら紹介していきます。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
自費出版における「奥付」とは?その意味と役割をわかりやすく解説
目次
奥付は、書籍の最後のページに掲載される情報で、「誰が・いつ・どのように発行したか」を明示するものです。
紙の本でも電子書籍でも、この部分があることで読者は発行者の信頼性を確認でき、著作権や発行責任の所在も明確になります。
特に自費出版の場合、商業出版社のように組織的なチェック体制がないため、奥付は「作品の公式情報」として信頼を得るための大切な役割を果たします。
奥付とは本の最後にある「責任表示欄」のこと
奥付は「責任表示欄」とも呼ばれ、本の発行に関する基本情報をまとめたものです。
具体的には、書名、著者名、発行日、発行者、印刷所などを記載します。
これがあることで、後から誤植や権利関係のトラブルが起きた際も、どの版がいつ発行されたかを明確に示せます。
たとえば私自身も初めての自費出版で奥付を入れ忘れ、後日修正版を出すときに混乱した経験があります。
小さな欄ですが、作品の“履歴”を守る大切な部分なのです。
商業出版と自費出版で奥付の位置づけはどう違う?
商業出版では、出版社が奥付の内容を決定し、法務や編集のチェックを通して正式に発行します。
一方、自費出版では著者自身が発行責任を負うため、奥付の情報も自分で正確に記載しなければなりません。
たとえば商業出版では「発行者=出版社」ですが、自費出版では「発行者=著者本人」や「個人サークル名」になるケースもあります。
また、商業書籍はISBN(国際標準図書番号)を必ず取得しますが、自費出版では任意の場合もあります。
公式ではISBNがなくても発行は可能ですが、書店流通や販売管理を考えるなら、奥付にISBNを記載しておく方が望ましいです。
ISBNの取得条件や紙・電子それぞれの扱いを詳しく知りたい方は、『自費出版でISBNコードは必要?紙・電子の違いと取得方法を徹底解説』もあわせて確認しておくと安心です。
電子書籍(Kindleなど)にも奥付は必要なのか
電子書籍の場合も、奥付の考え方は基本的に同じです。
Kindleのような電子出版では、紙のように物理的な最終ページはありませんが、本文の最後や巻末ページに奥付を配置することが推奨されています。
「Amazon Kindleでは明確な法的義務はないものの、KDP(Kindle Direct Publishing)のガイドラインでは、著者名や著作権表示などの明示が推奨されているとされています(詳細はKDP公式ヘルプ要確認)。」
私の経験上、奥付をきちんと入れておくと審査がスムーズに進み、トラブル時の対応も早くなります。
電子書籍は誰でも発行できますが、だからこそ「責任ある発行者であること」を示す奥付が信頼を高めるポイントになります。
Kindle向けに奥付の配置や書き方をより具体的に知りたい場合は、『Kindle出版の奥付とは?必要項目・作り方・正しい位置を徹底解説』をチェックしておくと、電子書籍専用のポイントが一目で整理できます。
自費出版で奥付が必要な理由と法律・ルール上の位置づけ
自費出版では、奥付を省略しても販売そのものはできますが、実務的には必須と考えた方がよいです。
なぜなら、奥付には「誰が責任を持ってこの本を発行したのか」という情報が集約されており、読者や取引先との信頼を左右するからです。
また、万が一トラブルが起きた際、奥付の有無で対応の明確さが変わります。
公式な出版物として扱ってもらうためにも、奥付は“法律の義務ではなく信頼の証”と考えるのが現実的です。
奥付が果たす3つの役割(発行責任・著作権・問い合わせ)
奥付には、大きく3つの役割があります。
1つ目は「発行責任の明示」です。
誰がこの本を作り、誰が発行したのかが明確になることで、著作物としての信頼が生まれます。
これは、商業出版では出版社が負う部分ですが、自費出版では著者自身がその役割を担うことになります。
2つ目は「著作権の保護」です。
「©著者名・発行年」と記載することで、著作権の存在を明示できます。
仮に無断転載やコピーがあった場合も、奥付の記載があることで、いつ誰が著作権を主張していたかを証明しやすくなります。
3つ目は「問い合わせ窓口の提示」です。
読者や書店が質問や取材を希望する際、奥付の連絡先があるとスムーズにやり取りできます。
ただし、個人情報の公開には注意が必要です。
メールアドレスやSNSアカウントなど、プライバシーを守りつつ対応できる手段を選びましょう。
法的義務はある?出版業界での慣習と現状
「実は、多くの一般的な書籍については、奥付を記載する明確な法的義務はないとされています(教科書など一部の例外は公式情報要確認)。
著作権法などでも、奥付の形式は法律よりも出版業界の慣例として扱われることが多いです。」
ただし、出版業界では、奥付がない本は正式な書籍として扱われないことが多いです。
たとえば書店流通やISBN登録を行う場合、発行日や発行者情報の記載が求められるため、実質的には必要不可欠といえます。
私も以前、ISBN取得を依頼した際に、発行者名が奥付に明記されていなかったため修正を求められたことがあります。
このように、「義務ではないが、実務上は不可欠」というのが現場の実態です。
費用や契約、流通も含めた自費出版全体のリスクや注意点は、『自費出版の注意点とは?費用・契約・流通を徹底解説して失敗を防ぐ』でまとめているので、奥付づくりと並行して目を通しておくと失敗を防ぎやすくなります。
印刷会社・電子書籍ストアで求められる奥付の有無
印刷会社によっては、納品前に奥付の有無を確認される場合があります。
「特にPOD(プリント・オン・デマンド)サービスを利用する際は、奥付や発行情報の記載が条件になっている場合があります(各社の利用規約・入稿ガイドは公式ヘルプ要確認)。」なぜなら、トラブル時の責任所在を明確にするためです。
「電子書籍ストアの場合、たとえばAmazon Kindleでは法的な義務はないものの、奥付や発行情報が整っている方が、審査時に確認しやすいと感じられることがあります(運用は公式ヘルプ要確認)。」公式ガイドラインでも「著者情報・著作権表示を明示することが望ましい」とされています。
実際、私のクライアントでも、奥付を入れ忘れた作品が一度審査でリジェクトされた例がありました。
内容には問題がなかったものの、「発行情報の欠如」が理由として挙げられています。
つまり、自費出版において奥付は、形式ではなく「発行者の責任と信頼を示す基本ルール」として考えておくと良いでしょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
自費出版での奥付の書き方と必須項目
奥付を書くときに迷いやすいのが、「どこまで記載すればいいのか」という点です。
紙の本と電子書籍では形式が少し異なりますが、基本となる考え方は同じです。
ここでは、自費出版で信頼を得るために必要な項目と、実際に使える書き方のコツを紹介します。
公式ルールと実務上のバランスを押さえておくと、後から修正する手間も減らせます。
奥付に必ず記載すべき基本項目(書名・著者名・発行日など)
奥付には、最低限以下の5項目を記載するのが一般的です。
1. 書名
2. 著者名(ペンネーム可)
3. 発行日
4. 発行者名(または発行所)
5. 著作権表示(© 著者名 年)
これらは「責任の明示」に関わる部分です。
とくに発行日と著作権表示は、トラブル時の証拠にもなるため、忘れずに記載しておきましょう。
また、日付は「2025年1月26日」や「2025年1月」など、正式な年月の形で書くのが無難です。
西暦・和暦どちらでも構いませんが、表記を統一することが大切です。
私の経験上、初版時に発行日を記載し忘れ、増刷時に混乱するケースが多いです。
奥付は地味ですが、書籍の履歴を守る“記録台帳”のような存在だと考えると良いでしょう。
任意項目として追加できる内容(連絡先・印刷所・発行所など)
基本項目に加えて、必要に応じて以下のような任意項目を追加することもできます。
・連絡先(メールアドレスやSNS)
・印刷所名または印刷サービス名(例:Amazon POD、グラフィックなど)
・発行所住所(個人出版の場合は省略可)
・デザインやイラスト制作協力者
・ISBN(取得している場合)
ただし、個人出版では個人情報の取り扱いに注意が必要です。
住所や電話番号をそのまま記載すると、意図しない連絡やトラブルにつながることがあります。
最近では「メールアドレスのみ」や「公式サイトURL」を記載する著者も増えています。
公式ではないSNSアカウントを載せる場合も、公開範囲や安全性をよく確認してからにしましょう。
電子書籍の場合の奥付テンプレート例
電子書籍(特にKindle出版)の場合も、奥付の考え方は同じです。
ただし、紙のように「ページの最終面」という概念がないため、本文の最後に1ページとして挿入する形になります。
以下は、実際に使える奥付テンプレートの一例です。
――――――――――――――――
書名:〇〇〇〇
著者:△△△△
発行日:2025年1月26日
発行者:△△△△(または個人名)
著作権:©△△△△ 2025
販売サイト:Amazon Kindle
――――――――――――――――
このように、構成をシンプルに保ちながら、必要な情報を明確にまとめることが大切です。
AmazonのKDP公式ヘルプでも、著者名や発行年を明示することを推奨しています。
私の経験では、電子書籍に奥付を入れると審査がスムーズになり、信頼性の高い作品として評価されやすくなります。
「電子だから省略してもいい」と思わず、読者への信頼を示す姿勢として入れておくのがおすすめです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
奥付の具体例とテンプレート:自費出版初心者向けサンプル集
奥付は「どんな書き方が正しいのか」が分かりにくい部分でもあります。
特に自費出版では、出版社のフォーマットがないため、最初に作るときに迷う方が多いです。
ここでは、紙の本と電子書籍それぞれに合ったサンプル例を紹介します。
そのまま使える形に近いので、テンプレートとして保存しておくと便利です。
紙の本向け:印刷所入りの奥付サンプル
紙の本を自費出版する場合は、印刷会社や製本サービスを利用することが多いです。
そのため、奥付には印刷所名を含めるのが一般的です。
以下は、紙の本でよく使われる奥付の基本例です。
――――――――――――――
書名:〇〇〇〇
著者:△△△△
発行日:2025年1月26日
発行者:△△△△
発行所:△△出版
印刷所:株式会社グラフィック
著作権:©△△△△ 2025
――――――――――――――
このように、発行者・発行所・印刷所の3点をそろえると、商業出版に近い印象になります。
とくに「印刷所名を入れておくと信頼性が高まる」ため、販路拡大を考えている人にはおすすめです。
ただし、個人印刷や小部数制作では印刷所名を省略しても問題ありません。
公式には義務ではないため、自分の目的に合わせて調整して構いません。
私自身も初めての本では印刷所を入れませんでしたが、後に書店販売を始めた際には追加しました。
印刷所入りの奥付は、後からの再発行時にも役立つ要素です。
Kindle出版向け:個人著者用の簡易奥付サンプル
電子書籍(Kindle)では、印刷所の記載は不要です。
その代わり、販売プラットフォーム(Amazon Kindle など)と著作権表示を中心にまとめます。
以下は、個人著者が使いやすいシンプルなテンプレートです。
――――――――――――――
書名:〇〇〇〇
著者:△△△△
発行日:2025年1月26日
発行者:△△△△
販売サイト:Amazon Kindle
著作権:©△△△△ 2025
――――――――――――――
Kindle出版では、このような形式で十分です。
Amazonの公式ガイドラインでも、著者名・出版年・著作権表示を推奨しています。
「また、Kindleでは奥付や発行情報を整えておくことで、審査時に内容を確認しやすくなると言われることがあります(実際の運用は公式ヘルプ要確認)。」省略しても販売自体は可能ですが、作品の信頼性を高めるためにも挿入をおすすめします。
奥付ページは、本文の最終ページに追加するか、「あとがき」の後に1ページ挟むと自然です。
注意書きや著作権表示を入れる際の注意点
奥付に著作権表示や注意書きを入れるときは、文面に注意が必要です。
過度に権利を主張する文言や、法律的に誤解を招く表現は避けましょう。
一般的な書き方は以下のようになります。
――――――――――――――
本書の内容の無断転載・複製を禁じます。
©2025 △△△△ All Rights Reserved.
――――――――――――――
これはシンプルで法的にも一般的な形式です。
もし引用や転載を許可したい場合は、「引用の際は出典を明記してください」と追記しておくと親切です。
また、注意書きを入れる場所は奥付の最下部が自然です。
Kindleの場合、改ページを入れて別ページにすることで見やすくなります。
私の経験では、著作権文を長く書きすぎると逆に不自然に見えることがあります。
短く、必要な情報を正確にまとめるのがポイントです。
奥付は小さな欄ですが、著者としての信頼と責任を示す「最後のひとこと」でもあります。
細部まで丁寧に作ることで、読者の印象が大きく変わります。
奥付で注意すべき落とし穴と失敗例
奥付は見た目こそ小さな欄ですが、実は著者の信頼性を左右する大切な部分です。
特に自費出版では、出版社のチェックが入らないため、著者自身がすべての情報管理を行う必要があります。
ここでは、初心者が見落としやすい3つの落とし穴を実例を交えて紹介します。
連絡先を省略したことで問い合わせが届かないケース
自費出版では、販売後に読者やメディアから問い合わせが来ることがあります。
しかし、奥付に連絡手段を記載していなかったために、チャンスを逃してしまうことも少なくありません。
たとえば、「感想を送りたい」「講演依頼をしたい」といった問い合わせが、読者から出版社経由で届くケースがあります。
ですが、発行者名だけでメールやSNSが不明な場合、相手が連絡を諦めてしまうのです。
実際、私の知人の著者も、NHKの取材依頼が印刷所で止まってしまったことがありました。 個人情報を出しすぎず、連絡手段を1つは明示しておくことが大切です。
おすすめは、問い合わせ専用のメールアドレスを作るか、公式サイトやフォームのURLを記載する方法です。
個人情報を公開しすぎてトラブルになった例
反対に、「誠実に見せたい」と思って住所や電話番号をそのまま載せてしまうケースもあります。
これは非常に危険です。
自費出版の場合、書籍は全国のネット書店や図書館にも出回ることがあるため、誰でも閲覧できる状態になります。
そのため、奥付に個人住所を記載してしまうと、ストーカー被害や営業勧誘などのリスクが生まれます。
近年は、奥付に個人住所を掲載しないのが一般的です。
代わりに「〇〇出版事務局」「公式メール」などの名義を使いましょう。
私も最初の出版時に、住所を削除して再入稿した経験があります。
出版社から「POD流通では住所不要です」と指摘され、修正後の方が安心して公開できました。
奥付は信頼を示す場所であって、個人情報の公開欄ではないという意識を持つことが重要です。
著作権や免責文の書き方を誤った事例
奥付で意外に多いのが、著作権や免責文の書き方の誤りです。
特に「©」マークのあとに年号を入れ忘れるミスがよくあります。
著作権表示は「© 著者名 発行年」の形式で記載するのが基本です。
発行年を入れないと、著作権の成立時期を特定しにくくなります。
また、免責文を書く際に「本書の内容に関して責任を負いません」と書いてしまうと、読者に冷たい印象を与えることがあります。
「内容の正確性には配慮しておりますが、利用に際してはご自身の判断でお願いいたします」といった表現の方が穏やかで実務的です。
私自身も、はじめての出版で免責文を強い口調にしてしまい、修正版で柔らかい言い回しに変更しました。
公式ルールでは定型文がありませんが、読者に安心感を与えるトーンで書くことがポイントです。
まとめ:奥付は「信頼と責任」を伝える最後のページ
奥付は、単なる形式ではなく、著者が読者に誠実さを伝える「最後のメッセージ」です。
小さな欄の中に、発行責任・著作権・連絡手段がすべて詰まっています。
自費出版では誰も最終チェックをしてくれないため、内容を確認するのは著者自身です。
特に発行日や著作権表示、連絡手段などは、後から修正が難しい部分なので注意しましょう。
経験上、しっかりした奥付がある作品は審査もスムーズで、読者からの信頼も高いです。
あなたの本を届けたい相手に安心して読んでもらうためにも、奥付は「作品の締めくくり」ではなく「信頼の証」として丁寧に仕上げることをおすすめします。
奥付で信頼を整えたあとは、『自費出版の営業とは?著者が動かす販売戦略と成功の秘訣を徹底解説』を参考にしながら、届けたい読者に本を広げる営業ステップも計画してみてください。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。