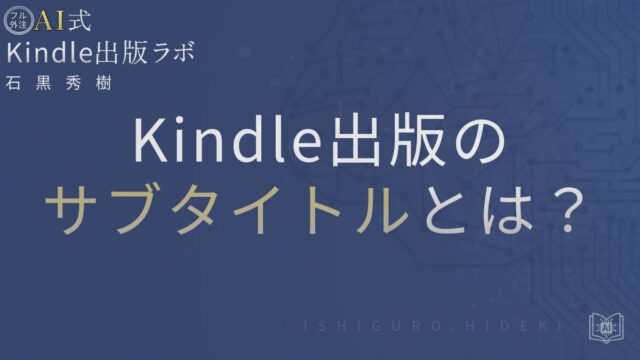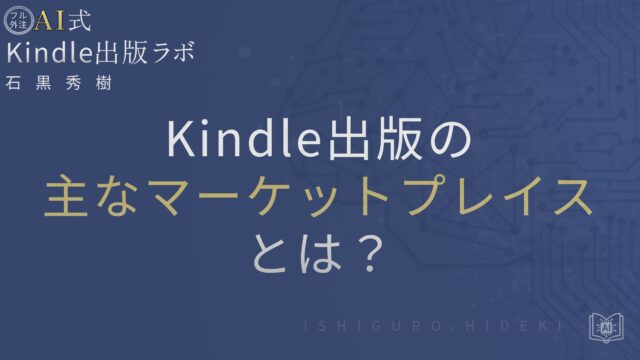自費出版の営業とは?著者が動かす販売戦略と成功の秘訣を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
自費出版をしたあと、「どうすれば本をもっと多くの人に届けられるのか」。
多くの著者が最初に直面するのは、この“営業”という壁です。
出版社が動いてくれると思っていたけれど、現実には本が店頭に並ばなかったり、ネットでも目立たなかったり。
本記事では、なぜ自費出版に営業が欠かせないのか、そして著者自身がどんな一歩を踏み出せば成果につながるのかを、経験者の視点から丁寧に解説します。
初心者の方でも理解できるよう、基本の考え方から実践のポイントまで順に整理していきましょう。
▶ 出版の戦略設計や販売の仕組みを学びたい方はこちらからチェックできます:
販売戦略・集客 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「自費出版+営業」が必要なのか:成功に向けた出発点
目次
自費出版を成功させるために重要なのは、「本を作る」力と「届ける」力の両方を意識することです。」
制作に力を注ぐ著者は多いですが、営業や販促を軽視すると、せっかくの作品が埋もれてしまうことも少なくありません。
ここでは、自費出版の営業がなぜ重要なのかを、3つの観点から整理していきます。」
自費出版をただ出すだけでは売れにくい理由
自費出版は、商業出版とは異なり、出版社が販売リスクを負いません。
つまり「出版=販売してくれる」ではなく、「出版=販売できる環境を作るスタートライン」にすぎないのです。
多くの自費出版サービスでは、Amazonや書店取次に登録する仕組みを整えてくれますが、それだけで売れるわけではありません。
読者は無数の書籍の中から自分に合う一冊を探しています。
その中で“偶然見つけてもらう”には限界があります。
だからこそ、著者自身が動き、「この本を誰にどう届けたいのか」を伝えていく営業活動が不可欠になります。
実際、私がこれまで見てきた著者の中でも、積極的に営業を行った方ほど口コミが広がり、書店での取り扱いも増える傾向がありました。
「出す」ことよりも「伝える」こと。
ここに成功の分かれ道があります。
「営業」と「宣伝・販促」の違いを理解する
初心者の方がよく混同しがちなのが、「営業」と「宣伝・販促」の違いです。
宣伝・販促は、SNS投稿や広告、プレスリリースなど「多くの人に知らせる活動」です。
一方で営業は、書店・企業・団体など、特定の相手に「直接提案して関係を築く活動」です。
たとえば、書店に自ら訪問して本を置いてもらえるよう交渉することや、企業研修用の冊子として導入を提案することがそれにあたります。
宣伝は広く伝える力、営業は“個別に届ける力”。
この2つを組み合わせて初めて、自費出版は「読まれる」段階に進むのです。
公式ガイドでも販促支援が紹介されていますが、実際は著者自身の関わり方次第で効果が大きく変わります。
宣伝・販促の全体像と具体的な打ち手については、『自費出版の宣伝方法とは?電子書籍と紙の本を売る戦略を徹底解説』で詳しく整理しています。
どんな読者に届けば“営業”が機能するのかを明確にする
営業を始める前に欠かせないのが、「誰に読んでほしい本なのか」を明確にすることです。
ターゲットが曖昧なまま営業しても、相手に響かず時間を浪費してしまいます。
たとえば、ビジネス書なら企業の教育担当者、エッセイなら同じ悩みを抱える読者層など、届けたい人の姿を具体的に描きます。
この設定が明確になると、営業先・販路・メッセージが一気に整理されます。
実務的には、「この本を手に取る人がどんな状況にいるか」を一文で言えるかが目安です。
ここまで整理できれば、あなたの営業は“押し売り”ではなく、“必要な人に手渡す行動”へと変わります。
最初は小さな一歩でも、明確なターゲットと目的意識を持つことが、長期的な成功につながるのです。
ターゲット設定と販路選び:自費出版の営業計画を立てる
営業を始める前に、まず整理しておきたいのが「誰に」「どこで」「どんな形で」本を届けたいかという全体像です。
ここが曖昧なまま進めると、営業の方向性がぶれやすく、結果的に時間や費用のロスにつながります。
私自身も初期の頃、ターゲットを明確にせずに動いた結果、まったく響かない層にアプローチしてしまったことがあります。
その経験からも、営業計画は最初の整理がすべての土台になると感じています。
「この章では、自費出版の営業計画として、ターゲットの言語化から販路選択、具体的な営業経路までを順に整理していきます。」
営業計画とあわせて基本の販路設計も押さえておきたい方は、『自費出版で本を売る方法とは?初心者が知るべき販路と集客の基本を徹底解説』もチェックしてみてください。
「誰に・どこで・どんな場面」で読まれる本かを言語化する
営業計画の第一歩は、読者像を明確にすることです。
これは単に「主婦層」「社会人」といった属性ではなく、「どんな悩みを持ち」「どんな状況でこの本を手に取るか」まで落とし込むことが重要です。
たとえば、自己啓発書なら「転職を考えている30代の会社員が夜にスマホで読む」、料理エッセイなら「休日にゆっくり過ごしたい人がカフェで読む」など、具体的なシーンを設定します。
このように描くことで、販路や営業先が自然と見えてきます。
著者の多くがつまずくのは、「すべての人に読んでほしい」という広すぎる想定です。
結果として誰にも刺さらない内容や営業になってしまいます。
強調しておきたいのは、“絞り込むことは、切り捨てることではない”という点です。
むしろ、自分の本が必要な人に確実に届くための選択なのです。
この段階で明確な読者像を言語化できれば、後の販路選びが格段にスムーズになります。
紙媒体と電子書籍それぞれの販路選択と営業チャネル
自費出版では、紙と電子のどちらを選ぶかによって営業のアプローチが変わります。
紙の書籍は、書店や取次を介して販売されるケースが一般的です。
ただし、在庫管理や返品リスクを伴うため、個人での営業は書店や地域イベント中心になります。
出版社の流通サポートを利用する場合も、契約内容によって販路範囲が異なるため、必ず事前確認が必要です。
「一方、電子書籍は在庫リスクがなく、Amazon Kindleなどのプラットフォームを通じて多くの国や地域に販売できます(対応エリアや条件は公式ヘルプ要確認)。」
ここでの営業は「読者にどう見つけてもらうか」が鍵です。
SNSでの発信やレビュー獲得、関連テーマでの露出など、デジタル上の営業戦略が重要になります。
私の経験では、紙と電子を組み合わせる「ハイブリッド型」の戦略が最も安定します。
紙でリアルな信頼を築きつつ、電子で広く届ける。
この二軸を意識すると、営業の幅がぐっと広がります。
書店営業、イベント出展、オンライン販売―3つの営業経路の特徴
自費出版の営業経路は大きく分けて3つあります。
まず「書店営業」です。
ここでは、地元の書店や独立系書店に直接訪問し、サンプルを持参して担当者に提案します。
重要なのは、ただ置いてもらうのではなく「なぜこの店に合うのか」を具体的に伝えることです。
実際、担当者も「この本を求めるお客様がいる」と感じたときに動いてくれます。
次に「イベント出展」。
これは読者との距離を縮める絶好の場です。
文学系や地域文化系イベントでは、来場者と直接会話できるため、販売以上にファン作りの場として効果的です。
書店営業よりも柔軟で、費用対効果も高いケースがあります。
最後に「オンライン販売」。
ここでは、SNSや自分のブログ、メールマガジンを通じて継続的に発信します。
いわば“自分メディア営業”です。
これを地道に続けることで、リアル営業では届かない層に本を届けられます。
ただし、最初から売上を急がず、信頼を積み上げる姿勢が大切です。
この3つの経路はどれも一長一短がありますが、最終的には「自分の読者がどこにいるか」を基準に選ぶことが最も効果的です。
書店で立ち読みする人、SNSで探す人、イベントで直接手に取る人。
その違いを意識して計画を立てると、無理なく自然な営業活動ができます。
営業は一度きりではなく、試行錯誤しながら積み重ねるプロセスです。
焦らず、自分のペースで育てていくことが結果的に長く続く成功につながります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
著者自ら動く営業術:自費出版後の具体的ステップ
本を出したあとに「何をすればいいのか」がわからない――これは多くの著者が直面する共通の悩みです。
出版はゴールではなく、スタート地点です。
ここでは、著者自身ができる3つの営業ステップを具体的に解説します。
それぞれの方法には特徴があり、得意分野や目的に合わせて選ぶことが大切です。
私自身、これまで複数の著者と関わる中で「どの手法をどう組み合わせるか」が結果を左右することを何度も見てきました。
焦らず、ひとつずつ試しながら自分に合う形を見つけていきましょう。
書店・取次への営業に必要な資料とトークポイント
書店営業を行う際に最も重要なのは「準備」です。
多くの方が、まず本を手に書店へ行ってしまいますが、それだけでは担当者の印象に残りません。
最低限必要なのは、販促用の資料(プレスリリース・チラシ・販売概要書)と、短く整理されたトークポイントです。
資料には「本の概要」「想定読者」「特徴的なテーマ」「販売実績(あれば)」などをまとめます。
担当者は限られた時間で判断するため、1枚の紙で魅力が伝わる構成が理想です。
また、口頭では「この書店のお客様に合う理由」を必ず添えること。
たとえば「この地域は教育関係の本がよく売れていると伺いました」といった一言が、信頼感を生みます。
注意したいのは、取次経由で全国流通できる出版社もありますが、実際には取次への直接交渉は個人では難しいという点です。
取次は販売実績と安定した供給が前提となるため、まずは書店単位の営業で関係を築くほうが現実的です。
地元書店から始めて、実績を積みながら拡げていく流れを意識しましょう。
これは地味に感じますが、着実に販売につながる最短ルートです。
オンライン・SNSを活用した自費出版本の営業方法
SNSを使った営業は、今の時代に欠かせないアプローチです。
特に電子書籍の場合、SNS経由での購入率が高く、レビューや口コミが売上を左右することもあります。
重要なのは「売り込み感を出さない」ことです。
宣伝ばかり投稿してしまうと、フォロワーの反応が鈍くなります。
私が見てきた成功事例では、著者の日常や制作背景を交えた自然な発信が読者との距離を縮めていました。
たとえば「この章を書いたときの気づき」や「取材で感じたこと」を写真付きで紹介するだけで、作品に親しみを持ってもらえます。
また、投稿の最後に「詳しくはプロフィールのリンクから」と案内を添えるだけで十分です。
直接的な誘導より、読者の“共感”を積み上げるイメージで進めましょう。
さらに、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSごとに特性があります。
Instagramはビジュアル重視、Xはリアルタイム性が強く、ハッシュタグ戦略が効果的です。
最初は一つのSNSに絞って継続することをおすすめします。
投稿を続けることでデータが蓄積し、「どんな発信に反応があるか」が見えてきます。
それが次の営業戦略のヒントにもなります。
イベント・セミナー・コラボを活用する「著者直販型営業」
最後に紹介するのは、著者が直接販売や交流を行う「直販型営業」です。
イベントやセミナー、トークショーなどで直接読者と会うことは、オンラインでは得られない信頼を築くチャンスになります。
特にエッセイや専門書の場合、著者の人柄が伝わるだけで読者の購買意欲が高まるケースもあります。
出展の際は、ただ本を並べるのではなく、「なぜこの本を書いたのか」を語れる準備をしておくこと。
この一言があるだけで、相手の記憶に残りやすくなります。
また、コラボイベントも有効です。
ジャンルの近い作家やクリエイターと合同で出展することで、互いの読者層に広がりが生まれます。
注意点としては、在庫や搬入出の手間を考慮すること。
私も初めて参加した際、在庫を持ち込みすぎて後半は運搬に苦労しました。
経験上、見込み客数の6〜7割程度の在庫がちょうどよいバランスです。
売り切れた場合は、後日発送の予約販売に切り替えれば対応できます。
このように、書店・オンライン・イベントの3経路を組み合わせることで、営業の幅は大きく広がります。
大切なのは、「どの経路が自分の本に最も合うか」を見極め、継続できる形で動くことです。
短期的な結果より、読者との信頼関係を育てる姿勢こそが、長く読まれる著者になる第一歩になります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
注意点と失敗しやすい落とし穴:自費出版の営業で気をつけること
自費出版の営業では、努力の方向を間違えると時間もお金も消耗してしまいます。
特に「営業=販売代行してもらえる」と誤解してしまうケースは非常に多いです。
この章では、著者が失敗しやすいポイントを3つに分けて整理し、注意すべき点を具体的に解説します。
私自身も過去に、営業代行に頼りすぎて失敗した経験があり、その教訓を踏まえてお伝えします。
営業まわりでありがちな失敗パターンや事前に避けたいポイントは、『自費出版で後悔しないための完全ガイド|失敗事例と対策を徹底解説』に具体例付きでまとめています。
営業代行や出版社の営業オプションを過信しないために
自費出版を扱う出版社の中には、「営業サポート」「販促プラン」などのオプションを提供しているところがあります。
ただし、これらのサービスの多くは「紹介」や「提案」にとどまり、実際に販売が保証されるわけではありません。
公式には「販売促進の一環」と明記されていますが、実務上は“動き方をサポートする”レベルに近いこともあります。
私が以前関わった著者の中には、「営業代行をお願いしたのに書店で見かけなかった」と不満を持つ方もいました。
原因は、出版社側が提案までしか行わず、継続的な交渉や棚管理を行っていなかったためです。
つまり、営業代行=自分の代わりに売ってくれる、ではないのです。
依頼する際は、対応範囲(訪問・電話・提案書提出など)を契約書や公式説明で必ず確認しておきましょう。
また、担当者とのコミュニケーションを取り、どの書店・販路を対象に動くのかを明確にすることが大切です。
コスト対効果を見極めるための「見える化」のポイント
営業活動には、交通費・印刷費・イベント出展費など、目に見えないコストがかかります。
これを感覚で判断してしまうと、「思ったよりお金が減っていた」「時間ばかり使っている」といった事態になりがちです。
特に、SNS広告や販促グッズなどは、効果が見えにくいまま出費が増えるケースが多いです。
おすすめなのは、営業活動を「見える化」することです。
日ごとの行動や費用、反応を簡単な表にまとめるだけで、どの施策が有効だったかがすぐにわかります。
たとえば「書店営業×5件→2冊販売」「Instagram投稿→PV増加」など、数字と結果を紐づけて整理します。
私も最初は手書きで記録していましたが、慣れてくるとGoogleスプレッドシートなどで管理すると便利です。
このデータが蓄積されることで、「今後どこに力を入れるべきか」が明確になります。
効率化の第一歩は、感覚ではなく数字で見ることから始まります。
著者が放置しやすい“フォローアップ営業”の重要性
営業を一度行ったあとに、そのまま連絡を絶ってしまう人は意外と多いです。
しかし、実際の成果は「最初の営業」ではなく、「その後のフォロー」で決まることが多いです。
書店や企業担当者は忙しく、提案を受けてもすぐに動けないことがあります。
そんなときに、1〜2週間後に軽くお礼と近況を添えたメールを送るだけで印象が変わります。
私の経験上、フォローを丁寧に続けた著者ほど、半年後に思わぬ機会を得ています。
たとえば、イベントでつながった相手から「別の場で紹介したい」と声をかけられるなど、地道な継続が信頼につながります。
また、フォローアップの内容は長文である必要はありません。
「先日はお時間をありがとうございました」「〇〇で取り上げていただいた反響がありました」など、短くても構いません。
営業は一度きりの勝負ではなく、関係を育てる過程です。
“営業=人とのつながりを維持する行動”と意識するだけで、行動の質が大きく変わります。
まとめ:自費出版で“届けたい人”に届く営業を始めるために
「自費出版の営業は、派手な手法よりも「誰に、どんな想いで届けたいか」を明確にし、それを地道に伝えていくことがとても大切です。」
出版はゴールではなく、著者としての新しいスタートです。
書店・オンライン・イベントなどの販路を組み合わせ、自分の強みを生かした営業を続けることで、少しずつ読者とのつながりが育ちます。
自費出版で動く前に商業出版との違いも整理しておきたい場合は、『自費出版と商業出版の違いとは?費用・流通・契約を初心者向けに徹底解説』もあわせて読んでおくと全体像がつかみやすくなります。
忘れてはいけないのは、どんなに小さな動きでも「自分の言葉で届けること」が読者の心に響くということです。
最初から完璧な営業計画はありません。
トライ&エラーを重ねながら、自分らしい伝え方を磨いていきましょう。
そうすることで、あなたの本はきっと“必要としている誰か”の手に届くはずです。
そして、その一冊が新しい出会いや次の創作へとつながっていくのです。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。