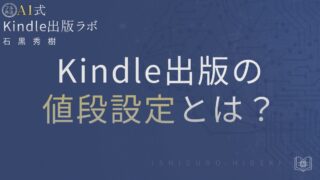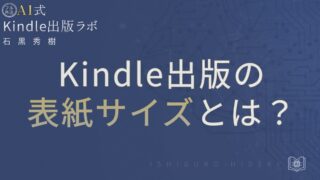Kindle出版の費用とは?初期費用ゼロで始める方法を徹底解説
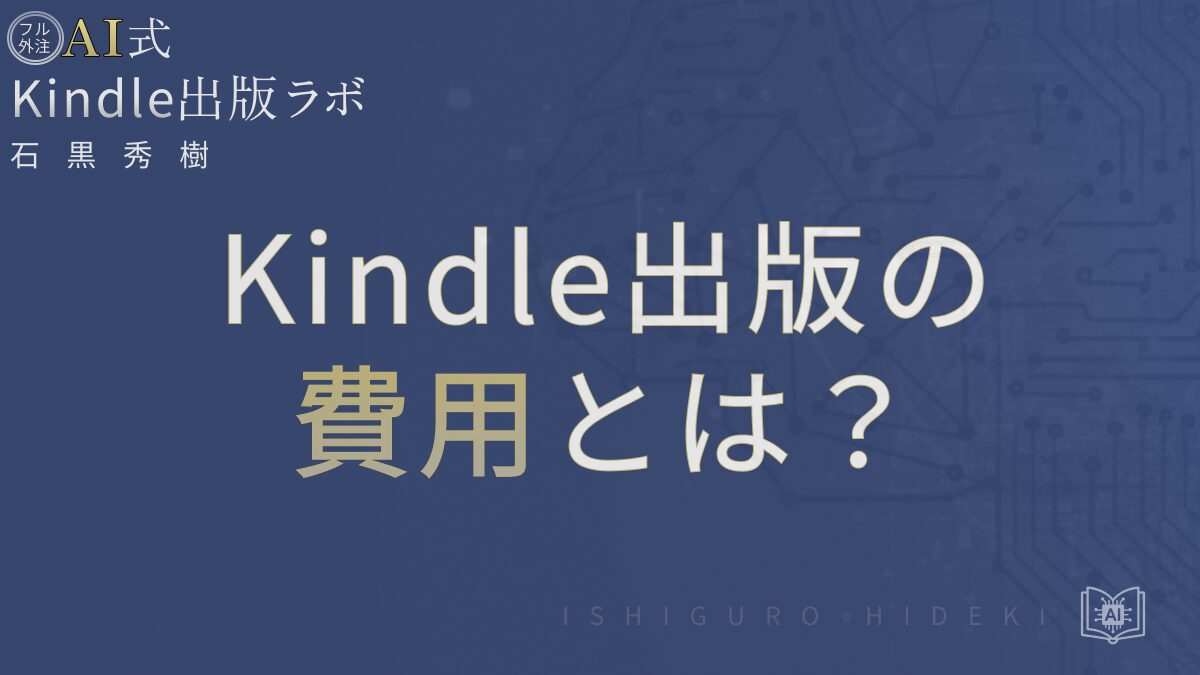
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版に興味はあるけれど、「費用ってかかるの?」と不安に思う方は多いです。
私自身も最初に調べたとき、「出版=お金がかかる」というイメージが強く、慎重に調べました。
実際、AmazonのKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)では、電子書籍の出版自体は無料です。
しかし、出版後に発生する「配信コスト」や、制作段階で発生しうる「外注費」など、知っておかないと損をするポイントもあります。
この記事では、Kindle出版における費用の有無と内訳を、初心者でも理解できるように整理して解説します。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
1.Kindle出版で「費用がかかるのか?」の疑問に答える
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
Kindle出版は「個人でも無料でできる」と聞いたことがあるかもしれません。
実際、その通りです。
ただし、仕組みを正確に理解しておかないと、「思わぬところでコストがかかっていた」ということもあります。
ここでは、KDPの基本構造と、「出版費用」という言葉の中身を整理していきましょう。
電子書籍(Kindle本)出版時の基本費用は無料という事実
Kindle本を出版するためのアカウント登録、原稿のアップロード、販売ページの作成までは、すべて無料で行えます。
この「無料で出版できる」というのは、KDP最大の特徴であり、他の出版方法と比べたときの大きな魅力です。
私も初めて出版したときは、手数料の請求などは一切なく、ほんとうにゼロ円で販売開始できました。
つまり、KDPでは「出すだけ」でお金がかかることはありません。
費用が発生するのは、制作の外注(任意)と、70%ロイヤリティ選択時の配信コスト(販売時控除)です。
Kindle出版の費用の全体像や不要な出費を避けるコツをさらに知りたい場合は、『Kindle出版の費用は本当に無料?必要コストと節約術を徹底解説』もあわせてチェックしておくと安心です。
「出版費用」に含まれるものとは何か?(外注・配信コスト・ロイヤリティ条件)
出版費用という言葉には、いくつかの意味が含まれます。
まず、最も一般的なのは「制作にかかる外注費」です。
たとえば、表紙デザインをプロに頼む、文章の校正を外注する、EPUB形式への変換を代行してもらうなどです。
こうした費用は任意であり、品質を上げたい人が選ぶオプションです。
次に、販売後に発生する「配信コスト」があります。
これは70%ロイヤリティを選択した場合のみ発生し、電子書籍データのファイルサイズに応じて1MBあたり数円が差し引かれる仕組みです。
日本のKDPでは、70%ロイヤリティを適用するために「KDPセレクト」への登録が必要です。
この点は見落としやすく、「70%を選んだつもりが35%しか受け取れなかった」というケースもあります。
最後に「ロイヤリティ条件」です。
電子書籍では、35%または70%のいずれかを選べますが、条件を満たしていないと自動的に35%扱いになります。
公式ヘルプでは詳細が公開されていますので、出版前に必ず確認しましょう(条件は変更される可能性があります)。
紙の本(ペーパーバック)と比較した場合の費用の違い
Kindle出版では電子書籍以外に「ペーパーバック(紙の本)」も出版できます。
電子書籍との大きな違いは、印刷コストが発生する点です。
ペーパーバックでは販売時に印刷コストが自動的に差し引かれ、その残りがロイヤリティとして支払われます。
つまり「出版時に払う費用」はゼロですが、「販売時にかかる原価」があるという仕組みです。
印刷コストはページ数や紙の種類で変わるため、KDPの公式計算ツールで確認すると安心です。
とはいえ、紙の本を選んでも出版自体は無料で、在庫リスクもありません。
この点は、一般的な商業出版とは大きく異なるKDPの強みといえます。
2.具体的に知る:Kindle出版にかかる可能性のある費用の内訳
Kindle出版は「無料で始められる」とはいえ、実際にはいくつかの場面で費用が発生する可能性があります。
とはいえ、これらは「やむを得ず払う」ものではなく、目的に応じて選べる費用です。
ここでは、出版にかかる主な3つの項目――外注費用・配信コスト・印税計算上の調整――を整理して解説します。
実務の中では、これらを知らずに始めて「思ったより利益が減った」というケースも少なくありません。
仕組みを理解しておけば、後悔せずに出版を進めることができます。
外注費用:表紙デザイン、EPUB化、校正・編集など
もっとも多くの人が検討するのが「制作の外注」です。
電子書籍は自分でWordやCanvaを使って作ることもできますが、見た目の完成度や読みやすさを高めたい人は外注を選ぶ傾向があります。
代表的な外注項目は、表紙デザイン、EPUBデータの変換、文章の校正・編集などです。
たとえば、表紙デザインをデザイナーに依頼すると、相場は5,000円〜15,000円ほど。
EPUB変換代行は1冊あたり数千円〜1万円程度が一般的です。
文章校正やリライトを頼む場合は、文字単価で0.5円〜2円ほどかかることもあります。
このように、外注費は「品質向上に投資するかどうか」で決まる任意のコストです。
私自身、初めて出版したときはすべて自作しましたが、2冊目では表紙だけ外注しました。
やはりプロに任せるとクリック率(CTR)が上がる傾向があり、見た目の印象が収益にも関係してくると感じます。
ただし、初出版の段階では「完璧さ」より「完了」を優先してよいでしょう。
慣れてから外注を取り入れるのが、もっともコスト効率の良い進め方です。
配信コスト:70%ロイヤリティ選択時の影響と日本版KDPの条件
Kindle出版では、販売価格に対して35%または70%のロイヤリティを選択できます。
このうち、70%を選ぶときに注意すべきなのが「配信コスト」です。
配信コストとは、電子書籍ファイルのサイズに応じて販売時に差し引かれる手数料のことです。
日本では通常、1MBあたり数円が引かれます(数値は公式ヘルプで確認を推奨)。
ここでの落とし穴は、画像が多い本や高解像度データを含む本です。
ファイルサイズが大きいほど配信コストが高くなり、利益率が下がります。
私が以前に作成したイラスト多めの解説書では、1冊あたり10〜20円ほど差し引かれ、思ったより利益が減りました。
配信コストは70%ロイヤリティ適用時に、ファイルサイズに応じてロイヤリティから控除されます(金額は公式ヘルプ要確認)。
配信コストやロイヤリティが最終的な振込額にどう影響するかは、『Kindle出版の収益はどう決まる?印税と既読の仕組みを徹底解説』で具体的な計算例とあわせて確認しておくとイメージしやすくなります。
また、70%ロイヤリティを適用するには、日本では「KDPセレクト」への登録が必要です。
登録していない場合は自動的に35%になります。
KDPセレクトは90日間の独占配信契約が条件となるため、他のプラットフォームでも販売したい人は慎重に選びましょう。
(この制度は定期的に更新されるため、詳細はKDP公式ヘルプ要確認です。)
価格設定・税・印税の計算が収益に与える影響
出版後の収益を左右するのが「価格設定」と「印税の仕組み」です。
Kindle出版では、著者が設定した価格に対してロイヤリティが計算されます。
ここで注意したいのは、Amazonの商品ページで表示される価格(消費税込み)と、著者が設定する価格(税抜き)が異なる点です。
印税は後者、つまり税抜き価格を基準に計算されます。
たとえば、設定価格が500円(税抜)で70%ロイヤリティの場合、配信コストを除いた約350円前後が収益です。
一方、同じ価格でも35%ロイヤリティでは175円前後になります。
35%と70%それぞれのロイヤリティの違いや向いているケースについては、『Kindle出版の印税とは?70%と35%の違いを徹底解説』で仕組みを整理しておくと、自分に合った印税設定を選びやすくなります。
さらに、KDPセレクトに登録していないと一部の販売地域では70%が適用されません。
このように、単純な「定価×印税率」では計算できない構造になっています。
また、日本の所得税の対象になるため、収益を得た後の確定申告も忘れずに。
特に副業としてKindle出版をしている場合、年間の印税収入が少額でも記録を残しておくと安心です。
印税にかかる所得税や確定申告の流れを事前に押さえておきたい方は、『Kindle出版の税金とは?源泉徴収と節税を徹底解説』を参考にして、税務まわりの不安を先に解消しておくのがおすすめです。
これらの点を把握しておけば、収益を最大化しつつ、無駄なトラブルを避けることができます。
最後に、実務上の補足です。
ロイヤリティは各マーケット通貨で計算され、支払い時に選択通貨へ換算されます(為替影響あり・公式ヘルプ要確認)。
公式の仕様を理解したうえで、実際の振込額を定期的に確認することが、安定した収益運用の第一歩です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
3.費用を抑えて出版するための実践ポイント
Kindle出版は、基本的に無料で始められます。
しかし、「無料で出せる」と言われても、どこまで自分でできるのか、何を気をつけるべきなのか、最初はわかりづらいですよね。
ここでは、私が実際に複数冊を出版してきた経験をもとに、初出版でムダな出費を避けつつ、効率よく進めるためのポイントを紹介します。
初出版で“無料出版”を実現するステップ(KDP登録~配信まで)
無料でKindle出版を実現するには、KDPの基本機能を最大限に活用することが大切です。
まず、Amazonアカウントを使ってKDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)に登録します。
登録後、WordやGoogleドキュメントなどで本文を作成し、KDPが対応している形式(.docxなど)でアップロードするだけで出版可能です。
表紙も、KDP内の「カバー作成ツール(Cover Creator)」を使えば、テンプレートをもとに無料でデザインできます。
慣れないうちは十分見栄えの良い仕上がりになるので、特別なツールを用意する必要はありません。
また、電子書籍(Kindle本)ではISBNは不要です。KDP側でASINが付与されます(紙は別途要件あり・公式ヘルプ要確認)。
このように、すべての工程をKDP上で完結させれば、完全無料で出版が可能です。
ただし、原稿や表紙の完成度を上げたい場合は、後述する外注を検討してもよいでしょう。
最初はコストをかけずに試し、その後で改善する方が、リスクも小さく成果を積み上げやすいです。
外注を使うか自分でやるか:コストと時間のバランス
外注を使うかどうかは、多くの著者が迷うポイントです。
私自身、最初の出版ではすべて自作で進めましたが、2冊目以降は部分的に外注しました。
特に「表紙デザイン」と「校正」は、読者の印象や信頼性に関わる部分です。
自作のメリットは、コストがかからないことと、スピード感があることです。
一方で、クオリティを一定以上に保つには時間と労力が必要です。
そのため、「自分の得意・不得意」を見極めながら分担するのが理想です。
たとえば、本文や構成は自分で書き、表紙だけをデザイナーに依頼するケースがよくあります。
依頼費用は5,000円〜10,000円ほどですが、クリック率や購入率に影響するため、投資効果は高めです。
時間を優先するなら、外注をうまく取り入れるのも一つの手です。
ただし、クラウドソーシングを利用する際は、著作権の扱いや契約内容を必ず確認しておきましょう。
ロイヤリティ70%を選ぶ際の注意点と“何が差し引かれるか”の整理
KDPでは、販売価格に対して35%または70%のロイヤリティ(印税率)を選べます。
多くの著者が「70%の方が得」と感じますが、仕組みを理解しておかないと、実際の受け取り額が想定より少なくなることがあります。
まず、日本で70%を選ぶには「KDPセレクト」への登録が必要です。
この登録をすると、出版した本を90日間Amazon独占で販売する代わりに、ロイヤリティが70%になります。
ただし、70%ロイヤリティには「配信コスト」が差し引かれます。
この配信コストは、電子書籍のファイルサイズに応じて1MBあたり数円が控除される仕組みです。
たとえば、画像が多い本やフルカラー作品は、配信コストが10〜20円を超える場合もあり、1冊あたりの利益が小さくなるケースがあります。
また、設定価格が250円未満または1,250円を超える場合は、自動的に35%ロイヤリティになる点にも注意が必要です。
「70%を選べば単純に2倍もうかる」という誤解は禁物です。
販売条件・ファイルサイズ・価格設定を総合的に見て判断することが重要です。
なお、ロイヤリティの支払いはドル建てで行われ、日本円への換算時に為替レートの影響を受けます。
そのため、実際の振込額は月ごとに多少変動します。
公式では為替レートや配信コストの基準が明示されていますが、最新情報はKDP公式ヘルプで確認するのが確実です。
このあたりを把握しておくと、「なぜ今月の印税が減ったのか?」と悩むこともなくなります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
4.よくある失敗・誤解とその回避策
Kindle出版の費用について調べると、「本当に無料なの?」「どこかでお金がかかるのでは?」という不安を持つ人が多いです。
実際、私も初出版のときは同じように感じました。
ここでは、特に初心者が陥りやすい誤解と、それを防ぐための具体的なポイントを紹介します。
「出版=高額費用が必要」という思い込みと真実
多くの人が持っている誤解のひとつが、「出版にはまとまったお金が必要」というものです。
これは紙の商業出版のイメージからくるもので、印刷・流通・在庫管理などのコストが高額になるため、その印象が強く残っています。
しかし、Kindle出版(電子書籍)は、登録も出版も完全に無料です。
Amazonのプラットフォーム上でデータを公開する仕組みなので、印刷費も在庫も発生しません。
私も最初は「出版ボタンを押したあとで課金されるのでは?」と半信半疑でしたが、実際には1円もかかりませんでした。
費用が発生するのは、制作を外注したときや、販売後の配信コストが差し引かれるケースのみです。
つまり、スタートにあたって「資金ゼロでも始められる」のがKDPの最大の強みといえます。
とはいえ、外注や広告を使うと費用はかかります。
ただしそれは“投資的な費用”であり、必須ではありません。
ここを混同して「Kindle出版=お金がかかる」と誤解してしまう人が多いのです。
「まずは無料で出してみて、次で改善する」くらいの気持ちで取り組むのが現実的です。
配信コストやロイヤリティ条件を把握していなかったために収益が低くなったケース
次によくあるのが、「ロイヤリティを70%に設定したのに思ったより儲からない」というトラブルです。
原因の多くは、配信コストや価格条件を正確に把握していないことにあります。
70%ロイヤリティを選ぶ場合、日本ではKDPセレクトへの登録が必須です。
これを知らずに登録しなかった場合、自動的に35%が適用されます。
また、70%ロイヤリティでは配信コストが差し引かれるため、画像が多い本では1冊あたりの利益が大幅に減ることもあります。
私も初期の頃、ファイルサイズを軽視して画像を多く入れた結果、想定より利益が下がった経験があります。
このような落とし穴を避けるには、出版前に「販売価格・ロイヤリティ条件・配信コスト」の3点を必ずセットで確認することです。
Amazonの公式ヘルプ内にはシミュレーション例も掲載されているので、事前に利益を計算しておくと安心です。
特に、価格を250〜1,250円の範囲に設定すること、そしてKDPセレクト登録を忘れないことが重要です。
日本版KDPの最新仕様確認の重要性(公式ヘルプ参照)
KDPの仕様や条件は、年に数回ほど小さな変更が加えられることがあります。
配信地域、ロイヤリティ条件、ページ単価などが改定されることもあるため、最新情報をチェックする習慣をつけましょう。
たとえば、海外のブログやYouTubeを参考にすると、米国版KDPの条件が紹介されていることが多いです。
しかし、日本版KDP(Amazon.co.jp)は独自の設定があり、「同じだと思っていたら違っていた」というケースも珍しくありません。
実際に私も、米国の記事をそのまま信じてロイヤリティの条件を誤解したことがあります。
情報を確認する際は、必ずKDP公式ヘルプの「日本(JP)」ページを参照してください。
特に、ロイヤリティ条件・KDPセレクト規約・ペーパーバック印刷費の計算方法などは、最新版を確認するのが確実です。
このひと手間で、後のトラブルを大きく防げます。
5.まとめ:Kindle出版の費用を正しく理解して始めよう
Kindle出版は、正しく理解すれば「初期費用ゼロで始められる」最もリスクの少ない出版方法です。
出版そのものに費用はかからず、外注や配信コストは必要に応じて選択できます。
ただし、ロイヤリティの条件や価格設定を誤ると、せっかくの収益が減ってしまうこともあります。
そのため、「無料で出せるけど、仕組みは理解しておく」という意識が大切です。
まずはKDPの基本的な流れを体験し、1冊目を出すことを目標にしましょう。
出版を通じて学んだ知識は、次の本や他のビジネスにも必ず役立ちます。
もし自分の言葉で伝えたいことがあるなら、今が始めどきです。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。