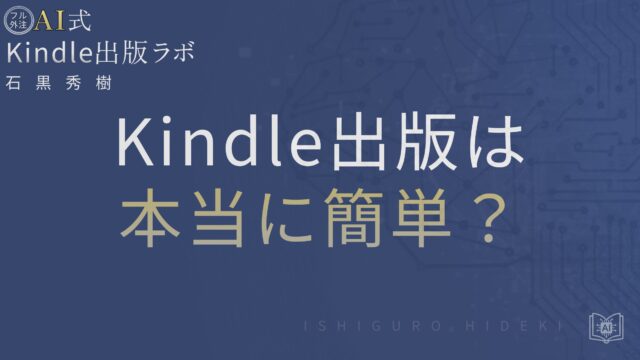Kindle出版の方法とは?日本向けKDPで電子書籍を最短で出す手順を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を調べると、たくさんの情報が出てきますが、初心者が一番知りたいのは「どう始めればいいの?」という一点です。
私も最初は用語や設定画面に戸惑いましたが、手順さえ整理すれば、思ったよりスムーズに出版できます。
この記事では、日本向けAmazon.co.jpで電子書籍を出すための最短ステップを、実体験と公式情報を踏まえてやさしく解説します。
余計な話は省いて、初心者が迷うところを先回りして説明しますね。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
【Kindle出版 方法】日本向けKDPで電子書籍を最短で出す手順(初心者向けガイド)
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
KDP(Kindle Direct Publishing)は、誰でも無料で電子書籍を出版できるAmazonのサービスです。
ただし、最初にアカウント設定や原稿準備など、押さえるポイントがあります。
「全部の機能を完璧に理解してから」ではなく、まず基本の流れを掴んで、小さく出して改善するほうが実務上はスムーズです。
実際に私も、初出版はシンプル構成で公開し、後から説明文や体裁を直しました。
Kindle出版とは?KDPの基本とできること(電子書籍中心/紙は最小限の補足)
Kindle出版とは、Amazonのプラットフォームに電子書籍を登録し、読者がKindleアプリや端末で読めるようにする仕組みです。
KDPを使えば、紙の在庫管理や印刷費は不要です。
日本向けの場合、主軸は電子出版です。
あとから必要に応じてペーパーバックを追加できますが、紙は別工程(表紙の厚み設定など)なので、まずは電子に集中するほうが負担が少ないです。
KDPでは、原稿ファイルと表紙ファイルをアップロードし、価格やロイヤリティを設定します。
初心者が驚くポイントですが、電子書籍はISBNが不要で、Amazon側でASINという識別番号が付与されます。
KDPは無料で使えますが、注意点もあります。
内容ガイドラインがあり、過度な刺激表現や不適切な記述はNGです。
ただし教育・注意喚起の文脈で抽象的に触れるのは問題ありません。
私の経験では、公式ヘルプを読みつつ進めると安心です。
細かい仕様がアップデートされることもあるため、迷ったら最新情報を確認しましょう。
まず何をする?KDPアカウント登録と日本向け設定(税務・銀行口座)
最初のステップは、AmazonアカウントでKDPにログインし、出版者情報を登録することです。
ここで税務情報(源泉徴収の扱いなど)と、売上の振込先となる銀行口座を設定します。
KDP登録の具体的な流れは『Kindle出版の登録手順とは?KDPアカウントから税務設定まで徹底解説』にも整理しています。
日本在住の場合、日本の銀行口座を設定すればOKです。
米国税務フォーム(W-8BEN)の入力が必要ですが、画面指示に沿って進めれば問題ありません。
コツとして、住所や氏名は公的書類と表記ゆれがないように入力しましょう。
実務上、表記揺れがあると審査で一時的に保留となるケースを見たことがあります。
アカウント登録時は、すぐ出版できなくても焦らなくて大丈夫です。
KDP側も最初の審査で慎重になる場合があるので、丁寧に入力すれば安心です。
ここをクリアすると、いよいよ原稿アップロードの準備に入れます。
公開までの全体フローを30秒で把握(本の詳細→コンテンツ→価格→公開)
KDPの作業画面は「本の詳細」「コンテンツ」「価格設定」の3ステップです。
この順番を理解しておくと、実作業で迷いません。
1. 本の詳細
タイトル、著者名、説明文、キーワード、カテゴリー
2. コンテンツ
EPUB原稿と表紙画像をアップロード、プレビューで体裁確認
3. 価格設定
ロイヤリティ(35% / 70%)と価格を設定
公開ボタンを押すと、審査に入ります。
反映時間は変動しますが、早ければ数時間、長いと数日かかることもあります。
反映時間は案件により変動します。目安は最大72時間程度で、最新の公式ヘルプを確認してください。
また、KDPセレクトは任意で、独占配信と各種プロモーションが利用可能です。日本での70%適用条件に関わる場合があるため、最新条件は公式ヘルプ要確認。
ただし、日本で70%ロイヤリティを選ぶ際の条件などは更新されることがあるため、最新の公式ヘルプで必ず確認してください。
ここまで理解できれば、出版までの流れは十分掴めています。
次は、原稿と表紙を整えて、実際にアップロードしていきましょう。
準備:原稿と表紙を正しく整える(つまずき最小化)
原稿と表紙の準備は、KDP出版の中で一番つまずきやすい部分です。
ここを丁寧に進めると、公開後の修正も少なくなり、スムーズに進みます。
私も最初の1冊はここで時間を使いましたが、基本を押さえれば難しくありません。
いきなり凝ったレイアウトを狙うより、まずはシンプルに整えるのがおすすめです。
迷いがちなポイントは「形式」「見栄え」「読みやすさ」の3つです。
順番に見ていきましょう。
EPUBの基本仕様については『Kindle出版のEPUB形式とは?作り方と注意点を徹底解説』でも確認できます。
原稿の作り方:EPUB推奨・リフロー中心の基本とWord原稿の注意点(改ページ・禁則)
KDPではEPUB形式が推奨されています。
EPUBは文字サイズや行数が端末に合わせて変わる「リフロー型」が基本です。
ただ、最初からEPUBを直接作らなくても大丈夫です。
WordはDOCX形式での入稿が前提です。EPUBでの入稿も推奨されます(細かな再現性はEPUBが安定/公式ヘルプ要確認)。
ただし、Wordの場合は改ページや改行の癖がそのまま反映されてしまうことがあります。
特に全角スペースやタブを多用すると、端末で表示が崩れます。
私も初期にこれで苦労し、Kindle Previewerで確認して修正を繰り返しました。 「見た目をスペースで調整しない」「段落スタイルを使う」という基本を意識すると、仕上がりが安定します。
また「禁則処理」(句読点が行頭に来ないようにするルール)は自動で完璧に処理されないことがあります。
文章が自然に見えるか、プレビューで最後にチェックしましょう。
目次・章立て・装飾の最小ルール(読みやすさ重視・公式ヘルプ要確認)
目次や章立ては、読みやすさと審査通過のためにも重要です。
見出しは「見出しスタイル」を使うと、自動的に目次生成ができて便利です。
ついやりがちなのが、装飾を増やしすぎることです。
太字・改行・画像を多用すると、端末によっては乱れが出ます。
公式ヘルプでも、過度な装飾は推奨されていません。
シンプルな段落構成で、章ごとに明確な区切りを作りましょう。
私の場合、見出し→リード文→本文という流れを統一すると、読みやすさが安定しました。
この段取りだけで、編集の手間がぐっと減ります。
また、目次リンクが正しく飛ばないと読者の離脱につながります。
KDPプレビューとKindleアプリの両方で確認するのがおすすめです。
表紙の作成:推奨サイズ・比率・文字可読性のチェックポイント
表紙はスクロール中のユーザーが最初に目にする部分です。
KDP推奨の表紙比率は縦横比1.6:1です。例は「縦2560×横1600px」(推奨)と明記します。
まずはこの比率を守りましょう。
比率が崩れると、自動調整で意図しないトリミングが入ることがあります。
タイトル文字は大きめ、背景はシンプルが基本です。
スマホで縮小表示して読めるサイズかどうかを確認してください。
私も最初、凝った背景画像を使って埋もれてしまいました。
背景を少し落ち着かせ、文字を太くしただけでクリック率が上がりました。
表紙作成ツールはCanvaや有料ツールなどありますが、無料でも十分作れます。
ただし、素材の利用規約と著作権には注意し、フリー素材でも商用利用可を確認しましょう。
最後に、KDPの「表紙プレビュー」で枠ズレがないかチェックするのを忘れずに。
推奨比率や解像度の基準は『Kindle出版の表紙サイズとは?初心者でも失敗しない最適設定を徹底解説』で詳細を整理しています。
以上で、原稿と表紙の準備はできました。
次はKDPの入力画面で設定を進め、公開のステップへ進みます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
実装:KDPの各画面でやること(Amazon.co.jp前提)
KDPの入力画面は、大きく3つのステップに分かれています。
ここを理解しておくと、迷わず一気に進められます。
私自身、最初は項目が多く感じましたが、順番に沿えば自然に設定できます。
途中で止まっても、下書き保存できるので安心してくださいね。
ポイントは「読み手に誤解を与えない」「Amazonのルールに沿う」という姿勢です。
これを意識するだけで、審査もスムーズに通りやすくなります。
本の詳細:タイトル・著者名・説明文・キーワードとカテゴリー設定の考え方
最初に入力するのが「本の詳細」です。
タイトル、著者名、説明文、カテゴリー、キーワードを設定します。
タイトルは内容が正確に伝わるものを選びましょう。
誇張表現や過度な煽りは避け、誠実な表現のほうが長期的にファンがつきます。
著者名は本名でもペンネームでも構いません。
個人的には、分野ごとに統一したペンネームを使うとブランディングしやすいです。
説明文は読者の「なぜ読むのか」を明確に書きます。
箇条書きや短文を使うと、スマホでも読みやすいです。
キーワードは検索に関係しますが、過剰な詰め込みは逆効果です。
自然な言葉で、読者が検索しそうな語句を選びましょう。
カテゴリーはAmazonの分類です。
ジャンルに合ったものを選び、迷ったら公式ガイドを参照してください。
「意外と合わないカテゴリーを選んでしまう」方も多いので、出版後に見直すのも手です。
コンテンツ:原稿と表紙のアップロード、プレビューワーでの体裁確認
次に「コンテンツ」ページで原稿と表紙をアップします。
電子書籍本文はEPUB推奨です。DOCX入稿→KDP変換も可能ですが、体裁再現は端末差が出るためプレビューで必ず検証を。
アップロード後はプレビューワーで必ず体裁確認をしましょう。
スマホ・タブレットなど複数モードがあるので、一通り確認がおすすめです。
ここでよくあるミスは「ページの余白」「画像の粗さ」「見出しリンク不具合」です。
私も初期は画像解像度不足で、後から修正しました。
章のリンクはしっかり飛ぶかチェックしておくと安心です。
表紙は前工程で作成済みのものをそのままアップします。
もし警告やエラーが出ても、落ち着いて指示に従えば問題ありません。
価格とロイヤリティ:35%/70%の基礎と日本向けの留意点(条件は最新の公式ヘルプ要確認)
ここが気になる方も多いポイントです。
KDPでは「35%」または「70%」ロイヤリティが選べます。
ただし、日本向け(Amazon.co.jp)で70%を選ぶには条件があります。
条件は変更されることがあるため、必ず最新の公式情報を確認してください。
印税まわりの前提は『Kindle出版のロイヤリティとは?70%と35%の違いと条件を徹底解説』で体系化しています。
価格は安ければ良いわけではありません。
内容と読者層に合わせ、無理のない価格帯を設定しましょう。
「他の著者は〇〇円だから…」と合わせるより、コンテンツの価値で判断したほうが長続きします。
また、KDPセレクトに登録するかもここで選べます。
独占配信やキャンペーン機能が使えますが、必ずメリット・デメリットを理解してからにしましょう。
公開・審査の目安:反映までの一般的な流れ(所要時間は変動・公式ヘルプ要確認)
すべて入力したら「出版」ボタンを押します。
ここからAmazonの審査が始まります。
目安は公式で「最大72時間程度」とされています。
実務上は数時間〜1日で反映されることもありますが、必ずとは限りません。
特に初回出版時は、審査が慎重になるケースも見ています。
ですので、急ぎの場合は余裕を持って進めておきましょう。
審査中に修正が必要な場合は、メールで通知が届きます。
落ち着いて確認し、該当箇所を修正すれば問題ありません。
公開後は商品ページが整うまで少し時間差が出ることもあります。
プレビューが変わる前に慌てないで、順次反映を待つと良いです。
次のステップでは、公開後の見直しや運用のヒントを紹介します。
ここまでできれば、出版プロセスはほぼマスターです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
事例・つまずき:初出版で多いチェック漏れと対処
初出版では、気づかないうちに小さなミスが積み重なりがちです。
出版後に読み返して「あ…ここ直したい」と思うのは誰でも通る道です。
私自身、初回は画像の粗さと段落の詰まりで差し戻し対応をしました。
落ち着いて見直せば解決できるので、慌てず進めましょう。
大切なのは、公開前に体裁・説明・ガイドラインの3点を見る習慣です。
順番にチェックポイントを押さえていきます。
よくある体裁崩れ:見出し階層・画像解像度・段落間の余白
体裁崩れは、最初に気づきづらいポイントです。
見出し階層を飛ばすと、目次や読みやすさに影響します。
「H2→H3→本文」という一貫した構造を意識しましょう。
画像は、解像度が低いと読者体験を損ねます。
特に小さなアイコンや図は、拡大に耐える画質で用意しておくと安心です。
段落間の余白も侮れません。
空行がなさすぎると、スマホで読むときに詰まって見えることが多いです。
プレビューワーでは、スマホビューを重点的に見てください。
実際のKindleアプリでも確認すると、微妙なズレに気づきやすいです。
説明文の書き方:教育的・注意喚起の文脈を保つ表現
説明文は、読者に「なぜこの本が必要なのか」を伝える場所です。
過度な煽りや断定は避け、価値と目的を明確にします。
アプローチとしては「悩み→本でできること→読むメリット」の順がわかりやすいです。
ただの宣伝文にならないよう、読者の理解を助ける姿勢を意識しましょう。
教育的な内容の場合は、過度に刺激的な表現は避け、適切な抽象度で説明してください。
これはKDPのガイドラインに沿う意味でも大切です。
私の経験では、第三者に読んでもらい「誤解が出ないか」確認すると精度が上がります。
作者目線だけだと、伝えたいことと受け取られ方がズレることがあります。
ISBNとASINの違い:電子はISBN不要/紙は別工程(必要時のみ)
電子書籍ではISBNは不要です。
KDP側でASIN(Amazon独自の識別番号)が自動付与されます。
私も最初は「ISBNって必要?」と迷いましたが、電子だけなら不要で問題ありません。
紙(ペーパーバック)を後で追加する場合のみ、ISBNに関する選択肢が出てきます。
ただし、ISBNの扱いは国や出版形態で異なるため、必要な場合は公式ヘルプを必ず確認してください。
コンテンツポリシーの基本:抽象的配慮と禁止事項の確認(公式ヘルプ要確認)
KDPには内容ガイドラインがあります。
読者を保護するため、過度に刺激的な表現や誤解を招く内容は禁止です。
教育文脈で必要な説明をする場合は、具体的すぎる表現を避け、抽象的な記述にとどめると安全です。
これにより、内容が健全な意図に沿っていることを示せます。
迷ったら公式ヘルプで最新のガイドラインを確認するのが基本です。
ガイドラインは更新されることもあるため、定期的にチェックしてください。
実務上、審査で指摘が入るケースもありますが、修正提案に沿って直せば問題ありません。
丁寧に対応する姿勢が信頼につながります。
初出版は学びの連続ですが、一歩ずつ進めれば必ず形になります。
次は出版後の調整と、継続的な改善ポイントに進みましょう。
補足:運用と見直し(最低限だけ)
出版後は「終わり」ではなく、軽くメンテナンスしていくと読まれやすくなります。
とはいえ、最初から高度なマーケティングをやる必要はありません。
最初はKDPの機能を最低限だけ理解し、必要なときにだけ手を入れる、この方針で十分です。
私も最初の1冊目は、いきなり攻めず「整える→反応を見る」だけに集中しました。
KDPセレクトの検討ポイント:独占やキャンペーンの基礎(日本向け条件は公式ヘルプ要確認)
KDPセレクトとは、電子書籍をAmazon専売にする代わりに、特典を受けられる仕組みです。
有名なのは「読み放題(Kindle Unlimited)」対象になることです。
初心者の方は「入ったほうがいいの?」と迷う部分ですが、答えは「本のジャンル次第」です。
教育系やハウツー系は、Unlimited経由での読まれ方が安定しやすい印象があります。
一方、限定性が高い専門分野やブランドを構築したい場合は、慎重に検討しても良いです。
ただし、条件やメリットは更新される場合があります。 判断前に公式ヘルプで、最新の独占条件や対象国を確認してください。
慣れないうちは、まず登録してみて、読まれ方や反応を見ながら次の判断をする方が経験値を積めます。
私も最初は「まず使ってみる→改善」で十分でした。
レビュー反映後の修正手順:本文差し替えと説明文の微調整
レビューが入ると、読者の視点が見えてきます。
初出版では「ここ説明不足だったか…」と気づくことも多いです。
修正はKDPの「コンテンツ」画面からできます。
原稿ファイルや説明文を差し替えるだけで再公開できます。
審査が再度入ることがありますが、通常はスムーズに進みます。
注意点として、頻繁な修正は負担になるので、気になる点をまとめて対応する方が楽です。
「誤字・理解しづらい箇所・最新情報の補足」あたりから手をつけると効果的です。
また、レビューには一喜一憂しすぎないのも大切です。
経験上、1〜2件の指摘で方向転換するより「数件まとまって出てから判断」が安定します。
ペーパーバックを追加する場合の最小要件と流れ(24ページ以上などは公式ヘルプ要確認)
電子書籍に慣れてきたら、ペーパーバックを追加する選択肢もあります。
紙で持ちたい読者や、信頼性アップにつながる場面もあります。
ただし、電子とは仕様が異なり、ページ数やサイズ、余白などの要件があります。
代表例として、紙は一定ページ数以上が必要です(例:24ページ以上など/最新条件は公式ヘルプ要確認)。
プリント用PDFを作成し、表紙も紙仕様に合わせて再調整します。
電子の延長で考えると戸惑うことが多いので、ステップとしては「2冊目以降」がおすすめです。
私の場合、紙版は名刺代わりにも活用しています。
イベントやセミナーでは、紙の方が印象に残りやすいことがあります。
ただし、最初の1冊目から無理に追う必要はありません。
電子で基礎を固め、必要性を感じたら取り組む、で十分です。
次は、必要な方に向けて応用編や収益化戦略も紹介していきます。
焦らず、着実に進めていきましょう。
まとめ:Kindle出版 方法の核心と次の一歩(チェックリスト付き)
ここまで、Kindle出版の基本から実装、公開後の最小限の運用まで解説してきました。
いきなり完璧を目指す必要はありません。
大事なのは、まず1冊出し、反応を見ながら改善することです。
私自身、初出版は緊張しましたが、振り返ると「やってみて流れが掴めた」のが一番の成果でした。
「準備→公開→見直し」という小さなサイクルを回せば、自然とスキルが積み上がります。
では、最後に最短ルートのチェックリストで復習しましょう。
最短ルートの再確認チェックリスト(登録→原稿→表紙→設定→公開)
Kindle出版を最短で進めるための流れをまとめました。
迷ったときは、この順番に沿って進めればOKです。
✅ KDPアカウント登録(税務・銀行口座の日本向け設定)
✅ 原稿をリフロー形式で整える(Word→EPUB推奨/目次は正しくリンク)
✅ 画像サイズと解像度を確認(小さすぎる画像は避ける)
✅ 表紙を推奨比率で制作(タイトルが小さすぎないかチェック)
✅ KDPの「本の詳細」でタイトル・著者名・説明文・カテゴリー入力
✅ 「コンテンツ」でファイルアップロード→プレビューワーで最終確認
✅ 「価格」でロイヤリティと設定を選択(35%/70%は公式条件確認)
✅ 公開ボタン→審査→販売開始
ここまで来れば、あとは読者の反応を見て微調整するだけです。
説明文の改善や、誤字修正などはいつでもできます。
出版は「手続きが多そう」に感じる方が多いですが、本質はシンプルです。 順番を守って淡々と進めれば、必ず出版できます。
そして1冊出すと、不思議と「次はどうしよう?」とワクワクしてきます。
あなたの知識や経験は、誰かの役に立ちます。
焦らず、丁寧に、楽しみながら進めていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。