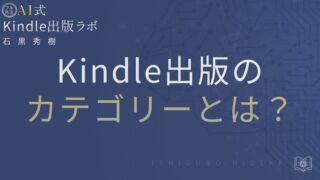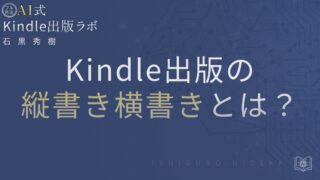のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるときに、最も多くの人が気になるのが「印税はいくらもらえるのか?」という点です。
電子書籍は紙の出版とは仕組みが異なり、手数料や印税率の計算も独特です。
本記事では、KDP(Kindle Direct Publishing)での印税の仕組みをわかりやすく整理し、初心者でもすぐに理解できるように解説します。
経験者の視点から、実際の数字のイメージと注意すべきポイントも交えて説明していきます。
▶ 印税収入を伸ばしたい・収益化の仕組みを作りたい方はこちらからチェックできます:
印税・収益化 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
印税とは?自費出版で知るべき仕組みと数字のリアル
印税は、著者が本の販売によって受け取る「成果報酬」です。
紙の出版では出版社を通して支払われますが、Kindle出版ではAmazonのシステムを通じて直接支払われます。
つまり、個人でも「出版社を介さずに印税を受け取る」ことが可能です。
この章では、その仕組みと計算方法を具体的に見ていきましょう。
印税(ロイヤリティ)とは何か:仕組みをかんたんに解説
印税(ロイヤリティ)とは、著者が本の販売価格に応じて得られる報酬のことです。
Kindle出版の場合、Amazonが販売プラットフォームとなるため、販売ごとに設定された印税率に基づいて自動計算されます。
紙の出版では印税率が約8〜10%ほどなのに対し、電子書籍では最大70%の印税率を得ることが可能です。
これは出版社や取次を介さない分、著者の取り分が大きくなるためです。
ただし、「販売価格×印税率=著者の収入」ではありません。
ここには「配信コスト」という仕組みが関係します。
これは電子データを読者の端末に配信する際にかかる手数料で、ファイルサイズによって金額が変動します。
そのため、データの重い写真集やカラー作品では、思ったより手取りが減るケースもあります。
また、印税は販売国やストアによってもルールが異なります。
本記事では日本のAmazon.co.jpを前提に説明していますが、もし海外のストア(例:Amazon.comなど)で販売する場合は、適用条件が異なることがあります(詳細は公式ヘルプ要確認)。
日本版Kindle Direct Publishing(KDP)での印税率:70%/35%の条件整理
KDPでは、販売価格に応じて印税率が「70%」または「35%」のどちらかで自動的に適用されます。
日本(Amazon.co.jp)で出版する場合、定価が250円〜1,250円の範囲に設定されていれば70%印税が適用されます。
一方、それ以外の価格帯(99円〜249円、または1,251円以上)では35%が適用されます。
70%印税は非常に魅力的ですが、適用にはいくつかの条件があります。
・70%印税は“対象国での販売”に対して適用されます。Amazon.co.jpでの販売は日本向けが対象です(対象国と条件は公式ヘルプ要確認)。
・70%印税は“価格帯・対象国への販売・配信コスト適用”が主条件です。KDPセレクト登録は必須ではなく、読み放題(KU)適用のための別制度です(公式ヘルプ要確認)。
・販売価格が規定範囲内であること
これらを満たしていれば、70%ロイヤリティが適用され、売上から配信コストを差し引いた金額の70%が著者に支払われます。
なお、紙の出版のように印刷費や在庫リスクは一切ありません。
そのため、Kindle出版は「リスクを抑えて高い印税率を得られる仕組み」として、個人出版の入り口として選ばれることが多いです。
ただし、制度や条件は時期によって変更されることもあるため、最新の内容は必ずKDP公式ページで確認しておきましょう。
実受取額=定価−配信コスト×印税率:計算の基本と注意点
KDPでは印税を計算するとき、次の式が使われます。
**「実受取額 =(リスト価格(税抜)− 配信コスト)× 印税率。日本ではリスト価格に消費税が含まれるため、計算時は税抜基準です(公式ヘルプ要確認)。」**
たとえば、販売価格が500円でデータサイズが5MB、印税率が70%の場合、配信コストは約5円(1MB=約1円)。
この場合、「例:リスト価格500円(税込)、ファイル5MB、70%印税の場合は(500÷1.1 − 5)×0.7 ≒ 314円。35%なら ≒ 158円(概算・公式ヘルプ要確認)。」** が著者の実際の受け取り額になります。
もし印税率が35%なら、(500 − 5)× 0.35 = **173円** です。
このように、同じ価格でも印税率とデータサイズによって手取り額が変わります。
画像を多く使う本やカラーの多いレイアウトでは、配信コストが上がるため注意が必要です。
また、PDFやWordなどから直接アップロードする場合、不要な余白や画像サイズの影響でファイルが重くなることがあります。
出版前にKindle Previewerなどで確認し、できるだけデータを軽くしておくのがおすすめです。
印税の仕組みはシンプルですが、「定価・ファイルサイズ・印税率」この3点のバランスを意識することが大切です。
とくに初出版の段階では、販売価格を500円前後に設定し、データを軽く保つことが収益を安定させるコツです。
印税を最大化するための価格設定と流通設計
印税を増やすためには、ただ「高く売る」だけでは不十分です。
Kindle出版では価格設定のほかに、ファイルサイズや配信方式の選び方も、最終的な印税額に大きく関わります。
ここでは、著者が実際に押さえておくべき3つの要素を解説します。
定価の目安と読者心理:250円〜1,250円帯が狙い目の理由
Kindle出版では、販売価格を250円〜1,250円の範囲に設定すると、70%の印税率が適用されます。
この価格帯は、読者にとっても「気軽に購入しやすい価格ゾーン」です。
特に500円前後は、内容への期待値と支払いやすさのバランスが取れており、多くの著者が実際に採用しています。
一方で、1,000円を超えると「この内容でこの値段なら紙の本を買いたい」と感じる読者も増えます。
電子書籍は「ワンクリックで買える手軽さ」が強みなので、価格が心理的なハードルにならないように調整しましょう。
価格設定は印税だけでなく、レビューや販売スピードにも影響します。
初出版ではあえて低価格(300〜500円)に設定して読者を集め、レビューが増えた段階で価格を上げるという戦略も効果的です。
この方法は、私自身も実践して効果を感じました。
一時的に印税単価は下がりますが、トータルで見れば販売数が増え、結果的に収益が安定します。
価格を決めるときは、ライバル作品の価格帯もチェックしましょう。
ジャンル別の平均価格を把握すると、「読者が求める価値」と「自分の作品の位置づけ」が明確になります。
過剰に安くするよりも、「適正価格で価値を感じてもらう」ことが、長期的なファンづくりにもつながります。
配信コスト(デリバリー料)と電子書籍ファイルサイズの影響
Kindle出版では、電子書籍を読者の端末に届ける際に「配信コスト(Delivery Fee)」がかかります。
これは1MBあたり約1円で、ファイルサイズが大きいほど手取り額が減ってしまいます。
テキスト中心の本であれば数円程度に収まりますが、画像や装飾が多い本では、配信コストが100円近くになることもあります。
その結果、印税計算後の実際の受け取り額が想定より少なくなるケースも見られます。
たとえば、500円の書籍でファイルサイズが5MB、印税率70%の場合、配信コスト5円を引いた495円×0.7=約346円が実際の印税です。
これが50MBだと配信コスト50円になり、手取りは315円まで下がります。
画像の多い書籍を作る際は、画質を落としすぎずに容量を軽くする工夫が必要です。
JPEGを圧縮したり、必要以上に大きな画像を使わないなどの対策をするとよいでしょう。
公式ガイドにも「高解像度を保ちつつファイルを最適化する」旨が明記されています。
また、WordやPDFで作成した原稿をそのままアップロードすると、余白や背景データが重くなりやすい傾向があります。
Kindle Createなど公式ツールを利用すると、サイズの最適化がスムーズに行えます。
これは地味ですが、印税を守る上で重要なステップです。
読み放題(KU/KDPセレクト)と購入型印税の違いを理解する
KDPセレクトに登録すると、「Kindle Unlimited(読み放題)」の対象になります。
このプログラムでは、読者が購入しなくても、読まれたページ数に応じて印税が支払われます。
購入型印税とは別に、ページ単価(KENP単価)という仕組みがあり、1ページあたり約0.5円前後(変動あり)が目安です。
読み放題で収益を得る仕組みはシンプルですが、注意点もあります。
まず、KDPセレクト登録中は他のプラットフォーム(note、楽天Koboなど)で同じ作品を販売できません。
独占配信契約のため、他ストア販売を考えている人は慎重に検討する必要があります。
また、ページ単価は月ごとに変動し、時期によっては想定より少なくなることもあります。
私の経験では、セール期間中や読者が多い月(年末など)は単価が下がりやすい傾向がありました。
ただし、読まれた分だけ確実に報酬が発生するため、継続的な収益を狙いたい人には向いています。
一方で、内容が濃い専門書やニッチなテーマでは、購入型のほうが安定するケースもあります。
読者が「読み放題ではなく、買って手元に置きたい」と感じるような価値を提供できれば、購入型でも十分に印税を得られます。
どちらが良いかは一概に言えませんが、「読み放題で知ってもらい、購入で信頼を得る」という流れが理想的です。
印税を最大化するには、「価格設定」「ファイルサイズ」「販売方式」の3要素をセットで考えることが重要です。
特に初期段階では、軽めのファイル+中価格帯+読み放題登録が最もバランスの良い戦略といえるでしょう。
稼げる印税を生む実例と避けたい失敗パターン
印税を増やすための理論を理解しても、実際の現場では「思ったより稼げなかった」という声が少なくありません。
その理由は、戦略の差です。
ここでは、Kindle出版で印税を伸ばした成功例と、よくある失敗パターンを具体的に紹介します。
経験者として感じた“リアルな落とし穴”も交えて解説します。
成功ケース:低予算・適価格・レビューで印税を伸ばした例
ある著者は、初めての電子書籍を「300円」に設定し、表紙も自作という低コストで出版しました。
宣伝費はゼロでしたが、SNSで日々の制作過程を発信していたことがきっかけで、多くの読者に届いたのです。
販売開始から1週間でレビューが数件つき、Amazon内の関連カテゴリーで上位表示されました。
その結果、1冊あたりの印税は少なくても、販売数の増加によって月1万円以上の印税収入を得ることができたそうです。
私自身の経験でも、「価格よりも信頼」が印税を左右することを実感しました。
レビュー数が増えるほど、購入率が上がりやすくなります。
読者は「他の人がどう感じたか」を重視するため、レビュー獲得の初期フェーズを戦略的に設計することが大切です。
また、Kindle Unlimited(読み放題)を併用したことも印税拡大につながった要因のひとつでした。
たとえ単価が低くても、読まれたページ数分の報酬が積み重なるため、安定収益に結びつきます。
「低価格で広く読まれる」ことで、著者としての信頼を築きやすい点も大きな利点です。
失敗ケース:価格設定がズレた・ファイルが重くて実受取が減った例
一方で、失敗例の多くは「価格設定」と「ファイルサイズ」に関係しています。
たとえば、初出版で内容が少ないにもかかわらず、1,000円以上の高価格に設定したケース。
結果的に購入が伸びず、レビューも集まらずに埋もれてしまったというパターンがあります。
電子書籍は紙の本と違い、「試し読み」や「即購入」が前提の世界です。
そのため、読者が内容を確認できない状態で高価格をつけると、心理的なハードルが上がります。
適正価格を見誤ると、印税率が高くても販売数が減るという悪循環に陥ることがあります。
もう一つの落とし穴は、ファイルサイズの肥大化です。
特に、画像を多く使ったエッセイやフォトブック形式では、1冊あたりの配信コストが想定より大きくなり、実際の印税が減ってしまうことがあります。
「高画質で見せたい」という気持ちは大切ですが、印税計算では1MB=約1円のコストが発生するため注意が必要です。
ファイルを軽くする方法としては、画像圧縮や余白削除、Kindle Createの利用が有効です。
特にWordやPDFで作った原稿を直接アップロードすると、不要なレイヤーや背景データが重くなる傾向があります。
出版前にプレビューでサイズを確認し、軽量化するだけでも、印税の減少を防ぐことができます。
印税問題のトラブル回避:契約・代行出版・ペーパーバックとの比較
最近では「Kindle出版を代行します」という業者も増えていますが、契約内容には十分注意が必要です。
中には、印税の一部を代行会社が受け取る仕組みになっているケースもあり、トラブルの原因となります。
KDPは無料で誰でも使えるプラットフォームなので、自分で手続きできる範囲はなるべく自分で行うのが安心です。
特に、出版後の権利関係(著作権や販売権)を明記しない契約は危険です。
Amazonのアカウントと出版データの管理者が一致していないと、後から修正や削除が難しくなる場合があります。
「楽だから」と代行に任せすぎるのではなく、印税の受け取り権限を自分で保持することを第一に考えましょう。
また、ペーパーバック出版(紙版)も検討する人が増えていますが、印税率は電子書籍より低くなります。
「ペーパーバックの印税は“リスト価格の60%−印刷費”です。電子70%と単純比較せず、印刷費が差し引かれる点が収益差の主因です。」
そのため、まずは電子書籍で安定的な販売を作り、その後に紙版を追加するのが現実的な流れです。
出版形態を問わず、印税トラブルを防ぐためには「契約内容」「口座登録」「権利の所在」を自分で管理することが重要です。
細かい部分ですが、これが信頼性と収益の両方を守る土台になります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
まとめ:印税を味方にする出版戦略の基盤
Kindle出版で印税を得ることは、決して一部の人だけの特権ではありません。
正しい仕組みを理解し、戦略的に運用すれば、誰でも安定した収益を得ることができます。
印税を増やす鍵は、「価格設定」「ファイルサイズ」「販売方式」「レビュー戦略」の4点です。
このうち1つでも欠けると、期待した結果が出にくくなります。
逆に、この4つをバランスよく整えることで、長期的に売れ続ける本を作ることが可能です。
私自身も最初は試行錯誤の連続でしたが、読者の反応を分析しながら改善を重ねるうちに、少しずつ印税が安定していきました。
KDPはシンプルな仕組みですが、その分、戦略と継続力が問われます。
印税は「数字」ではなく「信頼の積み重ね」です。
読者に誠実な本を届け続けることが、最も確実に印税を増やす方法です。
地道な努力が、やがてあなたの作品を「資産」に変えていくでしょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。