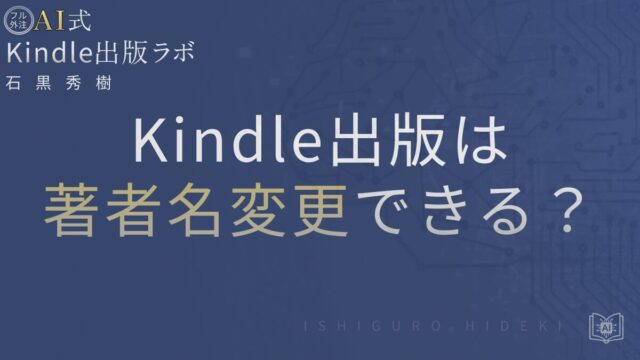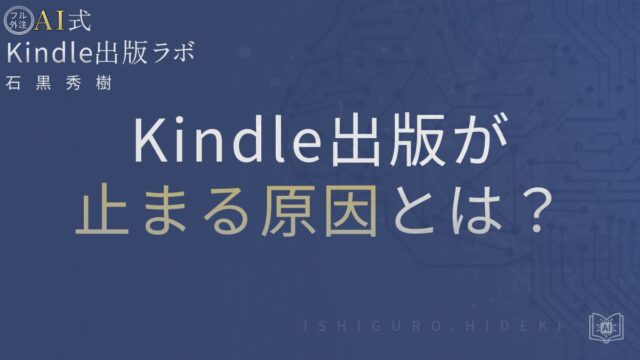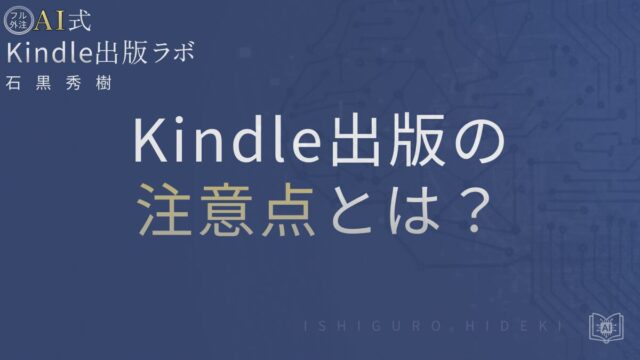自費出版でISBNコードは必要?紙・電子の違いと取得方法を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
まず最初に、ISBNについて一番多い質問は「自費出版でも必ず必要なの?」という点です。
答えは「販売先によって変わる」です。
本記事では、書店・Amazon・イベント頒布など、あなたの販路にあわせて判断できるよう、実務ベースで丁寧に解説します。
私自身、初めて紙の流通に挑戦したとき、申請タイミングを勘違いしてスケジュールがずれた経験があります。
そうした失敗談も交えながら、安心して進められるようにお伝えします。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
自費出版でISBNコードは必要?結論と判断軸
目次
自費出版でもISBNは取得できますし、条件によっては取得したほうが有利です。
ただ、取得には費用と時間がかかるため、目的と販路に合うかを先に整理することが大切です。
ISBNコードとは|自費出版でも使われる書籍の識別番号
ISBNコードとは、世界で書籍を識別するための固有番号です。
図書館検索や書店の流通管理で使われ、いわば「本のマイナンバー」のような役割があります。
出版社だけでなく、個人の自費出版でも取得できます。
実務ではISBNに加え、書籍JANコード(バーコード)も組み合わせて管理されることが多いです。
初心者の方は「ISBN=バーコード」と思いがちですが、実際は番号と画像生成が別工程です。 この区別を理解しておくと、印刷前の準備でつまずきにくくなります。
ISBNが「必要なケース」と「不要なケース」(紙/電子/POD)
書店流通や図書館配本を目指す場合、ISBNはほぼ必須です。
取次を通す流通網では、識別番号がないと取り扱いが難しいためです。
一方、AmazonのKindle電子書籍(KDP)では、ISBNなしでもASINで販売できます。
私も電子版のみのときはISBNを取得せず、紙版制作の段階で取得しました。
自宅でのイベント頒布や、友人・コミュニティ限定販売の場合、ISBNは任意です。 「知らないと必ず損する」ものではなく、流通戦略にあわせて選べる仕組みと捉えましょう。
なお、POD(プリントオンデマンド)の場合、サービスによってISBNの扱いが異なります。
「KDP紙本はISBN必須。一方で他社PODは要件が異なるため、各サービスの流通条件とISBN要否を事前確認してください。
最初に確認すべき判断軸|販路(どこで売るか)で決まる
ISBNが必要かどうかは、「どこで本を販売したいか」で決まります。
これが一番シンプルで、後悔がありません。
* 書店・図書館 → 必要
* Kindle限定 → 不要
* イベント頒布のみ → 不要
* 将来紙で流通させたい → 早めの取得検討
公式の案内ではISBNは任意ですが、実務では販路要件で判断される場面が多いです。
申請には日数がかかるため、出版スケジュールの後ろ倒しに注意してください。
私の周りでも、奥付制作の段階で慌てる方をよく見ます。
迷ったら「最終的な売り方」を先に決めるのが一番です。
ISBNの扱いの違いは『Kindle出版でISBNは必要?電子書籍とペーパーバックの違いを徹底解説』でも整理しています。
自費出版でISBNコードを取得するメリットとデメリット
ISBNを取得する最大の価値は、販売の選択肢が広がることです。
一方で、費用や手続きが必要なため、目的に応じた判断が大切です。
書店流通・図書館流通が可能になるメリット
ISBNは流通前提を満たす要素の一つで、取次経由での書店取り扱い『可』となる土台を作りますが、配本可否は別途条件や営業活動に左右されます。
図書館への納品や選書対象にもなりやすく、社会的な信頼につながる点は大きなメリットです。
多くの著者さんは「Amazonだけで十分」と思われますが、地域の書店に置いてもらえたときの反響はやはり特別です。
私も地元書店に並んだ際、友人や知人からの反応が増え、自分の活動を広げるきっかけになりました。
また、ISBNは図書館や書店のデータベース検索に登録されるため、長期的な読者獲得にもつながります。 “読まれ続ける本”を目指すなら、ISBN取得は有効な選択肢です。
費用がかかる・手続きが必要などのデメリット
デメリットとしては、費用や事務的な手続きが発生する点が挙げられます。
ISBNは管理センターで番号をセット単位で取得するため、初期費用はゼロではありません。
また、申請内容の確認や納品スケジュールとの調整が必要で、出版直前に焦る方もいます。
私自身、奥付制作の直前に申請してしまい、印刷スケジュールがタイトになった経験があります。
公式では「余裕を持って申請」と案内されていますが、実務では制作進行と並行しながら進めるため、意外とスケジュール管理が難しいです。 特に初出版の方は、申請〜番号付与までの時間を逆算して進めるのが安心です。
ISBNと書籍JANコード(バーコード)の関係
ISBNとバーコードは同じものと誤解されがちですが、実際には別のものです。
ISBNは書籍の識別番号で、書籍JANコード(13桁)は流通で読み取るためのバーコードです。
自費出版の場合、ISBN取得後にバーコード画像を作成し、書籍の裏表紙に配置する工程が発生します。
ここで画像サイズや配置を誤ると、書店でスキャンできず返品対象になることもあるので注意しましょう。
なお、電子書籍ではバーコードは不要ですが、紙版ではほぼ必須です。
公式の仕様と、印刷会社の入稿ガイドを併せて確認するとスムーズです。
以上のように、ISBN取得には費用と手間がかかるものの、販路の広さや信頼性という大きなメリットがあります。
出版の目的に応じて、無理のない形で検討してみてください。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
自費出版でISBNを取得する方法|手順と必要費用(最新ルールは公式確認)
ISBNの取得ルートは大きく2つあります。
自分で申請する方法と、出版サービスや出版社に代行してもらう方法です。
どちらが良いかは、コストと手間、そして発行予定冊数によって変わります。
自分で取得する|日本図書コード管理センターへの申請手順
自分で取得する場合、日本図書コード管理センター(日本出版インフラセンター)が窓口です。
公式サイトから申請し、現在はISBN-13(13桁)が付与されます。10桁表記は旧形式で、必要に応じ変換して用います(公式ヘルプ要確認)。
流れは次の通りです。
・オンライン申請(出版社情報の登録)
・必要書類の提出
・番号付与
・書誌情報の登録
番号は通常、1冊ずつではなく「番号の塊(ブロック)」単位で取得します。
初めての方は「1冊しか出さないのに?」と驚くことが多いですが、世界的にこの運用が一般的です。
費用と必要日数は、年度や申請状況によって変動します。 最新の料金表や処理期間は必ず公式サイトで確認してください。
実務的には、奥付や帯のデザインを決める前に番号が必要になるため、申請タイミングを遅らせないことが大切です。
私も初回は「原稿が完成してからでいいだろう」と考えてしまい、デザイン調整がギリギリになった経験があります。
出版社経由で取得する|外部サービス・代行の流れ
もう一つの方法は、出版社や自費出版サービスにISBNを付与してもらうパターンです。
この場合、番号はあなたではなく、その会社が「出版者」として管理します。
流れとしては、契約時にISBN取得オプションを選び、書誌情報を提供するだけのケースが多いです。
出版サービス側が書誌登録まで対応してくれるため、手続きが簡単なのが利点です。
ただし、番号の発行主体はサービス側になるため、将来の改訂版やシリーズ展開を考えるなら、管理方法を事前に確認しましょう。 自分の名義でISBNを継続運用したい場合は、最初から自分で取得するほうが柔軟です。
また、代行手数料が設定されている場合もあります。
費用がサービス料金に含まれるか、追加料金か、必ず見積時に確認しておきましょう。
ISBNのセット購入・申請期間・刊行スケジュールの注意点
ISBNは1冊単位ではなく、複数番号のセットで取得します。
「最初は1冊だけ」と思っても、増刷や電子版・紙版の別付番を考えると、無駄になることは意外と少ないです。
申請から付与までは、通常数日〜数週間ほど必要です。
これは年度や混雑状況に左右されるため、印刷予定日から逆算して余裕を持つことが重要です。
制作現場では、ISBN待ちでカバー制作が止まることがよくあります。
私もデザイナーさんに「番号まだですか?」と催促されたことがあり、スケジュール管理の大切さを痛感しました。
また、紙版と電子版で別のISBNが必要になることがあります。
この点は制作形式や販売方法で変わるため、最新ガイドラインを確認し、迷ったら管理センターや出版サービスに確認するのが確実です。
以上のように、自力取得は手間と準備が必要ですが、そのぶん自由度があります。
代行は負担が少ない反面、管理主体の違いを理解して選ぶと安心です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
紙と電子のISBNの違い|KDP(Kindle)ではどうする?
紙と電子ではISBNの扱いが大きく異なります。
知らないまま制作を進めると、出版直前で慌てるケースも多いので、早めに整理しておきましょう。
Kindle電子書籍はISBN不要だが、紙版刊行なら要検討
Kindle電子書籍(KDP)では、ISBNがなくても出版できます。
Amazon側が「ASIN」という独自の管理番号を付与してくれるため、手続き不要で販売が可能です。
この仕組みは、個人出版のハードルを大きく下げています。
私も初めての電子出版はISBNなしでスタートし、問題なく販売できました。
ただし、将来的に紙の書籍を制作する予定があるなら、早めにISBN取得を検討しておきましょう。 紙版で書店流通を目指すなら、ISBNが実質必須になるためです。
「とりあえず電子だけ」という方でも、のちに紙版を出すと決めたときに慌てないよう、スケジュールだけは把握しておくと安全です。
手続き全般の注意点は『Kindle出版のTIN入力とマイナンバー対応を徹底解説|日本在住者の正しい手順と注意点』でも触れています。
POD(プリントオンデマンド)のISBN取り扱い
POD出版とは、注文が入った分だけ印刷する仕組みです。
Amazonのペーパーバックや、一部のPODサービスがこれに該当します。
KDPのペーパーバック(POD)はISBNが必須です。自前のISBNを使うか、KDPの無料ISBNを選びます(公式ヘルプ要確認)。
ただし、KDPの無料ISBNでは出版社名(インプリント)は『Independently published』等となり、あなたの独自名義にはなりません(表記仕様は公式ヘルプ要確認)。
一方、書店流通型のPODサービスでは、ISBNが求められる場合があります。 同じPODでも「Amazon中心」か「書店流通を含むか」でISBNの扱いが変わる点は、初心者がつまずきやすいポイントです。
個人的には、将来的に販路を広げたい場合、最初から自分名義のISBNを持っておくほうが柔軟でした。
紙書籍と電子書籍でISBNが別になるケースに注意
紙版と電子版でISBNが別になるケースがあります。
これは「媒体が異なる場合は別番号を付与」という国際ルールに基づくものです。
ただし、ファイル形式の違い(EPUBやPDF)で別番号が必要かどうかは、最新ガイドラインを確認することが重要です。
公式では一定の基準が示されていますが、実務上は販売形式やプラットフォームで判断が分かれることもあります。
たとえば、私は紙版+Kindle版を同時に出した際、ISBNを2つ用意しましたが、電子専用のときはASINのみで運用しました。
事前に整理しておくと、番号の無駄も避けられます。
紙と電子を併用する場合、制作スケジュールや版管理が複雑になりやすいです。
迷ったときは、管理センターや出版サービスに確認し、最適な付番方法を選びましょう。
ISBNを取得しない自費出版の選択肢|目的別のベストプラクティス
ISBNを取らない選択肢にも、十分メリットがあります。
「広く書店流通させたい」のでなければ、制作コストや時間の節約につながります。
とくに、コミュニティ単位の販売や、まずは実験的に作品を出したいときは、ISBNなしでも問題ありません。 大切なのは、目的に合わせて最適な手段を選ぶことです。
自費出版は自由度が高いからこそ、仕組みを理解したうえで柔軟に判断すると、ストレスなく進められます。
個人販売・コミュニティ限定頒布ならISBNなしでも成立
自分のサイトや、知り合い・コミュニティでの配布程度であれば、ISBNは不要です。
同人誌文化に慣れている方には馴染みのある形ですよね。
例えば、
・講座やセミナー参加者向けのテキスト
・コミュニティ限定のハンドブック
・応援してくれる読者に向けた限定冊子
こうした場面では、ISBNなしでも十分機能します。
私も、クローズドな勉強会用に制作した冊子はISBNなしで配布しました。
必要な人に確実に届けば十分だったので、そのぶん制作に集中できました。
もちろん、SNSで少し広がると「一般販売はしないの?」と聞かれる場面もあります。
そこで、反応を見てからISBN取得+改訂版として正式リリース、という流れもおすすめです。
最初から完璧を狙わず、小さく出して改善していくのは、個人出版ならではの強みです。
SNS/note/自社EC/イベント販売の現実的な戦略
ISBNなしで成果を出したいなら、販路と導線づくりが重要です。
自分のホーム(自社サイトやSNS)に読者がいるほど、ISBNの必要性は下がります。
たとえば、こんな戦略があります。
・noteやメールリストで先行販売
・BoothやBASEなどECで販売
・イベントで直接頒布
・SNSで制作過程を共有し興味を育てる
この方法の良いところは、印刷部数を自由にコントロールできることです。
在庫リスクを抑えつつ、反応を見て増刷や改訂がしやすいです。
ただし、集客は「自分でつくる必要がある」という点は理解しておきましょう。
公式ストアに頼れない分、発信力やコミュニティ設計が武器になります。
実務的には、以下を整えておくと販売が安定します。
・読み手の悩みを明確にする
・販売ページにサンプルや目次を掲載
・購入後のフォローやフィードバック導線を用意
ISBNがなくても、丁寧に設計すればしっかり読まれます。
むしろ、読者との距離を近く感じられるのが、直接販売の醍醐味でもあります。
ISBN取得のよくある質問と誤解
ISBNまわりは、初めての方ほど迷いやすいポイントが多いです。
実際、出版サポートをしていると「それは誤解かも…」という質問をよく受けます。
「電子書籍でも必須?」など初心者がつまずくポイント
まず一番多い質問が「電子書籍(Kindle)でもISBNが必要ですか?」です。
結論として、KindleではISBNは不要で、AmazonのASINで管理されます。
ただ、これはAmazon特有の仕組みです。
他の電子書籍ストアへ横展開する場合は、ISBNが必要になるケースもあります。 “Amazonだけで完結するのか、他ストアも使うのか”で判断しましょう。
もうひとつ多い誤解が「ISBNがあると勝手に図書館や書店に並ぶ」というものです。
ISBNはあくまで識別番号であり、配本や営業活動とは別です。
ここは実務と制度のギャップを理解しておくと安心です。
私も最初のころ「ISBNがあれば自動的に広まるのかな」と淡い期待を持っていました。
結局は販促や紹介の工夫が重要で、番号は流通の“入口”にすぎませんでした。
ISBN取得後の奥付表記・バーコード制作の注意点
ISBNを取得した後に気をつけたいのが、奥付(おくづけ)への表記です。
奥付とは、書籍の最後に入れる「発行者・発行日・ISBN」などの情報欄です。
裏表紙まわりの注意点は『Kindle出版の裏表紙は必要?電子と紙の違い・作成ルールを徹底解説』が参考になります。
ISBNは正式な書式で記載する必要があり、誤植があると流通で問題が生じることがあります。
また、バーコード画像(書籍JANコード)は別途作成し、裏表紙に配置します。
ここでよくあるのが、バーコードのサイズや位置が不適切で書店のスキャナーが読み取れないケースです。 印刷会社のテンプレートや推奨サイズを必ず確認し、事前にデザイナーさんと共有しておくと安心です。
私も以前、バーコードの濃度が薄すぎて修正した経験があります。
見た目よりも機能性を優先する点は、実務ならではです。
奥付への正しい記載方法は『Kindle出版の奥付とは?必要項目・作り方・正しい位置を徹底解説』で確認できます。
まとめ|自費出版でISBNを取るかは「販路」で決める
ISBNは「取るべき/取らないべき」という単純な話ではありません。
どこで販売したいか、どんな読者に届けたいかで最適解が変わります。
書店流通や図書館配本を目指すなら取得が有効です。
一方、コミュニティ販売や電子限定ならISBNなしで十分なこともあります。
迷ったときは、次の順番で整理してみてください。
・最終的な販売ルート
・読み手との距離の近さ
・制作スケジュールとコスト
・将来の展開(紙/電子の両方か)
自費出版は自由度が高い分、ルールを理解して選択することが大切です。
じっくり計画しながら、自分らしい出版方法を見つけていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。