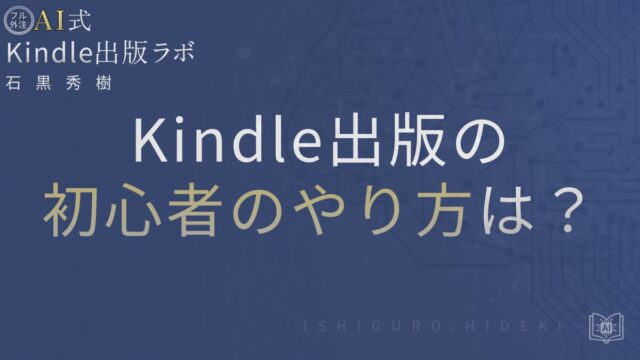自費出版で絵本を出す方法とは?紙と電子の選び方を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
自分の絵本を形にして親子や子どもたちに届けたい、でも「自費出版と商業出版って何が違うの?」という段階で止まってしまう方は多いです。
私自身、最初の企画が出版社の審査に通らず、自費出版に切り替えて成功した経験があります。
最初に基本を押さえておくと、遠回りせずに進められます。
この記事では、絵本を自費出版する前に知っておくべき基本と選び方を、初心者でも理解しやすくまとめます。
「どの方法が自分に合うのか」を判断できる状態を目指しましょう。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
自費出版で絵本を出す前に知るべき基本|商業出版との違いと選び方
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
自費出版 絵本の選択肢(紙・電子・オンデマンド)は多く、最初は違いが分かりにくいものです。
最初に全体像を理解し、目的や読者に合わせて選べるようにしておきましょう。
自費出版と商業出版の違い|費用負担・審査・流通のポイント
絵本の出版には、大きく「商業出版」と「自費出版」があります。
商業出版は、出版社が費用を負担し、審査を通過した作品を販売します。
一般流通(書店・取次)やプロによる編集が前提なので、広く届けたい場合に向いています。
ただし、審査ハードルは高めです。
私も最初は3社に持ち込みましたが、テーマと市場性の観点で通りませんでした。
「上手いかどうか」より「売れるかどうか」が判断軸になる場面が多いです。
対して自費出版は、作者が費用を負担して制作・発行します。
審査がない、または緩やかで、好きなテーマで作れます。
ただし流通や販売は自分で戦略を組む必要がある点が実務上の違いです。
公式には「流通可能」と説明されていても、実際は委託条件や在庫の扱いで調整が必要なこともあります。
「自分の想いのままに形にする」なら自費出版、
「全国流通と売上を目指す」なら商業出版、という整理が基本です。
商業出版との違いをさらに具体的な事例で確認したい場合は、『自費出版と商業出版の違いとは?費用・流通・契約を初心者向けに徹底解説』も参考にしてみてください。
自費出版で絵本を作る主な方法|紙の書籍・電子書籍・オンデマンド
自費出版の方法は3つに分けられます。
紙の書籍(オフセット印刷):
質が高く、絵本に合う発色や質感を出せます。
大量印刷で単価が下がりますが、在庫を抱えるリスクがあります。
電子書籍:
初期費用を抑えやすく、在庫が不要です。
電子は端末や年齢で体験が変わります。紙と電子は特性が異なるため、用途に合わせて選択し、詳細は各プラットフォームの公式ヘルプ要確認。
オンデマンド印刷:
注文が入った分だけ印刷する方式です。
部数が少ないと割高ですが、個人配布やテスト販売に向いています。
経験上、最初の1冊はオンデマンドや電子で小さく始め、反応を見て紙へ展開する流れが負担が少ないです。
絵本の自費出版が向いている人|目的別チェックリスト
以下のような目的がある方に、自費出版は特に向きます。
* 自分の子どもや園児に届けたい
* イベントや地域活動で配りたい
* 伝えたいテーマ(多文化・環境・教育など)が明確
* 商業出版の審査に左右されず発行したい
* 少数の読者から始め、段階的に広げたい
逆に、「全国の書店で販売されたい」「出版社のブランドで出したい」という場合は、商業出版の検討が合います。
とはいえ、最近は自費出版で人気になり、後から出版社の声がかかるケースも出ています。
最初の規模にこだわりすぎず、自分の軸に沿ってスタートすることが大切です。
絵本を自費出版する目的を決める|ターゲットとゴール設計
自費出版では「作品を作ること」よりも「誰に届けたいか」を先に決めることが、結果的に最短ルートになります。
ここを曖昧にしたまま進めると、印刷部数や販路が合わず、在庫や予算で悩むケースが多いです。
私も初期は紙の上製本を多めに刷ってしまい、保管場所に困った経験があります。
まずは届けたい相手と目的を明確にして、出版方法を逆算しましょう。
まず「誰に届けるか」を決める|親子・園や学校・地域イベント
絵本は「読む相手」が具体的になるほど、内容や制作方法が決まります。
親子向けなら読み聞かせやイラストの大きさが重要になりますし、園や学校向けなら教育テーマや安全な言葉選びが必要です。
地域イベントや図書館向けなら、地域性や文化性を入れると喜ばれます。
強く言いたいのは、読者像が決まれば、必要な仕様とコストも自然と決まるということです。
逆に「誰にでも向けたつもり」が一番迷いやすいです。
私が支援した方でも、最初は幅広い層を狙って失速し、対象を「園児の保護者」に絞った途端、反応が良くなった例が何度もあります。
まずは小さな範囲とコミュニティで響く形を狙いましょう。
紙か電子かを選ぶ判断軸|読み体験・予算・在庫・配布方法
絵本制作で次に迷うのが、「紙で出すか」「電子で出すか」です。
紙の絵本は、質感と読み聞かせ体験が魅力です。
特に幼児向けは紙での需要が根強い印象です。
ただし、印刷部数や保管場所、発送作業を考える必要があります。
電子書籍は、低コストで在庫不要です。
親御さんがスマホやタブレットで読むケースも増えています。
オンデマンド印刷なら、注文分だけ印刷できるので、イベント配布や少部数に向いています。
判断軸は以下です。
* 読み聞かせ体験の重視度
* 予算とリスク許容度
* 保管スペース
* 配布手段(手渡し/ネット)
初めての方は、小ロットオンデマンド+電子出版の併用が安心です。
実際、多くの制作者がこの方法でスタートしています。
紙と電子それぞれのトータルコストを俯瞰したい場合は、『自費出版の費用はいくらかかる?紙と電子の違いを徹底解説』も合わせて確認しておくと判断がしやすくなります。
書店で販売したい場合の注意点|流通網とISBNの確認
「せっかくなら書店に並べたい」という気持ちは自然です。
ただ、ここは注意が必要です。
書店流通ではISBNが求められることが多いですが必須かは販路次第です。取得主体や方法はサービスごとに異なるため、公式ヘルプ要確認。
自費出版サービスでは「書店販売可能」と書かれていても、
実際には委託条件や在庫調整が必要になるケースがあります。
また、返品リスクや手数料の割合は会社によって異なります。
公式サイトでは触れられない実務条件は、担当者に確認するのが安心です。
正直に言うと、最初の段階で全国流通を狙うより、
地元書店やオンライン販売から丁寧に広げた方が結果が出やすいです。
私がサポートした例でも、地域の書店と連携し、イベントを通じて読者を育てた作品が長く読まれています。
書店販売は「最終ステップ」と考えると、ムダなく進められます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
自費出版で絵本を作る手順|初心者でも進めやすい流れ
自費出版は「手順が複雑そう」と感じられがちですが、流れを押さえれば迷う場面は少なくなります。
私が制作サポートした方も、最初は不安が大きかったものの、順番に進めることでスムーズに完成にたどり着きました。
ここでは、初めてでも実践しやすい流れを紹介します。
企画とターゲット設定|テーマ・対象年齢・メッセージを明確に
まずは企画の方向性を決めます。
テーマ(何を伝えるか)
対象年齢(0〜2歳/3〜5歳など)
読者と読み手(子ども・親・保育者)
この3つが揃うと、ページ数や語彙の難易度、絵のタッチまで自然と決まります。
たとえば、0〜2歳向けなら擬音語やリズムが中心、ページ数も少なめが一般的です。
一方、4〜6歳向けはストーリー性や教訓が求められることもあります。
企画段階で「子どもが楽しむだけでなく、読み手の大人も読みやすいか」を意識すると、評価されやすいです。
自分の子や、身近な親子から感想を聞くのも効果的です。
小さな声が、改善のヒントになります。
シナリオとラフ制作|ページ数・構成・色彩の基本
次に、ストーリーとラフ(絵の下書き)を作ります。
絵本は一般的に24〜32ページ程度が多く、見開き単位で展開します。
最初はA4コピー紙でも良いので、簡単なダミー本を作りながら進めましょう。
実際に手に取ってページをめくると、テンポや間の取り方が見えてきます。
色彩は「子どもが理解しやすい明快さ」を意識します。
ただし、トレンドだけに寄せすぎず、自分らしい世界観も大切です。
ここで焦ると後工程で修正が重なるため、丁寧に整えると結果的に早いです。
編集・装丁・入稿準備|印刷仕様・電子形式の基礎
企画とラフが固まったら、編集やレイアウトに進みます。
印刷する場合は、紙の種類、サイズ、綴じ方、表紙の加工などを選択します。
絵本では上製本(ハードカバー)が人気ですが、そのぶんコストは上がります。
電子出版では、画像形式・解像度・縦横比に注意します。
画像解像度・縦横比・ファイルサイズ・推奨フォーマットはプラットフォームで異なります。最新仕様は公式ヘルプ要確認。
私は最初に公式ガイドを確認し、そのうえで実際の売れ筋作品を参考にしました。
公式通りでも、実際の見え方が微妙な場合があるので要チェックです。
入稿前にプロ校正や第三者チェックを依頼する方も多いです。
誤字や色味調整は、自分では気づきにくいものです。
出版サービスの選び方|自費出版会社・印刷サービス・電子配信
出版の方法は複数あります。
* 自費出版会社に依頼(編集〜流通までサポート)
* 印刷会社に発注(制作は自分、印刷のみ)
* 電子配信(Amazonなどのプラットフォーム)
費用や自由度はサービスによって大きく変わります。
公式サイトの説明だけでは分かりにくい部分もあるため、見積りとサンプルを取り寄せて比較するのがおすすめです。
また、担当者との相性も重要です。
制作は長く関わるので、質問に丁寧に答えてくれる企業を選びましょう。
販売・配布方法の決定|書店委託・EC・イベント・直接配布
制作が進んだら、販売方法を決めます。
* 自分のオンラインストア
* フリマアプリ・EC
* 地元書店での委託
* イベント・マルシェ
* 保育園・幼稚園・施設への配布
最初は、知り合いや地域のコミュニティから広げる方が成功しやすいです。
全国流通は魅力ですが、返品や在庫管理の負担が大きい場合もあります。
公的施設への寄贈や読み聞かせ会の開催は、作品の認知を広げる良い方法です。
強く言いたいのは、制作と販売はセットで考えるほど失敗が少ないということです。
「作ってから考える」より、「届け先を先に決める」ほうが実務的です。
より具体的な販路設計や集客の流れは、『自費出版で本を売る方法とは?初心者が知るべき販路と集客の基本を徹底解説』でステップごとに解説しています。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
費用と期間の目安|コストを抑える工夫と注意点
絵本の自費出版は「高そう…」という印象を持たれがちですが、設計次第でムダなく進められます。
費用は制作仕様や発行部数によって大きく変わります。
私が支援してきた中でも、企画段階で仕様を整理した方は、予算内で納得のいく作品に仕上がっていました。
ここでは、費用の見方と賢い選択ポイントを押さえましょう。
具体的な金額感やパターン別の費用構成を知りたい方は、『絵本の自費出版にかかる費用とは?相場・内訳・節約ポイントを徹底解説』でシミュレーションもチェックしてみてください。
費用が変動するポイント|カラー印刷・ページ数・部数・装丁
絵本の費用を左右する主な要素は次のとおりです。
* カラー印刷かどうか
* ページ数(一般的には24〜32ページ)
* 印刷部数
* 上製本(ハードカバー)や特殊加工
カラー絵本は印刷コストが上がりやすく、上製本は耐久性と高級感がある反面、単価が高くなります。
公式サイトで「◯冊で◯円」と提示されていても、実際には紙質やサイズ変更で増減することがあります。
ここでよくある失敗は、一番豪華な仕様で考えはじめてしまうことです。
まずは目的に合った必要十分な仕様に絞り、無理のない範囲で進めましょう。
少部数・オンデマンド印刷の活用|在庫リスクを抑える方法
「部数を多く刷るほど1冊あたりが安い」は事実ですが、在庫リスクを抱えるかどうかが分岐点です。
最初から数百冊を刷ってしまい、保管場所や販路に困る方もいます。
私自身、初回で自宅を箱だらけにした経験があります…。
オンデマンド印刷なら、必要な分だけ作れるため、少部数の試作やイベント向けに適しています。
少部数で反応を見てから増刷する流れは、心理的にも金銭的にも負担が少ないです。
電子出版の特徴とコスト構造|初期費用を抑えて発行
電子絵本は、初期費用を抑えやすいのが大きな魅力です。
データ形式や画像品質に注意しつつ、プラットフォームに沿った形式で制作します。
基本的に在庫リスクがなく、アップデートもしやすいです。
ただし、紙より読み聞かせ向きの操作性が制限される場面もあります。
実際、スマホ画面だとページの細かい表情が伝わりにくいという声もあります。
それでも、テスト出版や海外読者向け展開を考えるなら、電子は非常に有効です。
見積もり比較のチェック項目|仕様統一・納期・サポート範囲
サイズ・ページ・紙種・部数に加え、色校正種別(本機/簡易)やカラーモード(CMYK/RGB)、解像度を揃えて比較しましょう。
サイズ、ページ数、紙種、部数が揃っていないと、価格差の理由が見えません。
また、納期とサポート範囲も重要です。
* データ修正はどこまで対応か
* 入稿支援はあるか
* 色校正は可能か
公式には「対応可能」とあっても、実際は追加費用がかかることがあります。
担当者のレスポンスや説明の丁寧さも判断材料です。
慣れていないうちは、3社程度で見積もり+サンプル確認をおすすめします。
見本を手にすると、品質差がよく分かります。
以上が、費用と期間の基本的な考え方です。
次の章では、実例や配布スタイルについてさらに深掘りできます。
実例で学ぶ|目的別に見る自費出版絵本の成功パターン
目的が明確な絵本は、読み手に届きやすく、発行後の広がりも自然に生まれます。
ここでは、実際に多い3パターンを紹介します。
どれも「特別な才能」より、読み手の姿をしっかり思い浮かべた企画が軸になっています。
完璧さより、丁寧な届け方が成功の鍵です。
子ども向け読み聞かせ用|家庭・園・学校での配布事例
最も多いのが、家庭や園、学校で読まれることを想定した絵本です。
自分の子どもや、クラスの子たちに読んでほしいという気持ちから始まるケースが多いです。
家庭用では、親が読み聞かせしやすいリズムや文字サイズが好まれます。
園や学校向けでは、安全な言葉選びと教育的なメッセージが求められます。
私が支援した方の中でも、園長先生に渡したところ、読み聞かせイベントで紹介されて広がった例がありました。
口コミや対面の場から広がるのは、子ども向け絵本の強みです。
落とし穴としては、部数を多く刷りすぎることです。
家庭配布ならオンデマンドや少部数で十分な場合が多いです。
地域・文化を伝える絵本|地域イベントや観光での活用
地域の歴史や文化、生き物、祭りをテーマにした絵本も人気です。
自治体や観光協会、地域イベントと組み合わせるケースがあり、「地域の子どもに地元を知ってほしい」という思いが力になります。
このパターンでは、地元の専門家に簡単に確認してもらうと安心です。
公式資料では分からない伝統の細部や表現があるからです。
成功例では、地元図書館に寄贈し、口コミで広がり、後に観光案内所で販売されたケースもあります。
気をつけたいのは、地域の固有名称や写真の使用です。
公式ガイドラインで権利面を確認し、丁寧に進めるとトラブル防止になります。
オンライン中心で販売|SNS・EC・電子配信の組み合わせ
最近増えているのが、SNSやECを軸にした販売です。
制作過程やラフ画像を発信し、応援してくれる読者を集め、完成後に購入につなげます。
「制作ストーリーも作品の一部」になるのが特徴です。
電子書籍なら海外の読者にも届きますし、紙は少部数+受注生産で負担を抑えられます。
私もSNS投稿からファンが増え、次の作品の支援につながった例を多く見ています。
コツは、宣伝一辺倒にならず、制作の気づきや子どもの反応を共有することです。
ただし、SNSだけに頼ると反応がブレることがあります。 公式サイトやECページを持ち、販売動線を複数持つと安定します。
以上のように、目的ごとに最適な進め方があります。
「誰に届けたいか」から逆算すると、無理なく展開できます。
自費出版で絵本を出すときの注意点|トラブルを避けるポイント
自費出版は自由度が高い分、トラブルを未然に防ぐ意識が大切です。
特に絵本は、画像・表現・読者層の面で配慮が必要になります。
ここでは、経験上よくつまずきやすいポイントを整理します。
著作権とイラストの権利管理|素材利用と外注時の契約
絵本づくりでまず気をつけたいのは著作権です。
ネットの画像や既存キャラクターに似たデザインを使うのは避けましょう。
フリー素材でも、商用利用範囲や加工可否など利用規約が異なります。
外注する場合は、著作権(著作権譲渡か使用許諾か)・二次利用・クレジット表記を明確にした契約が安心です。
私は最初、口頭で進めてトラブルになりかけた経験があります。
「公式では自由に使える」と書かれていても、実務では追加許諾が必要な場合もあります。 著作権関連は事前に書面で確認が基本です。
流通条件と販促負担|書店販売の仕組みと現実的な期待値
書店販売は魅力的ですが、「置くだけで売れるわけではない」という認識が大切です。
書店流通にはISBNや取次契約が関わり、委託販売の場合、返品や手数料が発生します。
公式説明はシンプルでも、実務では手間や調整が多いです。
イベント連携やSNSで作品背景を伝えるなど、作者の販促活動次第で動きが変わります。
私の支援先でも、地元書店と協力イベントを行った作品が長く読まれました。
焦らず、少部数+地元書店→広域販売の順で進めると負担が少ないです。
在庫リスクと返品|紙出版でありがちな失敗を防ぐ
「多めに刷ったほうが安い」は正しいですが、在庫はリスクです。
ご自宅がダンボールで埋まる…という状況は、正直よく聞きます。
注文を見ながらオンデマンドや小ロット印刷で始め、反応に合わせて増刷するのが安心です。
書店委託の場合、返品が発生することもあり、破損本の扱いには規約が関わります。
不確実な部数は持たず、需要を確認しながら慎重に進めましょう。
品質管理とレビュー対策|子ども向け表現の配慮
絵本は子どもが読む前提なので、表現の健全性と読みやすさに気を配りましょう。
フォントが読みにくい、色が暗すぎる、年齢に合わないテーマなどは、レビューで指摘されやすいです。
完成前に身近な親子に読んでもらい、反応を見るのが有効です。
また、子どもの心理や発達に配慮し、刺激の強い描写は避けるようにしましょう。
公式ガイドラインを確認し、不明点はサポートに相談するのが安心です。
丁寧な確認作業ほど、信頼される作品になります。
まとめ|目的と読者から逆算して最適な出版方法を選ぶ
絵本の自費出版は、届けたい相手を明確にし、制作・流通・販促を逆算することで無理なく進められます。
豪華さより、「誰にどう届けるか」が作品の価値を高めます。
段階を踏みながら制作し、必要なところで専門家の手も借りると安心です。
無理のない形で、丁寧に作品を育てていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。