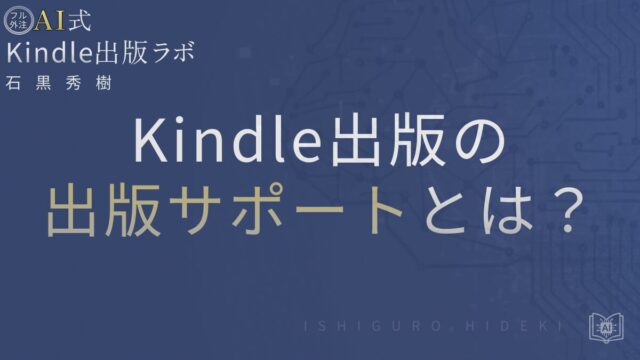自費出版の売り込みとは?初心者が失敗しない提案と販路戦略を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
本を自費で出版したあと、「どうやって読者に届けるか」で悩む方はとても多いです。
せっかく時間もお金もかけて作った一冊なのに、身近な人しか読んでくれない。そんな状況を変えたいと思うのは自然なことです。
「この記事では、『自費出版 売り込み』で悩んでいる方に向けて、自分の本をどう広め、どのように書店やネットで扱ってもらうかというテーマを、初心者にも分かりやすく整理していきます。」
経験者の立場から、よくある誤解や現場でのリアルな流れも交えてお伝えします。
▶ 出版の戦略設計や販売の仕組みを学びたい方はこちらからチェックできます:
販売戦略・集客 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
自費出版で「売り込み」を成功させるための全体像
目次
自費出版は「本を作ること」がゴールのように思われがちですが、実際はそこがスタートラインです。
出版後の「売り込み」をどう考えるかによって、本が届く範囲は大きく変わります。
ここでは、売り込みの意味と目的、そしてなぜそれが必要なのかを整理していきます。
自費出版+売り込みとは何か:一言定義と目的
自費出版における「売り込み」とは、自分の本を読者や書店に知ってもらうための働きかけを指します。
商業出版のように出版社が営業を代行してくれるわけではないため、著者自身が動く必要があります。
たとえば、地域の書店に置いてもらえるよう提案したり、SNSで作品の魅力を発信したりすることも、立派な「売り込み」です。
目的は単に売上を伸ばすことではなく、「本を必要としている読者に届けること」。
実際に、私が最初に自費出版したときも、最初の数週間はまったく動きがありませんでした。
ですが、知人の書店にテーマを説明して小部数で置いてもらったところ、少しずつ読者の反応が見え始めたのです。
こうした経験からも、売り込みは“宣伝”というより“本と人をつなぐ行動”だと感じます。
なぜ「売り込み」が必要になるのか:流通と宣伝の観点から
自費出版の本は、一般の商業書籍とは流通経路が異なります。
多くの場合、書店の全国流通には乗らず、ネット販売や地域流通に限られるため、自然に店頭に並ぶことはほとんどありません。
そのため、「売り込み」は読者との接点を作るための必須プロセスといえます。
ここを誤解してしまい、「出版社に任せたら書店に並ぶはず」と考える方も多いのですが、実際は出版社によって販売支援の範囲が大きく異なります。
公式には「販売サポートあり」と書かれていても、実務上は「紹介のみ」で終わるケースも珍しくありません。
また、宣伝の観点では「どんな本がどんな読者に刺さるのか」を著者自身が一番よく理解しているため、作り手の言葉で発信することに意味があります。
たとえば、読者の年代や関心を想定し、どんな場所で見てもらいたいかを考えるだけでも、宣伝の方向性が明確になります。
こうした意識を持つことが、後の販売戦略の土台になります。
自費出版の「売り込み」は、派手な営業活動ではなく、“誰にどう届けたいか”を自分の言葉で整理する行為だと捉えるのが実践的です。
自費出版本を売り込む手順と販路選びのポイント
自費出版をしたあとの「売り込み」は、思いつきではなく、販路(どこで売るか)を整理してから進めるのが基本です。
最初に方向性を決めておくことで、宣伝や在庫管理の手間を減らし、継続的に読者へ届けやすくなります。
ここでは、紙と電子書籍の違い、書店への提案書の作り方、そしてオンライン販売でのステップを順に見ていきます。
自費出版全体の流れや販路の種類については『自費出版で本を売る方法とは?初心者が知るべき販路と集客の基本を徹底解説』も合わせて読んでおくと、この記事の「売り込み戦略」がよりイメージしやすくなります。
紙媒体・電子書籍それぞれの販路(書店流通/オンライン販売)の違い
紙の本と電子書籍では、販売の仕組みがまったく異なります。
まず紙媒体の場合、書店流通を通すには「取次会社」と呼ばれる中間業者を経由するのが一般的です。
ただし、自費出版では取次を通せないケースが多く、地域書店などへ直接持ち込む「委託販売」が現実的な方法になります。
この場合、販売数や返品対応の条件を事前に確認することが大切です。
実務では、公式サイトに書かれている条件より柔軟に対応してくれる店舗もあれば、逆に厳しい基準を設けているところもあります。
そのため、最初から全国流通を狙うより、小規模から始めて反応を見ていくのが現実的です。
一方、電子書籍は在庫を持たずに販売できるのが最大の強みです。
Amazon Kindleや楽天Koboなどに登録するだけで、誰でも販売ページを作れます。
「販売手数料(ロイヤリティ率)はプランや販売ストアによって異なります。70%前後のプランもありますが、適用条件や正確な率は各ストアの最新の公式ヘルプを確認してください。(公式ヘルプ要確認)」
ここで注意したいのは、「登録しただけでは読まれない」という点です。
電子書籍は自由度が高い分、競合も多いため、タイトルや表紙、紹介文などの工夫が欠かせません。
経験上、タイトルに「誰のための本か」を一言入れるだけでもクリック率が上がる傾向があります。
紙と電子、それぞれの仕組みを理解し、自分の目的に合うルートを見極めましょう。
具体的な告知手段やキャンペーン設計については『自費出版の宣伝方法とは?電子書籍と紙の本を売る戦略を徹底解説』で、紙と電子それぞれの事例を詳しく紹介しています。
書店への提案書の作り方:テーマと読者像を明確に提示する方法
書店に売り込みをするときは、勢いよりも準備が大切です。
いきなり本を持ち込んでも担当者は困ってしまうため、まずは「提案書(販売資料)」を用意しましょう。
提案書には、以下の3点を簡潔にまとめます。
1. 本の概要(タイトル・ジャンル・ページ数)
2. 想定読者(どんな人に向けた本か)
3. 店舗側のメリット(地域性・話題性・季節性など)
これらをA4用紙1枚程度にまとめるだけで印象が変わります。
特に重要なのは、「どんな読者に届く本なのか」を明確に伝えることです。
たとえば、「地元の歴史を紹介する写真集」なら、観光コーナーや郷土資料の棚に置く理由が明確になります。
私の経験では、「この棚に置けそう」と担当者がイメージできた瞬間に、話が一気に進みました。
また、数冊単位での委託から始めると、店舗側のリスクも少なく、受け入れてもらいやすいです。
強引な売り込みではなく、「一緒に読者を増やす提案」を意識しましょう。
オンライン販売(自社EC・Kindle・オンデマンド)で「売り込み」を考えるステップ
オンライン販売は、自費出版との相性が非常に良い販路です。
まずKindleなどの電子書籍ストアに登録し、その後にSNSやブログで発信を組み合わせると効果的です。
販売開始後は、すぐに売上が伸びなくても焦らず、キーワードの見直しや価格調整を少しずつ行いましょう。
「Kindleのロイヤリティ70%プランには販売価格の範囲など複数の条件があります。具体的な金額や条件は変更される可能性があるため、必ず最新の公式ヘルプで確認してください。(公式ヘルプ要確認)」
自社ECサイトを使う場合は、在庫・配送管理が必要になりますが、読者との距離を近づけられるという利点があります。
また、最近はオンデマンド印刷を利用し、注文が入ってから1冊ずつ印刷する仕組みも広がっています。
これなら在庫リスクを最小限に抑えられます。
オンライン販売のコツは、「宣伝と販売を分けて考えない」ことです。
販売ページやSNS投稿も「読者との会話の場」と捉え、作品の背景や制作意図を少しずつ発信すると、自然に興味を持ってもらえます。
これらを積み重ねることで、短期的な売上ではなく、長く読まれる本づくりにつながっていきます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
売り込み時に押さえておきたい「読者・相手側の視点」
自費出版の「売り込み」でつまずく多くの人が見落としがちなのが、相手の立場です。
書店の担当者や読者が何を基準に本を選んでいるのかを理解していないと、どんなに熱意があっても届きにくくなります。
ここでは、書店側と読者側、両方の視点から考えるポイントを整理します。
書店・販売担当者が検討するポイント:在庫・回収・陳列など
書店にとって自費出版の本を扱うかどうかは、感情よりも「実務上の判断」が大きいです。
担当者がまず見るのは、「在庫スペース」「売れ行きの見込み」「返品対応」の3点です。
つまり、“置くだけで終わらない本かどうか”を冷静に見ています。
たとえば、地元ゆかりの内容や話題性のあるテーマであれば、少部数でも置いてみようと判断されることがあります。
一方、内容が良くても陳列棚のテーマと合わない場合は、見送られることも珍しくありません。
このあたりは、公式に「委託可能」と記載のある書店でも、実際には現場判断で対応が変わるケースが多いです。
また、回収や在庫リスクの負担をどうするかも大切な要素です。
多くの書店は、売れ残った場合に著者が引き取る「委託販売方式」を好みます。
「買い取り制」にしてしまうと、書店にとっては在庫負担が大きくなり、結果的に敬遠されやすくなります。
私の経験では、「3冊だけ置いていただき、2か月後に状況を見て引き取りも可能です」と伝えると、受け入れてもらえる確率が格段に上がりました。
要は、書店側のリスクを減らし、扱いやすい条件を提示することが信頼につながります。
読者の視点で考える「なぜその本を手に取るか」:魅力と動機を売り込み文に反映する
もうひとつ重要なのが、読者の立場からの視点です。
読者は「誰が書いたか」よりも「自分に関係があるか」で本を選びます。
つまり、タイトルや帯、紹介文などに「自分に向けられた言葉」があるかどうかが判断基準になります。
このとき役立つのが、「読者が本を手に取る瞬間」を想像することです。
たとえば、健康や暮らしに関するテーマなら、「自分にもできそう」「これなら続けられそう」という安心感を与える言葉を選ぶと伝わりやすくなります。
実際、キャッチコピーの1行を変えるだけで、オンライン販売のクリック率が2倍になった例もあります。
売り込み文や紹介ページを作るときは、「本の内容を説明する」のではなく、「読者の悩みをどう解決できるか」を中心に書くのがポイントです。
また、SNSやブログで発信する場合も、「この本があなたにどんな気づきを与えるか」という語り方のほうが反応が良い傾向にあります。
特に初心者の方がやりがちなミスは、「本の内容をすべて説明してしまう」ことです。
それではネタバレになり、購入意欲を下げてしまうこともあります。
あくまで「入り口を見せる」「共感を生む」ことを意識しましょう。
読者は“感情で興味を持ち、理屈で納得する”傾向があります。
その心理を理解すれば、売り込み文は自然と説得力のあるものになります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
自費出版の売り込みで実践する前に知っておきたい注意点と失敗を避けるための対策
自費出版の売り込みは、「勇気を出して動くこと」が大切ですが、勢いだけではうまくいきません。
現場では、思い込みや準備不足によるトラブルも少なくありません。
ここでは、よくある誤解と、信頼を保ちながらスムーズに進めるための基本対策を紹介します。
ありがちな誤解:「お願いすれば書店に並ぶ」「強く売り込めば決まる」について
自費出版を始めたばかりの方が最も陥りやすいのが、「お願いすれば置いてもらえる」「熱意を伝えれば決まる」という考え方です。
気持ちは大切ですが、書店の判断はあくまで「販売の見込み」と「運営上のリスク」で決まるのが実情です。
書店は1日に多くの営業連絡を受けており、全てに対応できるわけではありません。
また、「強くアピールすれば印象に残る」と思いがちですが、逆効果になることもあります。
相手のスケジュールを考えずに何度も電話や訪問をすると、迷惑と捉えられてしまうことがあります。
自分の作品を守りたい気持ちは理解できますが、売り込みの場では“熱量よりも配慮”を意識することが信頼につながります。
もうひとつの誤解は、「出版会社が営業をしてくれる」というものです。
一部の出版社は販売支援を行っていますが、多くは制作までが範囲であり、書店交渉や宣伝は著者自身が担います。
実際、契約書に「販売代行」と書かれていても、紹介レベルで終わる場合もあるので注意が必要です。
現場では、“出版社に任せきりにせず、自分で動く意識”が成功の鍵になります。
トラブルを避けるためのマナーと契約・費用の確認ポイント
売り込みを行う前に、必ず確認しておくべきなのが「契約条件」と「マナー」です。
まず、書店とのやり取りでは口約束を避け、必ずメールや書面で残しましょう。
委託販売の場合は、「販売期間」「販売冊数」「返品条件」を明確にしておくことが大切です。
特に注意したいのが、販売期間のトラブルです。
公式上では「3か月」となっていても、実際は店舗によって柔軟に延長してくれるケースもあります。
反対に、予定より早く引き上げを求められることもあるため、事前の確認が欠かせません。
「また、販売手数料(マージン)は店舗ごとに大きく異なります。事前に率や計算方法、振込タイミングなどを書面で確認しておくと安心です。」
これも契約前に確認しておくと安心です。
マナー面では、「在庫の補充・引き取りを自分で行う」「相手の繁忙期を避けて訪問する」など、小さな配慮が信頼を生みます。
実際に私が取材した著者の中にも、書店員との関係を丁寧に築いたことで長期的に扱ってもらえた方が多くいました。
売り込みを“交渉”ではなく、“協力関係を築くための対話”と考えると、自然と接し方も変わります。
最後に、費用面の注意です。
自費出版では、印刷・販売・宣伝に関わる費用を著者が負担します。
そのため、「成果保証型」「出版すれば必ず売れる」などの過剰なセールスには注意が必要です。
契約を結ぶ前に、複数の会社を比較し、口コミや契約書の細部まで確認するようにしましょう。
焦らず準備を整えれば、安心して売り込みに臨めます。
契約書や流通条件のチェックポイントを体系的に整理したい方は、『自費出版の注意点とは?費用・契約・流通を徹底解説して失敗を防ぐ』も事前に確認しておくと安心です。
自費出版と売り込み成功の事例と活用できるアイデア
自費出版の売り込みは、派手な宣伝や資金力よりも、コツコツと「届け方を工夫した人」が結果を出しています。
ここでは、実際に成果を上げた2つのケースを紹介しながら、初心者でも応用できるアイデアを解説します。
どちらも大きな投資をしていませんが、「自分にできる範囲で継続する」ことが成功につながっています。
少部数から始めて成功したケース:地域書店・イベントを活用した流れ
最初の事例は、地方在住の著者が「地域の文化と人」をテーマにしたエッセイを出版したケースです。
大手書店ではなく、地元の独立系書店や図書館イベントを中心に売り込みを行いました。
最初は10冊のみの委託販売からスタート。
地元新聞やフリーペーパーに取材をお願いし、読者層が重なる媒体に紹介してもらうことで、自然な形で認知を広げていきました。
この著者が特に意識していたのは、「売る」よりも「話題を作る」という姿勢です。
イベントでのトークやサイン会を通して本の背景を語ることで、来場者がSNSに写真を投稿し、口コミが広がりました。
書店の担当者も「地域の本として長く置ける」と評価し、半年以上の継続販売につながったそうです。
私自身も似た経験がありますが、地方の書店は「人とのつながり」を大事にする傾向があります。
一度信頼関係を築けると、次回の出版時にも応援してくれることが多いです。
電子書籍+SNS活用で販路を拡大したケース:副業としての出版も視野に
次の事例は、ビジネス系の電子書籍をKindleで出版したライターのケースです。
この方は、最初から「全国の読者に届ける」ことを意識し、SNSと連動させて販売を伸ばしました。
出版直後は売上がほとんどなかったそうですが、1か月目にTwitter(現X)で本の一部を引用した投稿が拡散。
それをきっかけにAmazonのおすすめ欄に表示され、徐々に売上が増えていきました。
注目すべきは、単に投稿したのではなく、「本の内容を無料で一部シェア」していた点です。
読者が「続きが気になる」と思う内容を選び、あえてリンクを1行だけ添えることで自然に誘導していました。
この手法は、商業出版のマーケティングでもよく使われる方法で、“売るための発信”ではなく“価値を共有する発信”と考えるのがポイントです。
また、電子書籍は改訂が容易なので、反応を見ながらタイトルや紹介文をリライトしていくことで販売を継続できます。
この著者も、月に1回ペースで小さな更新を繰り返し、半年後には副収入として安定した金額を得るようになりました。
まとめ:自費出版+売り込みで意識すべき3つのポイント
自費出版での売り込みを成功させるには、派手な宣伝よりも「信頼」「共感」「継続」が鍵になります。
まず1つ目は、相手の立場に立った提案を心がけることです。
書店でもSNSでも、相手が求めている情報や価値を理解して動くことが、長く続く関係を築きます。
2つ目は、少部数でも確実に反応を積み上げることです。
無理に全国展開を狙うより、小さな成功体験を重ねたほうが信頼性が高まり、次の出版やコラボにつながりやすくなります。
そして3つ目は、「売り込み」を“営業活動”ではなく“読者とのコミュニケーション”と捉えることです。
SNSや書店提案も、実は読者との接点づくりのひとつです。
焦らず、自分の作品と丁寧に向き合いながら発信していくことが、最も確実な方法だといえます。
全体の進め方やありがちな落とし穴を俯瞰したい方は、『自費出版で後悔しないための完全ガイド|失敗事例と対策を徹底解説』で出版前後のチェックポイントも一度整理しておきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。