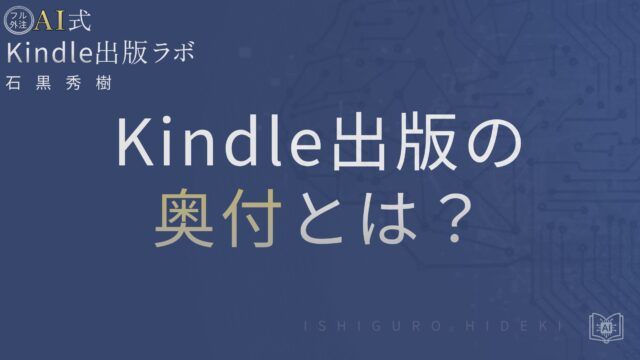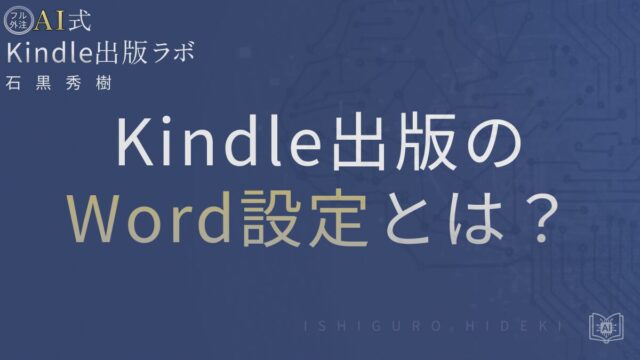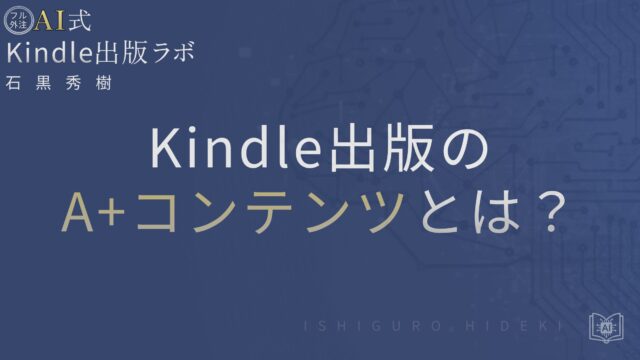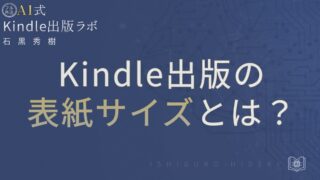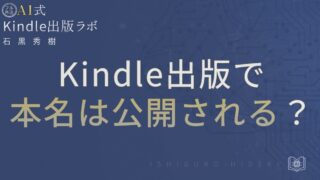Kindle出版は何で書く?おすすめ執筆ツールと入稿手順を徹底解説
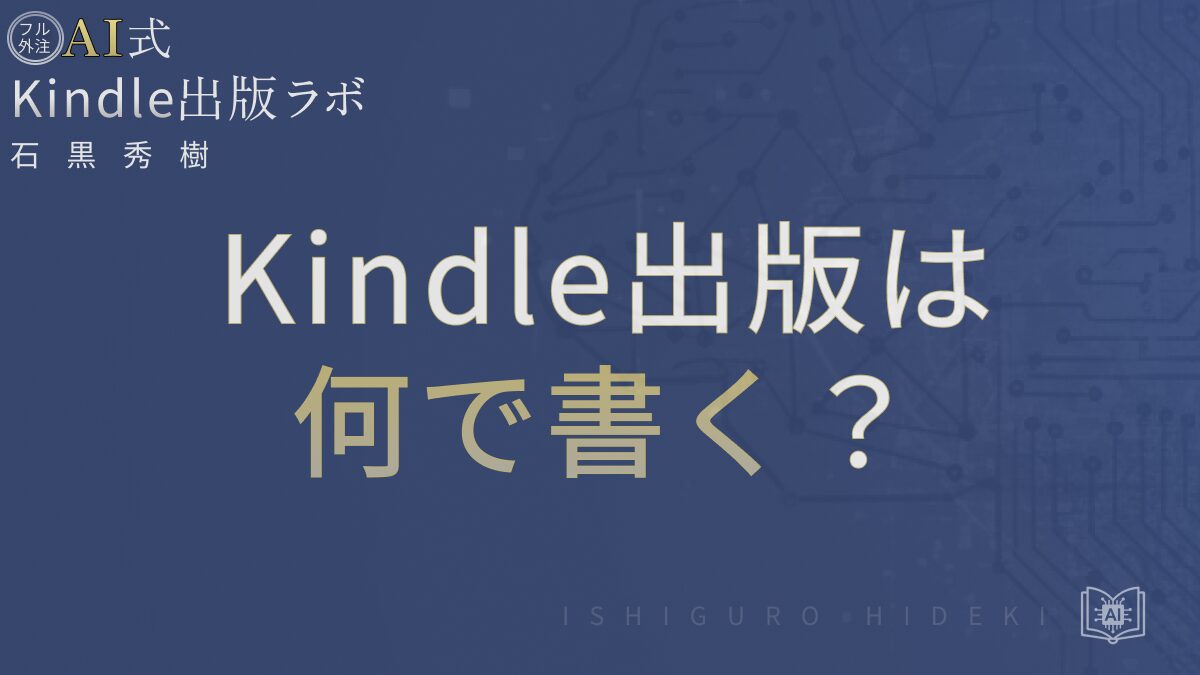
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めたいけれど、「原稿って何で書けばいいの?」「Wordでいいの?それとも専用のアプリがある?」と迷う方は多いです。
実際、Kindle出版では「使うツールで体裁や作業効率は大きく変わります。審査の速度や結果は内容・メタデータ等の適合性に依存します(公式ヘルプ要確認)。」
この記事では、初心者がまず理解しておくべき「執筆ツールの選び方」と「推奨されるファイル形式」をやさしく解説します。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版は何で書く?初心者が最初に知るべき基本
目次
Kindle出版では「どのツールで原稿を書くか」を決めることが、最初の大きなステップです。
Word、Googleドキュメント、Kindle Createなど、さまざまな選択肢がありますが、どれも一長一短。
この章では、まず「何で書く」という質問の意味から整理し、使えるツールと推奨形式を紹介します。
具体的なツールごとの違いを比較したい場合は、『Kindle出版におすすめのソフトとは?初心者でも崩れない原稿づくりを徹底解説』もあわせてチェックしてみてください。
「何で書く?」の意味と目的を明確にしよう
「何で書く?」とは、単に“どのアプリを使うか”という質問に留まりません。
Kindle出版における「書く」は、「構成を整え、体裁を整えて、Amazonに入稿できる原稿を作る」という一連の流れを指します。
たとえば、WordやGoogleドキュメントで文章を執筆し、体裁を整えたあとに「Kindle Create」で最終確認をしてKDPにアップロードする。
この流れが一般的です。
つまり、「何で書く?」とは“原稿を作るツール”と“最終入稿用の形式”をどう選ぶかという話になります。
初心者の方がよくある失敗は、「Wordで書けばそのまま出せる」と思ってしまうことです。
実際には、フォントや改行、余白設定がKindle端末で崩れるケースがあります。
そのため、原稿作成ツールと入稿形式の関係を正しく理解することが大切です。
電子書籍の原稿作成に使える主なツール一覧
Kindle出版でよく使われる原稿作成ツールは、以下の3つが中心です。
* **Microsoft Word(推奨)**:最も一般的で、KDP公式でも対応している形式。レイアウト調整がしやすく、初心者にも扱いやすいです。
* **Googleドキュメント**:無料で使え、オンラインでデータ共有できるのが魅力。Word形式(.docx)に変換して入稿可能です。
* **Kindle Create**:Amazon公式の編集ソフト。Wordで作成した原稿を取り込み、KPFファイルに変換して体裁を確認できます。
このほか、Macユーザー向けのPagesや、小説向けのScrivenerなどもありますが、初めて出版するならWordまたはGoogleドキュメント+Kindle Createの組み合わせが最もスムーズです。
筆者自身も、最初のKindle出版ではWordを使いました。
文字数カウントや見出し設定が直感的で、校正もしやすかったためです。
一方で、Googleドキュメントを併用しておくと、クラウド上に自動保存されるので、データ紛失のリスクを減らせます。
Kindle出版で推奨されるファイル形式(DOCX・KPF・EPUB)
Kindle出版で対応しているファイル形式は複数ありますが、初心者がまず押さえるべきは以下の3つです。
* **DOCX(Word形式)**:WordやGoogleドキュメントで作成した原稿をそのままアップロードできます。体裁が整っていれば、この形式だけで出版も可能です。
* **KPF(Kindle Create形式)**:Amazon公式ツール「Kindle Create」で作成されるファイル。電子書籍端末での見え方を確認しながら編集できるため、より安定した仕上がりになります。
* **EPUB形式**:外部ツールやデザインソフトで作成する場合に使用されるプロ向けの形式。デザインや画像が多い本で採用されることが多いです。
公式としてはどの形式でも対応していますが、初心者におすすめなのは「Wordで書いて、Kindle CreateでKPF形式に変換する」方法です。
これならレイアウト崩れが少なく、出版後の修正もスムーズに行えます。
なお、EPUBを使う場合は外部ソフトでの生成が必要になるため、上級者向けです。
「公式はDOCX・EPUB・KPFなどをサポートし、Kindle Create(KPF出力)の利用が案内されています。推奨表現の細部は最新版を確認してください(公式ヘルプ要確認)。」
最後に補足ですが、ペ「ペーパーバックは本文24ページ以上が目安です。入稿はPDFが一般的ですがDOCX等も対応があります。仕様は最新版を確認してください(公式ヘルプ要確認)。」
電子書籍とは仕様が異なるため、目的に応じて形式を選びましょう。
Kindle出版におすすめの執筆ツール比較
Kindle出版では、どのツールを使うかによって作業効率や完成度が大きく変わります。
特に初心者のうちは、使い慣れたソフトを選ぶことが安心です。
ここでは、実際に多くの著者が利用している主要ツールの特徴と注意点を比較して紹介します。
Wordで書く:定番で失敗しにくい理由
WordはKindle出版の原稿作成で最も多く使われているツールです。
理由はシンプルで、KDPが正式にWord形式(.docx)をサポートしているためです。
Wordでは、見出しや段落のスタイルを簡単に設定でき、本文・タイトル・見出しを一貫したフォーマットで整えられます。
特に、文字数カウント・改行・段落設定などを正確に管理できる点が、電子書籍出版では大きなメリットです。
ただし、Wordで直接KDPにアップロードする場合は、レイアウト崩れに注意が必要です。
見出しスタイルを「見出し1」「見出し2」と正しく設定していないと、自動生成される目次がうまく反映されません。
また、余白やインデントをスペースで調整すると、Kindle端末で崩れてしまうこともあります。
実務的には、Wordで原稿を仕上げた後、Kindle Createで最終確認するのがおすすめです。
Wordで原稿を整えたい方は、『Kindle出版×Word原稿の作り方とは?入稿手順と整形ポイントを徹底解説』を参考にすると、体裁崩れを防ぎやすくなります。
筆者も最初はWordのみで出版しましたが、端末で表示を確認すると改ページがずれてしまいました。
Kindle Createを併用することで、その不具合が解消されました。
Googleドキュメントで書く:無料でクラウド管理できる利点
Googleドキュメントは、無料で使えるうえにクラウド上で自動保存されるのが最大の強みです。
パソコンだけでなくスマホやタブレットからも編集できるため、スキマ時間に執筆したい方には最適です。
共有機能を使えば、共同執筆や校正者とのやり取りもスムーズに行えます。
ファイルはWord形式(.docx)でダウンロードできるため、そのままKDPに対応可能です。
ただし、Googleドキュメントにはフォントや余白設定のズレが起きやすいという弱点があります。
特に日本語フォントを多用している場合、Word形式に変換した際に自動的に置き換えられるケースがあります。
このため、入稿前にはWordで最終確認を行うのがおすすめです。
筆者も以前、Googleドキュメントで本文を書き、Wordに変換した際に行間が広がってしまった経験があります。
Googleドキュメントで執筆したい場合は、『GoogleドキュメントでKindle出版する方法とは?無料でできる手順と注意点を徹底解説』で変換時の注意点も確認しておきましょう。
原因は改行コードの違いでした。
このような細かなズレは、実際に出版する前にチェックしておくと安心です。
Kindle Createで書く:公式ツールの使いやすさと制限
Kindle CreateはAmazon公式の編集ツールで、Word原稿を読み込み、Kindle向けに最適化された形式(KPF)で出力できます。
電子書籍の見た目をプレビューしながら調整できる点が、他のツールにはない利点です。
段落や目次の自動設定、タイトル装飾などのテンプレートが用意されているため、デザインに自信がない人でも美しいレイアウトに仕上がります。
また、画像の配置や改ページなどを直感的に操作できるのも魅力です。
ただし、Kindle Createはテキスト中心の本には最適ですが、画像が多い本や特殊なレイアウトには不向きです。
また、ファイル形式が独自のKPF形式であるため、他ツールへの再編集が難しくなる点にも注意が必要です。
実際、筆者もエッセイ本を作成した際に、章ごとの装飾を変更したくてやり直そうとしたところ、KPFでは柔軟な再編集ができませんでした。
そのため、デザイン性を重視したい場合は、先にWordで原稿を作り込み、その後Kindle Createで整える流れが現実的です。
Pages・Scrivenerなど他ツールの選び方と注意点
Macユーザーであれば、Pagesを使って執筆することも可能です。
Pagesで書いた原稿はWord形式(.docx)に書き出せるため、KDPにアップロードできます。
ただし、レイアウト面ではWordより微妙にズレが生じる場合があり、見出し設定や段落構成を慎重に確認する必要があります。
Scrivenerは小説や長編向けの構成管理ツールとして人気ですが、出力設定が複雑で、初心者にはややハードルが高いです。
もし本格的に執筆を続けていく予定があるなら、Scrivenerを検討する価値はあります。
章ごとのメモ管理やプロット作成など、作家向けの機能が充実しています。
ただし、最終的な入稿はWordまたはKPF形式に変換する必要があります。
まとめると、初出版ではWord+Kindle Createの組み合わせが最も安定です。
GoogleドキュメントやPagesは補助ツールとして使い分け、効率よく進めるのが現実的でしょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
スマホ・タブレットでもKindle出版できる?
Kindle出版は基本的にパソコンで行うのが主流ですが、実はスマホやタブレットだけでも不可能ではありません。
外出先で執筆を進めたい方や、パソコンを持っていない方にとっては、スマホでの作業は大きな選択肢になります。
ただし、実際にやってみると「書ける」と「出版できる」は別問題だと気づくはずです。
ここでは、スマホだけで作業する際の限界と、体裁を崩さずに完成度を上げるためのコツを紹介します。
スマホ中心で出版まで進めたい方は、『スマホだけでできるKindle出版のやり方とは?初心者向けに徹底解説』もあわせて読むと、作業全体の流れをつかみやすくなります。
スマホだけで原稿を作る場合の限界と注意点
スマホでの執筆は、思いついたアイデアをすぐに書き留められるという点ではとても便利です。
特にGoogleドキュメントなどのクラウドツールを使えば、外出先でも執筆を継続できます。
しかし、実際にKindle出版の「原稿」として仕上げようとすると、いくつかの限界に直面します。
まず、スマホ画面ではレイアウト全体を確認しづらいという点です。
段落や改行、目次設定などを調整する際に、どうしても誤差が生まれやすくなります。
また、誤って自動変換された文字や記号がそのままKDPに反映されるケースもあります。
もう一つの落とし穴は、KDPの入稿画面やKindle Createなどの編集ツールがスマホ非対応であることです。
スマホから直接アップロードする方法もありますが、エラーが発生しやすく、ファイルのプレビューがうまく表示されないこともあります。
筆者も以前、スマホで書いた原稿をそのままアップロードしたところ、改ページの位置がずれてしまいました。
原因は「段落の余白設定」が自動調整されていたためです。
その経験から、スマホで下書きを書き、仕上げは必ずPCで行うようにしています。
クラウド保存とPC連携で体裁崩れを防ぐコツ
スマホで執筆を進めたい場合は、クラウドツールを活用してPCと連携させるのが現実的です。
GoogleドキュメントやDropbox Paperなどを使えば、スマホで書いた内容をPCで開き、Word形式に変換して整えることができます。
このとき重要なのは、クラウド上で保存しておくことです。
ローカル保存(スマホ本体のメモ帳など)は、誤ってデータを消してしまうリスクがあります。
自動保存されるクラウドツールを使えば、書きかけの原稿を安全に保管できます。
また、スマホでは入力ミスや自動変換の誤りも起こりやすいため、PCで最終チェックを行うことをおすすめします。
特にKindle Createを使ってKPF形式に変換する際は、改行や段落のズレが反映されやすいので注意が必要です。
実務的には、スマホで執筆 → クラウド保存 → PCで体裁調整 → Kindle Createで最終確認という流れが最も安定します。
この方法なら、移動中の執筆と本格的な編集をうまく両立できます。
筆者自身も、移動中にスマホで下書きを書き、自宅のパソコンで仕上げるスタイルに落ち着きました。
スマホだけで完結させようとせず、デバイスごとの得意分野を活かすのがポイントです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
原稿作成からKDP入稿までの流れ
Kindle出版の作業は、「原稿を書いてアップロードするだけ」と思われがちですが、実際はもう少しステップがあります。
特に初めての方は、Wordで書いた原稿をどの形式で保存するのか、どの段階でKindle Createを使うのかなど、迷うことも多いでしょう。
ここでは、原稿完成からKDP入稿までの4つのステップを、順を追って解説します。
実際の出版経験をもとに、注意点も交えながら紹介していきます。
Step1:下書きと構成づくりのポイント
まず最初に行うのは、原稿の下書きと全体構成の整理です。
ここで重要なのは、いきなり本文を書き始めないことです。
テーマやターゲット読者を明確にして、「伝えたいこと」を章ごとに分けておくと、後の編集が格段に楽になります。
例えば、自己啓発書であれば「問題提起 → 具体例 → 解決策 → まとめ」といった流れを決めておくと、読者の理解度も上がります。
この段階でWordやGoogleドキュメントを使っても構いませんが、箇条書き中心でまとめておくのがおすすめです。
筆者も最初の出版では、構成を曖昧にしたまま書き進めてしまい、途中で全体のバランスが崩れて書き直しになりました。
構成を先に固めておくことは、時間の節約にもなります。
Step2:Word(またはGoogleドキュメント)からDOCXで保存
本文が完成したら、KDPが対応している形式「.docx(Word形式)」で保存します。
Wordを使っている場合は、そのまま「名前を付けて保存」から選択できます。
Googleドキュメントを使っている場合は、「ファイル → ダウンロード → Microsoft Word(.docx)」を選べばOKです。
ここで注意したいのは、体裁を整える段階で余白や改行をスペースで調整しないことです。
Kindle端末では自動的にレイアウトが変わるため、見た目を無理に揃えると逆に崩れる原因になります。
また、見出しはWordの「スタイル」機能を使って設定しておくと、Kindle Createで自動的に目次を作成してくれます。
この段階で文字数チェックや誤字脱字も済ませておくと、後の修正がスムーズです。
Step3:Kindle CreateでKPFに変換してプレビュー確認
Wordファイルが完成したら、Amazon公式の無料ソフト「Kindle Create」を使います。
このツールでは、Word原稿を読み込み、Kindle端末向けに最適化されたファイル(KPF形式)に変換できます。
KPF形式のメリットは、Kindleデバイスでの表示をそのまま再現できることです。
段落のズレや改ページの位置を実際に確認できるため、出版前の最終調整に欠かせません。
Kindle Createを使うと、自動で章ごとの見出しや目次も作成してくれます。
ただし、画像の位置や余白などは端末によって多少の違いが出るため、プレビュー画面で複数のデバイスを確認しておくと安心です。
筆者は初出版時にプレビューを省略してしまい、スマホ版の表示で章タイトルが途中で改行される不具合に気づきませんでした。
こうした細かい見え方も、Kindle Createのプレビューで必ずチェックしておきましょう。
Step4:KDPへアップロードして最終チェック
最後に、完成したKPFファイルをKDP(Kindle Direct Publishing)の管理画面にアップロードします。
ここでは、タイトル・著者名・説明文・カテゴリー・キーワードなどを入力します。
アップロード後、「プレビュー」機能で最終確認ができます。
KDP上でのプレビューとKindle Create内の表示には微妙な差があるため、実際のKindle端末のプレビューも確認しておくと確実です。
また、KDPの審査では本文だけでなく、表紙・タイトル・メタデータもチェック対象になります。
タイトルや内容が一致していない場合は差し戻されることもあるため、公開前に整合性を確認しておきましょう。
アップロードが完了し、Amazonの審査を通過すると、「審査〜公開までの所要時間は変動します。数日以内が多いものの、状況により前後します(公式ヘルプ要確認)。」
審査結果が届くまでの間に、販売ページ用の紹介文や著者プロフィールを整えておくのもおすすめです。
筆者の経験では、初回出版は設定項目が多く感じるかもしれませんが、流れを一度つかめば2冊目以降はスムーズに進められます。
焦らず、一つひとつの確認を丁寧に行うことが、出版成功の近道です。
よくある失敗とトラブルを防ぐポイント
Kindle出版は手軽に始められる一方で、ちょっとした設定ミスや見落としによって体裁が崩れたり、公開後に修正が必要になるケースも少なくありません。
特に初出版では、公式マニュアル通りにやったのに「なぜかズレる」「レイアウトが変になる」と戸惑う人も多いです。
ここでは、筆者自身の経験も踏まえて初心者がつまずきやすいトラブルと、その回避法を整理して紹介します。
体裁が崩れる・改ページがずれる原因と対処法
体裁崩れや改ページのズレは、Kindle出版で最も多いトラブルの一つです。
原因の多くは、「Word上では整っているのに、Kindle端末で見ると崩れている」というパターンです。
この現象は、Kindle端末が自動的に文字サイズや余白を調整する仕組みのために起こります。
そのため、スペースや改行で無理に位置を調整するのはNGです。
段落の間隔を空けたい場合は、Wordの「段落設定」機能から正しく余白を設定しましょう。
また、ページ区切りは「Ctrl+Enter」(改ページ挿入)で行うのが安全です。
空白行を連続して改ページのように見せていると、端末表示でずれてしまうことがあります。
筆者も初出版のとき、章の切り替え位置がすべてズレてしまい、何度も再入稿をしました。
原因は改ページを空行で表現していたことでした。
Kindle Createでプレビュー確認を怠らないことが、一番の防止策です。
画像や表が多い原稿での注意点
写真やイラストを多く使う原稿では、レイアウトの崩れに特に注意が必要です。
Word上ではきれいに見えても、Kindle端末では縦横比が変わる場合があります。
画像はできるだけ「挿入 → 行内」に設定し、テキストと一体化させましょう。
「文字列の折り返し」や「前面に配置」にすると、端末表示で位置がずれてしまいます。
さらに、「電子書籍の画像はピクセル基準で最適化し、長辺推奨ピクセルやPPI目安は公式の最新値に合わせて調整しましょう(例:過度な高解像度は配信コスト増の原因。公式ヘルプ要確認)。」
表については、複雑なレイアウトは避け、できるだけシンプルにまとめるのがコツです。
縦長の表は改ページをまたぐ可能性があるため、分割して配置するか、画像化する方法もあります。
筆者も料理本のようなレイアウト原稿を作成した際、表がずれて見えるトラブルに遭いました。
最終的には、Wordで完成させた表を画像として貼り付けることで安定しました。
見た目を重視する本では、テキストより「画像として扱う」ほうが結果的に綺麗に仕上がる場合もあります。
再入稿や修正時に気をつけたいこと
一度出版した後で修正したい場合は、KDPの管理画面から「電子書籍の編集」で再入稿が可能です。
ただし、再入稿のたびにAmazonの審査が入り、反映まで最大72時間ほどかかる点に注意しましょう。
修正内容が軽微でも、「タイトル・著者名・内容紹介」などを変更すると審査に時間がかかる傾向があります。
そのため、再入稿はできるだけ回数を減らし、1回でまとめて行うのが理想です。
また、原稿を修正する際は、旧ファイルを上書きせず「バージョン番号」を付けて保存しましょう。
例:「mybook_v2.docx」「final_v3.kpf」などにしておくと、どれが最新版かすぐに分かります。
筆者も、修正時に古いファイルを誤ってアップロードしてしまい、古い原稿が公開されたことがありました。
KDPでは差し戻し後の再公開にも時間がかかるため、ファイル管理は慎重に行いましょう。
再入稿が完了した後も、Amazonの販売ページに反映されるまでにはタイムラグがあります。
そのため、更新後すぐには焦らず、数時間~1日ほど待ってから確認すると安心です。
このように、Kindle出版でのトラブルは「ちょっとした設定ミス」や「確認不足」から起こることがほとんどです。
制作中・入稿前・修正後の各段階で丁寧にチェックすることで、トラブルの多くは防ぐことができます。
実際の事例:初心者がWord+Kindle Createで出版した流れ
はじめてのKindle出版では、ツール選びや手順の迷いがつきものです。
ここでは、筆者自身が「Word+Kindle Create」を使って出版した実体験をもとに、初心者がつまずきやすいポイントや実際にかかった作業時間を紹介します。
これから同じ方法で出版を目指す方にとって、現場のリアルな流れをイメージできるはずです。
最初に迷った「どのツールで書くか」決断のきっかけ
最初に迷ったのは、「どのツールで原稿を書くか」でした。
Word、Googleドキュメント、Scrivener、Pagesなど、情報を調べれば調べるほど選択肢が出てきます。
最終的にWordを選んだ理由は、KDPが公式に「.docx(Word形式)」を推奨していること、そして多くのテンプレートや解説記事がWord前提で書かれていたからです。
さらに、Wordは見出し設定や目次作成の機能が整っており、Kindle Createとの相性も良いと感じました。
最初はGoogleドキュメントでも試しましたが、細かい余白設定や改ページの扱いに違いがあり、プレビューでズレが発生しました。
その経験から、「最初からWordで統一しておく方が安全」と判断しました。
結果として、Word+Kindle Createの組み合わせが最もスムーズで、KDPの仕様に合わせやすいと感じました。
Wordで書いてKDP公開までにかかった時間とコツ
執筆からKDPで公開するまでにかかった期間は、全体でおよそ2週間ほどでした。
初めてだったため、実際の執筆時間よりも、体裁調整やファイル形式の理解に時間を使いました。
原稿の文字数は約3万字。
Wordで執筆・見直し・見出し設定を終えるまでに3〜4日。
Kindle Createで調整とプレビューを行うのに2日ほど。
その後、KDPへのアップロードから販売開始までに3日ほどかかりました。
コツとしては、見出しスタイルを最初から設定しておくことです。
途中で見出しをつけ直すと、目次の再生成やデザイン調整が必要になり、手間が増えます。
また、段落ごとに改行や余白を整えておくと、Kindle Createに読み込んだときにズレが少なくなります。
もう一つ意外だったのは、表紙画像の準備に時間を取られたことです。
Word原稿が完成しても、KDPでは表紙や説明文、カテゴリ設定なども必要になるため、「出版準備=本文だけではない」ことを痛感しました。
Kindle Createでレイアウト調整した体験談
Kindle Createを使い始めたとき、最初に驚いたのは「思っていたよりシンプル」ということでした。
Wordファイルをドラッグ&ドロップするだけで章ごとに自動分割され、見出しも反映されます。
ただ、実際に使ってみると、細かいデザイン変更はあまり自由ではありません。
フォントや余白はある程度固定されており、見た目を完全に自分でカスタマイズすることは難しいです。
この点は、「自由にデザインしたい人」にとっては制限に感じるかもしれません。
とはいえ、KDP公式の変換ツールであるため、審査通過率や端末互換性の面では非常に安定しています。
筆者も一度、WordファイルをそのままKDPにアップロードしてレイアウト崩れを経験したため、最終的にKindle Createを使うようになりました。
また、プレビュー機能が非常に便利です。
スマホ・タブレット・Kindle端末それぞれの表示を切り替えながら確認できるため、「改行が変」「画像が途切れる」といった問題を事前に防げます。
初回出版時は、章タイトルの余白が狭く見えることに気づき、Kindle Create内で「テーマ設定」を変更して解決しました。
このように、細かな微調整をしながら理想の見た目に近づけることができます。
結果として、Wordで書いた原稿をKindle Createで整えたこの方法は、初心者でも再現しやすく、安定したレイアウトで出版できる王道パターンだと感じました。
初出版を終えた今でも、筆者はこの流れを基本として活用しています。
Kindle出版で「何で書くか」を選ぶ判断基準まとめ
Kindle出版では「どんなツールで原稿を書くか」によって、制作のしやすさも仕上がりも大きく変わります。
最適なツールは「どんな本を作りたいか」によって異なるため、自分の目的に合った選び方をすることが大切です。
ここでは、文章中心・画像中心の本の違い、初心者におすすめの組み合わせ、そしてペーパーバックを出す場合の補足をまとめて解説します。
目的別おすすめツール(文章中心/画像中心)
文章中心の本(エッセイ、実用書、小説など)を作る場合は、WordやGoogleドキュメントのように「テキスト編集に強いツール」が最も向いています。
特にWordはKDP公式が推奨している形式(.docx)に対応しており、見出し・目次・段落設定などが整っているため、Kindle Createとの連携もスムーズです。
一方で、写真集やイラスト中心の作品を作る場合は、CanvaやPowerPointなど、レイアウトを自由に設計できるツールのほうが向いています。
ただし、これらのツールを使う場合でも、最終的にはKDPが受け付けるファイル形式(PDFやKPFなど)に変換する必要があります。
そのため、デザイン重視の作品では「見た目を優先しつつ、ファイル形式をKDP対応に整える」という工程を意識しましょう。
筆者の経験上、文章メインならWord・デザイン重視ならCanva+PDFが安定しています。
最初から複数のツールを使い分けようとすると混乱するため、まずは1本の流れを決めてから試すのが安全です。
初出版ならWord+Kindle Createが最短ルート
初めてのKindle出版では、「Wordで原稿を書いてKindle Createで仕上げる」のが最短でトラブルも少ない方法です。
この組み合わせなら、構成からレイアウト、目次まで一連の作業がスムーズに行えます。
Wordは多くの解説記事やテンプレートがあり、初心者でもフォーマットに迷いにくいのがメリットです。
一方、Kindle CreateはAmazon公式の無料ツールで、Wordファイルを自動的に章ごとに認識してKPF形式に変換してくれます。
筆者も初出版時はこの組み合わせで作業しましたが、Word上で「見出しスタイル」をきちんと設定しておくことが後のレイアウト崩れを防ぐ鍵でした。
慣れてくるまでは、デザインや特殊な書式よりも「正しく出版できる流れ」を優先するのがポイントです。
ペーパーバック出版を考える場合の補足
電子書籍だけでなく、紙の本(ペーパーバック)としても出版したい場合は、レイアウトの考え方が少し変わります。
Kindle Createでは電子書籍向けの自動レイアウトが中心のため、紙版ではページサイズや余白を明確に設定する必要があります。
ペーパーバックを出す場合は、Wordの「ページ設定」でB5やA5サイズを指定し、改ページや見開き位置を意識して作るのが基本です。
また、画像や表を多く使う本では印刷時にずれが出ることがあるため、必ずKDPの「プレビュー(印刷プルーフ)」で確認しておくと安心です。
電子書籍と紙版を同時に出すときは、最初に電子書籍を完成させてから紙版に最適化するのが効率的です。
同時進行で進めると、レイアウトの修正が二重に発生することがあります。
まとめ:自分に合ったツールで出版を始めよう
Kindle出版では、どのツールを使うかで作業効率と仕上がりが変わります。
文章中心ならWord+Kindle Create、ビジュアル中心ならCanvaやPowerPoint、紙版も視野に入れるならWordのページ設定を活用するのが最適です。
最初から完璧を目指す必要はありません。
重要なのは、自分の目的に合ったツールで一冊を完成させる経験を積むことです。
一度出版の流れを掴めば、次の作品では格段にスムーズに進められるようになります。
ツールはあくまで手段。
「どんな本を届けたいか」を軸に、あなたにとって書きやすい環境から始めてみてください。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。