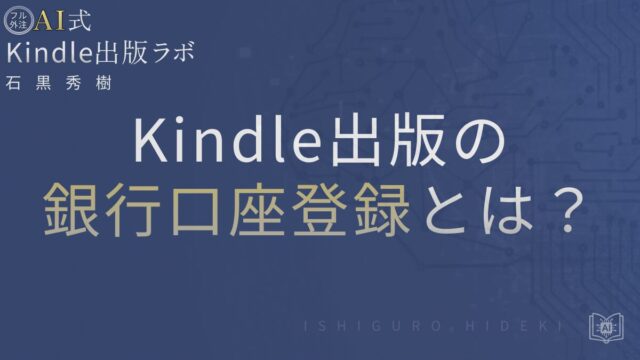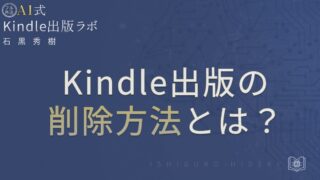Kindle出版の複数アカウントは危険?正しい名義管理と対処法を徹底解説
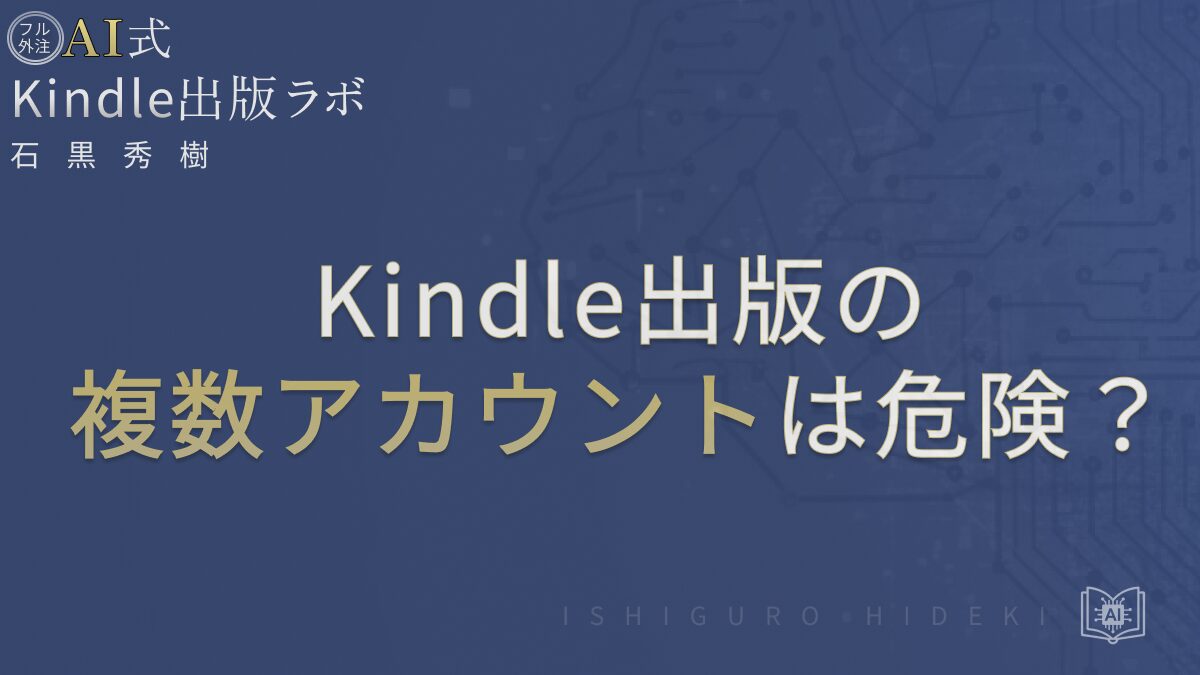
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めた人の中には、「ジャンルごとに別の名前で出したい」「家族でアカウントを分けたい」と考える方が少なくありません。
しかし、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)では原則として一人につき一つのアカウントしか持てません。
本記事では、なぜ多くの著者が「複数アカウント」について調べるのか、その背景と誤解の原因を解説します。
初心者でも理解できるように、実際の出版現場で起こりやすい勘違いや注意点も交えて紹介します。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「複数アカウント」を調べる著者が増えているのか
目次
Kindle出版を進めるうちに、「もう1つアカウントを作った方が便利では?」と思う瞬間があります。
特に、複数ジャンルを扱ったり、ペンネームを使い分けたい場合などです。
ただし、安易に別アカウントを作ると、後でアカウント停止などのトラブルに発展することもあります。
ここでは、なぜ著者が「複数アカウント」というテーマに関心を持つのかを整理していきます。
複数アカウントを考える背景:ジャンル分け・名義分け・家族出版
多くの著者が複数アカウントを考える理由の一つが、ジャンルや読者層を分けたいというニーズです。
たとえば、「ビジネス書」と「エッセイ」を同じ名義で出すとブランドの印象がぶれてしまうことがあります。
そこで「別名義のアカウントを作ればいいのでは?」と考える人が増えているのです。
また、「夫婦で別のテーマを出版したい」「親子でKindle本を出してみたい」というケースもあります。
しかし、KDPの利用規約上、同一人物が複数アカウントを持つことは禁止されています。
家族で出版する場合でも、それぞれが独立したアカウントを運営する場合は、名義・銀行口座・税務情報を明確に分ける必要があります。
この点を曖昧にすると、システム上で同一世帯として判定され、審査で止まることがあります。
検索者が本当に知りたいこと:「複数アカウントはOKか?」という疑問
検索者の多くが抱いている疑問は、単純に「複数アカウントって作っていいの?」という一点です。
KDPの公式ガイドラインでは、「同一人物が複数のアカウントを保持することは禁止」と明記されています。
理由は、印税の支払い・本人確認・著作権の管理を一元化するためです。
実務的にも、Amazonのシステムは登録メールや銀行口座、税務番号などから本人を特定できるようになっています。
つまり、別メールで登録しても、情報が一致すれば同一人物として検知される可能性が高いのです。
一方で、「法人として別アカウントを持ちたい」「個人と法人を分けたい」という相談もありますが、これもケースバイケースです。
法人として別に登録する場合は、登記情報や銀行口座が法人名義であることが必須条件です。
個人が同一である場合は、法人名義でもリスクが残るため、事前に公式ヘルプに問い合わせるのが安全です。
電子書籍(Kindle本)主体の出版運用で出てくる誤解と勘違い
Kindle出版では、「アカウント」と「著者名(ペンネーム)」が混同されがちです。
実際、多くの人が「別のペンネームで出すには別アカウントが必要」と思い込んでいます。
しかし、KDPでは1つのアカウント内で複数のペンネームを設定可能です。
たとえば、Aというアカウントで「田中太郎(ビジネス書)」と「青木蓮(エッセイ)」の両方を使い分けても問題ありません。
それぞれの著者ページ(Author Central)を作成すれば、読者側からは別人のように見えます。
ここを理解していないと、「ジャンルごとにアカウントを分けなければ」と誤解してしまいがちです。
また、実際の出版現場では「複数アカウントを使っていた人が後で統合を求められた」という事例もあります。
一度作ったアカウントは完全削除が難しいため、最初の設計を慎重にすることが大切です。
公式では「一人一アカウント」を明確に定めていますが、実務では意図せず重複してしまうケースもあるため、判断に迷ったら公式サポートに相談しましょう。
Kindle ダイレクト・パブリッシング(KDP)の規約と「複数アカウント」の扱い
KDPのアカウント運用において、最も誤解されやすいのが「複数アカウントを持つことの可否」です。
AmazonのKDPは世界共通の仕組みを使っていますが、Amazon.co.jp(日本版KDP)でも「一人一アカウント」が基本原則です。
ここを理解せずに、別のメールや銀行口座で複数登録してしまい、後からアカウント停止や支払いトラブルに発展するケースが少なくありません。
この章では、規約上の扱いと実務上の注意点を整理していきます。
KDP利用規約4.2:アカウントの複数所有禁止とは何か
KDPの「利用規約4.2」では、明確に「同一人物による複数アカウントの保持は禁止」と定められています。
これは、単に“メールアドレスを変えればOK”という話ではなく、KDPの内部システムが「氏名・銀行口座・税務情報」などをもとに本人を照合しているためです。
私の知る限りでも、「うっかりもう1つ作ったら支払いが止まった」「販売ページが消えた」という相談は非常に多いです。
Amazonのシステムは想像以上に厳密で、同一人物の重複を検知する仕組みが働いています。
そのため、意図せず2つ目を作ってしまった場合も、早めに公式サポートへ問い合わせて統合手続きを行うことが大切です。
もし放置しておくと、どちらのアカウントも審査中で止まる、または収益が保留になるケースがあります。
この点は、利用規約上のルールというよりも「運営上の信頼性確保」の観点から非常に重要です。
KDPアカウントの基本や複数アカウント禁止の詳細は『Kindle出版アカウントとは?登録手順と複数アカ禁止の理由を徹底解説』でまとめているので、あわせて確認しておきましょう。
公式ヘルプの明記:同一人物が2つ以上のKDPアカウントを持てない理由
公式ヘルプにも、「1人または1法人につきKDPアカウントは1つのみ」と明記されています。
その理由は、印税の支払い・本人確認・著作権管理を一元化するためです。
Amazonは、出版や販売の透明性を守るために、支払い元と受取人の一致を非常に重視しています。
実際、KDP登録時には税務情報インタビュー(Tax Interview)という本人確認があり、国籍・住所・納税番号などを入力する必要があります。
このデータは他のアカウントとも照合されるため、仮に別名義で登録しても同一人物として判断される可能性が高いのです。
一方で、「法人」としてのKDPアカウントを新たに作る場合は例外もあります。
その場合、法人として登記され、法人名義の銀行口座・税務情報を登録できることが前提です。
ただし、代表者が同じであっても個人と法人の両方で運用する際は、内容や契約上の整合性を十分に確認する必要があります。
公式ヘルプにも書かれている通り、曖昧な状態で複数運用すると審査落ちや支払い停止のリスクが生じます。
ペンネーム・著者名とアカウントは別扱いであるというポイント
ここで多くの人が混乱するのが、「ペンネームを分けたいから別アカウントが必要」という誤解です。
KDPでは1つのアカウントで複数の著者名(ペンネーム)を設定可能です。
つまり、「アカウント=本人確認・支払い情報の単位」、「ペンネーム=作品上の公開名」という別物として管理されています。
私自身も、異なるジャンルで複数のペンネームを使っていますが、アカウントは1つだけです。
作品ごとに著者名を指定できるので、ジャンルごとのブランド分けも問題ありません。
また、著者ページ(Amazon Author Central)を使えば、ペンネームごとに独立したページを作ることも可能です。
読者からは別人に見えますが、管理上は1つのアカウント内に統合されています。
これは、KDPが「出版管理の透明性」を最優先にしているからです。
別アカウントを増やすより、1つのアカウントでペンネームを分ける方が、長期的に見て安全で効率的です。
もしペンネーム運用の方法に迷った場合は、KDP公式ヘルプの「著者名の設定」項目を確認するのが確実です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
複数アカウントを作ってしまった/作ろうとしている時の実務とリスク
KDPでは「一人一アカウント」が原則ですが、実際には意図せず複数作ってしまう人が少なくありません。
例えば、メールアドレスを変えたときや、昔のアカウントを忘れて新規登録してしまうケースです。
複数アカウントは規約違反となるだけでなく、支払い保留やアカウント停止につながる可能性があるため、早めの対処が必要です。
ここでは、どんな形で「発見」されるのか、見つかったときにどうすればいいのか、そして新たに作ると何が起きるのかを具体的に解説します。
複数アカウントが発見されるケース:登録情報・IP・銀行口座などの紐づけ
KDPのアカウントは、Amazon側で複数のデータを照合して管理されています。
そのため、別のメールアドレスを使っても、氏名・銀行口座・税務情報・住所などが重なれば、同一人物として検知されます。
また、意外と多いのが「同じパソコンや同じIPアドレス」での利用です。
自宅や同じネット環境からログインしている場合、システム上では同一環境と判断されることがあります。
家族で出版している場合でも、同一Wi-Fiから複数アカウントにログインすると警告が出ることがあるため注意が必要です。
私自身も以前、他の著者の手伝いでKDPにログインしただけで一時的に警告を受けたことがあります。
それほどKDPは「同一人物による複数管理」に敏感なのです。
公式は明確に監視の仕組みを公表していませんが、実際にはデータの照合精度は高く、同一の銀行情報や納税番号は特に引っかかりやすい印象です。
既に複数アカウントがある場合の対処法:統合・削除・閉鎖の手順
もしも複数アカウントを持ってしまった場合は、まずKDPサポートに正直に申告することが重要です。
意図的な多重登録と見なされる前に、「誤って複数登録してしまった」「古いアカウントを忘れていた」と説明すれば、統合や片方の閉鎖を案内してもらえます。
サポートへの連絡は、KDPの「お問い合わせ」ページから行います。
英語でのやりとりになることもありますが、日本語でも問題ありません。
問い合わせる際は、以下のような情報を伝えるとスムーズです。
* 現在使用しているアカウントのメールアドレス
* 重複している可能性のあるアカウント情報(古いメール・登録名など)
* 出版している、または残っている本の有無
サポートから「どちらを残すか」「どのアカウントを閉鎖するか」の確認が入るため、指示に従って進めましょう。
閉鎖を依頼したアカウントは数日〜1週間ほどで利用できなくなり、登録作品も自動的に削除されます。
また、銀行口座や税務情報も自動的に紐付けが解除されるため、再利用する場合は残す側で再登録が必要です。
注意点として、閉鎖されたアカウントは再開できません。
一度削除された本のデータも復元できないため、事前にバックアップを取っておくと安心です。
別アカウントを新規に作るとどうなるか:停止・再開不可のリスク
「もう一つ作れば早いのでは?」と考えて新規登録するのは、最も避けるべき行為です。
新しいメールや別名義で登録しても、同一人物と判断されれば、すぐにシステム上で関連付けられます。
そして、多くの場合、どちらか一方、または両方のアカウントが審査保留または停止となります。
特に印税の支払いが発生している場合、保留中の金額が凍結され、サポート経由でも解除に時間がかかるケースがあります。
一度停止になると、本人確認書類の再提出や追加審査が必要となり、再開までに数週間かかることも珍しくありません。
この状態になると、「出版を継続したいのに本が出せない」という状況に陥ります。
実際に、アカウント凍結後に「別名義でやり直そう」とした人が再び停止になった例もあります。
KDPは利用規約に基づいて厳格に運用されているため、抜け道的な運用はまず通りません。
もし運用上の理由で複数名義を使いたい場合は、別アカウントではなく「1つのアカウントで複数ペンネームを使い分ける」のが正解です。
ペンネーム機能を活用すれば、ジャンル別のブランド管理ができるため、別アカウントを持つ必要はありません。
誤って新規アカウントを作ってしまった場合は、すぐに公式ヘルプから相談し、閉鎖または統合の対応を進めるようにしましょう。
万が一アカウント停止になった場合の流れや復活手順は『Kindle出版のアカウント停止とは?原因と復活までの流れを徹底解説』で詳しく解説しています。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
正しい運用:1アカウントで複数の出版名義を使う方法
KDPでは、ジャンルや作品の方向性に応じてペンネームを分けたい人が多いです。
その場合でも、新しいアカウントを作らず、1つのKDPアカウントの中で複数の著者名を設定することができます。
これはAmazon公式でも認められている方法で、正しい手順で行えば規約違反にはなりません。
ここでは、ペンネーム運用の具体的な方法と注意点を紹介します。
1つのKDPアカウントで複数ペンネーム(著者名)を使う利点と設定方法
1つのアカウント内でペンネームを分ける最大のメリットは、運営・収益・支払いを一元管理できることです。
印税の入金口座や税務情報を統一できるため、複数ジャンルを扱っても事務処理が非常にシンプルになります。
また、アカウントが複数に分かれていないため、審査・支払いのトラブルを避けやすいという実務的な利点もあります。
設定方法も難しくありません。
出版画面で「著者名(Author Name)」を入力する際に、作品ごとに異なるペンネームを設定できます。
この著者名は「本の表紙や商品ページに表示される名前」なので、作品のブランディングを自由にコントロールできます。
たとえば、ビジネス書は「田中啓介」、エッセイは「青木蓮」というように、ジャンルに合わせて別の名義を使うことが可能です。
さらに、Amazon Author Central(著者セントラル)を活用すれば、ペンネームごとに独立した著者ページを作成できます。
これにより、読者から見ても別人として自然に見え、複数のブランドを並行して運営できます。
実際、私自身もジャンル別に複数のペンネームを運用していますが、管理上の混乱は一切ありません。
「すべてを1つのKDPアカウントで完結できる安心感」は非常に大きいと感じています。
具体的なペンネームの設定手順や運用ポイントは『Kindle出版でペンネームを複数使うには?設定方法と注意点を徹底解説』を参考にしてみてください。
名義を分ける際の注意点:著者ページ/銀行口座/税務情報など
複数ペンネームを使う際には、いくつかの注意点があります。
まず重要なのは、著者ページ(Author Central)をペンネームごとに正しく分けることです。
同じアカウントで複数名義を持つ場合、それぞれ別の著者ページを作る必要があります。
この設定を誤ると、作品が誤って一つのページに混在してしまうことがあります。
次に、銀行口座や税務情報については「アカウント単位」で管理される点に注意しましょう。
著者名ごとに口座を分けることはできません。
もし法人運営や共同出版など特殊な形態を取る場合は、契約書や報酬分配の管理を別途行う必要があります。
また、実務的には「アカウント名」と「著者名」を混同しないことが大切です。
出版画面で入力する著者名は「表示名」であり、契約上の本人確認や支払い処理に使われる情報ではありません。
この違いを理解しておかないと、「名義を変えたら収益が振り込まれない」といった誤解を招くことがあります。
なお、ペンネームの数に明確な上限はありませんが、過剰に増やすと管理が煩雑になるため、2〜3名義程度から始めるのが現実的です。
ペンネームを整理して運用することで、ブランド構築と信頼性の両立がしやすくなります。
まとめ:Kindle出版で“複数アカウント”ではなく“名義管理”を考えよう
KDPを運用するうえで最も大切なのは、「アカウントを増やす」ことではなく、「1つのアカウントを正しく活かす」ことです。
複数アカウントを作るとリスクが増える一方で、ペンネームを使い分ける運用なら柔軟性と安全性を両立できます。
最後に、今回の要点を整理しながら、これから出版を始める人へのアドバイスをお伝えします。
要点のおさらい:複数アカウント禁止・1アカウントで名義分けが基本
KDPでは、「同一人物が複数のアカウントを持つことは禁止」というルールが明確に存在します。
これは、印税支払い・本人確認・著作権管理などを一元化し、システムの整合性を保つためです。
一方で、1つのアカウント内で複数のペンネームを使うことは正式に認められています。
したがって、ジャンルや読者層に応じて名義を分けたい場合は、アカウントを増やすのではなく、ペンネームを使い分けるのが正しい方法です。
「複数アカウント」ではなく「名義管理」を前提にした運用こそが、長く安全に出版を続ける鍵になります。
これから出版を始める人へのアドバイスと次のステップ
これからKindle出版を始める方は、まず1つのアカウントを確実に整えることを意識しましょう。
登録情報(氏名・住所・銀行口座・税務情報)を丁寧に設定し、後で変更が必要にならないようにしておくのが理想です。
出版を重ねるうちに複数ジャンルへ広げたくなるかもしれませんが、その段階でペンネームを追加すれば十分対応できます。
また、著者ページを作ることで、名義ごとにプロフィールや紹介文を分けることができ、作品の印象もより明確になります。
実務的なコツとしては、スプレッドシートなどで「ペンネーム別の作品リスト」を管理しておくと、更新漏れを防げます。
KDPはシンプルに見えても、アカウント運用を誤ると審査停止などのトラブルにつながるため、基本ルールをしっかり押さえておきましょう。
本名を出したくない場合の考え方や注意点は『Kindle出版で本名は公開される?ペンネームで匿名出版する方法を徹底解説』にまとめています。
最後にもう一度。
KDPは「誰でも簡単に出版できる」プラットフォームですが、「複数アカウントで運用できる」ものではありません。
正しいルールを理解し、名義を上手に使い分けながら、長期的なブランドとして育てていくことが何より重要です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。