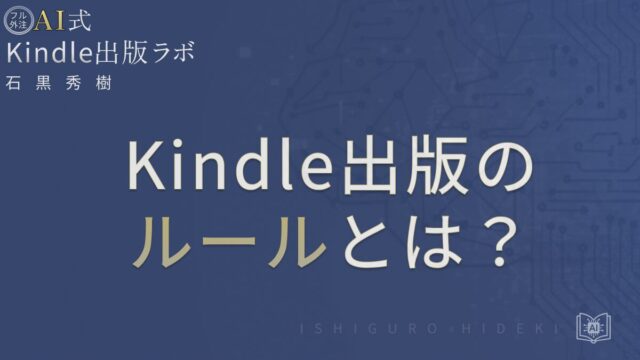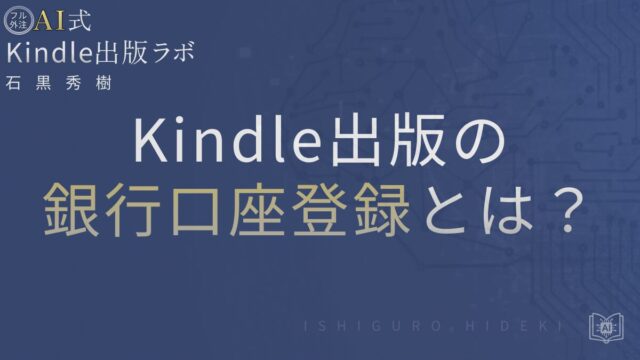Kindle出版の規約とは?審査通過のポイントと違反回避を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようとすると「規約が難しい」「どこまでがOKなのかわからない」という不安をほぼ全員が感じます。
私も初出版のとき、KDPのガイドラインを読み解くのにかなり時間を費やし、「これって違反なのか?」と何度も立ち止まりました。
この記事では、そうした不安を解消するために、KDPが求めるルールを実務経験にもとづいて整理し、「何を守れば審査で止まらずに済むか」を初心者向けに解説します。
結論から言うと、KDPの規約はすべてを暗記する必要はなく、守るべき柱を押さえれば十分に対応できます。
以下から、その全体像をやさしく理解できるようにまとめていきます。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
【日本向け】Kindle出版 規約の全体像と結論(KDP公式に基づく要点)
目次
KDPの規約は非常に細かく見えますが、実務では「どんな内容なら公開できるか」「権利的に問題はないか」「商品ページとの整合性が取れているか」という3つの軸で判断されます。
この章では、まず「Kindle出版の規約とは何を指すのか」「KDP公式のルールはどう整理されているのか」を確認し、記事全体のガイドラインとして共通認識を持っていただきます。
Kindle出版 規約とは?KDPの利用規約とコンテンツ基準の総称
「Kindle出版の規約」という言葉は、公式には1つの文書を指すものではありません。
実際には、KDPで出版する際に参照すべきルールの総称であり、主に以下の枠組みで構成されています。
* KDP利用規約(プラットフォーム全体の契約)
* コンテンツガイドライン(掲載できる内容の基準)
* 著作権ポリシー(権利侵害の禁止)
* メタデータポリシー(タイトルや説明文などの入力ルール)
* 品質基準(読みやすさや構成不備の判断)
これらはすべてAmazon.co.jpのKDP公式サイトに掲載されていますが、日本語訳でも抽象的な表現が多く、「禁止される表現」が具体例付きで網羅されているわけではありません。
そのため出版経験者の間では、「実際の運用ではどこまでがOKなのか?」という共通の悩みがよく出ます。
特に初めて出版する方は『規約の全体像を把握せずに細則だけを読み込んで迷子になる』ケースがとても多いです。
まずは「規約=いくつかのガイドに分かれている」と理解しておくことが重要です。
KDP 利用規約とコンテンツガイドラインの関係(何を守ればよいか)
具体的な禁止対象を知りたい方は、『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』で、審査基準と違反例を確認しておくと理解が深まります。
KDP利用規約は「KDPを使うこと自体の契約事項」であり、アカウント適格性や配信権、ロイヤリティなどの大枠を定めています。
一方、コンテンツガイドラインは「どんな内容ならKindleストアで公開可能か」を判断する基準になっています。
つまり利用規約は「KDPを使ってよいかどうか」の前提であり、コンテンツガイドラインは「その本を販売してよいかどうか」の判断軸です。
さらに、これらを補完する形で以下のガイドが適用されます。
* 著作権ガイド:他人の文章・画像・翻訳の不正使用を防止するための基準
* メタデータガイド:タイトル・説明文・著者名などを正しく入力するためのルール
* 品質ガイド:誤字脱字や構成の乱れなどによる低品質判定を回避するための項目
実務では、「利用規約を前提にしつつ、コンテンツガイドライン・著作権・メタデータを出版前チェックの軸として確認する」という流れになります。
そのためこの記事でも、これ以降の章では、出版前のチェックリストとして理解しやすい順番で内容を整理していきます。
出版前チェックリスト:最重要3本柱+1(電子書籍が主軸)
Kindle出版では「とにかく早く出したい」という気持ちになりがちですが、審査で止まったり公開後に販売停止になると、信頼も時間も大きく失います。
私自身、初期に「表現の判断が甘くて修正依頼が来た」経験があり、公開が1週間遅れたことがあります。
そこで、この章では出版前に必ず確認しておきたい4つの柱(内容・権利・メタデータ・AI申告)を、初心者にもチェックしやすい形で整理します。
特に「どこまでがグレーか」に悩む人が多いため、公式ルールを軸にしつつ、経験者の視点で「実務上の注意点」も含めて解説します。
KDP コンテンツガイドラインの遵守(不適切表現は抽象基準で判断・公式要確認)
コンテンツガイドラインは「どんな内容ならKindleストアに並べてOKか」を判断する基準です。
禁止対象には、過度に不適切な表現や暴力・差別を助長するものなどが含まれます。
ただし、ガイドラインではあえて抽象的な表現になっている部分が多く、「この単語ならOK」「この表現ならNG」という一覧が明記されているわけではありません。
特に成人向けの表現に関しては、「過度な描写」や「露骨なシーン」など抽象的な基準で判断されるため、経験者でも迷うことがあります。
実務的には、「販売ページの表紙や説明文に刺激的要素が前面に出ていないか」「中身が目的化した内容になっていないか」を確認するのが安全です。
また、暴力や差別を含むテーマでも、教育的文脈や啓発的な構成であるかどうかで判断が変わるケースがあります。
迷った場合はKDP公式ヘルプに該当する表現がないか確認し、それでも判断が難しければ構成を見直すか第三者の目線を取り入れると安心です。
KDP 著作権ガイドライン:引用・画像・翻訳の権利確認と許諾
引用や著作権の取り扱いに不安がある場合は、『Kindle出版の引用ルールとは?著作権とKDP審査を徹底解説』を参考に、安全な出典表記を確認しておくと安心です。
KDPでは、他人の文章や画像、翻訳を無許可で使用することは禁止されています。
これは「少し引用しただけ」「ネットで見た内容を要約しただけ」でも問題になることがあります。
引用を行う場合は、日本の著作権法における「引用のルール(出典明記・本文との主従関係など)」を満たす必要があります。
また、フリー素材サイトの画像でも「商用利用可」「再配布可」かどうかを確認し、条件に応じて出典表記やクレジットを入れる必要があるケースがあります。
特に画像や翻訳を「AIが生成したものだから大丈夫」と思い込むのは危険です。
実務では「念のためURLや利用条件をメモして証跡を残しておく」ことをおすすめします。
経験上、後から問い合わせが来ても、この証跡があるだけで対応のスピードと安心感が大きく違います。
KDP メタデータ(タイトル・表紙・説明・出版社名)の整合ルール
メタデータとは、タイトル、サブタイトル、著者名、出版社名、商品説明、シリーズ名など「本の外側の情報全般」を指します。
KDPでは、このメタデータと本文内容の整合性が取れていることが必須です。
例えば「儲かる方法を解説」と書いているのに内容が日記風だったり、表紙のタイトルと登録タイトルが微妙に違っていたりすると、審査で差し戻されやすくなります。
また、「誇張した実績」「専門的資格を持っていないのに資格名を表記する」など、過度な誤認を与える表現もNGとされます。
表紙の作り方や推奨サイズを詳しく知りたい場合は、『Kindle出版の表紙サイズとは?審査に通る作り方を徹底解説』も合わせて確認しておくと失敗を防げます。
私の経験では、タイトル変更だけで再審査対象になるケースがあり、時間をロスしたことがあります。
そのため、メタデータは「最初の段階で確定→構成と照らし合わせて整合性を確認」する流れが効果的です。
AI生成コンテンツの申告の扱い(生成は申告、支援は不要の区別/公式要確認)
近年のKDPでは、AI生成コンテンツの取り扱いに関する申告欄が追加されました。
ここで重要なのは、「AIが内容を生成した場合」は申告が必要ですが、「執筆の補助や校正に使っただけ」の場合は申告不要とされている点です。
具体例として「AIに書かせた文章を一部編集しただけ」は生成扱いになり、「自分が書いた文章の推敲をAIに手伝わせた」は支援扱いになるケースが多いです。
ただし、判断基準は更新される可能性があるため、申請前にKDP公式の最新ガイドラインを確認してください。
安全な運用としては、「生成か支援か判断に迷う→生成として申告する」ほうがリスクが低いと感じています。
AI申告をしていても、それだけで審査が不利になることは基本的にありませんが、虚偽申告はアカウントへの影響が出る可能性があります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
よくあるつまずきと対処:審査保留・販売停止を避けるために
この章では、KDP審査でよくつまずくポイントと、その対処法をまとめます。
実際に私が相談を受けるケースの多くは「規約を読んだはずなのに落ちた」「販売開始後に突然止まった」というものです。
原因の多くは、コンテンツ自体よりも“商品ページ”や“品質面”など外側の要素で引っかかっているケースです。
特にタイトル・説明文・表紙の印象が審査に大きく影響するため、この章での対策を押さえておくことで、無駄な差し戻しを防げます。
商品ページの誤解を招く表現・過度な誇張の禁止(Kindle出版 規約の観点)
KDPでは、タイトルや商品説明に「誤認を与える表現」や「根拠のない誇大な表現」が含まれると審査保留の対象になります。
例えば「1週間で誰でも確実に○万円」など、成功を確約するような語句は特に注意が必要です。
また、「医療的効果や資格名を断定的に記載」している場合も、裏付けがなければNG判定を受ける可能性があります。
私の経験では、特に「数字を含むキャッチコピー」を前面に出しすぎると審査で止まりやすくなる傾向があります。
そのため、「効果を断定せず、体験談や学習効果の可能性として表現する」ことが安全です。
さらに、「タイトル・表紙・説明文の主張が一致しているか」も重要です。
表紙で“副業ノウハウ本”と見せながら中身が“日記風エッセイ”だと、内容不一致で審査リスクが高まります。
品質基準:誤字・体裁崩れ・可読性不足への対処(読者体験の確保)
KDPの品質ガイドラインでは、「読みづらさ」そのものが審査対象になります。
特に以下のようなケースは要注意です。
* 明らかな誤字脱字の多発
* 文章の途中でフォントが崩れている
* 改行が極端に少なく、スマホで読みにくい
* ページのほとんどが画像のみ(説明不足)
初心者の方でよくあるのが、「とりあえず出版して後から直せばいい」という考え方ですが、審査段階で差し戻されてしまうことが多いです。
私自身も初期の頃、「とにかく早く出そう」として校正を甘くし、審査で品質改善を求められた経験があります。
また、Kindleではスマホでの読みやすさが重視されるため、段落の分かりやすさや適切な改行も評価に影響します。
文章に自信がない人は、校正用AIや第三者チェックを活用することで品質リスクを下げられます。
アカウント適格性と基本要件(年齢・契約能力など/日本向けKDP)
意外に見落とされがちなのが「KDPアカウント自体の適格性」です。
KDPの利用には契約行為が可能であることが前提です。年齢要件の明確な数値は<公式ヘルプ要確認>とし、各地域の運用に従ってください。
また、過去に規約違反でアカウント停止になっている場合、再登録しても審査通過が難しくなることがあります。
さらに、銀行口座・税情報が未登録または不備があると、審査自体に進めず公開できないケースもあります。
日本向けに出版する場合は、「Amazon.co.jp」側のKDPを利用する必要があり、米国版や他国版との混同には注意してください。
もし米国で収益が発生する場合は、源泉徴収や税務申告のルールも異なるため、公式ヘルプを確認することが必要です。
実務的には、出版前にKDPアカウント情報と税情報(TIN/EIN)の確認をしておくと安心です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
グレーを避ける判断軸:ケース別に「公式ヘルプ要確認」でリスク低減
KDPでは明確なNGラインが決められている一方で、「状況によって判断されるグレーゾーン」の領域も少なくありません。
特に引用や要約、パブリックドメイン素材の扱い、画像の権利、A+コンテンツなどは、初心者が判断に迷いやすいポイントです。
私自身、問い合わせを受けたり出版相談に乗る中で「これはOKかと思って出していたら、実は基準に触れていた」というケースも数件見てきました。
この章では、判断に迷いやすい代表的なケースを整理しながら、「迷ったら公式ヘルプに沿って再確認する姿勢」を持つことの重要性を具体例とともにお伝えします。
パブリックドメイン・要約・参考書の注意点(許諾・地域差の留意)
パブリックドメインとは「著作権の保護期間が終了し、自由に利用できる作品」のことです。
ただし、保護期間は国によって異なるため、日本と他国の基準が異なる場合があります。
日本では著作権者の死後70年が基本とされていますが、米国や他国基準を参考にして誤って扱うとトラブルの原因となります。
特に「海外のサイトでPDと書かれていた=日本でもOK」と判断するのは危険です。
また、既存の作品を「要約しただけ」あるいは「内容を言い換えただけ」のコンテンツも、その作品の構造や展開を強く踏襲している場合、著作権侵害と見なされることがあります。
学習参考書や用語解説集なども「元の資料をもとに自分なりの視点で構成・文章化しているか」がポイントになります。
私の経験では、「参考書系ジャンルは構成の独自性が低いと審査感触も厳しめになる傾向」があると感じます。
迷う場合は公式ヘルプの「パブリックドメインの基準」や「コンテンツポリシー」を確認し、必要であれば構成を再編集するのが安全です。
画像・イラスト・素材の利用範囲とクレジット表記(権利侵害を回避)
画像の利用に関するトラブルもよく見られるポイントです。
特にフリー素材を使う場合でも、「商用利用可」「再配布可」「加工可」「クレジット表記の有無」などの条件がサイトごとに異なります。
さらに、AI生成画像についても「学習元に著作権のある素材が含まれている場合はリスクがある」と指摘されるケースがあります。
私自身、フリー素材サイトの利用条件を確認せずに使いかけたことがあり、後から読み直すと「商用不可」だったことに気づいたため、急いで差し替えた経験があります。
KDPの公式ガイドラインでも「著作権の有無を明確にし、必要な場合は権利者への許可を得ること」と記載されています。
クレジット表記が求められている場合は、本文や巻末など適切な箇所に記載することをおすすめします。
「出典の記録を残しておく」「証跡を残す」ことは、あとで確認や修正が必要になった際のリスク回避になります。
A+コンテンツと表紙・本文の違い(掲載可否と品質要件)
A+コンテンツ(商品ページ拡張表示)は、出版後に利用できる追加機能で、画像や文章を使って内容をわかりやすく紹介できるツールです。
ただし、本の表紙や本文とは別のルールで審査されるため、ここで不適切な表現が含まれるとA+コンテンツだけが非承認となることがあります。
たとえば「医療効果の断定表現」や「公的機関を連想させるデザイン」「誇大広告的な画像メッセージ」などは、A+審査で止まることがあります。
また、A+に使用する画像サイズや文字量にも推奨基準があり、これを無視すると「品質不備」と判定されやすいです。
私が支援したケースでは、「本文では問題ない表現でも、A+画像にキャッチコピーとして大きく表示した結果、審査で引っかかった」例もありました。
そのため、「本文で通ったからA+も問題ないはず」と判断せず、公式のA+コンテンツガイドラインも確認したうえで作成することが重要です。
手順ガイド:KDP申請時に「どこを見て」「何を直すか」
出版ボタンを押す前後で「どこまで修正できるか」や「審査で止まった場合にどう対応するか」が分かっていないと、無駄に慌てることになります。
実際、出版サポートをしていると「今の状態で修正できるのか問い合わせる前に焦って全データを消してしまう」といったトラブルも稀にあります。
この章では、申請画面で押さえるべきポイントと、修正が可能な範囲、審査で保留になった場合の対処方法を、実務ベースでわかりやすく整理します。
「出版前にチェック・出版後に修正できる点・審査中に触れない点」を判断できるようにしておくことが重要です。
本の詳細情報(メタデータ)の更新可否と修正手順(審査中の制約)
本の詳細情報とは「タイトル、サブタイトル、著者名、シリーズ名、出版社名、キーワード、説明文」などのメタデータ部分です。
これらは「審査前」であれば自由に修正できますが、「審査中」になると一部の項目がロックされ、変更できなくなります。
特にタイトルや著者名は審査中の編集が制限されることがあるため、出版前にかならず確認しておくことが大切です。
表紙や本文の再アップロードは可能な場合がありますが、審査段階や変更内容により制限されることがあります。詳細は<公式ヘルプ要確認>。
ただし、修正を行うと審査がリセットされて再審査になるため、公開までの時間は延びます。
私の支援経験では、「申請後に内容の一部を変更したい」という相談が最も多く、その多くが「出版前に最終確認をしていなかった」ケースです。
対策として、出版前に「メタデータ確定用のチェックリスト」を作り、本文・表紙と一貫性があるか確認しておくと安心です。
申請画面でのAI生成コンテンツの申告位置と実務ポイント
KDPの申請画面には、「AI生成コンテンツの申告」を行う項目が設けられています。
申請画面ではAI生成の有無を申告します。対象は文章に限らず、画像や翻訳を含むケースもあります。最新の対象範囲は<公式ヘルプ要確認>。
たとえば「AIが文章を生成し、そのまま掲載した場合」は生成扱いになり、「人間が書いた原稿に対してAIが校正・改善提案のみ行った場合」は支援扱いになります。
ただし、判断に迷う場合は安全策として「AI生成」として申告する方が安心です。
実務上、AI申告をしているからといって審査で不利になるわけではありません。
むしろ「虚偽の未申告で後から指摘される」ほうがアカウントに影響を及ぼすリスクがあります。
申請欄は見落としやすい位置にあるため、初めての出版では注意して確認することをおすすめします。
審査で止まった時の切り分けと連絡先(公式要確認)
審査で保留や差し戻しになった場合、まず「どの項目に問題があるのか」をKDPからのメール通知やダッシュボードの警告文で確認します。
問題の種類は「コンテンツ(内容の問題)」「メタデータ(情報不一致)」「著作権」「画像や表現の不適切さ」「品質(誤字・改行・可読性)」などに分類されることが多いです。
もし記載内容が抽象的な場合は、タイトルや表紙の表現を見直し、説明文との整合性を確認するのが第一ステップになります。
それでも判断が難しい場合は、KDPサポートに問い合わせることができます。
KDPサポートは日本語対応があります。返信速度は時期や内容で変動するため、目安は示さず<公式ヘルプ要確認>とします。
私がサポート経験から感じるのは、「明確な質問内容(どこを修正すべきか)を添えて問い合わせると比較的スムーズに回答が得られる」という点です。
また、問題を解決した後は修正版をアップロードし、再審査の流れになります。
審査保留=アウトではなく、「修正の余地がある状態」と理解して落ち着いて対処することが大切です。
(補足)ペーパーバックは必要時のみ:最低限の差分に注意
ペーパーバック出版もKDPで可能ですが、電子書籍とはルールやチェックポイントが一部異なります。
電子版だけで完結する方は無理に同時展開する必要はなく、「紙版も出したい」と感じる明確な理由がある場合のみ検討すれば十分です。
私の経験上、「電子版で反応を確認してから紙版を出す」という流れが最もスムーズでリスクも低いと感じています。
ページ要件や入稿仕様など基本ルール(詳細は日本版公式ヘルプ要確認)
ペーパーバックは電子書籍とは異なり、「印刷」という前提があるため、最低ページ数や入稿仕様が細かく決められています。
日本向けでは、ペーパーバックの最低ページ数は「24ページ以上」とされており(公式ヘルプ要確認)、文字だけの書籍でも構成が必要です。
また、表紙データは電子書籍のような「単体画像」ではなく、「背表紙・裏表紙を含むフルカバー形式」で作成する必要があります。
ページサイズもA5や6×9インチなどの指定サイズに合わせたレイアウトが求められるため、電子書籍原稿をそのまま流用するのは難しいケースが多いです。
さらに「ノンブル(ページ番号)の有無」「マージン(印刷余白)」「塗り足し」など、印刷物の基本仕様を意識したデータ調整が必要になります。
このため、経験上「紙版は紙向けのレイアウトを前提として作り直す」ほうが品質面でも審査面でもスムーズです。
ペーパーバックガイドラインは専用項目があるため、紙版を制作するタイミングで日本版KDP公式ヘルプを必ず確認してください。
電子出版だけのつもりなら、本章の内容は「必要になったときに読み返せばOK」という位置づけで問題ありません。
長期的に出版を続ける予定がある方は、『Kindle出版で100冊を目指す前に知るべき規約と品質戦略とは?徹底解説』で、規約遵守と品質維持の両立を意識するのがおすすめです。
まとめ:Kindle出版 規約の「柱」を守って安全に出版する
Kindle出版の規約は、すべてを丸暗記する必要はありません。
大切なのは、以下の柱にそって確認することです。
* 内容(コンテンツガイドラインに沿っているか)
* 権利(引用・画像・翻訳に問題がないか)
* メタデータ(タイトル・説明文との整合性)
* AI生成の申告(生成/支援の区別)
これらを押さえた上で、品質と読者の理解しやすさを確保すれば、多くの場合スムーズに審査を通過できます。
よくある差し戻しの原因は「規約違反そのもの」よりも、「タイトルや表紙の過剰な表現」「構成の不整合」「内容の説明不足」など、「外から見える部分」にあることを忘れないようにしてください。
出版はゴールではなくスタートです。
安全に公開し、読者に向けて胸を張って届けられるよう、規約の柱を大切にチェックしていきましょう。
迷う箇所があれば、公式ガイドラインを参照しつつ、経験者の意見を取り入れることでリスクを大幅に減らせます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。