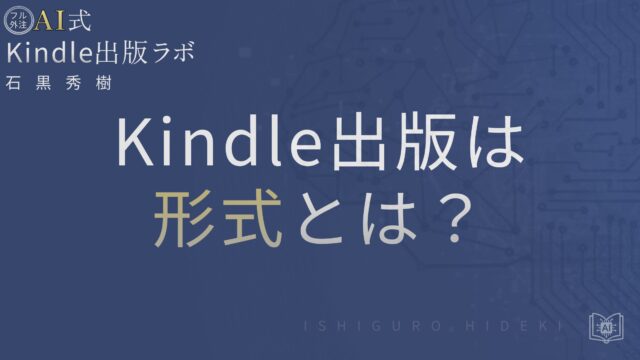Kindle出版×Word設定とは?崩れない原稿づくりの基本と整形手順を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「Word原稿でも大丈夫?」と不安に感じていませんか。
実は、Word(.docx)形式はKDPが正式に対応しているファイル形式のひとつです。
ただし、Wordで書いた文章をそのままアップロードしてしまうと、改行ずれやレイアウト崩れが起こることがあります。
この記事では、Word原稿をKDP仕様に整えるための基本設定と注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。
私自身も最初の出版時に「見た目は整っているのに崩れる」トラブルに苦労しましたが、正しい構造を理解すれば安定してきれいに仕上げることができます。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版×Word設定とは?KDPに対応した原稿整形の基本
目次
KDP(Kindle Direct Publishing)は、Amazonが提供する電子書籍出版サービスです。
Wordファイル(.docx)はこのKDPで正式にサポートされており、専門ソフトを使わなくても出版が可能です。
しかし、単にWordで文章を書くだけでは十分ではありません。
KDPが読み取るのは「文章の構造」であり、「見た目の装飾」ではないからです。
ここでは、Word原稿で出版するために押さえておきたい基本ポイントを整理します。
Word原稿でもKindle出版は可能?対応形式と保存ルール
『Kindle出版の文字数目安とは?初心者向けに基準と判断軸を徹底解説』では、Word原稿の分量を判断する際の基準を整理しています。
Wordで作成した原稿は、KDPに直接アップロードできます。
対応しているのは「.docx」形式のみで、古い「.doc」形式ではレイアウトが崩れる可能性があります。
保存時は「名前を付けて保存」から「Word文書(.docx)」を選択してください。
また、Word内のスタイル(見出し・段落など)はKDPの変換時に自動的に読み取られます。
そのため、手動で空白を入れたりフォントを固定したりすると、KDPでうまく反映されないことがあります。
Word原稿を使うメリットは、操作がシンプルで学習コストが低いことです。
一方で、「構造を意識しないままアップロードして崩れる」ケースが多いため、基本設定を理解しておくことが大切です。
手順全体の流れは『KDPの使い方とは?初心者が迷わず進める基本手順を徹底解説』にもまとまっています。
KDPが読み取る「構造」とは?見た目ではなく設定で整える理由
KDPが変換時に読み取るのは、文字の装飾ではなくWord内部の“構造情報”です。
たとえば「見出し1」や「段落設定」で文書構造を作ることで、KDPはそれを章や節として自動認識します。
一方、フォントサイズや色、空白など「見た目」で整えた部分は、Kindle端末では反映されないことが多いです。
なぜなら、電子書籍は可変レイアウトであり、読者が文字サイズや背景を自由に変更できるためです。
私も初めての出版時、「大きめの文字にすれば章っぽく見える」と思い込み、太字で整えていました。
ところがKDP上では章分けが反映されず、目次も生成されませんでした。
このように、「見た目」ではなく「スタイル設定」で整えることが、KDP仕様では欠かせません。
KDPの公式ヘルプでも、Word原稿の整形には「見出しスタイルを使うこと」「段落設定で整えること」が推奨されています。
これは電子書籍の構造を正しく認識させるための基本ルールです。
Word入稿・EPUB・Kindle Createの違いと使い分け方
Word入稿のほかに、「EPUB形式」や「Kindle Create(KPF形式)」を使う方法もあります。
それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることが大切です。
まず、Word入稿はもっとも手軽で初心者向けです。
文章中心の本(エッセイ・小説・実用書など)では十分対応できます。
一方、「Kindle Create」はAmazon公式ツールで、Word原稿を読み込んで電子書籍用に最適化してくれます。
章ごとのデザインや目次設定を自動で作ってくれるため、見た目を整えたい方には向いています。
最後に「EPUB形式」は汎用的な電子書籍形式ですが、HTMLやCSSの知識が必要な場合もあり、初心者にはやや難易度が高めです。
でんでんコンバーターなどの無料ツールもありますが、公式サポート外のため、変換エラーが起きた際は自己解決が必要です。
私の経験では、最初の1冊はWord入稿で仕組みを理解し、次にKindle Createを試すのが最もスムーズでした。
まずはWordで「構造を整える」ことを覚え、それをもとにKPF形式へ変換すると、表示崩れも少なく安定します。
Word入稿は、手軽さと実用性を両立できる方法です。
正しい設定を身につければ、誰でもKindle出版をスムーズに始められます。
Word原稿の設定手順|崩れないための5つの基本ルール
Wordで書いた原稿をKDPにアップロードする際、最も多いトラブルが「見た目のズレ」と「改行の崩れ」です。
これらの多くは、Word上で“整って見えるだけ”の状態で保存していることが原因です。
ここでは、Word原稿をKDP仕様に正しく整えるための5つの基本設定を、初心者にもわかりやすく順に解説します。
私自身も最初の出版時にこの設定を怠り、プレビューで行間が崩れ、画像が移動してしまった経験があります。
しかし、以下の手順を押さえておくだけで、再現性のある安定した原稿を作成できます。
①見出しスタイル設定:章・節を「見出し1・2」で構造化
Wordの「見出しスタイル」は、KDPが章や節を自動で判別するための重要な要素です。
特に「見出し1」は章タイトル、「見出し2」は節タイトルとして扱われます。
フォントサイズを大きくするだけでは構造情報が反映されないため、必ずWordの「スタイル」機能から見出しを設定しましょう。
設定方法は簡単です。
該当する章タイトルのテキストを選択し、「ホーム」タブのスタイルから「見出し1」をクリックします。
同様に、小見出し部分には「見出し2」を適用します。
これにより、KDP上で自動的に目次リンクが生成され、読者はスムーズに章を移動できるようになります。
“太字+フォント拡大”だけで章タイトルを作るのはNGです。
Word上では整って見えても、KDPでは構造を認識できず、目次が生成されないケースがあります。
実際に「見出しスタイル」を正しく使うと、KDPプレビューでの整合性が格段に安定します。
②段落と行間設定:空白やEnterで整えない
多くの初心者がやってしまうのが、「Enter」キーで無理やり段落間に空白を作る方法です。
見た目上は間が空いてスッキリ見えますが、Kindleでは可変レイアウトのため、読者側で文字サイズを変更すると段落間隔が不自然に広がることがあります。
正しい設定方法は、段落機能を使って「段落後の間隔」を調整することです。
「ホーム」タブ → 「段落」設定から、「段落後」に6pt〜12pt程度の間隔を設定しておくと自然に仕上がります。
また、行間は「1.2〜1.5行」程度が読みやすいとされています。
スペースやEnterは装飾ではなく制御という意識を持つと、崩れを防ぎやすくなります。
KDPはWordの「構造」を読み取るため、余分な改行や空白は不要です。
「空白や改行での体裁調整は崩れの原因になりやすいと広く指摘されています。見出し・段落設定で整えるのが実務的に安全です(詳細は公式ヘルプ要確認)。」
③改ページの正しい方法:「Ctrl+Enter」で固定ページ区切り
章の終わりで次の章を新しいページにしたい場合、単にEnterを連打して空白を作るのは避けましょう。
改行でページを整えると、端末によって文字数が変動し、思わぬ位置でページがずれることがあります。
正しいやり方は、カーソルを次章の冒頭に置いて「Ctrl+Enter」を押すことです。
これで「改ページ」が挿入され、KDPでも確実に章の切り替わりとして認識されます。
特に、章末に画像を配置している場合、この設定をしておかないと画像が次章に流れ込むことがあります。
プレビュー時に違和感がある場合は、この改ページ設定をまず確認しましょう。
④画像配置とサイズ調整:「行内」配置と解像度の目安
Wordで画像を挿入するときは、「文字列の折り返し」設定が重要です。
推奨されるのは「行内」配置です。
これにより、画像がテキストの流れに沿って安定し、KDP変換時にも崩れにくくなります。
表紙画像の作り方は『Kindle出版+Canvaで失敗しない表紙作成徹底解説』も参考になります。
一方、「四角」や「前面」などの配置は、画像位置が固定されず、端末によってズレることが多いです。
特に可変レイアウトの電子書籍では、画像と文字が重なってしまうケースもあります。
解像度は幅1000〜1600ピクセル程度を目安にすると、スマホやタブレットでも見やすい品質になります。
ファイルサイズが大きくなりすぎると、KDPアップロード時に時間がかかることもあります。
画質と軽さのバランスを意識して調整しましょう。
⑤目次の自動作成とリンク確認:プレビューで必ずチェック
見出しスタイルを使っていれば、Wordで「自動目次」を簡単に作成できます。
「参考資料」タブ → 「目次」から自動作成を選ぶと、見出し1・2が目次として反映されます。
目次を作った後は、KDPの「Kindle Previewer」でリンクが正しく動作しているか確認しましょう。
プレビュー画面で章をタップして正しくジャンプできれば問題ありません。
もし動作しない場合は、見出しスタイルの設定漏れや、目次を手動で書き込んでいる可能性があります。
Word目次は「自動生成+プレビュー確認」が鉄則です。
手動で目次を打ち込むとリンクが機能せず、読者が操作しづらくなります。
特に複数章構成の実用書やエッセイ集では、目次の完成度が読後体験を大きく左右します。
この5つの基本設定を守ることで、Word原稿はKDPにスムーズに反映され、表示崩れのリスクを最小限にできます。
最初は少し手間に感じるかもしれませんが、一度テンプレート化してしまえば、次回以降の出版が格段に楽になります。
KDP全体の運用イメージは『Kindle出版の入金はいつ?支払いサイクルと未入金対処を徹底解説』で把握できます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
KDPアップロード前のチェックリスト
KDPに原稿をアップロードする前に、必ず確認しておきたいのが「保存形式・プレビュー確認・レイアウト崩れ」の3点です。
どれも出版直前に慌てがちな部分ですが、この段階で丁寧にチェックしておくことで、公開後の修正作業を大幅に減らせます。
私自身も最初の出版時に、プレビューを軽く見ただけで公開してしまい、文字化けや改ページずれを修正する羽目になりました。
ここでは、実際のKDP運用に沿ったチェック項目を3つの視点から解説します。
保存形式は「.docx」推奨:古い.doc形式との違い
KDPが正式に推奨しているWordファイル形式は「.docx」です。
「.doc」は古いバージョン(Word 2003以前)の形式で、文字コードやレイアウト情報の互換性が低く、KDP側での変換精度が落ちることがあります。
特に、旧形式で保存されたファイルをKDPに直接アップロードすると、段落設定や改ページが無視されるケースがあります。
見出し構造や目次リンクが反映されないこともあるため、必ず「ファイル → 名前を付けて保存 → Word文書(.docx)」を選択してください。
また、Word以外のエディタ(例:GoogleドキュメントやPages)からエクスポートする場合も、形式を「.docx」に統一しましょう。
ファイル変換時に画像や表がずれることがあるので、エクスポート後はKDPのプレビューで必ず確認します。
公式ヘルプにも「.docx推奨」と明記されていますが、実務上でもこの形式が最も安定します。
万が一、古い原稿を利用する場合は、「別名で保存」して新しい形式に変換してから編集を行うのが安全です。
Kindle Previewerで確認すべきポイント4選
アップロードした原稿は、KDP上の「プレビュー」で確認するのが基本です。
ですが、Wordで見たとおりに表示されるとは限りません。
特に可変レイアウト(スマホ・タブレットなど)では、フォントサイズや改行位置が端末によって変化します。
Kindle Previewerを使うと、実際のKindle端末での表示をシミュレーションできます。
確認すべきポイントは以下の4つです。
1. **目次リンクが正しく機能しているか**
2. **改ページ位置がずれていないか**
3. **画像が正しい位置とサイズで表示されるか**
4. **段落の行間が不自然になっていないか**
特に、見出し構造を適用していないと、目次が生成されなかったり、章の途中で改ページが入ることがあります。
これはプレビューでしか気づけない問題なので、必ず複数端末の表示を確認しておくと安心です。
私の経験上、「スマホの縦表示」モードでの確認が最も重要です。
Wordで見たときに整っていても、スマホでは改行が意図せずズレるケースが多いからです。
プレビューで違和感を感じた箇所は、Word側で段落設定や改ページを修正し、再アップロードするのが確実です。
レイアウト崩れの主な原因と再発防止策
KDPでのレイアウト崩れには、主に3つの原因があります。
1. **手動改行やスペースで整えている**
2. **画像の配置を「四角」や「前面」にしている**
3. **非対応フォント(日本語書体)を使用している**
1つ目の手動改行や空白スペースは、Wordでは整って見えても、KDP変換時にズレが生じやすいです。
段落設定や「改ページ挿入」を使って調整することで、どの端末でも安定したレイアウトになります。
2つ目の画像配置は、「行内」以外の設定だとKDPが正しく位置を認識できません。
画像を選択して「文字列の折り返し → 行内」に変更するだけで崩れが解消されることも多いです。
最後に、フォントについてです。
日本語フォントは端末に依存するため、特定のフォント(例:游明朝、メイリオなど)を指定しても反映されません。
KDPでは端末側のフォントに自動変換されるため、原則として「標準フォント」のままにしておきましょう。
「Wordで整って見える=KDPでも整う」わけではないという意識が大切です。
公式ヘルプでは明示されていませんが、実務的には「段落設定・見出し構造・行内画像」の3点を守るだけで、ほとんどの崩れは防げます。
再発防止のためには、テンプレート化しておくのが効果的です。
1冊目で整えた設定を保存しておけば、次回の原稿作成が格段にスムーズになります。
こうした小さな習慣の積み重ねが、出版後のクレームや修正版アップロードの手間を減らします。
出版前に一度立ち止まり、丁寧にチェックすることが、最も効率的な「時短術」と言えるでしょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
よくある失敗と対処法|初心者がつまずきやすいポイント
KDPでの出版作業はシンプルに見えますが、実際にやってみると意外なところでつまずく人が多いです。
特にWord原稿で整えたつもりが、KDPにアップロードすると「レイアウトが崩れた」「目次が動かない」「画像がズレた」といった問題が起こりがちです。
私自身も最初の出版時は、何度もプレビューを確認して修正を繰り返しました。
ここでは、初心者がよく陥る3つの失敗と、その具体的な対処法を紹介します。
実際のトラブルを想定しながら理解すると、次回以降の出版で同じミスを防げます。
空白や改行でレイアウトを整えてしまう
Word上で「見た目を整える」ために、スペースや改行キーを多用してしまうのは初心者が最もやりがちな失敗です。
たとえば、章の余白を広くしたいからといってEnterを何度も押したり、中央寄せをスペースで調整したりするケースです。
こうした手動整形はKDPでは崩れの原因になります。
なぜなら、Kindle端末では文字サイズや表示幅を読者が自由に変更できるため、手動で入れた空白や改行が意図しない位置にずれてしまうのです。
整形は「段落設定」で行うのが基本です。
余白を作りたいときは「段落後の間隔」を設定し、中央寄せは「段落の配置」機能を使いましょう。
この方法なら、KDPが構造として正しく認識し、どの端末でも整った見た目を保てます。
また、「空白を入れたら崩れた」ときは、非表示文字(Ctrl+Shift+8)を表示して確認すると原因が見つかりやすいです。
これは実務で非常に役立つ小技なので、覚えておくと便利です。
見出しスタイルを使わず、目次が機能しない
次に多いのが、見出しを単なる太字や大文字サイズで作ってしまうケースです。
Word上ではそれらしく見えますが、KDPは「スタイル設定」された見出しだけを目次として認識します。
つまり、「見出し1」「見出し2」などを適用していないと、KDP上で自動目次が生成されず、読者が章を移動できなくなってしまうのです。
目次がないと読者の離脱率が上がり、レビューにも影響する場合があります。
対処法は、Wordの「スタイル」機能で見出し構造を明確にすることです。
章タイトルには「見出し1」、小見出しには「見出し2」を設定しましょう。
そのうえで、Wordの「参考資料 → 目次 → 自動作成」を選ぶと、目次とリンクが自動で生成されます。
KDP公式ヘルプでもこの方法が推奨されていますが、実務上はWordでの設定だけでは不十分な場合もあります。
アップロード後、必ず「Kindle Previewer」でリンクが正しく動くか確認してください。
見た目では問題なくても、目次リンクが飛ばないケースは意外と多いです。
画像がズレる・文字が切れるトラブルの対処法
画像がKDP上でズレたり、テキストが画像に重なったりするトラブルも頻発します。
特に「四角」や「前面」「背面」などの配置を使っている場合、端末サイズに合わせて画像位置が変わってしまいます。
正しい設定は「文字列の折り返し → 行内」です。
この設定にすると、画像が本文の一部として認識され、KDPでの変換でも安定します。
また、「端末の高解像度化を踏まえ、長辺1600px以上を基準に。図版は可読性優先で適宜2000px超も検討。最終はPreviewerで実機相当確認。」「容量が大きいほど配信コスト(70%ロイヤリティ選択時)が増える可能性があります。画像圧縮と不要画像の削除で軽量化を。具体の容量上限や計算は公式ヘルプ要確認。」
画像の解像度が高すぎると、KDPのアップロード時にエラーが出たり、プレビュー表示が重くなったりします。
逆に低解像度だとぼやけるため、実際にスマホで確認して調整するのが確実です。
「KDPでは端末ごとに表示が異なる」という前提を忘れずに、どの環境でも破綻しない配置を意識しましょう。
特に縦長の端末では、画像の上下余白が想定より狭く見えることがあります。
気になる場合は、Word上で段落後に6ptほどの間隔を追加しておくと安定します。
もし画像の位置がどうしてもズレる場合は、「Kindle Create」で最終調整を行うのもおすすめです。
WordよりもKDP変換に近い見え方で確認でき、軽微な修正なら簡単に対応できます。
これら3つの失敗は、どれも「見た目で整える」ことが原因です。
KDPは構造を重視する仕様のため、Wordでも「構造的に整える」ことを意識すれば、ほとんどのトラブルは防げます。
最初は地味な作業に思えるかもしれませんが、出版後に修正申請するよりはるかに楽です。
細部の整形こそが、読者の読みやすさと信頼につながる部分です。
実践事例:Word設定を整えたら出版がスムーズになった話
Word原稿の設定を整えるだけで、KDP出版の手間は大きく減ります。
これは理論ではなく、実際に多くの著者が体感していることです。
私自身も最初の出版では何度も修正を繰り返しましたが、Word設定を正しく理解してからは、再出版までの流れが驚くほどスムーズになりました。
ここでは、そんな実体験をもとに「失敗からの改善」と「テンプレート化の効果」を紹介します。
同じ失敗を繰り返さないための具体的なヒントとして参考にしてください。
初出版で崩れた失敗例と、再出版での改善手順
初めての出版では、見た目を整えることばかりに気を取られていました。
章の間を広く見せるためにEnterを連打し、画像の位置を「前面」にして自由に動かしていたのです。
しかし、KDPにアップロードした瞬間、すべてが崩れました。
改ページがずれ、画像は文字に重なり、目次リンクも反応しない状態でした。
当時は焦りましたが、原因を一つひとつ調べていくうちに、「Word上での見た目」と「KDPが認識する構造」は別物だと気づきました。
つまり、装飾ではなく構造を正しく設定する必要があったのです。
改善手順として取り組んだのは、以下の5つです。
1. 見出しスタイルを「見出し1・2」で統一
2. 改ページをEnterではなく「Ctrl+Enter」で固定
3. 画像の配置を「行内」に変更
4. 段落設定で行間・余白を整える
5. Kindle Previewerで端末ごとの確認
これらを実践すると、同じ原稿でも見違えるほど安定しました。
再出版後は、すべての端末でレイアウトが揃い、読者からも「読みやすい」とのレビューが増えました。
特に印象的だったのは、「Ctrl+Enter」ひとつで改ページが完全に安定したことです。
小さな工夫ですが、可変レイアウトでは絶大な効果があります。
Word設定の基本を押さえることが、スムーズな出版の第一歩だと痛感しました。
テンプレート化のメリット:2冊目からの時短効果
2冊目を執筆したとき、最初に作成したWord原稿をテンプレートとして再利用しました。
章構成やスタイル設定をそのまま流用できたことで、執筆作業の半分以上を省略できました。
このテンプレート化は、思っている以上に効率的です。
新しい原稿では、文章を差し替えるだけで構造が崩れず、プレビュー確認も最小限で済みました。
結果として、1冊目にかかった修正時間の約3分の1で出版まで到達できました。
また、テンプレートを使うと、誤設定による崩れやエラーがほぼ発生しなくなります。
特にKDPはバージョンアップのたびに細かい仕様変更がありますが、テンプレートをベースにしておけば、その影響を最小限に抑えられます。
テンプレート化のコツは、「完成原稿を再利用する」ことです。
Wordの「名前を付けて保存」で別名テンプレートを作り、見出し構造や段落設定を残したまま本文だけ削除しておきます。
この方法なら、次回以降の原稿作成が驚くほどスムーズになります。
出版を重ねるたびに「設定の手間が減る」だけでなく、「本づくりの精度」が上がっていくのも大きなメリットです。
Word設定をテンプレート化しておくことは、作業効率だけでなく、長期的な品質管理の面でも非常に効果的です。
最初は時間がかかっても、正しい設定を身につけておくことで、次の出版が一気に楽になります。
それが結果的に、継続的な出版活動を支える“基盤”になるのです。
ペーパーバック出版でWord原稿を活用する場合の補足
KDPでは電子書籍だけでなく、紙の本(ペーパーバック)も同じ原稿から出版できます。
ただし、Wordファイルをそのまま流用する際には、電子書籍とは異なる注意点があります。
特にページ数・余白・画像解像度・版面設計の4つを意識することが重要です。
電子書籍では可変レイアウト(文字サイズを変更できる形式)ですが、ペーパーバックは固定レイアウトです。
つまり、Word上の1ページ=印刷時の1ページとなるため、配置の正確さが求められます。
ここでは、よく質問される「24ページ以上の制限」と「版面設計の違い」について解説します。
24ページ以上が必要な理由と余白設定の注意点
KDPのペーパーバックには「24ページ以上でないと出版できない」という規定があります。
「これはKDPの印刷・製本仕様による最低ページ数要件です。背表紙の有無は紙厚やページ数に依存し、24ページ前後では背表紙なしになることがあります。」
本文だけでなくタイトルページや奥付もページ数に含まれるので、実際には原稿本文が20ページ程度でも問題ありません。
Wordで作成する際は、まずA5やB6など希望サイズに合わせてページ設定を行いましょう。
「レイアウト → 余白 → ユーザー設定の余白」で上下左右のバランスを整えます。
印刷では端まで文字を配置すると切れてしまうため、上下20mm、左右15mm以上の余白を確保しておくのが安全です。
また、ページ数が偶数で終わるように調整しておくと、印刷時のバランスが良くなります。
章ごとに必ず改ページを挿入(Ctrl+Enter)し、ページの途中で章が切れないようにするのもポイントです。
公式ヘルプにも余白基準は記載されていますが、実際には画像や脚注を多用する場合、少し広めに取ったほうが見やすく仕上がります。
印刷前に「印刷プレビュー」で確認しておくと安心です。
電子書籍との違い:改ページ・解像度・版面設計
電子書籍とペーパーバックでは、同じWord原稿でも設定の目的が異なります。
電子書籍は「端末で読みやすいレイアウト」、ペーパーバックは「紙で見やすいレイアウト」です。
電子版では改ページを細かく入れる必要はありませんが、紙版では章や節の区切りを明確にするために必須です。
改ページを忘れると、印刷時に中途半端な位置で章が始まってしまいます。
そのため、章タイトルの直前で必ず「Ctrl+Enter」でページを切り替えましょう。
次に画像です。
「電子書籍では解像度よりピクセル寸法が実用的指標です。長辺はおおむね1600px以上を目安にし、実機表示はKindle Previewerで確認。印刷(ペーパーバック)は300dpi推奨。」。
特に写真や図版を多く含む書籍では、低解像度だとぼやけて見えるため注意してください。
版面設計(本文領域の設定)も大きな違いです。
電子書籍は可変表示なので端末ごとに自動調整されますが、ペーパーバックでは版面サイズを自分で決める必要があります。
Wordでは「レイアウト → 余白 → ユーザー設定」で上下左右を調整し、1ページの行数や文字数を固定すると印刷品質が安定します。
最初は手間に感じるかもしれませんが、電子版と紙版を両立させると販売ページの信頼性がぐっと上がります。
「電子+紙セット」で購入されるケースも多く、収益面でも有利になるでしょう。
まとめ|Word設定を整えれば誰でもKindle出版できる
Word設定を理解しておけば、初めての出版でも迷わず進められます。
「書く」だけでなく「整える」工程が、読者に届く品質を決めるポイントです。
ここでは、出版前の最終確認と、継続的に出版するためのスキルアップの方向性をまとめます。
失敗しない3つの最終チェックポイント
出版前に確認すべきチェック項目は、次の3つです。
1. **ファイル形式が「.docx」になっているか**
2. **Kindle Previewerで目次・改ページ・画像を確認したか**
3. **余白・段落・スタイル設定を正しく整えたか**
これらを丁寧に見直すだけで、KDPでのトラブルはほとんど防げます。
特にプレビュー確認を省略しないことが大切です。
Wordで完璧に見えても、Kindle端末では崩れることがあります。
もし時間がないときでも、目次リンクと章タイトルだけは必ずチェックしましょう。
読者がページ移動で迷わない構成になっているかどうかは、満足度に直結します。
また、ペーパーバックを併用する場合は、余白とページ数の再確認を忘れずに。
たった数分の確認で、再提出の手間を大幅に省けます。
Word整形スキルを身につけると出版が加速する理由
Word整形のスキルを習得すると、出版のスピードと品質が一気に上がります。
1冊目は設定に時間がかかっても、2冊目以降はテンプレート化で効率化できます。
また、Wordの整形スキルはKDP以外の場面でも活かせます。
たとえば電子教材やPDF販売、noteやブログ記事のデザイン調整にも応用できます。
文章構造を意識する力がつくため、ライティング全体の質も向上します。
出版を継続するうえで重要なのは、「書く力」よりも「仕組み化の力」です。
Word設定をテンプレート化し、ミスの少ない作業環境を整えることが、安定した出版活動につながります。
Wordを使いこなせば、誰でもKindle出版の土台を築ける。
最初の1冊でつまずいても大丈夫です。
設定を理解すれば、次の1冊はもっと早く、もっと美しく仕上がります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。