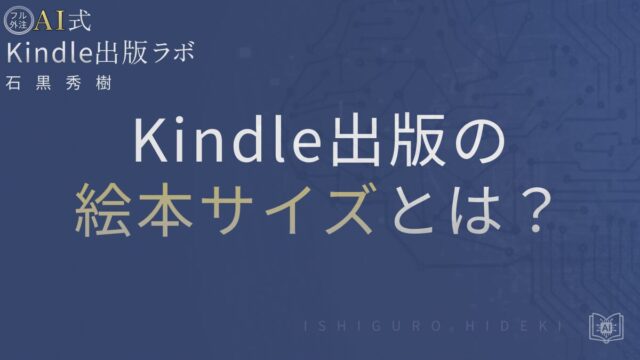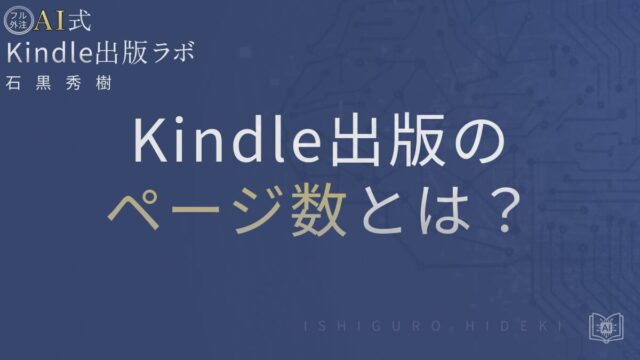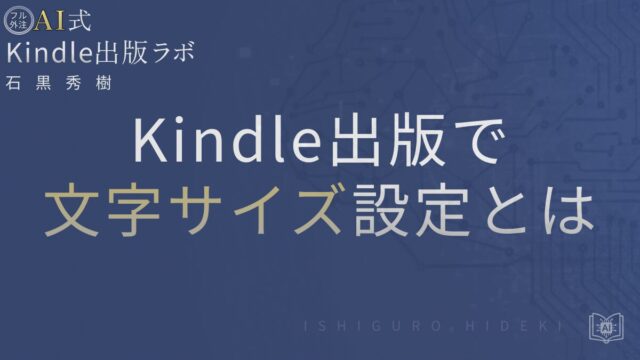Kindle出版のコミュニティ運営&サポート歴5年。
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版に取り組もうとしても、「章立てが決まらず、本文が一文字も進まない」という相談は非常によくあります。
実際、私も初めてKDPで出版したときは、構成が固まらずにWordを開いては閉じる日々が続きました。
では、どうすれば構成を迷わず固められるのでしょうか。
この記事では、Kindle出版(日本向け/Amazon.co.jp前提)における「構成=章立て+目次」の考え方を初心者にもわかりやすく解説します。
「HTML目次」や「論理目次(NCX)」といった専門用語にも触れつつ、実務ベースで理解できるように整理していきます。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の構成とは?章立てと目次の基本
Kindle出版における構成とは、単に「章が並んでいること」ではありません。
読者がスムーズに本を読み進められるよう、章立てと目次を連動させた設計が必要です。
ここでは、構成の全体像とAmazon.co.jpで求められる前提を理解することが第一ステップとなります。
Kindle出版全体のステップをあらかじめ押さえておきたい方は『 Kindle出版の始め方とは?初心者向けに全体の流れを徹底解説 』もあわせて読んでみてください。
Kindle出版の構成=章立て+HTML目次+論理目次(NCX)の設計
Kindle出版の構成は「章立て」だけではなく、「HTML目次」と「論理目次(NCX)」も含めた三つの要素で成り立っています。
章立ては、本の内容をどの順番で展開するかを決める骨組みです。
HTML目次は、読者が最初に目にする「本文内の目次」であり、クリック/タップで各章に飛べるようにリンクを設定します。
論理目次(NCX)は、Kindle端末やアプリの「目次メニュー」から章に移動できるようにするための内部構造です。
この論理目次は、適切な見出し階層(Wordの「見出し1」「見出し2」など)を設定することで自動的に生成されるケースが多いですが、レイアウトや形式によってはKDP審査で指摘されることもあります。
「とりあえず文章を書いてから目次を作る」という流れだと、論理目次が崩れやすく、審査で修正依頼が来るリスクがあります。
初心者は「構成→章立て→見出し設定→目次→本文」という順番を意識することが重要です。
Amazon.co.jp前提で押さえる用語と違い(電子書籍中心・紙は補足)
Kindle出版は「電子書籍(リフロー型)を前提とする」場合が多いため、紙の雑誌や固定レイアウトとは構成の考え方が異なります。
電子書籍では、読者がスマホで読むことを想定し、1章の文字量を詰め込みすぎない、見出しを細かく区切る、といった可読性の工夫が求められます。
一方、ペーパーバックを併売する場合は、KDPの仕様上「総ページ数や本文サイズによる制限」が加わり、「最低24ページ以上」などの条件が存在します(最新の数値は公式ヘルプで要確認)。
ただし、電子書籍版を先に設計しておけば、その章立てをベースに紙版へ調整しやすくなります。
海外市場向けのKDPでは仕様が異なる場合がありますが、日本向けに出版する場合はAmazon.co.jpのガイドラインを最優先にするのが安全です。
このように、日本向けKindle出版では「電子書籍の構成ルール」を理解した上で、必要に応じて紙版を補足的に考える流れが一般的です。
まず決めるべき全体アウトライン(雛形付き)
Kindle出版に取り組むとき、最初にやるべきことは「全体の流れ=アウトライン」を固めることです。
ここが曖昧なまま文章を書き始めると、途中で話がズレたり、必要な章が欠けたりして書き直しが発生します。
私自身も最初の出版では構成の迷走によって、完成までに倍近い時間をかけてしまった経験があります。
その一方で、あらかじめ仮の章立てを作っておくと、本文の執筆スピードが格段に上がります。
この段階では100%完成度の高いものでなくても構いませんが、「どんな順番で話を展開するのか」の流れは明確にしておきましょう。
Kindleでは、はじめに(導入)→本編→まとめ(おわりに)→巻末情報という流れが基本形となります。
このベース型を理解してから目的別に調整することで、構成の迷走を防ぎやすくなります。
構成は書きながら考えるのではなく、書く前に“道筋”として決めておくことがコツです。
構成づくりと併せて出版前のチェックポイントも整理しておきたい場合は『 Kindle出版の準備とは?審査落ちを防ぐ手順とチェックポイントを徹底解説 』を参考にしてみてください。
基本型:はじめに/本編3章/おわりに/巻末情報(著者・参考文献)
Kindle出版の初心者がまず押さえるべき基本構成は以下のようになります。
・はじめに(読者の悩み・読むメリットを提示)
・本編(3章をベースに展開)
・おわりに(まとめ・次の行動を促す)
・巻末情報(著者プロフィール/参考文献など)
この4パート構成は、ほとんどのジャンルに応用が可能です。
特に「本編3章」は「序盤:課題理解/中盤:解決策の展開/終盤:実践方法・応用」といった流れに当てはめやすく、読者の理解負荷も大きく下がります。
「はじめに」は意外と軽視されがちですが、ここで「なぜ読む必要があるのか」を明確にしないと、読者が途中で離脱してしまう原因になります。
「おわりに」では感情的なまとめや振り返りを入れることで、読後感を整える効果があります。
巻末情報には著者プロフィールや参考文献を記載します。
Kindleでは著者情報が信頼性につながる場合があり、実体験や実績がある場合は簡潔に記載することをおすすめします。
目的別テンプレ:ノウハウ本/体験記/解説書の章立て例
書籍のジャンルによって最適な章構成は少しずつ異なります。
目的に応じたテンプレートを使うと、より読者にとって読みやすい流れになります。
▼ノウハウ本(例:〇〇のやり方を教える)
・はじめに(悩み→解決策の提示)
・第1章:基本知識
・第2章:具体的な手順(ステップ形式)
・第3章:応用・継続のコツ
・おわりに→行動の促し
▼体験記形式(例:失敗→成功→学び)
・はじめに(経験の背景)
・第1章:過去の失敗と気づき
・第2章:成功への過程
・第3章:再現性のある学びと提言
・おわりに→読者へのエール
▼解説書・教材形式(深く理解させる構成)
・はじめに(基礎テーマの導入)
・第1章:概念・仕組み
・第2章:具体例・図解
・第3章:ケーススタディ・応用パターン
・おわりに→理解の確認
これらのテンプレートを参考にしつつ、自分のテーマに合わせて章数や順番を微調整してください。
テンプレートは「そのまま使うもの」ではなく、「迷走を防ぐための出発点」として活用するのがポイントです。
経験上、最初からオリジナル構成を作ろうとすると行き詰まりやすいため、まずはテンプレに乗せて考えたうえで必要に応じて削る・追加する流れがおすすめです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
目次の作り方(Word中心)と「リンクで飛べる」確認手順
Kindle出版では、構成を組んだあとに必ず「目次」を作ります。
ただし、Wordで文字を並べただけでは目次として機能せず、KDPの審査で差し戻されることもあります。
KDPで必須なのは論理目次です。本文内のHTML目次は推奨度が高いものの必須とは限りません(公式ヘルプ要確認)。
目次まわりの要件を含め、審査でチェックされやすいポイントは『 Kindle出版の規約とは?審査通過のポイントと違反回避を徹底解説 』でまとめて確認しておくと安心です。
この章ではWordを使った実務的な作成手順と、最終的に「リンクで飛べるか?」を確認する方法まで解説します。
私自身、初めての出版ではリンクが飛ばず、KDPから修正依頼が来たことがあるので、この工程は丁寧に進めることをおすすめします。
「見出し→自動目次→リンク確認」の流れを正しく行うことが、Kindle書籍の信頼性につながります。
Wordで見出しスタイルを設定→自動目次を作成(見出し1〜3の使い分け)
Wordで目次を作る前に、まずは各章・節・小見出しに「見出しスタイル」を適用します。
基本的には以下のような使い分けが一般的です。
・見出し1:章タイトル(第1章、第2章など)
・見出し2:章内の小見出し
・見出し3:さらに細分化が必要な場合の補足見出し
Wordの「ホーム」タブにある「見出し1」「見出し2」などをクリックするだけで適用できます。
この工程を省いて手動で太字にしたり大きな文字に変更しても、Kindle側では見出しとして認識されません。
見出しスタイルを適用したら、「参考資料」タブから「自動目次」を挿入すると、Wordが見出し階層に基づいて目次を生成します。
ここで章が抜けていたり小見出しが認識されていない場合は、見出しスタイルの付け忘れがないか見直しましょう。
見出しの調整が必要な場合は、目次を右クリックして「フィールドの更新」または「目次の更新」を行うことで修正が反映されます。
HTML目次(本文冒頭)を配置し、章へジャンプできるか検証
HTML目次とは、本文の冒頭または序文の直後に配置する「読者が最初に確認できる目次」です。
ここでは「第〇章」などの章タイトルをタップすると、その章にジャンプできるようになっている必要があります。
Wordの自動目次をそのまま本文の冒頭に配置すれば、基本的にリンクが設定されます。
ただし、改ページやテンプレートの設定によってリンクが無効になる点には注意が必要です。
KDPで公開する前に、Word上またはKindleプレビューアを使って「章タイトルをタップしたときに該当ページへ移動するか」を必ず確認してください。
KindleプレビューアはAmazon公式の無料ツールであり、実際のKindle端末に近い動作環境で確認できるため信頼性が高いです。
リンクが飛ばない状態で公開すると、読者が不便なだけでなく低評価につながる可能性があります。
論理目次(NCX)の考え方と必須要件【公式ヘルプ要確認】
論理目次(NCXまたはEPUB3の
電子書籍と紙版の違いを踏まえた原稿レイアウトの考え方については『 Kindle出版の原稿サイズとは?Word設定とレイアウト崩れを防ぐ基本を徹底解説 』もあわせてチェックしてみてください。
───
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AIと外注で“自分が作業しなくても印税を稼げる仕組み”を手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料プレゼント中📘

📱
最新の出版ノウハウをLINEで配信中!
AI×外注で出版したい方向けに、
限定動画や実践マニュアルも公開しています。