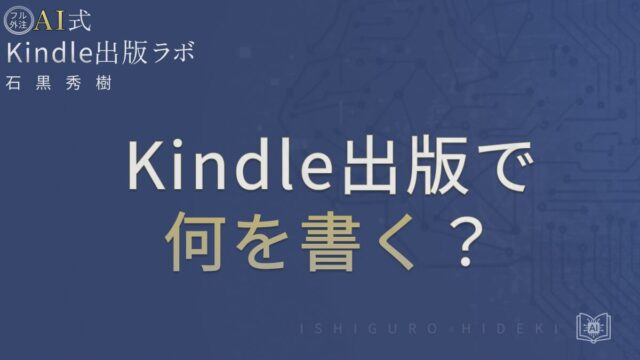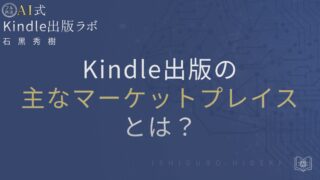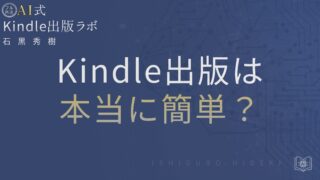Kindle出版のカテゴリーとは?選び方・設定手順・注意点を徹底解説
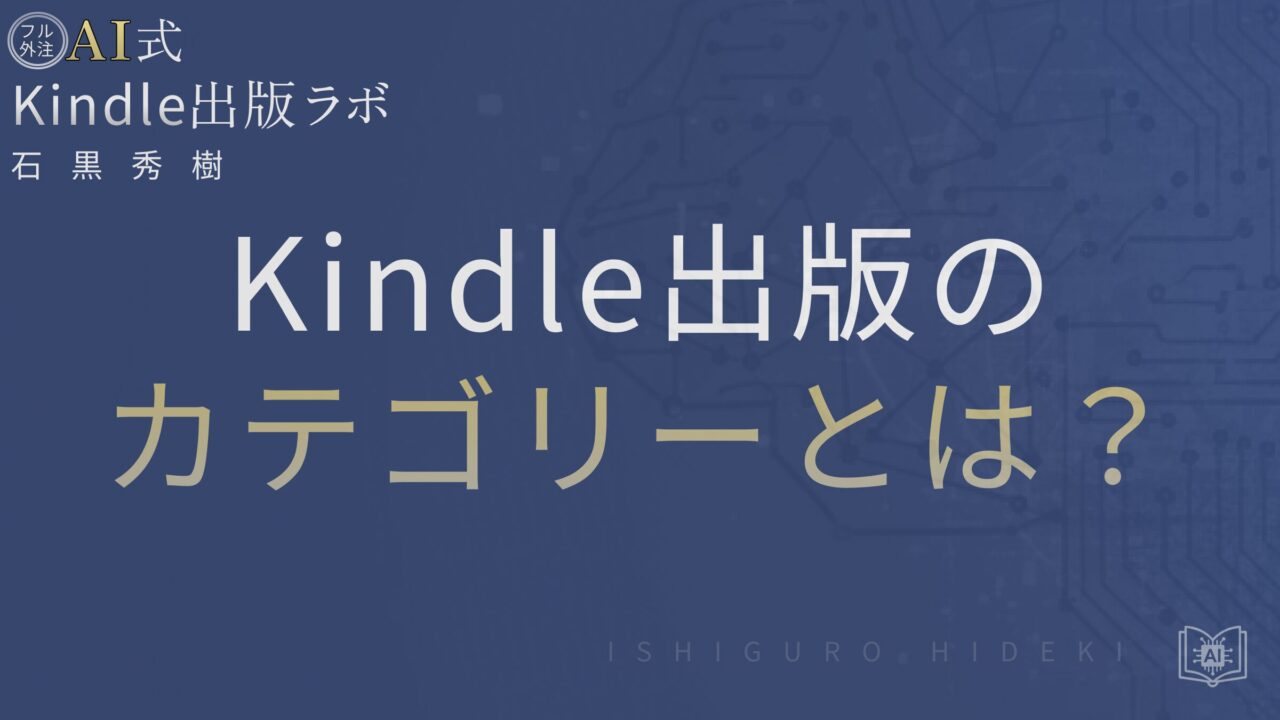
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版では、タイトルや表紙と同じくらい重要なのが「カテゴリー設定」です。
カテゴリーを適切に設定することで、読者に本を見つけてもらいやすくなり、ランキングの表示位置にも影響します。
一方で、KDPの管理画面やAmazonの構造は初見ではわかりづらく、ジャンルやキーワードとの違いも混同しやすいポイントです。 特に日本仕様のカテゴリー構造は米国と微妙に異なるため、海外記事をそのまま参考にすると誤解が生じやすい点にも注意が必要です。
この記事では、日本のAmazon.co.jpを前提に、「カテゴリー」の基本的な考え方と構造を初心者向けにわかりやすく解説します。
私自身も最初はジャンルやキーワードと混同して迷いましたが、一度理解してしまえば設定はシンプルです。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 人気ジャンルや成功事例を参考にしたい方はこちらからチェックできます:
出版ジャンル・成功事例 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の「カテゴリー」とは?日本仕様の基本と考え方
目次
カテゴリー設定は、出版する電子書籍を「どの棚に置くか」を決める非常に重要な要素です。
ここを曖昧なままにしてしまうと、意図しない読者層に表示されたり、ランキングにうまく乗らないという問題が起きやすくなります。
カテゴリーの意味|読者が探す棚とランキング枠のこと
Amazonにおける「カテゴリー」は、書店でいう「棚」のような役割を持っています。
ジャンルやテーマごとに細かく分類されており、読者はこの「棚」をたどって本を探したり、ランキングをチェックしたりします。
KDPの出版時には、このカテゴリーを選ぶことで、Amazon内での本の表示位置とランキングの対象枠が決まる仕組みになっています。
つまり、「どの棚に置くか」を戦略的に選ぶことが、露出と販売の両面でとても重要なのです。
よくある失敗として、「とりあえずなんとなく近そうなカテゴリを選ぶ」というケースがあります。
すると、意図した読者層に届かず、ランキングにも埋もれてしまう可能性があります。
ジャンル・キーワード・カテゴリの違いを整理(Kindle出版 カテゴリー 基本)
ここで混同されがちなのが、「ジャンル」「キーワード」「カテゴリー」の3つです。
名前が似ているため、最初は違いがわかりづらいですが、それぞれ役割が明確に異なります。
* **ジャンル**:書籍全体の方向性やテーマ(例:ビジネス、恋愛、自己啓発など)
* **キーワード**:検索結果に影響する補助的なワード。読者が検索バーに入力する語句に対応
* **カテゴリー**:Amazonの内部構造上の分類(棚)。ランキングと表示場所を決める軸
特に、カテゴリーはKDPの出版画面で指定する項目で、最終的な表示位置やランキング枠に直結します。
一方で、キーワードはSEO(検索最適化)的な補完要素として機能します。
公式ガイドラインでも、この3つは別々に設定するよう明記されていますが、実務上はジャンルとカテゴリーを混同して選んでしまう人が多いです。 カテゴリーは「露出枠の選定」、キーワードは「検索補助」と割り切るとわかりやすいでしょう。
具体的な設定手順と注意点は『Kindle出版のキーワード設定とは?売れる電子書籍に変わる実践ガイド』で詳しく解説しています。
Amazon.co.jp前提でのカテゴリ構造の特徴(日本向け)
Amazon.co.jpのカテゴリー構造は、米国のAmazon.comと細部が異なります。
日本では一部のサブカテゴリが存在しなかったり、分類の深さが違うケースがあるため、海外向けの解説をそのまま参考にすると齟齬が生じやすいです。
例えば、米国では「Kindleストア → Fiction → Romance → Subgenre…」と細かく階層が分かれていますが、日本では中間階層が存在しないカテゴリもあります。
このため、実際のKDP出版画面で見えるカテゴリと、Amazonの読者向けサイト上で表示されるカテゴリ構造が必ずしも一致しないこともあります。
KDPの管理画面で選択できるカテゴリー数は画面仕様に依存します(過去の変更例あり)。
現行仕様は管理画面の表示に従い、必要に応じて公式ヘルプ要確認としてください。
出版後に「思っていた棚と違う」と感じる場合は、KDPサポートに問い合わせることで表示カテゴリの変更が可能な場合もあります。
私も最初は米国の解説記事を見てカテゴリを設定しましたが、日本では同じ階層が存在せず、意図と違う場所に本が掲載されてしまったことがありました。
公式ヘルプや日本版Amazonの実際の書籍ページを参考にして設定するのが確実です。
Kindle出版のカテゴリー選び方|露出を高める基準
カテゴリーの選び方は、Kindle出版における「戦略の核」といっても過言ではありません。
どの棚(カテゴリー)に本を置くかによって、読者の目に触れる機会やランキングへの露出が大きく変わります。
単に内容に合っているカテゴリを選ぶだけでは不十分で、読者の検索行動や競合状況も考慮する必要があります。
私自身も最初の頃は内容だけで選んでいましたが、上位表示されず埋もれてしまったことがありました。 「適合・需要・競合」の3つの軸で冷静に判断することが、露出を最大化する近道です。
内容適合×読者意図×競合強度で絞る(選び方のフレーム)
まず大前提として、カテゴリーは本の「内容」に合致していることが必要です。
これはKDPの規約でも明記されており、意図的に不適切なカテゴリを設定することは禁止されています。
ただし、内容が合っていれば何でも良いというわけではありません。
露出を増やしたいなら、次の3軸を意識して絞り込むと効果的です。
1. **内容適合**:本の主題・テーマに合っているか
2. **読者意図**:そのカテゴリに本を探しに来る読者層と一致しているか
3. **競合強度**:同カテゴリ内の競合数・上位本の強さ
特に「読者意図」は見落とされがちです。
例えば「ビジネス」カテゴリの中でも、自己啓発寄りの本と実務書では読者層が異なります。
自分の本を誰に届けたいのかを明確にしてから、カテゴリを絞りましょう。
競合強度は、Amazonのランキングをチェックすればある程度把握できます。
上位にベストセラーや有名著者の本が並んでいるカテゴリは、初心者がいきなり上位に食い込むのは難しいです。
逆に、少しニッチなカテゴリを選べばランキング上位に入りやすく、初期の露出を確保できます。
需要調査と設計の進め方は『Kindle出版のSEOとは?タイトルとキーワード設計を徹底解説』を参照してください。
大カテゴリ/中カテゴリ/小カテゴリの使い分け(穴狙いと適合のバランス)
Amazonのカテゴリーは、大カテゴリ→中カテゴリ→小カテゴリと階層構造になっています。
例えば「Kindle本 > ビジネス・経済 > 自己啓発」のように、段階的に絞り込まれていきます。
ここでのポイントは、「大カテゴリは内容の軸、中カテゴリ・小カテゴリは露出戦略」と捉えることです。
大カテゴリで本の方向性をしっかり合わせつつ、小カテゴリで競合が少ない“穴”を狙うと、ランキングに乗りやすくなります。
例えば、同じ「自己啓発」でも、中カテゴリで「モチベーション」よりも「時間管理」の方が競合が少ない場合、後者を選ぶと露出のチャンスが広がります。
ただし、あくまで内容との整合性が最優先であり、ランキングだけを狙って不適切なカテゴリを選ぶのは規約違反になるため注意してください。
小カテゴリで“適合かつ競合が緩い場所”を見つけることが、初心者が最短で露出を取るコツです。
これは経験を積むと直感的に見極められるようになりますが、最初はランキングや実際の書籍例を見て判断するのが確実です。
禁止・制限ジャンルの抽象表現と留意点(KDP規約要確認)
KDPでは、特定のジャンルや内容に対してカテゴリー選択時に注意が必要なケースがあります。
具体的な表現は避けますが、性的描写や暴力描写など、Amazonのポリシー上で制限や注意が求められるジャンルがあるためです。
これらのジャンルでは、カテゴリー選択やキーワードの設定を誤ると、審査で差し戻しや販売制限がかかる可能性があります。
公式ガイドラインで明記されている部分もありますが、実務上は曖昧な判断が求められるケースもあるため、慎重な設定が必要です。
特に「グレーゾーン」とされる表現は、公式ヘルプを確認しつつ、カテゴリー名や説明文に直接的な表現を入れないようにしましょう。
私も過去に、カテゴリーとキーワードの組み合わせが原因で審査に時間がかかったことがあります。
このようなジャンルを扱う場合は、必ずKDPの最新ガイドラインを確認し、不明点はKDPサポートに問い合わせるのが安全です。
曖昧なまま進めると、後から非表示や削除になるリスクがあります。
審査の基準と差し戻し回避の要点は『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』にまとめています。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
KDPでカテゴリーを設定する手順(Amazon.co.jp 前提)
カテゴリー設定は、出版後に本がどの棚に並び、どんな読者に届くかを左右する重要なステップです。
ここを曖昧にしたまま進めると、読者の目に触れにくい位置に表示されたり、規約違反として差し戻されることもあります。
特に初心者の方は、「とりあえず近そうなカテゴリを選んでおけばいい」と思いがちですが、それでは露出が最適化されません。 KDPの管理画面の手順とAmazon.co.jpのカテゴリ構造を理解したうえで、丁寧に設定することが成功の第一歩です。
「本の詳細」からカテゴリ選択までの流れ(KDP 設定 手順)
まず、KDPの「本棚(Bookshelf)」にアクセスし、該当する書籍の「コンテンツを編集」をクリックします。
ここから「本の詳細」タブに移動し、書籍タイトルや著者名などの基本情報を入力する画面に進みます。
画面を少しスクロールすると、「カテゴリー(ジャンル)」という項目があります。
ここで、Amazonのカテゴリツリーに沿って、該当するカテゴリーを選択します。
たとえば「Kindle本 > ビジネス・経済 > 自己啓発」のように、階層構造で大カテゴリから順に選んでいく形式です。
このとき、内容と明確に一致するカテゴリを選ぶことが基本です。
ランキング目的で無関係なカテゴリを選ぶと、公開保留・修正依頼・表示制限の対象となる場合があります(公式ヘルプ要確認)。
実務上も、一度公開後にカテゴリを修正するのは手間がかかるため、最初にしっかり設定しておきましょう。
主マーケットを日本にし、関連カテゴリを最大3つ選ぶ
次に重要なのが、主マーケット(Primary Marketplace)の設定です。
主マーケットは価格の基準通貨を決める設定です。
カテゴリ表示の構造そのものを直接変更する項目ではありません。
日本向けの価格管理をしやすくするために『Amazon.co.jp』を主マーケットにするのが実務上は無難ですが、カテゴリの整合性は別途、選択したカテゴリ名と実際の棚構造で確認してください。
カテゴリーは**管理画面で選択可能な上限(例:最大3つ)**まで設定できます。
仕様は更新されることがあるため、最新の管理画面表示と公式ヘルプを必ず確認してください。
このとき、「1つはメインとなる内容カテゴリ」「残りは関連性の高い補助カテゴリ」というバランスで選ぶのがおすすめです。
例えば、自己啓発書の場合、「ビジネス・経済 > 自己啓発」をメインにし、「趣味・実用」や「教育・学参」など近接ジャンルを補助として選ぶと、露出の幅が広がります。
全カテゴリを同ジャンルで固めるより、内容と整合性のある周辺ジャンルを組み合わせることで、表示機会が増えるのがポイントです。
公開前チェックリスト:適合性・重複・表示名の最終確認
設定が完了したら、公開前に以下の3点をチェックしておきましょう。
1. **内容との適合性**:本の主題とカテゴリがずれていないか
2. **カテゴリの重複**:同じ系統を重複選択していないか
3. **表示名の確認**:Amazon上で実際にどう表示されるかを事前に確認
特に3つ目は見落としがちです。
KDP上の名称と、実際のAmazonサイト上のカテゴリ名が微妙に異なるケースがあるため、事前にAmazon.co.jpで似た本を検索して、どの棚に表示されているかを確認すると安心です。
私も最初の頃、カテゴリ名の微妙な違いを見落とし、思っていた棚と違う場所に表示されてしまったことがあります。
公式では設定後に修正可能とされていますが、実務的には反映までに時間がかかるため、事前確認が重要です。
これらをきちんと押さえておけば、出版後に「どこに表示されているのかわからない」といったトラブルを防ぎ、スムーズな販売開始ができます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
ありがちな失敗とKDP規約の観点(差し戻し・露出低下を防ぐ)
カテゴリー設定は一見シンプルに見えますが、実は露出・販売機会・審査通過率に直結する非常に重要な要素です。
公式の仕様を理解しないまま、他の記事を参考に自己流で設定すると、思わぬ形で「差し戻し」や「表示の埋没」を招くケースがあります。
ここでは、初心者がやってしまいがちな3つの失敗と、それがなぜ問題になるのかをKDP規約の観点から解説します。
筆者自身も最初の頃にこのあたりで手戻りを経験したことがあるので、ぜひチェックリスト的に確認してみてください。
米国記事のカテゴリ名を流用して不一致になる
もっともよくあるのが、米国向けのKDP解説記事やテンプレートをそのまま参考にしてしまい、Amazon.co.jpのカテゴリ構造と不一致になるケースです。
例えば、「Kindle eBooks → Health, Fitness & Dieting → Self-Help」のような米国のカテゴリ名を見て、そのまま日本版KDPに入力しようとすると、該当カテゴリが存在しない、あるいは位置が違うといったズレが発生します。
Amazon.co.jpは、米国とカテゴリ階層・表示名が一部異なる場合があります。
同一名のサブカテゴリが存在しないこともあるため、日本の実際の書籍ページで棚を確認してから選定するのが安全です。
実務的には、**実際のAmazon.co.jpで似た本を検索し、どのカテゴリに属しているかを確認してから設定**するのが一番確実です。
私自身も、初期の頃は米国ブログを見てカテゴリを設定し、審査時に差し戻しになった経験があります。 カテゴリは“日本の棚構造”に合わせて選ぶという基本を押さえておきましょう。
小カテゴリ過信で需要が薄く、露出が伸びない
次によくあるのが、「競合が少ないから」という理由だけで極端に細かい小カテゴリに設定してしまうパターンです。
確かに、小カテゴリに入るとランキング上位が狙いやすく見えるのですが、実際にはそのカテゴリ自体の閲覧数・購買数が少なく、露出がほとんど伸びないケースが多々あります。
たとえば「ビジネス・経済 > 自己啓発 > ごく一部の細分化されたテーマ」といった場所を狙うと、一時的にランキング1位になっても、アクセスがほとんど増えないことがあります。
カテゴリ選びは「競合の少なさ」だけでなく、「読者が実際に探している棚かどうか」で判断するのがポイントです。
上位表示を狙うなら、中カテゴリ以上で露出を確保しつつ、小カテゴリは補助的に活用するのが実務的です。
内容と合わないカテゴリで通報・評価低下リスク(公式ヘルプ要確認)
最後に注意すべきは、内容とカテゴリが一致していない場合のリスクです。
KDPでは明示的に「本の内容とカテゴリは一致していなければならない」と定められており、これに反すると出版差し戻しや修正指示の対象になります。
さらに、読者側からの「内容とカテゴリが違う」という通報や低評価レビューがつくと、販売ページの評価や露出にも悪影響が出る可能性があります。
特に、販売数を増やしたいからといって人気ジャンルに無理やり入れるような設定は避けましょう。
例えば、実用書を「恋愛・エンタメ系」のカテゴリに入れるなどは規約違反の対象になりやすいです。
KDPの公式ヘルプでも、禁止・制限ジャンルやカテゴリ選定のルールが細かく定められています。
不確かな点は自己判断せず、必ずKDP公式ヘルプを確認することが重要です。
この3つの失敗は、いずれも「よかれと思ってやった」結果起こるケースばかりです。
最初に正しい知識を押さえておけば、防げるものなので、出版前に一度チェックしておきましょう。
事例で学ぶ:ジャンル別のおすすめカテゴリ候補
ジャンルごとに適したカテゴリを選ぶことで、読者とのマッチ度が上がり、ランキングや露出機会も大きく変わります。
ここでは、実際の出版現場でもよく使われるカテゴリの傾向と、初心者がつまずきやすいミスマッチ例を交えながら解説します。
ビジネス・自己啓発系の定番と避けたいミスマッチ
ビジネス・自己啓発ジャンルでは、「ビジネス・経済」配下のカテゴリが基本軸になります。
特に「ビジネス・経済 > 自己啓発」は多くの著者が選ぶ定番です。
さらに内容によっては「ビジネス・経済 > マネジメント・人材管理」や「キャリア・転職」と組み合わせると、より内容に即した配置が可能です。
実務的には、テーマが『個人の働き方・マインド』寄りなら自己啓発系、『組織運営・経営』寄りならマネジメント/経営のカテゴリが内容適合の観点で妥当です。
最終判断は実際の棚構造と近い競合書籍の配置で確認してください。
ここを曖昧にすると、レビューで「カテゴリが違う」と指摘されるケースもあります。
注意したいのは、モチベーション系やライフストーリー系の本を「文学・評論」などに入れてしまうケースです。 ビジネス書なのに文学カテゴリに分類されると、ランキングも露出の枠もまったく異なるため、読者との接点が減ってしまいます。
米国記事のカテゴリ名をそのまま参考にして設定するのも、このジャンルで特に多いミスです。
実用・ハウツー(ライフハック・家計・学習)の効果的な組み合わせ
実用・ハウツー系の本は、単一カテゴリよりも「内容 × 目的」で2〜3カテゴリを組み合わせると効果的です。
例えば、家計・節約系なら「実用・暮らし > 家計・節約」と「ビジネス・経済 > 投資・マネー」を併用すると、読者層の広がりが期待できます。
ライフハックや時間術などの場合は、「実用・暮らし > 生活の知恵」と「自己啓発」を組み合わせると、モチベーション層にも検索されやすくなります。
また、学習系の内容(英語、資格、スキル習得など)は「語学・学習参考書」の中カテゴリを使うとマッチしやすいです。
このジャンルではカテゴリの粒度が細かいので、Amazon上で似た本を調べ、実際にどの棚に配置されているかを確認することが非常に有効です。
ありがちなミスは、広すぎる上位カテゴリだけを選び、読者が実際に探す小・中カテゴリを設定しないことです。
これでは検索・ランキングの両面で埋もれてしまいます。
趣味・健康・暮らし系での読者意図に合う棚選び
趣味・健康・暮らし系は、カテゴリ選びで「読者の検索行動」を強く意識する必要があります。
たとえば、ガーデニングや料理本などは、「実用・暮らし」の小カテゴリが細かく分かれており、どの棚に置くかで露出のされ方が変わります。
健康系であれば、「健康・医学 > 健康法」や「ダイエット・フィットネス」など、具体的なテーマのカテゴリを優先しましょう。
曖昧に「自己啓発」に入れてしまうと、読者層がズレてしまい、レビュー評価の低下にもつながることがあります。
趣味系では、「旅行」「アウトドア」「手芸」「ペット」など、それぞれ独立した小カテゴリが用意されています。
実務的には、1冊で複数のテーマを扱っている場合、**主軸となるテーマ1本に絞ってカテゴリを決める**ほうが審査や露出の観点で安定します。
筆者の経験上、このジャンルでは「どの棚に置かれているか」がそのままレビュー数やランキングの伸びに直結します。
細かいカテゴリ設定を面倒がらず、しっかり確認しておくことが成果につながるポイントです。
公開後の見直し:カテゴリ変更と検証のやり方
本を出版したあとも、カテゴリ設定は「一度決めたら終わり」ではありません。
実際には、公開後の反応を見ながらカテゴリを見直すことで、露出や売上が大きく改善するケースがあります。
とくに初出版の方は、最初から完璧にカテゴリを選べる人は少ないため、定期的なチェックと微調整が重要です。
ランキング・検索経路・CTRの簡易チェック方法(外部ツールなし)
まず基本になるのは、Amazonの販売ページやランキングページを定期的に確認することです。
KDPダッシュボードでは詳細な分析機能は限られますが、公開直後〜数週間は以下の3点を押さえておくとよいです。
1. **ランキングの推移**
カテゴリランキングが付いているか、順位が動いているかをチェックします。
もし販売があるのにランキングが表示されない場合、カテゴリ設定が不適切な可能性があります。
2. **検索経路の確認**
自分の本のタイトルやキーワードをAmazonで実際に検索してみて、どのカテゴリページに出ているか、どのワードで上位表示されているかを確認します。
このシンプルなチェックだけでも、読者の導線がカテゴリと合っているかどうかが見えてきます。
3. **CTR(クリック率)の目視チェック**
検索結果で表示されているのにクリックや売上につながっていない場合、カテゴリのターゲットがズレている可能性があります。
同ジャンルの競合書籍と並べて見たときに「浮いていないか」を確認するのがポイントです。
外部ツールを使わなくても、こうした簡易チェックを続けるだけで、カテゴリの方向性が合っているかを十分に検証できます。
正しい順位の確認手順は『Kindle出版ランキングの見方とは?Amazonで順位を正しく確認する方法を解説』をご覧ください。
カテゴリ変更の目安時期と反映の考え方(公式ヘルプ要確認)
カテゴリ変更は、すぐに頻繁に行う必要はありません。
一般的には、**公開から2〜4週間ほど経過してデータがある程度溜まった段階**で、初回の見直しをするのが適切です。
これは、Amazonのランキングや検索アルゴリズムが一定期間の販売データをもとに反映されるためです。
公開直後にコロコロ変えると、逆に評価が安定せず、アルゴリズム上の露出が伸びないケースもあります。
カテゴリ変更は、管理画面からの更新またはKDPサポート経由でのリクエストになります。
具体的な手順・反映時間は更新されることがあるため、最新の公式ヘルプ要確認としてください。
そのため、戦略的にタイミングを見極め、1回ごとに効果を検証しながら進めることが大切です。
価格・表紙・説明文との整合で総合最適にする
カテゴリを変更する際は、単体で考えるのではなく、**価格・表紙・説明文との整合性**も合わせて見直すと効果的です。
例えば、カテゴリをより専門的なニッチ分野に移す場合、表紙のデザインも専門書風に寄せると読者とのマッチ度が上がります。
一方、自己啓発寄りのカテゴリに変更するなら、説明文にエモーショナルな要素を増やすとCTRや購入率が向上する傾向があります。
また、価格設定も重要です。
競合と比べて極端に高すぎたり安すぎたりすると、カテゴリを変えても露出効果が十分に発揮されないことがあります。
筆者の経験では、カテゴリ変更だけでランキングが上がることもありますが、**複数の要素を一貫させることで相乗効果が生まれる**ケースが圧倒的に多いです。
カテゴリ変更は「単発の施策」ではなく、「全体最適の一部」として位置づけると成果が出やすくなります。
ペーパーバックのカテゴリーはどう扱う?(補足)
電子書籍が中心のKindle出版ですが、希望すれば同じ原稿を使ってペーパーバック(紙の本)も出版できます。
ここでは、電子書籍とペーパーバックでのカテゴリー設定の違いや、最低限注意すべきポイントを簡潔に補足します。
電子書籍との違いと最小限の注意点(紙は補足的に)
ペーパーバックの場合も、KDP上でカテゴリー設定を行いますが、電子書籍とは若干仕組みが異なります。
まず、カテゴリ数の上限は電子書籍と同様に最大3つまでですが、**ランキングや表示のされ方が紙の書籍の棚構造(Amazonの「本」ストア)に依存する**という点が重要です。
また、ペーパーバックではISBNの有無によって登録時の仕様が変わる場合があります。
KDP無料のISBNを利用する場合でも、基本的なカテゴリ選択はできますが、**電子書籍で設定したカテゴリと完全に一致するとは限らない**ことがあります。
特に注意したいのは、電子書籍側のカテゴリをそのままコピーしても、紙の本のストア構造には存在しないカテゴリ名が含まれているケースです。
この場合、公開時にKDP側で自動的に近いカテゴリへ割り振られることがあります。 意図しないカテゴリに振り分けられると、ランキング表示や検索経路がずれてしまい、露出が下がる原因になります。
そのため、ペーパーバックを発行する際は、事前にAmazon.co.jpの「本」カテゴリー内で該当ジャンルの棚を確認しておくのが安心です。
特に、ビジネス・自己啓発・趣味系は電子と紙で棚構造が微妙に異なることが多いので注意しましょう。
実務上は、電子書籍をメインとし、ペーパーバックは「補足的な出版」として扱う方がスムーズです。
紙での売上を狙うよりも、**電子書籍のカテゴリ戦略をしっかり固めた上で、紙は追加の販路と考える**のが現実的です。
まとめ|Kindle出版のカテゴリーは「適合×需要×競合」で決める
Kindle出版のカテゴリ選びは、単なるジャンル設定ではなく、読者との出会い方を決定づける重要な要素です。 「内容の適合性」×「検索・ランキングでの需要」×「競合強度」の3つを基準に設定することで、露出と売上の両方を最大化できます。
初回の設定で完璧を目指す必要はありません。
実際には、公開後のデータを見ながら改善していくことで、より本に合ったカテゴリにたどり着くケースが多いです。
カテゴリ選びを戦略的に行えば、広告や大量のレビューがなくても、自然検索だけで読者に見つけてもらえる土台を作ることができます。
公式ガイドラインをしっかり押さえた上で、実際の棚構造や競合状況も観察し、自分の本に最適なカテゴリを選んでいきましょう。
これが、Kindle出版で安定的に売上を伸ばすための第一歩です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。