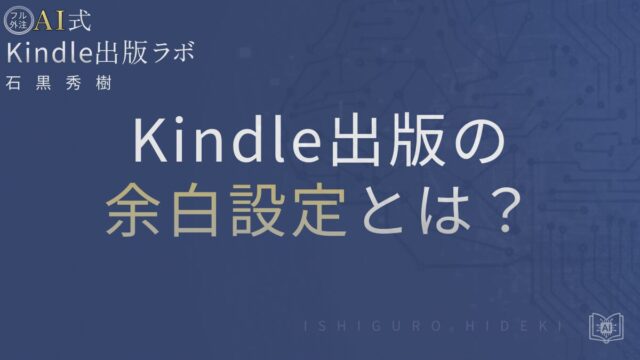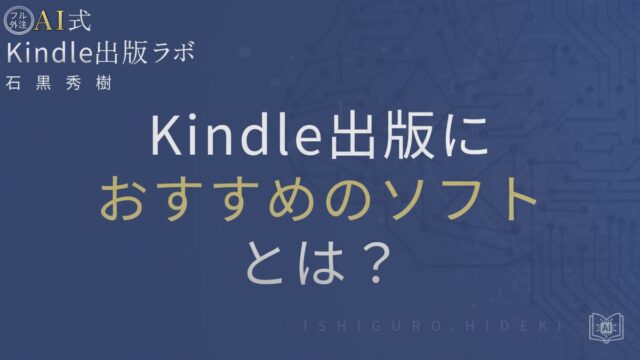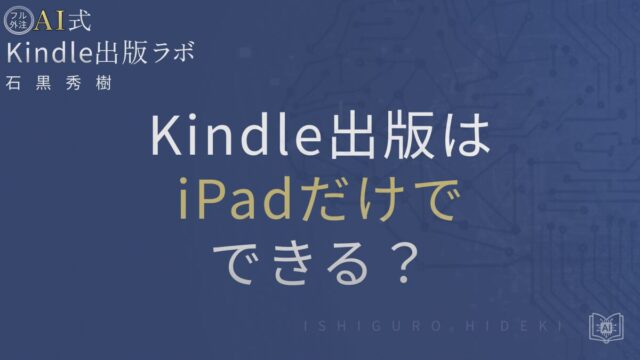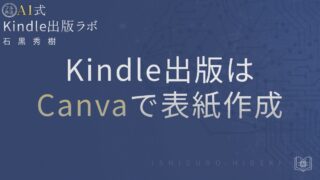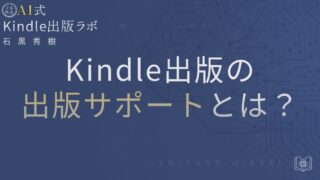Kindle出版のページ数は何ページ必要?電子書籍と紙の違いを徹底解説
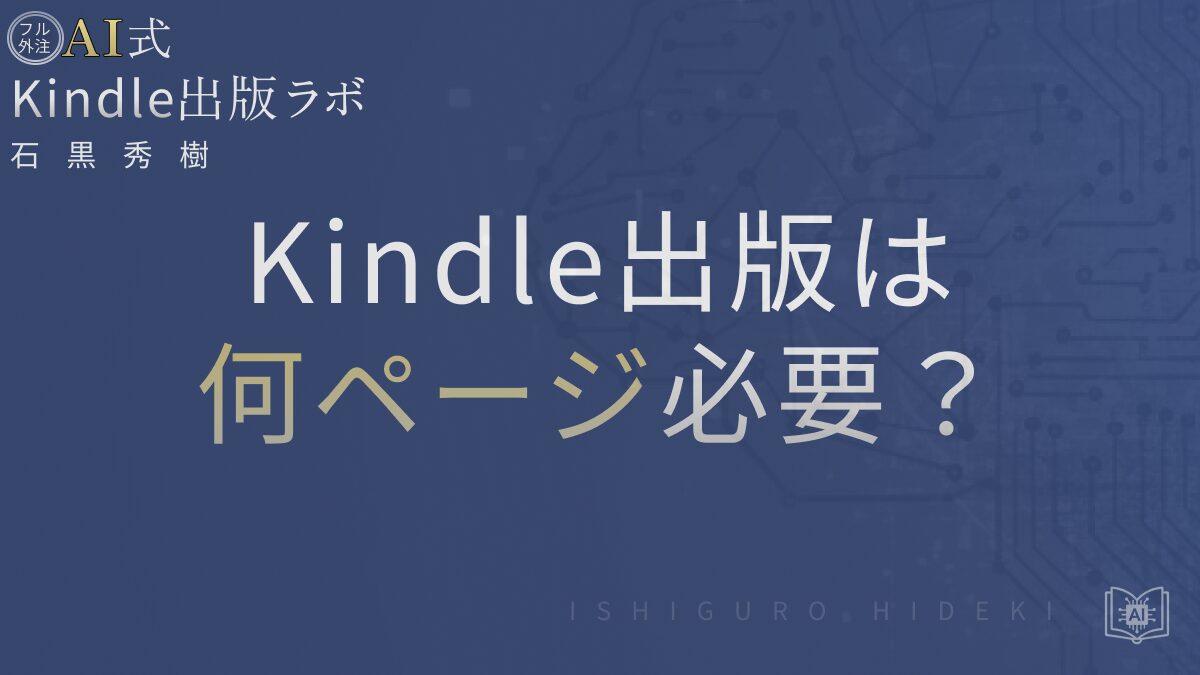
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、「何ページあれば出版できるの?」という疑問を持つ方はとても多いです。
特に初めてKDP(Kindle Direct Publishing)を使う場合、ページ数が少なすぎて審査に通らないのでは?と不安になりますよね。
この記事では、そんな疑問を解消しながら、実際の出版経験をもとに「ページ数の考え方」と「初心者が迷いやすいポイント」を整理して解説します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「Kindle出版 何ページ」が気になるのか?検索意図の背景
目次
Kindle出版を検索する多くの人が気にしているのは、「どのくらいの分量があれば本として成立するのか」という点です。
電子書籍は紙の本と違いページが固定されていないため、仕組みを理解していないと混乱しやすい部分でもあります。
また、Amazonの商品ページに表示される「本の長さ(ページ数)」を見て、これが出版条件に関係していると誤解するケースも少なくありません。
実際は、KDPの仕組み上、ページ数表示の有無は販売可否に直結しない一方、表示仕様は変更される可能性があります。最新の公式ヘルプ要確認と明記しましょう。
検索者が本当に知りたい「本の長さ規定」
検索者が最も知りたいのは、「Kindle出版には最低ページ数のルールがあるのか」という点です。
電子書籍(Kindle本)には、公式的な“最低ページ数の明記”は存在しません。
つまり、極端に短い作品でも出版自体は可能です。
ただし、実務的には10ページ未満のような極端に短い内容だと読者の満足度が低く、レビュー評価にも影響する恐れがあります。
読者体験の面から見ても、ある程度の「読みごたえ」がある構成にすることが重要です。
一方、紙のペーパーバックではKDPの公式ルールとして「24ページ以上でないと出版できない」と定められています。
電子書籍とはルールが異なるため、両方を同時に出版したい方は注意が必要です。
初心者著者が迷いやすいページ数の悩み状況
初めてKindle出版をする方の多くが、「文字数がどのくらいで何ページになるのか」が分からず、構成段階で手が止まってしまう傾向があります。
特にWordやGoogleドキュメント上ではページ数が固定されていますが、リフロー型の電子書籍は読者の端末サイズによってページ数が自動的に変動します。
そのため、KDPではページ数よりも「文字数」や「章立て構成」で全体ボリュームを判断するのが実務的です。
私自身も最初の出版時、「ページ数が少ないと販売できない」と思い込んでいましたが、実際は1万字前後の短編エッセイでも問題なく公開できました。
とはいえ、短すぎる作品は価格設定の自由度が低く、Kindle Unlimited(読み放題)の収益にも影響しやすいため、最低限の内容量は意識した方が良いでしょう。
公式規定はなくても、読者満足と販売実績の両立を考えると、経験的には1.5万〜3万字程度を目安にする著者が多い印象です。
要するに、Kindle出版における「何ページ必要か?」という悩みは、実際には“ページ数”よりも“内容の厚み”や“構成の工夫”に関係しています。
次章では、その具体的なルールと実践的な目安を詳しく見ていきましょう。
ページ数よりも全体構成を掴むには、『Kindle出版の本文テンプレートと構成例|初心者がそのまま使える書き方ガイド』を参考にするとイメージしやすいです。
日本向けKDPで「最低ページ数」の公式ルールを確認
Kindle出版を行う際にまず確認しておきたいのが、「出版できる最低ページ数のルール」です。
電子書籍と紙のペーパーバックでは規定が異なるため、ここを誤解すると「審査落ち」や「印刷できない」といったトラブルにつながることがあります。
初心者の方でもわかりやすいように、それぞれの仕組みを整理して解説します。
電子書籍(Kindle本)に最低ページ数の明記はあるのか
日本のKDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)では、電子書籍の最低ページ数に関する明確な規定は存在しません。
つまり、極端に短い本でも技術的には出版可能です。
公式ヘルプにも「ページ数〇ページ以上でないと出版できない」といった数値条件は記載されていません。
ただし、これは「どんな短い本でも歓迎」という意味ではありません。
内容が薄すぎる場合や、ページ数稼ぎの目的で同じ内容を繰り返すような構成は、Amazonの品質基準に抵触するおそれがあります。
経験上、レビュー審査や自動チェックの段階で「読者に価値を提供していない」と判断されると、公開前に差し戻されるケースもあります。
そのため、最低ページ数のルールはなくても“最低限の内容の厚み”が実質的な基準になっていると考えておくのが安全です。
目安として、1万〜3万文字程度(一般的なエッセイや短編解説書の分量)であれば、読者からの満足度も高く、審査でも問題になりにくい印象です。
もちろん、テーマによって適正なボリュームは変わりますが、初出版であれば「短すぎず、最後まで読める量」を意識して構成するのが良いでしょう。
また、固定レイアウトの電子書籍(マンガ・写真集・絵本など)では、ファイル容量やページ構成の都合でページ数が少ないとエラーが出る場合もあります。
この場合は技術的な問題として出版が止まるため、公式ヘルプで推奨されている形式や画像解像度を確認してください。
紙のペーパーバックで適用される「最低24ページ」などの規定
一方、ペーパーバック(紙の本)では明確な数値基準があります。
KDP公式の日本語ヘルプによると、ペーパーバックのページ数は最低24ページ以上である必要があります。
これは印刷と製本の技術的な理由によるもので、ページが少なすぎると紙の厚みが足りず本として形にならないためです。
また、カバーに背表紙(スパイン)を作る場合、79ページ以上(おおむね80ページ以上)が必要とされています。
80ページ未満の書籍では背表紙に文字が入らないため、デザイン面で制約が生じます。
この条件を知らずに「20ページ程度で印刷できると思っていた」とつまずく方も多いです。
私も初めてペーパーバックを制作したときに、「PDFでは20ページでも、印刷プレビューでエラーが出て進まない」という経験をしました。
その際、KDPの「カバーカルキュレーター」でページ数を増やすと、問題なく入稿できた経緯があります。
つまり、電子書籍は内容次第で自由度が高い一方、紙本は製本の仕組みによって最低ページ数が厳密に定められています。
両方を出版する場合は、電子書籍を先に作成し、紙の要件(24ページ以上)に合わせてボリュームを微調整する方法が安全です。
なお、ペーパーバックのページ数は印刷後の仕上がりに基づくため、原稿のWord上のページ数と一致しません。
正確な値を確認したい場合は、KDPの公式ツール「カバーテンプレート&計算ツール」で試算しておくと安心です。
このように、電子と紙ではページ数の考え方がまったく異なります。
出版目的や読者層に合わせて、どちらの形式を優先するかを決めておくと、後の修正や再アップロードの手間を減らすことができます。
電子と紙の両方で出版したい場合は、『Kindle出版のペーパーバック(紙の本)を作る方法と注意点まとめ』で詳しい手順を確認しておくと安心です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
電子書籍でページ数をどう考えるか?実務的な目安と戦略
電子書籍では、紙の本と違って「ページ数」よりも「読者がどう感じるか」が重要です。
同じ文字数でも端末サイズやフォント設定でページ数が変わるため、ページ単位での最適化はできません。
その代わりに、読者目線で満足できるボリューム感を意識するのが実務的な考え方です。
読者目線で「短すぎる本」が抱えるリスク
Kindle本でよくある失敗が、「内容が薄すぎてレビュー評価が低くなる」ケースです。
出版自体は可能でも、読者は「有料の本」として購入するため、数ページしかない本だと「中身がない」と感じやすくなります。
特にKDPの読み放題サービス(Kindle Unlimited)では、読まれたページ数に応じて報酬が支払われる仕組みのため、短すぎる作品は収益にも直結します。
私自身も初期の頃、1万文字程度のエッセイを出したところ、評価は悪くなかったものの「もう少し内容が欲しい」といったレビューが続きました。
短すぎる本は、内容が良くても“印象的に損をする”ことが多いです。
読者にとって「1冊を読んだ満足感」がないと、リピーターにつながりにくくなる点は意識しておきましょう。
文字数・章構成・ボリュームから逆算するページ数の目安
ページ数が端末によって変わるとはいえ、構成を考えるうえでの目安は必要です。
一般的に、Kindleリフロー型の電子書籍では「約250〜300文字で1ページ相当」と換算されることが多いです。
この目安をもとにすると、
– 1万文字=約40ページ
– 2万文字=約80ページ
– 3万文字=約120ページ
といったイメージになります。
短編エッセイなら1万文字前後でも成立しますが、実用書やノウハウ系の書籍なら2万〜3万文字以上が読み応えのあるラインです。
章構成としては、導入→本論→まとめの3部構成が基本で、各章ごとに小見出しを設けると読者が途中離脱しにくくなります。
また、同じボリュームでも見出しを適切に配置するだけで「読みやすく感じる本」になります。
KDPのプレビュー機能で全体の見え方をチェックし、1章が長くなりすぎないよう意識して調整しましょう。
価格設定・印税・読書体験とのバランスを意識する
もうひとつ重要なのが、ページ数と価格設定のバランスです。
KDPでは価格帯ごとに印税率が変わり、250円〜1,250円の範囲なら70%の印税を設定できます。
ただし、内容が薄い本を高価格に設定すると、読者の納得感を得にくくなります。
私の経験では、1万〜2万文字程度の短い本なら300〜400円前後が妥当です。
3万字を超える実用書クラスなら500〜700円程度でも評価が安定しやすい印象があります。
また、読書体験の満足度を上げるには「本の終わり方」も重要です。
ページ数が多いだけでなく、「読んでよかった」「また読みたい」と思わせる締め方を意識すると、自然と評価も伸びます。
ページ数の多さはあくまで目安です。
読者が感じる“密度”と“満足感”こそが本の価値を決めるため、数字にとらわれすぎず構成全体の完成度を高めることが大切です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
出版前にチェックすべき「ページ数」関連の注意点
Kindle出版を進める前に、意外と見落とされがちなポイントが「ページ数の扱い方」です。
特に電子書籍は、レイアウト形式やファイル構成によってページの見え方が変わるため、仕組みを理解していないと“審査前で止まる”などのトラブルにもつながります。
ここでは、出版前に必ず確認しておきたい2つの注意点を整理します。
固定レイアウト vs リフロー形式でページ数が変わる落とし穴
KDPで作成する電子書籍には、大きく分けて「固定レイアウト」と「リフロー型」の2種類があります。
固定レイアウトは、画像や文字の配置をそのまま固定する方式で、写真集・絵本・漫画などに向いています。
一方のリフロー型は、読者がフォントサイズや端末の向きを変えても文字が自動で流れる形式で、文章中心の本に向いています。
初心者がつまずきやすいのは、「Wordで50ページあったのに、Kindle Previewerで確認したらページ数が大幅に変わっていた」というケースです。
これはリフロー型では画面サイズによって改ページ位置が変動するため、ページ数が端末ごとに違って見えるからです。
また、固定レイアウトを使うときは、画像データが多すぎるとファイル容量が大きくなり、KDPのアップロード上限(650MB以内など)を超えてしまうことがあります。
この場合、圧縮や画質調整が必要になるため、出版前にプレビューでチェックしておくことをおすすめします。
私自身、以前に固定レイアウトで絵本を作ったとき、解像度を上げすぎてエラーが出た経験があります。
KDPの推奨解像度は用途(表紙・本文・固定/リフロー)で異なります。表紙は長辺2,560px推奨など、最新の公式ヘルプ要確認とし、用途別に最適化してください。
固定かリフローかを最初に決めておくことが、ページ数トラブルを防ぐ最大のポイントです。
途中で形式を変更すると、ページ構成や目次リンクが崩れることもあるので注意しましょう。
商品ページに「本の長さ(ページ数)」が表示されないケースと対処法
Kindleストアの商品ページを見ると、「本の長さ:○○ページ」と表示されている本があります。
しかし、いざ自分の作品を出してみると「ページ数が表示されない」という相談もよくあります。
この「本の長さ」は、KDPが自動的に計算する値で、主にリフロー型の本に対してAmazonシステムが“推定ページ数”を表示しています。
ただし、すべての本に必ず表示されるわけではありません。
ページ数が少ない場合や、特定の形式(固定レイアウト・画像中心の本)の場合は、Amazon側で表示対象外になることがあります。
また、KDPの登録直後は情報反映までに時間がかかることがあり、私の経験では最長で72時間ほど経ってからページ数が表示されたケースもありました。
そのため、非表示になっていても数日待つことで自動的に表示されることがあります。
それでも表示されない場合は、ファイル形式やメタデータに問題がある可能性があります。
その際はKDPサポートへ問い合わせると、フォーマットや設定を確認してもらえます。
サポートは日本語対応で、フォームから問い合わせると2〜3営業日以内に返信が届くことが多いです。
表示の有無は販売や審査に直接影響しませんが、読者にとって“読みごたえの指標”になるため、整っている方が印象が良いです。
アップロード時にプレビュー確認を行い、異常がないか早めにチェックするようにしましょう。
レイアウト形式の違いを理解したい方は、『Kindle出版で固定レイアウトとリフロー型を使い分ける方法』をチェックしておくとよいでしょう。
まとめ:Kindle出版でページ数を決めるときのポイント
Kindle出版において、ページ数は“審査条件”ではなく“読者満足”に直結する要素です。
電子書籍には公式な最低ページ数の規定がありませんが、内容が薄すぎるとレビューや評価に悪影響が出る可能性があります。
一方で、ペーパーバックには明確なページ数制限(最低24ページ以上)があるため、紙版も視野に入れている場合は早めに構成を整えることが大切です。
また、固定レイアウトかリフロー型かを最初に決めることで、後々のトラブルを防げます。
さらに、商品ページの「本の長さ」表示が反映されない場合も焦らず確認と時間経過を待つ姿勢が必要です。
最終的に重要なのは、ページ数ではなく読者にどれだけ価値を届けられるかという視点です。
あなたの体験や知識を丁寧にまとめることで、ページ数を超えた信頼と評価が自然とついてきます。
—
**
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。