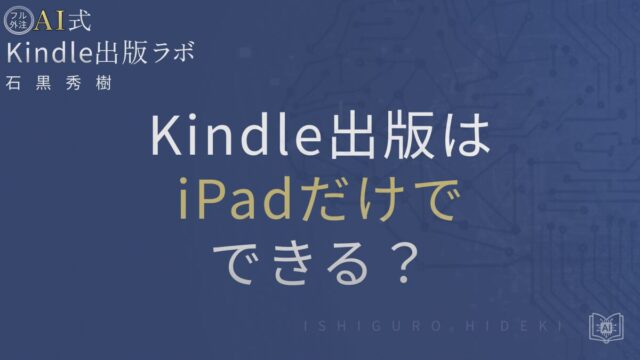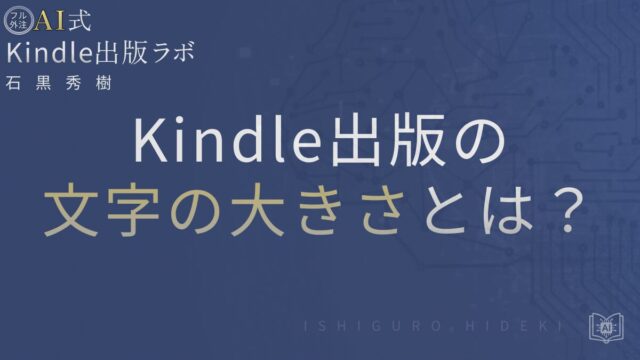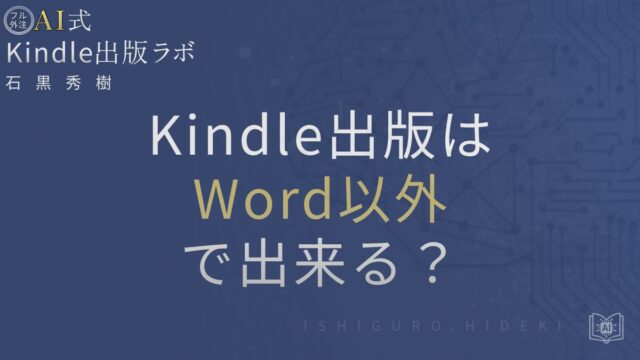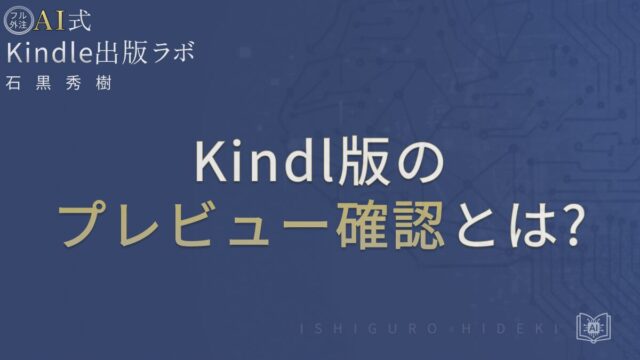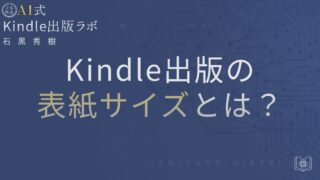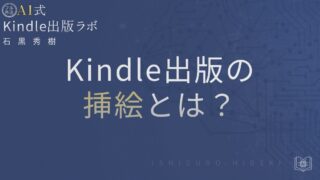Kindle出版のページ数とは?電子と紙で異なる基準を徹底解説
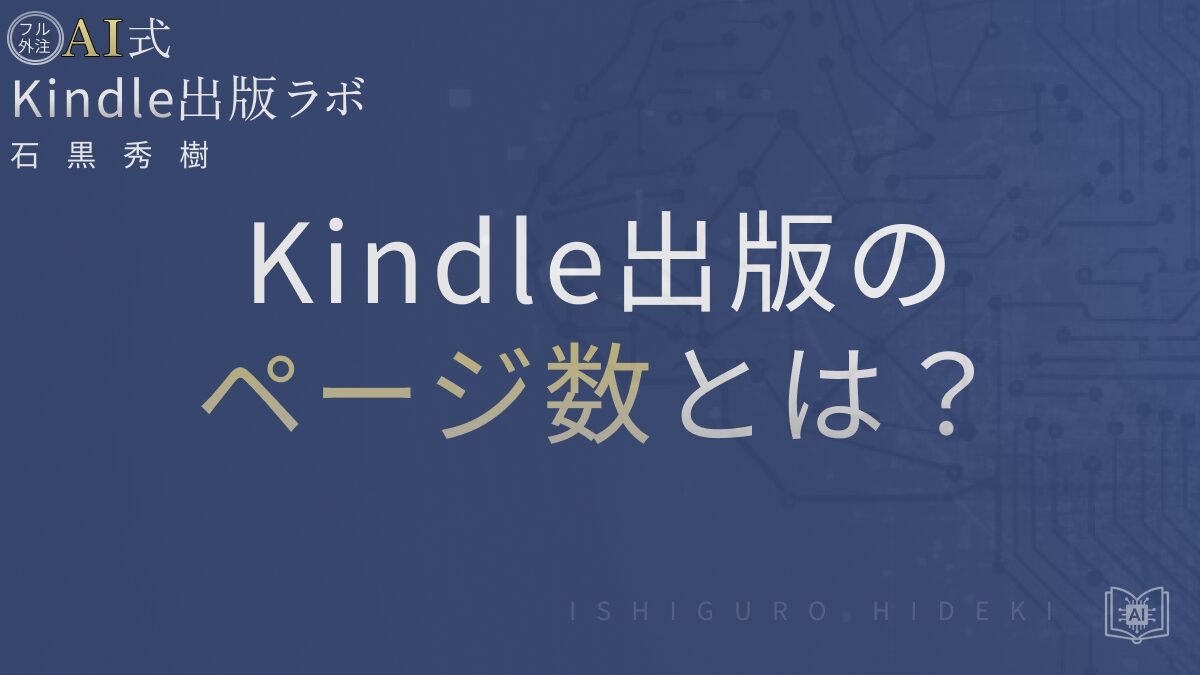
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの人がまず気にするのが「ページ数ってどれくらい必要なの?」という点です。
実は、電子書籍と紙(ペーパーバック)ではルールがまったく違います。
電子は固定のページ数という概念がなく、紙は24ページ以上が必須。
この違いを知らないと、思わぬところで審査や体裁のトラブルになることもあります。
この記事では、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の公式仕様と、実際に出版してきた経験をもとに、初心者でも迷わない「ページ数の正しい考え方」を整理していきます。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
【結論】Kindle出版のページ数:電子は固定基準なし/紙は24ページ以上
目次
Kindle出版では、電子書籍とペーパーバックでページ数の考え方がまったく異なります。
電子(リフロー型)はページが読者の設定で可変するため、ページ数という固定の概念が存在しません。
一方、ペーパーバックは印刷物として扱われるため、物理的なページ数が必要です。
そのため、KDPの公式仕様上、ペーパーバックは24ページ以上が必須条件とされています。
この違いを押さえるだけで、出版準備の効率が格段に上がります。
Kindle出版 ページ数の最短回答(初心者向けまとめ)
「Kindle出版で何ページあればいいですか?」という質問には、こう答えます。
電子書籍なら、固定のページ数は不要です。
なぜなら、電子書籍(リフロー型)はスマートフォンやKindle端末で文字サイズ・行間を自由に変えられるからです。
つまり、1ページという単位が人によって違います。
リフロー型は可変表示のため固定下限は設けられていません。
審査では内容の有用性や体裁が重視されます(公式ヘルプ要確認)。
ただし、あまりに短すぎて中身が薄いと読者の満足度が下がるため、章立てや構成には注意が必要です。
一方、紙(ペーパーバック)は事情が異なります。
印刷の都合上、KDPでは**24ページ未満の書籍は登録できません**。
これは日本も米国も共通の基準です。
背表紙の有無や印刷コストもページ数に応じて変わるため、紙で出す場合は最初に想定ページ数を決めておくとレイアウト調整がスムーズです。
検索意図を満たす本記事の読み方(導入とゴール)
この記事では、検索でよくある「Kindle出版 ページ数」に関する疑問をすべて整理します。
まず、電子書籍ではなぜページ数という概念がないのか。
次に、Kindle Unlimited(読み放題)での収益計算に関係する「KENPC」とは何か。
そして最後に、ペーパーバックで必要なページ数と、構成の決め方を説明します。
この3つを理解すれば、もう「何ページあればいいの?」と迷うことはなくなります。
実務的にも、「本文の長さをどう設計すれば読みやすく、審査にも通るのか」という感覚がつかめるはずです。
公式ルールと実際の出版現場での差を知ることが、スムーズな出版の第一歩です。
電子(Kindle本/リフロー型)の「ページ数」の考え方
電子書籍、特にリフロー型(文字サイズが可変のタイプ)では、「ページ数」という考え方が紙の本とまったく異なります。
出版を始めたばかりの方ほど「何ページ書けばいい?」と悩みますが、実はその問い自体が紙の感覚から来ていることが多いです。
Kindle電子書籍では、ページは“端末や読者設定で変わる動的な単位”であり、固定的な数値ではありません。
そのため、ページ数を目標にするよりも「どのくらいの内容を、どう構成するか」に意識を向けることが重要です。
Kindle出版 ページ数とは?可変表示のしくみ(%表示とページ番号の扱い)
Kindle端末で本を読むと、ページ数ではなく「読了率(%)」で表示されることに気づくと思います。
これは、読者が文字サイズを変更したり、スマートフォン・タブレット・PCなど、異なる画面サイズで読むためです。
文字が大きければページ数は増え、小さければ減ります。
つまり、**ページという概念が固定されていない**のです。
公式ガイドラインでも、「リフロー型の電子書籍はページ番号を入れないことを推奨」とされています。
ページ番号を入れてしまうと、端末によってズレたり、リンクが壊れたりする原因になります。
実際、私も最初に紙の本の感覚でページ番号を入れてしまい、目次のリンクがずれてしまった経験があります。
電子では「%表示」と「位置情報(ロケーション)」が自動的に付与されるので、ページ番号を入れる必要はありません。
ページ数の最低条件はある?「固定下限なし」の根拠と注意点(公式ヘルプ要確認)
電子書籍には、紙のような「◯ページ以上でないと出版できない」という下限はありません。
KDPの公式ヘルプにも明確なページ数の制限は書かれていません。
ただし、審査では「読者にとって有用な内容であるか」が重要視されます。
つまり、あまりに内容が薄かったり、誤字脱字や空白ページばかりの原稿は審査で指摘されることがあります。
「ページ数より中身の質」――これが電子書籍における一番の基準です。
私の体感では、実用書なら原稿用紙換算で30〜50枚(1万〜2万文字)でも成立しますし、しっかりしたテーマなら5万文字程度が読みやすい長さです。
ただし、テーマやジャンルによって最適なボリュームは変わるため、内容の完成度を優先しましょう。
KDPはページ数で審査を落とすことはありませんが、「体裁不備」や「内容が未完成」と判断されるケースはあるため注意が必要です。
ページ数ではなく“どのくらいの文字数を書けばいいか”の具体的な目安は『Kindle出版の文字数とは?最適な分量と目安を徹底解説』で詳しく解説しています。
文字数の目安より大事なこと:読了率・見出し構成・改行設計
多くの初心者が「文字数の目安」を気にしますが、それよりも大切なのは“最後まで読まれる構成”です。
読者の離脱を防ぐには、見出しを細かく分け、1章あたりを短くまとめることが効果的です。
Kindle Unlimitedのような読み放題サービスでは、読了率が高い作品のほうが読者満足度も上がり、結果的に収益にもつながりやすくなります。
また、改行を多めに入れてスマホでも読みやすい体裁を意識しましょう。
特にリフロー型では、1文を短く区切るだけで可読性が大きく変わります。
私も最初の頃は「紙の原稿のように詰めて書くクセ」がありましたが、電子書籍では“空白のリズム”が読者の集中を保つポイントになります。
固定レイアウト・コミック等の場合の例外の考え方(概要のみ/詳細は公式参照)
一方で、写真集や漫画、絵本のようにページ単位でデザインが決まっている「固定レイアウト型」もあります。
この場合は、紙の本に近い形式となり、ページ数が固定されます。
ただし、固定レイアウトは通常のリフロー型よりもデータ容量が大きく、制作に専門知識が必要です。
KDP公式では「固定レイアウトは画像中心・ページデザイン重視の書籍に限定」と明記されています。
設定方法や推奨仕様は随時更新されるため、必ず公式ヘルプの最新情報を確認してください。
特にスマホやタブレットでは表示崩れが起きやすいため、事前にプレビュー機能でチェックしておくのがおすすめです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle UnlimitedとKENPC:ページ数と収益の関係
Kindle出版を行うとき、ページ数が直接的に収益に関わるのは「Kindle Unlimited(読み放題)」に登録している場合です。
リフロー型の電子書籍には固定のページ数はありませんが、Kindle Unlimitedでは「読まれた分」に応じて報酬が支払われるため、KDPは独自の換算基準を設けています。
この基準がKENPC(Kindle Edition Normalized Page Count:標準化ページ数)です。
ページ数というより「読まれた分量の共通単位」と考えると分かりやすいでしょう。
KENPC(標準化ページ)とは?Kindle Unlimitedの既読計測の基本
KENPCとは、KDPが独自に定めた「標準化ページ数」で、作品ごとに自動的に計算されます。
端末や文字サイズに依存せず、全作品を同じ基準で比較できるようにするための仕組みです。
既読ページに応じたロイヤリティの対象はKindle Unlimited(KDP Select)等です。
Prime Readingは別枠の施策で条件が異なります(公式ヘルプ要確認)。
たとえば、読者があなたの本を100ページ中50ページまで読めば、支払い対象は「50 KENP」となります。
報酬は「月ごとに設定されるグローバル基金(KDP Select Global Fund)」から分配されます。
そのため、月によって1ページあたりの単価が変わるのが特徴です。
私も出版当初、1ページ=固定の値段だと思い込んでいましたが、実際は毎月微妙に変動します。
公式では「KENPCの算出方法」や「KENP単価」は明示されておらず、あくまでKDPが内部的に管理しています。
信頼できる情報源は、KDP公式の「Selectレポート」や「ヘルプページ」です。
「1ページ単価は固定?」よくある誤解と最新情報の確認方法(公式ヘルプ要確認)
多くの人が「KENPC=固定単価」と勘違いしますが、実際には毎月の基金総額と全世界で読まれたKENP総数によって変動します。
つまり、「ページ単価」はKDPが毎月発表するグローバル基金の分配結果で決まるのです。
この仕組みは日本も海外も基本的に同じですが、各国の読者数や基金規模により若干の差が出る場合があります。
毎月の単価を確認するには、KDPの「レポート」ページ内にある「Kindle Unlimitedページ数既読」欄をチェックするのが一番確実です。
また、KDP公式ブログでも時折、月ごとの基金総額が発表されています。
一方で、SNSなどには「今月の単価は〇円」などの噂も流れますが、公式以外の数字は目安程度に見るのが安全です。
私の経験上、1KENPあたりの金額はここ数年で大きく変動しておらず、概ね安定しています。
ただし、ジャンルや読者数の変化で微妙に増減することがあるため、最新の情報は毎月確認する癖をつけましょう。
短すぎる/長すぎる原稿で起きがちな離脱と対策(章分割・要約・目次)
KENPCは「読まれた分」に応じて報酬が決まるため、単純に「長ければ得」というわけではありません。
むしろ、無理に長くした作品は中だるみで読者が離脱し、結果的に読まれたKENPが少なくなるケースもあります。
私自身、初期の本で「文字数を稼ごう」と意識しすぎて中盤で離脱されることが多く、平均読了率が下がってしまった経験があります。
一方で、短すぎる本も注意が必要です。
内容が薄いとレビューで「情報が少なすぎる」と指摘されやすく、評価が下がる原因になります。
大事なのは「量」よりも「読後に得られる満足感」です。
章立てを工夫してテンポよく読み進められる構成にする、要点を章末でまとめる、目次をわかりやすく整理するなどの工夫が有効です。
“最後まで読まれる本”こそが、結果的にKENPC収益を最大化します。
また、リフロー型の場合、文字数を増やすよりも構成や流れを整えるほうが読者満足度に直結します。
読みやすさを最優先にした編集こそ、Kindle出版で長く収益を得る秘訣です。
ページ数だけでなく「そもそも読まれない」問題を改善したいときは、『Kindle出版で読まれない原因とは?商品ページ改善で既読を増やす方法』も併せてチェックしておくと、読了率アップの具体策が見つかります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
ペーパーバック(紙)のページ数ルール【補足】
電子書籍と違い、ペーパーバックではページ数が明確に定義されています。
紙の本は実際に印刷されるため、製本の都合上「最小ページ数」や「最大ページ数」のルールが存在します。
特にKDPのペーパーバックは24ページ未満では登録できないという点を、まず押さえておきましょう。
この章では、最低ページ数の仕組みと、ページ数によって変わる印刷コストや背表紙の有無、そして電子と紙を併売する際の設計の流れを詳しく解説します。
KDPペーパーバックの最低ページ数24ページと上限の目安(判型・用紙による)
KDPの公式ガイドによると、ペーパーバックは最低24ページ以上でなければ出版できません。
これはAmazon.co.jpでも米国版KDPでも共通の仕様です。
ページ数が24未満の原稿をアップロードすると、エラーメッセージが表示され登録自体ができません。
上限については、判型(サイズ)や紙質によって異なります。
最大ページ数は用紙色やインク種で変動します(例:白黒内⾯:白紙は上限が高め、カラーは低め)。
正確な上限は公式ヘルプで確認してください。
カラー印刷や大きい判型(B5など)にすると上限はさらに下がります。
これは、紙の厚みや製本の安定性が影響するためです。
実際には、読者が手に取りやすい厚みを意識すると150〜250ページあたりが最もバランスが良い印象です。
経験上、これ以上厚くなるとコストが上がり、印刷・配送コストがロイヤリティを圧迫することがあります。
短い原稿の場合は、目次や奥付、著者プロフィールを丁寧に整えて体裁を整えると見栄えが良くなります。
ページ数のルールだけでなく、実際の登録手順までまとめて確認したい場合は『Kindle出版で紙の本を出すには?ペーパーバックの条件と手順を徹底解説』を参考にしてみてください。
背表紙や印刷コストとページ数の関係(レイアウト調整の考え方)
ペーパーバックの魅力の一つは「背表紙」がつく点ですが、これにも条件があります。
背表紙が印刷されるのは、ページ数が一定以上になった場合のみです。
背表紙の文字可否はスパイン幅(例:0.0625インチ以上)が目安で、必要ページ数は紙厚で変わります(公式ヘルプ要確認)。
それ以下では、背表紙が非常に細くなり、印刷がずれるリスクがあるため推奨されません。
また、ページ数が増えると印刷コストも上がります。
KDPのロイヤリティ計算では、「基本印刷費+ページ単価×ページ数」という仕組みが採用されています。
そのため、販売価格を安く設定しすぎると、ページ数が多い本ほど利益が少なくなります。
私も最初は価格設定を安易に決めてしまい、印刷費を差し引くとほとんど利益が出なかったことがあります。
販売価格は、印刷費を試算してから逆算で決めるのがおすすめです。
ページ数=コストとデザインの両立点を意識し、見た目と利益のバランスを取ることが大切です。
KDPの「プレビュー機能」で厚みを確認し、背表紙のデザインを合わせると完成度が高まります。
電子と紙を併売する場合の設計ステップ(版下準備と体裁の違い)
電子書籍とペーパーバックを同時に出版する場合、原稿は基本的に同じ内容を使えますが、版下(レイアウトデータ)をそれぞれ調整する必要があります。
電子書籍はリフロー型(自動調整)ですが、紙は固定レイアウトのため、行送り・余白・ページ番号・ノンブル(ページ下の番号)などを自分で設定します。
実務上は、まず電子書籍を仕上げてから紙版を作るのがおすすめです。
理由は、電子版の本文を整える段階で誤字脱字や構成のズレを修正できるからです。
その後、WordやInDesignなどで印刷用テンプレートに流し込み、表紙と本文のPDFをKDPにアップロードします。
メタデータが一致すると自動でリンクされることが多いですが、結合されない場合はサポート依頼で統合を申請します。
この連携はKDPが自動判定するため、タイトル・著者名・出版日などの情報を完全に一致させることが大切です。
タイトル表記が微妙に違うと別商品として扱われ、レビューも別々になるので注意が必要です。
電子と紙の両立は、見せ方と信頼感を高める効果があるため、初出版の方にもおすすめです。
特に自己啓発・実用書・教育系ジャンルでは、紙の存在が読者の安心感につながる傾向があります。
印刷ルールを理解したうえで、無理のない範囲で併売に挑戦してみると良いでしょう。
実例で学ぶ:ページ数の設計フロー(初心者でも迷わない手順)
Kindle出版では、「ページ数をどう設計するか」は多くの初心者がつまずくポイントです。
最初からページ数を意識して書こうとすると、途中で行き詰まってしまうこともあります。
そこでおすすめなのが、「読者目線で設計 → 書く →整える」という3ステップ方式です。
この流れを意識することで、内容の質を落とさず、ページ数も自然に整っていきます。
ここでは、実際に私が出版してきた経験をもとに、初心者でも迷わない手順を紹介します。
ステップ1:読者ニーズ→章立て→目次(Kindle出版 目次と階層見出し)
最初のステップは「誰に、何を届けるか」を明確にすることです。
いきなり本文を書き始めるよりも、まず読者が求めている情報を整理し、章立てを作るほうが効率的です。
たとえば、初心者向けノウハウ本なら「導入→基本→応用→まとめ」という4章構成でも十分です。
次に、各章の中で扱うトピックを箇条書きにし、それをそのまま見出し(H2・H3)として目次化していきます。
この段階では文字数を気にせず、内容の流れが自然かどうかを優先してください。
Kindleでは目次が自動生成されるため、見出し構造(階層H2→H3)を正しく設定することがとても重要です。
目次があるだけで読者の離脱率が下がり、最後まで読まれやすくなります。
私の経験では、1章につき3〜5セクション(小見出し)を設定すると、全体の流れが整理されやすく、ページ数も自然にまとまります。
短すぎる章が多いと全体が薄く見えるので、章ごとのボリューム感も確認しましょう。
ステップ2:テンポ重視の本文設計(短文・改行・図表の挿入判断)
次のステップでは、本文を執筆していきます。
電子書籍では「テンポの良さ」が読みやすさの鍵になります。
1文を短く区切り、改行をこまめに入れると、スマホでもストレスなく読めます。
特に、1段落が3行以上続くと読みづらくなる傾向があります。
私も最初の頃は「紙の原稿のようにまとめて書くクセ」がありましたが、読者のレビューで「読みづらい」と指摘されてから、改行を意識するようになりました。
以降、平均読了率が明らかに上がりました。
また、必要に応じて図表や箇条書きを入れるのも効果的です。
グラフや箇条書きがあるだけで視覚的なリズムが生まれ、ページ数の見た目も整います。
ただし、過剰に挿入すると読みづらくなるので、1章に1〜2カ所程度を目安にするとよいでしょう。
「見た目の余白」もコンテンツの一部と考えると、読者の集中力を維持しやすくなります。
Kindleリーダーでは端末ごとに表示幅が変わるため、PCだけでなくスマホのプレビューでも必ず確認しましょう。
ステップ3:電子向け体裁チェック→必要なら紙用にページ調整
執筆が終わったら、最後は全体の体裁チェックです。
まず、Kindle Previewer(KDP公式のプレビューア)で「文字のズレ」「段落間の余白」「目次リンクの動作」を確認しましょう。
これを怠ると、読者側でページが崩れて見えることがあります。
電子書籍だけ出版する場合は、基本的にこれで完了です。
ですが、後からペーパーバック版を出す予定がある場合は、このタイミングで調整をしておくとスムーズです。
紙用にレイアウトを整えるときは、章ごとにページが切り替わるように改ページを挿入し、ページ番号(ノンブル)を設定します。
また、奥付(著者情報・発行日など)を入れておくと、書籍としての完成度が上がります。
私の場合、電子→紙の順で制作すると、全体の流れを崩さずに済みました。
紙版では文字サイズを少し大きめにしたり、余白を広めに取るなどの微調整も必要です。
その結果、同じ原稿でも電子では約120ページ、紙では約160ページになりました。
最終確認では、「誰がどの端末で読んでも見やすいか」を基準にすることが最も大切です。
出版直後のトラブルを防ぐだけでなく、レビュー評価の安定にもつながります。
ページ数はあくまで結果として整うものであり、読者にストレスを与えない体裁を目指すことが成功への近道です。
よくある質問・つまずき(Kindle出版 ページ数のFAQ)
Kindle出版を始めた方が最初に戸惑うのが、「ページ数が見えない」「ページ番号を入れるべき?」「短すぎると審査に落ちる?」といった点です。
これらは実際に多くの初心者が同じように悩む部分ですが、仕組みを理解すれば不安はすぐ解消できます。
ここでは、KDP公式の仕様と実際の出版経験をもとに、よくある質問をわかりやすく整理しました。
「ページ数が表示されない」→%表示が基本/端末差の理由
Kindle本を開いたとき、「全◯ページ」「残り◯ページ」といった表示がないのに驚く人が多いです。
ですが、これは不具合ではありません。
Kindleのリフロー型(通常の電子書籍形式)では、読者が文字サイズや表示方向を自由に変えられるため、ページ数という概念がそもそも固定されていません。
その代わりに表示されるのが「読了率(%)」や「残り時間」です。
これは端末が自動的に進捗を計算して表示しているもので、読者が設定を変えるたびに動的に変化します。
私も初めて出版したとき、「ページ数が消えた?」と焦りましたが、これはKindle端末の仕様通りの挙動でした。
固定のページ数が必要な場合(例:論文集や絵本など)は、固定レイアウト形式を選ぶ必要があります。
この点はAmazon公式でも明確に説明されていますが、スマホ版Kindleアプリと端末版で表示形式が異なることもあるため、複数端末で動作確認しておくと安心です。
「ページ番号は必要?」→電子では基本不要/紙では付与の考え方
電子書籍ではページ番号を入れないのが基本です。
リフロー型では、ページ番号を入れても端末ごとにずれてしまい、目次リンクや本文内の参照(「◯ページを参照」など)が正しく機能しません。
そのため、公式ガイドラインでも「ページ番号を削除するか、入れないことを推奨」とされています。
もしページ区切りを明示したい場合は、「第1章」「第2章」などの見出しで章立てを整理すると良いです。
章の切れ目を分かりやすくするだけでも、読者にとっては十分な目安になります。
ただし、ペーパーバック版を同時に出す場合は話が別です。
紙の本ではページ番号(ノンブル)があることで引用や索引が機能します。
実際、私も電子版では番号を外し、紙版ではページ下部にノンブルを入れました。
同じ原稿でも、体裁は出版形式によって切り替えるのが基本です。
「短すぎると審査落ち?」→内容の質・体裁の方が重要(公式ヘルプ要確認)
「30ページしかないけど出版できるの?」という質問をよく受けますが、答えは「はい、可能」です。
Kindle電子書籍にはページ数の下限がありません。
ただし、Amazonの審査では「読者にとって価値のある内容か」「内容が完成しているか」が重視されます。
つまり、ページ数が短くても、しっかりとした内容であれば問題ありません。
反対に、100ページあっても中身が薄い、誤字脱字だらけ、空白ページばかりといった場合はリジェクトされることがあります。
公式ヘルプにも、「形式的・内容的な品質要件を満たすこと」と明記されています。
私の経験では、実用書やエッセイの場合、1万〜3万文字(目安で約40〜80ページ)あれば十分に読み応えがあります。
とはいえ、これはあくまで目安であり、テーマやジャンルによって最適な長さは異なります。
「短い=ダメ」ではなく、「中身が薄い=審査に通らない」という考え方を持つと安心です。
不安な場合は、KDP公式ヘルプの「コンテンツガイドライン」を一度確認しておくと良いでしょう。
ペーパーバックでは物理的な制約(24ページ以上)があるため、紙にする場合のみページ数を意識すれば十分です。
まとめ:Kindle出版 ページ数の決め方と最小限のチェックリスト
Kindle出版では、ページ数を気にしすぎる必要はありません。
なぜなら、電子書籍とペーパーバックではページの考え方がまったく異なるからです。
ここまで紹介してきた内容を整理しながら、初心者が迷わず出版準備を進めるための最小限チェックリストをまとめます。
「どの形式で出すのか」と「読者にどう読ませたいか」を意識するだけで、出版の品質が一気に上がります。
ペーパーバックで必要なページ数と、電子との違いをもう少し詳しく知りたい方は『Kindle出版の最低ページ数とは?電子と紙の違い・注意点を初心者向けに徹底解説』もあわせてチェックしてみてください。
電子は固定基準なし/紙は24ページ以上—まずここを押さえる
電子書籍(リフロー型)には「最低ページ数」という概念がありません。
読者が端末設定で文字サイズや行間を変えられるため、ページは可変であり、固定値にはならないのです。
ページ数ではなく、章立て・見出し構成・読みやすさを重視しましょう。
一方で、ペーパーバックは印刷物のため、24ページ未満では登録できません。
この基準はAmazon.co.jpでも共通で、印刷工程の都合上の制約です。
短すぎる原稿を紙で出す場合は、目次や著者紹介ページなどを加えてページ数を調整します。
私も初出版の際に21ページでエラーが出て焦りましたが、奥付とあとがきを追加することで解決しました。
電子と紙、それぞれの物理的制約を理解して進めることが最初の一歩です。
KENPCは既読計測の標準指標—単価は月次で変動(公式ヘルプ要確認)
Kindle Unlimitedに登録している場合、ページ数は「KENPC(標準化ページ数)」として換算されます。
これはKDPが独自に設定している共通基準で、端末や文字設定に依存しません。
読者がどれだけ読んだかによって収益が決まる仕組みです。
ただし、KENPC自体や1ページあたりの報酬単価は固定ではなく、月ごとのグローバル基金(KDP Select Global Fund)によって変動します。
そのため、毎月のKDPレポートや公式ブログで最新の金額を確認しておきましょう。
私は初期の頃、単価が固定だと思い込み、収益見積もりがずれた経験があります。
こうした誤解を避けるためにも、「公式ヘルプで数値を確認する習慣」を持つことが重要です。
構成・読了率・可読性を優先—数値はガイド、品質が本質
ページ数やKENPCはあくまで「結果」であり、「目的」ではありません。
重要なのは、最後まで読まれる本を作ることです。
章ごとにテンポを整え、読者が飽きずに進められる構成を心がけましょう。
読了率が高い作品ほどレビュー評価も安定し、長期的に売れ続ける傾向があります。
また、見た目のデザインや改行も大切です。
特にスマホで読む人が増えているため、1文を短く、余白を多くとるだけで印象が変わります。
「何ページ書いたか」ではなく「どれだけ読まれたか」が最終的な評価軸です。
数値はあくまで目安として使い、読者の体験を第一に設計することが、Kindle出版で長く愛される作品を生む鍵になります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。