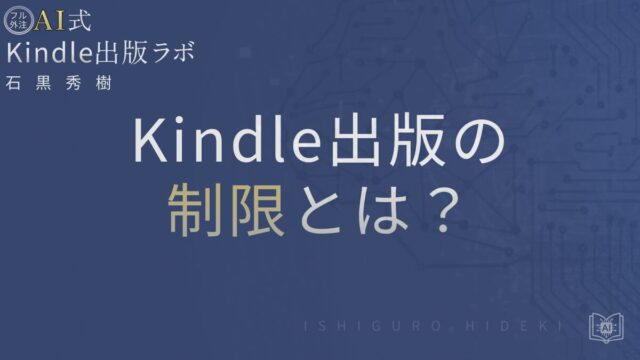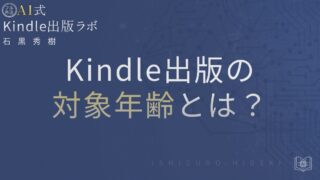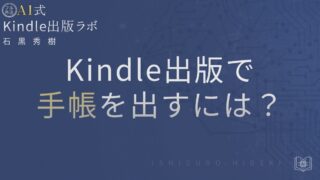Kindle出版の著者名変更はできる?手順と注意点を徹底解説
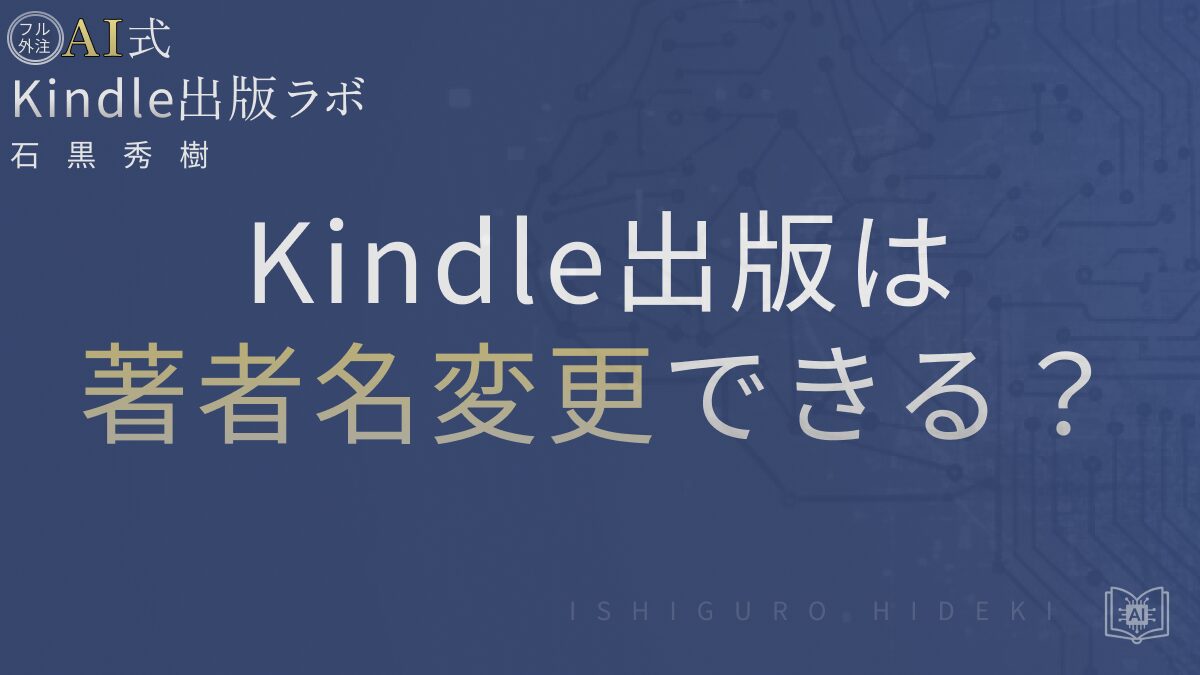
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「著者名を変えたい」と思ったことはありませんか。
ペンネームを統一したい、誤字を直したい、改名したい…そんなとき、何が可能で何ができないのかを明確に知ることがとても重要です。
この記事では、出版後の著者名変更が可能かどうか、そのルールと注意点を、私の実務経験とともに丁寧に解説します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
著者名変更は可能?Kindle出版で知るべき基本ルール
目次
Kindle出版(KDP)では、登録時に「著者名(Author)」という欄があります。
一方で「著者等(Contributors)」という、共著者やイラストレーター等の欄も存在します。
この二つの違いをまず知っておくことが、名義変更の判断において非常に重要です。
著者名(Author)は「その本の主として著した人」の名前として扱われ、出版後の検索・表示・著作権表示などで中心的な役割を果たします。
著者等(Contributors)は、著者以外に貢献した人々を記録するための補助的なフィールドです。
私の経験では、出版直後に「Author欄だけ違っていた」という理由で表示がバラバラになったケースもありました。
そのため、初めから正確な著者名を入力することを強くおすすめします。
KDP公式では「著者名フィールドの修正は原則できない」とされており、実務上も多くの著者がこの点で迷っています(公式ヘルプ要確認)。
つまり、著者名(Author)を出版後に変更することは基本的に不可能と覚えておきましょう。
ペンネームで活動している人は、名義変更の前に『Kindle出版でペンネームは使える?安全な設定方法と注意点を徹底解説』を確認しておくと理解が深まります。
「著者名(Author)」「著者等(Contributors)」の違いを整理
「Author」欄に入れた名前は、Amazon商品ページで“著者”として表示され、書籍を代表する名詞になります。
「Contributors」には、イラストレーター、翻訳者、共同著者など、補助的な役割の人を入れられます。
この違いを理解しないと、例えば「ペンネームに変更したいがContributors欄だけ変えればよい」と勘違いしてしまう誤りが発生します。
実務上、私も「共著者の意図的な入れ替え」でAuthor欄が間違ったまま出版された案件を見たことがあります。
そうした場合、後からの修正が非常に手間となります。
そのため、初期入力時に「この名前が主著者として公開されて問題ないか」をチェックしておくのが賢明です。
出版後に主著者名を変更できない理由とKDP仕様
なぜ出版後に“Author”を変えられないのでしょうか。
「理由は、著者名が販売ページ・著者ページ・レビュー等に強く紐づく主要メタデータで、後からの差し替えは整合性を損なうためです(公式ヘルプ要確認)。」
変更可能にすると、過去の購入者レビュー・ランキング・著者ページとの整合性が崩れるリスクがあります。
実務的には、私も出版後に「改名したから本の著者も変更したい」と問い合わせた経験がありますが、KDPサポートからは「新しい版として再出版をお勧めします」という案内でした。
これはKDP公式にも「大幅な著者名変更は新しい作品として扱う必要がある」と記載されています(公式ヘルプ要確認)。
なお、「海外ストアでは取り扱いが異なる場合があります。必要時のみ最新の公式ヘルプを確認してください(公式ヘルプ要確認)。」
ガイドライン上での制約を詳しく知りたい場合は『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』を参考にしてください。
実務でのケースと対策:Kindle出版+著者名変更の現実
Kindle出版では、「著者名を変えたい」と思ったときに取れる手段が限られています。
特に出版後の変更はシステム上制約が多く、誤字修正とペンネーム変更では対応方法がまったく異なります。
ここでは、実際のKDP運用経験をもとに、現実的な対処法と注意点を整理します。
誤字・表記ゆれの修正手順とKDP問い合わせ方法
著者名の「誤字」や「表記ゆれ」は、KDPのサポートを通じて修正が可能なケースがあります。
たとえば、「やまだ 太郎」とすべきところを「やまだ たろう」としてしまった場合などが該当します。
このような軽微な誤りであれば、KDPの管理画面から直接修正できないため、サポートセンターに問い合わせて依頼します。
問い合わせ時は、「該当書籍のASIN番号」「現在の著者名」「修正後の正しい著者名」を明記してください。
サポート側で確認が取れ次第、数日以内に修正対応されるのが一般的です。
ただし、審査が再度行われる場合があるため、即時反映ではない点に注意が必要です。
KDP公式ヘルプでも「軽微な誤りの修正のみ対応」と明記されています。
つまり、意味が変わるような改名やペンネーム変更は、修正ではなく「別の書籍」として扱われることになります。
私の経験でも、「誤字修正」はスムーズに通った一方で、「著者名全体の変更」は再出版扱いとなり、販売ページも新しく作成されました。
また、表記ゆれ(例:「Taro Yamada」と「TARO YAMADA」など)も場合によっては修正対象です。
ただし、Amazonの検索エンジンは大文字・小文字を区別しないため、実務上は修正の必要がないことも多いです。
どうしても統一したい場合は、販売上の混乱を避けるため、出版前の段階でしっかり確認しておくことが大切です。
実際のKDP操作画面を確認したい方は『Kindle出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説』を見ながら進めるとスムーズです。
ペンネーム変更・改名時の新刊扱いと既刊対応の流れ
ペンネームや本名を変更したい場合は、「既刊の著者名を差し替える」のではなく、新しい名義で新刊として再出版するのが基本対応です。
理由は、KDPのシステムが「著者名」を書籍データの識別情報の一部として扱っているためです。
たとえば、以前の著者名で出版した本を「別名義に統一したい」と考えた場合、既刊はそのまま残し、新しい名義で再登録・再出版する必要があります。
これにより、Amazon上では別の著者ページが生成されますが、「著者等(Contributors)」に旧名を補足することで、読者に関連性を示すことができます。
私自身、改名後にペンネームを変えたい著者をサポートしたことがあります。
その際は、既存の販売ページを削除せず、「新しい名義で同一内容を再出版」する形を取りました。
その結果、レビューは引き継がれませんでしたが、読者が新しい名義でも検索しやすくなり、再出発としては効果的でした。
ポイントは、「改名=ブランド変更」と考えることです。
過去の実績やレビューを保持したい場合は、旧名の書籍を残し、著者紹介ページで新名義への移行を明記するのが安全です。
この方法なら、旧著者ページへの流入も維持できますし、Amazonのアルゴリズムに混乱を与えるリスクも軽減できます。
なお、ペーパーバック版を併売している場合は、著者名変更後の再出版が電子書籍よりも時間がかかります。
紙版ではISBN相当のデータ再割り当てが必要になるため、反映に数日〜1週間程度を見ておくとよいでしょう(公式ヘルプ要確認)。
総じて、Kindle出版で著者名を変更したい場合は、誤字修正ならサポート依頼、改名やペンネーム変更なら再出版という2パターンに分けて考えるのが実務的です。
焦らず、どちらのケースに該当するのかを整理して進めると、トラブルを防げます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
変更せず行える対応とリスク整理:著者名変更以外の選択肢
著者名を変更できない場合でも、実は「著者ページ」や「共同著者の設定」など、間接的に対応できる方法があります。
ただし、それぞれにリスクや限界があるため、意図せず読者を混乱させてしまうこともあります。
ここでは、KDPを運用する上で現実的に選べる代替策と、その注意点を整理します。
著者ページ(Author Central)での表示名変更と書籍の関係
Amazonには、著者自身が管理できる「Author Central(オーサーセントラル)」という仕組みがあります。
ここではプロフィール文や写真を編集でき、表示名も変更が可能です。
ただし、この「表示名の変更」は、KDPに登録されている著者名そのものを変更するわけではありません。
つまり、Author Central上では新しい名前を表示できても、商品ページの著者欄は変わらないという点が重要です。
KDPのデータベースでは、著者名がメタデータとして固定されているため、Amazon内の「販売ページ」と「著者ページ」で一時的に不一致が生じることもあります。
実務上は、ペンネーム変更の過渡期などに「Author Centralの表示名を新名義」「KDPの著者欄を旧名義」にしておくケースもあります。
この方法であれば、旧書籍を残したままプロフィールの更新ができるため、ブランド移行時の橋渡しとしては有効です。
ただし、あまりに異なる名義を使うと「別人のように見える」リスクがあるため、プロフィール文などで経緯を説明しておくと読者に誤解されません。
プロフィール編集や表示名の統一を行う際は『Kindle出版の著者ページとは?作り方と表示改善を徹底解説』もあわせて確認すると効果的です。
複数名義・共同著者扱いの構成と誤解を避けるポイント
もうひとつの方法として、「共同著者(Co-Author)」の仕組みを活用する方法があります。
KDPの「著者等(Contributors)」欄には複数名を登録できるため、旧名と新名を併記することも可能です。
たとえば、「山田花子/HANAKO YAMADA」と2名体制にすることで、検索時にどちらの名義でもヒットするようになります。
ただし、この方法はあくまで「共著として登録する」という扱いです。
Amazonのシステムは別人として処理するため、旧名と新名を“同一人物”と認識してくれるわけではありません。
そのため、プロフィール欄などで「改名に伴い表記を変更しています」と補足することが大切です。
実務的な注意点として、共同著者登録を多用すると、クレジット表示が煩雑になりやすい点があります。
特に、表紙デザインやメタデータの整合性を保つ必要があるため、名義統一を意識する場合は一時的な措置と考えるのが賢明です。
最も安全な運用は、「既刊は旧名義のまま」「新刊は新名義で統一」とし、著者ページ内でリンクを設けて読者を誘導する方法です。
この形であれば、Amazonの検索精度を維持しつつ、過去のレビューや販売履歴も保てます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
まとめ:Kindle出版で著者名を変える前に確認すべき3点
著者名変更は、単なる見た目の修正ではなく、Amazonのシステム構造そのものに関わる部分です。
焦って操作してしまうと、販売履歴やレビューが引き継げないなどの影響もあるため、慎重な判断が必要です。
主著者名は基本変更不可、まずは誤字修正から
KDPの仕様上、著者名(Author)は出版後に自由に変更することはできません。
まずは「誤字や記号ミス」など、軽微な修正に該当するかを確認しましょう。
該当する場合は、KDPサポートに問い合わせることで修正が受理されるケースがあります。
誤字修正と名義変更の違いを混同しないことが大切です。
たとえ一文字違いでも、意味が変わる場合は「別名義」と判断されることがあります。
問い合わせ時は、ASINと正しい著者名を明確に伝え、修正理由を簡潔にまとめておくとスムーズです。
新しい名義なら“新版”扱いで再出版を検討
ペンネーム変更や改名の場合は、既存書籍を編集するよりも「新名義で新版を出版」する方が確実です。
その際、旧著者ページを残しておき、プロフィールで「旧名義での出版実績」を明記すると、読者にも安心感を与えられます。
私の経験でも、改名後に再出版した著者は「旧レビューは引き継げなかったけれど、読者の混乱は防げた」と話していました。
再出版時にはタイトルや表紙を微調整し、Amazonの重複コンテンツ判定を避ける工夫も忘れないようにしましょう。
最終的な判断は「旧実績を残すか、新ブランドとして出直すか」です。
どちらが自分の今後の活動方針に合っているかを整理してから動くことで、著者としての信頼性を守りながらスムーズに移行できます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。