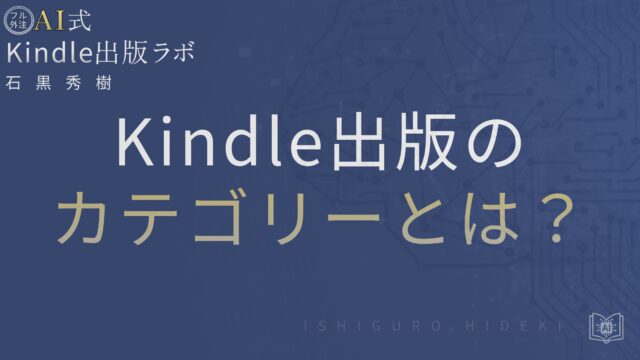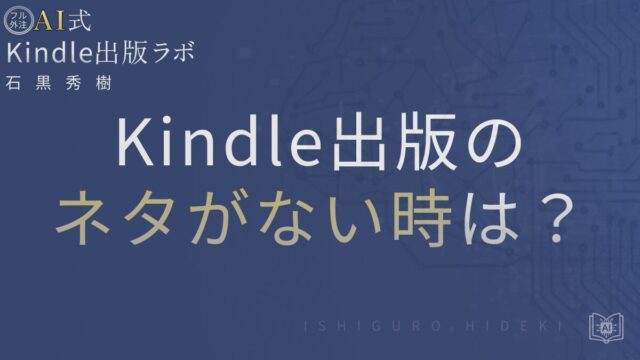Kindle出版を「やってみた」体験レポートと成功のポイント
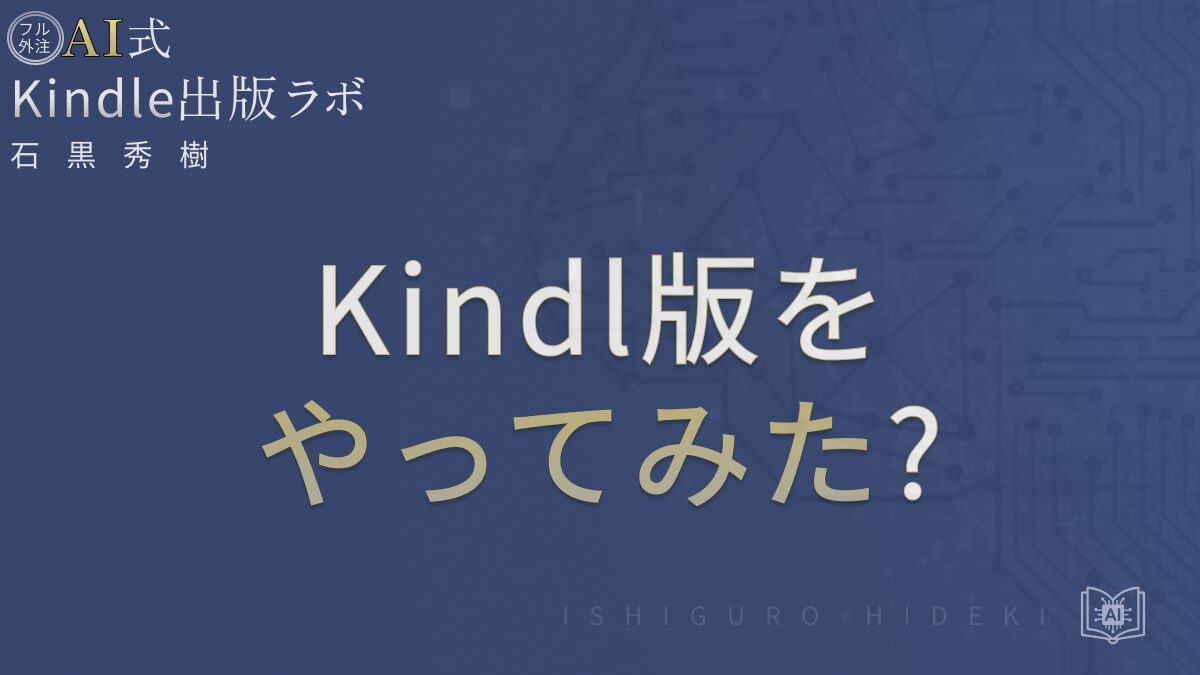
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
最初に結論からお伝えします。 Kindle出版は「やってみた」人だけが、本当の全体像を理解できます。
やってみる前は「難しそう」「本当に売れるの?」と不安に感じる人が多いですが、実際に出版してみると、想像していたよりも手の届く世界だと気づくはずです。
この記事では、Kindle出版を実際に体験した視点から、始め方・制作・収益化までをリアルにまとめています。
初めての方でも「これなら自分でもできそう」と思えるよう、実際の流れと気づきを段階的に解説していきます。
▶ 人気ジャンルや成功事例を参考にしたい方はこちらからチェックできます:
出版ジャンル・成功事例 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版「やってみた」体験が知りたい人へ
目次
Kindle出版は年々注目度が高まっています。
SNSやYouTubeでも「Kindle出版やってみた」という投稿が増えていますが、情報の多くは断片的です。
実際のところ、「どんな流れで出版するのか」「何が一番大変なのか」「どのくらい稼げるのか」といったリアルな体験談が知りたいという声が多くあります。
そこで本記事では、筆者自身がKDP(Kindle Direct Publishing)で電子書籍を出版して感じた流れと、初心者がつまずきやすいポイントをわかりやすく整理しました。
「とにかくやってみたいけど、全体像がつかめない」という方に向けて、実例ベースでお伝えします。
「Kindle出版+やってみた」で検索する人の背景と目的
このキーワードで検索する人の多くは、すでに「Kindle出版に興味があるけれど、まだ行動できていない」段階にいます。
特に次のような悩みを持っている人が多いです。
・自分にも本を出せるのか不安。
・どんな準備や費用がかかるか知りたい。
・実際に出版した人の「リアルな声」を聞きたい。
検索意図としては、How to(やり方)とリアル体験の中間にあります。
つまり、ノウハウだけでなく、「やってみた人の実感」を求めているわけです。
実際、KDPの公式ページを見ても手順は説明されていますが、「どの作業にどれくらい時間がかかるか」「審査で落ちた場合どうすればいいか」といった実務的な部分までは載っていません。
そこでこの記事では、公式情報と実体験のギャップを埋めながら、初心者が出版をスムーズに進めるための現実的な道筋を解説します。
本記事で得られる「実践データ」と「使える知見」
本記事を読むことで、以下の3つの知見を得られます。
1. Kindle出版の流れが一目でわかる。
2. 実際に出版してみた人の「時間・コスト・成果」のリアルデータを知る。
3. 出版後にやるべき運用・改善のポイントを学べる。
特にこれから初めて出版する方にとっては、「どの段階でつまずくか」「どこを工夫すれば効率化できるか」といった部分が具体的にイメージできるはずです。
記事の後半では、筆者の初月の実データや、想定外のトラブルも率直に紹介します。
KDPをこれから始める人が、同じ失敗を避けながら出版を進められるよう、実務的な視点でまとめています。
Kindle出版は、経験の有無よりも「一歩踏み出す勇気」と「仕組みの理解」が大切です。
この記事が、その第一歩を安心して踏み出すためのガイドになれば幸いです。
実践解説:Kindle出版を実際に始めるまでの流れ
Kindle出版は思っているよりもシンプルな流れで進められます。
とはいえ、手順を間違えると後で修正に時間がかかることもあります。
ここでは、出版までの3段階 ― 企画・制作・出稿 ― に分けて、実体験をもとに分かりやすく解説します。
具体的な登録から公開までの詳細な流れは『Kindle出版の始め方を初心者向けに徹底解説|登録から公開までの手順』で手順ごとにまとめています。
公式ガイドの通りにやってもうまくいかないのは、「実務的なコツ」を知らないからです。
それを踏まえて、一つずつ整理していきましょう。
企画段階:テーマ選定と販売戦略の決め方
Kindle出版の最初のステップは「何を書くか」を決めることです。
テーマを選ぶときは、まず「自分が経験してきたこと」か「誰かの役に立てる情報」を軸に考えましょう。
売れやすい題材をより具体的に整理したい方は『Kindle出版のテーマ選びとは?初心者でも売れる題材の見つけ方を徹底解説』もあわせてチェックしてみてください。
たとえば、仕事や趣味で得たノウハウ、生活を工夫するアイデアなどは立派な出版テーマになります。
よくある失敗は、「需要がありそうだから」という理由だけでテーマを決めてしまうことです。
こうした本は一見魅力的に見えても、内容にリアリティがないため、レビューで信頼を失うケースが多いです。
実際に書いてみると分かりますが、自分の経験や考えをもとにしたテーマの方が継続して執筆できます。
Amazonで売れている書籍を参考にしつつ、「自分だから書ける切り口」を意識することが大切です。
また、販売戦略も最初に決めておきましょう。
出版直後に多くの読者に届けるためには、Kindle Unlimited(読み放題)への登録がおすすめです。
読者が無料で読める分、ページ閲覧数による印税(KENP報酬)を得られる仕組みがあります。
ただし、KDPセレクト(独占配信プログラム)に登録すると、他の電子書店での販売が制限されるため、複数サイト展開をしたい人は注意が必要です。
このあたりは「公式ヘルプ要確認」となりますが、戦略次第でどちらを選ぶか変わります。
テーマと戦略を決めたら、章立て(目次構成)を先に作るのがおすすめです。
構成を決めてから本文を書くと、迷いが減り、出版までのスピードが大幅に上がります。
制作段階:原稿作成・Wordや目次設定のポイント
原稿は、Microsoft WordまたはGoogleドキュメントで作成するのが一般的です。
特にWordでの書式設定や整形のコツは『Kindle出版×Word原稿の作り方とは?入稿手順と整形ポイントを徹底解説』で詳しく解説しています。
特にWordはKDPとの相性が良く、後で「論理目次(リンク付き目次)」を自動で生成できます。
ここで重要なのが「見出しスタイル」の設定です。
単に文字を大きくしたり太字にするだけでは、KDPが「章」として認識しません。
見出し1を章タイトル、見出し2を節タイトルとして設定し、Wordの「参考資料」タブから「目次」を挿入します。
この方法で作れば、KDPにアップロードしたときに自動的にリンク付き目次として反映されます。
もう一つの注意点は、画像や表の配置です。
Word上での見た目が正しくても、KDP変換時にズレることがあります。
画像は「文字列の折り返し」を「行内」にしておくと安定します。
また、フォントや余白などを細かく装飾しすぎると、端末によってレイアウトが崩れる場合があります。
公式では「シンプルな書式を推奨」とされていますので、可読性重視で作るのが安全です。
私自身、最初の原稿ではフォントサイズや余白をいじりすぎて、Kindle端末で改行が崩れました。
結局、Wordのデフォルト設定に戻したところ、スムーズに審査を通過できました。
出稿段階:KDP入稿・審査・価格設定・Amazonでの公開
原稿が完成したら、KDP(Kindle Direct Publishing)のマイページで出版登録を行います。
手順はシンプルで、書籍情報(タイトル・著者名・紹介文)を入力し、原稿ファイル(.docxなど)と表紙画像をアップロードします。
KDPでは「内容プレビュー」と「審査」が最終関門です。
プレビューでは端末ごとの表示を確認できるので、必ずチェックしましょう。
審査は通常1〜3日で完了しますが、内容によっては数日かかる場合もあります。
特に引用・出典の扱い、画像の著作権、成人向けコンテンツの表現などには厳格な基準があります。
不明点がある場合は、公式ヘルプを確認するか、サポートに問い合わせてください。
価格設定は、自分で自由に決められますが、初心者の方は300〜600円程度から始めるのが現実的です。
70%印税の条件や具体的な価格戦略については『Kindle出版の価格設定とは?70%印税を得るための条件と最適価格を解説』でより踏み込んで解説しています。
KDPの印税は70%または35%のどちらかを選べますが、70%を選ぶにはAmazon.co.jpでの価格設定や配信地域の条件があります(詳細は公式要確認)。
最後に、公開ボタンを押すとおおむね1日以内にAmazon上に反映されます。
初めて自分の名前で本が並んだ瞬間は、きっと忘れられない体験になるはずです。
実際に出版してみると、手順自体は難しくなくても「地味な確認作業が多い」と感じるでしょう。
ですが、そこを丁寧に行うことで審査の通過率が上がり、読者にとっても読みやすい本に仕上がります。
Kindle出版は、地道な作業を積み重ねるほど品質が上がる仕組みです。
焦らず、確実にステップを進めていきましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
体験レポート:私がやってみた「初月の結果と学び」
実際にKindle出版をやってみて感じたのは、想像していたよりも地道で、でも手応えのある作業だということです。
初月から大きな収益を得たわけではありませんが、「一冊を形にする力」と「読者の反応を見る楽しさ」は、何にも代えがたい経験でした。
ここでは、私自身のデータや学びをもとに、これから始める方が現実的なイメージをつかめるよう、率直に共有します。
数字だけでなく「気づき」も含めたリアルな体験談として読んでください。
時間・コスト・作業量:私の実データ公開
初めての出版にかかった期間は約3週間でした。
仕事の合間に進めたので、1日2〜3時間程度の作業です。
内訳としては、原稿執筆に約20時間、構成調整やWordでの整形に10時間ほど。
最初の出版では、執筆よりもKDPの仕様理解に時間がかかりました。
特にWord目次の設定や、画像サイズの調整など、細かい部分でつまずく人は多いと思います。
費用面では、ほとんどかかっていません。
Wordをすでに使っていれば、0円で出版できます。
私は表紙デザインだけ外注し、Canvaでデザイン案を作った上でデザイナーに依頼しました。
費用は3,000円ほどでしたが、仕上がりの印象が大きく変わったので、結果的には良い投資でした。
もし自作する場合は、CanvaやPhotopeaなど無料ツールでも十分対応できます。
ただ、印象的な表紙を作るには、文字のバランスやフォント選びに時間をかける必要があります。
全体を通して感じたのは、「作業量の多さよりも情報の整理」が重要だということです。
執筆自体よりも、KDPでの登録手順や審査の仕様を理解するほうが時間を要しました。
一度手順を覚えれば、2冊目以降はぐっとスピードが上がるので、最初の1冊は学びとして割り切るのがコツです。
印税・売上構造:電子書籍から得られた収入と仮説
初月の売上は約2,800円でした。
販売数は15冊、Kindle Unlimitedのページ閲覧(KENP)報酬が全体の約6割を占めていました。
つまり、購入よりも「読み放題」で読まれる割合のほうが多かったということです。
KDPでは印税率を35%か70%から選べます。
私の場合、70%を選択したため、1冊あたり約210円の印税が発生しました(価格300円設定)。
ただし、70%印税は販売価格の条件やAmazon.co.jpでの配信地域指定など、細かいルールがあります。
ここは「公式ヘルプ要確認」となりますが、仕組みを理解しておくことが大切です。
出版後に感じたのは、売上よりも「アクセスデータを見る習慣」が重要だという点です。
Amazon KDPのダッシュボードでは、日別の閲覧数・販売数・KENPページ数が確認できます。
このデータを見ながら、タイトルや説明文を修正すると反応が変わることがありました。
たとえば、タイトルの前半に「体験談」を入れただけでクリック率が上がったこともあります。
SEOというより、「読者の関心を意識した一文の違い」が結果に直結するのだと実感しました。
想定外のトラブルとその対応策(やってみたからこそ分かった)
一番焦ったのは、初回審査で「目次エラー」が出たときです。
Word上では正常に見えていたのに、KDPの変換後にリンクが切れていたのです。
原因は、章タイトルの一部に「見出しスタイル」が適用されていなかったことでした。
修正して再アップロードしたところ、無事に審査を通過しました。
このような不具合は、プレビューで必ず確認すれば防げます。
公式でも推奨されている「Kindle Previewer」を使えば、端末ごとの表示を再現できます。
もう一つの想定外は、公開後にレビューがすぐに反映されなかったことです。
Amazonではレビューが一定の条件を満たさないと表示されないことがあるため、焦らず待つしかありません。
公式対応の範囲外ではありますが、これは多くの著者が経験する“あるある”です。
また、販売開始直後に価格を頻繁に変更すると、ランキングや検索順位に影響が出ることがあります。
価格設定は初期段階でしっかり決めておくのが無難です。
Kindle出版では、すべてが自分の裁量で決められる一方、責任も伴います。
ですが、トラブルを一つずつ乗り越えることで、出版の仕組みが深く理解できます。
“やってみた”経験こそが、次の成功の最短ルートです。
最初の不安や戸惑いも、振り返れば貴重な教材になります。
焦らず、1冊ずつ積み上げていきましょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
注意点・長期運用:“やってみた”から次のステップへ
初出版を終えると、多くの人が「次はどうすればいいの?」と感じます。
Kindle出版は一度出したら終わりではなく、むしろそこからが本当のスタートです。
ここでは、出版を継続的に発展させていくための考え方と、実務的な運用のコツを紹介します。 最初の1冊は“練習”、2冊目以降からが“戦略”という意識を持つと、長く続けられます。
リピート出版やシリーズ化を見据えた準備
1冊出版すると、すぐに次の構想が浮かぶ方も多いです。
このとき意識したいのは「シリーズとして読まれる流れ」を作ることです。
たとえば、同じテーマの中で切り口を変えたり、ステップアップ形式で内容を分けるなどです。
「第1章で基礎を語り、第2章では実践へ」といった形にすると、次作への導線が自然につながります。
また、シリーズ化を前提にすると、デザインやタイトルの統一感も重要です。
表紙のトーンやレイアウトをそろえるだけで、読者はシリーズとして認識しやすくなります。
Wordファイルのテンプレートを共通化しておくと、目次構造やフォント設定も統一でき、制作時間を短縮できます。
一方で、よくある失敗は「とりあえず次を出す」ことです。
勢いで出すと品質が安定せず、シリーズ全体の評価を下げてしまう場合があります。 “早く出す”よりも“ブランドを築く”意識で進めると、結果的に読者の信頼を積み重ねやすくなります。
ペーパーバック・紙書籍との使い分け(日本版KDP対応)
KDPでは、電子書籍だけでなく「ペーパーバック(紙版)」も発行できます。
ただし、これはあくまで電子書籍を基盤にしたオプションと考えるのが現実的です。
日本版KDPでは、印刷・配送はAmazon側で対応しますが、24ページ以上という制限があります。
また、「カラー印刷や画像を多用する場合は印刷コストが上昇します。価格設定は公式ヘルプの計算ツールで事前確認すると安心です。」
実際、私が試したときも「紙で読みたい」という読者層は一定数いました。
とくに自己啓発・ノート形式の本では、書き込みたい人が多く、ペーパーバック版が意外と好評でした。
一方で、デザイン重視の表紙やレイアウト崩れが起きやすいため、電子版とは別ファイルで調整したほうが安全です。
「『電子=手軽に読める』『紙=手元に残したい』など読者の行動特性に合わせた企画設計を意識すると効果的です。」
ただし、「KDPのペーパーバック機能には仕様変更が生じる場合があります。最新情報は公式ヘルプを必ず確認してください。」
海外向けの仕様とは異なる点もあるため、「Amazon.co.jp専用の設定」で進めるのが確実です。
継続出版で差がつく「読者目線」と「運用体制構築」
Kindle出版を継続するうえで、最も重要なのは「読者目線を保ち続けること」です。
最初は「とにかく出す」ことが目的でも構いませんが、次第に「読まれること」「リピートされること」がゴールに変わります。
そのためには、レビューや読者の声をしっかり見て改善する姿勢が欠かせません。
たとえば、「もっと図が欲しかった」「章ごとのまとめがあると嬉しい」など、レビューの要望は次作のヒントになります。
読者のフィードバックを分析して改善していくことが、継続的な出版の最大の学びになります。
また、出版を続けるほど、制作・入稿の作業がルーチン化されていきます。
テンプレート化や外注の仕組みを作っておくと、ストレスを減らして長く続けられます。
たとえば、次のような体制づくりが効果的です。
・表紙デザインは固定のテンプレート化
・校正チェック用のリストを用意
・販売後のSNS投稿・レビュー確認を週1回にまとめる
「こうした“小さな仕組み”を整えることで、次回以降の出版作業が安定し、時間効率も向上します。」
出版の継続は「作業の積み上げ」ではなく「仕組みの積み上げ」です。
最初の1冊で学んだことをベースに、少しずつ自分のスタイルを築いていきましょう。
まとめ:Kindle出版を“やってみる”価値と次の一歩
Kindle出版を「やってみた」ことで分かるのは、想像以上に奥が深い世界だということです。
出版はゴールではなく、学びと表現のスタート地点でもあります。
最初は小さな成果でも、そこから得られる経験は大きな財産です。
自分の言葉が誰かに届く感覚は、何度経験しても新鮮で、やりがいがあります。
これから始める方は、まず1冊を出すことに集中してください。
その1冊が、自分の未来の基準になります。
そして、次に進むときは「より読まれる工夫」「より良い体験の提供」を意識してみてください。
それが、Kindle出版を長く続ける上での最大の鍵です。
“やってみた”から“続けていく”へ。
「あなたの一冊が、誰かの日常を変える小さな灯になるかもしれません。」
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。