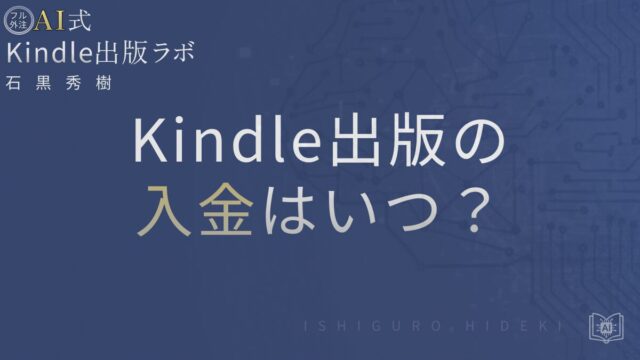Kindle出版で儲ける仕組みとは?印税と収益計算を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「本当に儲かるのか」と疑問を感じる人は多いです。
私自身、最初は「売れたら70%の印税がもらえる」と聞いて期待しましたが、価格設定やコストを理解していないと赤字にもなり得ることがわかりました。
この記事では、儲かる・儲からないの分かれ目となる仕組みを、初心者でも理解できる順序で解説します。
結論から言うと、Kindle出版は仕組みを理解すれば利益を狙えるモデルですが、曖昧な状態で始めると「思っていたより稼げない」状態に陥りやすいのが実情です。
そのため、この記事ではAmazon.co.jp向けKDPのルールと収益構造を前提に、どこで差が生まれるのかを整理しながら進めていきます。
▶ 印税収入を伸ばしたい・収益化の仕組みを作りたい方はこちらからチェックできます:
印税・収益化 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で本当に儲かる?結論と前提条件をわかりやすく解説
目次
Kindle出版は「無料で始められる副業」として話題になりやすい一方で、「出したけどほとんど収益にならなかった」という声も多いです。
収益性は「印税率の選択」「価格設定」「ジャンル」「読まれる仕組み」の4つが大きく影響します。
この章では、まず“儲かると言われる理由”と“実際の現実”を整理し、正しいスタート地点に立つための理解を深めます。
Kindle出版が儲かると言われる理由と現実
Kindle出版が儲かると言われる背景には、「最大70%の印税」「在庫不要」「低コスト」が挙げられます。
実際、私が初めて制作した教材系の電子書籍でも、制作コストを抑えたことで黒字化自体は早く実現できました。
特に、価格を適正に設定し、一定数の既読ユーザーを継続的に獲得できれば、1冊で長期的に収益が入るケースも存在します。
しかし現実として、「出しただけでは売れない」という声も少なくありません。
読者に見つけられないまま埋もれてしまうケースや、印税構造を理解せずに価格設定を間違えることで、配信コストが高すぎて実質赤字になることもあります。
このように「儲かる可能性はあるが、正しい前提を知らないと思ったより稼げない」というのが実務的な実感です。
「儲け」を判断するための前提(日本のAmazon.co.jpでのKDP仕様)
Kindle出版の儲けを判断するには、自分の収益が「電子書籍の販売印税」「Kindle Unlimitedなどの読み放題収益」「必要な配信コスト」を加味したうえで決まることを理解する必要があります。
Amazon.co.jpを対象とする場合、70%ロイヤリティを選択できる条件は「一定の価格帯」「対象地域への設定」「KDPセレクト登録が必要なケースがある」などが組み合わさります。
なお、KDPセレクトへの参加が常に必須というわけではなく、日本の70%ロイヤリティ適用条件は価格帯・対象地域・配信コスト等の要件で決まります。最新の適用要件は公式ヘルプ要確認。
「70%=セレクト必須」と誤解する人が多い傾向にあります。
現在の日本向け仕様は、Amazonの公式ヘルプページで随時確認する必要があります。
また、Kindle Unlimitedの収益は「読まれたページ数による分配」となるため、販売印税とは計算方法が異なります。
このように、KDP仕様の前提を理解せずに「とりあえず70%で売ればいい」と考えると、配信コストや価格帯の設定を誤って収益が伸びない原因になります。
ここから先の章では、さらに印税率の違いや価格設定のポイントを踏まえ、どこで利益が変わるのかを具体的に確認していきます。
Kindle出版全体の報酬の流れを先に押さえておきたい場合は『Kindle出版の報酬とは?ロイヤリティ計算と稼ぎ方を徹底解説』もあわせて読んでおくと、この記事の位置づけが理解しやすくなります。
Kindle出版の収益構造:印税率70%と35%の違いと条件
Kindle出版の利益が大きく変わるポイントは「印税率の選択」です。
KDPではおもに「70%」と「35%」の2つが選択でき、どちらを選ぶかで収益に大きな差が出ます。
ただし、70%を選ぶには一定の条件があり、知らずに設定すると自動的に35%になるケースもあるため注意が必要です。
私自身、初期の頃に価格帯を誤って設定し、本来70%でいけた本が35%になってしまい後 “もう少し確認しておけば…” と後悔したことがあります。
ここでは、印税率の基本構造を整理しながら、収益の差がどこで生まれるかを理解していきます。
70%と35%の具体的な条件やシミュレーションを詳しく知りたい方は『Kindle出版のロイヤリティとは?70%と35%の違いと条件を徹底解説』もチェックしてみてください。
70%ロイヤリティの適用条件(価格帯・対象地域・KDPセレクトなど)
70%ロイヤリティが適用されるのは、一定の条件を満たした場合のみです。
主な条件は以下のとおりです。
・販売価格がAmazon指定の範囲内であること(正確な価格帯は公式ヘルプ要確認)。
・対象となる販売地域に日本(Amazon.co.jp)が含まれている
・KDPセレクトへの登録が必要な場合がある(Amazonの仕様変更履歴により変化するため公式確認が必須)
ここで特に注意したいのが「価格帯」と「KDPセレクト」の扱いです。
価格を最低ライン以下に設定した場合は自動的に35%扱いになります。
また、70%印税を狙っている人の多くは「とりあえずKDPセレクトに入れる」と判断しやすいですが、これは販売戦略によっては必ずしも正解ではありません。
とはいえ、初心者の場合は条件をそろえやすい70%を選ぶほうが収益が安定しやすい傾向があります。
35%の場合の特徴と使われやすいパターン
35%ロイヤリティは「価格が条件外」「70%の条件を満たさない」「あえて低価格で広く配布したい」といった場合に適用されます。
低価格の集客目的や、シリーズの第1巻を普及させたい場合に使われることがあります。
私もシリーズ展開を目的に、第1冊目だけ低価格の35%で出し、2冊目以降を70%にしたことがあります。
ただし、収益を目的とする場合は、35%だと利益率が大幅に下がるため、その意図を明確にしておく必要があります。
「安くすれば売れる」という期待だけで35%を選ぶと、販売数が伸びなかった場合に赤字リスクが高まるため慎重に判断しましょう。
KDPセレクトやKindle Unlimitedによる収益の変化
KDPセレクトに登録すると、Kindle Unlimited(読み放題サービス)対象になります。
読み放題の場合、印税ではなく「既読ページ数」に応じた分配方式となります。
これは「KDPセレクト グローバル基金」という枠から、読まれたページに対して分配される仕組みです。
私の経験では、ジャンルによっては販売収益よりも読み放題のページ収益が上回るケースもありました。
ただし、読み放題向きでない内容(超専門書やニッチな分野)の場合は、販売型を優先したほうが有利な場合もあります。
また、読み放題の対象にするということは、KDPセレクト専属配信(他プラットフォームに出せない)になるため、販路戦略とも合わせて考える必要があります。
このように、印税方式と読み放題方式の違いを理解したうえで、「販売型で稼ぐか」「既読型で稼ぐか」を考えることが重要です。
続く章では、収益をより具体的にイメージできるよう、価格設定や配信コストの考え方を整理します。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
利益を最大化するKindle出版の価格設定と収益計算の考え方
Kindle出版で「どの印税率を選ぶか」と同じくらい重要なのが、「価格をどう設定するか」です。
印だけ見てここまで意識しない初心者も多いのですが、実は同じ印税率でも価格設定を1つ間違えるだけで、利益が倍以上変わることがあります。
私自身、最初は販売価格だけを見て「このくらい手取りになるだろう」と感覚で考えていたのですが、配信コストの存在を知ってから考え方が大きく変わりました。
この章では「収益の計算式」「赤字の仕組み」「読み放題(Kindle Unlimited)の考え方」の3つを順番に整理しながら、価格戦略を立てるための基礎となる部分を解説します。
販売額−配信コスト=手取り額の基本式
Kindle出版の収益計算の基本式は以下のとおりです。
販売額 × 印税率 − 配信コスト = 手取り額
実際にいくらで販売すればよいか、具体的な価格帯の決め方は『KDPの価格設定とは?70%印税を得るための条件と最適価格を解説』でステップごとに解説しています。
ここでいう「配信コスト」とは、電子書籍のデータサイズに応じて発生する費用です。
特に画像を多用した作品や、リッチなデザインの本はファイルサイズが大きくなりやすく、70%印税を選んでいる場合は配信コストが引かれる点に注意が必要です。
一方、35%印税を選択した場合は配信コストが引かれない仕組みです。
この違いは意外と見落とされやすく、画像主体の作品ではあえて35%を選ぶというケースもあります。
ただし、利益面では70%のほうが条件が揃えば有利なことが多いので、画像量とのバランスを見ながら選ぶ必要があります。
また、実務上は「想定読者がいくらなら買いやすいと感じるか」も加味して価格を検討します。
価格設定を誤ると「売れても赤字」になる理由
販売価格が低すぎると、配信コストに対して手取り額が極端に小さくなり、場合によってはほとんど利益にならないことがあります。
たとえば、70%印税を選んでいても、画像が多くデータサイズが大きい場合、1冊あたり数円〜数十円単位で配信コストを取られることがあります。
この状態で販売価格を低く設定しすぎると、1冊あたりの利益がほとんど残らないか、実質的に「ほぼトントン」の状態に陥ります。
私も経験がありますが、意外と「配信コストがどのくらいかかるか」を意識して価格設定を見直すと、利益の伸びが改善されるケースがあります。
「安いほうが売れるだろう」と思って極端に低価格で設定すると、販売数が伸びなかった場合に実質的な赤字に近い状態になりやすいので注意が必要です。
価格は「読者の価値認識」「ジャンルの相場」「配信コスト」などを基準に決めることが大切です。
Kindle Unlimitedの既読ページ数収益の考え方
KDPセレクトに登録すると、Kindle Unlimited(KU)に加入している読者は無料でその本を読むことができます。
この場合、収益は「読まれたページ数」に応じて分配される仕組みとなっています。
分配額は「KDPセレクト グローバル基金」と呼ばれる総額から按分されるため、1ページあたりの単価は月ごとに変動します。
私の経験では、読まれやすいテーマの本やストーリー型の書籍は、販売よりもKU収益のほうが大きくなる例もありました。
一方で、ニッチな専門書や「必要な部分だけ読まれる」タイプの本だと、販売型のほうが収益性が高いこともあります。
KU収益を安定させたい場合は「最後まで読まれやすい構成」「目次の流れ」「読み進めたくなるリズム」なども戦略として重要になります。
このように、価格設定は「販売型」「読み放題型」のどちらを軸にするかによって変わるため、収益モデルを意識した構成が求められます。
次の章では「なぜKindle出版で儲からないケースがあるのか」というポイントを整理しながら、利益を損なう原因と改善策について解説します。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版が儲からないと言われる原因と改善ポイント
「Kindle出版は稼げない」「結局ほとんど売れない」という声が出る背景には、いくつかの共通した原因があります。
私も最初の頃は販売画面すら見てもらえず、1か月で数冊しか読まれなかった経験があります。
多くの場合、「仕組みが悪い」のではなく、「見つけてもらえない」「信頼されない」「需要がずれている」の3つが原因です。
この章では、それぞれの落とし穴と改善の方向性を整理します。
“売れない理由”を構造的に把握すると、改善の優先順位が明確になり、収益化までの道が見えやすくなります。
検索で見つからない(タイトル・キーワード設計ミス)
Kindle出版で最も多い失敗は、「Amazon内で読者に発見されない」ことです。
タイトルや説明文に適切なキーワードが含まれていないと、検索結果に表示されにくくなります。
たとえば、初心者向けの解説書なのに専門的なタイトルにしてしまうと、検索ニーズとずれてしまうケースがあります。
また、「Amazonの検索バーに出るサジェスト(予測キーワード)」を無視してタイトルをつけてしまい、結果的に需要の薄いワードで勝負してしまうこともあります。
私も初期にニッチな表現を使いすぎて検索露出が極端に低くなった経験がありました。
改善のポイントとしては、「実際に検索されているキーワード」「悩みを表す言葉」「ターゲット読者が使いそうな表現」を踏まえてタイトルとキーワード欄を整えることです。
内容が薄くレビューが伸びないケース
内容が薄い本は、一度買われてもレビューで低評価がついたり、途中で読まれなくなることがあります。
特に「タイトルが魅力的なのに内容が期待を下回る」場合は、読者の不満につながりやすくなります。
私自身、読み放題でたまたま手にとってもらえた本が「期待より情報が少ない」と評価され、リライトを余儀なくされた経験があります。
レビューが伸びないと検索順位にも影響し、結果的に新規読者に届かなくなります。
改善には「1冊の中で何を解決する本なのかを明確にし、情報密度を適切に高める」ことが大切です。
また、無理に内容量を増やすのではなく、「一貫性」と「実用性」を意識することが評価につながります。
ジャンル選びの失敗と需要リサーチ不足
需要の少ないジャンルや、競合が強すぎるジャンルを選ぶと、収益化が難しくなることがあります。
特に初心者が「自分が書きたい内容」だけで出版すると、市場とのズレが生じることがあります。
公式としてジャンル選択の正解があるわけではありませんが、実務上は「検索ボリュームがあり、レビュー件数が適度なジャンル」を狙うと成果につながりやすくなります。
私は市場調査を行わずに専門性が高すぎるテーマで出した本がほとんど読まれず、後からジャンルの再選定を行ったことがあります。
出版前にAmazonランキングやカテゴリ上位本を確認し、「読まれているテーマ」「埋もれにくい切り口」を見極めることで、初速が出やすくなります。
次の章では、どのようなジャンルが比較的収益につながりやすいのか、注意が必要なテーマはどこかを整理していきます。
Kindle出版で儲けやすいジャンルと注意すべきジャンル
出版ジャンルの選び方は、Kindleで「稼げるかどうか」に直結します。
内容が良くても、需要がほとんどないジャンルに参入すると収益化までに時間がかかります。
一方で、「安定して検索されるテーマ」や「読了されやすい構成のジャンル」は初心者でも成果につながりやすい傾向があります。
ただし、ジャンルによってはKDPの規約や審査で引っかかりやすく、掲載が制限される可能性もあるため注意が必要です。
この章では、「初心者でも利益化しやすいジャンル」と「扱いに慎重さが求められるジャンル」をわかりやすく整理します。
初心者に向くジャンル(需要が安定しやすい領域)
初心者が取り組みやすく、比較的安定して需要があるジャンルとしては、以下のような領域が挙げられます。
・ライフハック(習慣術・時間術など)
・副業やスキル習得系(ブログ・在宅ワーク・スキル解説)
・自己啓発(小規模ながら安定した需要)
・マニュアル形式のノウハウ(手順解説型の構成)
・初心者向けの入門本(専門書よりも読まれやすい)
私の経験上、特に「〇〇を始める人向けの入門ガイド」は一定の需要があり、レビューも得やすい傾向があります。
また、検索して購入されるだけでなく、Kindle Unlimitedで「とりあえず読む」対象にも選ばれやすいため、既読ページ収益を得やすい点も魅力です。
重要なのは「すでに上位が強すぎるジャンルに正面から挑まないこと」と「自分の経験を活かせる切り口で差別化すること」です。
たとえば「副業」ジャンルでも「会社員が夕方1時間でできた実例」など、体験ベースでニッチに切ると競争を避けながら需要を拾いやすくなります。
どのテーマを選べば収益につながりやすいかをより具体的に知りたい場合は『Kindle出版で売れるジャンルとは?初心者向けの選び方と成功の秘訣を徹底解説』も参考にしてみてください。
KDP規約で注意が必要なジャンル(抽象的に触れる)
一方で、KDPの規約上、取り扱いに注意が必要なジャンルも存在します。
Amazonでは、センシティブな表現が含まれるコンテンツや、露骨な描写・刺激的な内容を含むジャンルは制限対象となることがあります。
また、過度な煽り表現や誤解を招く健康系・投資系の内容にも注意が必要です。
公式上は「ガイドラインに違反する内容は禁止」と記載されていますが、実務上は「境界線があいまいなジャンル」もあり、レビュー審査でリジェクトされるケースもあります。
私も過去に「用語や表現の抽象化が不十分」と判断され、タイトルと説明文の修正を求められた経験があります。
もしデリケートな領域に触れる場合は、“教育・注意喚起の文脈であること”を明確にし、誤解を招く言い回しを避けることが重要です。
また、健康・投資関連では「効果を断定しない」「個人の体験レベルに留める」「公式情報やエビデンスを併記する」ことで信頼性が高まります。
ジャンル選びの段階で規約のグレーゾーンを避け、継続的に出版できるカテゴリーを選ぶことが長期的な収益安定につながります。
次の章では、利益を伸ばすためのステップと継続戦略を具体的な流れとして整理していきます。
Kindle出版で安定して儲けるためのステップと継続戦略
Kindle出版は「1冊出して終わり」のモデルではなく、改善と再展開を前提とした継続戦略があると収益が安定しやすくなります。
実際、私が最初に出した本も初月は数冊でしたが、リライトとタイトル改善、シリーズ展開により継続的な収益につながりました。
この章では、「市場リサーチ→出版→改善→シリーズ化」という成長ステップと、広告や外部発信の使い方について解説します。
大切なのは“1冊を出すまで”ではなく“出してからどう育てるか”という視点を持つことです。
市場リサーチ→出版→改善→シリーズ化の流れ
Kindle出版で安定的に収益を積み上げるための代表的な流れは以下のとおりです。
1. 市場リサーチ:需要のあるテーマを確認する
2. 出版:ニーズに沿った初稿をリリース
3. 改善:レビューや検索動向を見てリライト
4. シリーズ化:関連テーマで複数展開
市場リサーチでは、Amazonランキングやサジェストキーワードを確認し、「読者が探している悩み」を軸にテーマを決めます。
出版後は、レビューや既読ページ数の推移を見ながら改善点を洗い出し、タイトル・説明文・本文の調整を段階的に行います。
実際、タイトルを「抽象系」から「悩み直球型」に変更しただけで表示順位が上がり、売上が伸びた経験があります。
シリーズ化は「1冊読んだ人が次も読みたくなる構造」を作ることが目的です。
たとえば「副業入門→実践編→稼ぐコツ→拡張戦略」など、階段的なシリーズ展開にすると継続読者が増えやすくなります。
シリーズが増えるほど“1冊から複数冊へ繋がる収益導線”が生まれるため、長期的な収益安定につながります。
広告・外部発信の使い方(Amazon広告は赤字リスクに注意)
出版直後の書籍を認知してもらう方法として、「Amazon広告(スポンサープロダクト広告)」や「SNS発信」「ブログ連携」があります。
Amazon広告は、本の露出を高める効果がありますが、クリック単価(CPC)によっては広告費が収益を上回ることもあるため慎重な運用が必要です。
特に、レビューが少ない初期段階で高額なキーワードを狙うと、広告費だけが膨らみやすくなります。
実務的には「まずは小さな予算で広告を試し、どのキーワードでCTR(クリック率)とCVR(購入率)が高いかを検証する」のがおすすめです。
また、個人ブログやX(旧Twitter)、YouTubeなどで「出版の背景」や「内容の一部」を発信することで、興味を持った読者からの購入や読み放題アクセスが期待できます。
「著者=そのジャンルの経験者」という認識が読者に伝わることで、信頼性が高まりレビューもつきやすくなります。
広告だけに頼らず、「市場での発見性+著者としての存在感」をセットで高めることが、Kindle出版の継続的な収益につながります。
次の章では、紙の出版も検討したい人向けに、ペーパーバック出版の収益構造と注意点について補足します。
(補足)ペーパーバック出版で利益が変わるケース
Kindle出版は電子書籍が中心ですが、ペーパーバック(紙の本)も併せて出版することで利益構造が変わる場合があります。
特に、ビジネス系や資格系ジャンルでは「紙で読みたい」という読者層が一定数存在するため、電子書籍だけよりも収益の幅が広がるケースがあります。
ただし、ペーパーバックには印刷コストがかかるため、価格設定が電子書籍とは異なる点に注意が必要です。
電子書籍で収益モデルを理解したうえで、紙の出版を追加検討するのが安全な流れです。
印刷コストと24ページ以上の条件を理解する
ペーパーバック出版には、KDPによって「本文が24ページ以上あること」という最低ページ数の条件があります。
さらに、印刷形式(白黒/カラー)、ページ数、裁断サイズによって印刷コストが変動し、その分が販売価格から差し引かれる形になります。
たとえば、白黒印刷でモノクロ構成のペーパーバックであれば印刷コストを抑えやすいですが、写真やカラー図版を多用する場合はコストが高くなります。
そのため、電子書籍よりも価格を高めに設定するのが一般的です。
私の場合、電子書籍を800円で販売していた本を1,380円でペーパーバック化しましたが、紙版のほうが「物として所有したい」「線を引きながら読みたい」というニーズを拾い、別ラインで安定的に販売され続けています。
ペーパーバックは原価が存在するため、価格帯の検討と利益計算を電子書籍とは別で考える必要があります。
また、紙版を出すことで「電子+紙の両方で上位表示される」ケースもあり、結果的に電子版の露出が増えることもあります。
ただし、いきなりペーパーバックから始めるのではなく、「電子書籍で反応を確認してから紙を追加する」という流れのほうが実務的にはリスクが低くなります。
まとめ:Kindle出版は「仕組み理解+価格設定」で儲けやすくなる
Kindle出版で儲けられるかどうかは「運」ではなく、「印税率」「価格設計」「ジャンル選び」「改善と展開」という仕組みの理解度で大きく左右されます。
70%印税やKindle Unlimitedの収益構造を理解し、販売価格やコストとのバランスを考えることで、狙って利益を出すことができます。
また、検索されやすいタイトル設計やレビューにつながる内容構成、需要のあるジャンル選びも重要なポイントです。
出版後は改善とシリーズ展開を行い、必要に応じてペーパーバック化や広告、外部発信などを組み合わせることで、安定的な収益につながります。
Kindle出版は「1冊で終わる副業」ではなく、「仕組みを理解して継続すれば育つ資産型モデル」です。
まずは小さく出版して仕組みを体験し、少しずつ改善と展開を進めることで、長期的に収益が積み上がる状態を作っていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。