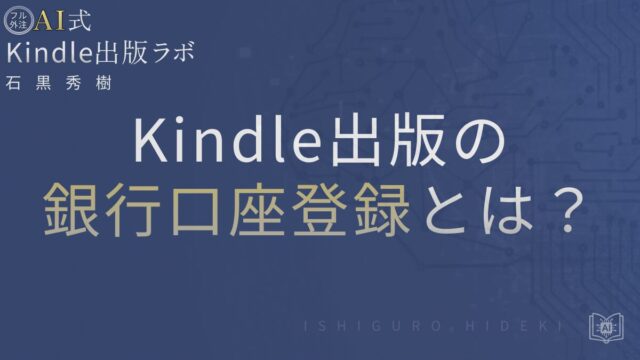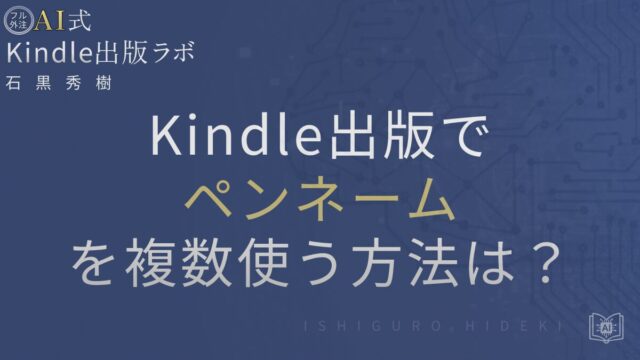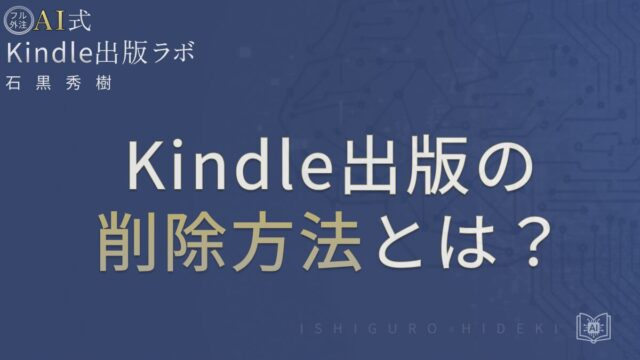Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようとすると、まず気になるのが「審査って何を見られるのか」「どのくらい時間がかかるのか」という点です。
特に初めて出版する人の多くが「72時間以内には公開されるらしい」という噂だけを頼りに進めてしまい、現実とのギャップに焦るケースがよくあります。
実際は、原稿内容だけでなく、権利、メタデータ、表紙の整合性まで総合的に確認されるため、ちょっとした不備でも審査が長引くことがあります。
この記事では、私自身が初出版時に差し戻しを経験した失敗も踏まえつつ、Kindle出版における審査の全体像と基本概念をわかりやすく整理していきます。
まずは「Kindle出版 審査」が何を指すのかをシンプルに押さえるところから始めましょう。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
「Kindle出版 審査」とは?—審査の一言定義と全体像をまず把握
目次
審査を正しく理解することが、出版準備の第一歩です。
焦って「とにかく出す」ことを優先すると、公開が遅れるどころか、差し戻しメールに何度も対応することになります。
ここでは、Kindle出版の審査がどのような基準で行われるのか、そして公開までの流れを整理しておきます。
Kindle出版の審査=内容・権利・メタデータ・表紙が規約適合かの確認
Kindle出版の審査は、単に「文章が読めるかどうか」を判断するものではありません。
KDPガイドラインとポリシーに基づき、内容・著作権・表現の適切性・メタデータの整合性などが総合的にチェックされます。
ここでいう「内容」は文章の質ではなく、規約違反がないかどうかという視点です。
著作権の不備や引用の不明確さ、出典を明示しない他者コンテンツの流用などは、差し戻しの理由になりやすいです。
AI生成コンテンツの扱いも近年明確化されており、「どの程度AIに依存しているか」に応じて開示が必要になるケースがあります(詳細は公式ヘルプ参照)。
またタイトルや説明文などのメタデータが内容と一致していない場合も、不承認や修正要求につながることがあります。
表紙が過度に扇情的な表現に偏っている場合や、解像度・文字可読性が低い場合も修正を求められます。
初心者が見落としやすいのは「規約違反と判断される境界が思ったより広い」点です。
公式は明確な数値で線引きしていないため「セーフと思って出したら差し戻された」という声も珍しくありません。
規約違反になりやすい具体例やグレーゾーンを整理しておきたい方は、事前に『Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説』に目を通しておくと安心です。
審査期間の目安と公開までのタイムライン(通常は幅で計画/公式ヘルプ要確認)
「審査時間は数時間〜数営業日の幅があります。最新の目安は公式ヘルプ要確認。
ただし“最大72時間”という数字はあくまで目安であり、コンテンツ内容や予約設定の有無、市場の混雑状況によって前後します。
実務的には「半日で通るときもあれば、数日以上かかることもある」くらいの幅で考えるのが現実的です。
加えて、審査が完了しても、商品ページが検索に反映されるまでに時間差が生じる場合があります。
私の場合も、審査完了メールからランキング反映まで丸1日程度かかったことがあります。
このため、発売日を指定して予約販売をする場合は、余裕を持ってスケジュールを組むことが大切です。
また「公開=販売開始」と考える方も多いですが、実際にはページの表示、検索結果への反映、ランキング反映が順次起こるため、急にアクセスが増えるとは限りません。
ここで焦って「落ちたのでは?」と不安になり、何度も本棚を更新してしまうのは出版初心者あるあるです。
審査時間ごとの具体的なケースや、待ち時間中に確認しておきたいポイントについては『Kindle出版の審査にかかる時間とは?遅延原因と対策を徹底解説』もあわせてチェックしてみてください。
初回で通すための準備チェックリスト(Kindle出版 審査 通過のコツ)
審査は通過して当たり前と思われがちですが、実はちょっとした不備で差し戻される例は少なくありません。
私自身、初出版時に引用の出典表記が曖昧だったことで再提出になり、公開が数日遅れたことがあります。
ここでは、審査をスムーズに通すために押さえるべきポイントを、チェックリスト形式でわかりやすく解説します。
「事前に整えておけば通るもの」がほとんどです。
そのため、不安がある方は以下の項目に沿って確認しておくと安心です。
著作権・引用の整合性を確認(出典明記・権利者の許諾)
KDPの審査では、文章のオリジナリティよりも「著作権を侵害していないかどうか」が最優先でチェックされます。
特に引用部分や他者の言葉・データを使う場合は、出典の明記が必須です。
著作権者の許諾が必要なコンテンツを無断で使うと、差し戻しや販売停止につながることがあります。
引用は「必要最小限」「主従関係が明確」「出典を明示」の3点を守ると、安全性が高くなります。
ブログの延長感覚で出典を省略すると、後から再提出の原因になることが多いです。
不安な場合は、公式ヘルプにある「コンテンツガイドライン」を確認し、許諾の必要性を判断しましょう。
AI生成コンテンツは開示、AI支援は原則開示不要の線引き(公式ヘルプ要確認)
AIによるコンテンツ作成が増えたことで、KDPではAI生成コンテンツの扱いが明確化されています。
大まかな基準として「AIが文章や画像の生成を主体的に行った場合」は「AI生成」として開示が必要になります。
一方で、「構成のヒントを得た」「校正に利用した」などのAI支援は、基本的に開示不要とされています。
ただし、Amazon側の判断基準は変動する可能性があるため、最新の公式ガイドラインを確認することが大切です。
開示が必要なコンテンツを未申告のまま提出すると、審査で差し戻される可能性があるため注意してください。
AIを使っていても、「どこまでが支援でどこからが生成か」という線引きを意識して原稿を整理することが重要です。
タイトル/説明/カテゴリ/キーワードのメタデータを内容と一致させる
Kindle出版で意外と差し戻しが多いのが「メタデータの不整合」です。
タイトルと内容がかけ離れていたり、説明文が誇張的だったりすると、「誤解を与える恐れがある」と判断されることがあります。
カテゴリやキーワードが内容とかけ離れていると、ユーザー体験を損なうため修正を求められるケースもあります。
メタデータは「内容の案内板」のような役割を持つため、誇張しすぎず、内容を正確に表すことが大切です。
特に初心者向けなのか、実践者向けなのかを明確にするだけでも、審査通過率が上がりやすくなります。
また、説明文は「目次+メリット」で構成すると、読者にも審査側にも意図が伝わりやすくなります。
表紙画像の可読性・権利・規格(推奨サイズ等は公式ヘルプ要確認)
表紙は読者の目を引くだけでなく、審査対象としても重要なチェックポイントになります。
特に注意すべき点は「テキストの可読性」「画像の権利」「規定サイズ」です。
表紙に使用する写真やイラストは、商用利用可能であることを確認し、必要に応じてライセンスを明記することが望ましいです。
また、文字が小さすぎて読めない、色が背景と同化している場合は、審査で修正を求められる場合があります。
「表紙サイズ・比率・解像度は随時更新されます。最新の推奨値と比率は公式ヘルプ要確認。
表紙は「おしゃれさ」だけでなく「伝わるかどうか」を意識して作ることが、審査通過にも販売にもつながります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
提出〜公開までの流れと「審査中」の注意点(Amazon.co.jp前提)
原稿やメタデータ、表紙が整ったら、いよいよKDPの本棚から原稿を提出します。
この段階で「公開ボタンを押したらすぐ販売される」と思い込む方も多いのですが、実際には審査・公開・反映という複数のステップを経て読者に表示されます。
ここでは、提出後にどんな流れで本が公開されるのか、そして審査中にやってはいけない落とし穴を整理しておきましょう。
この流れを理解しておくと、公開待ちの不安がかなり軽くなります。
本棚ステータスの見方と審査中は編集不可/公開後に更新
KDPに原稿を提出すると、本棚上のステータスが「審査中(In Review)」に変わります。
この状態になると、原稿・タイトル・表紙などの内容は編集できなくなります。
途中で間違いに気づいても、審査中は修正ができないため、一旦審査が終わるまで待つ必要があります。
審査が完了すると、「ライブ(Live)」または「公開済み(Published)」のようなステータスに変わります。
「公開後は修正できますが、再保存で再審査になる場合があります。重要修正はまとめて行うのが無難です。
ただし、再度更新を行うと再び審査プロセスに入るため、頻繁な修正は公開タイミングを遅らせる原因になります。
私は過去に公開直後の細かい修正を繰り返し、いつまでたっても安定公開にならなかった経験があります。
できれば初版は「最低限読める完成度」を確保してから出すほうが、審査によるタイムロスが少なくなります。
商品ページ・ランキング・検索への反映ラグの理解(遅延=不合格ではない)
審査が通過し「Live」になった後も、すぐに検索に表示されるとは限りません。
Amazonの商品ページは即時公開されることもありますが、検索結果・ランキング・サジェストなどに反映されるまでタイムラグが発生する場合があります。
この反映遅延は不具合ではなく、システム側の処理による自然なタイムロスです。
実務上、数時間~半日程度遅れてランキングに載るケースも珍しくありません。
この段階で「落ちたのでは?」と誤解してしまう出版初心者は多いです。
自分の端末で表示されなくても、他のユーザーには表示されている場合もあります。
焦らず「反映には時間差がある」という前提でスケジュールを組んでおきましょう。
公開ステータスになっているのに検索やランキングに出てこないときのチェック手順は『Kindle出版で反映されない原因とは?72時間ルールと対処法を徹底解説』でケース別にまとめています。
予約販売の活用と発売日設計のコツ(日本向け/他国は補足のみ)
発売日を事前に設定し、予約ページを先に公開できる「予約販売(プレオーダー)」も活用できます。
この方法では、審査を発売日前に通しておけるため、告知しながら読者に準備期間を与えることができます。
特に初出版では「公開された瞬間に読者が来ない不安」を和らげるメリットがあります。
ただし、予約開始後に原稿を大幅に修正する場合は締め切りまでに再提出が必要になるため、完成度が低いまま進めるのはリスクがあります。
また、米国や他国では予約設定のルールや審査タイミングが異なる場合があるため、Amazon.co.jp前提で進めることが重要です。
発売日は「余裕を持って審査が通るタイミング」から逆算して設定することをおすすめします。
公開直後に販売戦略を動かす場合も、予約活用が有効です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
差戻し・保留のよくある原因と回避策(Kindle出版 審査に落ちる前に)
審査に落ちるケースには一定の傾向があります。
「何が悪かったのか分からない」という状態になってしまうと、修正にも時間がかかり、公開が大幅に遅れてしまいます。
ここでは、よくある差戻しの原因と、その回避方法をわかりやすく整理します。
特に初出版では「内容そのものよりも形式的な不備」が原因になることが多いです。
実際、私も初期のタイトル設計ミスで差し戻されたことがあり、細かい基準を理解しておくことの重要性を痛感しました。
誤解を招くタイトル/サブタイトル・シリーズ表記の不整合
タイトルとサブタイトルが誇張されすぎていたり、内容と乖離していたりする場合、審査で修正を求められることがあります。
たとえば「誰でも1日で稼げる」「完全無料で即副収入」など、極端に断定的で根拠が薄い表現は注意対象になりやすいです。
また、シリーズ設定を行う際に、タイトルにシリーズ名が含まれていない・巻数表記が不自然といった不整合も差戻しの対象になります。
実務的には「タイトル=内容の要約」「サブタイトル=対象読者+メリット」程度にとどめておくと安全性が高いです。
特にシリーズ物の場合、一冊目の基準が通れば、二冊目以降もスムーズに審査を通過しやすくなります。
反復的・自動生成的と見なされる構成は修正(独自価値の明確化)
KDPでは「反復的で自動生成的」と見なされるコンテンツを問題視しています。
これは、同じ文を機械的に繰り返しているだけの原稿や、テンプレの穴埋めに近い構成にも当てはまる場合があります。
特に近年はAI生成コンテンツの増加により、「構成が単一」「意図が伝わらない」と判断されると審査が長引くケースもあります。
そのため、章ごとに読者へ届けたいメッセージや価値を明確にし、「この本でしか得られない視点」を入れておくことが大切です。
文章の完成度よりも「意図・方向性が伝わるかどうか」が重要視される傾向があります。
私は初期の原稿で「内容が薄い」と判断され、追記を求められたことがありましたが、独自の経験や事例を加えたことでスムーズに通過しました。
配慮が必要な表現は抽象化し、教育・注意喚起の文脈を維持
刺激的な表現や過度にセンセーショナルな内容は、KDPガイドラインで制限されています。
ただし、教育的・注意喚起的な文脈であれば内容の取り扱いは認められる場合があります。
重要なのは「感情を煽るためではなく、理解を促す目的で書いていること」が伝わる構成になっているかどうかです。
たとえば、過激な表現をそのまま描写するのではなく、抽象化する・リスク説明とセットにすることで通過しやすくなります。
公式では定量的な基準が明記されていないため、「少しでもグレーに感じた場合は抽象化する」くらいの姿勢でちょうどよいです。
実務的には「具体例を出しつつも詳細な描写は避ける」「読者への注意喚起や啓発として提示する」ことで審査をスムーズに通過できます。
トラブル発生時の対処(Kindle出版 審査 差戻し・保留)
審査に出した後、差戻しや要対応の通知が届くことがあります(文言は時期やUIで異なるため、公式ヘルプ要確認)。
ですが、ここで慌てず、メッセージ内容を正しく読み取り、問題点を一つずつ整理すれば、再提出で通過できるケースがほとんどです。
審査通過は「やり直しができない試験」ではなく、「修正を前提としたプロセス」と考えると気持ちが楽になります。
ここでは、差戻しが起きたときのメッセージの見方と修正手順、問い合わせ前に確認すべき項目を整理します。
差戻しより一歩進んだ「出版停止」レベルのトラブルと、その復活までの流れを詳しく知りたい場合は『KDPの出版停止とは?原因と再公開手順を徹底解説【Kindle電子書籍対応】』も参考にしてみてください。
差戻しメッセージの読み解き方と再提出手順(電子書籍)
KDPから差戻しがあった場合、多くはメールおよび本棚ステータスのメッセージで理由が伝えられます。
メッセージは英語で届くこともありますが、構造は比較的シンプルです。
典型的には以下のような形式で書かれています。
・問題のカテゴリ(例:Metadata Issue/Content Guidelines)
・どの部分に問題があるか(例:Title does not match content)
・修正が必要な点や参考ガイドラインへのリンク
この内容を整理し、該当箇所を修正したうえで、再度「保存して公開」から再申請すればOKです。
私の経験では、内容そのものが完全に否定されるケースは稀で、修正で通過する例は少なくありませんが、保証はできません。指摘カテゴリを公式ガイドラインで照合しましょう。
もし曖昧な指摘で意味がわかりにくい場合は、指摘されたカテゴリ名から「KDP Content Guidelines」で該当項目を読み直すと理解しやすくなります。
焦って適当に再提出するのではなく、「何が原因だったか」を一度可視化することがポイントです。
問い合わせ前の自己診断チェック(原稿・メタデータ・表紙・開示)
差戻し理由が不明瞭だった場合、すぐに問い合わせる前に、自分で以下の観点からチェックすることをおすすめします。
✅ 原稿:反復的・無意味な記述、引用の不明確さ、不適切表現の過度な詳細化はないか
✅ メタデータ:タイトル/説明文/シリーズ情報/カテゴリに矛盾がないか
✅ 表紙:文字が見づらくないか、内容と一致しているか、権利関係はクリアか
✅ AI生成コンテンツ:開示すべき内容を未申告で提出していないか
この自己診断を行うことで、審査側の視点を理解しやすくなります。
それでも原因が見つからない場合は、KDPサポートに問い合わせが可能です。
問い合わせ時は、「指摘内容がどのガイドラインに該当するか不明です」「改善に向けて詳細なヒントをいただけますか?」という形で丁寧に相談すると回答が得やすくなります。
なお、再申請を繰り返すと審査期間が延びる傾向がありますので、できるだけ一度で問題を解消することを意識しましょう。
(補足)ペーパーバック併売時の最小限ポイント
Kindle出版では電子書籍のみで公開することが多いですが、読者層によってはペーパーバックを併売すると購入率が高まるケースもあります。
ただし、ペーパーバック版には電子書籍とは異なる審査ポイントや物理的な仕様の確認が必要です。
私は初めてペーパーバックを設定した際、余白設定の不備で数回差し戻されてしまい、「電子と同じ感覚で出すとつまずく」ことを痛感しました。
ここでは補足的に、最低限押さえておきたいポイントを整理します。
電子書籍を前提としつつ、紙版を出すなら「紙ならではの条件」を漏れなく確認することが重要です。
最小ページ数や印刷仕様・余白設定の確認(詳細は公式ヘルプ要確認)
ペーパーバックを発行する場合、KDP公式では最小ページ数の基準が設けられています。
たとえば一般的な白黒のペーパーバックでは「24ページ以上」が必要とされています(最新の基準は公式ヘルプで要確認)。
また、印刷時にはノド(綴じ部分)を考慮した余白を取る必要があり、電子書籍用に作成した原稿のままだとバランスが崩れることがあります。
さらに、表紙も印刷用に背幅を含めたPDF形式で作り直す必要がある点に注意してください。
印刷に対応していないサイズや解像度の表紙をそのまま使うと、差し戻しや自動修正による歪みにつながります。
実務的には「KDPペーパーバック用テンプレート」を活用すると失敗が少なくなります。
なお、審査期間も電子と異なる場合があり、印刷工程を伴うため、公開までに電子版より時間がかかることがあります。
まとめ:審査は“幅で設計”、整合性で通す—Kindle出版を滞りなく進める
Kindle出版の審査をスムーズに通すためには、「通過するかどうか」ではなく「通過しやすい準備ができているか」を意識することが大切です。
強引なインパクト狙いではなく、内容・タイトル・表紙・開示情報などの整合性を整えれば、大きなトラブルなく進められます。
特に審査時間は“最短時間”ではなく“幅”で見積もることがポイントです。
原稿は「独自性」「正確な権利情報」「適切な配慮」を意識し、メタデータは「内容と一致しているか」を基準に見直してください。
審査中の修正はできないため、提出前のチェック体制を整えることが、公開までの時間ロスを減らす最大のコツになります。
もし差し戻しが起きても、冷静にメッセージを読み取り、要点を修正して再提出すれば問題ありません。
ペーパーバック併売を考えている場合は、紙版特有の仕様にも注意しながら検討していきましょう。
安心して出版まで進められるよう、ガイドラインと実体験をバランスよく参考にすることが成功への近道です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。