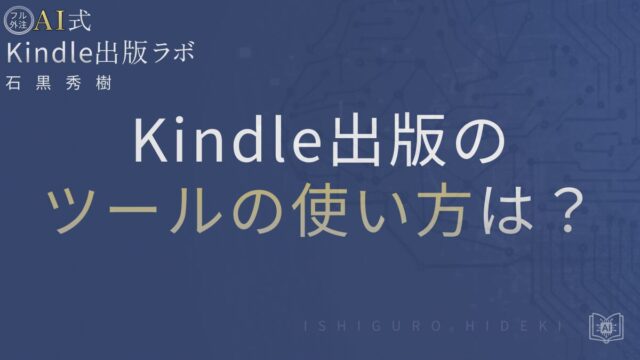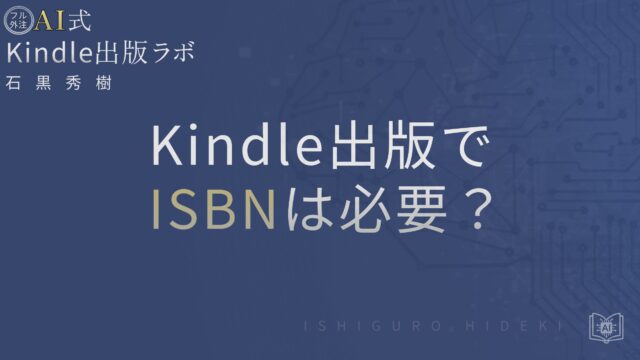自費出版の費用はいくらかかる?紙と電子の違いを徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
自費出版を検討するとき、最初に気になるのが「実際いくらかかるの?」という点ですよね。
実は、出版の形態や依頼先によって費用は大きく異なります。
この記事では、紙と電子それぞれの違いや、費用の内訳・相場を整理しながら、初心者の方でも現実的な目安をつかめるように解説していきます。
経験者の立場から、実際に見積もりで見落としがちなポイントや、無駄な出費を防ぐコツも交えてお伝えします。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
自費出版の費用はいくらかかる?基本の考え方と相場感
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
- 1 自費出版の費用はいくらかかる?基本の考え方と相場感
- 1.1 自費出版の費用はなぜ人によって違うのか
- 1.2 「紙の本」と「電子書籍」で費用構造が異なる理由
- 1.3 自費出版の費用相場:最低限〜一般的な目安
- 1.4 制作費:原稿校正・デザイン・編集の料金目安
- 1.5 印刷費:部数・仕様・カラーによる価格変動
- 1.6 流通・書店委託費:在庫リスクと販売手数料の関係
- 1.7 電子出版の初期費用と無料でできる範囲
- 1.8 有料代行サービスの利用時に発生するコスト
- 1.9 ロイヤリティ・販売手数料の仕組みと注意点
- 1.10 自分でできる作業を増やしてコストを削減する方法
- 1.11 出版社やサービスを比較する際の見るべき項目
- 1.12 見積書で見落としやすい追加費用と注意点
- 1.13 しがちな「追加料金」の確認ポイント
- 2 費用をかける価値がある部分と節約すべき部分
- 3 実例で見る:10万円以内・30万円以内でできる自費出版
- 4 まとめ:目的と予算に合わせた出版計画を立てよう
自費出版の費用は、「どんな目的で」「どんな形で」本を出すかによって大きく変わります。
印刷部数を増やしたり、デザインを凝ったりすれば費用は上がりますし、電子出版にすれば印刷代はゼロになります。
ここではまず、自費出版の費用が人によって違う理由と、紙と電子での構造の違い、そしておおよその相場を整理しておきましょう。
自費出版の費用はなぜ人によって違うのか
自費出版は、いわば「オーダーメイド出版」です。
著者が選ぶ内容・デザイン・ページ数・販売方法によって、かかるコストは変わります。
たとえば、同じ原稿量でもモノクロとフルカラーでは印刷費が2〜3倍違うことがあります。
また、業者によっては編集や校正を含めた「丸ごとサポート」型のプランを提供しており、その分の人件費が加算されます。
公式サイトでは「◯万円から可能」と書かれていても、実際に希望を伝えると追加費用が発生するケースも少なくありません。
私の経験でも、「簡単な構成でOK」と伝えていたつもりが、写真調整や表紙デザインで想定外の見積もりになったことがありました。
見積もり時には、どこまでが基本料金に含まれているのかを必ず確認しましょう。
「紙の本」と「電子書籍」で費用構造が異なる理由
紙の本は、制作費に加えて印刷・製本・流通コストが大きな比率を占めます。
部数が増えるほど1冊あたりの単価は下がりますが、在庫リスクがあるのが現実です。
一方、電子書籍は印刷費が不要なため、初期費用を抑えやすく、在庫リスクもありません。
ただし、代行業者を使う場合は登録料やデータ整形費などが発生することがあります。
「また、販売時にはAmazonなど各プラットフォームの手数料やロイヤリティ条件が適用されます。
具体的な印税率や条件は変更される可能性があるため、最新の公式ヘルプを確認してください。(公式ヘルプ要確認)」
紙の本は制作から納品まで時間とコストがかかる分、贈呈用や記念出版に向いています。
電子書籍は、スピーディーにリリースしたい人や副業・収益化目的に適しています。
どちらが良い悪いではなく、目的に合った形式を選ぶことが大切です。
自費出版の費用相場:最低限〜一般的な目安
紙の自費出版の場合、個人向けサービスでは数十万円規模の費用がかかるケースが多く、30万円以上になる例も少なくありません。
ただし、仕様やページ数、サービス内容によって大きく変動するため、具体的な金額は各社の最新料金表で確認してください。」
簡易印刷や少部数なら10万円台で済むこともありますが、商業流通(書店販売)を目指す場合は流通登録費などが追加されます。
電子書籍出版では、Kindleなどを利用すれば0円〜数万円で可能です。
ただし、プロにデザイン・編集を依頼する場合は、5〜20万円程度の外注費がかかることがあります。
私自身、初めて電子書籍を出したときは、デザインと校正を外注して合計約8万円ほどでした。
低コストでも形にはなりますが、「読まれる本」にするには、内容・見た目・タイトル設計にある程度の投資が必要だと実感しました。
電子出版の費用感をさらに詳しく知りたい場合は『 Kindle出版の自費出版費用とは?電子書籍のコストと始め方を徹底解説 』もあわせて確認できます。
紙の自費出版は、もっとも「本らしさ」を実感できる方法ですが、その分コスト構造が複雑です。
原稿を仕上げてから印刷・流通までの各工程に費用が発生し、選ぶ仕様によって最終的な総額が大きく変わります。
ここでは、制作費・印刷費・流通費の3つの柱を中心に、実際の相場感を交えながら整理します。
制作費:原稿校正・デザイン・編集の料金目安
制作費は、原稿の内容を整える「編集・校正」や、表紙・レイアウトなどの「デザイン」にかかる費用を指します。
文章の誤字脱字チェックだけであれば数万円程度ですが、構成全体の見直しや文体調整まで依頼すると10万円を超えることもあります。
また、表紙デザインをプロに任せると、おおよそ3〜8万円が相場です。
自分で作成する場合は無料でも可能ですが、印象を大きく左右するため、ここに費用をかけるかどうかが読者への第一印象を決めるポイントになります。
さらに、本文の組版(ページレイアウト)も意外と見落としがちな工程です。
文字の位置や余白の取り方、段落の揃え方などは読みやすさに直結します。
この作業を出版社や制作会社に依頼すると、ページ数によっては5万円前後の費用が追加されることもあります。
公式サイトでは「編集込み」と書かれていても、実際は表紙や組版が別料金の場合も多いので、契約前に範囲を確認しておきましょう。
印刷費:部数・仕様・カラーによる価格変動
印刷費は、紙の自費出版で最も大きなコストになります。
一般的に、100部単位での印刷が多く、仕様や部数によって1冊あたりの単価が変わります。
たとえば、モノクロの本文でA5サイズ・100ページ程度なら、100部印刷で約5万円〜8万円が目安です。
これがフルカラーになると、印刷費が倍以上になることも珍しくありません。
また、紙の種類やカバー仕様によっても費用が変動します。
光沢紙・マット紙の選択、カバーの有無、帯のデザインなど、細かい設定の積み重ねが最終的な金額を左右します。
私の経験上、初めての出版では「とにかくきれいに仕上げたい」と思いがちですが、印刷費を抑えたい場合は、まずは試し刷り(小ロット印刷)で仕上がりを確認するのがおすすめです。
公式の印刷会社でも、少部数向けプランを用意しているところが増えています。
流通・書店委託費:在庫リスクと販売手数料の関係
印刷が終わったあとは、販売や保管に関する費用が発生します。
紙の本を書店に並べたい場合、流通登録や販売代行を行う会社を通す必要があります。
このとき発生するのが「流通・書店委託費」です。
通常、販売価格の30〜40%前後が流通手数料として差し引かれます。
書店販売を希望する場合、書籍JANコード(バーコード)取得費用が別途1〜2万円ほどかかることもあります。
ISBN取得や表示項目の詳細は『 自費出版の奥付とは?意味・書き方・注意点を徹底解説【電子書籍対応】 』で整理できます。
また、委託販売の場合は「売れ残り(返品)」のリスクも考慮が必要です。
在庫を自宅で保管する場合はスペースの問題があり、倉庫保管を選ぶと月額費用が発生します。
ここでよくある失敗が、「全部書店に置いてもらえる」と思い込み、結果的に在庫が戻ってくるケースです。
現実には、初回は数店舗のみの扱いになることが多く、販売実績が出てから拡大される仕組みです。
紙の自費出版は、完成したときの達成感が大きい一方で、コスト構造が複雑です。
事前に全体の流れを把握しておくことで、予算オーバーや赤字を防ぎやすくなります。
次の章では、電子書籍出版にかかる費用の特徴と、紙との違いを具体的に見ていきます。
電子書籍出版は、紙の本に比べて初期費用が格段に抑えられるのが大きな特徴です。
特にAmazonのKindle出版(KDP)は、個人でも簡単に始められる仕組みが整っており、制作から販売までをすべてオンラインで完結できます。
ただし、無料でできる範囲と、有料サービスを利用した場合のコストを正しく理解しておかないと、思わぬ出費につながることもあります。
ここでは、電子書籍出版の費用構成を実際の事例を交えてわかりやすく解説します。
電子出版の初期費用と無料でできる範囲
Kindleダイレクト・パブリッシング(KDP)を使えば、基本的には初期費用ゼロで電子書籍を出版することが可能です。
アカウント登録からデータのアップロード、販売設定まで、すべて無料で行えます。
紙の出版のような印刷費や在庫管理費が不要なため、金銭的なリスクが少ないのが最大のメリットです。
ただし、完全無料で完結させようとすると、デザインや編集のクオリティに差が出ることがあります。
WordやCanvaなど無料ツールで表紙を作ることも可能ですが、見た目の印象が作品の信頼感につながるため、販売を目的とする場合は最低限の投資を検討する価値があります。
私自身も最初は無料ツールで作成しましたが、後からプロに依頼した表紙に差し替えたことで、購入率が目に見えて上がりました。
KDPの無料出版の仕組みは『 Kindle出版の費用とは?初期費用ゼロで始める方法を徹底解説 』でも詳しく確認できます。
有料代行サービスの利用時に発生するコスト
電子出版を代行会社に依頼する場合、作業内容に応じて費用が発生します。
一般的な代行サービスでは、原稿整形・表紙デザイン・出版手続き代行などをまとめたパッケージが多く、相場は3万円〜10万円程度です。
ページ数や画像の有無によって追加料金が発生することもあります。
注意すべきなのは、契約形態や著作権の扱いです。
代行会社によっては、著者名義ではなく会社名義で出版されたり、販売報酬が自動的に分配される仕組みになっている場合もあります。
公式のKDPガイドラインでは、著作権の保持は著者本人にありますが、実務上は契約書の文言によって異なるケースがあるため、依頼前に確認が必要です。
また、レビュー投稿や販売促進をうたう過剰なサポートを行う業者には注意が必要です。
KDPの規約に抵触する可能性があるため、信頼できる実績のある代行サービスを選ぶことが大切です。
ロイヤリティ・販売手数料の仕組みと注意点
Kindle出版では、販売価格に応じて印税(ロイヤリティ)が支払われます。
「一般的に、Kindle出版では販売価格帯など一定の条件を満たした場合に高いロイヤリティ率を選択できますが、詳細な条件は随時変更されることがあります。
たとえば、500円の電子書籍を販売した場合、70%設定なら「仮に高いロイヤリティ率が適用される場合でも、販売価格に対して一定割合が著者収益となるイメージです。
ただし、配信コストや税、為替などが差し引かれるため、実際の受取額は売上レポートで確認する必要があります。」
ただし、70%ロイヤリティを選ぶ場合は、配信コスト(データ転送量)として数円〜十数円が差し引かれる点に注意が必要です。
また、Amazon以外の地域での販売では税制上の源泉徴収が発生する場合もあります。
このあたりは公式ヘルプを確認しつつ、実際の売上明細を定期的にチェックするのがおすすめです。
実務的な感覚としては、1冊あたりの利益よりも「継続的に販売できる仕組み」を意識したほうが安定します。
広告やSNSで一時的に売上が伸びても、読者の満足度が低いとレビュー評価が下がり、アルゴリズム上の露出も減ってしまうためです。
出版後のメンテナンスを含めて、長期的な視点で収益を考えるとよいでしょう。
電子出版はコストを抑えつつ自分の作品を広められる手段ですが、無料でできる範囲と必要経費のバランスを取ることが大切です。
特に、代行サービスやロイヤリティ設定など、仕組みを理解したうえで選択することで、無駄な出費を防ぎ、安心して出版を進められます。
自費出版の費用は、事前の工夫や確認次第で大きく差が出ます。
とくに初めて出版する人ほど「言われるままに契約してしまう」ケースが多く、後から予想外の費用が発生して驚くこともあります。
ここでは、コストを抑えながら質を落とさないための実践的なコツと、見積もり段階でチェックしておくべきポイントを解説します。
自分でできる作業を増やしてコストを削減する方法
まず最も効果的なのは、外注せずに自分でできる作業を増やすことです。
たとえば、原稿の誤字脱字チェックや簡単なレイアウト調整は、自分でも十分対応可能です。
最近ではWordやGoogleドキュメントでも校正支援機能が充実しており、無料で使えるツールも増えています。
また、表紙デザインもCanvaやFigmaなどの無料デザインツールを使えば、テンプレートから比較的きれいな仕上がりにできます。
ただし、「自分でできること」と「専門的な仕上がりが必要な部分」の線引きが大切です。
たとえば、書店流通を目指す場合や電子書籍の販売ページで目立たせたい場合は、プロのデザイナーに依頼するほうが結果的に費用対効果が高いこともあります。
また、印刷費を抑えるには、モノクロ印刷を基本にしつつ、必要なページのみカラーにする方法もあります。
印刷部数を少なめに設定し、需要を見ながら追加印刷する「オンデマンド印刷」もおすすめです。
初期費用を抑えつつ品質を維持したい人には特に向いています。
出版社やサービスを比較する際の見るべき項目
出版社や代行サービスを選ぶときは、料金だけで判断しないことが重要です。
実際の見積もりでは、「基本料金にどこまで含まれているか」を確認するのが第一歩です。
たとえば、表紙デザインやISBN取得、流通登録などが「オプション扱い」になっている場合、後から追加費用が発生します。
公式サイトでは「10万円で出版可能」と書かれていても、実際は必要な作業を追加すると倍近くになるケースも珍しくありません。
私が以前相談を受けたケースでも、安さを重視して契約したところ、校正作業が別料金で最終的に見積もりが2倍になっていたことがありました。
契約前に「含まれる項目」「別途費用がかかる項目」を明確にすることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。
さらに、出版後のサポート内容も比較しましょう。
出版して終わりではなく、販売促進やアフターサポートが含まれるかで長期的な収益性が変わります。
サポートの範囲が曖昧な会社は、後から追加費用を請求されることがあるため注意が必要です。
見積書で見落としやすい追加費用と注意点
見積書を見る際は、金額の合計だけでなく、明細に目を通すことが大切です。
特に「校正回数」や「修正費用」に関する記載は要チェックです。
初回の修正は無料でも、2回目以降に追加費用がかかるケースがあります。
また、印刷見積もりでは送料や納品費が別途になっている場合も多く、これを見落とすと想定より高くなります。
さらに、書店流通を希望する場合はISBN取得費や流通登録料、販売手数料なども加わります。
これらは一見小さな金額に見えても、積み重なると予算を圧迫します。
「他社より安い」と感じても、全体の合計コストで比較するようにしましょう。
自費出版の見積もりは、一見わかりづらくても仕組みを理解すれば難しくありません。
焦らず複数社を比較し、信頼できる担当者と相談しながら進めることで、無駄な出費を抑え、納得できる出版を実現できます。
しがちな「追加料金」の確認ポイント
見積もり段階では気づきにくいのが、後から発生する「追加料金」です。
多くの人が見落とすのは、修正・再校正・データ変更などの“細かな手数料”です。
たとえば、初回の校正までは無料でも、2回目以降は1回ごとに5,000円〜1万円かかることがあります。
また、印刷後の誤植修正やカラーバランスの再調整などは、再印刷扱いになるケースがほとんどです。
そのため、「修正は何回まで無料か」「どの段階で料金が発生するのか」を事前に確認しておくことが大切です。
契約書や見積書に明記されていない場合は、口頭ではなく必ずメールなどの文面で確認を残しましょう。
さらに、書店流通を希望する場合は、ISBN取得や流通登録費が「オプション扱い」になっていることがあります。
サイトでは「出版一式〇万円」と書かれていても、実際にはISBNやバーコード発行費、納品送料などが別途請求される場合もあるため要注意です。
こうした追加費用は少額でも積み重なれば大きな負担になるため、最初の見積もりで総額を確認しておくと安心です。
最後に、納期の遅延対応も意外な落とし穴です。
「特急料金」や「データ納期の延長ペナルティ」が設定されている会社もあるため、スケジュール管理には余裕を持ちましょう。
経験上、無理に短納期を求めるより、通常進行で丁寧に進めた方が結果的にコストも品質も安定します。
費用をかける価値がある部分と節約すべき部分
自費出版の予算を考えるうえで重要なのは、「すべてを安くする」ことではなく、費用をかけるべき部分と節約できる部分を見極めることです。
限られた予算の中でも、作品の印象や売上に直結するポイントを押さえれば、無理なくクオリティを保てます。
編集・デザインなど品質に直結する部分への投資
まず、費用をかける価値が高いのは「編集」と「デザイン」です。
どんなに内容が良くても、誤字や文体の不統一が多いと、読者の信頼を失ってしまいます。
プロの校正者に依頼すれば、文章の流れや読みやすさがぐっと洗練され、作品の完成度が上がります。
特に商業書籍と並べて販売したい場合は、表紙デザインの印象が売上を左右します。
Amazonなどのオンラインストアでは、表紙画像が“購入の第一印象”になります。
「少し地味かな?」と感じたら、プロデザイナーの力を借りてブラッシュアップするのがおすすめです。
実際、デザインを変更しただけでクリック率が倍になったという事例も少なくありません。
さらに、編集・校正・デザインをまとめて依頼する場合は、複数業者を別々に頼むよりも、一括プランにした方がコストが安くなることがあります。
ただし、見積書に含まれる作業範囲をしっかり確認し、不要なオプションを外すようにしましょう。
宣伝・流通・在庫管理などでの無駄な支出を防ぐ方法
一方で、削減しやすいのが宣伝費や在庫管理費です。
広告や販売促進に費用をかけても、ターゲットが明確でなければ効果は薄いです。
特に「販売代行プラン」や「書店展開保証」といったサービスは、一見魅力的でも、実際には在庫を抱えるリスクや高い手数料がかかることがあります。
おすすめは、まず無料でできる範囲から始めることです。
SNSで作品の裏話や制作過程を発信するだけでも、共感によって自然な読者層を築けます。
また、Kindle出版など電子書籍の場合は、在庫管理費が不要なため、紙よりもコスト面で有利です。
流通面では、「書店での取り扱い」にこだわりすぎないことも一つの考え方です。
書店委託には販売手数料が発生しますが、オンライン販売なら手数料を抑えながら継続的に売上を得られます。
特に、長期的に販売する予定の方は、初期費用よりも「維持コストが少ない仕組み」を選ぶと安定します。
自費出版は、費用をかける場所と抑える場所を見極めれば、限られた予算でも十分に高品質な本を作れます。
焦らず見積もりを比較し、自分の目的に合った最適なバランスを見つけていきましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
実例で見る:10万円以内・30万円以内でできる自費出版
「自費出版は高い」というイメージを持つ人も多いですが、近年は10万円以下でも十分に出版できるケースが増えています。
費用を抑えるには、どんな形態を選ぶか、どこまで自分で作業できるかがカギになります。
ここでは、実際の予算感をもとに、電子書籍と紙の出版のそれぞれで可能なプランを紹介します。
10万円以内でできる電子書籍出版の具体例
電子書籍なら、10万円以内でも十分に出版が可能です。
たとえばAmazonのKindleダイレクト・パブリッシング(KDP)を使えば、登録や出版の手数料は無料です。
かかる費用は、主に表紙デザインや原稿の編集・校正など、品質を上げるための外注費用のみです。
たとえば、自分で原稿を執筆し、Canvaなどで簡単な表紙を作成すれば、0円でも出版できます。
ただし、より完成度を高めたい場合は、校正やデザインをプロに依頼するのがおすすめです。
外注の目安としては、表紙デザインが1万円前後、原稿チェックや構成アドバイスが2〜3万円ほどです。
実際に筆者がKDPで出版した際は、全体で約8万円ほど。
校正者に依頼して誤字脱字を修正し、デザインだけ外注する形にしました。
印刷費が不要なので、完成後すぐに販売を開始でき、在庫リスクもゼロ。
売上から印税(ロイヤリティ)70%が入る仕組みのため、継続的に販売すれば十分に回収が可能です。
このように、電子出版は少ない費用でも始めやすく、副業やライティング活動の第一歩としても適しています。
重要なのは、費用をかける部分を明確にし、無料ツールを上手く活用することです。
30万円前後で実現できる紙の自費出版プラン
紙の本を出版したい場合、30万円前後が一つの現実的なラインです。
「オンデマンド印刷(少部数印刷)を利用すれば、大量印刷をしなくても少部数から制作できます。
仕様やページ数によっては、印刷・製本費を比較的おさえられるケースもありますが、具体的な金額は印刷会社の見積もりや料金シミュレーターで確認してください。」
残りの費用は、編集・デザイン・ISBN取得・流通登録などに充てるイメージです。
出版社を通さず、自分でISBNを取得して流通に乗せることもできますが、初めての方は手続きの代行を依頼したほうがスムーズです。
その場合でも、20万円〜30万円ほどで出版まで完結できます。
注意したいのは、印刷部数を欲張りすぎないことです。
「100冊刷れば安くなる」と思って多く印刷しても、販売が伸びず在庫を抱えて赤字になるケースは少なくありません。
まずは30〜50冊の小ロットで様子を見て、反応を見ながら増刷するのが安全です。
紙の本は、手に取れる魅力がある一方で、印刷費や保管費がかかる点がデメリットです。
しかし、イベント配布や営業ツールとして使うなど、目的を明確にすれば十分に価値のある投資になります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
まとめ:目的と予算に合わせた出版計画を立てよう
出版の費用は一律ではなく、「どんな目的で」「どんな読者に届けたいか」によって変わります。
安くても良い場合もあれば、あえて費用をかけた方が信頼性や販売力が高まるケースもあります。
最後に、目的別の考え方と赤字を防ぐコツを整理しておきましょう。
費用だけでなく「目的」に合う出版形態を選ぶ
電子書籍は、低コストで始めやすく、スピード重視の人に向いています。
ブログやSNSで発信している人が、実績を形にする方法としても最適です。
一方、紙の本はプレゼントやイベント販売など、リアルな魅力を重視する人におすすめです。
どちらの形態を選ぶにしても、「誰に、どんな想いで届けたいのか」を明確にしておくことが大切です。
目的が定まると、費用の優先順位も自然と見えてきます。
「売上よりも経験」「販売よりもブランディング」といった目的によって、最適な投資額は変わるのです。
赤字を防ぎながら理想の出版を実現するポイント
赤字を防ぐ最大のコツは、「収益を見込める範囲でコストを抑える」ことです。
そのためには、印刷部数・仕様・宣伝費の3つをバランスよく調整しましょう。
特に紙の出版では、部数を抑えて在庫リスクを軽減するのが基本です。
また、制作費を一括で払う前に、見積書を細かく確認することも重要です。
「修正料」「流通登録料」などが後から追加される場合があるため、契約前にすべての条件を確認しておきましょう。
電子出版の場合は、最初の完成度にこだわりすぎず、出版後に改訂していくスタイルもおすすめです。
KDPでは、内容やデザインの更新が自由にできるため、初期費用を抑えながら改善できます。
出版は一度きりの大きなイベントではなく、育てていくプロジェクトのようなものです。
目的を明確にし、予算に合わせて柔軟に計画を立てることで、無理なく理想の出版を実現できます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。