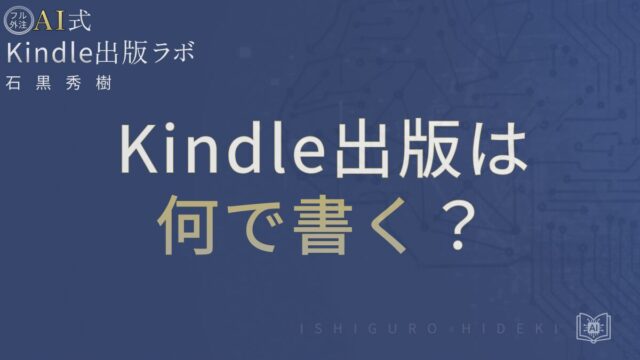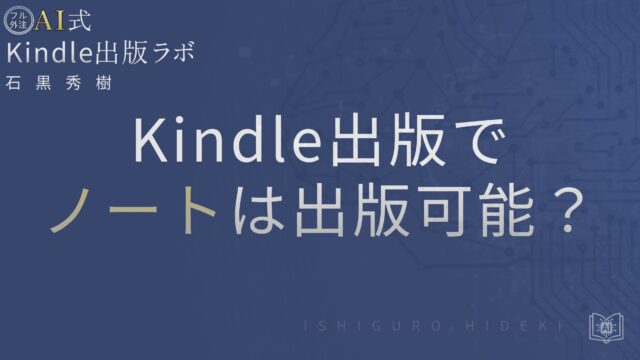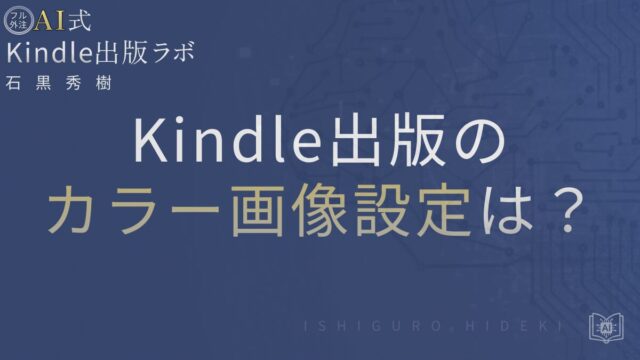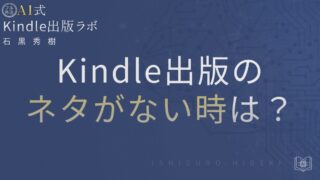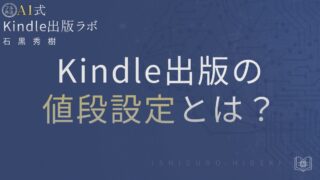Kindle出版のWord設定とは?崩れない電子書籍の作り方を徹底解説
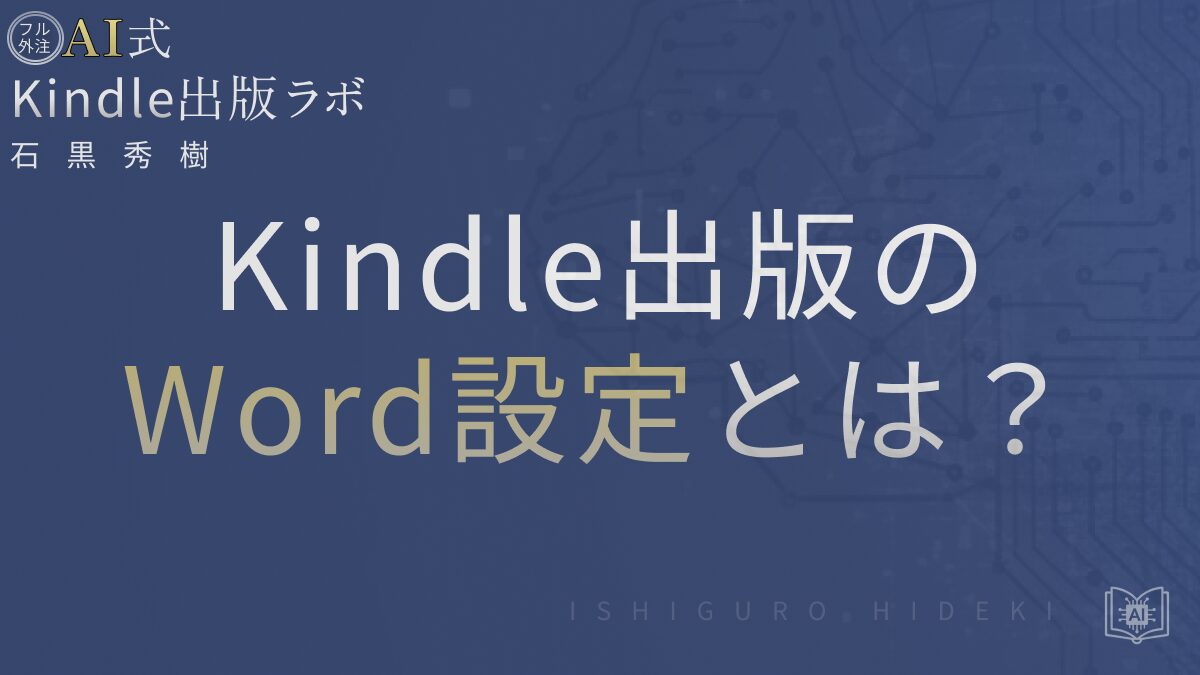
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「Word原稿をアップしたらレイアウトが崩れた」という経験、ありませんか。
Wordは多機能で使いやすい反面、KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)の仕様を理解していないと、体裁が思わぬ形で崩れてしまうことがあります。
この記事では、なぜWord設定がKindle出版で重要なのかを、実体験に基づきながらわかりやすく解説します。
特にこれから初めて電子書籍を出す方がつまずきやすい「Word特有の落とし穴」に焦点を当て、失敗を防ぐ実務的なポイントを紹介します。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「Word設定」がKindle出版で重要なのか
目次
Kindle出版でWord設定を軽視すると、どんなに内容が良くても読者にとって「読みにくい本」になってしまいます。
電子書籍はスマートフォンやタブレットなど端末ごとに自動的にレイアウトが変化するため、紙のように固定レイアウトを前提とした設定では対応しきれません。
そのため、Word原稿の段階でリフロー型(文字サイズや行数が可変)に対応した書式を整えておくことが非常に重要です。
ここではまず、電子書籍と紙書籍の構造的な違いと、Word原稿が崩れやすい典型例を押さえておきましょう。
電子書籍(Kindle本)と紙書籍の書式違い
Kindle本の多くは「リフロー型」と呼ばれる形式です。
これは、読者が端末で文字サイズや行間を自由に変更できるようになっており、ページ数は固定されません。
つまり、紙書籍のように「1ページにこの行数」「ここに画像を配置」といった設計はできず、構造的に流動する文章構成を意識する必要があります。
一方、Wordはもともと印刷前提で使われてきたソフトです。
そのため、余白を空白行で調整したり、ページ番号を固定したりといった操作をついしてしまいがちです。
しかし、これをそのままKDPにアップすると、プレビュー画面で改ページや画像位置がずれてしまうケースが非常に多いのです。
実際、筆者も初回出版時に「見出しがページの中ほどで切れる」「画像が次の章に飛んでしまう」といった崩れを経験しました。
この失敗の原因は、Word側の見た目に合わせて「手動整形」をしていたことでした。
電子書籍では、Word上の見た目を整えるよりも、構造(見出し・段落・改ページのタグ)を正しく設定することが大切です。
Word原稿で体裁が崩れやすい典型例
では、どんな設定や操作が崩れの原因になるのでしょうか。
代表的な例をいくつか挙げます。
まず、空白行を複数入れて改ページを作るケースです。
Wordでは見た目が整っても、KDP変換時にはその空白が端末の画面サイズによって圧縮または拡大され、予期せぬ余白になります。
次に、独自フォントや特殊な文字装飾を多用するケースです。
Kindleでは一部のフォントが再現されず、デフォルトフォントに置き換えられることがあります。
そのため、本文は標準フォント(MS明朝、游明朝など)をベースに設定するのが安全です。
また、画像の挿入方法にも注意が必要です。
「テキストの折り返し」で配置した画像は、端末サイズにより大きく崩れます。
画像は「行内」に設定し、Word上で本文と同じ流れに沿わせるのが基本です。
さらに、ヘッダー・フッター・ページ番号を設定してしまうのもよくある誤りです。
電子書籍ではページ番号の概念がないため、これらの要素は正しく表示されません。
筆者の経験上、Word設定を正しく整えるだけで、KDPプレビューでの修正時間を半分以下に短縮できます。
逆にここを怠ると、公開直前に体裁崩れを修正する羽目になり、時間を大きく浪費します。
「Word設定は後で直せばいい」と思わず、原稿作成の最初から正しい設定を行うことが、Kindle出版成功の第一歩です。
Wordで原稿を準備する|基本設定とテンプレート作成
Wordでの原稿準備は、Kindle出版の品質を左右する最初の関門です。
「後で整えればいい」と思って設定を後回しにすると、最終段階でレイアウト崩れが連鎖的に発生します。
筆者自身も最初の出版時、Word原稿をそのままアップして何度も修正を繰り返す羽目になりました。
ここでは、最初から崩れにくいWord設定を整える方法と、執筆効率を上げるテンプレート作成のコツを解説します。
フォント・サイズ・行間・インデントの基本設定
まずは本文の基本設定です。
本文のフォント指定は端末側フォントに置換される場合があるため、装飾書体前提での体裁依存は避ける。基本は標準系の書体想定で設計。
実務的には「游明朝」「MS明朝」「游ゴシック」のいずれかが無難です。
独自フォントや装飾書体は避け、端末側の自動変換に任せる方が安全です。
文字サイズは10.5〜12ポイントが読みやすい範囲です。
Word上では12ポイントでも、Kindle端末では読者が文字サイズを変更できるため、あくまで「基準」として設定します。
行間は1.15〜1.5倍を目安にし、詰まりすぎず空きすぎない範囲で調整しましょう。
インデント(字下げ)は、段落設定で「最初の行を1字下げ(約0.5cm)」に指定します。
スペースキーで手動で下げるのはNGです。
KDP変換時に空白が不規則に扱われ、読みにくい段落になることがあります。
これらの設定を「標準スタイル」に反映しておくと、本文全体に自動適用されて効率的です。
見出しスタイル(見出し1/見出し2)を設定する理由
見出しは、Wordの「スタイル」機能を使って設定します。
「見出し1」「見出し2」を使うことで、KDP側で自動的に章・節の構造を認識し、目次リンクを生成できます。
単に文字を太字にしたり大きくしただけでは、見出しとして認識されません。
この点は、Kindle初心者が最もつまずくポイントです。
公式ヘルプでも、Wordの見出しスタイルの使用を推奨しています。
実際に筆者も、見出し設定を忘れてアップロードした際、KDPプレビューで「目次が空白」「章間のジャンプが効かない」状態になりました。
Wordの見出し1=章タイトル、見出し2=節タイトル、とルールを決めておくと整然とした構造になります。
さらに、Wordの「ナビゲーションウィンドウ」で章構成を確認できるようになるため、全体の構成把握も容易です。
この設定を怠ると、後で目次のリンク設定を手作業でやり直すことになり、作業時間が何倍にも膨らみます。
KDPに限らず、電子書籍の構造設計の基本は「見出しタグの正しい使い分け」です。
見出し構造の整え方をさらに具体的に知りたい方は『Kindle出版の原稿の書き方とは?見出しと目次で整える基本手順を徹底解説』もあわせて確認してください。
テンプレートを作って効率化する手順
原稿を複数冊出版する予定がある場合は、最初にテンプレートを作っておくと便利です。
テンプレートとは、本文・見出し・行間・余白・目次の書式を統一した“原稿のひな型”のことです。
一度設定しておけば、新しい本を作るときもゼロから設定し直す必要がありません。
手順はシンプルです。
まず、基本設定(フォント・サイズ・行間・インデント・見出しスタイル)を整えたWordファイルを開きます。
次に「名前を付けて保存」から「Wordテンプレート(.dotx)」を選択し、保存します。
これを元に新規原稿を作成すれば、自動的に同じ書式が適用されます。
筆者の経験では、テンプレート化しておくと1冊あたりの整形時間を30〜40%短縮できます。
とくに、AIや外注で原稿を量産する場合、テンプレートがあるだけで品質のブレを防げます。
公式ガイドラインにはテンプレートの提供はありませんが、Wordの標準機能で十分対応可能です。
まとめると、Word設定の基本は「最初に整える・手動調整を避ける・構造で制御する」。
この3つを意識することで、KDPアップロード後の崩れや修正時間を大幅に減らせます。
出版をスムーズに進める第一歩は、Wordの設定を“整った状態で始める”ことです。
初心者でもすぐ使えるテンプレート設定例は『Kindle出版のテンプレートの選び方と使い方を徹底解説|初心者が失敗しないポイントとは』で具体的に紹介しています。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle出版用Word原稿の具体的な手順(目次・画像・改ページ)
Word原稿をKDPにアップロードする前に整えておくべき項目は、大きく「目次」「画像」「改ページ」の3つです。
この3点を正しく設定しておくと、KDPで自動変換された後も読みやすく、端末間での表示崩れが起きにくくなります。
ここでは、公式ガイドラインに沿いながら、実際の執筆経験に基づいた実務的なポイントを整理します。
目次を自動作成し、リンクを有効化する方法
まず、Wordの「自動目次」を使うことで、KDPが章構造を正しく読み取り、Kindle端末上で“目次からジャンプ”できるようになります。
この仕組みは、Wordで設定した「見出し1」「見出し2」スタイルをもとに自動生成されます。
太字やサイズ変更だけではKDPが章を認識できないため、見出しスタイルの設定が前提です。
手順は次の通りです。
1. 各章タイトルを「見出し1」、節を「見出し2」に設定。
2. 「参考資料」タブ →「目次」→「自動目次」を挿入。
3. 作成された目次を選択し、右クリックで「フィールドの更新」を行う。
これで、見出しを追加・修正した際も自動でリンクが更新されます。
ただし、KDPにアップロード後に一部リンクが切れることもあります。
これは、Wordの「手動目次」や余計な改行・ページ番号を含んだ場合に起こりやすいです。
筆者も初期の頃、見た目を整えようとして手動で目次を編集し、KDPでリンクが無効になった経験があります。
公式ヘルプでも、“自動目次を使用し、Word標準の見出しスタイルに従う”ことが推奨されています。
目次リンクの抜け漏れを防ぐチェックリストは『Kindle出版の目次とは?論理目次の作り方と確認方法』で必ず確認しておきましょう。
自動生成される目次の仕組みや構造化のコツは『Kindle出版の目次とは?論理目次の作り方と確認方法を徹底解説』で手順付きで解説しています。
画像・リンク・改ページ処理で押さえるべきポイント
画像は「テキストの折り返し」を使わず、「行内」に設定します。
これにより、本文と画像が一体化し、端末の画面サイズが変わってもレイアウトが崩れにくくなります。
本文中の画像は長辺1000px以上を目安にし、ファイルサイズは過度に重くしない(公式ヘルプ要確認)。比率固定で“行内”配置。
端末間の表示差を最小化する画像の最適値は『Kindle出版の画像設定とは?サイズ・形式・解像度を徹底解説』が参考になります。
リンクは「ハイパーリンクの挿入」から設定し、できるだけ本文に自然に埋め込む形にします。
URLをそのまま貼るよりも、文中にキーワードをリンク化した方が見た目も整います。
ただし、Amazonのポリシー上、読者を他サイトに誘導する過度なリンクは避けましょう。
改ページは「Ctrl+Enter」で挿入します。
空白行を複数入れて改ページを作ると、KDP変換時に余白が大きくなったり章タイトルがズレたりします。
また、章末に不要な改ページを残すと、電子書籍上で不自然な空白ページが発生します。
筆者の経験上、1冊に数百箇所もある空白を削除するのはかなり手間です。
作業中から「段落記号(¶)」を表示し、改ページを明確に管理しておくとミスを防げます。
「画像は行内」「改ページはCtrl+Enter」という2つの基本ルールを徹底するだけで、レイアウト崩れの9割は防げます。
画像サイズや比率の具体的な最適値については『Kindle出版の画像設定とは?サイズ・形式・解像度を徹底解説』に詳しくまとめています。
WordファイルのDOCX形式でアップロードする際の注意点
KDPでは、Wordファイル(.docx)をそのままアップロードできます。
一方で、古い形式(.doc)や他ソフトから変換したファイルを使うと、変換時に文字化けや段落ズレが起こることがあります。
必ず「ファイル → 名前を付けて保存 → Word文書(.docx)」を選びましょう。
形式選びと変換時の注意点は『Kindle出版のデータ形式とは?対応ファイルとアップロード手順を徹底解説』も合わせて確認してください。
端末別の最終確認フローは『Kindle出版のプレビュー確認とは?オンラインとPreviewerの使い方を徹底解説』に沿って進めると漏れがありません。
アップロード後は、KDPプレビューアで各端末(スマホ・タブレット・Kindle端末)の表示を必ず確認します。
公式ガイドでは、変換後の確認を推奨していますが、実際にはプレビュー画面で章タイトルや画像位置がずれているケースが非常に多いです。
筆者も経験上、特に図表の前後に余白が生まれやすいため、必要に応じて画像上部に1行の改行を入れると安定します。
また、Word特有のフィールドコード(目次・脚注・リンクなど)は変換後に挙動が異なることがあります。
もし自動リンクが効かない場合は、一度Word上で「すべて更新」を行ってから再アップロードするのが確実です。
電子書籍の表紙はKDPで別途登録が基本。本文ファイルに重複挿入は避けるのが原則(ただし表示目的で入れる運用もあり・公式ヘルプ要確認)。奥付は本文側で管理可。
ペーパーバック版を作る場合はPDF形式でテンプレートに合わせて出力する必要がありますが、電子書籍とはルールが異なります。
そのため、電子書籍用は必ずリフロー型のDOCXを使用するのが基本です。
これらの設定を守れば、KDPの変換プロセスで大きな崩れはほぼ起きません。
Wordの段階で「構造を意識した原稿づくり」を意識しておくことが、出版後のトラブル防止につながります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
よくあるトラブルとその回避策(アップ後の崩れ・目次未リンクなど)
Kindle出版では、Word原稿をアップロードした後に「プレビューで崩れて見える」「目次が機能しない」といったトラブルが起こることがあります。
これらはWord側の設定ミスがほとんどですが、慣れていないと原因を特定しにくいものです。
ここでは、KDPで実際に起きやすい3つのトラブルと、その回避策を順に解説します。
レイアウトが崩れる原因と対策
もっとも多いのが、アップロード後に文字や画像の位置がズレる「レイアウト崩れ」です。
原因の多くは、Word内で「見た目を整えるための手動調整」をしていることにあります。
たとえば、空白行で余白を作る、スペースでインデントを取る、段組みを使う――これらは印刷前提の手法であり、電子書籍では不安定になります。
電子書籍はリフロー型(文字サイズや画面比率によって文章が流動する形式)なので、行や段の位置は端末ごとに変化します。
そのため、Wordの「段落設定」や「改ページ」を使って構造的に余白を管理するのが正解です。
画像がズレる場合は、「行内」以外の配置設定を使っている可能性が高いです。
Wordの「文字列の折り返し」を「行内」に変更すると、本文と一緒に画像が動き、ズレが起きにくくなります。
また、画像サイズが大きすぎる場合もKDP変換時に縮小されることがあります。
幅は600〜800ピクセル程度を目安に、Word上で圧縮ではなく「トリミング」で調整するのがおすすめです。
さらに、箇条書きや表を多用すると、KDPで意図しない余白が入ることがあります。
筆者も、Word上では整っていた表が、Kindleプレビューでは縦に間延びしてしまった経験があります。
表はできるだけシンプルにし、行数を減らすことで安定します。
公式では、複雑な表は画像に変換して挿入する方法も案内されています。
要するに、「Wordで見た目を整える」より「構造を正しく設定する」ことが、崩れを防ぐ最大のポイントです。
目次がリンクされない・ページ表記がズレる問題
目次のリンクが効かない、ページ表記がずれる――これも非常に多いトラブルです。
この原因は、「手動目次」や「ページ番号」を使っていることにあります。
Wordの自動目次機能を使わずに手入力で作った目次は、KDP変換時にリンク構造が失われます。
正しい手順は、見出しスタイルを設定したうえで「自動目次」を挿入することです。
こうすることで、KDP側が見出し構造を認識し、目次リンクを自動生成します。
目次を更新する際は、「フィールドの更新」→「すべて更新」を必ず実行してください。
筆者もこれを忘れてアップロードした際、Kindle端末で章ジャンプが機能しませんでした。
また、Word上の「ページ番号」は電子書籍では無意味です。
リフロー型の電子書籍ではページ数が端末や文字サイズで変化するため、固定のページ番号を挿入しても正しく反映されません。
代わりに、章タイトルで構成を整理し、目次リンクで移動できるように設計しましょう。
なお、プレビュー時に「目次が表示されない」場合でも、KDPで公開後は正しく機能することがあります。
この挙動はKDP特有のもので、必ずしもエラーではありません。
それでも不安な場合は、KDP公式の「Kindle Previewer」を使って端末別の表示を確認すると安心です。
KDP公式ガイドラインで確認すべきポイント
KDP公式ガイドラインは、Wordでの電子書籍作成に関して詳細な手順を公開しています。
ただし、すべてを読むとかなりの分量がありますので、最低限チェックすべき箇所を整理します。
まず、KDP公式ヘルプの「Word原稿の作成」ページには、対応フォント・スタイル・改ページ方法が明記されています。
ここで特に重要なのは、「見出しスタイルを使用する」「自動目次を利用する」「ページ番号を入れない」という3点です。
これらはAmazon.co.jpでも共通で適用されています。
また、画像や表の挿入方法、特殊記号の扱いも公式でガイドされています。
たとえば、数式ツールを使った場合、変換後に文字化けする可能性があるため、画像化を推奨しています。
一方で、公式情報だけではカバーしきれない“実務上の注意”もあります。
たとえば、「Word上では正常でも、KDPプレビューで改ページがずれる」ケース。
これは非表示文字や段落マークが影響していることが多く、「非表示文字を表示」して確認すれば原因がわかります。
筆者の経験では、公式の手順に従いつつ、自分なりの「原稿チェックリスト」を持つことが最も効果的です。
アップロード前に目次・画像・改ページを確認するだけで、ほとんどのトラブルは防げます。
KDPガイドラインは頻繁に更新されるため、不確かな点は必ず最新の公式ヘルプを参照しましょう。
Wordの使い方がわかれば誰でも対応できますが、仕様変更に備えて「公式+実践」の両面から確認しておくのが安心です。
まとめると、KDPのトラブルは事前のWord設定で9割防げます。
電子書籍は構造で制御する媒体であり、「手作業で整える」より「正しいルールに沿って組み立てる」意識が何より大切です。
実践事例:Word原稿から出版までスムーズに行った著者の流れ
ここでは、実際にWord原稿を使ってKDP出版をスムーズに進めた著者の2つの事例を紹介します。
どちらも特別なスキルは必要ありませんが、「Word設定を最初に整えること」が結果的に大きな時短につながっています。
特に、テンプレート活用と画像処理の工夫は、初心者にとって最も効果的なポイントです。
事例紹介:テンプレート活用で30分で見出し→目次完成
最初の事例は、個人で自己啓発書を出版したAさんのケースです。
Aさんは、最初の原稿作成時にWord設定を何も意識しておらず、アップロード後に章の位置がずれるなどの問題が発生しました。
それをきっかけに、2冊目の制作では最初から「テンプレート化」を取り入れました。
Aさんが作成したテンプレートには、あらかじめ「標準」「見出し1」「見出し2」「引用」などのスタイルを設定し、行間とインデントも統一。
この状態で本文を流し込むと、Wordが自動的に構造を認識し、わずか30分で見出しと目次が整ったといいます。
結果として、目次リンクも自動的に生成され、KDPのプレビュー確認で修正不要だったとのこと。
筆者自身も同じ手法を実践していますが、テンプレートを作っておくと、章ごとの書式ズレを気にせず執筆に集中できます。
また、KDPで複数冊を出す場合も、書式統一ができるためブランドイメージを保ちやすくなります。
Wordのテンプレート機能は地味ですが、「書式ミスを根本から防ぐ最も確実な方法」です。
事例紹介:画像・リンク配置で文字化けやズレを回避した例
次に紹介するのは、写真多めの趣味本を出版したBさんの例です。
Bさんは、最初にアップロードした際に「画像が切れて見える」「リンクが動作しない」という問題に直面しました。
原因は、Wordの「文字列の折り返し」を使って画像を自由配置していたことでした。
そこで、すべての画像を「行内」に変更し、幅を本文領域に収まるよう調整。
また、外部リンクをそのままURLで記載せず、本文中のキーワードにハイパーリンクを設定しました。
この2点を修正するだけで、文字化けもズレも完全に解消。
KDPプレビューで全端末チェックを行っても、表示崩れは一切なかったそうです。
筆者も画像の多い本を制作した経験がありますが、Word上の見た目を優先すると高確率で崩れます。
そのため、「行内配置+本文幅で統一」は画像付き原稿の鉄則です。
特にスマホで読まれることを前提に考えると、シンプルな構造のほうが圧倒的に読みやすくなります。
このように、Word原稿の正しい設定を早い段階で取り入れることで、修正コストをほぼゼロにできるのが大きなメリットです。
テンプレートや配置ルールは一度作っておけば何度でも使えるため、出版を継続的に行う人ほど効果を実感できるでしょう。
まとめ|Word設定を整えてKindle出版を成功させよう
Kindle出版では、原稿の内容以上に「Word設定の正確さ」が完成度を左右します。
どんなに文章が良くても、章がズレたり画像が崩れたりすると読者の評価に直結します。
逆に、基本ルールを守るだけで仕上がりが劇的に安定します。
今回紹介したように、見出しスタイル・自動目次・行内画像・改ページの4つを意識するだけで、初心者でも高品質な電子書籍が作成可能です。
特別なツールや知識は不要で、Wordの標準機能だけで十分対応できます。
筆者の経験から言えば、Word設定を整えた原稿は、KDPプレビューでもほぼ修正なしで通過します。
この段階を丁寧に行うことが、最終的な作業効率と品質を決定づけます。
最後にもう一度だけ強調します。
「見た目で整えるのではなく、構造で整える」。
これがKindle出版のWord設定における最大の成功法則です。
この原則さえ押さえれば、どんな端末でも崩れない読みやすい本を作ることができます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。