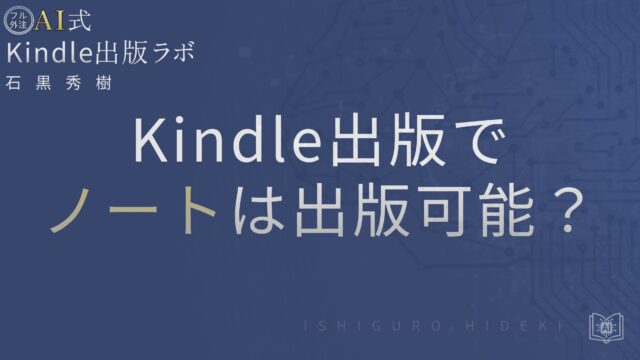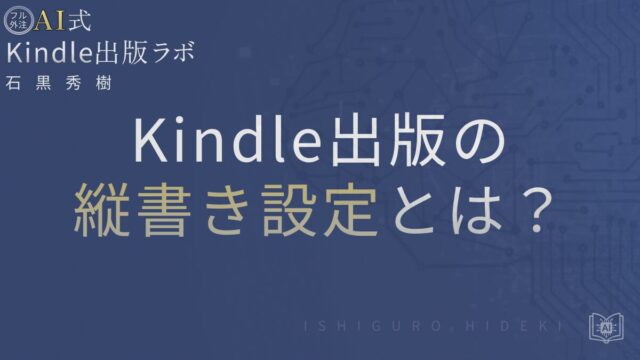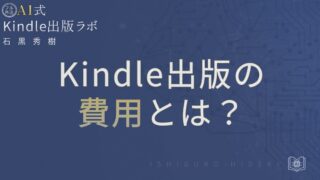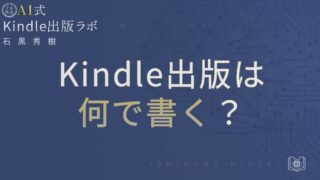Kindle出版の表紙サイズとは?初心者でも失敗しない最適設定を徹底解説
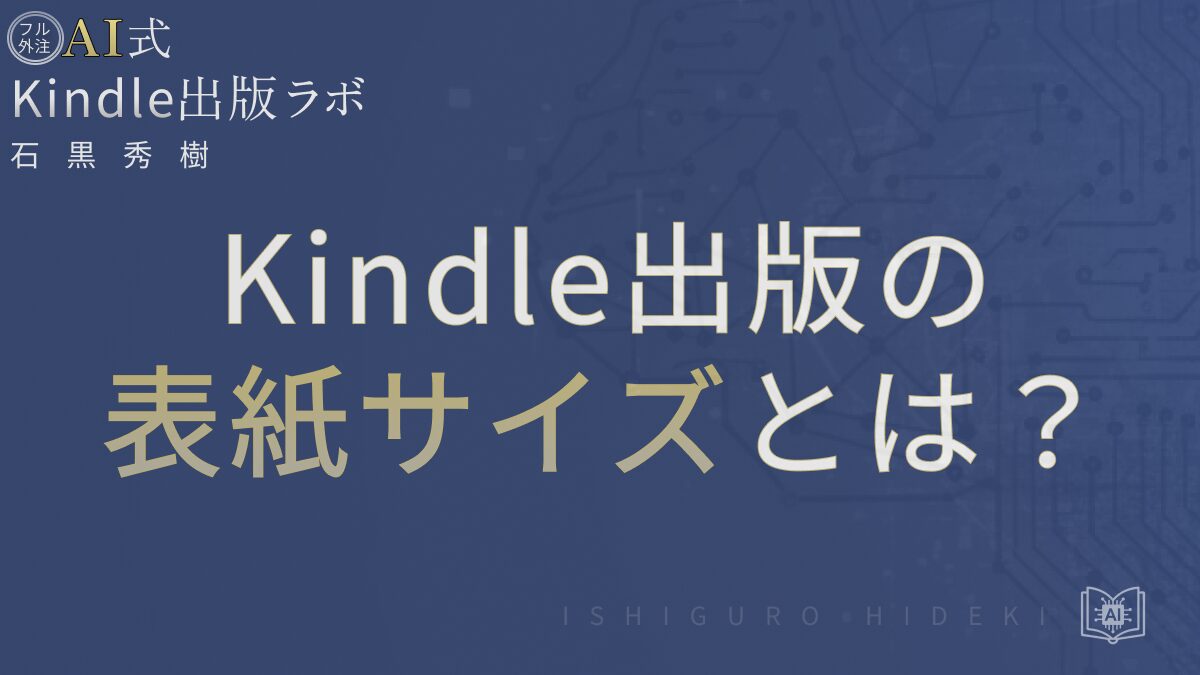
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
見栄えの悪いサムネイルや、アップロード後に「画像が粗い」「文字が切れた」という失敗を避けるためには、最初に正しいサイズを設定することが重要です。
この記事では、Amazon.co.jp 向けのKindle出版に最適な表紙サイズと、公式ガイドラインに基づく根拠を、初心者にもわかりやすく解説します。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
【結論】Kindle出版の表紙サイズは「縦2560×横1600・比率1.6:1」が基本(Amazon.co.jp向け)
目次
Kindleの表紙サイズは、まず「縦2560ピクセル × 横1600ピクセル」が基本です。
この比率(1.6:1)は、Amazonの販売ページやKindleアプリのサムネイル表示に最も適した形です。
日本の書籍のような縦長比率にしたくなる気持ちもわかりますが、Kindleではあくまでデジタル画面での見え方が重視されます。
そのため、紙の書籍感覚で設定すると「帯が切れる」「余白が広すぎる」などのズレが起きやすいです。
ここでは、KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)の公式推奨をもとに、なぜこのサイズが最適なのかを見ていきましょう。
表紙サイズと比率の全体像を先にざっと押さえておきたい方は、『Kindle出版の表紙サイズと比率とは?初心者が失敗しない設定を徹底解説』もあわせて読んでみてください。
Kindle出版 表紙サイズとは?サムネにも最適化できる推奨寸法の意味
「表紙サイズ」とは、Kindleストアの商品ページやアプリで表示される電子書籍の“顔”となる画像の縦横寸法のことです。
読者が最初に目にする部分なので、ここが整っていないと作品の印象が大きく損なわれます。
KDPの最小要件は長辺1000px以上、最大は長辺10000px程度です。比率1.6:1を満たすなら例として1000×625px以上が目安です(公式ヘルプ要確認)。
このサイズにしておけば、スマホ・PC・タブレットのいずれでも見栄えが安定し、拡大・縮小時の劣化も最小限で済みます。
また、1.6:1という比率は、横幅が広すぎず縦長すぎないため、タイトルや著者名が自然に収まるのも特徴です。
経験上、縦を長くしすぎるとタイトルが小さく見えたり、検索一覧のサムネで目立たなくなったりするので、あえてこの比率が選ばれています。
Kindle出版 表紙サイズの根拠:公式ヘルプ要件(比率・形式・色・容量は最新を確認)
Amazon公式ヘルプでは、電子書籍のカバー要件として以下の項目が示されています。
* 比率:1.6:1(縦長)
* 画像サイズ:推奨2560×1600ピクセル
* 形式:JPEGまたはTIFF
* 色:RGB(CMYKは非対応)
* 容量:50MB未満
この要件を守ることで、審査でリジェクトされにくく、ストア上での表示品質も安定します。
特にRGBカラーを使うことは忘れやすいポイントです。
印刷用のCMYKのままだと、色がくすんで見えたり、端末によって表示が崩れたりします。
また、公式は最低解像度の目安を示していますが、制作時は300ppi相当の画素密度で作成すると小サイズ表示でも輪郭が保たれます(dpi/ppiの用語は混同に注意、公式ヘルプ要確認)。
72dpiはあくまで“画面表示に必要な最低ライン”と理解しておくと良いでしょう。
もし最新仕様に変更があった場合は、KDP公式ヘルプページで最新情報を確認してください。
公式要件は随時更新されることがあり、古いブログ情報を参考にすると不具合が起こる場合があります。
この基本を押さえておけば、ほとんどのケースで「画像が粗い」「表示が切れた」といったトラブルは防げます。
作る前のチェックリスト:Kindle表紙で最低限そろえる仕様
Kindle出版の表紙づくりで一番多い失敗は、「サイズと設定をきちんと確認せずに作ってしまうこと」です。
表紙は作品の顔であり、最初に読者の目に入る部分です。
ここを正しく設定しておかないと、デザインの良し悪し以前に「審査で弾かれる」「サムネで潰れる」といった問題が起きてしまいます。
以下では、実際に出版経験をもとに、最低限そろえるべき4つの仕様(比率・形式・容量・背景処理)をわかりやすく整理しました。
比率1.6:1と推奨サイズ2560×1600の理由(小さな表示でも潰れない)
Kindleの表紙サイズで推奨されている比率は1.6:1(縦2560×横1600)です。
このサイズは、AmazonストアのサムネイルやKindle端末での自動リサイズに最も適しており、拡大縮小しても文字がつぶれにくいのが特徴です。
縦を長くしたり横を広げたりすると、画像の端が切れることがあります。
特に「紙の本の感覚で縦長にする」人が多いですが、電子書籍では画面比率が異なるため、バランスが崩れがちです。
私も最初の出版時に「書影が細長すぎて読者から見づらい」と言われた経験があります。
最初から推奨比率で作っておくと、すべてのデバイスで安定した見た目を保てます。
Kindle 表紙の画像形式と色空間:JPEG/TIFF・RGBを基本に
KDPが正式にサポートしている画像形式はJPEGまたはTIFFです。
どちらでも問題ありませんが、ファイル容量を抑えやすいJPEGが一般的です。
印刷物では「CMYK」が標準ですが、Kindleはディスプレイ表示なので「RGB」を使用します。
CMYKのまま入稿すると、色がくすんだり、思ったより暗く表示されることがあります。
制作ソフトで色空間を確認し、必ずRGBに変換してから書き出しましょう。
これは意外と見落としがちなポイントで、プロのデザイナーでもたまに混同する部分です。
画像の解像度や容量、保存形式をまとめて確認したい場合は、『Kindle出版の画像設定とは?サイズ・形式・解像度を徹底解説』で細かな設定ポイントをチェックしておくと安心です。
容量・解像度の考え方:圧縮は最小限/dpi・ppiは公式ヘルプ要確認
KDPでは、表紙画像の容量を50MB未満に抑える必要があります。
ただし、容量を減らすために過剰に圧縮すると、文字の輪郭がにじんで見えることがあります。
私は以前、容量を10MB以下にしようと圧縮しすぎて、スマホ表示でタイトルがぼやけた経験があります。
適度な圧縮を心がけ、文字がシャープに見える状態を保つことが大切です。
また、公式では「72dpi以上」と記載されていますが、実際には300ppi程度で作成しておくと印象がぐっと良くなります。
dpi(ドットパーインチ)とppi(ピクセルパーインチ)は似ていますが、dpiは印刷向け、ppiは画面表示向けの数値です。
KDPではppiの考え方で設定しておけば問題ありません。
不安な場合は、公式ヘルプで最新仕様を確認するようにしましょう。
白や淡色背景の“細枠”ルール:3〜4pxの境界でサムネ溶けを防ぐ
背景が白や淡い色の表紙では、Amazonのストア画面に並んだときに「背景と同化して見えづらい」問題がよく起こります。
この対策として、KDPの公式でも3〜4ピクセルの薄いグレーや黒の枠線を推奨しています。
単純な線でも、サムネイルで見たときに表紙の輪郭がはっきりし、他の書籍と差がつきます。
私も白ベースの表紙を出したとき、枠なしだと「余白だけの画像」と誤認されかけたことがありました。
一見地味なルールですが、特にスマホでの視認性に大きく関わる部分です。
書き出し前に小さな表示で確認し、白背景が消えていないかチェックすると安心です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
見え方を左右するデザイン原則(サムネ対策)
Kindle出版の表紙は、ただ美しいだけでは意味がありません。
読者がAmazonストアで並んだ書影の中から「思わずクリックしたくなる」ことが目的です。
そのためには、サムネイルでどう見えるかを意識したデザインが欠かせません。
ここでは、特に初心者が失敗しやすい3つのデザイン原則を紹介します。
タイトルは大きく短く:Kindle サムネで読める文字サイズ設計
Kindleの表紙で最も重要なのは、タイトルの「読みやすさ」です。
画面に表示されるサムネイルは非常に小さく、スマホだと幅200ピクセル程度しかありません。
つまり、どれだけ凝ったフォントや装飾を使っても、読めなければ意味がないのです。
私自身、初期の作品ではタイトルを細い明朝体にしてしまい、一覧で完全に文字がつぶれてしまった経験があります。
理想は、短く太めのフォントを使い、最小表示でも読める大きさにすることです。
長いタイトルの場合は、改行位置を意識して上段と下段に分けるとバランスが整います。
「短く・太く・中央に」——これがサムネイルで映える基本形です。
情報の優先順位づけ:副題・著者名・要素の引き算
表紙デザインの失敗で多いのが、「全部を詰め込みすぎる」ことです。
タイトル、副題、著者名、キャッチコピー、装飾…すべて入れると情報過多になり、結果的に何も伝わらなくなります。
特にKindleの電子書籍は、読者が一覧で数秒しか見ないため、1秒で伝わる構成にすることが大切です。
私が制作をサポートした著者の多くも、最初は「要素を減らす勇気」が持てませんでした。
しかし、不要な要素を削った途端、クリック率が上がるケースは非常に多いです。
副題やコピーは、小さく配置しても十分効果があります。
主役はあくまで「タイトル」。他の要素は“引き立て役”として整理しましょう。
余白とコントラスト:小画面での視認性を最優先
表紙を作るとき、余白を「もったいない」と感じて埋めてしまう人がいます。
しかし、デザインの世界では「余白は呼吸スペース」とも言われます。
要素同士の距離が詰まりすぎると、文字がごちゃついて読みにくくなるからです。
背景と文字のコントラスト(明暗差)も非常に重要です。
白地に薄い黄色の文字、黒地に紺などの組み合わせは、スマホでは完全に埋もれてしまいます。
シンプルに「明るい背景×濃い文字」または「暗い背景×明るい文字」に統一しましょう。
私の経験では、背景に写真を使う場合も、彩度を落として文字を際立たせると見やすさが一気に上がります。
「余白」と「コントラスト」の2つを意識するだけで、デザイン全体の完成度は大きく変わります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
制作フロー:最短で“適合&見栄え”に到達する手順
ここまでのポイントを踏まえたうえで、実際にKindle表紙を制作する手順を確認しておきましょう。
ここで紹介する流れは、デザイナーだけでなく、自作派の著者にも役立ちます。
KDPの要件を満たしながら、最短で完成度を高める工程を意識してください。
カンバス設定:最初に2560×1600で開始(リサイズ前提にしない)
最初に画像編集ソフト(CanvaやPhotoshopなど)でキャンバスサイズを設定します。
最初から2560×1600ピクセルに設定するのがポイントです。
後からリサイズすると、文字や画像がぼやけたり、配置がずれる原因になります。
制作段階から最終サイズで作ることで、余計な修正を防げます。
表紙全体の構成や作業手順を一から確認したい場合は、『Kindle出版の表紙作り方とは?初心者でもできるデザイン手順と注意点を徹底解説』を参考にしながら進めると、迷わず完成までたどり着けます。
また、文字や要素を配置する際は「中央寄せ」を意識しましょう。
Kindleでは自動的に余白調整がかかることがあるため、中央バランスを取っておくと安心です。
文字と要素の安全余白:端からの離し方とガイド線
KDPでは「重要な要素を端に寄せない」ことが推奨されています。
端ぎりぎりまで文字を置くと、端末によっては切れてしまう可能性があるためです。
経験的には、端から最低でも100ピクセル程度の余白を確保しておくと安心です。
PhotoshopやCanvaなどでは、ガイド線を引いて安全領域を作ると配置が安定します。
また、中央揃えにすることで、どの端末でも均等に見える仕上がりになります。
書き出し前の検証:縮小プレビューと容量チェックのコツ
表紙を完成させたら、必ず「縮小プレビュー」で確認しましょう。
実際のサムネイルサイズに縮小して、文字が読めるか、色が飛んでいないかを確認します。
次に、画像の容量が50MBを超えていないかチェックします。
JPEG形式で保存する際に「品質80〜90%」に設定すれば、見た目を保ちながら容量を抑えられます。
私も最初は100%品質で書き出して容量オーバーになったことがありましたが、この設定で解決しました。
最後に、RGB設定が維持されているかを再確認し、アップロードすれば完了です。
小さなチェックですが、このひと手間がトラブル防止につながります。
制作フロー:最短で“適合&見栄え”に到達する手順
Kindleの表紙は、感覚だけで作ると必ずどこかで不具合が出ます。
「サイズは合ってるのに端が切れた」「画像が粗い」など、原因の多くは制作手順の順番ミスです。
ここでは、私が実際にKDP出版を繰り返す中で磨いた最短で見栄えと規格を両立する制作フローを紹介します。
一度流れを掴めば、次回以降の作業は半分以下の手間で済みます。
カンバス設定:最初に2560×1600で開始(リサイズ前提にしない)
最初に画像編集ソフト(Canva・Photoshop・Pixlrなど)で、新規ファイルを「2560×1600ピクセル」で作成します。
この時点で間違えると、後から修正してもぼやけたり比率がずれたりして、仕上がりに影響します。
初心者の方に多いのが「A4サイズで作ってあとで変える」というパターンです。
ですが、Kindleの比率(1.6:1)はA4とは異なるため、文字や画像の位置がズレます。
最初から正しい比率で作業することが、後悔しない近道です。
もし別サイズで作った場合は、拡大ではなく縮小で調整すると劣化を最小限に抑えられます。
また、ファイル単位でテンプレートを保存しておくと便利です。
私も最初は毎回サイズ入力をしていましたが、テンプレ化してから作業時間が半分になりました。
KDPのガイドラインは時々更新されるため、制作前に公式ヘルプの数値を再確認する癖もつけておきましょう。
文字と要素の安全余白:端からの離し方とガイド線
次に、文字や画像を配置するときの「安全余白」を確保します。
Kindleでは、端末やアプリによって微妙にトリミングされる場合があります。
そのため、文字やロゴをギリギリに配置すると、審査には通っても実際の表示で切れてしまうことがあります。
目安としては、上下左右100ピクセル以上は余白を確保するのが安全です。
私は最初の頃、タイトルをぎりぎりまで広げて配置した結果、スマホ版で下部が削られてしまいました。
見た目のバランスを取るよりも、「どんな端末でも読める配置」を優先するのがコツです。
ソフトのガイド線(ルーラー)を使って、中央軸を可視化しておくと便利です。
このガイドに合わせて要素を配置すれば、左右のずれや傾きが起きにくくなります。
また、タイトル・副題・著者名などのテキスト要素は、デザインよりも「可読性」を基準に整えることが大切です。
見た目よりも読みやすさを重視することで、審査後のトラブルも減らせます。
書き出し前の検証:縮小プレビューと容量チェックのコツ
表紙が完成したら、最後に行うべきは「検証」です。
この段階を省略すると、後で修正アップロードをする羽目になります。
まず、画像を縮小してプレビューし、タイトルや副題が読めるか確認しましょう。
実際のAmazonストアでは、幅200ピクセル前後で表示されることが多いです。
このサイズで文字が潰れていないなら、ほぼ合格です。
私も最初の頃は「画面全体では完璧」でも、一覧表示で完全に読めないことがありました。
プレビューを見ながら微調整することで、視認性の高いデザインに仕上がります。
次に、ファイル容量をチェックします。
KDPでは50MB未満という制限がありますが、私は常に20MB前後を目安にしています。
JPEG形式なら品質を80〜90%に設定すると、見た目を保ちながら容量を抑えられます。
また、書き出し時にRGBカラーが維持されているかも確認してください。
書き出し時の設定でCMYKに変換されると、色味が暗くなることがあります。
最後に、ファイル名を半角英数字にして保存し、アップロード時のトラブルを防ぐのも地味に重要です。
Kindle表紙の制作は、慣れれば30分以内で仕上がります。
ただし、そのためには「正しい順番」で作業することが前提です。
これらの手順を一度テンプレート化しておけば、次回以降の作業は格段にスムーズになります。
よくあるトラブルと解決策(Kindle出版・電子表紙)
どんなに丁寧にデザインしても、実際にアップロードしたときに「思っていた見え方と違う」と感じる人は多いです。
Kindleの表紙トラブルは、慣れていない人ほど同じミスを繰り返しがちです。
ここでは、私自身の経験も交えながら、よくある4つの問題とその対処法を整理して解説します。
ぼやけ・粗い:元画像の不足/過度圧縮の見直しと再出力
一番多いのが「画像がぼやける」「文字がにじむ」といったトラブルです。
原因の多くは、元画像の解像度不足か、JPEG圧縮を強くかけすぎていることです。
KDP側で画像が処理される可能性があるため、過度な圧縮は避けて品質80〜90%程度での書き出しを基準にしましょう(公式ヘルプ要確認)。
実務的には、解像度300ppi・品質80〜90%のJPEGで書き出すのが最も安定します。
また、Web上の素材をそのまま使うと、そもそも解像度が足りずに粗くなる場合があります。
もし画像を拡大して使う場合は、ぼかし補正やノイズ除去のフィルタを活用するのも一つの方法です。
それでも改善しない場合は、素材を差し替えるか、高解像度で作り直すのが確実です。
白背景が消える:薄灰の細枠で境界を明確化
背景が白や淡色の表紙を使うと、Amazonストアの背景(白)と同化して「どこまでが表紙か分からない」ことがあります。
この現象は、デザインとしてはきれいに見えても、サムネイル一覧では完全に埋もれてしまいます。
公式でも推奨されているように、3〜4ピクセルの薄いグレーまたは黒の枠線を外周に引くだけで劇的に改善します。
私も以前、白背景のまま出したところ、「クリックしても画像が反応しない」と勘違いされたことがありました。
この“細枠ルール”は地味ですが、視認性アップと誤解防止の両面で効果的です。
書き出し前にサムネサイズ(200px程度)でプレビューし、境界が見えるか必ず確認しておきましょう。
比率ズレ・はみ出し:カンバス固定+トリミングで統一
表紙の縦横比がズレると、KDPのプレビュー画面で上下が切れたり、端が黒く表示されたりします。
原因は、途中でカンバスサイズを変更したり、画像をリサイズして比率が崩れたまま書き出すことです。
この問題を防ぐには、制作の最初から最後まで2560×1600の比率を固定するのが鉄則です。
どうしても別比率の素材を使う場合は、中央配置にして余白部分を背景色で埋めるときれいに収まります。
私は以前、A4比率の画像を無理やり合わせて端が切れたことがあり、それ以降テンプレートを固定して使うようにしました。
もしKDPで警告が出た場合は、画像全体を少し縮小し、再トリミングすれば解消できるケースが多いです。
アップ後の表示差:端末・アプリ差は想定し最小要件を遵守
最後に意外と盲点なのが、「端末やアプリによって見え方が違う」という点です。
Kindle端末・スマホ・PC・Fireタブレットでは、色味や明るさの再現が微妙に異なります。
特に黒背景や暗めの色合いは、端末によって沈んで見えることがあります。
これは不具合ではなく仕様なので、完全一致は不可能です。
そのため、制作時は「どの端末でも破綻しない中間色」を選ぶのが安全です。
経験上、やや明るめ・やや彩度を抑えたトーンにすると、どの環境でも安定して見えます。
また、KDPにアップした後は、プレビュー機能で各端末の見え方を必ず確認しましょう。
特定端末で崩れて見える場合も、比率と最小サイズ(縦2560×横1600)を守っていれば審査上の問題はありません。
公式の表示要件に沿っていれば、軽微な見え方の違いは許容範囲内と考えて大丈夫です。
作例とテンプレ活用:失敗を避ける最短ルート
初めてKindle出版の表紙を作るとき、「何を参考にすればいいのか分からない」という声をよく聞きます。
ゼロからデザインを組もうとすると時間がかかるうえ、構成のバランスを取るのも難しいです。
ここでは、実際にクリック率の高かった表紙の共通点と、手早く仕上げるためのテンプレ活用法を紹介します。
私も最初の頃は手探りで作っていましたが、今ではこの2ステップを押さえるだけでほとんど失敗しなくなりました。
良い表紙の共通点:強いタイトル/高コントラスト/情報の引き算
売れているKindle本の表紙には、いくつかの共通点があります。
まず、目を引くのは「タイトルの力」です。
フォントや配置よりも、“ひと目で読める太さと短さ”が最優先です。
長いタイトルは途中で切れるため、上段と下段で分けるか、サブタイトルを後半に回すとバランスが良くなります。
次に重要なのが「コントラスト」。
明るい背景に暗い文字、または暗い背景に明るい文字を重ねると、遠目でもくっきりと見えます。
中間色どうし(例:ベージュ×茶色)だと、スマホではほぼ判別できません。
特にサムネサイズでは明暗差が印象を左右するため、コントラストを意識して配色を決めましょう。
最後に「情報量の整理」です。
タイトル・副題・著者名・コピーなどを詰め込みすぎると、全体が窮屈になります。
読者は数秒で判断するので、1枚の表紙で伝えるメッセージはひとつに絞るのが理想です。
実際、私が支援した著者の中でも、要素を減らして余白を広げた作品のほうが、クリック率が明確に高い傾向がありました。
「見せたい情報を削る勇気」が、デザイン成功の第一歩です。
テンプレの使い方:比率固定→色替え・写真差替えで時短
デザインに慣れていない方は、テンプレートを使うのが最短ルートです。
特にCanvaやAdobe Expressなどでは、Kindle向けサイズのテンプレも多く、初心者でもプロ品質の見た目に近づけます。
Canvaを使って具体的にどのテンプレートを選び、どのようにカスタマイズすればよいかは、『Kindle出版+Canvaで失敗しない表紙作成徹底解説』で手順付きで詳しく紹介しています。
使う際のポイントは、必ず「比率固定」で始めることです。
テンプレのサイズを変更すると、文字や画像がずれて比率も崩れるため、必ず2560×1600のまま編集します。
そこから色を変えたり、写真を差し替えたりするだけで印象を一新できます。
この方法なら、構図やバランスを保ったまま、わずか15〜30分で表紙が完成します。
私自身、最初はゼロから作って3時間以上かかっていましたが、テンプレ活用後は制作時間が10分の1に減りました。
テンプレをベースにして、文字配置や配色だけを自分のテーマに合わせて調整する。
これが「効率よく・美しく・規格通り」に仕上げる最短手順です。
まとめ:まずは2560×1600・比率1.6で“見える化”し、細枠と縮小検証で仕上げる
Kindle出版の表紙は、まず正しいサイズ設定(縦2560×横1600・比率1.6:1)を守ることが基本です。
これをベースに、タイトルの読みやすさ・色のコントラスト・余白の取り方を意識するだけで、印象は大きく変わります。
仕上げの段階では、白背景の細枠追加と縮小プレビュー確認を忘れないでください。
これをやるかどうかで、スマホでのクリック率に確実な差が出ます。
最初はテンプレートを使っても構いません。
経験を重ねるうちに、自分の作品に合ったスタイルが自然と身についていきます。
焦らず、KDPの公式ルールを守りながら、「見える表紙」を一枚ずつ磨いていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。