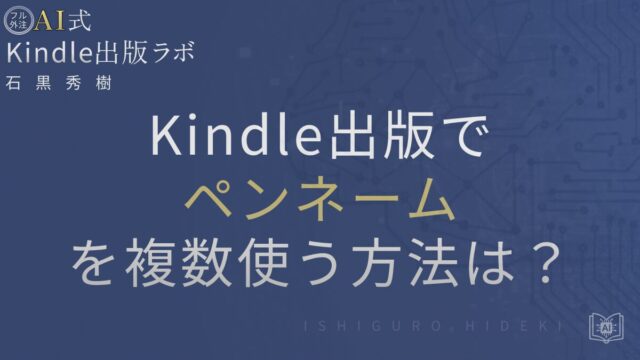Kindle出版は副業禁止の会社でもできる?就業規則と税金の注意点を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版に興味はあるけれど、「うちの会社、副業禁止なんだけど大丈夫かな?」と迷っていませんか。
実際、この質問は非常に多くの人が抱える不安のひとつです。
結論から言えば、Kindle出版自体は法律で禁止されていません。
ただし、勤務先の就業規則に副業禁止の条項がある場合、一定の制限を受ける可能性があります。
この記事では、Kindle出版が「副業」にあたるかどうか、その判断基準と注意点を整理し、会社員でも安全に始めるための基本を解説します。
Kindle出版を会社員として安全に始めるための就業規則と税務上の注意点は、『Kindle出版は副業禁止の会社でもできる?就業規則と税金の注意点を徹底解説』で詳しく整理しています。
特に、実際に出版している人が陥りやすい落とし穴や、公式ガイドラインと実務上の違いについても触れます。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版は副業禁止の会社でもできる?【結論:就業規則で決まる】
目次
Kindle出版を「副業」として扱うかどうかは、法律よりも勤務先の就業規則に左右されます。
同じ「会社員」でも、企業ごとに副業の扱い方が異なるため、一律に「OK」「NG」とは言えません。
実際、厚生労働省が副業を推奨する方針を出してから、多くの企業が副業規程を緩和しましたが、依然として禁止または許可制を設けている会社も少なくありません。
つまり、「Kindle出版=必ず副業禁止に抵触する」とは限らないのです。
就業規則では、会社の信用を損なう行為や、業務に支障をきたす副業を制限している場合が多く、趣味・創作活動としての出版であれば問題にならないケースもあります。
ただし、勤務時間中の執筆や、会社の機密情報に関連する内容を扱うと懲戒対象となるおそれがあります。
まずは、自分の会社の規程を読み直すことから始めましょう。
Kindle出版とは?個人でもできるAmazonの電子書籍出版
Kindle出版とは、Amazonが提供する「Kindleダイレクト・パブリッシング(KDP)」という仕組みを使い、誰でも自分の本を電子書籍として販売できるサービスのことです。
専門的な知識や出版社との契約がなくても、文章やイラストなど自作コンテンツをアップロードすれば、AmazonのKindleストアで販売が可能になります。
印税(ロイヤリティ)は条件により35%または70%のレートで支払われます(適用条件は公式ヘルプ要確認)。
個人が自分のペースで作品を公開できる自由さが最大の魅力ですが、その分、責任も伴います。
著作権や表現内容、税務処理など、すべてを自分で管理する必要があるため、会社員の副業として始める場合は慎重な判断が求められます。
「副業禁止」の会社でもKindle出版ができるかを判断するポイント
「うちの会社、副業禁止なんだけど、出版してもいいの?」という質問に対する答えは、ケースによって変わります。
判断の基準は次の3点です。
1. **就業規則に明記されているか**
「許可なく報酬を得る副業を禁止する」と書かれている場合は、明確に副業扱いとなります。
一方で、「営利目的の他事業」などと限定されていれば、創作活動が趣味の範囲と認められるケースもあります。
2. **会社との競合があるか**
勤務先の業務内容に関連するテーマ(例:会社のノウハウ・医療情報・顧客情報など)を出版すると、競業や守秘義務違反にあたる可能性があります。
3. **報酬の有無と規模**
KDPの印税はAmazonから支払われるため、一定の金額を超えると「所得」として申告が必要です。
特に給与所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が発生します。
公式上は問題なくても、住民税の処理方法によって会社に副業が知られるケースもあるため、事前に税務署や自治体の窓口で確認しておくのが安全です。
また、KDPは副業可否を判断する立場にはありません。
Amazonのガイドラインは「出版内容と著作権」に関するものであり、雇用契約上の副業問題は利用者自身の責任で判断する必要があります。
Kindle出版は法律で禁止されていないが、会社の就業規則に注意
Kindle出版そのものは、日本の法律で禁止されている行為ではありません。
誰でもAmazonのKDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)を使えば、自分の作品を電子書籍として公開できます。
しかし問題になるのは、法律ではなく「勤務先の就業規則」です。
会社ごとに副業のルールが異なり、たとえ創作活動でも「収益が発生すれば副業」と見なされることがあります。
そのため、KDPの利用を始める前に、まずは会社の規定を正確に理解しておくことが重要です。
副業禁止の根拠:会社ごとの就業規則で異なる理由
副業禁止の根拠は「法律」ではなく、各企業が定める就業規則です。
一般的に、企業は社員の勤務態度や会社の信用を守るため、「業務に支障が出る副業」「競合する事業への関与」「会社資産の不正利用」などを禁止しています。
つまり、副業を一律に禁止しているのではなく、「会社の利益を損なうおそれがある行為」を制限しているのです。
たとえば、勤務時間中にKDPの原稿を執筆したり、職場のノウハウを題材に本を出したりするのは明確にNGです。
一方で、仕事とは関係のない内容を、自宅で執筆・出版する場合は、問題視されないことも少なくありません。
ただし、「報酬を得る行為」と明記されている規定では、少額でも印税収入が発生すれば「副業」と判断されることがあります。
会社によっては、申請すれば認められるケースもあるため、判断に迷う場合は人事や労務担当に確認しておくと安心です。
創作活動や著作権収入は「副業」に当たるのか
多くの会社員が気になるのが、「趣味の延長で書いた電子書籍が副業にあたるのか?」という点です。
結論から言うと、報酬(印税)が発生した時点で「副業」とみなされる可能性があります。
ただし、すべての創作活動が問題になるわけではありません。
たとえば日記的なエッセイやイラスト作品など、職務とは無関係で、会社の業務に影響を与えない内容なら、趣味として扱われる場合もあります。
一方で、企業の機密や専門分野に関連した内容を出版すると、競業避止義務に抵触するリスクがあります。
著作権収入は「雑所得」や「事業所得」として扱われ、金額によって確定申告が必要になる点も忘れないようにしましょう。
特に、印税が年間20万円を超える場合は、給与以外の所得として確定申告を行う義務が発生します。
この手続きの有無で、税務上のトラブルが起きるケースもあるため注意が必要です。
会社にバレるリスクと「住民税通知」の仕組み
副業が会社に知られるきっかけの多くは、「住民税」の通知です。
Kindle出版で得た印税は、翌年の住民税に反映されます。
そして、会社が従業員の住民税を給与から天引きして納付している場合、住民税額が通常より多くなることで「副業収入があるのでは?」と気づかれることがあります。
このリスクを避けるには、確定申告の際に「住民税を自分で納付する(普通徴収)」を選択する方法があります。
ただし、すべての自治体で確実に対応できるわけではないため、必ず役所や税務署で確認してください。
また、マイナンバー制度の影響で、収入の追跡がより正確になっています。
そのため、故意に申告をしない、印税を「なかったこと」にするのは非常に危険です。
副業禁止の会社でも、誠実に対応していればトラブルを回避できるケースは多いです。
実際に私自身も、以前は会社員として出版を行っていましたが、勤務時間外での創作活動として問題視されませんでした。
要は、「会社に迷惑をかけない姿勢」と「正しい申告」が最も大切なのです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
副業禁止の会社員がKindle出版を安全に行うための対策
副業禁止の会社に勤めている場合でも、慎重に準備をすればKindle出版を行うことは可能です。
ただし、何も確認せずに始めてしまうと、会社規則や税務処理の面で思わぬトラブルになることがあります。
ここでは、会社員が安全にKindle出版を進めるための実践的なポイントをまとめます。
特に「事前確認」と「情報管理」を意識することが、リスクを最小限に抑える鍵です。
勤務先の就業規則・誓約書の確認方法
まず最初にやるべきことは、勤務先の就業規則を確認することです。
副業禁止の文言がある場合でも、具体的にどこまでが禁止されているのかを把握することが大切です。
「営利目的の活動」「会社と競合する業務」「会社の信用を損なう行為」など、禁止対象の範囲は企業によって異なります。
印刷した就業規則を読むだけでなく、入社時に署名した誓約書やコンプライアンス規定も見直しておきましょう。
これらには、副業や情報発信に関する具体的なルールが記載されている場合があります。
実務的には、人事・総務に匿名で質問したり、「副業」ではなく「創作活動」として確認をとるのも一つの方法です。
ただし、メールなど記録が残る形で問い合わせると社内に情報が残るため、相談内容は慎重に伝えるのが安心です。
匿名・ペンネームで出版する際の注意点
Kindle出版ではペンネーム(筆名)を自由に設定できます。
そのため、副業禁止の会社員でも、実名を出さずに出版することは可能です。
ただし、「匿名なら絶対にバレない」と過信するのは危険です。
Amazonアカウントの登録情報や税務処理の段階では、本人確認書類や銀行口座情報を提出する必要があるため、Amazon側には実名が登録されます。
また、SNSでの宣伝や口コミで筆名と実名が結びつくケースも多く、うっかり発言が原因で発覚することもあります。
筆名を使う場合でも、プロフィール欄や本の紹介文で勤務先や職業が特定される表現は避けましょう。
「個人の創作活動」として成立する範囲で運用するのが、安全な出版スタイルです。
テーマ選びで避けるべき内容(競業・倫理・過度な表現)
出版する内容の選定も非常に重要です。
副業禁止の会社員がトラブルになりやすいのは、「競合・機密・倫理違反」の3つの領域です。
まず競合については、会社の業務内容と近いテーマ(たとえば医療従事者が健康指南書を出すなど)は、競業とみなされるおそれがあります。
次に機密性では、社内で知った情報や取引先に関する内容を出版に使うのは厳禁です。
これらは著作権以前に守秘義務違反として処分対象になることもあります。
最後に倫理面です。
KDPのコンテンツガイドラインに違反する場合は、公開制限や削除の対象になります。表現の可否は文脈と程度によります(公式ヘルプ要確認)。
Amazonでは年々審査が厳格化しており、公開停止やアカウント制限になるケースもあります。
特に、成人向けや宗教・政治などセンシティブなテーマを扱う場合は、抽象化して書く・教育的文脈にするなど、ガイドラインに沿った表現に留めましょう。
内容を一度、公式の「KDPコンテンツガイドライン(日本版)」で確認することをおすすめします。
税金・確定申告の基本:年間20万円超の所得ルール
Kindle出版で得た印税収入は、原則として「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
給与所得以外の収入が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。
20万円以下であっても、住民税の申告は必要な場合があります。
確定申告をしないと、翌年の住民税額が正しく計算されず、会社に副業が知られてしまうリスクもあります。
住民税を自分で納付(普通徴収)に変更できる自治体もありますが、対応の可否は地域ごとに異なります。
心配な場合は、税務署や市役所に事前相談しておくとよいでしょう。
また、印税はAmazonから米ドルで支払われることがあり、為替レートの変動によって金額が前後します。
実務的には、振込明細やKDPレポートを保管し、年間合計を日本円に換算して申告します。
特に複数冊を出版する場合は、スプレッドシートなどで記録を残しておくと後で楽になります。
税金の扱いを曖昧にしたまま出版を続けると、思わぬ追徴課税になることもあります。
最初の1冊目から、きちんと管理する習慣をつけておきましょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
実際にKindle出版を副業として始めた人のケースと注意点
Kindle出版は、在宅でできる副業として注目を集めています。
しかし、会社員の立場で出版を行う場合、同じ「出版」でも扱い方によって結果が大きく分かれます。
ここでは、実際にKindle出版を始めた人のケースをもとに、問題にならなかった例とトラブルになった例を比較しながら、注意すべきポイントを解説します。
結論から言うと、「時間・内容・届出」の3点を意識すれば、大きな問題を防ぐことができます。
副業禁止の会社で出版しても問題にならなかったケース
ある会社員の方は、副業禁止規定がある企業に勤めながら、趣味でKindle出版を始めました。
テーマは「日常の気づき」や「エッセイ集」など、業務とは無関係な内容です。
収益も数百円〜数千円ほどと少額で、勤務時間外にすべての作業を行っていました。
このケースでは、就業規則の「会社業務に支障を与える副業」に該当せず、結果的に問題視されることはありませんでした。
また、筆名を使って匿名で活動し、SNSでの宣伝も控えめにしたことで、社内に知られるリスクも抑えられました。
KDPの仕組みを理解し、印税を正しく申告していた点もポイントです。
このように、会社の信用や時間を侵さない形で出版を行えば、実質的なトラブルは起きにくいのです。
逆にトラブルになったケースと共通点
一方で、トラブルになった人の多くには、いくつかの共通点があります。
代表的なのは、「勤務時間中に原稿を書いていた」「社内のノウハウを流用した」「税金の申告を怠った」などです。
ある例では、営業職の方が自社の販売手法をまとめた電子書籍を公開したところ、社内情報の持ち出しと見なされ、懲戒処分を受けました。
また、印税収入を申告しなかったことで住民税が増え、会社経由の通知で発覚するケースもよくあります。
もうひとつ多いのは、SNSでの告知や著者プロフィールから勤務先が推測されてしまうパターンです。
会社に直接迷惑をかけるつもりがなくても、外部の人から指摘されて社内に伝わるケースもあります。
これらのトラブルは、どれも「少しの油断」から起きているのが実情です。
トラブルを防ぐ3つの実務ポイント(時間・内容・届出)
Kindle出版を安全に続けるには、次の3点を意識すると効果的です。
1つ目は「時間」です。
勤務時間内には一切作業をせず、執筆や編集はあくまで就業後や休日に行うようにしましょう。
勤務中の作業は「業務専念義務違反」にあたる可能性があります。
2つ目は「内容」です。
会社の業務に関わる情報や、顧客データ、社内の用語・マニュアルなどは絶対に使用しないこと。
また、誤解を招くような発言や、特定の人物・企業を連想させる内容も避けるべきです。
3つ目は「届出」です。
副業申請制度がある会社では、あらかじめ相談・申請しておくと安心です。
仮に禁止されている場合でも、「創作活動として行いたい」と伝えれば許可が出ることもあります。
もし相談が難しい場合でも、確定申告や住民税の納付方法など、公的な手続きだけは必ず行いましょう。
これらを徹底することで、会社との信頼関係を保ちながら、安心してKindle出版を続けることができます。
特に副業禁止の会社員にとっては、「どこまでがOKなのか」を自分で判断できるようになることが、最大のリスク回避策です。
Kindle出版を始める前に確認すべきチェックリスト
Kindle出版を始める前に確認しておきたいのは、「思いつきで始めないこと」です。
出版は誰でも簡単にできますが、会社員であれば法的・実務的な注意点を押さえておかないと、思わぬトラブルを招く可能性があります。
ここでは、始める前にチェックすべき基本ポイントを整理します。
特に就業規則・KDP規約・税務処理の3点は、出版前に必ず目を通しておきましょう。
出版前に必ず確認したい法的・実務的ポイント
まず確認すべきは、勤務先の就業規則と副業に関する誓約内容です。
ここで「営利目的の活動を禁止」とある場合、印税が発生するKindle出版は副業扱いになることがあります。
そのため、就業時間外での活動であっても、内容やテーマ次第で制限される場合があります。
また、著作権・商標・肖像権の確認も欠かせません。
引用や著作権の扱いに迷う場合は、『Kindle出版の引用ルールとは?著作権とKDP審査を徹底解説』で引用の条件とKDP審査の基準を確認しておくと安心です。
特に引用や画像使用などは、出典明記や使用許可を取る必要があるケースがあります。
公式ヘルプにも記載されていますが、第三者の著作物・商標の無断使用はポリシー違反となり、公開拒否や取り下げの対象になり得ます(引用等の適法要件は公式ヘルプ要確認)。
さらに、出版物の内容が特定の人物・企業・宗教・政治を批判・誹謗するものにならないよう注意しましょう。
これらは「ガイドライン違反」だけでなく、名誉毀損など法的なリスクにもつながります。
実務的には、チェックリストとして以下を意識すると安心です。
* 勤務先の就業規則の確認
* 内容が競合・守秘義務に抵触しないか
* 引用・画像の出典確認
* 内容の客観性と倫理面の確認
この4点を押さえるだけで、出版後のトラブルを大幅に防げます。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の利用規約の基本
KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)は、Amazonが提供する無料の電子書籍出版サービスです。
誰でもアカウント登録をすれば利用できますが、実際に出版する前に利用規約とコンテンツガイドラインを必ず確認してください。
規約では、著作権・内容・価格設定・印税率・配信地域などのルールが定められています。
たとえば、70%印税を受け取るには「価格範囲」「配信地域」「配信設定」の条件を満たす必要があります。
また、成人向け・暴力的・過度な表現を含む作品は公開制限や削除の対象になることがあります。
公式ガイドライン上では「教育的・芸術的・文学的な目的での表現」は許可される場合もありますが、実際の審査では判断が厳しい傾向です。
そのため、曖昧な表現や境界線上のテーマは控えるのが無難です。
規約は定期的に更新されるため、出版前に最新版を読む習慣をつけましょう。
公式ヘルプページ(https://kdp.amazon.co.jp/help/)からいつでも確認できます。(https://kdp.amazon.co.jp/help/)からいつでも確認できます。)
出版後の価格設定や印税率の考え方については、『Kindle出版99円設定とは?印税率と価格戦略を徹底解説』で具体例を交えて解説しています。
もし米国でも売上が出た場合の税務補足(簡潔に)
KDPで出版した電子書籍は、Amazon.com(米国サイト)を通じて海外の読者にも販売される可能性があります。
この場合、米国での売上に対して源泉徴収税が発生することがあります。
ただし、日本在住の個人が日本の税務居住者である場合、日米租税条約によって源泉徴収率を0%に軽減できます。
申請には、KDPアカウント内の「税務情報インタビュー(Tax Interview)」で、マイナンバーを含む個人情報を入力する必要があります。
この手続きを行っておけば、米国側での税金が二重に課されることを防げます。
もし設定に不安がある場合は、税理士や公式ヘルプの案内を確認してください。
なお、為替レートや支払いタイミングによって日本円換算額が前後するため、申告時は振込明細を保存しておくことをおすすめします。
継続的な出版活動を安全かつ効果的に進めたい方は、『Kindle出版で100冊を目指す前に知るべき規約と品質戦略とは?徹底解説』も参考になります。
まとめ:Kindle出版は「会社規程を理解して正しく行動」すれば可能
Kindle出版は、誰でも挑戦できる一方で、会社員の場合は副業規定や税務処理など確認すべき点も多いです。
「法律で禁止されていないから大丈夫」と安易に始めると、後から修正が難しくなるケースもあります。
重要なのは、始める前に「リスクを知り、手順を整える」という意識を持つことです。
就業規則を尊重し、創作を継続することが最善のリスク回避策
最も確実なリスク回避策は、勤務先の就業規則を尊重しながら、自分のペースで創作を続けることです。
KDPは、自分の言葉や経験を形にできる素晴らしい仕組みです。
焦らず、自分の生活リズムを守りながら、着実に出版を積み重ねていくことが長期的な成功につながります。
副業禁止の会社員でも、誠実に対応し、ルールの範囲で行動すれば問題なく出版活動を続けられます。
出版を「リスク」ではなく、「自己表現の一部」として大切にしていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。