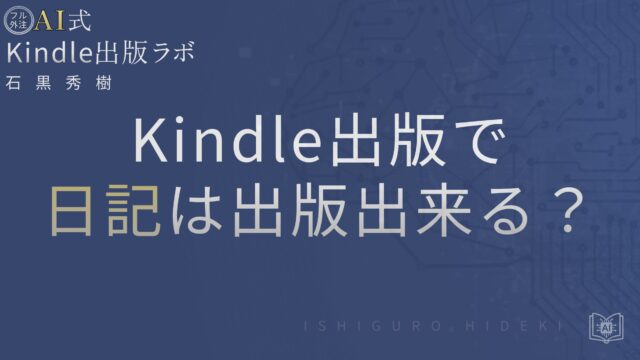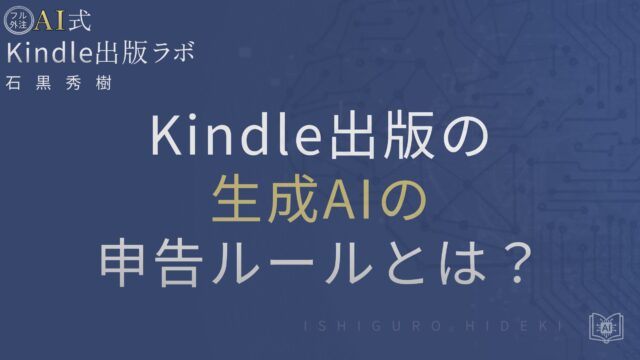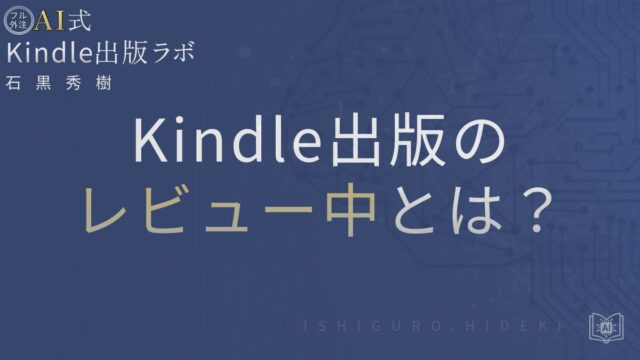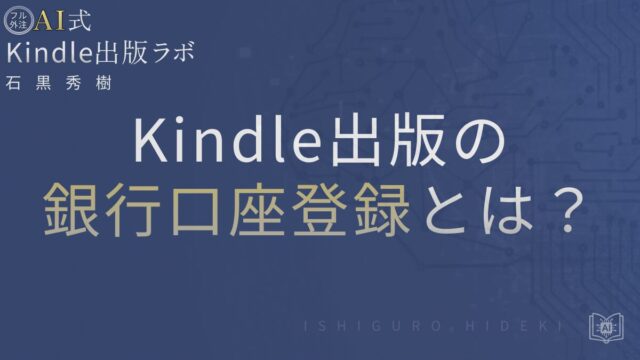Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインと審査落ち防止の徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるときに多くの人が気にするのが、「どんな内容が禁止されているのか」という点です。
ガイドラインを知らずに出版してしまうと、審査で差し戻されたり、最悪の場合アカウント停止になることもあります。
この記事では、KDP(Kindle Direct Publishing)の禁止事項を日本向けの最新ルールに基づいてわかりやすく解説します。
これから出版する人はもちろん、すでに電子書籍を出している方も、見落としがないか確認するつもりで読んでみてください。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインの全体像
目次
- 1 Kindle出版の禁止事項とは?KDPガイドラインの全体像
- 1.1 禁止事項の定義と範囲(コンテンツ・メタデータ・販売行為)
- 1.2 日本向けKDPで重視されるポイント(Amazon.co.jp前提)
- 1.3 最新ルールは公式ヘルプ要確認:更新の追い方
- 1.4 著作権侵害・転用・二次利用の禁止(引用ルールと出典)
- 1.5 AI生成物の扱いと透明性(不確実点は公式ヘルプ要確認)
- 1.6 刺激的表現・公共の秩序に反する内容の回避(抽象的説明)
- 1.7 医療・金融など専門情報の注意点(誤情報・免責の明記)
- 1.8 低品質コンテンツの基準(短すぎる・重複・自動生成の乱用)
- 1.9 タイトル・サブタイトルの偽装や過剰キーワードの禁止
- 1.10 著者名・シリーズ名の誤用とブランドなりすまし
- 1.11 カテゴリ・キーワードの不一致(関係ない語句の挿入)
- 1.12 説明文の誇大表現と検索スパムの境界線
- 1.13 見返り提供・評価交換・身内依頼のレビュー禁止
- 1.14 一斉購入の扇動などランキング操作のNG例
- 1.15 SNSやサロンでのレビュー募集のリスクと代替策
- 1.16 独占配信条件の違反(他サイト重複掲載・抜粋公開)
- 1.17 価格整合性とロイヤリティ条件の注意(35%/70%)
- 1.18 無料キャンペーン運用時の留意点(規約内の範囲)
- 1.19 最低ページ数・印刷品質・表紙要件の基本
- 1.20 ISBN・版の扱いと電子版との関連付け(日本向け)
- 1.21 表紙・タイトルでの不適切表現指摘への対応
- 1.22 引用・画像使用の権利確認漏れと再審査手順
- 1.23 重複・類似書籍判定(セルフコンペ)の回避策
- 2 公開前チェックリスト:審査落ちを防ぐ最終確認フロー
- 3 まとめ:Kindle出版の禁止事項を踏まえた安全運用
Kindle出版でいう「禁止事項」とは、Amazonが定めるKDPガイドラインに違反する行為や内容のことを指します。
対象は、原稿の中身だけでなく、タイトル・著者名・説明文・販売方法など多岐にわたります。
つまり、文章や表現だけでなく、登録情報の扱い方にもルールがあるということです。
禁止事項の定義と範囲(コンテンツ・メタデータ・販売行為)
KDPで定める禁止事項は大きく3つの領域に分かれます。
1つ目はコンテンツ(本文や画像などの内容)に関するもの。
2つ目はメタデータ(タイトル・説明文・キーワードなど)の不正利用。
3つ目は販売行為(レビュー操作・不正な価格設定など)です。
たとえば、他人の著作物を無断で転載したり、過剰なキーワードをタイトルに詰め込んだりするのはNGです。
また、「レビューを書けば特典がもらえる」といった行為もAmazonの規約違反にあたります。
実際には、公式ルールで明確に禁止されていないケースでも、運用上で問題視される場合があります。
そのため、「グレーゾーンだから大丈夫」と考えるのは危険です。
日本向けKDPで重視されるポイント(Amazon.co.jp前提)
KDPは世界共通のシステムですが、日本向け(Amazon.co.jp)の審査では特に慎重に扱われる分野があります。
たとえば、医療・健康・金融などの専門分野は、誤情報を避けるために内容の正確性や根拠が求められます。
また、Amazon.co.jpでは日本語表現の品質も重視され、誤字脱字が多い、内容が薄いなどの理由で「品質不十分」と判断されるケースもあります。
海外情報を翻訳して転載するだけの書籍も注意が必要です。
販売目的での量産や、AI生成物の明記なし出版なども、近年では指摘対象になりやすくなっています。
最新ルールは公式ヘルプ要確認:更新の追い方
KDPのガイドラインは不定期に更新されます。
特にAI生成コンテンツやレビュー関連のルールは、2023年以降に何度か改訂が行われています。
出版者として重要なのは、「公式ページで定期的に確認する」習慣をつけることです。
公式の「KDPコンテンツガイドライン」や「ヘルプセンター」をブックマークし、年に数回はチェックしておくと安心です。
また、SNSや一部のブログで出回る「非公式情報」には注意が必要です。
実務では、「公式ではこうだが、実際はこう運用されている」という違いがあることもありますが、最終判断はあくまでAmazonの審査基準に従うのが安全です。
以上が、Kindle出版における禁止事項の基本的な考え方です。
次の章では、具体的なコンテンツ関連の禁止例について、もう少し踏み込んで見ていきましょう。
Kindle出版では、最も多いトラブルが「コンテンツの内容そのものが規約違反だった」というケースです。
本文の質や表現の仕方、引用の扱い方などが基準を満たしていないと、出版後に販売停止や審査差し戻しになることもあります。
ここでは、著作権からAI生成物の扱いまで、特に注意すべき禁止事項を具体的に解説します。
著作権侵害・転用・二次利用の禁止(引用ルールと出典)
引用や出典の扱いをより具体的に知りたい場合は、『Kindle出版の引用ルールとは?著作権とKDP審査を徹底解説』を確認しておくと安全です。
他人が作成した文章や画像を無断で使用することは、著作権法に抵触します。
Kindle出版では、たとえ「引用」や「参考」と記載していても、出典が不明確だったり引用の範囲を超えていると認められないことがあります。
引用する場合は、以下の2点を必ず意識してください。
① 引用部分が主張の補助として必要最小限であること。
② 出典を明記し、全体のバランスで自作部分が中心であること。
特にネット記事や画像素材を安易に使うのは避けましょう。
「フリー素材」と書かれていても、商用利用や改変が禁止されているケースもあります。
また、Amazonは「著作権違反の疑いがある書籍」に対して公開停止やアカウント警告を行う場合があります。
念のため、公開前に自分の原稿が第三者の権利を侵していないかをチェックしましょう。
AI生成物の扱いと透明性(不確実点は公式ヘルプ要確認)
2023年以降、AI生成コンテンツの扱いについてKDPの規約が更新されました。
AIツールで生成した文章や画像を使用する場合は、「AI生成である」旨を申告する義務が設けられています。
現時点では、AI生成=禁止ではありませんが、人間による監修・編集を伴わない完全自動生成は審査で弾かれることがあるため注意が必要です。
生成物をそのまま掲載するのではなく、内容を確認し、自分の見解や修正を加えることが求められます。
また、公式ヘルプでも「AI生成物の扱いに関する詳細は随時更新中」とされており、現時点での運用は流動的です。
出版直前に必ずKDP公式ページを確認し、最新情報を反映させましょう。
刺激的表現・公共の秩序に反する内容の回避(抽象的説明)
KDPでは、公序良俗に反する表現、過度に刺激的な内容、暴力的・差別的な描写などを含む書籍は出版できません。
具体的な基準は明示されていませんが、「公共の秩序を乱す」「特定の人物や団体を攻撃する」「過度な描写」と判断されるものは削除対象になります。
ここで大切なのは、「自分では問題ないと思っても、第三者が不快に感じる可能性があるか」を意識することです。
Amazonの審査はグローバル基準に沿っているため、日本では問題ないと思える内容でも却下されることがあります。
一方で、社会問題や心理的テーマを扱うなど、意図が教育的・啓発的な場合は、文脈によって認められるケースもあります。
判断が難しい場合は、表現を抽象化し、直接的な表現を避けましょう。
医療・金融など専門情報の注意点(誤情報・免責の明記)
健康・医療・お金に関する内容は特に慎重さが求められます。
「治療法」「投資の成功例」「節税ノウハウ」などを断定的に書くと、誤情報とみなされるリスクがあります。
専門分野の知識を扱う場合は、根拠となるデータや出典を明示し、読者が自己判断できるようにすることが重要です。
また、免責事項(本書は医療行為・投資助言を目的としない)を明記しておくことをおすすめします。
公式では禁止されていないテーマでも、誤解を与える内容や誇張された表現は差し戻し対象になることがあります。
執筆時には「専門家でない人が読んでも誤解しないか」を基準に確認すると良いでしょう。
低品質コンテンツの基準(短すぎる・重複・自動生成の乱用)
文字数が少ない原稿の出版を検討している方は、『Kindle出版に最低文字数はある?品質と目安を徹底解説』もあわせてチェックしておくと判断の参考になります。
KDPでは、品質の低いコンテンツも禁止対象とされています。
これは「ページ数が少ない」だけではなく、「内容が薄い」「既存作品の焼き直し」「構成が乱れている」といったケースも含まれます。
特にAIによる自動生成やテンプレートを繰り返しただけの書籍は、読者満足度が低く、Amazonのアルゴリズムで表示制限がかかることもあります。
出版前に自分で読み返し、「この本は誰の役に立つか?」を客観的に考えることが大切です。
また、複数のタイトルで似たような内容を繰り返す「量産型出版」も注意が必要です。
一見審査を通っても、のちに統合・削除されるケースがあります。
KDPは、「読者に価値を提供する本」を最も重視しています。
ルールを守るだけでなく、内容の質を高める姿勢こそが、長期的な出版活動の信頼につながります。
Kindle出版では、本文の内容だけでなく「タイトル」や「キーワード」などの設定情報も厳しくチェックされます。
これらの情報は「メタデータ」と呼ばれ、Amazonの検索やランキングに直接影響する重要な要素です。
意図せず違反してしまうケースも多いため、SEO目的であってもやりすぎには注意が必要です。
以下では、タイトルやカテゴリ設定で特に誤解されやすい禁止事項を整理して解説します。
タイトル・サブタイトルの偽装や過剰キーワードの禁止
KDPでは、タイトルやサブタイトルに本来関係のないキーワードを詰め込む行為は禁止されています。
たとえば、「Kindle出版で月収100万円!最短で稼ぐ完全攻略ガイド【副業・在宅ワーク・AI活用】」のように、関係の薄いワードを羅列するのはNGです。
Amazonのシステムは、タイトル=読者への案内情報として扱います。
そのため、検索対策のつもりでも過剰なキーワードは「スパム」とみなされ、販売停止につながることがあります。
また、タイトル内で「公式」「認定」「公認」など、根拠のない表現を使うのも避けましょう。
Amazonでは事実に基づかない肩書きや誤解を招く表現を禁止しています。
タイトルは「本の中身を正確に表す」ことを第一に、SEO対策は説明文やキーワード設定で行うのが安全です。
著者名・シリーズ名の誤用とブランドなりすまし
著者名やシリーズ名の設定にも注意が必要です。
実際に執筆していない人物名を使う、または有名人・企業名を意図的に模倣する行為は、ブランドなりすましとして厳しく取り締まられます。
たとえば、「AI出版編集部」や「Amazon公式チーム」など、読者が誤解するような名称を使用するのはアウトです。
また、著者名に過剰なキーワードを入れる(例:「副業ライターKindle出版専門家」)のも規約違反とされる場合があります。
シリーズ名を設定する場合も、他の著者のシリーズと似たタイトルを付けると混同を招くため避けましょう。
Amazonではブランドや識別名の一貫性を重視しており、長期的に出版を続ける場合ほど、この部分の整合性が信頼につながります。
カテゴリ・キーワードの不一致(関係ない語句の挿入)
書籍のカテゴリやキーワード設定も、意図せず違反になりやすい部分です。
たとえば、恋愛小説を出版するのに「ビジネス」カテゴリを選んだり、内容に関係のない人気ワード(例:「ダイエット」「投資」など)をキーワードに入れたりするのはNGです。
Amazonのアルゴリズムは、メタデータと本文の内容の整合性を分析しています。
不一致が多いと、検索結果から除外されたり、ランキング対象外になるリスクがあります。
実務的には、「読者が実際に探すであろう言葉」+「内容に即した語句」の組み合わせが最適です。
SEO目的だけでなく、読者にとって誠実な設定を意識しましょう。
また、出版後にカテゴリを変更したい場合は、Amazonサポートを通じて依頼できます。
不正に複数カテゴリへ登録する裏技的な方法は、現在すべて検出・修正対象になっています。
説明文の誇大表現と検索スパムの境界線
説明文(商品紹介文)はSEO効果が高いため、力を入れる人も多い部分です。
しかし、ここでも「誇大表現」や「キーワード乱用」は規約違反にあたります。
たとえば、「誰でも1日でベストセラー!」「絶対に稼げるKindle出版法」といった断定的な表現は避けましょう。
根拠のない誇張や成功保証は、読者を誤解させるとして削除されることがあります。
また、説明文内でキーワードを繰り返しすぎると、Amazonの検索システムにスパムとして認識されます。
自然な日本語の流れを保ちつつ、主要キーワードを2〜3回程度に抑えるのが理想です。
「検索に強く、かつ誠実な文章」こそが、結果的に最も読まれる説明文になります。
過剰な装飾よりも、読者の信頼を得る構成を意識することが、長期的な成果につながります。
Kindle出版において、レビューやランキングは売上に直結する重要な要素です。
しかし、レビューの促し方や販売促進の方法を誤ると、KDPの規約違反になる可能性があります。
特に、Amazonでは「公正なレビュー環境」を守るために、レビュー依頼やランキング操作に関する取り締まりを年々強化しています。
ここでは、ありがちなNG行為と、安全に評価を集めるための代替策を詳しく解説します。
見返り提供・評価交換・身内依頼のレビュー禁止
最も多い違反が、「レビューを書いたら〇〇プレゼント」といった見返り型の依頼です。
Amazonはこれを「報酬付きレビュー」とみなし、厳格に禁止しています。
たとえ少額のギフト券やお礼のメッセージでも、見返りを前提としたレビュー依頼はすべてNGです。
また、家族や友人など身近な人に「星5つをつけて」とお願いする行為も、規約違反にあたります。
KDPの審査部門では、レビュー投稿者と著者の関係性を自動で検出する仕組みがあります。
不自然なレビューの偏りや、特定地域からの集中投稿が見られると削除・警告対象になることもあります。
レビューを増やしたい場合は、読者が自然に感想を残したくなるような誠実な作品作りと販売ページ設計を意識しましょう。
一斉購入の扇動などランキング操作のNG例
Kindleランキングの順位を上げるために、SNSやサロンで「発売日に一斉購入しよう」と呼びかける行為も、Amazonの規約で禁止されています。
これは「ランキング操作」に該当します。
特に、特典付きで「購入報告をした人に限定プレゼントを配布する」といった企画は、販売実績を人為的に操作した行為と判断される場合があります。
実際、短期間で大量の売上が発生した場合、Amazonのシステムが異常検知を行い、ランキングを一時停止することもあります。
こうした操作は一見効果的に見えますが、アカウントの信頼性を大きく損なうリスクがあります。
安全な方法としては、「キャンペーン期間中に無料配布(0円販売)」を設定する、または「読者に役立つ情報をシェアして自然に拡散される」形にするのが望ましいです。
SNSやサロンでのレビュー募集のリスクと代替策
SNSやオンラインサロンで「レビューしてくれる方募集」と呼びかけるケースも増えていますが、これも注意が必要です。
レビュー目的の募集や「相互レビュー」は、Amazonのポリシーで明確に禁止されています。
とくにX(旧Twitter)やLINEグループなど、非公式な場でレビュー交換を持ちかけると、投稿削除やアカウント停止に至ることもあります。
代わりにおすすめなのは、読者アンケートや感想フォームを用意し、作品改善につなげる方法です。
感想の中で自然に「Amazonのレビューもぜひ」と促す程度なら問題ありません。
また、書籍内に「レビュー投稿はこちら」とURLを載せること自体は認められていますが、「評価を依頼する文言」は避け、読者の自由意思を尊重する形で記載しましょう。
実際、誠実なレビューほど読者の信頼を得やすく、結果的にロングセラーにつながります。
短期的な数よりも、長く支持される本づくりを意識することが何より重要です。
KDPセレクトに登録すると、Kindle UnlimitedやKindleオーナーライブラリーでの配信、無料キャンペーンなどの特典が得られます。
一方で、特典を受ける代わりに守らなければならない「独占配信の条件」や「価格設定のルール」も存在します。
ここでは、初心者がつまずきやすいKDPセレクト関連の禁止事項と実務上の注意点を整理して解説します。
独占配信条件の違反(他サイト重複掲載・抜粋公開)
KDPセレクトに登録した作品は、Amazon以外の電子書籍ストアでは販売できません。
この「独占配信」は、KDPセレクトの最も重要なルールです。
たとえば、同じ作品をnoteやBOOTHなどで販売したり、同一内容をPDF配布するのは規約違反になります。
部分的に内容を掲載する場合でも注意が必要で、「抜粋公開」がどこまで許されるかは公式ヘルプ要確認です。
「KDPセレクト登録中は、抜粋公開に上限が設けられています(目安は全体の一定割合。具体値は公式ヘルプ要確認)。」実際、KDP側で「重複コンテンツ」と判定されると、販売停止やロイヤリティ停止の対象になるケースもあります。
独占条件は登録期間(90日間)のみ適用されるため、その期間を過ぎれば他サイトで販売することが可能です。
ただし、自動更新設定のままだと継続して独占配信が続くため、終了したい場合は手動で解除する必要があります。
価格整合性とロイヤリティ条件の注意(35%/70%)
KDPではロイヤリティ率が「35%」と「70%」の2種類に分かれています。
70%を選択する場合は、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、販売価格はAmazon.co.jpで250円〜1,250円の範囲内であること。
さらに、「他サイトでの低価格販売があると、Amazonが価格を自動調整したり、条件によりロイヤリティが変更される場合があります(公式ヘルプ要確認)。」
たとえば、自分のブログや別プラットフォームで同じ内容を低価格で販売していると、KDPの自動システムが検出し、Amazon上の価格を自動で引き下げたり、ロイヤリティを35%に変更されることがあります。
また、ファイルサイズが大きい画像系作品は配信コスト(データ転送料)が差し引かれる点にも注意が必要です。
画像中心の書籍では、70%ロイヤリティでも実際の受取額が想定より低くなることがあります。
実務上は、テキスト中心なら70%を選び、画像が多い作品や短編書籍では35%を選ぶのが安全です。
無料キャンペーン運用時の留意点(規約内の範囲)
KDPセレクトの特典として「5日間まで無料キャンペーンを実施できる」機能があります。
ただし、この無料配布も規約内で正しく運用しなければなりません。
無料期間中はAmazon以外で配布を行わないことが大前提です。
また、SNSなどで「無料期間中にDLしてレビューを書いてください」と呼びかけるのも、レビュー操作とみなされる恐れがあります。
無料キャンペーンは、読者に知ってもらうきっかけとしては非常に有効です。
ただし、キャンペーン終了後の価格戻しを忘れると、ロイヤリティが正しく反映されないことがあるため、終了設定は必ず確認しましょう。
また、無料配布を繰り返しすぎるとアルゴリズム上の評価が下がることがあります。
販売実績と読者レビューのバランスを見ながら、計画的に活用するのが理想的です。
KDPセレクトは、うまく使えば露出を増やす強力な仕組みですが、規約を誤解すると販売停止リスクもあります。
公式ガイドラインを定期的に確認しつつ、誠実な出版を心がけることが、長期的な信頼と収益につながります。
KDPでは電子書籍のほかに、紙の本として販売できる「ペーパーバック出版」機能も提供されています。
電子版と同じ原稿を活かして販売できる点が魅力ですが、印刷物としての基準があるため、電子書籍とは異なる注意点を理解しておくことが大切です。
ここでは、日本向けKDPでのペーパーバックに関する基本的な禁止事項と実務上の注意点をまとめます。
最低ページ数・印刷品質・表紙要件の基本
ペーパーバックでは、まず「ページ数」と「印刷品質」に関する制限があります。
KDPの公式基準では、最低24ページ以上でなければ印刷ができません。
これは表紙を除いた本文のページ数であり、短すぎる作品は物理的に製本できないためです。
エッセイや詩集などの短編作品を印刷したい場合は、余白ページや挿絵を加えることで調整する方法もあります。
印刷品質については、画像の解像度(300dpi以上)が求められます。
画像が低解像度のまま入稿すると、印刷時にぼやけたり、販売が停止されることもあります。
とくにカラー印刷を選ぶ場合は、ファイル容量が大きくなりがちなため、アップロード時の最適化にも注意が必要です。
ペーパーバック表紙の推奨サイズやテンプレート設定は、『Kindle出版の表紙サイズとは?審査に通る作り方を徹底解説』で画像付きで確認できます。
表紙は「背幅」「塗り足し」「トンボ」を正確に設定する必要があります。
KDPのテンプレートを利用するとミスを防ぎやすいですが、実際にはPDFの寸法が1mmでもずれていると審査でリジェクトされるケースもあります。
そのため、「電子版の表紙をそのまま使う」ことは原則避けるようにしましょう。
ペーパーバック用は、背表紙を含めた専用デザインが必要です。
ISBN・版の扱いと電子版との関連付け(日本向け)
日本のKDPでは、ペーパーバックを出版する際にAmazon独自の「無料ISBN」を利用できます。
自分でISBNを取得する必要はありません。
ただし、「KDPの無料ISBNは正式なISBNです。ただし発行主体(インプリント)はKDP側となり、同じISBNを他社サービスで再利用できません。」
商業出版のように全国流通を目指す場合は、別途日本図書コード管理センターを通じてISBNを取得する必要があります。
電子書籍とペーパーバックを同時に販売する場合は、KDPの設定で「関連付け」を行うことで、同一作品として表示されます。
これにより、読者が電子版と紙版を選択できるようになり、販売ページが統一されます。
ただし、タイトルや著者名、コンテンツ内容が完全に一致していないと関連付けが承認されません。
「電子版では第1版、紙版では改訂版」といった違いがある場合は、別作品として扱われることになります。
また、紙版の販売価格はAmazon側が自動的に印刷コストを加味して計算するため、電子版と同額に設定することは難しいです。
実務的には、電子版よりも数百円高く設定するケースが多いです。
最後に注意したいのは、ペーパーバック出版を行う際に、内容の一部を別媒体(ブログや同人誌など)で公開している場合です。
電子書籍と同様、著作権の整合性が取れていないと審査で保留となることがあります。
出版前に必ず、公式ガイドラインの「ペーパーバック作成の要件」ページを確認し、最新情報をチェックするようにしましょう。
ペーパーバック出版は、作品の完成度を一段と高め、手に取ってもらえる形にする魅力的な方法です。
ただし、印刷ならではの制約を理解し、正しい手順で進めることが、トラブルを防ぐ最も確実な方法です。
KDPの審査では、出版後に「差し戻し」や「修正依頼」が届くことがあります。
初めて出版する人ほど、この通知を受け取って驚くかもしれませんが、焦る必要はありません。
多くのケースは、規約違反というよりも「表現や設定の不備」によるものです。
ここでは、差し戻しや警告が起きやすい代表的な事例と、その対処法を実体験ベースで解説します。
表紙・タイトルでの不適切表現指摘への対応
最も多いのが「表紙またはタイトルに関する指摘」です。
KDPでは、誤解を招く表現や、過剰な宣伝文句を含むタイトルは認められていません。
たとえば「Amazonランキング1位!」や「無料特典付き」といった文言は、実際の証拠がない限り禁止されています。
また、「◯◯公式」など、ブランドや企業名を含むタイトルも誤解を生むため差し戻しの対象になります。
表紙画像についても同様で、裸や性的な印象を与える構図、暴力的な要素などは審査で止まりやすいポイントです。
たとえ芸術的な意図があっても、KDPは“全年齢向けの閲覧環境”を重視しているため、慎重な判断が求められます。
修正の際は、該当部分を削除・変更し、再アップロードすれば再審査が可能です。
私の経験では、修正後に24〜48時間で販売が再開されることが多く、丁寧に対応すれば問題ありません。
引用・画像使用の権利確認漏れと再審査手順
引用や画像素材の扱いも、差し戻し理由の上位に入ります。
KDPでは、第三者の著作物(写真・歌詞・文章など)を無断で使用することを禁止しています。
特に、フリー素材サイトの画像でも「商用利用不可」や「クレジット表記必須」とされているものを誤って使うケースがよくあります。 「商用利用OK・クレジット不要」の明記がある素材を選ぶことが基本です。
引用の場合も、出典明記と引用範囲のバランスが重要です。
自分の文章より引用部分が多い構成だと、「転載コンテンツ」とみなされる可能性があります。
もし権利に関する指摘で差し戻された場合は、該当部分を削除または差し替え、出典情報を明確にした上で再申請します。
修正版を提出すると、通常は数日以内に再審査が行われ、問題がなければ販売が再開されます。
重複・類似書籍判定(セルフコンペ)の回避策
意外と知られていないのが、「自分の作品同士が似すぎている」ことで発生する差し戻しです。
これはKDPのシステムが「類似コンテンツ」と判定した場合に起こります。
たとえば、タイトルや構成、本文の大部分が同一で、一部だけ改訂したような場合です。
公式には「読者に混乱を与える類似出版は禁止」とされています。
特に、表紙デザインやタイトルに「Vol.2」「改訂版」とだけ書き換えたものは、自動検出されやすい傾向があります。
別作品として出したい場合は、内容を3割以上変更する・構成を刷新する・目的を明確にするなど、明確な差別化が必要です。
私自身も過去に短編集を分冊化した際、タイトルが似ていたため警告を受けた経験があります。
最終的に、各巻ごとにテーマを明確化し、表紙と説明文を差し替えることで解決できました。
重複判定を避けるには、出版前に「既存作品と比較して新しい価値があるか?」をチェックリスト化するのがおすすめです。
KDPの審査は厳格ですが、明確な基準に基づいて行われています。
差し戻しは「失敗」ではなく、「より信頼される出版物に近づくためのプロセス」です。
落ち着いて原因を見直し、改善を重ねることで、確実にスムーズな出版につなげることができます。
公開前チェックリスト:審査落ちを防ぐ最終確認フロー
KDPの出版審査では、細かな不備が原因で「保留」や「差し戻し」になるケースが少なくありません。
公開直前のチェックを徹底することで、スムーズに販売を開始できます。
ここでは、審査落ちを防ぐための最終確認ポイントを3つの観点から整理します。
コンテンツ品質・表現チェック(抽象表現の徹底)
まず最も大切なのは、コンテンツそのものの品質と表現の適正です。
KDPは“読者が安心して読める環境”を重視しているため、刺激的・攻撃的・差別的と受け取られる表現は避けなければなりません。
とくに詩やエッセイなど感情的な作品では、意図せずセンシティブな語句が含まれることがあります。
その場合は、直接的な表現を避け、「抽象的・比喩的な言い回しに変える」のが有効です。
また、誤字脱字や段落崩れ、改ページのずれなども意外と見落とされがちです。
最終的には「自分が読者だったら読みやすいか」という視点で確認しましょう。
メタデータ整合性チェック(タイトル・著者・カテゴリ)
次に重要なのが、タイトルや著者名などの「メタデータの整合性」です。
これはKDP審査で非常に厳しく見られる項目です。
タイトルやサブタイトル、表紙の文字情報、KDPの入力欄の内容が完全に一致していないと、差し戻しになることがあります。
特に多いのが、サブタイトルを表紙に入れているのにKDP側では未記入のケースです。
また、著者名をペンネームで登録する場合は、同一作品内で統一することが必須です。
「電子書籍上では英字、本文では日本語名」などは混乱を招くため避けましょう。
カテゴリも重要です。
ターゲット読者とかけ離れたジャンルを設定すると、ランキングや露出にも影響します。
公式ガイドラインでは「正確なカテゴリ登録」が求められており、過剰にキーワードを盛り込むのはスパム扱いとなる場合があります。
配信設定・KDPセレクト条件・価格の整合確認
最後に、配信設定や価格周りのチェックを行いましょう。
特にKDPセレクトを利用する場合は、「独占配信条件」と「価格整合性」の2点を必ず確認してください。
他サイトや自分のブログなどで同じ内容を公開していると、規約違反とみなされます。
価格設定も、他プラットフォームより高すぎたり低すぎたりすると、自動で修正されることがあります。
「70%ロイヤリティは販売価格帯やその他条件を満たす必要があります(具体条件は公式ヘルプ要確認)。」
配信地域の選択、出版権の有無、販売開始時刻なども、公開前に必ず再チェックしておくと安心です。
審査落ちの多くは「うっかり見落とし」によるものです。
出版直前こそ冷静に、1つずつ項目を確認していきましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
まとめ:Kindle出版の禁止事項を踏まえた安全運用
KDP出版は、規約を理解し誠実に運用すれば、長期的に安定した活動を続けられる仕組みです。
禁止事項を意識することは、単に“違反を避ける”ためだけでなく、読者からの信頼を積み重ねるための基礎でもあります。
ここでは、運用面で意識しておきたい2つのポイントをまとめます。
「公式準拠+読者視点」で長期運用を目指す
KDP出版のルールは、クリエイターを制限するためのものではありません。
むしろ、読者が安心して購入できる環境を保つためのガイドラインです。
作品づくりでは、「公式準拠+読者視点」を意識することが大切です。
公式のルールを守りつつ、「読者にどう見えるか」「どんな価値を届けたいか」を考えることで、自然と品質の高い作品になります。
私の経験上、KDPで継続的に売れている作家ほど、この「信頼性」と「誠実さ」を重視しています。
迷ったら公式ヘルプ要確認:更新に追随する習慣
KDPの規約や審査基準は定期的に更新されます。
特にAI生成コンテンツやメタデータ関連のルールは、ここ1〜2年で大きく変わりました。
もし判断に迷う場合は、必ず公式ヘルプやガイドラインを確認しましょう。
公式情報は最も信頼できる根拠であり、KDPチームの方針を把握するうえでも欠かせません。
また、出版者フォーラムや海外のKDPコミュニティをチェックすると、実際の事例や最新傾向も把握しやすいです。
Kindle出版を安全かつ長期的に続けるコツは、「知ることを止めないこと」。
日々アップデートされる環境の中で、自分の出版活動を柔軟に整えていく姿勢が、最終的な信頼と成果につながります。
長期的な出版活動を見据えるなら、『Kindle出版で100冊を目指す前に知るべき規約と品質戦略とは?徹底解説』を読み、品質と継続運用のバランスを理解しておくと良いでしょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。