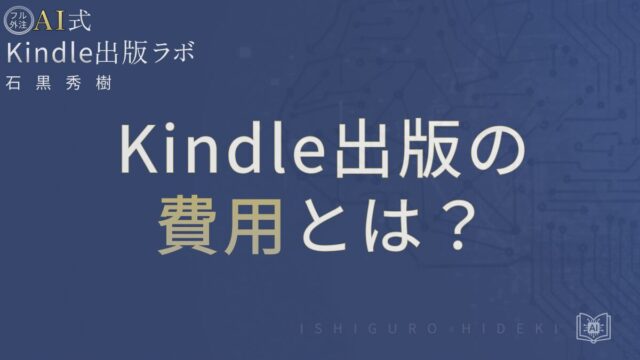Kindle出版の作り方とは?電子書籍を最短で公開する手順を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようと思っても、最初にぶつかる壁は「そもそもどう作ればいいの?」という点です。
ネット上には多くの情報がありますが、実際にやってみると「原稿の形式が違った」「表紙サイズが合わない」など、意外な落とし穴が多いものです。
この記事では、そうした初心者がつまずきやすいポイントを整理しながら、「Kindle出版+作り方」で検索する人が本当に知りたい内容を、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の公式情報と実務経験の両面から解説します。
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「Kindle出版+作り方」で検索する人が多いのか
▶ 初心者がまず押さえておきたい「基礎からのステップ」はこちらからチェックできます:
基本・始め方 の記事一覧
目次
Kindle出版の作り方を検索する人の多くは、「やりたい気持ちはあるけれど、最初の一歩が不安」という段階にいます。
電子書籍は無料で出版できますが、形式や設定を間違えると審査で止まったり、見栄えが崩れたりします。
全体の流れを短時間で把握したい場合は『 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐥𝐞出版の作り方とは?電子書籍を最短で公開する手順を徹底解説 』も参考になります。
そのため、多くの人が“正しい順番”と“全体の流れ”を早く知りたいのです。
検索者が「作り方」を知りたい本音とは何か
検索者が求めているのは、「Kindle本を出すには何から始めればいいのか」という明確な道筋です。
多くの方はすでに原稿の一部を書いていたり、Wordで本を作ってみた経験があります。
しかし、KDPにアップロードする際の形式(リフロー型・固定レイアウト)や、Wordの書式設定の違いが理解できておらず、「このまま出せるのか?」という不安を抱いて検索しています。
実際に私自身も初めて出版したとき、見出しスタイルを設定していなかったため、目次が自動生成されず苦労しました。
「やってみたけれどエラーが出た」「公式説明が抽象的でわかりにくい」──この“実務のズレ”を補いたい人が多いのが特徴です。
検索者の知識レベルと背景状況の見極め
検索ユーザーの多くは、KDPをまだ使ったことがない初心者です。
「アカウント登録」「ロイヤリティ設定」「プレビュー確認」など、用語そのものが初耳という人も少なくありません。
一方で、すでにブログやnoteで文章を書いている人が多く、基本的なライティングスキルはあります。
そのため、求められているのは「専門的な解説」ではなく、「すぐ試せる具体的な手順」です。
特に重要なのは、“公式ヘルプで読める内容”をそのまま繰り返すのではなく、実際の操作画面でどう動けばいいかを示すこと。
上位表示されている記事でも「ステップごとのスクリーンショット」や「テンプレート例」を添える傾向が強くなっています。
「電子書籍/ペーパーバック」どちらを想定しているかの傾向
検索キーワードが「Kindle出版+作り方」の場合、主な関心は電子書籍(Kindle本)にあります。
ペーパーバックを想定するケースは全体の2〜3割ほどで、「電子書籍を出した後に紙でも出したい」という流れが多い印象です。
日本版KDPでは、電子書籍が中心であり、ペーパーバックはオプション的な扱いです。
特に初心者の場合、まずは電子書籍を完成させ、その後にペーパーバックを検討するのが現実的です。
実務的にも、電子書籍の体裁を整えてから紙版を作る方が修正が少なく済みます。
もし米国など海外向けにも販売したい場合は、税務・価格設定が一部異なるため、公式ヘルプで該当項目を必ず確認しましょう。
電子書籍(Kindle本)を出版するために押さえるべき手順
Kindle出版は、流れさえつかめば決して難しい作業ではありません。
ただし、やみくもに作業を進めると、体裁崩れや審査エラーに直結します。
ここでは、実際に出版を完了させるための基本ステップを順番に整理します。
最初に知っておきたいのは、「原稿→表紙→KDP入力→プレビュー確認」という流れを守ることです。
この順序を意識するだけで、出版までの手戻りを大幅に減らせます。
原稿の作り方:Word・ePub・フォーマットで気を付ける点
原稿は、Microsoft Wordを使うのが最も一般的です。
KDPはWordファイル(.docx)を自動変換してKindle形式にしますが、書式や段落の作り方を誤ると崩れやすくなります。
特に注意すべきは、「空白を使ってレイアウトを整える」こと。
これをすると、端末ごとの表示でズレが発生します。
代わりに、段落設定や中央寄せを使って整えましょう。
Word原稿の具体的な整え方については『 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐥𝐞出版のWord設定とは?崩れない電子書籍の作り方を徹底解説 』で詳しくまとめています。
また、見出しはWordの「スタイル機能」を活用して設定するのがポイントです。
これにより、Kindle側で自動的に目次を生成してくれます。
私自身も、初期の出版時にこれを忘れて「目次がない」と警告を受けたことがあります。
スタイルの適切な設定=審査通過の第一歩だと考えておくといいでしょう。
画像を挿入する場合は、コピー&ペーストではなく「挿入→画像」から追加します。
貼り付け方式だと、内部データに余計なコードが入り、ファイルサイズが重くなることがあります。
ファイル形式としてはePubも利用可能ですが、初心者はWord形式で問題ありません。
最終的にはKDPのプレビューで確認し、崩れがないかをチェックしましょう。
表紙の作り方:サイズ・解像度・KDP入力用テンプレート
表紙作成時の具体的なサイズ基準は『 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐥𝐞出版の表紙サイズとは?初心者でも失敗しない最適設定を徹底解説 』が参考になります。
表紙は、電子書籍の「顔」となる最重要部分です。
電子書籍表紙の推奨は長辺2,560px・縦横比1.6:1が目安です。dpiは印刷向け指標で、電子表紙ではピクセル基準を優先します(公式ヘルプ要確認)。
CanvaやPowerPointでも作成可能ですが、電子表紙はCover Creatorや推奨寸法に従って作成します。テンプレートは主にペーパーバック(背表紙・裏表紙を含む)向けです。
公式テンプレートでは、タイトルや著者名の配置位置を示しており、審査時に弾かれにくい構造になっています。
また、画像の端に文字を寄せすぎると、端末によっては文字が切れる場合があります。
中央寄せ・余白確保・高解像度を意識すれば、基本的に問題ありません。
背景やフォントも派手すぎず、読みやすさを重視するのがおすすめです。
特に文字数が多いタイトルでは、背景を単色にしてコントラストを高めると視認性が上がります。
アカウント作成とKDPへの設定入力の流れ
次に、KDPアカウントを作成します。
Amazon.co.jpのアカウントがあれば、そのままKDPにログイン可能です。
新規登録時には、氏名・住所・銀行口座・税務情報を入力します。
日本の銀行口座を登録すれば円建て入金が可能です(一部支払方法・しきい値の条件あり。公式ヘルプ要確認)。
税務情報は、米国の源泉徴収条項に関するフォームが表示されますが、日本居住者であれば条約適用(源泉0%)が選択可能です。
出版設定の入力では、
1. 本の詳細(タイトル、著者名、説明文)
2. コンテンツ(原稿・表紙アップロード)
3. 価格とロイヤリティ設定
の3ステップで進みます。
どの項目も後から修正可能なので、最初は迷わず進めて大丈夫です。
ただし、「著者名」と「表紙上の名前」は一致していないとエラーになるので注意しましょう。
アップロード・プレビュー・公開の手順とポイント
ファイルのアップロードが終わったら、「Kindleプレビューツール」で実際の見え方を確認します。
このツールでは、スマホ・タブレット・Kindle端末など複数の画面をシミュレートできます。
ここで改行ずれや画像の欠けがないかをしっかり確認してください。
アップロード作業の細かな流れは『 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐥𝐞出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説 』で確認できます。
審査は通常24〜72時間で完了します。
ただし、成人向け要素や不明瞭な画像を含むと、審査が長引く傾向があります。
審査に落ちた場合は、KDPからメールで具体的な理由が通知されます。
内容を修正したら、再度「再公開」をクリックするだけで再審査に進めます。
プレビュー確認を省くと、修正の手間が何倍にもなるので、最初に徹底しておくのがコツです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle出版を成功させるための実践ポイントとよくあるつまずき
ここからは、出版を実際に進めたあとによく起きるトラブルや、経験者だからこそ分かる「成功のコツ」を紹介します。
失敗を防ぐ最大のポイントは、「急がない」こと。
どんなに小さなズレでも、審査リジェクトの原因になることがあるため、一つずつ丁寧にチェックしていきましょう。
体裁崩れ・改行・目次・画像配置で起きやすい失敗例
体裁崩れの原因で多いのは、「Wordで見えている通りに表示される」と思い込むことです。
Kindleではフォントや改行の扱いが異なり、意図せず空白が生じるケースがあります。
改行をスペースで調整するのは避け、段落設定で統一しましょう。
目次の自動生成がうまくいかない場合は、見出しスタイルが未設定の可能性が高いです。
また、画像をページ内で固定したい場合は、行内ではなく段落として配置するのが安全です。
私自身も以前、画像をコピペで貼った結果、KDP変換後に位置がずれた経験があります。
KDP上ではWordの「見た目」と一致しないことを前提に、Previewerで都度確認が鉄則です。
KDP公式ガイドラインでチェックすべき項目(日本版)
KDPの審査は、内容そのものよりも「技術的・品質面」で判断されることが多いです。
日本版ガイドラインでは、レイアウトの乱れ、誤字脱字、過剰な広告要素などが主なリジェクト対象に挙げられています。
特に、Amazonのカタログを誤解させるようなタイトル・著者名・説明文はNGです。
また、公式には「本文中のURLは機能しない場合がある」と記載されています。
実際の販売ページではリンクが無効になることもあるため、必要最低限にとどめましょう。
ガイドラインは頻繁に更新されるため、執筆時点での最新ヘルプを確認する習慣が大切です。
価格設定・ロイヤリティ・日本向け配信の最低限チェック(詳細は公式要確認)
価格設定では、「ロイヤリティ率」を理解しておくと後悔がありません。
KDPでは35%と70%の2種類があります。
70%を選ぶには、販売価格を250〜1,250円の範囲に設定する必要があります。
また、70%ロイヤリティでは配信手数料が発生します(1MBあたり数円)。
電子書籍のファイルサイズが大きいと、利益が減ることがあるので、画像は圧縮しておくのが安全です。
日本向け配信では、Amazon.co.jpを含む主要国を選べば問題ありませんが、海外向け販売を希望する場合は税務情報の設定が必要です。
価格は後から変更できるので、まずは標準価格でリリースし、販売データを見ながら調整するのがおすすめです。
KDP公式では「価格改定は数時間で反映」と記載されていますが、実際は24時間ほどかかるケースもあります。
公式の理想値と実務上のラグを把握することが、スムーズな運用のコツです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
実際に出版した後に知っておきたいこと
出版が完了した瞬間はホッとしますが、実はそこからが本当のスタートです。
KDPの管理画面では売上・評価・レビューなど、次に活かせる情報が数多く得られます。
また、公開後に誤字やデザイン修正をしたい場合の流れも知っておくと安心です。
ここでは、出版後の運用で必ず押さえておきたいポイントを3つ紹介します。
販売開始後のダッシュボード確認とレポート活用
KDPのダッシュボードは、いわば「売上管理の司令塔」です。
ここでは販売部数・ロイヤリティ見込額・レビュー数などを一括で確認できます。
初めて出版した方は、まず「レポート」タブで国別の売上傾向を定期的にチェックするのがおすすめです。
日本だけでなく米国や英国でも少数ながら購入されることがあるため、世界的な視点を持つと意外な発見があります。
また、「本の詳細」では販売ステータス(公開・一時停止・審査中)を確認できます。
Amazon上で反映に時間がかかる場合でも、KDPダッシュボードにはリアルタイムに近い情報が表示されます。
レビューは通知されないため、定期的にAmazon商品ページを確認して読者の声を拾いましょう。
ユーザーのコメントから改善点が見えることも多く、次の作品づくりに役立ちます。
修正・改訂・再出版の流れと注意点
誤字脱字やレイアウト崩れなど、公開後に修正したい箇所が見つかるのは自然なことです。
その場合は、KDPダッシュボードで該当作品を開き、「電子書籍の内容を編集」から原稿ファイルを再アップロードします。
再審査が行われますが、通常は24〜48時間で再公開されます。
電子書籍はISBN不要です。タイトルや著者名の大幅変更は再審査や商品ページ表示に影響する場合があります(公式ヘルプ要確認)。同一作品として扱いたい場合は内容のみを更新しましょう。
同じ本として扱いたい場合は、内容だけを更新しましょう。
また、Amazonの検索結果に反映されるまでにタイムラグが生じることがあるため、再公開後すぐには反映されないこともあります。
焦らず数時間〜1日ほど待って確認すると安心です。
改訂版を出す場合は、書籍説明欄に「第2版」「改訂版」などを明記すると読者に親切です。
同一タイトルのまま更新すると、購入者には自動的に最新版が配信される場合がありますが、確実ではありません。
この挙動はAmazonの仕様によって変わるため、配信が反映されない場合はKDPサポートに問い合わせるのが確実です。
(必要なら)ペーパーバック出版の補足:電子が主軸のため簡潔に
電子書籍を出した後、「紙の本としても販売したい」と思う方は多いです。
KDPでは同じ管理画面からペーパーバック出版も可能です。
ただし、紙版ではページ数が24ページ以上必要であり、表紙・背表紙・裏表紙を含めたデザインデータを用意する必要があります。
テンプレートはKDP公式サイトからダウンロードできます。
仕様を満たしていれば、印刷品質の確認後に自動で販売が開始されます。
ただし、色味や余白の見え方が電子版と異なるため、事前にプレビューを行いましょう。
初回は印刷見本(プルーフ版)を注文して確認するのも安心です。
電子書籍とペーパーバックは同時に扱えますが、初心者はまず電子版を完成させてから紙版に進むのが現実的です。
まとめ:Kindle出版+作り方を迷わず進めるために
Kindle出版の作り方は、一見すると複雑に見えますが、順序さえ守れば誰でも実現できます。
原稿・表紙・KDP入力の流れを理解し、プレビューで確認すれば、初心者でも十分に完成度の高い電子書籍を作れます。
出版後は、ダッシュボードで販売状況を分析し、読者の反応を見ながら改善していくことが大切です。
この「出して終わり」にしない姿勢が、長く読まれる著者になる第一歩です。
もし本記事で紹介した内容の中で迷う箇所があれば、KDP公式ヘルプページを必ず参照してください。
公式ルールと実務の違いを理解しながら、あなた自身のペースで出版を進めていきましょう。
最後に一言。
Kindle出版は“特別な人だけができること”ではありません。
小さな一冊でも、自分の経験や知識を形にする価値があります。
その第一歩を、今日から始めてみてください。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。