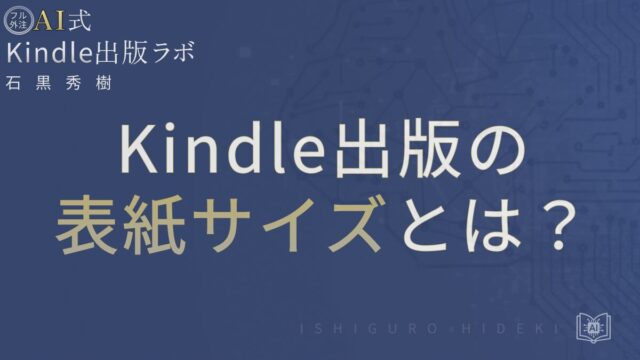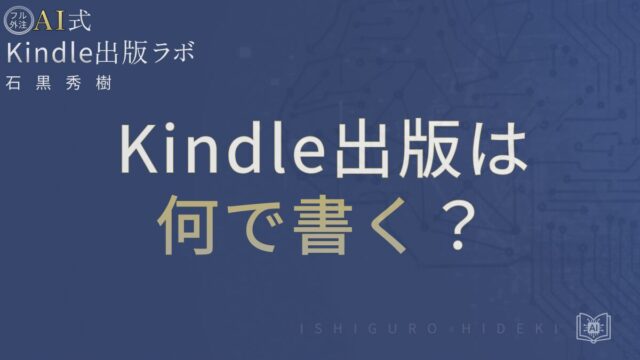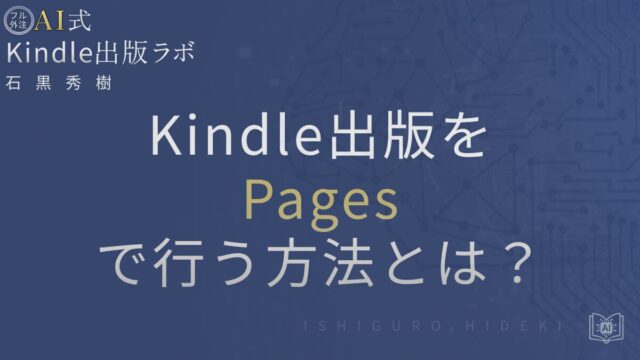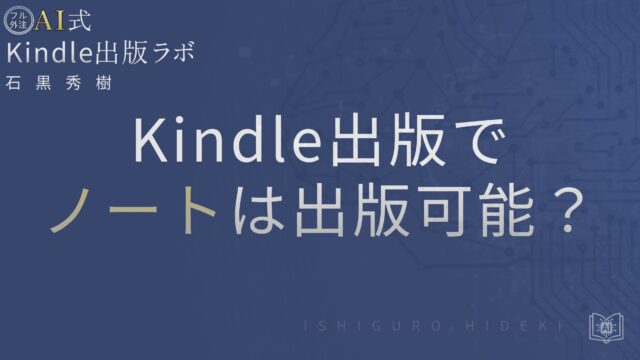Kindle出版のファイル形式とは?EPUB推奨の理由と選び方を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、「EPUB」「DOCX」「KPF」など複数のファイル形式が出てきて、どれを使えばいいのか迷ってしまう人が非常に多いです。
特に初めての入稿前は、形式選びを間違えると表示崩れや審査トラブルにつながるため、不安になるのは自然なことです。
本記事では、日本のAmazon.co.jp向けKDPを前提に、「いま最も安全な形式はどれか」「なぜEPUBが推奨されやすいのか」を軸に、実務目線でわかりやすく整理します。
公式ガイドラインに基づきつつ、経験者が実際に陥りやすい注意点も交えて解説しますので、読むだけで迷いがかなり解消されるはずです。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版のファイル形式で迷う人へ:まず知るべき基本と最新状況
目次
Kindle出版では複数の入稿形式が利用できますが、すべてが同じ条件で推奨されているわけではありません。
特に2023年以降は、MOBI形式の扱いが変わったことで、従来の解説サイトと最新情報にズレが発生している点に注意が必要です。
この章では、まず「どんな形式があるのか」「なぜMOBIが外されつつあるのか」「現時点で公式が推奨している形式はどれか」を理解することから始めます。
Kindle出版に使えるファイル形式一覧(EPUB/DOCX/KPFなど)
Kindle出版では、主に以下のファイル形式が使用できます。
EPUB(推奨形式)
DOCX(Word原稿でそのまま入稿可能)
KPF(Kindle Create専用形式)
PDFは主にペーパーバック本文の入稿で使用します。電子書籍(固定レイアウト含む)はEPUBまたはKPFが基本です(公式ヘルプ要確認)。
EPUBは「電子書籍の国際標準形式」であり、複数の端末でレイアウトが崩れにくい点が評価されています。
DOCXはWordで執筆する人が多いため初心者に馴染みがありますが、装丁次第で崩れやすく、変換精度も安定しないことがあります。
KPFはKindle Createという公式ツールを使用して出力される専用形式で、レイアウトをある程度視覚的に調整しやすい点が特徴です。
ペーパーバックではPDF入稿が基本となりますが、電子書籍部分とは仕様が大きく異なるため、本文では補足にとどめます。
初心者でも扱いやすく、かつ審査トラブルを避けやすいのはEPUBかKPFのいずれかであるケースが多いです。
MOBI形式はなぜ推奨されなくなったのか(受付終了の背景)
かつてはMOBI形式が「Kindle専用フォーマット」として多くの解説サイトで推奨されていました。
しかし、MOBIは現行のKDP入稿形式としては推奨外で、受付対象外の領域があります。最新の可否は公式ヘルプ要確認。
その背景には、「EPUBの普及」「端末の仕様統一」「ファイル変換の自動化」があり、MOBIを維持する必要性が薄れたことが挙げられます。
実際、Kindle Previewerなどの公式ツールも、EPUBを基準として検証が行われるようになっています。
そのため、過去の情報に従ってMOBIで用意しても、最新の審査環境と合わずに不具合が発生するリスクがあります。
日本のKDP(Amazon.co.jp)における公式推奨形式と根拠
日本向けKDPの公式ヘルプでは、電子書籍の入稿形式として「EPUB」が明確にサポート対象として記載されています。
また、Word(DOCX)ファイルやKindle Createで出力されたKPF形式も入稿できますが、いずれも最終的にKindle用の配信用フォーマットへ変換されます。内部仕様は非公開のため詳細は公式ヘルプ要確認。
この点からも、「変換前提の形式」より「最初からEPUBとして整えた方が完成度が高い」という考え方が推奨される理由になります。
さらに、EPUBは「Previewerでの確認」「修正」「再入稿」がしやすく、長期的に管理する点でもメリットがあります。
そのため、実務の現場では「EPUBを第一候補」「必要に応じてKPF」「Word原稿はあくまで素材」と捉える人が多いです。
Kindle出版に最適なファイル形式はEPUB:その理由とメリット
Kindle出版では複数の入稿形式が使えますが、最も安定して利用されているのがEPUB形式です。
公式が推奨しているというだけでなく、実際に出版してきた経験からも「最初からEPUBで整えると後工程がスムーズになる」ケースが多いと感じています。
この章では、EPUBが選ばれる理由と、入稿までの基本ステップ、さらにWord原稿から変換する際のポイントをわかりやすく解説します。
EPUBを公式が推奨する理由(互換性・表示崩れ防止)
EPUBは電子書籍の国際標準規格として広く採用されている形式です。
EPUBの基本仕様をより詳しく知りたい場合は『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版のEPUB形式とは?作り方と注意点を徹底解説』も参考になります。
Kindle端末やスマホアプリでも安定して表示されるため、読者の閲覧環境によるレイアウトの崩れが起きにくいという特徴があります。
また、KDPの公式ヘルプでも「電子書籍の入稿形式としてEPUBがサポートされている」と明記されており、サポート面でも安心感があります。
実際の制作現場でも、「最初はWordのまま入稿してみたが、段落のズレや目次の不具合が発生し、最終的にEPUBに作り直した」という声をよく聞きます。
最初からEPUBとして整えておけば、変換時の乱れが少なく、修正作業の負担も減らせます。
さらに、Kindle Previewerでの表示テストもEPUBを基準として行われるため、完成形を確認しやすい点も大きなメリットです。
EPUB入稿の基本的な流れと必要なツール例
EPUB形式で入稿する場合の全体的な流れは以下の通りです。
1.原稿をWordやGoogleドキュメントで作成
2.EPUB形式に変換できるツールで整形
3.Kindle Previewerで表示確認
4.KDPにEPUBファイルとして入稿
EPUBの作成には、「Sigil」「Googleドキュメント+拡張機能」「Vellum(Mac向け)」などのツールが使われます。
また、Kindle Createを使ってKPFに変換する方法もありますが、KPFも内部的にはEPUB構造に近いものであり、視覚的にレイアウトを整えやすい点で選ばれることがあります。
実務では「EPUBを直接作るか、Kindle CreateでKPF化して仕上げるか」がよく選ばれるパターンです。
Word(DOCX)原稿からEPUB化する際の注意点
Word(DOCX)原稿からEPUBを作る場合、構造を意識して文書を作っておくことが非常に重要です。
見出しを「太字で強調」するだけではなく、「スタイル(見出し1、見出し2)」を正しく設定しておくことで、EPUB変換時に目次が正しく生成されます。
また、改行と段落の区別を曖昧にしてしまうと、変換後に意図しない行間になりやすくなります。
画像を多用する原稿では、サイズや解像度が過剰だとEPUBファイルが重くなり、審査中にエラーが発生することもあるため注意が必要です。
実際、私も初期の頃にWordから変換した際、画像サイズが原因でアップロード時に警告を受けたことがありました。
このようなトラブルを避けるためにも、変換後はKindle Previewerで「スマホ画面」「タブレット画面」で必ず確認することをおすすめします。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
EPUB以外の選択肢:DOCX・KPF・固定レイアウト形式の使い分け
EPUBが最も推奨される形式であることは確かですが、実務では「DOCXでそのまま入稿できないか」「Kindle Createで作ったKPFの方が楽では?」と感じるケースも少なくありません。
さらに、漫画・写真集・図解など、EPUBでは対応しにくいジャンルも存在します。
この章では、EPUBを基本としつつも、他の選択肢を使うべき場面を丁寧に整理していきます。
Word(DOCX)でそのまま入稿する場合のメリットとリスク
Word(DOCX)でそのまま入稿できるのは、初心者にとって大きなメリットです。
特に「文章中心で構成がシンプルな本」なら、一度そのまま入稿してみたいと考える方も多いでしょう。
作業工程が少ないため、スピード重視で試しに出版してみる場合には有効な方法です。
ただし、DOCX入稿には注意点もあります。
Wordの “見た目の整え方” がEPUB変換時に必ずしも反映されるとは限らず、段落やインデントが崩れることがあります。
太字や箇条書きの表現は正しく反映されても、余白位置や行間などの細かい装飾は想定と異なることがあるため注意が必要です。
入稿前のチェック手順については『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説』で確認できます。
また、Word特有の「勝手な改行」「段落の混在」によって、読みづらい構成になる失敗もよく見られます。
そのため、DOCX入稿を選ぶ場合は、必ずKindle Previewerでの表示確認を前提に進めたほうが安心です。
Kindle CreateでKPFを作るべきケースと日本語の注意点
Kindle Createは、Amazonが公式に提供している制作ツールです。
文章をブロック単位で整理しながら装飾できるため、Wordよりもレイアウトが安定しやすいという利点があります。
KPFはレイアウトを比較的再現しやすい形式です。ただし端末差で表示が変わる場合もあるため、Previewerでの確認は必須です。
ただし、日本語特有の縦書きや禁則処理(一行の行頭に記号が出ないようにするなど)には制約がある場合があります。
実際、細かい行間調整が必要な書籍や、文章のリズムを大切にするエッセイ系では、KPFでは思ったような表現にならなかった経験があります。
「装飾をある程度固定しつつ、簡易的に仕上げたい場合」にKPFは有効であり、「完全に自由なレイアウトにしたい場合」には不向きです。
なお、KPFは内部的にEPUB構造に近いため、最終出力をチェックする際もKindle Previewerで確認する流れは同じです。
画像主体の固定レイアウト形式が適するジャンルとは
固定レイアウト形式は、ページ単位で表示内容を固定する方式です。
固定レイアウトを使うべきケースは『𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗲出版の固定レイアウトとは?リフローとの違いと判断基準を徹底解説』が補足になります
漫画や絵本、写真集、図鑑、スライド風の教材など、画像ベースでページ全体のデザインを重視するジャンルに向いています。
文章を自由に拡大・縮小するリフロー形式(EPUBやKPF)とは違い、レイアウトが崩れないため、視覚デザインを保つ必要がある場合に有効です。
ただし、固定レイアウトはスマホでは拡大操作が必要になる場合があります。読者体験は作品特性に依存するため、プレビューで適合性を確認してください。
また、KDPでは固定レイアウトの審査基準が厳しく、画像解像度やページ構成が要件を満たさないとリジェクトされるリスクもあります。
そのため、「視覚型コンテンツに限定される」という点を理解した上で選択する必要があります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
ファイル形式選びでよくある失敗と表示崩れを防ぐ方法
ファイル形式を正しく選べていても、入稿後の表示に問題が生じることがあります。
特に初心者に多いのが「Wordではきれいに見えていたのに、スマホで表示するとズレる」「画像が切れてしまう」といったケースです。
この章では、よくある失敗の原因と、それを事前に防ぐためのチェック方法をわかりやすく整理します。
スマホ・タブレットでレイアウト崩れが起こる原因
レイアウト崩れが起こる主な原因の一つは、「固定レイアウト前提の考え方で文章を作ってしまうこと」です。
Wordでページ単位を意識しすぎると、Kindleのリフロー(自動的に文字サイズや行送りが調整される形式)ではズレが発生しやすくなります。
また、改行と段落を混同してしまい、スマホで表示した際に意図しない空白ができることもよくあります。
もう一つの原因は、画像や文字装飾を過度に使いすぎることです。
特に、段組みやテキストボックスをWordで使ってしまうと、Kindle側で正しく解釈されない場合があります。
「紙のレイアウトをそのまま電子書籍に持ち込もうとする」と崩れやすい、という点を覚えておくと失敗を防ぎやすくなります。
Kindle Previewerで事前チェックする重要性
Kindle Previewerは、入稿前に書籍の実際の表示状態を確認できる公式ツールです。
PC・タブレット・スマホなど複数端末のプレビューが可能で、文字のズレ・画像の切れ・目次の動作確認などが行えます。
このツールを使わずに入稿してしまうと、公開後に読者からクレームを受けるリスクが高くなるため、必ずチェック段階を挟むことをおすすめします。
実務上は「Previewerで問題がなければ、公開後の表示も安定しやすい」と言われています。
逆に、Previewerで違和感があった時点で修正しなければ、KDPの審査段階で指摘されることもあります。
見た目を整える目的だけでなく、審査通過率を高めるためにもPreviewer確認は欠かせません。
認識されにくいフォント・画像サイズ・目次設定の注意点
Kindleでは一部フォントが正しく表示されない、もしくはデバイスによって代替フォントに置き換えられることがあります。
そのため、特殊フォントの埋め込みは避け、標準的なフォントを使用することが推奨されます。
また、画像は解像度が高すぎるとファイル容量が増えすぎ、逆に低すぎるとぼやけるため、KDPの公式推奨に沿ったサイズ設計が必要です。
目次に関しても、「見出しを太字で書いただけでは自動認識されない」という点に注意が必要です。
WordやEPUB制作時には「見出しスタイル(Headingタグ)」を適切に使うことで、Kindle側で目次として正しく登録されます。
このステップを飛ばしてしまうと、読者が目次ジャンプできず、読み進めづらくなる原因になります。
ペーパーバック出版を併用する場合のファイル形式(補足)
Kindle出版では電子書籍を中心に進める方が多いですが、「後から紙の本(ペーパーバック)も出したくなった」というケースはよくあります。
実際、私も電子版のみでスタートした後、読者から「紙で読みたい」という声を複数いただいたことで、ペーパーバック版を追加した経験があります。
この章では、電子書籍との違いやPDF形式が必要になる理由を、初めての方でもわかりやすく整理しておきます。
紙版はPDF形式で入稿する必要がある理由
ペーパーバックは「紙に印刷されること」が前提のため、EPUBのようなリフロー形式(文字サイズが自動調整される仕組み)は使えません。
そのため、ページ単位でレイアウトが確定されたPDF形式での入稿が求められます。
PDFはページごとのレイアウトが固定されるため、印刷工程に適した形式となります。
また、ペーパーバックでは「裁ち落とし」「余白」「ノド(綴じ側の空白)」など、印刷特有のルールに沿ったデータ作成が必要です。
これは電子書籍制作にはほぼ必要ない要素であり、ペーパーバック制作では独自に調整を行う必要があります。
EPUBやDOCXをそのまま紙版に流用できるわけではなく、PDF用にページ構成を再設計する必要がある点に注意してください。
電子書籍とペーパーバックで形式が異なる点の整理
電子書籍とペーパーバックでは、目的も仕様も大きく異なります。
以下のポイントで違いを整理しておきましょう。
・電子書籍:リフロー型が主流(EPUB/KPF)
・ペーパーバック:固定型PDFでページ単位のレイアウトが必要
・電子書籍:文字サイズ変更が可能
・ペーパーバック:すべての読者に同一レイアウトで印刷
・電子書籍:画像は端末サイズに合わせて自動調整される場合あり
・ペーパーバック:画像解像度が低いと印刷時に粗くなる
電子版と紙版を同時に制作する場合、文章構成は共通にしても、レイアウト設計はそれぞれに適した形で調整するのが一般的です。
実務では「まず電子版をEPUBで完成 → 読者の反応次第で紙版をPDFで再構成」という流れが取りやすく、負担も抑えられます。
無理に同じ形式で一括制作しようとせず、用途に応じて形式を切り替えることで、品質と作業効率の両方を保つことができます。
Kindle出版のファイル形式に迷わないための判断フローチャート
ここまで形式ごとの特徴を見てきましたが、「結局どれを選べばいいのか」が最初の疑問だと思います。
実務では、文章主体か画像主体か、レイアウトの自由度をどこまで求めるかによって自然と選択肢が決まってきます。
この章では、判断をスムーズにするための考え方をシンプルに整理します。
文章主体ならEPUBが最優先になる流れ
文章メインの書籍(エッセイ・解説書・ハウツー本・実用書など)であれば、基本的にEPUBを第一候補にしてください。
理由は単純で、本文の見やすさ・端末での可変表示・公式サポートの安定性を考えると、EPUBが最もバランスに優れているからです。
Word原稿をそのまま入稿することも可能ですが、仕上がりにバラつきが出やすく、最終的にEPUBベースで整えることになるケースが多いです。
私自身も文章中心の本では「EPUBで整えてからPreviewerで確認→細部を修正」という流れを徹底することで、審査通過率と読者満足度の両方が安定するようになりました。
「文章中心=EPUB」「Wordは途中工程」という意識を持って進めると、迷う時間が大幅に減ります。
KPFや固定レイアウトを選ぶべき例外ケース
とはいえ、すべての本がEPUBで最適とは限りません。以下のような場合は別形式を検討する価値があります。
【KPFが向いている例】
・ある程度ページ装飾を固定したい
・箇条書き・囲み枠などを視覚的に整えたい
・Kindle Createのテンプレートで十分仕上げられる内容
【固定レイアウト形式が向いている例】
・画像や図表がページの大部分を占める
・写真集・イラスト集・絵本・教材スライド
・視覚デザインを完全固定したい場合
KPFは「EPUBより装飾しやすいが自由度は限定的」、固定レイアウトは「自由度が高いが作業負担も大きく審査も厳しめ」という立ち位置です。
実務的には、「EPUBで十分か」「KPFで固めた方がきれいか」「画像主体か」の3ステップで考えると判断しやすくなります。
“内容の性質”と“読者の読み方”をイメージすることで、形式選びは自然と絞り込まれます。
まとめ:Kindle出版はEPUBを基本にしつつ、用途に応じて形式を使い分けよう
Kindle出版のファイル形式は選択肢が多く見えるため、最初は迷ってしまいがちです。
しかし、文章中心であればEPUBが最も安定しており、多くのKindle本はこの形式で制作されています。
Word(DOCX)はあくまで原稿段階の形式として考え、最終的な入稿形式としては慎重に扱う方が安全です。
一方、デザインや装飾性を重視する場合はKPF、画像主体のビジュアルコンテンツでは固定レイアウト形式を選ぶことが有効になります。
必要に応じてPreviewerで検証しながら形式を見直すことで、読者の読みやすさと審査の通過率を両立できます。
電子版の完成度が高ければ、ペーパーバックなど他形式展開もスムーズに進められます。
本記事を参考に、自分の書籍に最適な形式を見極めながら、あなたらしい出版プロセスを確立していただければと思います。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。