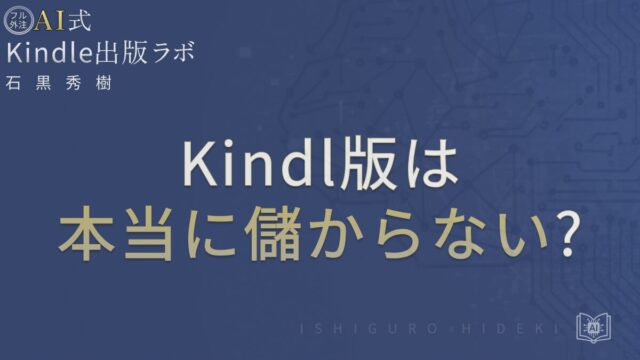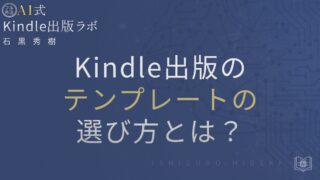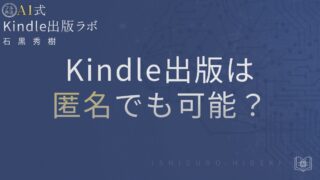Kindle出版の手数料とは?ロイヤリティと配信コストを徹底解説
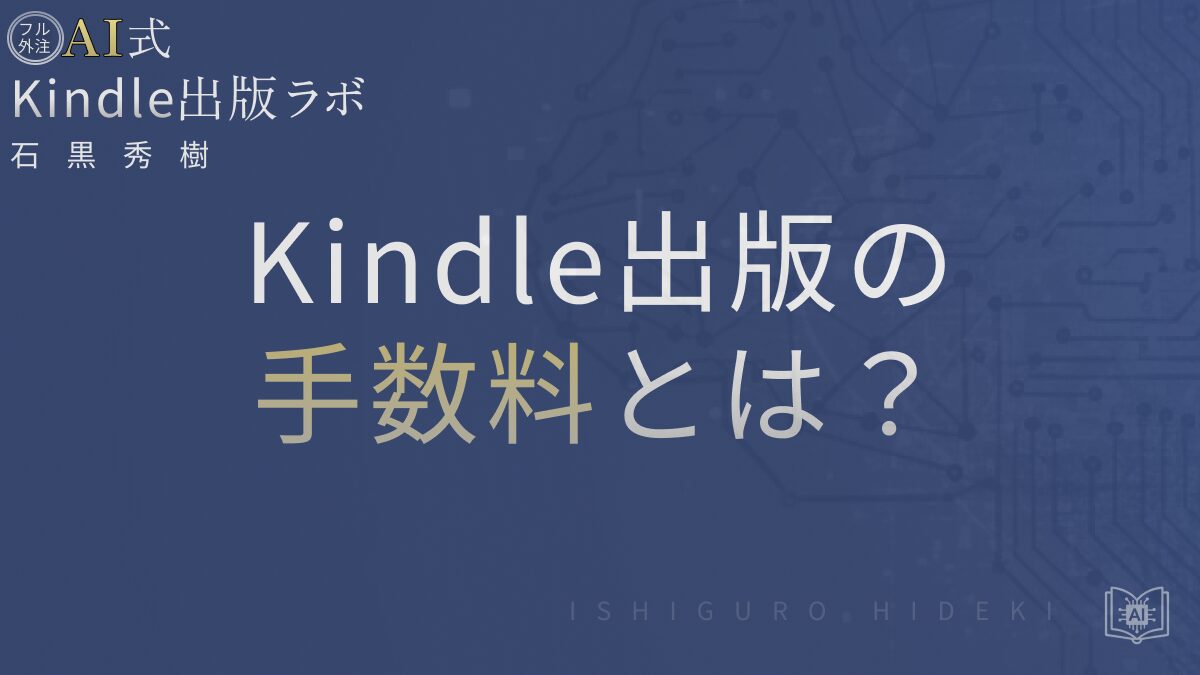
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようとしたとき、多くの人が最初につまずくのが「手数料って結局いくら取られるの?」という疑問です。
電子書籍を販売して得た収益から、どんな項目が差し引かれ、どのように印税が計算されるのか――これは収益を安定させる上でとても重要なポイントです。
この記事では、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)における手数料の仕組みを、初心者でも迷わず理解できるように整理します。公式ヘルプで説明されている内容を踏まえながら、実際の運用上で気をつけたいポイントや“落とし穴”にも触れていきます。
▶ 印税収入を伸ばしたい・収益化の仕組みを作りたい方はこちらからチェックできます:
印税・収益化 の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
なぜ「Kindle出版+手数料」で検索されるのか
目次
Kindle出版の手数料に関する検索が多いのは、それだけ「収益の仕組みがわかりづらい」と感じている人が多いからです。
出版自体は無料で始められるものの、実際には販売価格やファイルサイズなどによって、実際に手元に残る金額が変わってきます。
そのため、「どんな手数料が発生するのか」を正確に知りたいというニーズが高いのです。
手数料の全体像と計算イメージをさらに整理したい場合は、『Kindle出版の料金とは?手数料・印税・配信コストを徹底解説』もあわせて読んでおくと、数字ベースでのシミュレーションがしやすくなります。
検索者が知りたい手数料の本質とは何か
多くの人が気にしているのは「KDPがどのように収益を分配しているか」です。
Amazonが取る“手数料”というより、実際には「ロイヤリティ(印税率)」と「配信コスト」の組み合わせで、最終的な収益が決まります。
つまり、販売価格の中からAmazonが一定の割合を受け取り、残りが著者の収益になるという仕組みです。
ただし、これを単純に「印税70%だから7割もらえる」と誤解している人が多く、実際には配信コストなどの差し引きがあるため、もう少し複雑です。
「手数料」という言葉が意味するもの:ロイヤリティ・配信コスト・振込時の手数料など
KDPで「手数料」と呼ばれる要素は、主に次の3種類に分けられます。
1つ目はロイヤリティ率(印税率)。
販売価格に応じて35%または70%が設定され、どちらを選ぶかで収益が大きく変わります。
2つ目は配信コストです。
電子書籍のデータサイズ(MB単位)に応じて数円〜数十円が差し引かれる仕組みで、画像の多い書籍では注意が必要です。
3つ目は「「日本の銀行口座へのEFTは通常手数料なし・最低支払額の制限もありません。小切手・海外送金等では条件が異なる場合があります(公式ヘルプ要確認)。」複数の国で販売している人は確認しておくと安心です。
電子書籍(Kindle本)向けとペーパーバック向けでの手数料・コスト構造の違い
電子書籍とペーパーバックでは、手数料の考え方が少し異なります。
電子書籍はファイルデータの配信コストがメインですが、ペーパーバック(紙の本)は印刷コストと配送コストが発生します。
たとえば、モノクロ印刷かカラー印刷かによっても印刷コストが変わるため、紙の出版を検討している方は公式のKDP計算ツールを使って事前に試算しておくのが安全です。
「電子書籍は通常、任意に0円設定はできません。KDPセレクトの無料キャンペーン等の例外のみ無料化が可能です(公式ヘルプ要確認)。」ペーパーバックは印刷原価の関係で、最低販売価格が自動的に設定されます。
どちらの場合も、公式ヘルプで常に最新の情報を確認しておくことが重要です。
Kindle出版でかかる主要な手数料と収益構造を理解する
Kindle出版の「手数料」は、実際にはいくつかの要素が組み合わさって構成されています。
単純に「販売額の何%が取られる」という仕組みではなく、ロイヤリティ率・配信コスト・印刷費などが複合的に作用する点が重要です。
ここでは、電子書籍とペーパーバック(紙書籍)それぞれにかかるコスト構造を整理していきましょう。
電子書籍のロイヤリティ率35%/70%と手数料の関係
ロイヤリティとは、販売価格のうち著者が受け取る印税率のことです。
Kindle出版では「35%」と「70%」の2種類があり、どちらを選べるかは販売価格や販売国によって変わります。
多くの著者が目指すのは70%ロイヤリティです。
しかし、これはすべての書籍に自動的に適用されるわけではありません。
日本では販売価格が250円〜1,250円(税込)に設定されている場合にのみ、70%ロイヤリティを選択できます。
また、KDPセレクトに登録していないと対象外になるため、最初にチェックしておきましょう。
一方で、販売価格が範囲外の場合や特定の国での販売時は自動的に35%ロイヤリティが適用されます。
このあたりの仕組みは公式ヘルプに細かく書かれていますが、実務上は「販売価格を1,000円前後に設定しておけば70%を維持しやすい」と覚えておくと良いでしょう。
ただし、70%ロイヤリティの場合は「配信コスト」が差し引かれる点に注意が必要です。
35%/70%それぞれの具体的な計算例やパターン別の考え方は、『Kindle出版のロイヤリティとは?70%印税の条件と仕組みを徹底解説』で詳しく解説しているので、ロイヤリティ設計を見直すときの参考にしてみてください。
配信コスト(電子書籍のファイルサイズ等による差し引き)の仕組み
配信コストとは、電子書籍を購入者へ送信する際に発生する「データ転送料金」です。
Amazonのサーバーを通じて読者の端末にデータを配信するため、そのファイルサイズに応じて料金が引かれる仕組みになっています。
たとえば、Amazon.co.jpの場合、配信コストは1MBあたり約1円(※公式ヘルプ要確認)です。
つまり、100MBの書籍なら100円前後が差し引かれることになります。
画像を多く使った絵本・写真集・デザイン本では、この差し引きが大きくなるため要注意です。
反対に、文章中心の書籍であれば配信コストはごく小さく、ほとんど影響しません。
実際に出版してみると、「高画質の表紙画像を入れたらファイルサイズが大きくなって利益が減った」というケースもよくあります。
画像はWeb用(72dpi程度)に圧縮し、なるべく軽くすることがポイントです。
また、PDFではなくEPUB形式で制作することで、無駄な容量を抑えることができます。
配信コストは地味ですが、長期的な印税収益を左右する要素です。
紙(ペーパーバック)出版時の印刷・配送料・その他コストの基本(補足)
ペーパーバック(紙書籍)を出版する場合は、電子書籍とは異なるコスト構造になります。
「主な費用は印刷コストです。配送料は著者に個別控除されません。ロイヤリティは『(定価×60%)−印刷コスト』で算出されます(公式ヘルプ要確認)。」
印刷コストはページ数と印刷形式(モノクロ/カラー)によって変わり、たとえば100ページのモノクロ本なら1冊あたり数百円が差し引かれます。
配送コストは、Amazonが読者へ本を届ける際の送料です。
これもAmazon側が自動的に差し引き、著者の印税額が決まります。
「ロイヤリティは60%で固定です。算出は『(定価×60%)−印刷コスト』が基本です(公式ヘルプ要確認)。」
電子書籍と違い、ページ数が増えるとコストが直接上がるため、原稿を無駄に長くせず構成することも大切です。
また、ペーパーバックの最低価格は印刷原価によって自動的に決まるため、希望価格を入力しても調整される場合があります。
このため、紙書籍を予定している人は、事前にKDPの印税シミュレーターで確認しておくと安心です。
Kindle出版では、こうしたコストを理解しておくことで、初めて「いくら売れたらいくら利益になるのか」を正確に把握できます。
特に70%ロイヤリティを狙う場合は、販売価格・データ容量・配信コストのバランスを意識することが、安定した収益を得る鍵です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
手数料を抑えて収益を最大化するための実践ポイント
Kindle出版で継続的に収益を得るためには、手数料の仕組みを理解したうえで、いかに“無駄なコストを減らすか”が重要です。
ロイヤリティ率の選択、ファイル容量の調整、価格戦略の組み立て方によって、同じ本でも手元に残る金額は大きく変わります。
ここでは、経験者の視点から実践的な工夫を紹介します。
ロイヤリティ率70%を選ぶための条件と戦略
ロイヤリティ70%を得るためには、いくつかの条件があります。
まず、販売価格が250円〜1,250円(税込)の範囲に設定されていること。
そして、KDPセレクトに登録していることが基本条件です。
また、販売対象国(Amazon.co.jpを含む)で70%ロイヤリティを適用できる設定を行う必要があります。
うっかり設定を見落とすと、35%ロイヤリティになってしまうこともあります。
実際に筆者も初回出版時に、価格を範囲外に設定してしまい収益が半減した経験があります。
「価格帯は読者層・容量で最適値が変わります。まずは70%適用範囲内で仮設定し、実売と配信コストを見ながら調整してください(公式ヘルプ要確認)。」
ただし、価格を高くしすぎると購入率が下がる傾向があるため、内容とターゲット層に合わせて調整しましょう。
最初は700円〜900円程度の価格帯から始め、売上データを見ながら修正していくのがおすすめです。
配信コストを下げるためのファイル軽量化・画像最適化のコツ
配信コストはファイルサイズに比例して増えるため、できるだけ軽量化しておくことが重要です。
特に、画像やグラフィックの多い書籍は容量が膨らみやすく、収益に直接影響します。
画像を使う場合は、印刷用ではなくWeb向け(72dpi〜150dpi)の解像度で十分です。
また、ファイル形式はPNGよりJPEGのほうが軽くなりやすく、圧縮率を調整して見た目と容量のバランスを取るとよいでしょう。
EPUB形式で作成すると、テキストベースのデータ構造になり、PDFよりもファイル容量を抑えられます。
筆者の経験では、同じ本文でもPDF版はEPUB版の約3倍の容量になったことがあります。
つまり、データの作り方ひとつで印税が数%変わることもあるということです。
ファイルをアップロードした後も、「KDPプレビュー」で実際のファイルサイズを確認し、想定より大きい場合は再調整しておきましょう。
価格設定・販売戦略で手数料負担に強い設計をする方法
価格設定は、ロイヤリティ率や配信コストを踏まえた“戦略的な設計”が欠かせません。
単純に「安くすれば売れる」という考えではなく、利益が残るバランスを見極める必要があります。
たとえば、300円以下では35%ロイヤリティしか得られず、1冊売れても利益はわずかです。
一方、800〜1,000円台の価格設定なら、70%ロイヤリティで配信コストを引いても実質的な利益が確保しやすくなります。
また、KDPセレクトのキャンペーン機能を使えば、一時的に価格を下げてランキング上位を狙い、その後価格を戻すという戦略も有効です。
これは経験者の間では「スパイク戦略」と呼ばれることがあり、長期的に読者層を広げるのに効果的です。
大切なのは、「価格」「ロイヤリティ」「配信コスト」を常にセットで考えることです。
1つだけを最適化しても、他の要素とのバランスが崩れると結果的に収益が減ってしまいます。
定期的に販売データを見直し、最も安定して利益が出る価格帯を探す姿勢が大切です。
具体的な価格帯ごとのメリット・デメリットや、70%印税を維持しながら売れやすい価格を探る手順については、『Kindle出版の価格設定とは?70%印税を得るための条件と最適価格を解説』でさらに掘り下げています。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
まとめ:手数料構造を理解してKindle出版を成功させるために
Kindle出版では、販売手数料やロイヤリティの仕組みを正しく理解しておくことが、安定収益の第一歩です。
特に70%ロイヤリティを維持しつつ、配信コストを最小限に抑える工夫が鍵になります。
一見ややこしい手数料構造も、慣れてしまえばシンプルです。
「販売価格」「ファイル容量」「ロイヤリティ率」の3つを常に意識すれば、利益の見通しを立てやすくなります。
また、公式ガイドラインは定期的に更新されるため、KDP公式ヘルプをチェックして最新の条件を確認しておくことも大切です。
仕組みを理解してから出版することで、Kindle出版は“趣味の延長”から“資産になるコンテンツビジネス”へ変わります。
焦らず一歩ずつ、収益構造を味方につけながら、自分らしい作品を届けていきましょう。
売上だけでなく読み放題や既読ページ数も含めた“トータル収益”の仕組みを整理したい場合は、『Kindle出版の収益はどう決まる?印税と既読の仕組みを徹底解説』をあわせて読むと、長期的な収益設計のイメージがつかみやすくなります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。