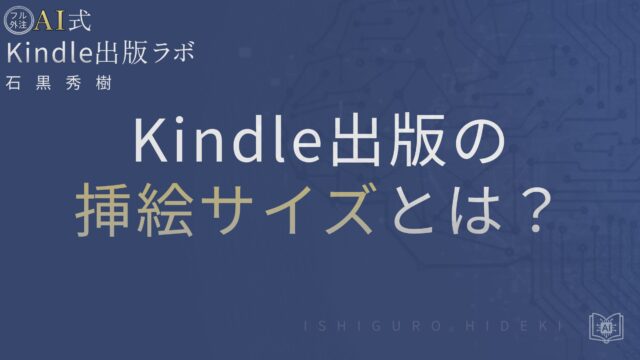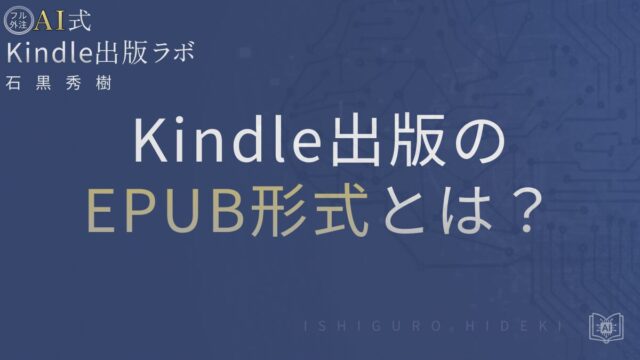Kindle出版のフォーマットとは?Word原稿から正しい形式を選ぶ方法を徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの人が最初につまずくのが「フォーマット」の部分です。
どんなに内容が良くても、レイアウトが崩れて読みにくいと、読者の満足度は大きく下がってしまいます。
一方で、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の設定を正しく理解しておけば、最初の一冊目からスムーズに出版できます。
この記事では、KDP日本版での正しいフォーマット選びと、その背景にある仕組みを、初心者にもわかりやすく解説していきます。
私自身、初めて出版したときに「目次が反映されない」「画像の位置がずれる」といった失敗を経験しました。
そうした経験を踏まえながら、実務上の注意点も交えて説明します。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
はじめに:なぜ「フォーマット」がKindle出版で重要なのか
目次
Kindle出版では、フォーマットが「読みやすさ」と「信頼性」を左右します。
紙の本なら、印刷会社が体裁を整えてくれますが、電子書籍では著者自身が整える必要があります。
つまり、出版工程の中でもっとも土台となるのがフォーマットなのです。
「フォーマット」とは何かを簡単に整理
フォーマットとは、電子書籍として正しく表示されるための「文章構造とデータ形式」のことです。
もう少し平たく言えば、「どう見せるか」を決める設計図のようなものです。
KDPで出版する際、対応している主なファイル形式は「Word(.docx)」や「EPUB」などがあります。
このうち、もっとも推奨されているのがWord形式です。
KDPのシステムがWordファイルを自動でEPUB形式に変換してくれるため、特別なツールを使わなくても出版が可能です。
ただし、目次の設定や見出しタグ(スタイル)を正しく使っていないと、変換後にズレが発生します。
公式ヘルプでも基本的なルールは示されていますが、実際には「見出しスタイルを正確に使う」「不要な改行を避ける」といった細かい部分が仕上がりを左右します。
私自身も最初の出版では、Word上ではきれいだったのに、Kindleでプレビューすると段落が崩れて見えることがありました。
その原因は、装飾や改行の癖がWord特有のタグとして残っていたためです。
フォーマットを理解することは、こうした小さなトラブルを防ぐ最初の一歩です。
Kindle出版の全体像から整理したい方は、先に『Kindle出版とは?初心者が無料で始める電子書籍の基本と仕組みを徹底解説』を読んでおくと、このフォーマット解説の位置づけがより分かりやすくなります。
読者体験と変換トラブルが起きる背景
フォーマットが適切でないと、読者はすぐに「読みにくい」と感じてしまいます。
特にリフロー型(文字が可変表示される形式)では、読者の端末によって表示サイズや行間が変化します。
そのため、作者が意図した位置に画像や改行を固定しようとすると、かえって崩れの原因になるのです。
「端末ごとに最適化される」という前提を理解して構成を組むことが、電子書籍づくりの基本です。
また、WordからEPUBへの変換時には、自動的にコードが生成されます。
ここで、余計な段落記号やインデントが残っていると、意図しないスペースや改行が生まれます。
こうしたトラブルを防ぐには、原稿の段階で余白や装飾を最小限にしておくことが大切です。
経験上、テンプレートを使うよりも、自分でWordのスタイル機能を理解して整えた方が、最終的にきれいな仕上がりになります。
KDPは基本的に日本語にも最適化されていますが、縦書き・ルビ・段組などは制約が多く、複雑な構成を避けるのが無難です。
フォーマットを整えることは、単なる技術的な作業ではなく、読者が心地よく読むための「体験設計」でもあります。
その意識を持つだけで、あなたの本の印象は大きく変わります。
対応ファイル形式とおすすめ形式を知る(KDP日本向け)
Kindle出版を行う際、最初に理解しておきたいのが「対応ファイル形式」です。
原稿データの形式は、出版後のレイアウトや表示の安定性に大きく影響します。
特に日本語書籍では、縦書き・ルビ・画像の扱いなどで崩れやすいため、形式選びを間違えると再提出になることもあります。
ここでは、実際の出版現場でもっとも使われている形式を中心に、公式仕様と実務上のポイントを整理します。
Word原稿のページ設定や余白・文字サイズの決め方については、『Kindle出版の原稿サイズとは?Word設定とレイアウト崩れを防ぐ基本を徹底解説』で、フォーマットとセットで押さえておくと安心です。
推奨される原稿ファイル形式(Word/DOCX)
初心者から上級者まで幅広く利用されているのが、Word(.docx)形式です。
Word(.docx)原稿はKDPでEPUBに自動変換されます。細部の要件や例外は公式ヘルプ要確認。
特別なツールやプログラム知識がなくても、直感的に操作できるのが大きな利点です。
また、Wordの「見出しスタイル」を使うことで、目次の自動生成にも対応できます。
これはKDP側のシステムが見出しタグ(h1/h2相当)を認識してくれるためで、章構成を正しく設定しておくことが非常に重要です。
実際、私が最初に出版した際も、Wordのスタイルを使わずに太字だけで章タイトルを書いていたところ、KDPの目次に反映されませんでした。
そのため、見出しは必ず「ホーム」タブのスタイル指定を利用することをおすすめします。
改ページは「Ctrl+Enter」で設定し、不要な空白や改行は極力減らしましょう。
見た目を整えるつもりで半角スペースを多用すると、変換後に段落が崩れる原因になります。
この点は、公式ヘルプでも「段落の整形には改行や空白を使わず、スタイルで調整」と記載されています。
もう一点、Wordで原稿を作成する場合は、フォントやサイズを統一しておくことが大切です。
日本語フォントはKDP側で自動的に置き換えられるため、特定のフォントに依存しないレイアウトにしておくと安全です。
Word形式は操作がシンプルで、修正や再提出もしやすいため、最初の一冊にはもっとも向いている形式と言えるでしょう。
EPUB・MOBI・KPFなどの補足形式とその位置づけ
EPUBは、電子書籍全般で標準的に使われている形式です。
ただし、KDPではWord原稿をアップロードすれば内部的にEPUBへ自動変換されるため、自分でEPUBを作る必要はありません。
EPUBを手動で作成するのは、レイアウトやCSSを細かく調整したい中級者〜上級者向けの方法です。
たとえば、文章に背景色をつけたい、段組を特定の場所に固定したいといった場合にはEPUB形式が有効です。
一方、MOBI形式は以前Amazon専用フォーマットとして利用されていましたが、現在はEPUBへの統一が進んでおり、MOBIでの新規アップロードは非推奨です。
既存のMOBIファイルもそのまま利用できますが、今後はEPUBまたはWordでの運用を想定しておく方が安全です。
また、KDP専用のツール「Kindle Create」を使うと、「KPF」という形式で保存できます。
これはKDP専用のフォーマットで、レイアウトを視覚的に調整しながらプレビューできるのが特徴です。
文章中心の書籍よりも、写真や表、レイアウトが複雑な教材系・ビジュアルブック系に向いています。
ただし、KPF形式を使うと修正時にツール上での再編集が必要になるため、Wordほど手軽ではありません。
実際の現場では、「原稿はWord形式で管理」「必要に応じてKindle Createで微調整」という流れが一般的です。
Word(.docx)からのアップロードは一般的で、KDPが自動変換に対応しています。詳細仕様は公式ヘルプ要確認。
したがって、EPUBやKPFはあくまで補足的な手段として理解し、基本はWord(.docx)で進めるのが安心です。
同一原稿を流用できる場合もありますが、紙は余白・ノンブル・トンボ等の体裁調整が必要なことが多い点に注意。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
レイアウト方式の選び方:「リフロー型」と「固定レイアウト型」
Kindle出版で原稿を作成する際、次に重要なのが「どのレイアウト方式を選ぶか」という点です。
KDPでは大きく分けて「リフロー型」と「固定レイアウト型」の2種類があります。
どちらを選ぶかによって、読者の見え方や操作性、さらには審査時のチェック内容まで変わります。
それぞれの特徴と、向いている本のタイプを理解しておくことで、出版後のトラブルを防ぐことができます。
リフロー型の特徴と一般文章向けの理由
リフロー型は、文字の大きさや画面サイズに合わせて自動的に文章が流れる形式です。
読者がスマートフォンやタブレットでフォントサイズを変更しても、テキストが端末に合わせて再配置されるのが特徴です。
小説・エッセイ・ビジネス書など、テキスト中心の書籍にもっとも適しています。
この方式の最大のメリットは、「読みやすさ」と「柔軟性」です。
どんな端末でも自然に表示されるため、読者が自分の好みに合わせて読み進められます。
出版者側としても、ファイルサイズが軽く、販売時のダウンロードコストを抑えられる点も利点です。
ただし、注意点もあります。
画像や表を多く使うと、位置が変わってレイアウトが崩れることがあります。
特に、Wordで改行やスペースで無理やり整えた原稿は、リフロー変換後にズレるケースが多いです。
公式ヘルプでは「段落整形に改行を使わず、スタイル機能で調整」と明記されていますが、実際の現場でもこのルールを守るだけでトラブルが半減します。
私自身も初めて出版したとき、改ページをせずに画像を挿入してしまい、プレビューで次章の冒頭に食い込んで表示されたことがあります。
原因は単純で、「画像の位置指定を行内に設定していなかった」ことでした。
このように、リフロー型では「構造的な整え方」が何よりも大切です。
公式としても、KDP日本版では文章中心の書籍にはリフロー型を推奨しています。
迷ったらリフロー型を選ぶのが基本、と覚えておくと安心です。
固定レイアウト型の特徴と画像・図版重視のケース
固定レイアウト型は、ページのデザインや構成を紙の本のように固定して表示する方式です。
見開きページや図版・写真・イラストを使った本に向いており、読者がどの端末で見ても同じレイアウトになります。
雑誌、写真集、絵本、レシピ本、教材などでは、この形式を選ぶことでビジュアルをそのまま再現できます。
ただし、この形式は扱いがやや難しく、KDPの審査でも注意が必要です。
特に日本語書籍の場合、縦書きやルビ表示に制約があり、正しく設定しないと文字化けが起きることがあります。
また、ファイルサイズが大きくなりやすく、読者の端末によっては読み込みに時間がかかることもあります。
もう一つのデメリットは、読者がフォントサイズを変更できない点です。
そのため、スマートフォンでは文字が小さくなり、可読性が下がることがあります。
実際、私も初期のころにレシピ本を固定レイアウトで制作しましたが、スマホ表示では文字が潰れてしまい、結局リフロー型に作り直した経験があります。
固定型はデザインを忠実に再現できる反面、閲覧環境の幅が狭くなる点を理解しておくことが大切です。
固定レイアウトを採用する場合は、KDP公式の「Kindle Create」や「InDesign」など専用ツールを使うのが安全です。
独自の設定やスクリプトを使うと、審査時に不備として差し戻されることがあります。
公式ガイドにも「固定レイアウトは一部カテゴリ向け」と明記されているため、一般的な文章中心の出版では無理に採用する必要はありません。
最終的に、リフロー型と固定レイアウト型の選択は、「読者にどんな体験を届けたいか」で決めるのが基本です。
文章の内容が中心ならリフロー型、ビジュアル重視なら固定レイアウト型。
このシンプルな指針を守ることで、初めての出版でも迷わず進めることができます。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Word原稿からKindle出版までの具体的手順
ここでは、実際にWordで作成した原稿をKindle出版に反映させるまでの流れを解説します。
KDPで最も多い出版トラブルは、実は内容ではなく「形式設定ミス」によるものです。
体裁を整える段階で少し意識を変えるだけで、審査通過率も読みやすさも格段に上がります。
アカウント開設やメタデータ登録など出版全体の流れとチェックポイントは、『Kindle出版の準備とは?審査落ちを防ぐ手順とチェックポイントを徹底解説』でまとめているので、フォーマット設定とあわせて確認しておくとスムーズです。
Wordでのスタイル・目次・改ページ設定の基本
Word原稿を作成する際は、まず「見出しスタイル」を正しく設定することが最優先です。
「見出し1」を章タイトルに、「見出し2」を節に使うようにすると、KDPが自動で構造を読み取って目次を生成してくれます。
装飾的に太字やフォントサイズで区別するだけでは、Kindle側では見出しと認識されません。
また、Wordの目次機能を使えば、KDPでのリンク付き目次にスムーズに変換されます。
自動生成の目次を使わずに手入力した場合、リンクがうまく機能せず、読者が章移動できないケースが多発します。
これも審査で差し戻される原因の一つです。
改ページについては、「Ctrl+Enter」での改ページ挿入が基本です。
Enterキーで改行を繰り返してページを送ると、端末によっては不自然な余白ができてしまいます。
特にスマートフォンではそのずれが顕著です。
一見地味ですが、Wordの操作を“印刷用”ではなく“電子書籍用”として意識することが重要です。
段落設定では、行間を「固定値」ではなく「自動」にしておくと安全です。
フォントサイズはKDPで自動調整されるため、無理に装飾するよりも、見出しや本文の区別をシンプルに統一する方が読みやすくなります。
私の経験では、過度な装飾(中央寄せ・色付き文字・異なるフォント混在)はすべて変換時の崩れにつながりました。
KDPでは「見た目」より「構造の正確さ」を優先することが結果的に美しい仕上がりになります。
KDPへのアップロードとプレビューチェックのポイント
原稿が完成したら、次はKDPにアップロードします。
まずKDPにログインし、「本棚」から「新しい本を作成」を選びます。
ここで原稿ファイル(WordやEPUBなど)をアップロードし、プレビュー画面でレイアウトを確認します。
プレビューでは「オンラインプレビュー」と「ダウンロードプレビュー」の2種類があります。
どちらも確認できますが、特にオンラインプレビューはブラウザ上で実際のKindle端末に近い表示を再現できるのでおすすめです。
ここで注意すべきは、改ページ・目次リンク・画像位置の3点です。
画像が意図せず別ページに飛んでいる、目次リンクが動かない、改ページがずれている場合は再調整が必要です。
もう一つのチェックポイントは「端末ごとの見え方」です。
KDPプレビューではスマートフォン・タブレット・Kindle端末などを切り替えて確認できます。
文章だけの本でも、端末によって行間や改ページのタイミングが微妙に異なります。
私が最初に出版した際も、スマホでは正常でもKindle端末では画像が右に寄っていました。
これはWordで「文字の折り返し」を「行内」にしていなかったのが原因でした。
プレビューが完了したら、「保存して続行」を押す前にもう一度ファイルサイズを確認しておきましょう。
ファイルが重すぎるとアップロードエラーが起きることがあります。
特に写真入りの原稿は圧縮してから再アップロードすると安定します。
最後に、プレビューで問題がなければ「Kindle電子書籍を出版する」をクリックして完了です。
審査期間は可変です。混雑状況や内容によって変動します(最新の目安は公式ヘルプ要確認)。
出版後もKDP管理画面から再アップロードで更新可能なので、最初から完璧を目指す必要はありません。
むしろ、実際に読者の端末でどう見えるかを確認しながら改善を重ねていく方が自然です。
電子書籍の強みは、修正や更新が容易なことです。
焦らず、段階的に完成度を上げていきましょう。
フォーマットでよくある失敗とその対策
フォーマットの設定は地味に見えて、実はKDP出版の成否を左右する部分です。
慣れていないと、プレビュー時に「えっ、こんな表示になるの?」と驚くこともあります。
ここでは、多くの初心者がつまずきやすい典型的な失敗例と、その防ぎ方を実務ベースで解説します。
KDP審査で実際にチェックされるポイントや差し戻し事例については、『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』で詳しく紹介しているので、フォーマット調整とセットで読んでおくとトラブルをぐっと減らせます。
文字化け・見出し崩れ・目次反映されないケース
まず最も多いのが「文字化け」です。
原因はWord原稿に使われているフォントがKDPの変換環境に対応していないことが多いです。
特に日本語フォントを多用した場合に発生しやすく、明朝体・ゴシック体など標準フォントの使用が安全です。
フォントを装飾的に変えると、端末によっては置き換えがうまくいかず、表示エラーになります。
もう一つ多いのが「見出し崩れ」です。
Wordで見た目を整えようとして、スタイルを使わずに手動でフォントサイズや太字を設定していると、KDPが構造を認識できません。
この結果、本文と見出しの区別がつかなくなり、レイアウトが乱れたり、章タイトルが本文の途中に見えることもあります。
見出しスタイルを使って構造を明確にすれば、自動で目次生成にも対応します。
「目次が反映されない」トラブルもこの流れで起こります。
Wordで手動入力した目次は、リンク構造が付与されていないため、KDPが正しく読み込めません。
自動目次を挿入するか、「見出し1・2」で構成された章タイトルを使うことで自動リンクが生成されます。
これは公式ヘルプでも推奨されており、私の経験でもこの方法を守るだけで審査通過率が上がりました。
また、原稿内に余分な改行や空白が多いと、変換後の段落が不自然に空くこともあります。
特に、文末にスペースを残したり、改ページ代わりに改行を連打するのはNGです。
原因を突き止めづらいため、Wordの「段落記号表示」で確認してから提出するのが確実です。
スマホ/タブレットでの表示崩れを防ぐための確認方法
表示崩れを防ぐには、プレビュー前に必ず「KDPプレビュー」で複数端末を確認することです。
これは当たり前のようで、意外と見落とされがちです。
KDPのプレビュー画面では、スマホ・タブレット・Kindle端末などを切り替えて確認できます。
この時、改ページ・画像位置・文字詰まりを1ページずつチェックするのが基本です。
スマートフォンでは、フォントサイズを小さく設定しても、読者側で拡大・縮小できるため、過度な装飾は不要です。
固定幅や余白を手動で設定していると、画面の端に空白ができてしまうことがあります。
公式仕様では「リフロー型では端末に合わせて自動で最適化される」とされていますが、実際には文頭のインデントがずれることもあります。
特に段落冒頭の全角スペースは要注意です。
画像はJPEG/PNG(sRGB)で適切に圧縮し、長辺解像度は用途に応じて調整。推奨値は公式ヘルプ要確認。
KDPは自動圧縮を行いますが、元画像が大きすぎると、画質が劣化したり、ページ遷移が遅くなります。
また、画像の「文字の折り返し」を必ず「行内」に設定しておきましょう。
これを忘れると、端末によって画像が本文の外に飛び出してしまいます。
私が過去に経験したケースでは、プレビューでは問題なかったのに、実機(Kindle Paperwhite)で見たら画像が中央寄せになっていませんでした。
原因は「中央揃え」ではなく「段落中央寄せ」で設定していたためです。
こうした微妙な差もKDPの変換では影響します。
確認を怠らないことが、最終的な品質を左右します。
出版前の最終チェックは「別の端末で見る」。
これが最も確実なトラブル防止策です。
端末による表示の差を理解しておけば、修正の優先度も判断しやすくなります。
まとめ
Kindle出版では、フォーマット設定が全体の印象を決定します。
内容が良くても、体裁が乱れているだけで読者の離脱率は上がります。
逆に、きちんと整えられた本はそれだけで信頼感を生み、レビュー評価にもつながります。
Wordのスタイル設定、目次構造、改ページ方法、そしてプレビュー確認。
この4つを押さえておけば、初出版でも安定した仕上がりになります。
特にKDPでは更新が容易なので、最初から完璧を求めず、改善を重ねる姿勢が大切です。
最後にもう一度。
フォーマットは「技術」ではなく「読者への思いやり」です。
読者がストレスなく読める形を目指すことが、結果的に長く読まれる作品づくりにつながります。
焦らず、ひとつずつ整えていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。