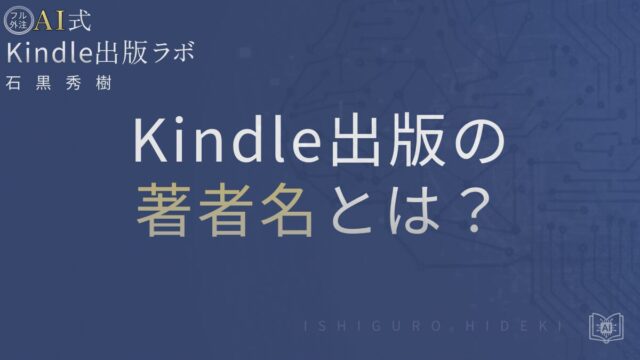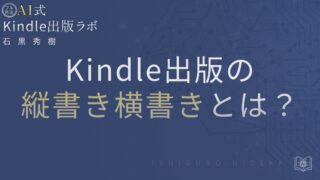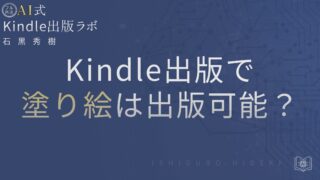Kindle出版の日記は電子or紙?出版可否と注意点を徹底解説
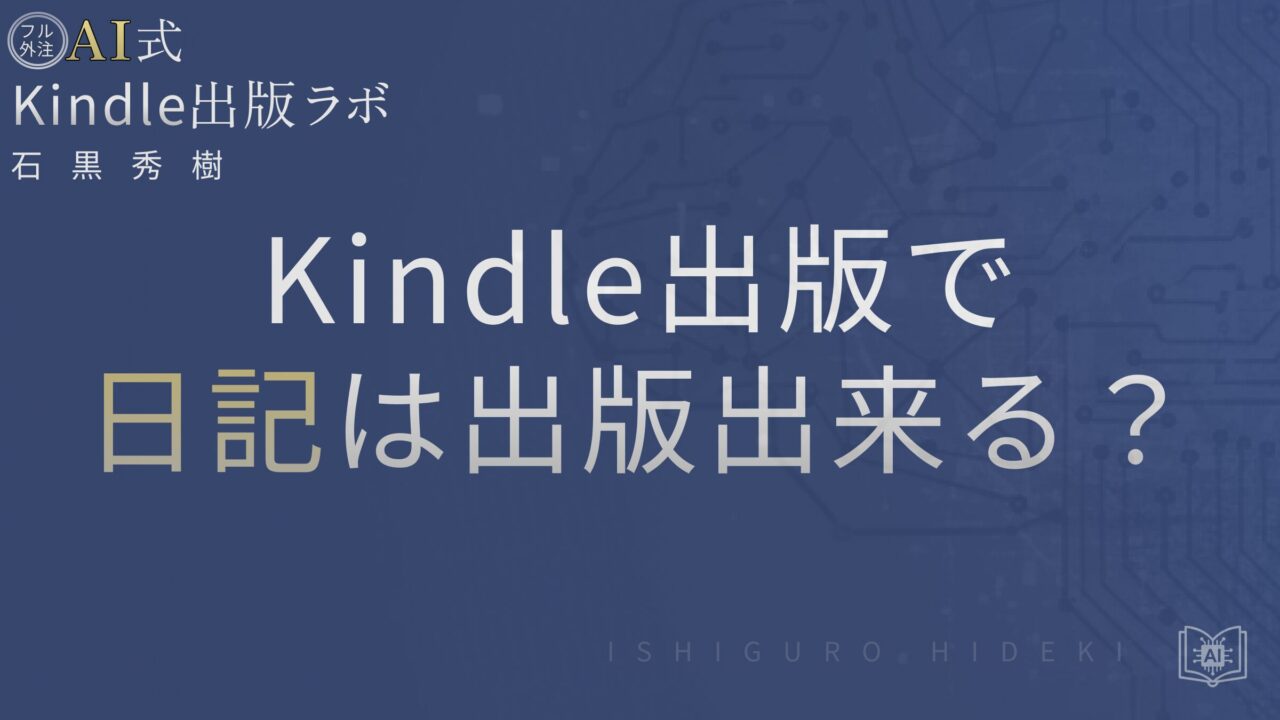
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「日記」を出したいと考える人は少なくありません。
自分の体験を残したい人、日記帳フォーマットを販売したい人、あるいは副業として電子書籍を出したい人など、目的はさまざまです。
ただし、「日記」というジャンルは、KDPの規約や品質ガイドラインに特有の注意点があり、そのままでは出版できないケースもあります。
この記事では、読む日記と書き込み式日記帳の違い、KDPのルール、電子書籍と紙の扱いの差まで、初心者でも迷わないように体系的に解説します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で「日記」は出版できる?まずは基本を理解しよう
目次
Kindleでは、日記の出版は可能です。
ただし、形式や内容によっては制限や審査落ちのリスクがあるため、まずは基本を押さえることが重要です。
読む日記と書き込み日記帳の違いとは?
日記には大きく分けて、著者自身の記録をまとめた「読む日記」と、ユーザーが自由に書き込むための「書き込み式日記帳」の2種類があります。
読む日記は、自分の経験や心情、日常の記録を文章としてまとめたものです。エッセイや回想録のような形式であれば、通常の電子書籍として問題なく出版できます。
一方、書き込み式日記帳は、日付欄や質問欄などのフォーマットを用意し、読者が記入して使うことを目的とした書籍です。
これはKDPの電子書籍では構造上の制限があり、通常のリフロー型では適していません。
特に電子書籍では、ユーザーが実際に書き込むことは基本的に想定されていないため、「空白ページだけの本」は審査で却下される可能性が高いです。
この点を知らずにテンプレートをそのままアップロードして落とされるケースは非常によくあります。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の規約と品質ガイドの確認
KDPでは、コンテンツポリシーと品質ガイドラインが明確に定められています。
日記に関連して特に注意が必要なのは、以下の2点です。
1つ目は、「有用なコンテンツ」であること。
読む日記の場合は、ただの日付羅列ではなく、内容が伴っている必要があります。数行のメモだけを羅列しただけの本は、低品質コンテンツとみなされる可能性があります。
2つ目は、「反復的で中身がないテンプレート」への対応です。
書き込み式の場合、同じページを機械的に複製しただけの本は、審査でリジェクトされやすいです。公式の品質ガイドでも「コンテンツの独自性と有用性」が重視されています。
公式では明文化されていない部分でも、実務上は「見た瞬間にテンプレだけ」と判断されるとNGになることがあるので、表現や構成には注意が必要です。
規約やガイドラインは更新されることもあるため、出版前に必ずKDP公式ヘルプを確認してください。
電子書籍とペーパーバック(日記帳)の扱いの違い
電子書籍とペーパーバック(日記帳)は、KDP上でも扱いが大きく異なります。
電子書籍(リフロー型)は、文章を読むことを前提としているため、日記帳形式には不向きです。入力欄を設けたり、PDFのような固定レイアウトで日記帳を再現しようとする人もいますが、リフローではレイアウト崩れが起きやすく、審査で落ちる原因になります。
一方、ペーパーバックでは書き込み式の日記帳を販売することが可能です。
ただし、ページ数や構成にも一定の基準があり、24ページ未満では出版できないなどのルールがあります。
また、紙でもテンプレートを大量に繰り返しただけのものは、品質面でリジェクトされる可能性があります。
そのため、紙の場合も、使いやすさや独自性を意識したデザインが必要です。
日記帳が紙向きになりやすい理由は、まず『Kindle出版の形式とは?リフロー型・固定レイアウト・対応ファイル形式を徹底解説』で仕組みを押さえると理解が早いです。
読む日記をKindle電子書籍として出版する場合のポイント
読む日記は、KDPでも比較的スムーズに出版できるジャンルのひとつです。
ただし、単なるメモ書きや羅列では品質面で却下される可能性があるため、いくつかのポイントを押さえる必要があります。
読む日記の可読性は縦横の選び方で変わるため、『Kindle出版の縦書きと横書きとは?設定方法とジャンル別の使い分けを徹底解説』も合わせて確認してください。
個人の日記・回想・体験記は出版可能な理由
KDPでは、著者自身の体験や記録をまとめた日記・エッセイ・回想録の出版は認められています。
これは、コンテンツとして独自性があり、読む価値があると判断されるためです。
たとえば、子育ての日々を記録したエッセイや、留学体験をまとめた日記、長期の闘病記などはよく見られるジャンルです。 「自分の言葉」で綴られていることが重要で、他者の文章を寄せ集めたものやAIの出力をそのまま載せるだけでは審査を通過しにくい傾向があります。
また、公式ヘルプでも「日記や個人の記録の出版は可」と明記されていますが、実際には内容が薄い場合やテンプレート的な繰り返しが多い場合、品質面でリジェクトされるケースがあります。
そのため、「読む」ことを意識した構成や語り口が求められます。
個人情報・第三者情報の扱いと注意点
日記や回想録では、本人だけでなく周囲の人や具体的な場所が登場することがあります。
ここで注意したいのが個人情報や第三者のプライバシーの扱いです。
名前・住所・勤務先など、個人を特定できる情報をそのまま記載すると、公開後にトラブルになる可能性があります。
実名を避け、仮名やイニシャルに置き換える、場所をぼかすなど、プライバシーへの配慮が不可欠です。
また、他者が書いた文章や写真を許可なく転載することもNGです。
日記の中で引用したい場合は、著作権や使用許諾の確認を必ず行ってください。
特に過去のSNS投稿をそのまま貼り付けるケースは要注意です。
「自分の投稿だからOK」と思いがちですが、SNSには画像やコメントなど第三者が関わる要素も多く、権利関係が複雑になることがあります。
読み物としての日記を電子書籍化する基本手順
読む日記をKindleで出版する手順は、一般的な電子書籍とほぼ同じです。
まず、WordやGoogleドキュメントなどで原稿をまとめます。
時系列で並べるだけでなく、テーマ別に章立てをすると読みやすさが上がります。
1日ごとに短いエピソードを区切る構成も人気です。
次に、KDP用に原稿を整形します。
リフロー型の電子書籍では、余計な改行や空白が多いとレイアウト崩れを起こしやすいので注意してください。
ファイル形式は、Word(.docx)をそのままアップロードする方法が最も簡単です。
EPUB形式に変換する場合もありますが、初心者はWordで十分対応できます。
KDPのオンラインプレビューに加え、Kindle Previewerでも複数端末の挙動を検証すると精度が上がります。
実機確認も推奨。
最後に、タイトル・著者名・説明文などのメタ情報を登録し、審査に進みます。
内容がしっかりしていれば、読む日記ジャンルは比較的スムーズに通過することが多いです。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
書き込み式「日記帳」を出版したい場合の選択肢
読む日記とは違い、書き込み式の日記帳はKDPの扱いがやや特殊です。
実際、電子書籍ではうまく対応できない部分が多く、ペーパーバックでの出版が基本になります。
ここでは、その理由と出版の流れ、そしてKDP特有のルールについて整理しておきましょう。
なぜ電子書籍では日記帳が不適合になりやすいのか
KDPの電子書籍(リフロー型)は、端末やアプリによって文字サイズや表示レイアウトが可変です。
そのため、紙のノートのような「罫線」「書き込み欄」「日付フォーマット」を意図通りに配置することが難しくなります。
たとえば、Wordで罫線を作っても、Kindle端末で表示するとズレてしまったり、行間が変わって入力欄が崩れるケースがよくあります。 このレイアウトの不安定さが、電子書籍で日記帳を作る際の一番の落とし穴です。
公式としても「書き込み式のノートやワークブックはリフロー型ではなく固定レイアウトが必要」としていますが、固定レイアウトは用途が限られます。
日記帳用途では運用が難しい場合があります(公式ヘルプ要確認)。
そのため、電子書籍で日記帳を作るよりも、ペーパーバック(紙)で出版する方が現実的です。
ペーパーバック(紙)で日記帳を出版する基本的な流れ
ペーパーバックでは、レイアウトが固定されるため、日記帳のような罫線入りや書き込みスペースのある本も問題なく制作できます。
手順は大きく次の通りです。
まず、Wordやデザインソフト(Canvaなど)で、書き込み欄を含めた紙面を1ページずつデザインします。
サイズはKDP推奨のB5やA5、もしくは米国標準サイズ(6×9インチ)を使うのが一般的です。
その後、PDF形式で原稿を保存し、KDPのペーパーバックとしてアップロードします。
表紙も、背幅を含めたフルカバーサイズ(1枚画像)を作成する必要があります。
ペーパーバックにはISBNが付与(自前orKDPの無料提供)。
ASINは商品ページ識別子で併存します。用語を区別して記載。
デザインの品質やページ数(24ページ以上)が基準を満たしていれば、比較的スムーズに通過します。
書き込み欄のズレや罫線の崩れは、最終的に印刷プレビューで細かくチェックすることが重要です。
ここを怠ると、実物が届いてから修正になることも多いので注意してください。
紙の運用や識別子の扱いは『Kindle出版でISBNは必要?電子書籍とペーパーバックの違いを徹底解説』で整理しておくと迷いません。
低コンテンツ書籍のルールと注意点(公式ヘルプ要確認)
書き込み式の日記帳は、KDPの区分では「低コンテンツ書籍(Low-content books)」にあたります。
これは、読者が読むコンテンツよりも、書き込み欄や繰り返しのページが中心の本を指します。
2022年以降、KDPでは低コンテンツ書籍の登録ルールが明確化され、タイトルや説明文の付け方、メタデータの設定方法などに細かい基準が設けられています。
内容がほぼ白紙のノートやカレンダー形式の場合、ジャンルやキーワード設定を誤ると審査で却下されるケースもあります。
また、低コンテンツ書籍のISBN付与や配布範囲は仕様変更の影響を受けやすい項目です。
最新の取得可否は公式ヘルプ要確認。
書籍はISBNの無料取得が対象外になる場合があります(米国KDPではISBN不要扱いですが、日本語書籍では注意が必要です)。
最新の仕様は公式ヘルプで必ず確認し、ページ数・内容・メタ情報がガイドラインに沿っているか事前にチェックしておきましょう。
実務的には、表紙デザインとタイトルの差別化が非常に重要です。
同じような「日記帳」が大量に並んでいる中で埋もれないために、テーマやターゲットを明確にした表紙とタイトルを考えると、販売面でも有利になります。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
ジャンル別・目的別|「日記」出版の実例と判断基準
日記と一口に言っても、その形はさまざまです。
読み物としてのエッセイ型、書き込み式のテンプレート型、両者を組み合わせた複合型など、ジャンルや目的によって適した出版方法が異なります。
ここでは、それぞれのタイプごとの実例と、ジャンル判断の基準を具体的に紹介していきます。 自分が「どんな目的で出版したいのか」を明確にすることが、方向性を間違えない一番のポイントです。
エッセイ・体験記タイプの日記出版例
まずは「読む日記」に分類される、エッセイや体験記タイプです。
これは著者自身の人生や日々の記録を文章としてまとめ、読者に読ませる形で出版するもので、KDPでもっともスムーズに電子書籍化できます。
たとえば、ある主婦の方が子育ての奮闘記を日記形式でまとめた例があります。
毎日の出来事を淡々と綴るだけでなく、そのとき感じた感情や気づき、背景のエピソードを加えることで読み物としての魅力が増し、多くの共感を集めました。
Word(DOCX)で原稿を作成し、縦書きか横書きは内容に合わせて選択。読み方向はKDP側で設定し、プレビューで確認。
このタイプでは「日記=文章コンテンツ」なので、KDPの品質基準を満たしやすく、審査で落ちるケースも少ないです。
書き込み式日記帳・テンプレート帳の活用例(ペーパーバック)
一方、書き込み式の日記帳やテンプレート帳は、電子書籍ではなくペーパーバック(紙)で出版するのが基本です。
例えば、「1日3行で続ける感謝日記」や「ビジネス習慣の記録ノート」など、テーマや目的を明確にしてテンプレート化した書き込みページを繰り返し配置する構成がよく見られます。
こうした本は、中身のデザインが勝負です。
罫線や記入欄の配置を丁寧に作り込み、シンプルでも使いやすいレイアウトに仕上げることが重要になります。
KDPでは「低コンテンツ書籍(Low-content)」として分類されるため、タイトル・メタデータ・カテゴリ設定などをしっかり行う必要があります。
また、ノート類はジャンル競争が激しいため、表紙デザインやテーマの切り口を工夫することで差別化することも欠かせません。
複合型(日記+ワーク・コラムなど)の構成アイデア
最近は、「読む日記」と「書き込む日記帳」を組み合わせた複合型も人気です。
たとえば、最初の数ページで著者自身の体験記や日記エッセイを掲載し、そのあとに読者自身が書き込めるワークページを用意する構成です。
この形式のメリットは、著者の世界観や考え方を伝えつつ、読者が自分ごととして書き込む余白を持てる点にあります。
日記+コラム、日記+目標設定シート、日記+チェックリストなど、テーマ次第で構成の幅は広がります。
制作面では、前半を電子書籍(読み物)として、後半をペーパーバックの書き込みページにする“分冊方式”もあります。
もしくは、ペーパーバック1冊の中で前半=読み物/後半=ワークとする構成も可能です。
ただし、複合型は構成が複雑になるため、KDP登録時のカテゴリや説明文を丁寧に書かないと、審査で誤分類されることがあります。
特に「読み物としての要素」が薄いと低コンテンツ扱いになる可能性もあるため、注意が必要です。
複合型では、電子と紙それぞれの特性を理解し、構成と登録設定を明確にすることが成功のカギです。
よくある勘違いと審査・販売停止を避けるための注意点
日記の出版は一見シンプルに見えますが、実はKDPのガイドラインや審査基準でつまずく人が少なくありません。
とくに「書き込み式日記帳」やAIを活用した原稿では、公式のルールと実務のギャップがあるため、注意して進める必要があります。
ここでは、実際によくある勘違いや販売停止につながりやすいポイントを整理して解説します。 見落としやすい部分を事前に押さえておくことで、余計なトラブルや再審査を防ぐことができます。
「空白ページの多い本=低品質」とみなされるケース
KDPでは、空白ページが多い書籍は「コンテンツ不足(低品質)」と判断されることがあります。
これは特に、書き込み式の日記帳やテンプレート本で起こりやすいトラブルです。
例えば、1ページに日付と罫線だけがあるノートを200ページ分並べただけの書籍は、内容が薄いと見なされる可能性が高いです。
表紙やタイトルがどれだけ整っていても、中身が単調だと「出版停止」や「登録却下」になることがあります。
実際のところ、公式ヘルプでは明確なページ数基準は示されていませんが、審査担当者が「読者に実質的な価値を提供しているか」を重視している印象です。
そのため、テンプレート本でも冒頭に使い方の説明や例文、テーマ解説などを入れてコンテンツとしての厚みを出すと良いでしょう。
空白ページを並べるだけでは出版できないという点は、初心者が最も勘違いしやすいポイントです。
メタデータ・カテゴリ設定の誤りによる販売停止
もう一つ多いのが、メタデータ(タイトル・著者名・説明文など)やカテゴリ設定のミスによる販売停止です。
例えば、書き込み式日記帳を「小説・文学」カテゴリに設定してしまうと、読者体験との乖離が大きくなり、KDPの審査で引っかかることがあります。
また、タイトルやサブタイトルに実際の内容と関係のないキーワードを詰め込みすぎるのもNGです。
特にSEO目的で不自然にキーワードを連ねると、アルゴリズムだけでなく目視の審査でも警告や停止の対象になります。
実務上、ジャンルが「読む日記(エッセイ型)」か「書き込む日記帳(テンプレ型)」かによって、正しいカテゴリ・説明文の書き方はかなり変わります。
公式ヘルプにも例があるので、設定前に一度確認しておくと安心です。
読む日記と書き込み式ではカテゴリ選定が変わるため、『Kindle出版のカテゴリーとは?選び方・設定手順・注意点を徹底解説』の基準を参照して設定してください。
AI生成コンテンツの日記を出版する場合の開示義務
2023年以降、KDPではAI生成コンテンツの取り扱いルールが明確化されました。
AIで本文やテンプレートを生成した場合は、登録時に「AI生成コンテンツ」のチェックを入れて開示する必要があります。
とくに、AIで自動的に日記本文を生成した場合、これを開示しないと販売停止やアカウント警告の対象になる可能性があります。
一方、単にAIを使ってレイアウトを補助したり、文章の推敲をしただけの場合は、開示の対象にはなりません。
「どこまでがAI生成にあたるのか」を曖昧なまま登録するのが一番危険です。
迷った場合は、KDPの公式ガイドラインを確認し、必要に応じてサポートに問い合わせるのが安全です。
まとめ|日記出版は「読むか」「書くか」で方向性が決まる
日記の出版は、内容によって電子書籍とペーパーバックの使い分けが明確に分かれます。
読み物としてのエッセイ・体験記なら電子書籍、書き込み式のテンプレート本なら紙(ペーパーバック)が基本です。
どちらの場合も、KDPのガイドラインを踏まえたうえで構成やメタデータを丁寧に設計することで、審査をスムーズに通過し、読者にとっても価値ある本に仕上げることができます。
最初に「読む本か・書く本か」を明確にし、それに沿って出版形式・構成・設定を決めることが、日記出版成功の第一歩です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。