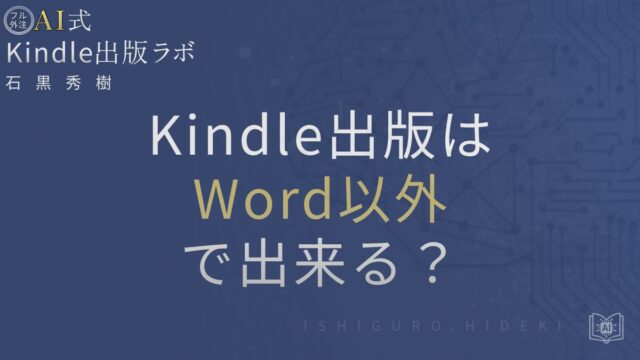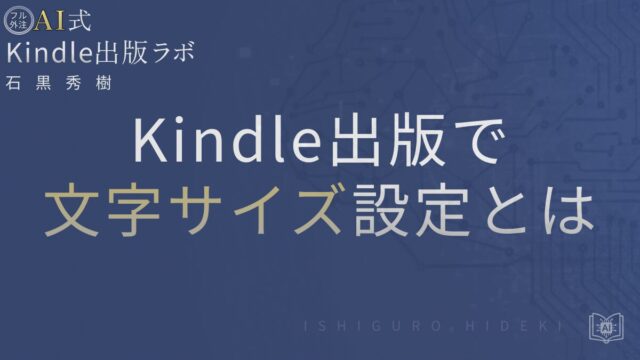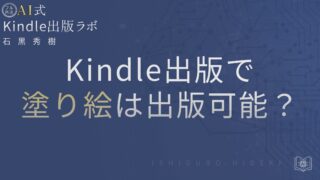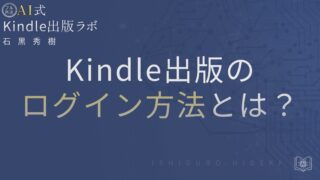Kindle出版でノートは出せる?電子では不可の理由と紙で出す手順を徹底解説
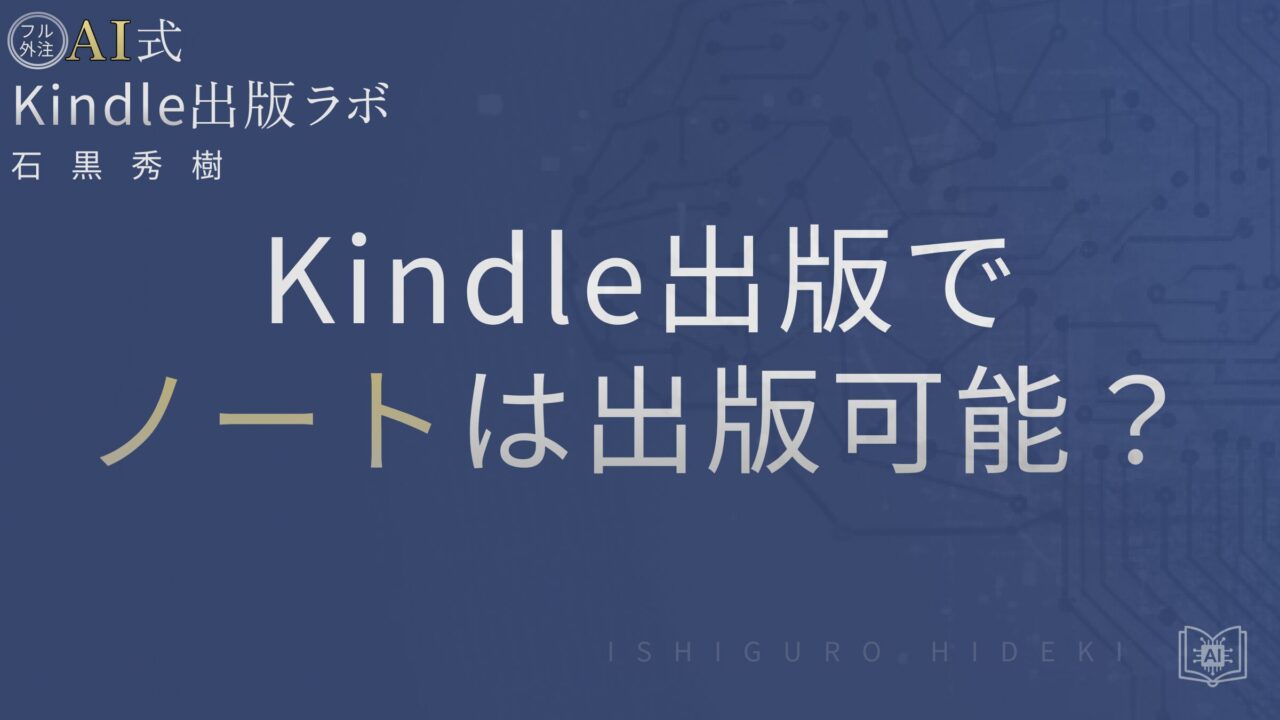
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を調べていると、「ノート」や「日記帳」「ワークブック」を出したいという声をよく聞きます。
実際、私自身も最初にKDPを触ったとき、「これなら簡単に電子書籍でノートを出せるのでは?」と考えていました。
しかし、いざ申請すると電子書籍では“ノート形式”は原則として認められていないことを知り、思わぬところで却下される人が非常に多いジャンルだと気づきました。
この記事では、Kindle出版でノートを出そうと考えている方に向けて、電子でNGになる理由と、正しい出版形式(紙)を選ぶための基本ルールをわかりやすく解説していきます。
特に初心者の方がつまずきやすいポイントを実体験を交えて紹介しますので、出版前にしっかり確認しておきましょう。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版でノートは電子不可?出版前に知る基本ルール
目次
「ノート出版」は、一見すると手軽に始められそうに見えますが、KDPのルールを理解していないと最初の段階でつまずいてしまいます。
ここでは、KDPにおける「ノート」の扱いと、電子書籍で非対応となる理由、そして公式が明示している対象カテゴリを順番に整理していきます。
「ノート」とは?KDPでの扱いと一般的な意味の違い
まず、一般的に「ノート」という言葉は、日記帳やメモ帳、ワークブックなど、読者が自分で書き込むことを前提とした“記入用の冊子”を指します。
一方、KDP(Kindle Direct Publishing)では、「読者が書き込むことを主な目的とするコンテンツ」は電子書籍として適していないと明確に位置づけられています。
この点を勘違いして「普通の文章本と同じようにノートも電子で登録できる」と思い込む方が非常に多いです。
実際、私も最初に何も考えず「ノート形式」で電子書籍の原稿を作成し、申請してみたところ、審査であっさり却下されました。
KDPでは「本」としての内容があることを重視するため、罫線や空白ページばかりの構成では、電子書籍としての価値が認められにくいのです。
Kindle電子書籍で“ノート形式”が非対応になる理由
Kindle電子書籍は、スマホ・タブレット・PCなど、デジタル端末で「読む」ことを前提に設計されています。
つまり、読者がペンで直接書き込むような使い方は想定されていません。
KDPの品質基準でも、「パズルや塗り絵、日記帳など、書き込みを主目的とするコンテンツはKindle本として適さない」と明記されています。
そのため、ノートを電子書籍として申請すると、審査で却下される、あるいは一時的に通っても後から販売停止になるケースが少なくありません。
また、公式ヘルプには明確な基準が書かれていますが、実際の審査現場では「罫線の多さ」や「内容の薄さ」で判断されることもあり、ケースによっては微妙なラインで落ちることもあります。
「これはOKだろう」と思って出したものが、予想外に却下されるというのは、経験者のあいだではよくある話です。
電子では不可となる背景や線引きは、**『Kindle出版の規約とは?審査通過のポイントと違反回避を徹底解説』**で具体例つきで確認してください。
KDP公式ガイドラインで明記されている対象カテゴリ(パズル・日記帳など)
KDPの公式ガイドラインには、Kindle本に適さないコンテンツとして、以下のようなカテゴリが明記されています。
* 日記帳・手帳・ワークブック
* パズルブック・塗り絵・練習帳
* 罫線や空白ページが大部分を占める低コンテンツ本
これらは、電子ではなく紙(ペーパーバック)での出版を想定したカテゴリです。
特に、罫線や空欄が続くページは「コンテンツがない」と判断されやすく、電子では通りません。
ペーパーバックでは「低コンテンツ本」という扱いで申請できるため、ノートを出したい場合は出版形式を電子ではなく紙に切り替えることが必須になります。
この点を理解していないと、「なぜか通らない」「販売停止になった」といったトラブルに直結します。
初心者ほど「文章を書かなくていいから簡単」と思いがちですが、実際にはKDP特有のルールがあるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
Kindle出版でノートを出したい人が最初に理解すべきこと
ノートをKindleで出版したい場合、まず理解しておくべきは「電子書籍ではなく、ペーパーバック(紙の本)で出すのが基本」という点です。
これはKDPのルール上、避けられないポイントです。
知らずに電子で申請してしまい、「なぜか審査で落ちる」「販売停止になった」というケースは初心者によくあります。
ここでは、出版形式の選び方や登録時のチェック項目、そして最低要件について、実務に沿って解説します。
電子書籍ではなく「ペーパーバック」での出版が基本になる
ノート形式の本は、KDPでは「電子書籍」ではなく「ペーパーバック」で出版するのが基本です。
これは、読者が内容を“読む”ための電子書籍と、“書き込む”ためのノートでは、利用目的がまったく異なるためです。
KDPの公式ガイドラインでも、書き込みを主目的としたコンテンツはKindle本には適さないと明記されています。
実務的にも、電子では罫線や空白のあるページが適切に表示されなかったり、読者が書き込めなかったりと、ユーザー体験の面で問題が起こりやすいのです。
そのため、KDPではノート・ワークブック・日記帳などは紙(ペーパーバック)での出版を想定しています。
私も最初のころ、電子書籍でノートを出そうとして却下されました。
その後、ペーパーバックに切り替えて申請したところ、すんなり通った経験があります。
形式を間違えると、内容がどれだけ整っていても審査では通らないため、最初の段階で出版形式を正しく選ぶことが重要です。
低コンテンツ本として登録する際のチェック項目と注意点
ノートをペーパーバックで出版する場合は、「低コンテンツ本」として登録する必要があります。
「低コンテンツ本」とは、文章や解説がほとんどなく、罫線や空白ページなど、読者が書き込むスペースが中心となる本のことです。
KDPの登録画面では、出版時に「この本はコンテンツが少ないですか?」という項目があり、該当する場合はチェックを入れます。
ここを見落として申請すると、後から修正が必要になったり、場合によっては却下されることもあります。
注意点として、低コンテンツ本は拡張流通など一部機能が対象外になる場合があります。
無料ISBNの可否は地域・仕様で異なる可能性があるため、公式ヘルプ要確認。
また、罫線の配置やページ構成が雑だと、審査で引っかかる可能性もあります。
公式では明確な数値基準は示されていませんが、実務的には「同じページの繰り返しでも丁寧に整える」「罫線や余白がずれていないか確認する」といった細かい調整が通過率に影響します。
ここをおろそかにして「テンプレだけでいいや」と思うと、思わぬところで修正を求められることもあります。
24ページ以上など、ペーパーバック出版の最低要件
ペーパーバックには、KDP上で定められた最低ページ数があります。
ノートを含むすべてのペーパーバックは、最低24ページ以上が必要です。
これは、印刷の都合上、24ページ未満では製本できないためです。
ページ数が足りないと、その時点で申請が通らないので注意してください。
また、24ページギリギリで提出するよりも、ある程度余裕を持たせた構成にしておくと安心です。
実務では、表紙や冒頭ページ、余白などを含めると、思っているよりページ数が増える(または減る)ことがあります。
特に罫線だけのページ構成だと、デザインの崩れが起きやすいので、入稿前にプレビュー機能でしっかり確認しましょう。
この確認を怠ると、印刷後にずれが生じて再入稿になるケースもあります。
ノート出版は「低コンテンツだから簡単」と思われがちですが、実際には細かいルールや注意点が多いジャンルです。
最初のうちにこれらのポイントを押さえておくと、後の手戻りが大幅に減り、スムーズに出版できます。
最低ページ数や落とし穴は、『Kindle出版のページ数は何ページ必要?電子書籍と紙の違いを徹底解説』でチェックしてから入稿しましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
ノート出版のよくある勘違い・つまずきポイント
ノート出版は「文章が少ない=簡単」と思われがちですが、実際には初心者がつまずきやすい落とし穴がいくつもあります。
これは、KDPのルールが通常の電子書籍とは異なる部分が多く、感覚で進めると引っかかるためです。
私自身、最初は「これくらいなら大丈夫だろう」と思って申請し、何度か却下を経験しました。
ここでは、特に多い3つの勘違い・ミスについて具体的に見ていきましょう。
“読む日記”と“書き込む日記”の違いは、『Kindle出版の日記は電子or紙?出版可否と注意点を徹底解説』で整理できます。
「電子でも日記はOK」と思い込んで審査で却下されるケース
最も多いのは、「日記なら文章も書いてるし、電子でも出せるはず」と思い込んで申請し、審査で却下されるケースです。
KDPでは、日記といっても「読む日記」と「書き込む日記」はまったく別の扱いになります。
著者自身が文章を書き、それを読ませる「読む日記」は通常の電子書籍として申請できますが、読者が書き込むスペースが中心の「日記帳」は電子では不可です。
この違いを理解していないと、見た目はしっかりした本なのに「コンテンツ不足」と判断され、審査で落ちてしまいます。
私も初めてノートを電子で申請したとき、「内容が少なすぎる」という理由で却下されました。
罫線ページを増やしても意味はなく、むしろ電子で出すこと自体がルール上NGだったのです。
「日記=OK」という思い込みが最大の落とし穴なので、出版前にKDPの公式ガイドラインを必ず確認することをおすすめします。
note(サービス)とノート(冊子)の混同によるミス
もう一つ多いのが、「note」という言葉の混同です。
日本では文章投稿サービス「note」が一般的に浸透しているため、「noteの記事をKindleで販売したい」という人も少なくありません。
しかしKDPで「ノート」といえば、手書き用の冊子やワークブックを指します。
この違いを理解せずに「noteのコンテンツをそのままアップしたら通るだろう」と思い込むと、内容が中途半端になり、審査で弾かれることがあります。
実際、noteの文章は改行や構成がWeb前提になっていることが多く、そのままでは電子書籍としての体裁が整っていません。
文章をまとめ直さずに申請すると、「コンテンツの体裁が整っていない」と判断される可能性があります。
この点はKDPのルールというよりも、実務上のフォーマットの問題です。
初心者の方は特に、「noteとノートは別物」と頭を切り替えることが大切です。
装丁や内容が「読む本」と見なされないパターンに注意
最後に意外と多いのが、装丁や中身の作りが原因で「本」と見なされないケースです。
表紙が白地にタイトルだけだったり、中身が罫線ばかりだったりすると、KDPの審査で「本としての体裁を満たしていない」と判断されることがあります。
これは公式にも「コンテンツが少ない場合は審査対象になる」と明記されていますが、実務的にはデザインの印象やページ構成も判断に影響します。
例えば、私が以前つくったノートでは、内容的には問題なかったのに、表紙デザインがあまりにシンプルすぎて再提出になったことがありました。
特に罫線本・ワークブック系は「中身が薄く見える」ため、装丁やレイアウトに気を配らないと審査で落ちるリスクが高くなります。
内容だけでなく、見た目の「本らしさ」も重要という点は、初心者が見落としやすいポイントです。
こうした勘違いやつまずきは、事前に正しい知識を持っていれば防げるものばかりです。
出版前に一度立ち止まり、KDPの公式情報と実際の出版事例を照らし合わせて確認しておくと安心です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版でノートをペーパーバックとして出す手順
ノートは電子ではなくペーパーバックで出すのが基本とお伝えしましたが、実際の手順は思っているほど複雑ではありません。
ただし、通常の文章主体の本とは登録フローやファイル準備の考え方が少し異なるため、最初にポイントを押さえておくとスムーズです。
ここでは、登録時の出版形式の選択から原稿・表紙の作成、価格設定・販売開始までを順番に解説します。
KDPアカウントでの登録時に選ぶべき出版形式
KDPでノートを出版する場合は、まずアカウントにログインし、「本棚」から「+ペーパーバックを作成」を選びます。
電子書籍ではなく、必ず「ペーパーバック(紙)」を選択してください。
ここを間違えると、その後の工程でやり直しになってしまうため、最初の段階での選択が重要です。
タイトル・著者名・説明文などは、通常の書籍と同様に入力します。
その後の「本の内容」セクションにある「この本はコンテンツが少ないですか?」という項目では、ノートの場合は必ず「はい」にチェックを入れます。
これが、いわゆる「低コンテンツ本」としての登録にあたります。
チェックを忘れると、プレビュー画面でエラーが出たり、審査時に差し戻しされることがあるので注意しましょう。
また、ジャンル設定やキーワード入力も重要です。
ノートの場合、「日記」「メモ帳」「ワークブック」などのカテゴリを適切に選び、ユーザーが検索しやすいキーワードを意識して設定してください。
ここで内容とカテゴリがズレていると、販売開始後に検索結果にうまく表示されないことがあります。
PDF原稿と表紙の準備方法(罫線・余白・装丁の基本)
ペーパーバック用の原稿は、WordやCanva、PowerPointなどで作成し、最終的にPDFに変換して入稿します。
ノートの場合、本文は罫線や方眼、チェックリストなどがメインになることが多いですが、余白・罫線・ページ数などの基本設計がずれていると審査で落ちる原因になります。
特に多いのが、ページのマージン(余白)が狭すぎるパターンです。
印刷時に綴じ部分が欠けたり、テキストや罫線が切れてしまうと、そのまま販売できません。
KDP公式の「ペーパーバック用テンプレート」を使用すると安全です。
表紙はKDPのガイドラインに沿って作成します。
推奨は表1(表紙)、背表紙、裏表紙を一体化したPDFを入稿する形式です。
表紙デザインはシンプルでも構いませんが、「本としての体裁」が重要です。
タイトルや著者名が明確に読めること、背景画像が粗くないことをチェックしてください。
私が初めてノートを作ったとき、罫線の太さをページによって変えてしまい、印刷プレビューでガタついて見えることがありました。
細かい部分ですが、こうした整合性が出版後のクオリティに直結します。
原稿と表紙は、KDPのプレビュー機能で何度も確認してから提出するのが安心です。
価格設定・販売開始までの流れを初心者向けに解説
原稿と表紙をアップロードしたら、最後に価格設定を行います。
ペーパーバックでは、印刷コストをもとにした最低価格が自動的に表示されるので、それを下回る価格は設定できません。
印刷コストはサイズ・ページ数・インク有無で自動計算されます。
表示される最低価格を基準に設定してください。
最低価格に数百円を上乗せして設定するのが一般的です。
価格設定が終わったら、出版内容を確認して「出版」ボタンを押します。
審査期間は通常数日で前後します。最新の目安は公式ヘルプ要確認。
審査が通れば、自動的にAmazonの販売ページが生成され、販売が開始されます。
ここでのよくある落とし穴は、プレビューを確認せずに提出してしまい、印刷ズレや表紙崩れで差し戻しになるケースです。
出版前に必ずKDPのプレビューで仕上がりをチェックしましょう。
一見地味な作業ですが、最終的な見栄えや審査スピードに大きく関わる部分です。
ノート出版は、慣れれば1冊あたり数時間で作業できます。
しかし、最初はこの基本手順を丁寧に踏むことで、無駄な差し戻しや修正を防ぐことができます。
ノート出版で失敗しないためのチェックリストとまとめ
ここまで解説してきたように、ノート出版は「低コンテンツだから簡単」というイメージとは裏腹に、事前のルール理解と基本設計を間違えると、審査で落ちる・販売停止になるといったトラブルにつながりやすいジャンルです。
最後に、出版前に確認しておきたいKDPの規約と注意点を振り返りつつ、電子と紙の違いをしっかり理解してから進めることの重要性をまとめます。
出版前に確認すべきKDP規約と注意点の振り返り
ノート出版で一番大切なのは、KDPの公式ガイドラインを正しく理解しておくことです。
電子書籍では、読者が書き込むことを主な目的とした本(例:日記帳・ワークブック・塗り絵・パズルなど)は対象外と明記されています。
これを知らずに電子書籍で申請すると、ほぼ確実に審査で却下されます。
ペーパーバックで出版する場合も、いくつかの要件があります。
たとえば、ページ数は最低24ページ以上、登録時には「低コンテンツ本」にチェックを入れること、余白・罫線・レイアウトが印刷用に整っていることなどです。
これらを守っていないと、審査段階で修正を求められたり、販売後にクレームが入ることもあります。
私も最初のころ、プレビューを確認せずに申請してしまい、印刷ズレで差し戻しになった経験があります。
特にノートは罫線やチェックリストなど、同じページの繰り返しが多いため、1ページのズレが全体に影響することがあります。
申請前にプレビューで印刷イメージを必ず確認することは、初心者が見落としがちな重要ポイントです。
電子と紙の違いを理解してから出版することが成功の鍵
ノート出版では、「電子と紙の違い」をきちんと理解して進めることが成功への第一歩です。
電子書籍は「読む」ことが前提なので、罫線や空白を多用するノート形式には不向きです。
一方、ペーパーバックは「書き込む」ことを前提にしているため、ノートや日記帳などに適しています。
KDPの公式でも、この区別は明確に示されていますが、実務では「電子でも通るのでは?」と勘違いして申請し、時間をムダにする人が少なくありません。
私も初めてノートを出したときは、電子で出してから「これはNGです」と差し戻されました。
その後、紙で出し直したらスムーズに通過したので、最初から紙で進めていれば…と少し悔やんだ記憶があります。
最初の段階で電子と紙の性質を理解し、正しい形式を選ぶことが、無駄なやり直しを防ぐ一番の近道です。
特に初心者のうちは、手順を一度体系的に覚えておくと、2冊目・3冊目の制作が格段に早くなります。
以上のポイントを踏まえて出版準備を進めれば、ノート出版での大きな失敗はかなり防げます。
KDPのルールに沿って、丁寧に作業を進めていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。