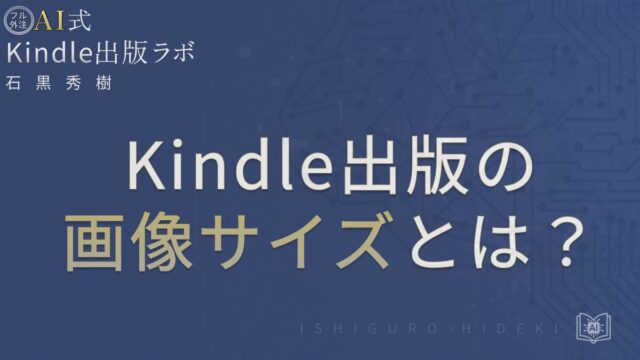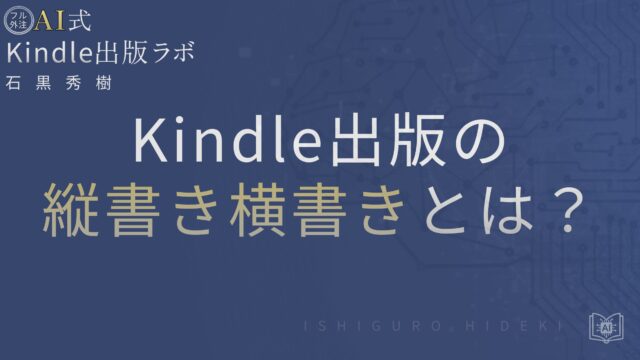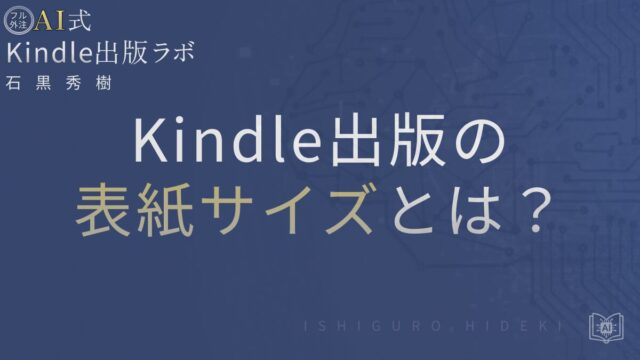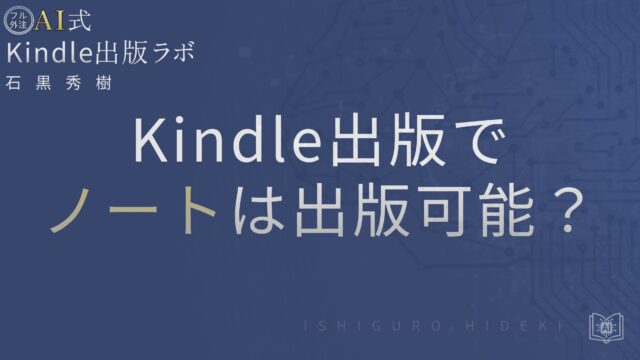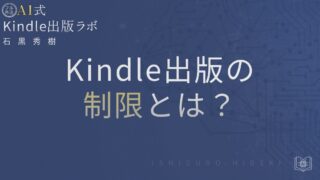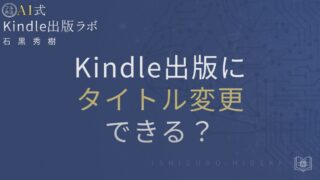Kindle出版におすすめのソフトとは?初心者でも崩れない原稿づくりを徹底解説
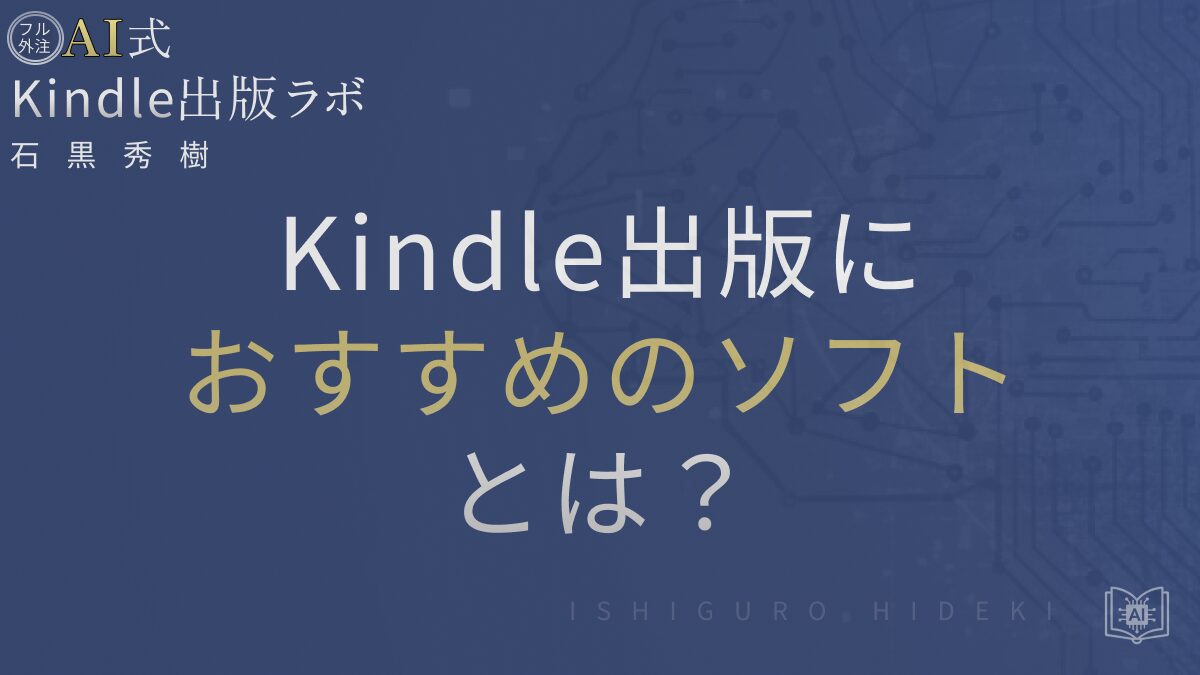
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めようと思ったとき、最初に迷うのが「どのソフトを使えばいいのか?」という点です。
原稿を書くだけならWordでも十分に見えますが、いざKDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)にアップロードしてみると、行間が崩れたり、目次が反映されなかったりといったトラブルが起こりがちです。
この記事では、Kindle出版に必要なソフトの基本と、Amazon公式が推奨するツールの使い分けを中心に解説します。
初心者でも迷わずに出版準備を進められるよう、実際の作業経験をもとにした注意点やコツも交えて紹介します。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版に必要なソフトとは?初心者が最初に知るべき基本
目次
Kindle出版は「原稿を作る」「体裁を整える」「最終チェックをする」という3つの段階に分かれます。
それぞれに適したソフトを選ぶことで、仕上がりの品質が大きく変わります。
特に電子書籍は紙の本と違い、読者が使う端末(スマホ・タブレット・Kindle端末)によって表示が変わるため、見た目を整えるソフト選びがとても重要です。
ここではまず、「Kindle出版で必要なソフトとは何か?」という基本を整理しましょう。
執筆ツール全体の比較や入稿までの具体的な流れをざっくり把握したい方は『Kindle出版は何で書く?おすすめ執筆ツールと入稿手順を徹底解説』もあわせて読んでおくと、今回の記事の位置づけがより分かりやすくなります。
Kindle出版ソフトとは何か?目的と役割を簡単に解説
Kindle出版における「ソフト」とは、単に文章を書くためのツールではありません。
原稿作成・フォーマット整形・プレビュー確認といった出版工程全体をサポートするものを指します。
つまり、文章を作るだけでなく、KDPに適したデータ形式へ整えることが目的です。
具体的には、以下のような段階でソフトが使われます。
* **原稿作成**:WordやGoogleドキュメントなど、書くためのソフト
* **体裁調整**:Kindle Createなど、KDP形式に合わせるためのソフト
* **表示確認**:Kindle Previewerなど、最終チェック用ソフト
この3つを理解しておくと、どこで何を使うべきか迷いません。
なお、公式ヘルプによると、KDPがサポートしている主なファイル形式は「Word(.doc/.docx)」「EPUB」「KPF(Kindle Create形式)」です。
特に日本語の縦書きやルビを扱う場合は、KPF形式が安定しており、Amazon自身も推奨しています(詳細はKDP公式ヘルプ要確認)。
Amazon公式が推奨する無料ツール「Kindle Create」とは
Kindle CreateはAmazon公式の電子書籍編集ツールの一つです。KPF出力に強みがあります。
無料で利用でき、Wordなどで作成した原稿を取り込んで、KDPで読みやすいレイアウトに整えることができます。
特に便利なのが、**見出しや目次を自動で生成してくれる機能**です。
文章中の「見出しスタイル」を認識して目次に変換してくれるため、初心者でも簡単に本格的な電子書籍を作れます。
さらに、Kindle Createではフォントや段落のスタイルも簡単に変更できます。
紙の書籍のようにページ数を固定する必要がなく、端末サイズに応じて自動調整してくれる点も魅力です。
実際に使ってみると、「Wordのままアップロードしたときのズレ」が驚くほど解消されます。
経験的にも、Word+Kindle Create+Previewerの3点セットが最も安定して仕上がる組み合わせです。
ただし、縦書きや画像中心の本では一部レイアウトが崩れる場合があるため、その場合はPreviewerでの確認を必ず行いましょう。
Word・Googleドキュメント・Pagesなど他ソフトとの違い
WordやGoogleドキュメント、Pagesは「原稿を書く」ためには十分ですが、「出版用に整える」機能は限られています。
特に日本語の縦書きやルビ表示は、Kindle端末で正しく反映されないことがあります。
Wordの場合、構成見出しを使えば目次データが生成されますが、段落間の余白や画像位置がKDP上でずれることも多いです。
Googleドキュメントはオンラインで手軽に書ける一方、EPUB出力の整合性が不安定で、改ページが意図通りにならないケースもあります。
Pages(Mac向け)はデザイン性が高いですが、KDPとの互換性には注意が必要です。
そのため、これらのソフトは「原稿作成用」として使い、最終的な整形はKindle Createに任せるのが実務的な流れです。
Kindle Createで開けば自動的にKPF形式が生成されるため、データの整合性が保たれ、出版後のトラブルも減らせます。
経験上も、最初からすべてを完璧に整えようとするより、まずは「原稿→Kindle Create→Previewer」という最短ルートを意識した方が、仕上がりも安定します。
Kindle出版に使える主要ソフト比較:無料と有料の選び方
Kindle出版を始める際、まず悩むのが「どのソフトを使えば失敗しないか」という点です。
公式でもさまざまな形式がサポートされていますが、実際の作業では無料ソフトだけでも十分対応できます。
ただし、用途や目的によっては有料ソフトの方が適している場合もあります。
ここでは、無料ソフト・有料ソフトそれぞれの特徴と、電子書籍とペーパーバックの違いによる最適な選び方を、実体験を交えて解説します。
無料で使える代表的ソフト3選(Word/Googleドキュメント/Kindle Create)
無料で使えるソフトの中では、Word・Googleドキュメント・Kindle Createの3つが定番です。
それぞれの役割と強みを理解しておくことで、スムーズに出版まで進められます。
まず、Wordは最も多くの著者が利用しています。
レイアウトや段落設定が細かく調整でき、見出しを設定しておけば自動で目次も作成可能です。
ただし、WordファイルをそのままKDPにアップすると、行間や改ページのずれが発生するケースがあります。
実際に私も最初の出版時にこのミスを経験し、プレビュー画面で表示が崩れてやり直しになりました。
そのため、Wordは「原稿を作る」ためのソフトと割り切り、最終的な整形はKindle Createに任せるのが安全です。
次に、Googleドキュメントはクラウド上で作業できるのが魅力です。
チームや外注ライターと共同で原稿を作る場合に非常に便利です。
ただし、EPUB形式への変換に対応しているものの、フォントや改ページの再現性は低く、Kindle端末上での見え方が安定しません。
編集履歴を残したいときや、軽い下書き段階で使うのに向いています。
最後に、Kindle CreateはAmazon公式の無料ソフトで、KDP形式(KPFファイル)を簡単に作成できます。
Wordなどで作成した原稿を読み込み、フォーマットを自動で整えてくれるため、初心者でも本格的な電子書籍を作成可能です。
特に、見出し・目次の自動生成機能や端末別プレビュー機能が優秀です。
私自身もKindle Createを導入してから、出版作業の効率が格段に上がりました。
結果的に、「Wordで原稿→Kindle Createで整形→Previewerで最終確認」の流れが最も安定しています。
実際にGoogleドキュメントだけで原稿作成から入稿まで進めたい場合は『GoogleドキュメントでKindle出版する方法とは?無料でできる手順と注意点を徹底解説』で具体的な操作手順と注意点をチェックしてみてください。
有料ソフト(InDesignなど)を使うケースと注意点
有料ソフトでは、Adobe InDesignが代表的です。
デザイン性が高く、ページレイアウトを細かく設定できるため、雑誌・写真集・レイアウト重視の書籍に向いています。
特にペーパーバックで美しい余白や画像配置を保ちたい人には有効です。
ただし、InDesignを使うには専門的な知識と時間が必要です。
EPUB出力にも対応していますが、日本語縦書きやルビの設定は環境によって崩れることもあります。
また、ソフト自体のコストが高いため、初出版では費用対効果が合わない場合も多いです。
実務的には、無料ツールで十分に整う原稿を、無理にDTP(デスクトップ出版)環境で作り直す必要はありません。
Kindle Createは公式提供の主要ツールですが、すべてのケースで十分と断定はできません。用途によりEPUB制作や他ソフトが有効な場合もあります(公式ヘルプ要確認)。
もしInDesignを使う場合は、最終確認を必ずKindle Previewerで行うことを忘れないようにしましょう。
電子書籍とペーパーバックで最適ソフトが異なる理由
電子書籍とペーパーバックでは、求められる仕上がりが異なります。
電子書籍は文字サイズや余白が読者側で調整できるため、「流し込み型」のレイアウトになります。
そのため、Kindle Createなどのリフロー型(可変レイアウト)ソフトが最適です。
一方、ペーパーバックは紙のページ構成が固定されるため、デザインの自由度が高い反面、ページ数や余白のバランスを自分で整える必要があります。
この場合、InDesignやCanvaのようなデザインツールを使うと、表紙や章ページを見栄えよく作ることができます。
ただし、KDPではペーパーバックに最低ページ数(24ページ以上)などの条件があるため、制作前に必ず公式ガイドラインを確認しておきましょう。
実際には、多くの著者が電子書籍からスタートし、慣れてからペーパーバックを併売する流れを選んでいます。
まずはKindle CreateとPreviewerを使って電子版を安定させ、その後デザインを加えた紙版を作るのが現実的な進め方です。
この手順なら、制作の手間と品質のバランスを保ちながら出版を継続できます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Kindle Createの使い方と手順:原稿から出版までの流れ
Kindle出版は、「原稿を書いたらすぐアップロードすればいい」という単純な流れではありません。
実際には、見た目の整った本に仕上げるための工程がいくつかあります。
ここでは、Wordで原稿を作ってから、Kindle Createを使い、最終的にKDPで出版するまでの一連の手順を、初心者にもわかりやすく解説します。
実際の作業画面やプレビューの感覚をイメージしながら読むと、理解しやすくなるはずです。
ステップ1:Wordなどで原稿を作成する
まず最初に行うのが、Wordなどで原稿を作成する工程です。
この段階では「読みやすさ」と「構造」を意識して文章をまとめることが大切です。
特に、KDPでは見出しの設定が重要です。
Wordの「見出し1」「見出し2」などのスタイルを使うことで、後のKindle Createで自動的に目次が生成されます。
また、改行や段落の間隔を手動で調整しすぎないよう注意しましょう。
Word上ではきれいに見えても、KDPにアップロードした際に行間がずれたり、余白が不自然になることがあります。
私も最初の頃はスペースや改行を多用してしまい、プレビューで崩れてやり直した経験があります。
公式ヘルプでも推奨されているように、「構造はシンプルに」「見出しスタイルを活用」が基本です。
画像を挿入する場合は、なるべくJPEGまたはPNG形式で、サイズを軽くしておきましょう。
容量が大きいとファイル全体のアップロードに時間がかかるだけでなく、販売ページの表示速度にも影響します。
ステップ2:Kindle Createでフォーマットを整える(KPF形式)
Wordで原稿を書き終えたら、次はKindle Createで体裁を整えます。
このソフトはAmazonが公式に提供しており、Wordファイルをドラッグ&ドロップで読み込むだけで、電子書籍向けのレイアウトに自動変換してくれます。
読み込みが完了すると、見出しを検出して自動的に目次を作成してくれます。
また、章ごとのレイアウトやフォント、余白などをテンプレートから選ぶだけで整えられるため、初心者でも安心です。
私自身も初出版のときはこの機能に助けられました。
Wordで調整していた細かなズレが一気に整い、まるで書籍のような仕上がりになったのを覚えています。
仕上がったデータは、Kindle Create専用形式「KPFファイル」として保存します。
この形式はKDPに直接アップロードでき、文字の崩れが少なく、端末サイズにも柔軟に対応してくれます。
特に日本語の縦書きやルビを扱う場合は、EPUBよりKPF形式の方が安定する傾向があります。
ただし、画像が多いレイアウトや複雑な段組みを使う場合は、Previewerで事前に必ず確認しておきましょう。
ステップ3:Kindle Previewerで表示を最終チェック
次のステップは、Kindle Previewerによる最終確認です。
これは、Kindle Createで作成したKPFファイルを実際の端末上でどのように表示されるかを確認するためのツールです。
公式から無料でダウンロードできます。
チェックでは、以下の3点を重点的に確認してください。
1. 章タイトルや目次リンクが正しく動作しているか
2. 行間・改ページが不自然になっていないか
3. 画像サイズや余白が端末ごとにずれていないか
特に「スマートフォン」「タブレット」「Kindle端末」など、画面サイズが異なる3種類のプレビューを確認しておくと安心です。
ここで問題が見つかっても、Kindle Createに戻って修正できるため、焦らず何度か確認を繰り返しましょう。
経験上、Previewerを省略すると、後から「行間が詰まりすぎて読みにくい」といったレビューがつくこともあります。
見た目の最終チェックは、出版品質を左右する大切な工程です。
Kindle Previewerのインストール方法や端末別チェックの具体的な手順は『Kindle出版のプレビュー確認とは?オンラインとPreviewerの使い方を徹底解説』でまとめているので、初めてプレビュー作業をする前に一読しておくと安心です。
ステップ4:KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)にアップロード
最終チェックが終わったら、いよいよ出版手続きです。
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)のサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
「本棚」画面から「電子書籍またはペーパーバックを作成」を選択し、タイトル・著者名・説明文などの基本情報を入力します。
次に、「コンテンツ」タブでKindle Createで作成したKPFファイルをアップロードします。
アップロード後、KDP上でもプレビュー確認ができるので、もう一度レイアウトを最終確認しておきましょう。
その後、「価格設定」画面で販売価格と印税率(通常は35%または70%)を選択します。
出版ボタンを押せば、通常は72時間以内にAmazonストアに反映されます。
最初の出版では緊張するかもしれませんが、一度流れを体験すれば2冊目以降は驚くほどスムーズです。
なお、KDPは自動で国別ストアにも配信されるため、特別な申請は不要です。
ただし、米国KDP仕様とは一部異なるため、Amazon.co.jpのヘルプを基準に確認しておくと安心です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
Kindle出版ソフトを選ぶときの注意点とよくある失敗例
Kindle出版では、どんなに内容が良くても、レイアウトが崩れてしまうと読者の印象は大きく下がります。
特に、WordファイルをそのままKDPにアップロードした場合や、画像を多く使う作品では、思わぬ形で見た目が変わることがあります。
ここでは、Kindle出版の現場で起きやすい3つの失敗例とその対処法を、実際の経験をもとにわかりやすく解説します。
「なぜそうなるのか」「どうすれば防げるのか」を知っておくだけで、出版の仕上がりは格段に安定します。
Wordファイルをそのままアップして行間が崩れる原因
Wordで原稿を作成すると、見た目が整っているように感じますが、そのままKDPにアップロードすると行間や段落が崩れることがあります。
原因は、Wordがもともと「紙印刷用」に最適化されていることにあります。
つまり、フォントサイズ・余白・段落設定などが固定値で作られているため、Kindleのような「リフロー(可変)型」の画面では再現されにくいのです。
実際、私が初めて出版した際も、本文の途中で不自然な改ページが入ったり、行間が詰まりすぎたりする現象がありました。
Word(.docx)アップロードもKDPでサポートされています。実務上はKPFで安定しやすい傾向があるため、KPFを推奨としつつ公式ヘルプ要確認としてください。
KPF形式は、端末サイズに合わせて自動調整されるため、レイアウト崩れのリスクを大幅に減らせます。
また、Wordで段落間に「空白行(Enter)」を連続で入れるのも避けましょう。
余白を調整したい場合は、段落設定から「段落後の余白」を設定する方が安定します。
行間ズレやレイアウト崩れを防ぐ具体的なWordの設定方法については『Kindle出版のWord設定とは?崩れない電子書籍の作り方を徹底解説』で画面イメージ付きで詳しく解説しています。
目次や改ページがうまく反映されないときの対処法
次によくあるトラブルが、目次や改ページが正しく反映されないケースです。
これは、Wordの「見出しスタイル」が適切に設定されていないことが主な原因です。
KDPは文章中の「見出し1」「見出し2」などを自動的に検出して目次を作ります。
そのため、単に太字や大きな文字にするだけでは、見出しとして認識されません。
正しい設定を行えば、Kindle Create上で自動的に目次リンクが生成され、読者がスムーズに章を移動できるようになります。
逆に設定を誤ると、目次が空欄になったり、リンクが機能しなかったりします。
また、改ページを入れたいときに「Enterキー連打」で空白を作るのも避けましょう。
公式ガイドにもある通り、「改ページ挿入(Ctrl+Enter)」を使用するのが正しい方法です。
私自身も初期の出版で「目次がすべて同じページにリンクしてしまう」というミスを経験しました。
原因は、見出しスタイルの階層が混ざっていたことです。
こうした細かい部分も、Kindle Createでプレビューを確認すれば事前に修正できます。
時間をかけてでもこの段階でチェックしておくと、後のトラブルを防げます。
画像が多い作品(イラスト・写真集など)で気をつける設定
画像中心の作品では、文字中心の本とは異なる注意が必要です。
特に、解像度とファイルサイズのバランスを取ることが重要です。
高画質のまま挿入するとファイル容量が大きくなり、KDPアップロード時にエラーが出ることがあります。
逆に圧縮しすぎると、読者の端末で画像がぼやけてしまいます。
画像は長辺ピクセル数などの要件が中心です。印刷向けの解像度と混同せず、最新の推奨値は公式ヘルプ要確認と明示してください。
また、画像はテキストの背面ではなく、インライン(本文と同じ段に配置)で挿入するのが基本です。
これを守らないと、Kindle端末によっては画像がページの途中で切れることがあります。
私が写真集を出したときも、最初は見開きの左右で画像がズレてしまいました。
原因はWordの自動配置設定が「上下中央」になっていたためでした。
画像配置は「段落に合わせる」または「インライン」に設定するのが安全です。
さらに、画像中心の作品では「固定レイアウト」に対応したテンプレートを使うと、表示崩れを防げます。
画像やレイアウトにこだわるほど、端末による違いが顕著に出ます。
そのため、最終的にはKindle Previewerで複数デバイスの表示を確認し、必要に応じて調整を繰り返すのが確実です。
見た目が整った作品は、それだけで読者の信頼度を高める大切な要素になります。
Kindle出版ソフトのおすすめ組み合わせと活用事例
Kindle出版において「どのソフトを使うか」は、作業効率だけでなく完成度にも大きく影響します。
実際に私自身、いくつかの組み合わせを試してみて、「安定して失敗しにくい構成」と「デザインにこだわりたい人向けの構成」は明確に違うと感じました。
ここでは、目的に合わせたおすすめソフトの組み合わせと、成功例から学べる使い方を紹介します。
初心者におすすめ:Word+Kindle Create+Previewerの3点セット
初めてKindle出版に挑戦する人には、「Word+Kindle Create+Kindle Previewer」の3点セットがおすすめです。
この組み合わせは、無料で導入できるうえに、Amazon公式のサポート範囲内で安定して動作します。
Wordで文章を作成し、見出しや段落を整理したら、Kindle Createで体裁を整えます。
Createを使うことで、見出しをもとに自動的に目次が生成され、レイアウトも電子書籍用に最適化されます。
最後にPreviewerで端末別の見え方を確認すれば、基本的なトラブルはほぼ防げます。
この流れを確立しておくと、執筆→整形→確認→出版という一連の作業を迷わず進められます。
私が講座で指導した受講者の多くも、最初の1冊はこの方法でスムーズに出版しています。
「公式ツールで整える」ことが、最も確実な成功ルートです。
デザイン重視の方向け:CanvaやInDesignの併用方法
一方で、表紙やページデザインにもこだわりたい方は、CanvaやInDesignの併用がおすすめです。
Canvaは無料でも使いやすく、Kindle書籍の表紙テンプレートも豊富に揃っています。
KDP公式のサイズガイドに沿って作成すれば、そのままアップロード可能です。
InDesignは有料ですが、文字組みや余白設定を細かく調整したい方に向いています。
特にイラスト集やビジュアルブックなど、見た目の統一感が重要な作品で力を発揮します。
ただし、InDesignから直接KDPにアップロードするのではなく、一度EPUB形式に書き出してからPreviewerでチェックすることを忘れないでください。
実際、私が過去にデザイン重視の書籍を手掛けた際も、InDesignで細部を整えた後、Kindle Createで最終調整を行いました。
見た目と機能性の両立を図るなら、「デザインは外部ツール」「最終整形はKindle Create」と役割を分けるのが現実的です。
実際の出版事例に学ぶフォーマット成功パターン
成功している著者ほど、ソフトの選び方がシンプルです。
例えば、自己啓発書やエッセイなど文章中心の作品は、「Word+Kindle Create」で十分完成度が高くなります。
一方、イラストや写真が多い作品では、「Canvaで画像調整→CreateでKPF出力→Previewer確認」という流れが鉄板です。
実務的なポイントは、「どの工程で何を調整するか」を明確に分けることです。
最初からすべての要素を1つのソフトで完結させようとすると、表示崩れの原因になります。
経験的にも、原稿作成→デザイン調整→プレビュー確認の3ステップに分けることで、制作トラブルを最小限にできます。
この考え方は、どんなジャンルのKindle本にも共通しています。
まとめ:Kindle出版は「ソフト選び」で8割決まる
Kindle出版を成功させるためには、文章力やデザイン力だけでなく、どのソフトを使うかの選択が重要です。
ここまで紹介してきた通り、無料ツールでも十分に高品質な作品を作ることが可能です。
むしろ、操作に慣れたソフトで進める方が、完成までのスピードも上がります。
最初にKindle Createを選ぶ理由と安心感
Kindle Createは、Amazonが公式に提供している唯一の電子書籍編集ソフトです。
対応形式のKPFファイルはKDPに最も最適化されており、文字化けやレイアウト崩れが起きにくいのが特徴です。
また、テンプレートが豊富で、専門知識がなくても書籍らしい見た目に仕上げられます。
初心者の方にとっては、これ以上心強いツールはありません。
私自身、初期の出版で他ソフトを試した際は何度もレイアウトの修正に追われましたが、Createを使い始めてからはその手間がほぼなくなりました。
「シンプルで崩れにくい」それがKindle Create最大の魅力です。
電子書籍出版を成功させる3つのポイント
電子書籍を安定して出版するためのポイントは、次の3つです。
1つ目は、ソフトの役割を正しく分けること。
Wordは執筆、Createは整形、Previewerは確認、と工程ごとに使い分けましょう。
2つ目は、プレビュー確認を怠らないこと。
端末別に表示を確認し、文字ズレや改ページの乱れを必ずチェックします。
3つ目は、更新作業を恐れないこと。
KDPでは出版後でも内容を修正・再アップロードが可能です。
初回から完璧を目指すより、改善を前提に進める方が結果的に質が高まります。
私も1冊目の出版後に誤字や行間ズレを修正しましたが、読者の反応が格段に良くなりました。
「出して終わり」ではなく、「更新を続ける姿勢」が信頼を生みます。
ペーパーバック出版を考える場合の補足(24ページ以上の仕様)
ペーパーバック出版を考えている方は、電子書籍とは少し異なるルールに注意が必要です。
KDPでは、ペーパーバック版は24ページ以上でないと出版できません。
また、固定レイアウトで作成するため、電子書籍よりもページ構成や余白の扱いがシビアです。
そのため、InDesignやCanvaなど、紙向けデザインに強いツールを併用すると良いでしょう。
ペーパーバックはKDPの印刷プレビュー(Print Previewer)で全ページを確認してください。電子書籍はKindle Previewerを使います。
特に印刷用PDFでは、表紙サイズや裁ち落とし部分の設定が異なるため、公式テンプレートを必ず参照するようにしましょう。
ペーパーバックを出すと、作品に「実物感」が加わり、読者の信頼にもつながります。
電子書籍に慣れたら、次のステップとして挑戦してみる価値は十分にあります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。