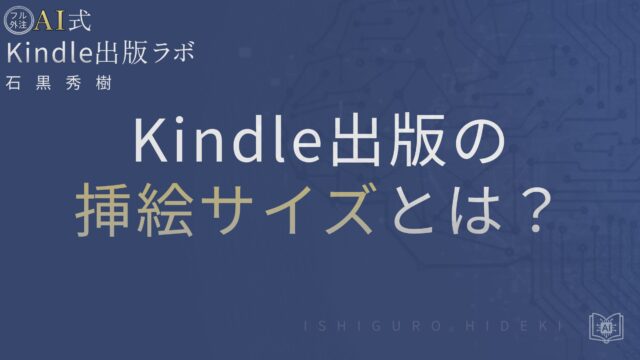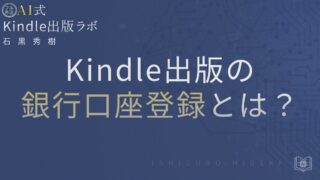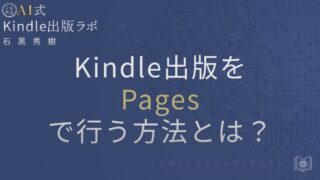Kindle出版はWord以外でもできる?対応形式とおすすめツールを徹底解説
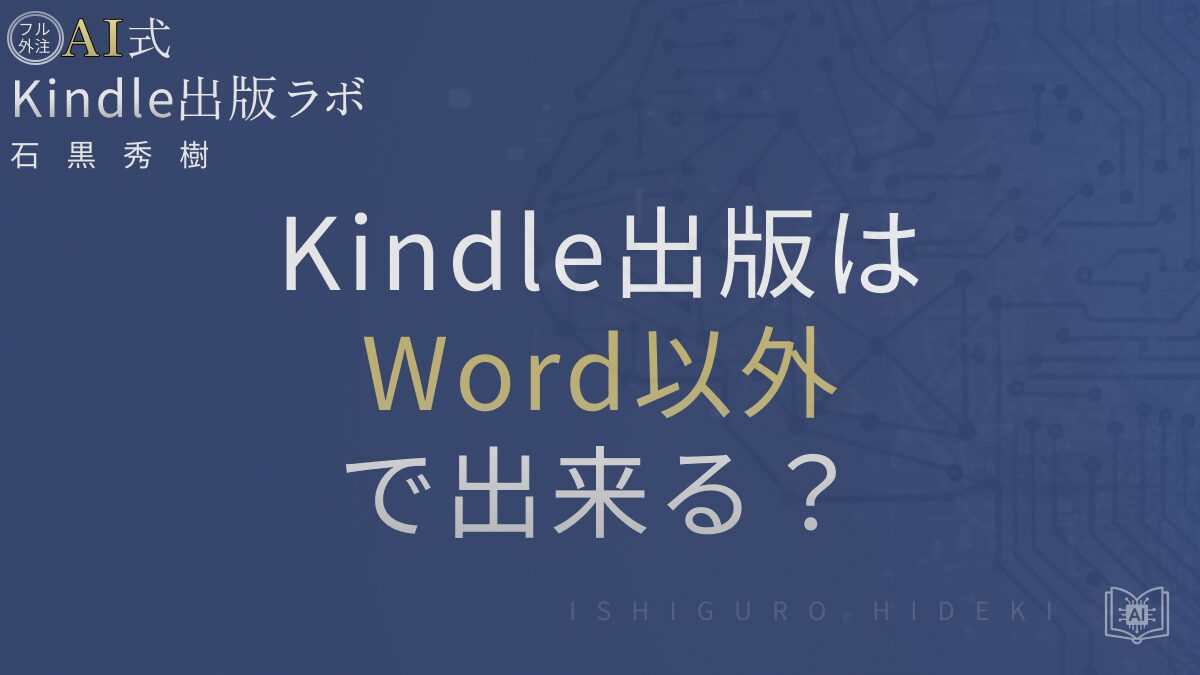
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めたいけれど、「Wordがないとできないの?」と悩む方は意外と多いです。
実はWord以外でも問題なく出版できます。
KDP(Kindle Direct Publishing)は、EPUB・DOCX・KPFなど複数の形式に対応しており、GoogleドキュメントやApple Pagesなどの無料ツールでも出版可能です。
この記事では、「Wordを持っていない人」や「別ツールで作業したい人」に向けて、対応環境やメリットをわかりやすく紹介します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で「Word以外」を使いたい人が増えている理由
目次
近年、Kindle出版のハードルはどんどん下がっています。
以前は「Wordで原稿を作るのが当たり前」とされていましたが、今では無料のクラウドツールでも問題なく出版が可能です。
ここでは、Word以外を使う人が増えている背景を、実際の体験を交えながら解説します。
Wordがなくても出版できるの?初心者が最初に迷うポイント
Kindle出版を調べていると、多くの解説記事や教材で「Word形式(.docx)で原稿を作る」と書かれています。
そのため、「Wordがないと出版できない」と誤解してしまう人が少なくありません。
しかし実際のところ、KDPはWord専用ではなく、複数のファイル形式をサポートしています。
EPUB(電子書籍用の標準形式)や、KDP公式ツール「Kindle Create」で作成するKPF形式なども使用できます。
筆者も最初はWordで原稿を作っていましたが、Macに乗り換えた際にPagesやGoogleドキュメントを試したところ、ほぼ同じ手順で出版できました。
Wordがなくても、レイアウトや見出し構成を整えればKDPの審査は問題なく通ります。
Word以外のツールを使うメリット:コスト・環境・操作性
Wordを使わない最大の理由は、コストと操作環境にあります。
Microsoft 365のサブスクリプションは年額費用がかかるため、Kindle出版を試してみたい初心者には少しハードルが高く感じられます。
一方、GoogleドキュメントやApple Pagesなら無料で使え、クラウド上でデータを管理できるため、パソコンが変わっても作業を続けられます。
また、Googleドキュメントは自動保存機能があるため、突然のフリーズや電源トラブルにも強いのが魅力です。
筆者も、長文の原稿を書いている途中にWordが強制終了してデータが飛んだ経験があるため、今はほぼGoogleドキュメント一択です。
さらに、オンライン共有がしやすいため、校正や編集の依頼を外注する際にも便利です。
KDPにアップロードする前に共同編集者がチェックできるので、作業効率がぐっと上がります。
Windows以外(Mac・Chromebook・iPad)でも対応可能な現状
Kindle出版が広がったもう一つの理由は、Windows以外のデバイスでも出版作業が完結できるようになったことです。
Macでは標準アプリ「Pages」でEPUB形式を書き出せますし、ChromebookでもGoogleドキュメントを使えば同様のことが可能です。
iPadでも外付けキーボードとGoogleドキュメントがあれば、原稿の執筆・修正・入稿まで一通りの作業が行えます。
KDPの管理画面もブラウザで動作するため、デバイスの違いによる不具合はほとんどありません。
ただし、フォントやレイアウトが異なる環境ではプレビュー表示が崩れる場合があります。
筆者の経験では、アップロード前にKDPのプレビュー機能で確認しておくと安心です。
今では、Windowsユーザー以外にも、MacやiPadで出版している人が増えています。
特にテキスト主体の電子書籍なら、Wordにこだわる必要はまったくありません。
Kindle出版でWord以外に使える対応形式とツール
Kindle出版では、Word以外にも対応しているファイル形式が複数あります。
「Wordがないと出版できない」と思われがちですが、実際にはEPUB・DOCX・KPFといった形式で入稿可能です。
さらに、GoogleドキュメントやApple Pagesなどの無料ツールでも原稿を問題なく作成できます。
ここでは、それぞれの形式とツールの特徴、そして実際の作業手順を具体的に解説していきます。
KDPで受け付けられるファイル形式(EPUB・DOCX・KPF)とは
KDP(Kindle Direct Publishing)で主に対応しているのは、EPUB、DOCX、KPFの3種類です。
EPUBは電子書籍の国際標準フォーマットで、Kindle以外のストア(楽天Koboなど)でも使われている形式です。
柔軟にレイアウトが変化する「リフロー型」に対応しており、テキスト主体の本に最適です。
DOCXはWordで作成する標準的なファイル形式です。
KDPが自動で変換してくれるため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。
ただし、Wordがない場合はGoogleドキュメントやPagesでも同形式で書き出せます。
KPFは、KDP公式の無料ソフト「Kindle Create」で作成する専用ファイル形式です。
見出し・目次・レイアウトを整えやすく、完成度の高い仕上がりになります。
特に挿絵やレイアウトを重視したい人にはおすすめです。
なお、旧形式であるMOBIはすでに非推奨となっています(公式ヘルプでも告知済み)。
過去の情報を参考にする際は注意が必要です。
KDPが対応している形式の全体像やそれぞれの違いを整理したい場合は、『Kindle出版のファイル形式とは?EPUB推奨の理由と選び方を徹底解説』もあわせてチェックしておくと判断しやすくなります。
GoogleドキュメントでのKindle原稿作成と出力方法
Googleドキュメントは、無料で使えるクラウドベースのワープロツールです。
ブラウザ上で作業でき、保存や共有も自動で行われるため、データ消失のリスクが少ないのが大きな利点です。
Kindle出版用の原稿を作る場合、まずは「タイトル」「見出し(h1〜h3)」「本文」「改ページ」などを適切に構成します。
その後、「ファイル」→「ダウンロード」→「EPUB出版物(.epub)」を選択するだけで書き出せます。
KDPにそのままアップロードしても問題ありませんが、プレビューでレイアウトが崩れていないか必ず確認しましょう。
特に、箇条書きや改ページ位置が意図しない形で反映されることがあります。
筆者の経験では、段落間に1行空けるなど、シンプルな構成を心がけると審査通過率が安定します。
GoogleドキュメントはWordよりも柔軟性に欠けますが、シンプルな原稿には最適な選択肢です。
実際の画面手順や設定方法を詳しく知りたい方は、『GoogleドキュメントでKindle出版する方法とは?無料でできる手順と注意点を徹底解説』を見ながら進めるとスムーズです。
Apple Pagesを使ったEPUB書き出し手順と注意点
Apple Pagesは、MacやiPadに標準搭載されている文書作成ツールです。
Wordのような機能を備えつつ、EPUB形式で直接書き出せるのが大きな強みです。
書き出し方法は簡単で、「ファイル」→「書き出す」→「EPUB」を選択し、タイトルや著者名を入力するだけです。
フォントや余白設定も自動で最適化されるため、初心者でも安心して使えます。
ただし、装飾を多用しすぎると、Kindle端末でレイアウトが崩れることがあります。
特に、独自フォントやテキストボックスを多用したデザインは避けた方が安全です。
筆者は以前、Pagesの独自フォントを使ってKDPにアップロードしたところ、プレビューで文字化けが発生しました。
この経験から、フォントは標準の「ヒラギノ」「Times New Roman」などを使うことをおすすめします。
MacユーザーでPagesをメインに使いたい場合は、『Kindle出版をPagesで行う方法とは?Macユーザー向け徹底ガイド』でEPUB書き出しから入稿までの流れを一通り確認しておくと安心です。
Kindle Createを使ったKPFファイル作成の流れ
Kindle Createは、Amazon公式が提供する無料の編集ソフトです。
KDP用に最適化されたKPFファイルを簡単に作成できるため、より完成度の高い書籍に仕上げたい人に向いています。
使い方は、まずWordまたはEPUBで作成した原稿をインポートし、見出しスタイルを設定します。
次に、目次や章タイトル、表紙画像などを追加し、プレビューで体裁を確認します。
完成したら「ファイル」→「エクスポート」→「KPFとして保存」を選択し、KDPにアップロードします。
特に見出しスタイルを正しく設定しておくと、Kindle端末で自動的に目次が作成される点が便利です。
Kindle Createは一見複雑に見えますが、テンプレートに沿って操作すれば初心者でも数時間で慣れます。
筆者も最初の出版で使用しましたが、想像以上に手軽でした。
Scrivener・Markdownなど執筆ツールとの連携方法
ScrivenerやMarkdownエディタを使う著者も増えています。
これらは、長文を章ごとに整理できるため、執筆効率が高いのが特徴です。
Scrivenerでは、完成した原稿を「EPUB」や「DOCX」でエクスポートできます。
Markdownの場合は、無料ツール「Pandoc」などを使ってEPUBに変換可能です。
ただし、ツールによっては日本語の改行処理やルビ表記に対応していないこともあります。
特にMarkdownはテキストベースのため、改ページ位置や見出し設定を慎重に確認する必要があります。
筆者の感覚としては、Scrivenerは構成重視、Markdownはシンプルな文章重視と考えると選びやすいです。
最終的にはKDPが読み込める形式(EPUB・DOCX・KPF)で出力できれば問題ありません。
Kindle出版では、必ずしもWordに依存する必要はありません。
自分の作業スタイルやデバイス環境に合ったツールを選ぶことで、より快適に出版作業を進められます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Word以外の形式を使う際の注意点と落とし穴
Word以外のツールや形式を使うときは、自由度が高い反面、いくつかの落とし穴があります。
特にEPUBやPDFなどの形式は、見た目が綺麗でもKindle端末上で崩れることがあるため注意が必要です。
ここでは、実際によくあるトラブルやその回避方法を、実務の視点からまとめました。
MOBIやPDF形式が非推奨・限定利用とされる理由
以前はKindleといえば「MOBI形式」が定番でしたが、現在はKDPでのMOBI入稿は非推奨となっています。
理由は、Kindleの新しい端末やアプリではEPUB・KPF形式が主流になり、MOBIでは表示が崩れることがあるためです。
PDFも同様に扱いが限定的です。
PDFはレイアウトが固定されるため、スマホやタブレットなど画面サイズが異なる端末では文字が小さく読みにくくなります。
特にリフロー型(自動的に文字が流れる形式)の書籍を想定している場合、PDFでは読みづらくなる傾向があります。
「PDFは固定レイアウト用途に限られる場面が多く、リフロー型では制約が大きいと案内されています(公式ヘルプ要確認)。断定的な“推奨しない”表現は避けます。」
実務上も、PDFでアップロードした原稿はプレビューで崩れる確率が高く、筆者も最初の出版時にこの落とし穴にハマりました。
EPUB出力時によくあるレイアウト崩れと対処法
EPUBはKindle出版の標準的な形式ですが、出力時にレイアウトが崩れるケースがあります。
特に多いのが「余分な改行」「文字サイズのバラつき」「見出しが認識されない」といった問題です。
これらの原因は、執筆ツール(GoogleドキュメントやPagesなど)によって自動で挿入される隠しタグや書式設定にあります。
一見問題なさそうな文書でも、KDPの変換時に意図しないCSS(スタイル情報)が反映されてしまうことがあります。
対策としては、「EPUB出力後にCalibreなどの無料ツールで再確認する」のが有効です。
Calibreでプレビューを確認すれば、行間・段落・フォントのズレを事前に修正できます。
筆者も最初はそのままKDPにアップロードしてしまい、行間が極端に広がる現象が起きました。
それ以来、必ずプレビューで確認してから提出するようにしています。
ファイルサイズや画像圧縮に関するKDPの制限
KDPでは、アップロードできるファイルサイズに制限があります。
1ファイルあたり最大650MBまでと定められており、これを超えるとアップロードエラーになります。
特に注意が必要なのは、画像の多い書籍です。
EPUB形式では画像を埋め込むたびにファイルサイズが大きくなるため、圧縮が不十分だと容量オーバーになりやすくなります。
「画像は表示サイズに合わせて適切なピクセル数を確保しつつ圧縮し、画質は劣化しすぎない品質でJPEG保存を推奨します。解像度基準は端末依存のため一律dpi指定は避け、公式ヘルプ要確認。」
また、KDPは自動で最適化を行うこともありますが、事前に軽量化しておく方が安全です。
筆者の経験では、解像度を落としても表示品質に大きな差はなく、むしろ読み込み速度が改善されました。
特にスマホで閲覧されることが多いジャンルでは、軽さがユーザー体験に直結します。
審査エラーを防ぐためのチェックリスト(公式ヘルプ要確認)
Word以外の形式で入稿する場合、KDPの審査でエラーが出やすい点を把握しておくことが大切です。
以下は筆者の経験と公式ヘルプをもとにしたチェックリストです。
* タイトル・著者名が原稿とKDP登録情報で一致しているか
* 目次リンクが正常に機能しているか
* 表紙画像がKDP推奨サイズ(縦2560px以上)を満たしているか
* EPUBまたはKPFファイルの構造が破損していないか
* 特殊文字(絵文字や全角記号など)が正しく表示されるか
これらを事前に確認しておくと、KDP審査での差し戻しを防げます。
特にタイトルや著者名の不一致はよくあるミスなので、アップロード前に慎重に確認しましょう。
なお、KDPの仕様変更やガイドラインは時期によって更新されることがあります。
疑問点がある場合は、Amazon公式の「KDPヘルプセンター」で最新情報を確認するのが確実です。
Word以外の形式を使うことで、出版環境は広がりますが、その分だけ注意も必要です。
公式ガイドラインと実務上の経験を両立しながら、安定した出版を目指しましょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
実際の出版事例:Wordを使わずにKindle出版した体験談
ここでは、筆者自身や実際の著者仲間が体験した「Wordを使わずに出版した具体例」を紹介します。
無料ツールを上手に組み合わせることで、コストを抑えながらクオリティの高い電子書籍を作ることができます。
「本当にWordなしで大丈夫?」と不安な方も、きっと安心できるはずです。
GoogleドキュメントからEPUB化して出版した実例
筆者が最初にKindle出版したときは、Googleドキュメントだけで原稿を作成しました。
理由はシンプルで、Wordが入っていなかったからです。
Googleドキュメントはクラウド上で作業できるので、パソコンが変わっても続きから作業できるのが強みです。
また、自動保存があるため、作業中にデータが消える心配もありません。
執筆後は「ファイル」→「ダウンロード」→「EPUB出版物(.epub)」で出力。
「KDPにアップロードして審査を通過しましたが、レイアウトは毎回プレビューで検証し、必要なら再調整します(端末差異あり)。」
「見出しスタイルを正しく設定すると目次が生成される場合があります。確実性を高めるにはKindle Create等で目次を再確認・調整してください。」
ただし注意点として、余白や改ページの扱いには少し癖があります。
特に見出しの直後に改行を入れすぎると、EPUB上で余白が不自然に広がることがあります。
筆者はこの点で何度か修正を繰り返しましたが、最終的にはレイアウトの少なさが逆に読みやすさにつながりました。
「Wordがなくても出版できる」ことを実感した瞬間でした。
PagesとKindle Createを併用して表紙や体裁を整えたケース
次に紹介するのは、Macユーザーの著者が実践した方法です。
この方はApple純正アプリの「Pages」で原稿を書き、EPUB形式で書き出したあと、Kindle Createで仕上げを行いました。
Pagesはフォントや段落スタイルが美しく、Mac標準搭載なのでコストもかかりません。
しかも「EPUBとして書き出す」機能が標準で備わっているため、特別なソフトを入れる必要もありません。
「その後、Kindle CreateにはDOCX(または対象PDF)をインポートし、見出しや目次を整えました。EPUBは直接インポート非対応です(公式ヘルプ要確認)。」
Kindle Createでは表紙も簡単に設定できるため、Canvaなどで作った画像を挿入するだけで完成度が上がります。
このケースでは、Wordを使うよりもむしろ作業がスムーズでした。
Pagesの段階で整っていた書式がそのまま反映され、KDPのプレビューでも崩れはほとんど見られませんでした。
ただし、Pages特有の「余白が狭くなる」仕様に注意が必要で、本文が詰まって見えることがありました。
筆者もPagesを使う際は、章ごとに改ページを入れるよう意識しています。
Wordを使わないことで作業効率が上がった実感と注意点
Wordを使わずに出版作業を行う最大のメリットは、無駄な設定やファイル管理に時間を取られないことです。
GoogleドキュメントやPagesは自動保存・共有機能が充実しており、外出先でもスマホやタブレットで原稿を修正できます。
筆者の場合、以前はWordファイルをUSBに保存して持ち運んでいましたが、現在はすべてGoogle Drive上で完結しています。
クラウドベースに変えたことで、「ファイルが見つからない」「バックアップを取り忘れた」といった小さなストレスがなくなりました。
一方で、注意すべき点もあります。
GoogleドキュメントやPagesは便利な反面、見た目を整える装飾機能が限られています。
特に「目次リンク」や「脚注」などはWordほど細かく制御できないため、最終確認はKindle CreateやCalibreで行うのが安心です。
つまり、Wordを使わなくても出版はできますが、「シンプルさ」と「確認の丁寧さ」がポイントになります。
筆者自身、複雑なレイアウトを避け、あえて余白を活かしたデザインにしたところ、読者レビューで「読みやすい」と評価されました。
Word以外のツールでも、丁寧に仕上げれば十分に高品質な書籍を作ることが可能です。
自分に合った執筆環境やツール選びをもっと具体的に知りたい方は、『Kindle出版におすすめのソフトとは?初心者でも崩れない原稿づくりを徹底解説』も参考にしながら環境を整えてみてください。
まとめ:Word以外でも安心して出版できる環境を整えよう
Kindle出版は、もはやWordが必須の時代ではありません。
Googleドキュメント、Apple Pages、Kindle Createなど、無料または低コストのツールで十分に出版できます。
特に最近は、クラウド環境で作業できるツールが増えており、パソコンにソフトをインストールする必要すらありません。
これにより、Windows・Mac・iPad・Chromebookなど、どのデバイスでも出版が可能になっています。
大切なのは、「自分に合った作業環境を整えること」です。
使いやすいツールを選び、KDPのガイドラインを守りながら、少しずつ慣れていけば大丈夫です。
最初は不安でも、Word以外の方法を一度経験すれば、その手軽さと自由度に驚くはずです。
一歩ずつ準備を整えて、自分らしい本を安心して届けていきましょう。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。