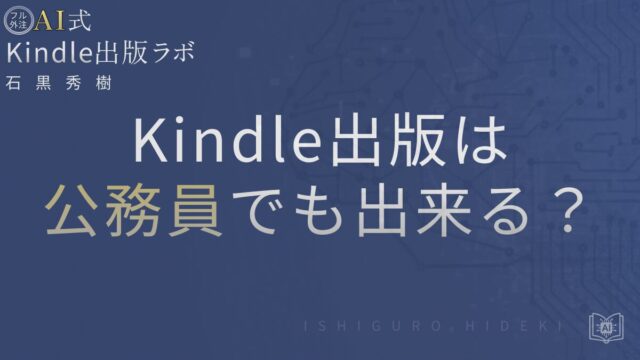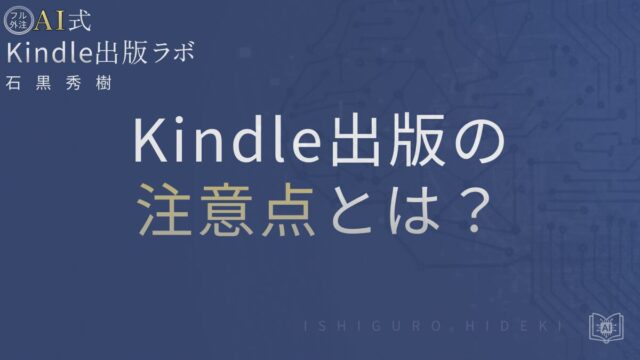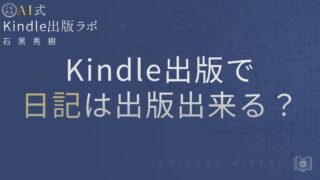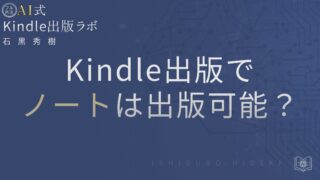Kindle出版+塗り絵は電子NG?紙版で出す手順と注意点を徹底解説
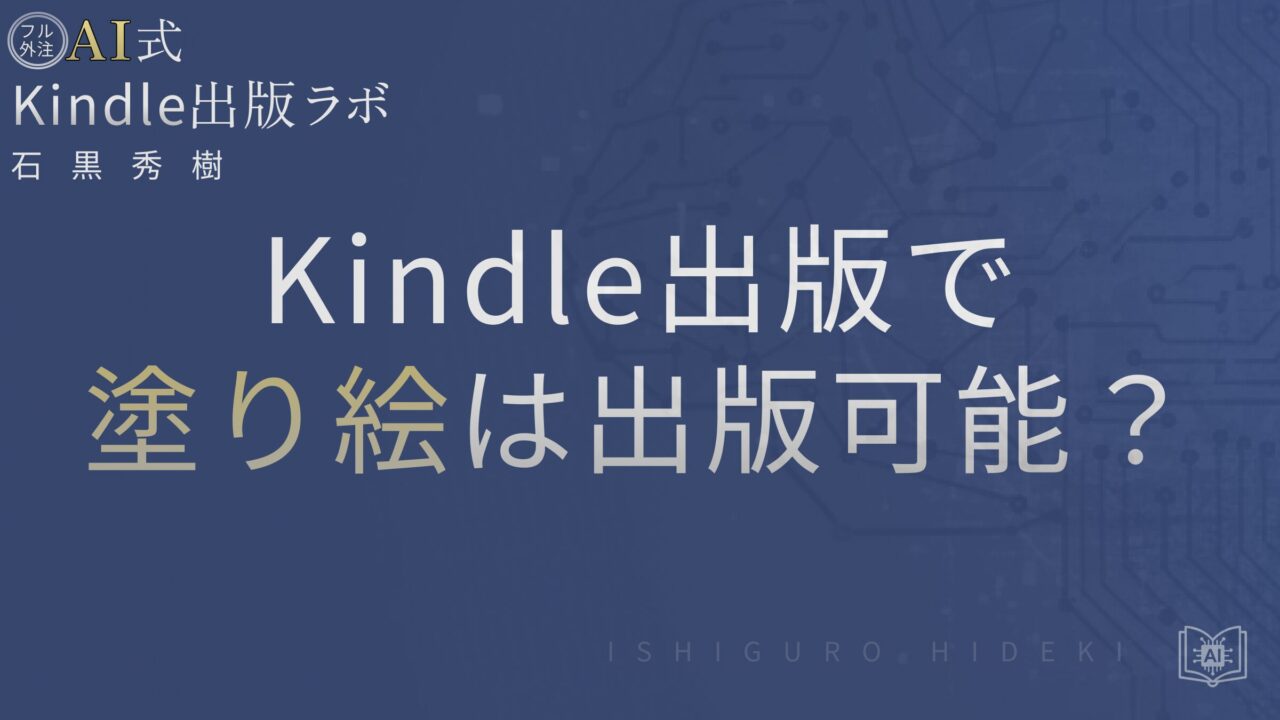
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で「塗り絵」を出そうと考えたとき、多くの人が最初に迷うのが「電子で出せるのか、それとも紙がいいのか」という点です。
実は、ここを最初に正しく押さえておかないと、後でデータを作り直したり、審査で却下されるなど、思わぬ遠回りになることがあります。
この記事では、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の仕様に基づきながら、「電子では難しい理由」と「紙版が主流になる背景」を初心者にもわかりやすく解説します。
実際に何冊も出版してきた経験を踏まえて、公式ガイドだけではわかりにくい実務上の注意点もあわせて紹介します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 規約・禁止事項・トラブル対応など安全に出版を進めたい方はこちらからチェックできます:
規約・審査ガイドライン の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で塗り絵を出したい人が最初に知るべきこと
目次
塗り絵本をKDPで出版する場合、最初に押さえるべきなのは、電子書籍は塗り絵用途に基本的に不向きという点です。
固定レイアウト等で成立する例もありますが、個別審査で判断されます(公式ヘルプ要確認)。
多くの初心者はこの点を見落とし、電子用にデータを作ってから「うまく表示されない」「審査に通らない」といった壁にぶつかります。
この章では、なぜ電子では難しいのか、なぜ紙版が主流なのか、そして初心者がよく誤解しがちなポイントを順に説明します。
電子出版の可否を判断するには、まず形式を理解するのが大切です。詳しくは『Kindle出版の形式とは?リフロー型・固定レイアウト・対応ファイル形式を徹底解説』をご覧ください。
「Kindle出版+塗り絵」は電子では難しい理由
まず大前提として、Kindle端末は「本を読む」ことに特化しており、塗り絵のように線画に色を塗る用途には向いていません。
モノクロ表示の端末も多く、細い線や濃淡の表現が潰れてしまうケースがよくあります。
たとえ白黒の塗り絵画像を掲載しても、端末によっては拡大しても見えにくく、ユーザー体験として成立しません。
また、KDP電子書籍はEPUB等が推奨で、PDFは原則非対応です。
固定レイアウトは可能ですが機能や審査は限定的で、可否は個別審査です(公式ヘルプ要確認)。
実際、私自身も初期の頃に「電子版で塗り絵本を出そう」として申請したところ、レイアウト不備や閲覧不適合を理由にリジェクトされた経験があります。
公式ヘルプ上も、塗り絵のような用途を想定した明確なガイドラインはなく、審査基準はケースによって判断されるため、安定した運用は難しいのが現状です。
このような理由から、電子書籍で塗り絵本を成立させるのは、技術的にも審査的にもハードルが高いと考えておくのが現実的です。
紙版(ペーパーバック)が主流になる背景とメリット
一方、塗り絵本では紙版(ペーパーバック)で出版する方法が主流になっています。
KDPのペーパーバックは、300dpi以上の高解像度で画像を配置すれば、印刷でもきれいに再現できます。
端末依存の問題もなく、ユーザーは実際に色鉛筆やペンで塗ることができるため、商品としての満足度が高いのです。
加えて、ペーパーバックではページ数や余白などの仕様をこちらで細かく設計できるので、塗り絵に適した構成に仕上げやすいというメリットもあります。
実際に販売されている塗り絵本の多くはペーパーバックで、24ページ以上というKDPの最低基準をクリアしつつ、印刷コストと価格設定をうまく調整して収益化されています。
カラー印刷は『標準』『プレミアム』がありますが、提供可否や仕様は国・在庫拠点で異なる場合があります(公式ヘルプ要確認)。
よくある誤解と初心者がつまずきやすいポイント
初心者の方がよく陥るのは、「Kindle=電子だから、まずは電子で出そう」という思い込みです。
ところが、電子用に作ったデータは、そのままでは紙版に流用できないことが多く、結局一から作り直す羽目になります。
もうひとつ多いのが、画像の解像度や余白の設定を軽視するパターンです。
KDPのプレビューでは綺麗に見えても、印刷すると線がぼやけたり、端が切れてしまうケースは珍しくありません。
さらに、AIで画像を作る場合は、KDPの申告ルールにも注意が必要です。
生成した画像をそのまま使う場合は「AI生成コンテンツ」として申告が必要で、アシスト用途のみなら申告不要という細かな区分があります。
このあたりは公式ヘルプでも確認できますが、実際に審査で引っかかるケースもあるので、「仕様+実務」の両方を理解しておくことが重要です。
また、表紙のレイアウトや余白設定なども、公式テンプレートを使っていても微妙なズレが起きることがあるので、KDPのプレビュー機能で細部まで確認しておくと安心です。
初心者ほど「テンプレを使えば自動でうまくいく」と思いがちですが、実際にはちょっとした設定ミスが完成度に大きく影響します。
ここを最初に理解しておけば、塗り絵本出版の全体像がかなりスムーズになります。
KDP(Amazon)の仕様を理解しよう|塗り絵本出版の基本知識
KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)で塗り絵本を出す場合、最初に押さえるべきなのが「電子と紙では仕様も審査基準もまったく違う」という点です。
とくに電子書籍は「文章を読む」前提で作られているため、塗り絵のような画像中心のコンテンツでは制限が多く、想定通りに表示されないことが少なくありません。
一方でペーパーバックは、印刷物としての要件(解像度・ページ数・余白など)をクリアすれば比較的安定して出版できるため、塗り絵本の主流は紙版となっています。
ここでは、出版にあたって理解しておくべきKDPの基本仕様や、紙版の最低条件、価格設定の考え方を順に解説します。
KDPの基本仕様と電子書籍での制限点
KDPの電子書籍(Kindle本)は、リフロー型と固定レイアウト型の2種類があります。
多くの通常書籍はリフロー型で、読者の端末サイズに合わせて自動的に文字や画像が流し込まれます。
しかし、塗り絵の場合は画像の位置や余白が重要になるため、リフロー型ではレイアウトが崩れやすく、実用的ではありません。
固定レイアウト型を選ぶことも可能ですが、日本のKDPでは一部の機能が限定されており、画像中心のコンテンツは審査で非承認になるケースも見られます。
また、Kindle端末の多くはモノクロ表示です。
高精細な線画であっても、端末によっては線が潰れたり、拡大しても細部が見えにくいことがあります。
私自身も電子で挑戦した際、プレビューではきれいに見えていたのに、実機で確認すると全体がぼやけてしまい、泣く泣く作り直した経験があります。
公式ヘルプでも明確な塗り絵向けガイドは存在せず、審査基準もケースごとに判断されるため、電子での塗り絵出版は安定しづらいのが実情です。
ペーパーバックで塗り絵を出版するための最低条件(ページ数・解像度など)
ペーパーバック(紙版)の場合、まず押さえるべきはKDPの基本的な入稿条件です。
本文の画像は300dpi以上の高解像度で作成する必要があります。
これは、印刷時に線がかすれたり滲んだりするのを防ぐためです。
Web用の72dpiや96dpiの画像をそのまま使うと、プレビューでは綺麗に見えても、実際の印刷では線がぼやけることが多いので注意しましょう。
ページ数は最低24ページ以上が必須です。
この数字は表紙を除いた本文部分のページ数で、KDPの印刷仕様上の最低基準です。
また、余白やノド(中央の綴じ部分)の設定も重要です。
テンプレートを使えば自動で設定されますが、イラストがギリギリまで配置されていると印刷時に切れてしまうことがあるので、実際にはテンプレートよりも数ミリ余裕を持たせるのが安心です。
私も最初の頃はテンプレートを信じ切って配置し、何冊かは中央部分が削れて印刷されてしまったことがあります。
こうした細かな設定こそが、完成度を左右します。
線画の潰れを防ぎたい方は、『Kindle出版の挿絵サイズとは?スマホ表示に最適な縦横ピクセル数を徹底解説』も参考になります。
印刷形式(標準/プレミアム)と価格設定の考え方
KDPのペーパーバックには、「標準カラー印刷」と「プレミアムカラー印刷」の2種類があります。
標準は印刷コストを抑えられ、塗り絵本でも多く使われている形式です。
プレミアムは発色や仕上がりが非常にきれいですが、印刷コストが高くなるため、価格設定とのバランスが重要になります。
印刷コストはKDPのロイヤリティ計算に直接関わる項目で、販売価格から印刷費が差し引かれる仕組みです。
つまり、コストが高いほど著者の受け取り額が減るということです。
実際、私も最初はプレミアム印刷で設定したのですが、価格を高くすると売れ行きが鈍り、かといって価格を下げると利益がほぼゼロになる、というジレンマに陥りました。
最終的には標準印刷で十分なクオリティを確保しつつ、手頃な価格で販売する形に落ち着きました。
価格設定は、印刷費・ロイヤリティ・販売戦略を総合的に考える必要があります。
公式ヘルプには計算式も載っていますが、著者校正版(プルーフ)や著者用コピーを注文し、印刷品質と価格感を現物で確認しましょう。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
塗り絵本をKDPで出版する具体的な手順
ここでは、実際にKDPで塗り絵本を出版する流れを、初心者向けに4つのステップで紹介します。
公式の手順だけを見ると簡単そうに見えますが、実際は各ステップに注意点があり、そこを押さえておくことで仕上がりや審査通過率が大きく変わります。
ステップ①:原稿データ(塗り絵画像)を準備する
まずは本文となる塗り絵画像を用意します。
先ほど触れた通り、解像度は300dpi以上が必須です。
線画の太さも重要で、細すぎる線は印刷時に消えてしまうことがあります。
私はIllustratorなどで作るときは、0.5〜1pt程度を基準にしています。
AIで生成する場合は、細部が甘くなることもあるため、仕上げに軽く修正を加えると印刷映えしやすくなります。
ファイル形式は、最終的にはPDFにまとめますが、元データはPNGやTIFFの高解像度画像で問題ありません。
ステップ②:KDP用テンプレートにレイアウトを反映する
KDP公式のテンプレートをダウンロードし、そこに画像を配置していきます。
テンプレートには余白やノドのガイドがあり、塗り絵本の場合はイラストが中央や端に近づきやすいので、ガイド線をしっかり確認しながら作業することが大切です。
私は最初、テンプレートにぴったり合わせただけで入稿し、中央の一部が切れてしまったことがあります。
印刷は一発勝負なので、数ミリの余裕を持って配置するのがコツです。
ステップ③:表紙データを作成し、KDPにアップロードする
表紙は、本文のページ数によって背幅(本の厚さ)が変わるため、KDPのカバー計算ツールで正確なサイズを確認してから作成します。
背幅がズレていると、審査で差し戻されるだけでなく、印刷後にデザインが左右にズレることもあります。
表紙デザインはフルカラーが可能なので、塗り絵本の世界観を伝える重要なポイントです。
ただし、著作権や商標を侵害しないよう注意が必要です。
AI画像を使用する場合は、KDPの申告ルールに従い、必要に応じて申告を行いましょう。
ISBNやASINなど、紙と電子の識別子の違いは『Kindle出版でISBNは必要?電子書籍とペーパーバックの違いを徹底解説』で詳しく説明しています。
ステップ④:プレビューで仕上がりを確認し、出版申請する
データをすべてアップロードしたら、KDPのプレビュー機能で実際の仕上がりを確認します。
この段階で余白のズレや画像の欠けを見落とすと、そのまま印刷されてしまうため、細部までチェックすることが大切です。
私は一度、1ページだけ上下が反転しているのに気づかず出版してしまい、後から修正版を出す羽目になりました。
プレビューで気になる点があれば、その場で修正し、PDFを差し替えましょう。
最終チェックが終わったら出版申請を行い、KDPの審査を待ちます。
審査結果は数日以内が多い一方、状況により長引くことがあります。
目安であり確約ではありません(公式ヘルプ要確認)。
この段階で大きな修正が発生しないよう、事前準備を丁寧に進めるのが成功のコツです。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
塗り絵本出版で気をつけたい注意点とよくあるトラブル
塗り絵本の出版は、通常のテキスト中心の書籍と比べて「画像の質」や「仕様の適合」が問われるため、思わぬ落とし穴が多いジャンルです。
とくに初心者の方は、公式ガイドをそのままなぞって進めても、実際の審査で非承認になったり、印刷で仕上がりが大きく崩れたりするケースが少なくありません。
ここでは、私自身の経験も踏まえて「審査」「画像の品質」「AI画像の取り扱い」という3つの観点から、よくあるトラブルとその回避策を紹介します。
電子版での審査落ち・非承認の事例と回避策
まず多いのが、電子版(Kindle本)での審査落ちです。
電子書籍はテキスト主体の利用を前提としているため、塗り絵のような画像中心のコンテンツは、固定レイアウトでも通りにくい傾向があります。
実際に、私も初めて塗り絵本を申請した際は「閲覧に適さない内容」という理由で非承認になりました。
プレビュー上では綺麗に見えていても、Kindle端末によっては拡大しても線が潰れてしまい、読者体験を損ねると判断される場合があります。
また、ファイル形式や画像の扱いが不適切な場合も審査で引っかかります。
KDPでは電子書籍の本文にPDFを直接アップロードできず、画像中心の本を強引にリフロー型で作るとレイアウトが崩れやすいです。
固定レイアウトを使っても、日本のKDPでは対応機能が一部制限されているため、海外の事例をそのまま真似してもうまくいかないことがよくあります。
このため、電子での塗り絵本出版は「審査に通るかどうかがケースバイケース」になり、安定運用が難しいのが現実です。
最初から紙版での出版を前提に準備するのが、最も安全かつスムーズな方法といえます。
画像解像度・塗りやすさ・余白設定のミスに注意
画像関連のトラブルは、出版後に気づいて手戻りになるケースが非常に多いです。
特に多いのが、300dpi未満の画像をそのまま使ってしまうパターンです。
画面上では綺麗に見えても、実際の印刷では線がぼやけたり、細部が潰れたりしてしまいます。
一度出版した本を差し替えるのは手間がかかるので、入稿前のチェックを徹底しましょう。
塗り絵の場合、線の太さや間隔も仕上がりに大きく影響します。
細すぎる線は印刷時に消えてしまい、逆に太すぎると塗るスペースが狭くなって塗りづらい本になります。
私は最初の頃、細かさを追求しすぎて、読者から「細部が潰れて塗れない」というフィードバックをもらったことがあります。
また、余白(マージン)設定にも注意が必要です。
テンプレート通りに配置したつもりでも、中央寄り(ノド側)の線が綴じ込みにかかって見えづらくなるケースが多いです。
実務的には、テンプレートよりも2〜3mm余裕を持たせて配置するのがおすすめです。
こうした細かい調整が、最終的な完成度を大きく左右します。
AI生成画像を使う場合のKDP申告ルール
AI画像を活用して塗り絵を制作する人も増えていますが、KDPではAI生成コンテンツに関する申告が義務化されています。
2023年以降、KDPでは「AIが生成したコンテンツ」と「AIが制作を補助したコンテンツ(アシスト)」を区別し、前者は申告が必要と明記されています。
たとえば、プロンプトを入力して生成された画像をそのまま使用する場合は「AI生成」として申告が必要です。
一方で、AIで下書きを作成し、その後自分で線を描き直したり加工したりした場合は「アシスト扱い」となり、申告は不要とされています。
注意したいのは、審査の段階でAI画像の申告漏れが見つかると、非承認や差し戻しになる可能性があることです。
特に、複数ページにAI画像を使っている場合はチェックが入ることが多い印象があります。
私も実際に、申告を忘れて提出した際に修正依頼が来たことがあります。
AIを使うのは問題ありませんが、KDPのルールに沿って正しく申告することが重要です。
公式ヘルプも随時更新されているため、出版前には必ず最新情報を確認しておきましょう。
成功事例とジャンル別の塗り絵本アイデア
塗り絵本のジャンル選びは、単にイラストを用意するだけでなく「読者がどんな目的で塗り絵を楽しみたいか」を踏まえることが重要です。
実際に売れている本を見ても、ジャンルの切り口や構成にしっかりとした方向性があります。
ここでは、人気ジャンルの傾向と、シンプルな構成で長く売れ続けている事例を紹介します。
人気ジャンル(動物・植物・マンダラなど)の傾向
KDPでよく売れている塗り絵本のジャンルとしては、動物・植物・マンダラ・日常風景などが定番です。
特に動物と植物は、日本でも海外でも人気が高く、イラストのバリエーションを出しやすいのが特徴です。
動物なら犬や猫といった身近なものから、ファンタジー系の生き物まで幅広く展開できます。
植物はシンプルな線画でも映えるため、制作のハードルが比較的低いジャンルです。
マンダラは「大人の塗り絵」として根強い人気があります。
繰り返し模様の幾何学的なデザインは、塗る工程そのものが“癒し”になるということで、特に30〜50代の読者層に支持されています。
私が出版したマンダラ系の塗り絵本も、SNSなどで「リラックスしたいときに塗っています」というレビューを多くいただきました。
また、季節や行事をテーマにしたジャンルも人気があります。
たとえば「春の花と動物」「クリスマスの街並み」「日本の四季」など、テーマを明確に打ち出すことで、販売期間に合わせた需要を取り込みやすくなります。
ジャンル選びの段階で「誰に・どんな場面で塗ってもらいたいか」を具体的にイメージすると、内容がぶれにくくなります。
シンプルな構成でロングセラー化した事例
KDPでは、凝った装丁や複雑な構成にしなくても、内容が的確であれば長く売れ続けるケースがあります。
私が印象的だったのは、とてもシンプルな「1ページに1イラスト」の構成で、数年以上コンスタントに売上を出している動物の塗り絵本です。
イラストは線がはっきりしていて塗りやすく、全体的に余白がしっかり取られており、初心者でも気軽に楽しめる作りになっていました。
もうひとつは、季節ごとの植物を1冊にまとめた作品です。
派手な装飾や余計な要素が一切なく、「春夏秋冬それぞれの植物を塗る」というコンセプトが明確でした。
こうした本は、発売直後に爆発的に売れるというよりも、検索経由や口コミでじわじわと読者を増やし、結果としてロングセラーになっています。
重要なのは、内容のクオリティとコンセプトを明確にすることです。
奇をてらったアイデアよりも、ターゲット読者のニーズにきちんと応える本の方が、結果的に長く売れ続ける傾向があります。
私自身も、最初に作った凝った構成の本より、後から出したシンプルなテーマ本の方が安定した売上を記録しました。
まとめ|塗り絵本は紙版でKDP出版するのが現実的
ここまで解説してきたように、Kindleで塗り絵本を出版する場合は電子ではなく紙版(ペーパーバック)を前提に準備するのが現実的です。
電子書籍では端末仕様や審査の不確実性が大きく、安定した運用は難しいのが現状です。
一方、紙版であればKDPの仕様をきちんと押さえることで、誰でも出版・販売が可能です。
出版時の注意点としては、画像解像度や余白設定、AI画像の申告ルールなど、細部まで丁寧に確認することが大切です。
また、ジャンルや構成を明確にすることで、出版後のロングセラー化も狙えます。
派手な装飾よりも、読者が「塗りやすい」と感じる作りを意識しましょう。
最後に、出版は一度で完璧に仕上げようとせず、最初は1冊をきちんと完成させることに集中するのがおすすめです。
印刷版は実際の仕上がりを手に取って確認できるので、改善点も見えやすく、経験を重ねるほど完成度が上がっていきます。
塗り絵本は一見シンプルに見えて、細部の設計力が問われるジャンルです。
丁寧な準備とテーマ設計を心がければ、初心者でも十分にKDPで成果を出すことができます。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。