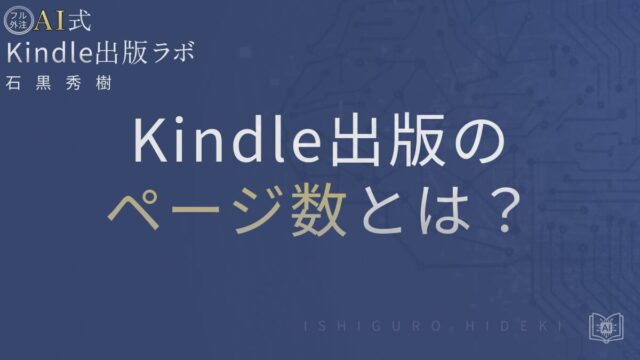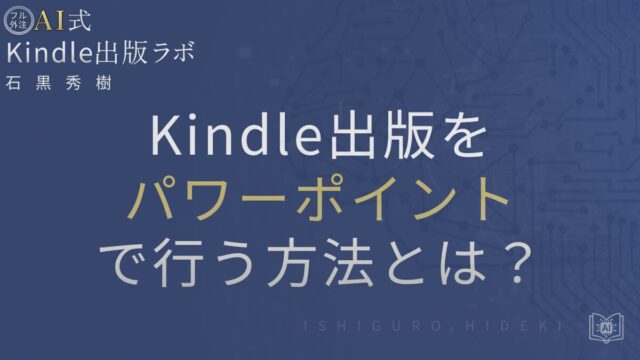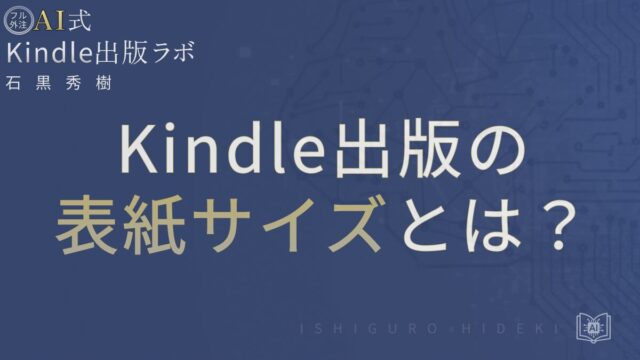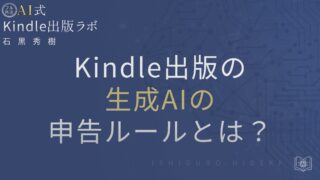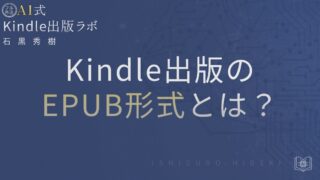Kindle出版のアップロード手順とは?失敗しない入稿とプレビュー確認を徹底解説
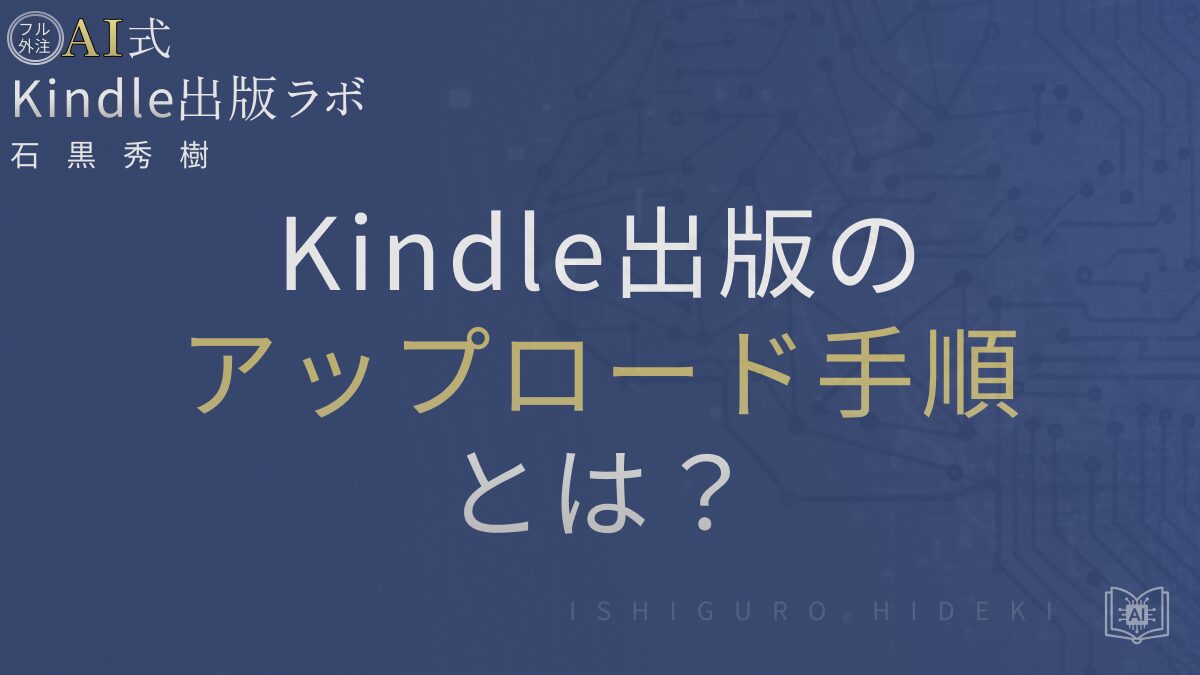
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの人が最初につまずくのが「アップロード」です。
「どの画面で、どのファイルを入れるのか」「形式はこれでいいのか」と迷う方がとても多いです。
この記事では、Amazon KDPで原稿や表紙をアップロードする仕組みと注意点を、初心者にもわかりやすく解説します。
特に「コンテンツ」タブの意味や、電子書籍と紙書籍(ペーパーバック)で異なる手順を整理して理解することが目的です。
経験者の視点から、実際にやってみたときの“あるある”も交えて紹介します。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で「アップロード」とは何かを理解する
目次
KDPにおける「アップロード」とは、あなたが作成した電子書籍の原稿ファイルと表紙データをAmazonのシステムに入稿する工程を指します。
この作業はKDPの「コンテンツ」タブで行われ、出版手続きの中でも最も重要なステップのひとつです。
ここを正確に理解しておくと、審査や公開がスムーズに進みます。
Amazon KDPにおける「アップロード」「コンテンツ」タブの役割
KDPの管理画面では、「詳細」「コンテンツ」「価格設定」という3つのタブで出版情報を登録します。
このうち「コンテンツ」タブが、原稿と表紙をアップロードする中心の画面です。
Word(.docx)やEPUBなど、KDPが指定する形式のファイルをここで選択して入稿します。
アップロード後はKindle向け形式に自動変換され、プレビューで表示を確認できます(具体的な内部形式名は非表示)。
この段階で体裁崩れやリンク切れを確認し、修正することが大切です。
経験上、プレビューを飛ばしてそのまま進めてしまうと、行間のズレや画像の欠けが見つからず、公開後に修正版を再アップロードする手間が発生します。
公式では「プレビューで必ず確認」と明記されていますが、実際には見落とす方が多いので注意してください。
また、KDP上の「アップロード」ボタンは、単なるファイル提出ではありません。
Amazonの審査システムに渡る最初のチェックポイントでもあります。
たとえば、表紙の縦横比が推奨値(1:1.6)から大きく外れていると、警告やエラーが出ることがあります。
このように「アップロード」は技術的な登録作業であると同時に、品質管理の入口ともいえるのです。
電子書籍と紙書籍(ペーパーバック)のアップロードの違い
KDPでは電子書籍(Kindle本)とペーパーバック(紙の本)をどちらも同じ画面で扱えますが、アップロード内容は異なります。
電子書籍の場合、アップロードするのは「原稿ファイル」と「表紙画像」の2点だけです。
ファイル形式はEPUB、DOCX、KPFなどに対応しており、画像解像度や目次のリンク構造に注意すれば問題ありません。
一方、ペーパーバックでは印刷用の原稿データ(PDF形式推奨)と、背表紙を含むフルサイズの表紙データを求められます。
ページ数や用紙サイズ(A5・B6など)によって表紙の寸法が変わるため、電子書籍よりも正確なサイズ設定が必要です。
電子書籍はKindle端末やアプリの画面サイズに合わせて自動調整されますが、紙の場合はズレが印刷に反映されるため、より厳密なチェックが求められます。
実務的には、まず電子書籍を完成させたうえで、後からペーパーバック版を追加登録する流れが一般的です。
Amazon.co.jpのKDPでは、電子書籍だけでも十分販売可能で、ペーパーバックは「希望者向けオプション」として考えて問題ありません。
ただし、どちらを選んでも、アップロードの基本的な目的は同じです。
つまり、読者に見やすく安全なデータを提供するための最終確認ステップという点を忘れないようにしましょう。
ペーパーバック版も検討するなら、『Kindle出版で紙の本を出すには?ペーパーバックの条件と手順を徹底解説』を参考に別データの作り方を押さえてください。
KDPで原稿と表紙をアップロードする手順(実践)
KDPでのアップロード作業は、「手順を知っているかどうか」でスムーズさがまったく違います。
特に初回は迷いやすいですが、流れをつかめば10分ほどで完了します。
ここでは、KDPの実際の操作画面をイメージしながら、原稿と表紙をアップロードする一連の流れを具体的に解説します。
KDP本棚から“電子書籍を新規作成”する方法
KDPにログインすると「本棚」という管理画面が表示されます。
右上にある「+電子書籍またはペーパーバックを作成」ボタンから、新しい出版プロジェクトを始めます。
ここで「Kindle電子書籍」を選択すると、「詳細」「コンテンツ」「価格設定」の3つのタブが順に出てきます。
アップロード作業を行うのは「コンテンツ」タブです。
「詳細」タブではタイトルや著者名、説明文、キーワード、カテゴリなどを設定します。
この部分を丁寧に入力しておくと、検索時の表示順位や読者のクリック率にも関わるため、意外と重要です。
ただし、ここではまだアップロードは不要。
焦らず次の「コンテンツ」に進みましょう。
原稿ファイルの形式と注意点(EPUB/DOCX/KPFなど)
「コンテンツ」タブでは、まず原稿ファイルをアップロードします。
対応形式はEPUB、DOCX、KPFの3つが主流です。
Wordで書いた原稿ならDOCX形式のままで構いません。
ただし、段落の空白やページ区切りが正確に反映されないことがあるため、KDPのプレビューで確認が必要です。
EPUBは電子書籍専用の形式で、装飾を多用したり、他のアプリで整形したい場合に向いています。
KPFは「Kindle Create」というAmazon公式ツールで作成する形式で、見出しや目次を自動生成できる点が便利です。
公式ではどの形式も受け付けていますが、WordファイルをKDPに直接アップロードするときは余計な空白行や改ページ記号を削除しておくのがコツです。
これを怠ると、改ページが想定と異なってしまうケースがあります。
経験上、ファイル名を半角英数字にしておくとトラブルが少ないです。
日本語ファイル名のままでもアップロードできますが、まれに文字化けして「エラー」表示になることがあります。
公式ヘルプにも明確な規定はありませんが、実務的には英数字推奨です。
迷ったらまず『Kindle出版のデータ形式とは?対応ファイルとアップロード手順を徹底解説』で、用途別の最適形式を確認してから入稿しましょう。
表紙ファイルの仕様と最適サイズ・フォーマット
次にアップロードするのが表紙です。
電子書籍の表紙は、JPEGまたはTIFF形式で、縦横比が1:1.6(例:1600×2560ピクセル)になるよう推奨されています。
電子書籍表紙はピクセル寸法(例:幅1600×高2560、比率1:1.6)を優先し、実サイズが十分になるよう最適化しましょう(dpiは画面表示に直接影響しません/公式ヘルプ要確認)。
KDPには「表紙作成ツール」もありますが、クオリティを重視するなら自作またはデザイナー依頼が安心です。
経験的に、ファイルサイズが大きすぎるとアップロードに時間がかかるか、エラーが出ることがあります。
5MBを超える場合は圧縮して再保存するのが安全です。
ペーパーバック用の表紙は、背表紙や裏面を含めたPDF形式を求められますが、電子書籍では単体の表紙画像だけで問題ありません。
ここを混同して再提出になるケースが非常に多いので注意してください。
表紙は比率と余白が命です。制作前に『Kindle出版の表紙サイズと比率とは?初心者が失敗しない設定を徹底解説』をチェックしておくと安全です。
アップロード後の「プレビューと品質チェック」の流れ
原稿と表紙をアップロードしたら、次は「Kindleプレビューア」で仕上がりを確認します。
KDPのブラウザ上でプレビューできるほか、無料のデスクトップ版アプリも利用可能です。
ページのズレ、目次リンク、画像配置などを細かく確認しましょう。
ここで体裁崩れを放置すると、審査で差し戻される可能性があります。
特に目次リンク切れや画像が本文からはみ出すレイアウトは、審査担当者がチェックするポイントです。
プレビューで体裁に違和感があれば必ず修正してください。許容範囲の解釈は変わる可能性があるため、最新の公式ヘルプを確認しましょう(公式ヘルプ要確認)。
プレビューが完了し、問題がなければ「保存して次へ」で価格設定画面に進みます。
この段階で初めて「アップロードが完了」といえます。
つまり、KDPのアップロードは“ファイルを入れるだけ”ではなく、“品質確認までを含めた工程”という点を意識しておくと、失敗がぐっと減ります。
仕上がり確認の具体手順は『Kindle出版のプレビュー確認とは?オンラインとPreviewerの使い方を徹底解説』で画面別に解説しています。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
アップロードで起こりやすい失敗と解決策
KDPのアップロード工程はシンプルに見えますが、実際にやってみると小さなトラブルが意外と多いです。
特に初回は、ファイル形式の不備や体裁崩れなどで「アップロードエラー」と表示されることがよくあります。
ここでは、実際の現場でよく起こる失敗とその解決策を具体的に紹介します。
実務的な視点を持っておくことで、公開遅延や再審査を防ぐことができます。
体裁崩れ・レイアウト崩れの原因と直し方
もっとも多いトラブルが、原稿をアップロードしたあとにレイアウトが崩れるケースです。
WordやEPUBで作成した段落構成が、KDP上のプレビューで大きくズレてしまうことがあります。
原因の多くは、不要な改行や空白、段落設定の自動変換です。
特にWordファイルを使う場合、見た目を整えるためにスペースやタブで位置を合わせている人が多いですが、Kindleではこれが「文字化け」や「空白の乱れ」として表示されます。
正しい方法は、スタイル設定(段落・見出し・中央揃え)を使って整形することです。
また、KDPではフォント情報が自動で上書きされるため、本文フォントを明示的に指定する必要はありません。
実体験として、私は以前、目次リンクの設定を「ページ番号」で作ってしまい、KDP変換後に全リンクが無効化されるという失敗をしました。
Kindleではページ数の概念が端末によって変わるため、「ページ番号リンク」ではなく「見出しへのハイパーリンク」で設定する必要があります。
この違いを理解しておくと、審査落ちを防ぐことができます。
画像エラー・ファイル読み込み失敗の対応
次に多いのが、画像関連のトラブルです。
画像が正しく表示されない、あるいはアップロード自体が途中で止まる場合は、ファイル容量や解像度が原因であることが多いです。
KDPの公式推奨は、解像度300dpi・ファイルサイズ5MB以下。
これを超えると、アップロード時に「ファイルが大きすぎます」と表示されることがあります。
実際には、2〜3MB程度が最も安定します。
特に写真やイラストを多く含む書籍では、画像をJPEG形式に変換し、圧縮率を少し上げて再保存すると安定します。
また、ファイルパスに日本語が含まれているとアップロードが止まる場合があるため、英数字だけにしておくと安心です。
もうひとつの落とし穴は、画像の「縦横比」。
KDPでは端末の画面比率に合わせて画像を自動調整しますが、極端に縦長または横長の画像はトリミングされることがあります。
余白を広めに取っておくことで、端末間の表示差を抑えられます。
アップロードできない・エラーになる代表的ケースと対処法
「アップロードが始まらない」「途中で止まる」といったケースも珍しくありません。
この場合、まずはブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みするのが基本です。
Google Chromeでうまくいかないときは、FirefoxやEdgeに切り替えると成功することもあります。
また、ファイル名に記号(例:「!」「?」「・」「()」など)が含まれていると、KDPの内部で処理が止まることがあります。
シンプルな英数字にして再アップロードしてみてください。
公式では特に制限が明示されていませんが、実務上は英小文字+ハイフンのみが最も安定します。
さらに、ネット回線が不安定だとアップロードが途中で途切れることもあります。
この場合は一度ログアウトし、時間をおいて再試行するのが有効です。
それでも改善しないときは、AmazonのKDPサポートに問い合わせフォームから状況を伝えると、原因を調査してもらえます。
最後に、アップロードエラーの9割は「ファイル名」「容量」「形式」のどれかに起因します。
焦って何度も再送信するよりも、一度冷静にそれらの要素をチェックしてから再試行する方が早く解決します。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
成功例・ケーススタディ:アップロードで苦労した事例と改善策
アップロード作業では、公式ガイドを読んでいても「なぜか通らない」「見た目が崩れる」といったトラブルが起こることがあります。
ここでは、私自身や受講者の方々が実際に経験したケースをもとに、失敗から学べる改善策を紹介します。
初めてKDPに挑戦する方が同じつまずきを避けられるよう、実務的な視点で解説していきます。
初心者が表紙サイズで落ちたケース
もっとも多いトラブルのひとつが「表紙サイズの不一致」です。
KDPでは推奨サイズを縦横比1:1.6(例:1600×2560ピクセル)としていますが、この比率を守らないと「アップロードできません」または「品質エラー」として却下されます。
ある初心者の方は、画像編集アプリで正方形に近い表紙を作成し、そのままアップロードしたところ、端が自動トリミングされてタイトル文字が欠けてしまいました。
Amazonの審査では、文字が切れている表紙や解像度の低い画像は販売品質に影響すると判断され、再提出を求められることがあります。
このような場合の改善策は、まず「カバーサイズを固定比率で作る」ことです。
Canvaなどのデザインツールで「1600×2560px」のキャンバスを設定すれば、推奨比率を維持したまま制作できます。
また、テキストを端ギリギリに配置せず、上下左右に10〜15%程度の余白を取るのがコツです。
実務上の補足として、ペーパーバック版を同時に出す場合は、背表紙を含めたサイズが異なるため、別データを用意する必要があります。
電子版と紙版の表紙を兼用しようとすると審査で落ちやすいため、「電子書籍用」「紙書籍用」で分けて管理しておくとトラブルを防げます。
目次リンク不具合でプレビュー崩れしたケース
次に多いのが、Word原稿をそのままアップロードして「目次リンクが動かない」「プレビューでずれる」という問題です。
特にWordで自動目次を使っていない場合、KDP変換時にリンクが途切れてしまうことがあります。
これは、見出しスタイルを正しく設定していないことが主な原因です。
あるケースでは、「目次ページを手打ちで作成 → 各章にページ番号リンクを貼る」という方法を使っていたため、Kindleプレビューではすべて無効になっていました。
Kindleはデバイスによってページ数が異なるため、ページ番号を基準とするリンク構造は通用しません。
見出しタグ(Wordの「見出し1」「見出し2」)を設定し、Kindle CreateまたはKDPの自動変換に任せるのが最も確実です。
私も最初の頃、手作業で目次を作ってしまい、10章分のリンクが切れて公開前日に差し戻しになったことがあります。
焦りましたが、見出しスタイルを適用して再アップロードしたところ、わずか10分で修正完了。
それ以来、原稿段階から「章構成と見出しスタイル」を整えておくようにしています。
プレビュー画面では、目次リンクを必ず実際にクリックして確認してください。
見出しが飛ばない場合や順番が崩れている場合は、WordやEPUBの内部リンク設定に誤りがあるサインです。
KDPの自動修正機能は限界があるため、自分で確認するのが最も確実です。
最後に、「アップロード後に必ずプレビュー確認を行う」ことを習慣にしましょう。
見た目のズレやリンク切れは、早い段階で修正すれば審査の遅延を防げます。
経験者でも一度はつまずく部分ですが、確認を怠らなければ問題なく進められます。
まとめ
Kindle出版におけるアップロード作業は、一見シンプルですが、細部に注意が必要です。
特に原稿や表紙は「形式・サイズ・構造」を正確に整えることが重要です。
そのうえで、プレビューで体裁とリンクを確認することが、審査をスムーズに通す最大のコツです。
アップロードはKDPの出版工程の中でも、品質を左右する要です。
多少の手間を惜しまず、1つずつ丁寧に確認すれば、初回から問題なく公開まで進められます。
慣れてくると、原稿の作成から公開まで半日で完了できるようになります。
あなたの電子書籍が、読者にとって読みやすく魅力的な1冊になるよう、最終チェックを大切にしてください。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。