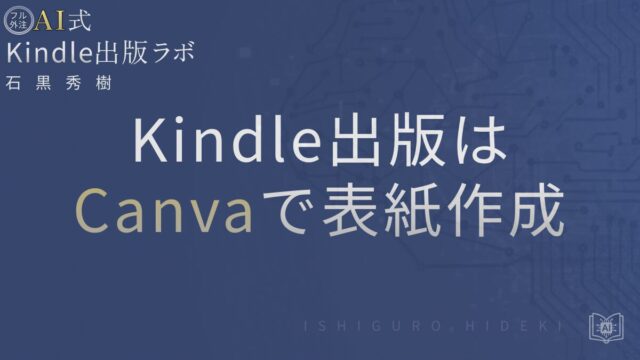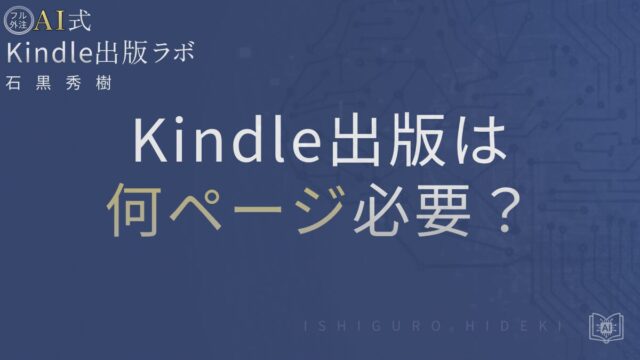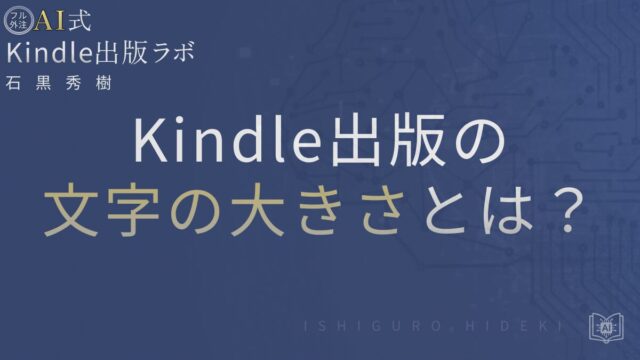絵本の自費出版にかかる費用とは?相場・内訳・節約ポイントを徹底解説
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
絵本を自費出版したいけれど、「実際いくらかかるのか」「紙と電子でどれくらい違うのか」が気になる方は多いです。
「この記事では、初心者にもわかりやすく、絵本の自費出版にかかる費用目安と内訳の全体像を解説します。」
実際の制作経験や見積もり事例をもとに、印刷・イラスト・デザインなどの具体的な内訳と、費用を抑えるための考え方も紹介します。
「どこにお金がかかるのか」を理解しておくことで、ムダな支出を防ぎ、納得のいく形で出版を進められるはずです。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
絵本の自費出版にかかる費用の全体像
目次
自費出版とは、出版社を通さずに自分の費用で作品を制作・発行する方法です。
絵本の場合は「子ども向けに作りたい」「自分の作品を形に残したい」といった個人目的が多く、必ずしも商業的な利益を追求するものではありません。
ただし、理想の仕上がりを求めるほど費用は高くなるため、構成や印刷方法を事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、絵本を自費出版する際の費用構造と、紙と電子それぞれの特徴を整理していきます。
自費出版+絵本とは:商業出版との違いと目的
商業出版では出版社が費用を負担し、売上から著者に印税が支払われます。
一方、自費出版は著者自身が全ての費用を負担し、自由に内容やデザインを決められるのが特徴です。
目的も異なり、「子どもや孫に贈りたい」「作品集として残したい」「イベントで頒布したい」など、個人的な想いを形にするケースが多いです。
ただし、自由度が高い分、編集や印刷の判断を自分で行う必要があり、初心者にとっては悩むポイントも多いでしょう。
自費出版と商業出版の違いや、どちらを選ぶべきかの判断軸を整理したい場合は、『自費出版と商業出版の違いとは?費用・流通・契約を初心者向けに徹底解説』もチェックしてみてください。
絵本の制作費用の内訳:印刷・製本・デザイン・イラスト料など
絵本制作の費用は、大きく分けて「制作費」と「印刷費」に分かれます。
制作費には、シナリオ構成、イラスト制作、デザイン、編集、校正などが含まれます。
特に絵本はフルカラーが基本のため、イラスト費用の割合が高くなります。
イラストを自作する場合はコストを抑えられますが、外注する場合は1ページあたり5,000円〜20,000円程度が相場です。
印刷費は、ページ数・サイズ・部数・紙質によって変動します。
一般的にA4やB5サイズで20〜30ページ程度の絵本をフルカラー印刷する場合、100部で10万円前後からが目安です。
また、製本方法(中綴じ・上製本)によっても単価が変わるため、目的に合わせた仕様選びが重要になります。
費用目安の相場:紙の絵本と電子絵本の違い
「紙の絵本を自費出版する場合、印刷・製本・配送などのコストが発生するため、全体で20万〜50万円程度になる例もあります。実際の金額は仕様や部数、依頼先によって大きく変わるため、各社の料金表と見積もりで確認してください。」
「一方、電子書籍(Kindleなど)で出版する場合は、印刷や在庫が不要なため、データ制作費のみで済むケースもあります。制作内容や外注範囲によりますが、数万円台から始められる例もあり、正確な費用は各社の見積もりと公式ヘルプ要確認です。」
ただし、電子書籍でもイラストやデザインに外注費がかかる場合があります。
また、紙の絵本は「物としての存在感」やプレゼント向きという強みがありますが、販売ルートが限られる点に注意が必要です。
電子書籍は低コスト・在庫ゼロで発信できる一方で、閲覧環境によって色味が異なる場合があるなど、制作面での工夫も求められます。
実際の出版目的やターゲット層によって、最適な形を選ぶのが成功のポイントです。
紙と電子それぞれの特徴や出版の流れを全体から整理したい方は、『自費出版で絵本を出す方法とは?紙と電子の選び方を徹底解説』もあわせて読んでおくと判断しやすくなります
出版方法別の費用比較と特徴
絵本を自費出版する際、出版方法の選び方で費用は大きく変わります。
ここでは、「紙の絵本」「電子書籍」「オンデマンド印刷」の3つの方法について、それぞれの特徴と注意点を整理しておきましょう。
経験者の立場から言えば、出版方法を誤って選ぶと、予算だけでなく完成後の販売方法にも影響が出ます。
目的(贈答用・販売用・作品集など)に合わせて選ぶのが成功の近道です。
紙の絵本を自費出版する場合の費用と注意点
紙の絵本は、最も伝統的で「形に残る満足感」がある出版方法です。
印刷・製本・流通まで含めると、全体で20万〜50万円程度かかるケースが一般的です。
内訳としては、印刷費が最も大きな割合を占め、部数を増やすほど単価は下がりますが、在庫リスクも増します。
特に初めての方が見落としがちなのが、「見本用」や「修正版」の再印刷費用です。
一度に全数印刷する前に、必ず少部数でのテスト印刷を行うと安心です。
また、印刷所によって紙質や発色の仕上がりが異なるため、見積もり比較は必須です。
公式サイトでは「フルカラー対応」と書かれていても、実際は光沢紙かマット紙で発色が変わるなど、実務上の差があります。
さらに、ISBNの取得や書店流通を希望する場合は、別途費用が発生します。
「販売も視野に入れたいのか」「プレゼントとして作りたいのか」で、最適なプランが異なる点を理解しておきましょう。
電子書籍(Kindle・オンデマンド)で出版する場合の費用と流れ
電子書籍で絵本を出版する場合、印刷や在庫が不要なため、初期費用を大幅に抑えられます。
データ制作費や表紙デザイン、レイアウト調整などを含めても、3万〜10万円程度で始めることが可能です。
Kindleダイレクトパブリッシング(KDP)では、出版費用そのものは無料で、売上から手数料を引いた分が収益として入ります。
ただし、フルカラー絵本の場合、ファイル容量や画像解像度に注意が必要です。
大きな画像を多用するとファイルサイズが上がり、端末での表示速度に影響することがあります。
電子書籍の利点は、印刷費が不要で修正も簡単にできる点です。
ただし、販売後の「色味の見え方」がデバイスによって異なるため、意図した色調を完全に再現するのは難しい場合があります。
私の経験では、特に暗い背景のページでは、タブレットとスマホで印象が変わることがありました。
色校正を意識した制作データを作ることで、仕上がりを安定させられます。
電子書籍まわりの基本仕様やKDPの全体像を押さえておきたい方は、『Kindle出版とは?初心者が無料で始める電子書籍の基本と仕組みを徹底解説』を先に読んでおくと、この章の理解がスムーズになります。
オンデマンド印刷を使うとどう変わる?小ロット出版のコスト感
オンデマンド印刷とは、必要な部数だけを印刷できる仕組みです。
通常の大量印刷に比べて単価は高めですが、在庫を抱えずに済むのが最大の利点です。
10〜50部程度の小ロット出版を検討する方には、非常に相性の良い方法といえます。
たとえば、AmazonのKDPでは「ペーパーバック出版(オンデマンド印刷)」に対応しており、注文が入った分だけ印刷・発送されます。
これにより、在庫リスクがなく、初期費用もほぼ不要で出版できます。
一方で、単価がやや高くなるため、大量配布やイベント販売には向きません。
また、紙質や綴じ方の選択肢が限られている点も確認が必要です。
実際に使ってみると、「紙の質感を重視したい人」には物足りないと感じることもあります。
ですが、試作品や個人の記録用としては非常に便利です。
「まず形にしたい」「反応を見てから増刷したい」という人におすすめできる出版方法です。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
費用を抑えるコツと選び方のポイント
絵本の自費出版は「思っていたより高い」と感じる人も多いですが、実は工夫次第でかなり費用を抑えることができます。
特に、印刷仕様や外注費の調整、見積もりの取り方を工夫することで、仕上がりの質を保ちながらコストを下げることが可能です。
ここでは、制作経験者の視点から、初心者でも無理なく実践できる節約のポイントを紹介します。
印刷仕様でコストを調整する方法(ページ数・紙質・部数)
印刷費を抑える一番のポイントは「仕様を見直すこと」です。
絵本はページ数が増えるほど紙の使用量が増え、製本工程も複雑になります。
特に30ページを超えると印刷単価が上がる傾向にあるため、内容を整理してページ数を抑えるのが効果的です。
また、紙質を選ぶ際は「高級紙=良い仕上がり」と思われがちですが、実際は作品のテイストに合う紙を選ぶことが大切です。
例えば、温かみのあるタッチならマット系の紙でも十分魅力的に仕上がります。
部数についても「多く刷るほど単価が下がる」と言われますが、初版から大量に印刷すると在庫を抱えるリスクがあります。
最初は50〜100部ほどの小ロットで印刷し、反応を見てから増刷するのが安全です。
イラスト・デザインの外注費を抑えるポイント
絵本制作で意外に大きなコストになるのが、イラストとデザインの外注費です。
特にプロのイラストレーターに依頼する場合、1枚あたり数千円から数万円と幅があります。
ここでのポイントは「依頼内容を明確に伝えること」です。
「ざっくりとしたイメージで任せる」と修正が増え、その分コストもかかります。
最初に構成案やカラーパレットを共有し、完成イメージを具体的に伝えるだけでも大きく違います。
また、クラウドソーシングを活用すれば、個人クリエイターに比較的手頃な価格で依頼することも可能です。
ただし、著作権の扱いには注意が必要です。
「商用利用OK」「クレジット表記不要」など、利用条件を必ず確認してから契約しましょう。
過去には、著作権の範囲を誤解してトラブルになるケースもあります。
そのため、使用範囲や納品形式を明記しておくのが安全です。
見積もりを比較する際の注意点と確認項目
見積もりを取る際は、金額だけでなく「何が含まれているか」を細かく確認することが大切です。
たとえば「印刷費」と記載されていても、データチェック費や色校正が別料金になっている場合があります。
複数社に依頼するときは、同じ仕様(ページ数・サイズ・紙質)で比較するのが鉄則です。
そうしないと、安く見えても実際には仕上がりに差が出ることがあります。
また、公式サイトのシミュレーター見積もりは参考になりますが、特殊加工(箔押しやPP加工など)を加えると一気に価格が変わることも。
実際に私が依頼したときも、初回見積もりより2割ほど上がった経験があります。
担当者に「最終的な総額」と「納期」を確認してから契約するのが安心です。
特に初めての方は、メールや電話で質問しても丁寧に答えてくれる業者を選ぶと、後悔が少ないでしょう。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
実際の事例から見る絵本自費出版の費用感と工夫
実際に絵本を自費出版した人の体験から学べることは多いです。
「いくらかかったのか」「どんな工夫で費用を抑えたのか」「販売までどうつなげたのか」など、リアルな数字や流れを知ることで、自分の出版計画の参考になります。
ここでは、個人での制作事例と、副業・クリエイター活動としての出版事例の2つを紹介します。
個人制作の事例:少部数での出版と販売までの流れ
個人で絵本を作ったある方のケースでは、最初に「家族や友人に贈ること」を目的に制作が始まりました。
フルカラー20ページの絵本を100部印刷し、費用は約25万円ほど。
印刷所の見積もりを複数比較し、本文の紙質をマット紙に変更してコストを下げたそうです。
仕上がりの質を保ちながら価格を調整する、典型的な成功パターンです。
印刷が完成した後は、地元の小さな書店に直接交渉して委託販売をスタート。
最初は10冊ほどしか置いてもらえなかったものの、口コミやSNSで少しずつ反応が広がり、追加発注が入るようになりました。
ここでのポイントは「販売を急がず、作品を丁寧に育てる姿勢」です。
在庫リスクを避けるため、初回印刷を少部数に抑えたのも賢い判断でした。
公式情報では「流通登録すれば全国で販売可能」とされていますが、実際は宣伝や販促を自分で行う必要があります。
販売経路を地元中心に絞ったことで、無理のない形で出版を楽しめた好例です。
副業・クリエイター活動としての絵本出版事例
副業として絵本を出版する人も増えています。
特に最近は、Kindleの電子書籍やオンデマンド印刷を活用するケースが多いです。
印刷費が不要なため、初期費用3万〜10万円ほどで始められるのが特徴です。
あるデザイナーの方は、自分のイラストを活かして絵本を電子出版し、SNSで販売を宣伝しました。
販売価格を500〜700円に設定し、1冊あたりの印税は35〜70%ほど。
最初の月に数十冊が売れ、「作品づくりが副収入につながった」と話しています。
特に、絵本のテーマを「子育て」「季節」「動物」など共感されやすい内容に絞ったのがポイントです。
一方で、よくある失敗は「制作段階での自己満足」です。
電子出版では印刷の制約がないため、色味や文字サイズを軽視しがちですが、スマホやタブレットで読むユーザーにとっては見づらくなることがあります。
出版前に複数の端末で確認しておくと、後から修正する手間を減らせます。
副業として成功している人の多くは、1冊で終わらせず「シリーズ化」や「関連グッズ展開」へ広げています。
これにより、継続的に作品を発信でき、ファンとの関係も築けるのです。
「1冊出して終わり」ではなく、「次につながる出版設計」を意識することで、収益と創作活動の両立がしやすくなります。
自費出版で失敗しないための注意点
絵本の自費出版は、夢を形にできる素敵な体験ですが、その一方で注意を怠ると「思っていたよりお金がかかった」「契約内容がよく分からなかった」といったトラブルに発展することもあります。
ここでは、特に多い失敗例とその防ぎ方を解説します。
高額プラン・宣伝費のトラブルに注意
自費出版の見積もりでよくあるのが、最初は数十万円と提示されても、途中で宣伝費やデザインオプションが追加され、結果的に倍近くの費用になってしまうケースです。
「全国の書店に並べます」「テレビ取材を紹介します」といった営業トークには慎重になるべきです。
実際には、そうした広報活動が本当に行われる保証はなく、費用対効果も不透明なことが多いからです。
また、出版社や代行サービスの中には「プロモーションプラン」として高額なオプションを勧めるところもあります。
公式サイト上では魅力的に見えても、実際は書店に1〜2冊が短期間だけ並ぶだけのケースもあります。
もし販路拡大を目的とするなら、SNS発信やイベント出展など、自分でできる範囲の宣伝を工夫した方が効果的です。
一度契約するとキャンセル料が発生することもあるため、見積書や契約内容をよく読み、「どの費用が必須で、どこからがオプションか」を必ず確認しておきましょう。
経験上、良心的な業者は見積もり段階で細かい内訳を出してくれます。
不明点をはぐらかすような対応があれば、契約は保留にするのが安全です。
契約・権利・印税条件の確認ポイント
もう一つ多いトラブルが、著作権や印税の扱いに関するものです。
自費出版では、基本的に著作権は作者本人に残るのが一般的ですが、中には「出版会社が販売権を独占する」ような契約条項が含まれている場合もあります。
後から「他サイトで販売したい」と思っても、契約上できないことがあるのです。
印税率も確認が必要です。
「紙の書籍の印税率は、契約形態によって大きく異なります。一般的な商業出版では販売価格の5〜10%程度とされることもありますが、自費出版では印刷や流通コストを差し引いた後の利益をもとに計算されるケースもあります。具体的な率や計算方法は契約書と公式ヘルプ要確認です。」
つまり、見かけの印税率が高くても、実際の収益は思ったより少ないことがあるということです。
契約書に「印税計算の基準」が記載されているかを必ず確認しましょう。
電子書籍の印税計算やロイヤリティ率の違いを具体的に確認したい方は、『Kindle出版のロイヤリティとは?70%と35%の違いと条件を徹底解説』もセットで読んでおくと安心です。
「また、電子書籍出版(Kindleなど)の場合、印税率は35%または70%などのプランが用意されていますが、適用条件や仕様は変更される可能性があります。具体的な条件は必ず最新の公式ヘルプを確認してください。(公式ヘルプ要確認)」
例えば、70%を受け取るには価格設定を一定範囲内にする必要があるなど、公式ガイドラインに従う必要があります。
公式ヘルプを確認しつつ、出版社経由ではなく自分で管理したい人は、KDPのようなプラットフォームを選ぶのも一つの方法です。
信頼できる業者は、契約書やガイドをすべて公開しており、問い合わせにも丁寧に対応してくれます。
「安いから」「早いから」ではなく、「説明が明確で納得できるかどうか」を基準に判断することが、安心して出版するための第一歩です。
まとめ:絵本の自費出版費用は「目的×仕様」で決まる
絵本の自費出版は、かける金額よりも「どんな目的で出すか」によって最適な形が変わります。
贈り物や作品集として残したいなら少部数印刷、販売を目指すなら電子書籍やオンデマンド出版が向いています。
費用のすべては、仕様の選び方と目的の明確さでコントロールできるということを覚えておきましょう。
印刷やデザインにこだわるほど費用は上がりますが、「必要な部分にだけお金をかける」ことで満足度の高い仕上がりにできます。
最後に、見積もりは必ず複数社に取り、契約内容を一つずつ確認すること。
焦らず比較しながら、自分の想いと予算に合う方法を選ぶことが、後悔のない出版につながります。
夢を形にする絵本づくりは、慎重さと工夫次第で十分実現できるのです。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。