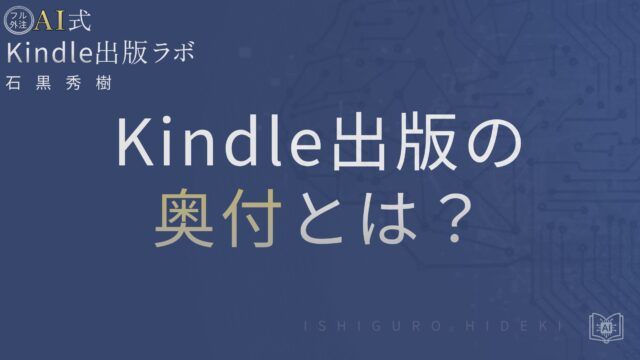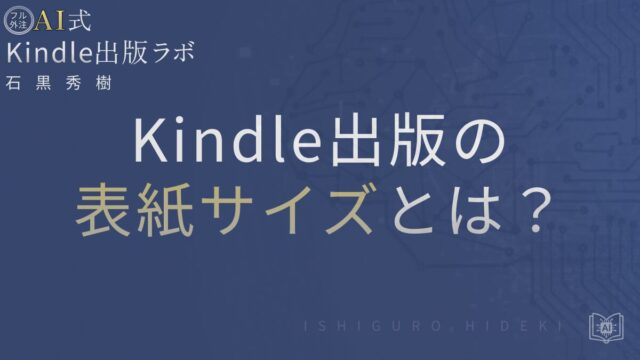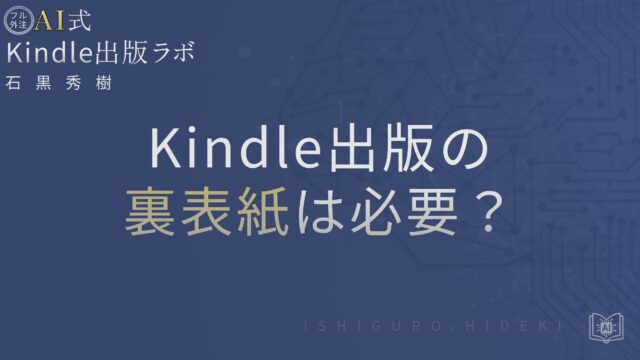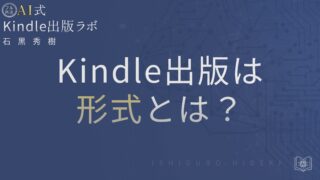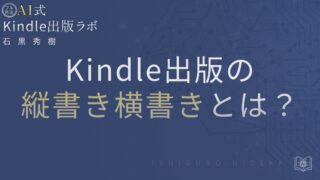Kindle出版の挿絵サイズとは?スマホ表示に最適な縦横ピクセル数を徹底解説
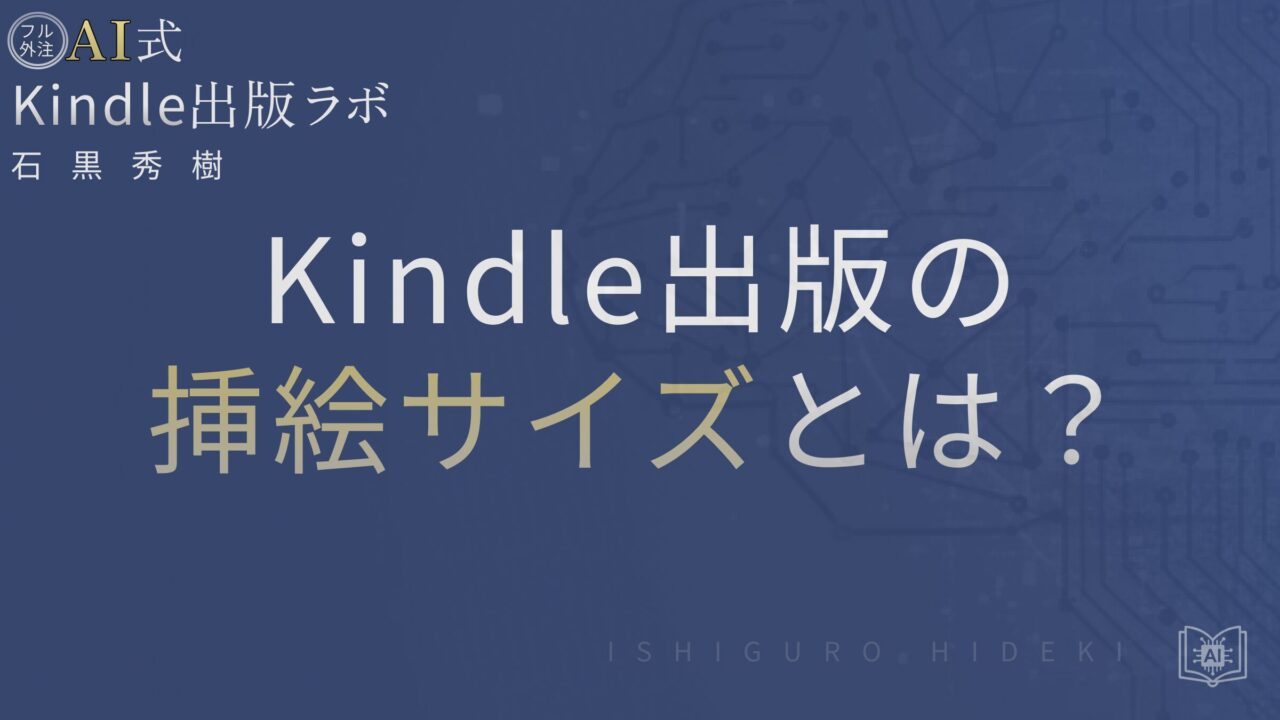
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版で挿絵を入れるとき、多くの人が最初につまずくのが「画像サイズって、結局どう設定すればいいの?」という点です。
私自身も初期の頃、画像がぼやけたり、スマホで見たときに余白だらけになったりして、何度もやり直した経験があります。
この記事では、KDP(Kindle ダイレクト・パブリッシング)の公式仕様に基づきつつ、実際の出版現場でよくある落とし穴やコツを交えながら、初心者でも迷わず設定できるように丁寧に解説していきます。
リフロー型の電子書籍を前提とし、特にスマホ閲覧での見え方を重視して説明します。
公式と現場感に少しズレがある部分もあるので、そのあたりも正直にお話ししますね。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版で挿絵を入れるときの画像サイズは?基本の考え方を解説
目次
Kindle出版で挿絵を設定するときに最初に押さえておきたいのは、リフロー型と固定レイアウト型の違いです。
日本のKindle本では多くの場合、文章を中心にしたリフロー型が使われます。
リフロー型では、読者の端末やフォントサイズによって本文のレイアウトが自動で変わるため、紙の本のようにページサイズを固定してデザインすることはありません。
この特性を理解しておかないと、「画像をピクセル数で設定したのに、表示が崩れた」というトラブルが起きやすくなります。
形式選びの前提は『Kindle出版の形式とは?リフロー型・固定レイアウト・対応ファイル形式を徹底解説』で整理しておくと迷いません。
リフロー型では横幅は自動調整される
リフロー型の電子書籍では、横幅は端末の画面サイズに合わせて自動的に調整されます。
つまり、こちらで「横幅を何pxに固定する」という考え方は基本的に不要です。
画像を挿入すれば、画面の横幅に合わせて拡大・縮小されて表示されます。
特にスマホでは、ほぼすべての画像が画面幅いっぱいに広がるため、「横サイズを厳密に合わせる」というよりは、解像度が十分であるかどうかを意識する方が重要です。
経験上、横幅が小さすぎる画像(例:600px程度)を挿入すると、画面幅いっぱいに拡大された際にぼやけたり、文字がつぶれることがあります。
そのため、横幅は最低でも1200px以上を確保しておくと安心です。
スマホ閲覧では縦サイズが表示を左右する
横幅が自動調整される一方で、挿絵の「縦サイズ」は読者の閲覧体験に大きく影響します。
縦が短すぎる画像を挿入すると、スマホで表示したときに上下に余白が多く出てしまい、画面がスカスカに見えてしまいます。
逆に、縦長すぎると1画面に収まらず、読者がスクロールしながら見なければならなくなるため、読みづらくなります。
実務的には、縦サイズを1800〜2400px程度に設定すると、スマホの画面にちょうどよく収まることが多いです。
このサイズ感を目安にしておくと、余白や拡大縮小の不自然さを避けられます。
なお、端末によって見え方に差があるため、プレビュー機能を使って複数端末で確認しておくと安心です。
PPI(解像度)とピクセルサイズの関係を理解しよう
画像の「解像度」を調べると、「PPI(pixels per inch)」という言葉を目にすると思います。
これは1インチあたりに何ピクセルあるかを示す数値で、高精細表示には表示サイズに見合う解像度(例:300ppi相当)が目安です。
最新の推奨値は公式ヘルプ要確認。
たとえば、本文幅を4インチ分のサイズで表示したい場合は、4×300=1200pxが必要になる、という計算です。
ただし、リフロー型では実寸(インチ)を厳密に指定できるわけではないので、実務的には「横幅1200px以上」「縦1800〜2400px前後」を目安にしておけば、ほとんどのケースに対応できます。
PPIはあくまで画質の基準として理解しておけば十分です。
また、Wordなどの画像設定で自動圧縮がオンになっていると、せっかく高解像度で用意した画像でも実際の出力時に劣化してしまうことがあります。
後の章で詳しく解説しますが、この設定は最初にオフにしておくのがおすすめです。
Kindle出版における挿絵の推奨サイズ(縦・横)の目安
挿絵をきれいに見せるためには、なんとなくの感覚ではなく、ある程度の目安を持って画像サイズを設定することが大切です。
特にスマホ表示を基準に考えると、縦サイズと横サイズのバランスが仕上がりに大きく影響します。
KDP公式でも「表示サイズで300PPIを推奨」とされていますが、実際の出版作業では「縦横ピクセル数の目安」を先に押さえておくと迷いが減ります。
ここでは、リフロー型の電子書籍で一般的によく使われるサイズの目安を、用途別にわかりやすく解説します。
縦サイズは1800〜2400pxが目安(スマホ全画面にフィット)
スマホでの閲覧を想定する場合、最も重要になるのが縦サイズです。
縦が短すぎると上下に余白が出てしまい、ページがスカスカに見える原因になります。
逆に縦長すぎると、1枚の挿絵が1画面に収まらず、読者がスクロールしながら見ることになり、テンポが悪くなることがあります。
そのため、縦1800〜2400px前後を目安に設定しておくと、多くのスマホ端末でバランスよく表示されます。
私も最初は縦1500px程度で作ってしまい、プレビューで余白だらけになって作り直したことがありました。
端末によって微妙に見え方は異なるため、KDPのプレビュー機能を使って複数端末で確認するのがおすすめです。
横サイズは1200px以上を基本に、本文幅に合わせる
横幅は、端末に合わせて自動的に調整されるため、厳密に「このピクセルでなければならない」という決まりはありません。
ただし、元画像の解像度が不足していると、拡大表示されたときにぼやけたり、文字がつぶれたりする原因になります。
そのため、横幅は最低でも1200px以上で作成しておくと安心です。
実際、横幅が800px程度の画像を使ったときは、スマホで拡大されて文字が潰れてしまい、再提出になったこともありました。
横サイズは本文のレイアウトに合わせるだけでなく、画質面でも妥協しないことがポイントです。
文字入りの図版は画面幅の80%で読みやすさを確保
グラフや図表など、文字や細かい情報が含まれる画像は、ただ大きければいいというものではありません。
全幅いっぱいに表示すると見やすい一方で、文字が小さすぎたり、余白がなくなって詰まった印象になることがあります。
文字入り画像は読みやすさを優先し、本文幅をやや狭めに配置するのが実務上は安全です(例:全幅ではなく適度な余白を確保)。
数値は公式ヘルプ要確認。
実務的にも、横幅1000〜1300px前後で作っておくと、スマホ画面でも無理なく文字が読めるサイズ感になります。
細かい文字がある場合は、なるべく拡大しなくても読めるように調整しておきましょう。
図版の見やすさと活用例は『Kindle出版のA+コンテンツとは?作成手順・活用法・注意点を初心者向けに徹底解説』も参考になります。
小さな飾り画像やサムネは800px以上を目安に
章の区切りに入れるイラストや、デザイン的な飾り画像などは、大きすぎる必要はありません。
ただし、あまりに小さいとスマホ表示でぼやけるため、最低でも横幅800px以上を確保しておくのがおすすめです。
このサイズであれば、拡大されても画質の劣化が目立ちにくく、軽量で使い勝手も良いです。
用途に応じてサイズを変えることで、見やすさとデータ容量のバランスを取ることができます。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
Word・画像ファイル形式・解像度設定の実務ポイント
画像サイズの目安を決めたあとは、実際に原稿を作成するときの設定がとても重要です。
ここを疎かにすると、どれだけ高解像度で画像を用意しても、最終的なKDPアップロード時に画質が劣化したり、思わぬ不具合が起きることがあります。
特にWordで原稿を作成している人は、初期設定のままでは「勝手に画像が圧縮される」仕様になっているため、必ずチェックが必要です。
さらに、画像のファイル形式やSVGの扱いにも注意点があります。
ここでは、実際の出版作業で押さえておくべき基本設定と、公式仕様とのズレを踏まえた実務上のポイントを紹介します。
Wordの画像圧縮をオフにして劣化を防ぐ
Wordには、挿入した画像を自動的に圧縮してファイルサイズを軽くする機能があります。
一見便利そうですが、この設定をオンのままにしておくと、せっかく高解像度で用意した画像が出力時に劣化してしまうことがあります。
特に挿絵内の文字がつぶれたり、線画がにじむといったトラブルは、この設定が原因になっているケースが多いです。
実際、私も最初の頃は気づかずに提出し、プレビューで画像がぼやけてしまい、すべて差し替えになったことがありました。
対策は簡単で、Wordの「ファイル」→「オプション」→「詳細設定」から「画像のサイズと画質」の項目を開き、「ファイル内の画像を圧縮しない」にチェックを入れるだけです。
この一手間で画質の劣化を大幅に防げるので、原稿を作り始める前に必ず設定しておきましょう。
JPEGは写真、PNGは文字や線画・図版に向いている
画像形式の選択も画質とデータ容量のバランスに直結します。
基本的に、写真やグラデーションのある画像はJPEG、文字や線画・図版はPNGを使うのがベストです。
JPEGはファイルサイズを抑えつつ写真をきれいに表示できる形式ですが、圧縮時に細かい文字や線がにじむことがあります。
一方、PNGは非圧縮で、線や文字をくっきりと表示できるため、表や注釈付きの図版などに向いています。
ただし、PNGはファイルサイズが大きくなりやすいので、挿絵が大量にある場合は容量上限に注意が必要です。
実務的には、図版はPNG、写真はJPEGと使い分けるだけで、ほとんどのケースをカバーできます。
SVGはリフロー型で非推奨(KDP公式で注意喚起)
SVG(ベクター形式)は拡大・縮小しても画質が落ちない理想的な形式に見えますが、KDPのリフロー型では注意が必要です。
公式ヘルプでも「SVGはサポート対象ではあるが、Kindle Previewerや実機で表示崩れが起こる場合がある」と明記されています。
特に、SVGは端末やレンダリング差で表示が不安定な場合があります。
使用時は実機検証のうえ、問題があればPNG/JPEGに書き出すのが安全です(公式ヘルプ要確認)。
私も試しにSVGを使ってみたことがありますが、Previewerでは正常に見えても、実機のKindle端末で文字が消えるという現象が起きました。
どうしてもSVGを使いたい場合は、一度PNGに書き出してから挿入する方法が安全です。
リフロー型ではSVGのメリットを活かしきれないため、現場ではPNGまたはJPEGで統一するのが無難です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
挿絵サイズでよくある失敗・注意点と対策
挿絵サイズの設定は、数字を守ればそれで終わりというものではありません。
実際の出版現場では、数値を理解していても「プレビューで見たら思っていたのと違った」ということが少なくありません。
ここでは、初心者が特につまずきやすい失敗パターンと、その対策を具体的に紹介します。
すべて私自身や受講生の方が実際に経験した例なので、「あるある」と思う方も多いはずです。
縦が短すぎて余白が出るケース
スマホで挿絵を見たときに「上下に白い余白が出て、画面がスカスカに見える」というのは非常によくある失敗です。
原因は、縦サイズが小さすぎることにあります。
本文の横幅は端末に合わせて自動調整されますが、縦のサイズはそのまま反映されるため、縦が短いと空白部分が目立ってしまうのです。
私も初期の頃、縦1500pxで画像を作ってしまい、プレビューを見たら余白だらけになって修正する羽目になりました。
対策はシンプルで、縦1800〜2400px前後を目安に画像を用意することです。
このサイズなら多くのスマホ端末でちょうどよく表示され、余白が不自然に目立つこともありません。
横や解像度が不足してボケるケース
もうひとつ多いのが、「画像が横に広がって表示されるときにボケてしまう」というケースです。
これは元画像の横幅や解像度が不足していることが原因です。
特に、Wordで画像を挿入したあとに圧縮がかかってしまうと、見た目では気づかなくても出力時に劣化することがあります。
小さい画像(例:横800px)を使うと、スマホで拡大表示されたときに文字や線が潰れることが多いです。
私も一度、画像の横幅を甘く見ていたせいで、表の文字が全部滲んでしまい、やり直しになりました。
対策としては、横幅は最低1200px以上を確保し、Wordの画像圧縮をオフにしておくことが基本です。
プレビューで実機チェックをして、拡大しても文字が潰れないか確認する習慣をつけると安心です。
大きすぎる画像は容量過多や処理エラーの原因になる
「高画質にしたいから」といって、必要以上に大きな画像を使うのも落とし穴です。
ファイルサイズが大きくなりすぎると、KDPのアップロード時や端末での表示時に処理が重くなり、エラーや表示崩れの原因になります。
特に、PNGで大量の図版を使っている場合は要注意です。
実務的には、容量が過大だと処理が重くなるため、画質と総容量のバランスを最適化してください。
具体閾値は端末・構成によるため、公式ヘルプ要確認。
高解像度にすることと、データ容量を適切に抑えることのバランスが大切です。
画像圧縮ツールや書き出し時の設定を活用すると、画質を保ちながら容量を減らすことができます。
紙版の体裁や画像まわりの考え方は『Kindle出版の裏表紙は必要?電子と紙の違い・作成ルールを徹底解説』で詳しく解説しています。
固定レイアウトの場合のサイズ設定(補足)
固定レイアウトは、リフロー型とは異なり、ページ全体のデザインを固定して配置する形式です。
絵本や写真集などでよく使われます。
この場合は、ページ全体を1枚の画像として扱うケースも多く、300PPI以上の高解像度が推奨されています。
ただし、固定レイアウトは用途・要件が限定されるため、採用時は対応端末や要件を公式ヘルプで必ず確認してください。
日本向けではリフロー型が主流です。
固定レイアウトを使う場合は、KDP公式のガイドを必ず確認し、対応端末や要件を事前に把握しておくことが重要です。
電子と紙での要件差は『Kindle出版でISBNは必要?電子書籍とペーパーバックの違いを徹底解説』であわせて確認してください。
まとめ:Kindle出版の挿絵サイズは「縦重視+適正解像度」で迷わない
挿絵サイズで迷ったときは、複雑に考えるよりも、まず「縦は1800〜2400px、横は1200px以上」という基本ラインを押さえることが大切です。
そこに、画像形式の使い分け(JPEGとPNG)や、Wordの圧縮設定オフといった実務的な工夫を組み合わせることで、見栄えと処理の安定性を両立できます。
公式の推奨はあくまで基準値なので、最終的にはプレビューや実機での確認が欠かせません。
細かいテクニックよりも、基本を正確に押さえて着実に仕上げることが、Kindle出版では一番の近道です。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。