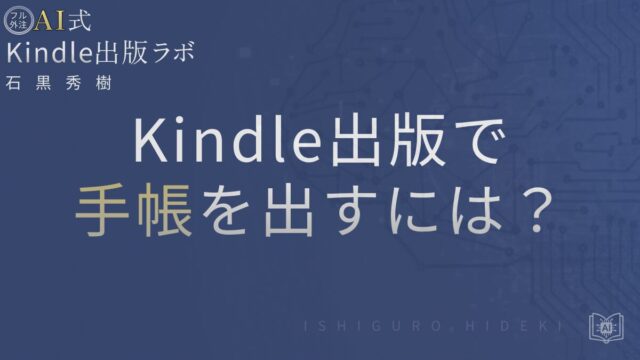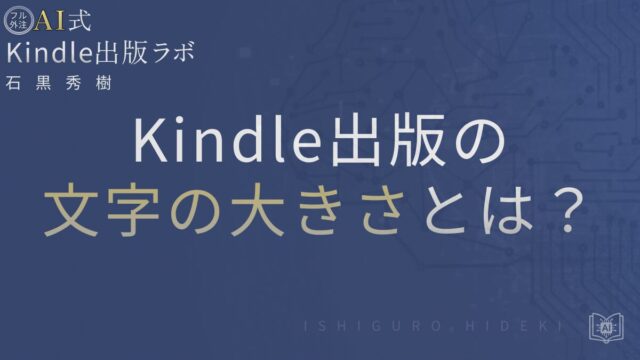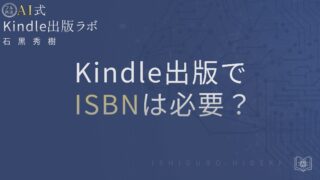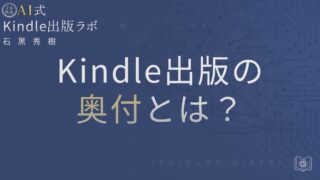Kindle出版の裏表紙は必要?電子と紙の違い・作成ルールを徹底解説
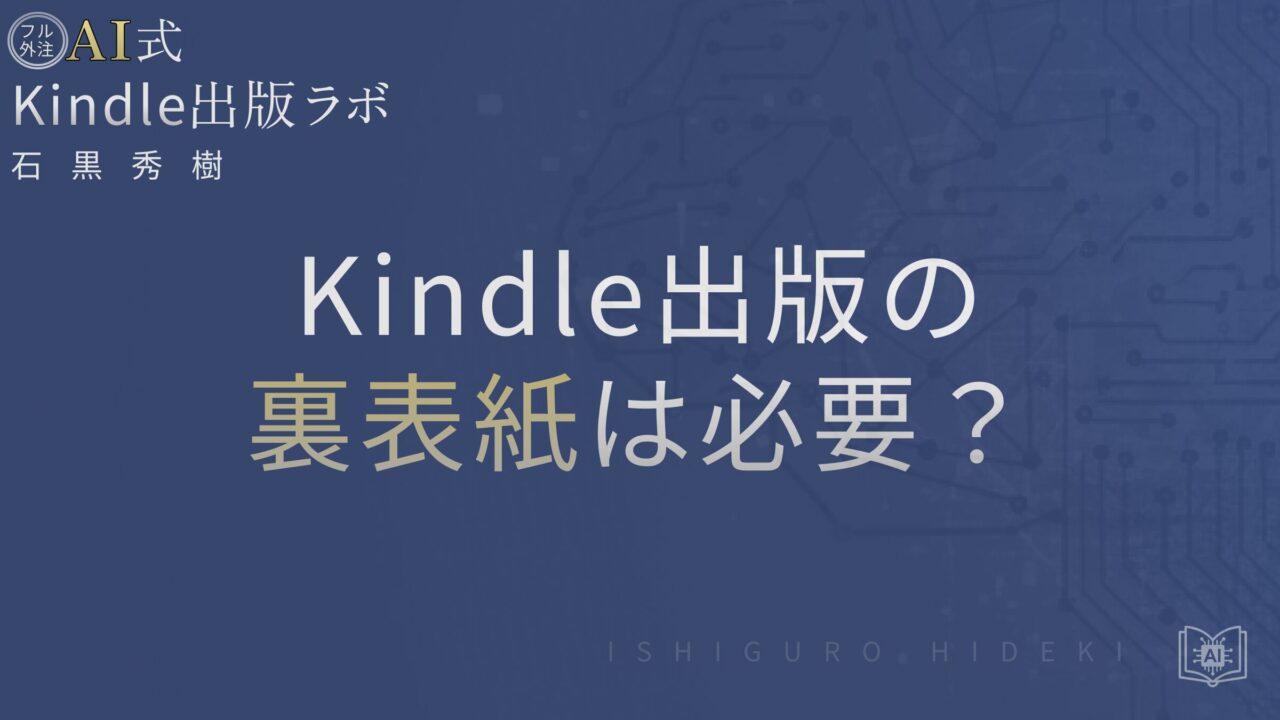
のべ600名以上・累計5,000冊以上の出版を支援してきた石黒秀樹が解説します。
Kindle出版を始めるとき、多くの方が最初に迷うのが「裏表紙って必要なの?」という点です。
電子書籍と紙の本では仕組みが大きく異なり、この違いを理解していないとカバー画像の入稿で差し戻しになるなど、思わぬ手戻りが発生します。
私自身、初めてペーパーバックを出したときに「表紙だけでいい」と思い込み、KDPから修正依頼が来て慌てた経験があります。
この記事では、日本のAmazon KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)における裏表紙の扱いについて、初心者にもわかりやすく解説していきます。
電子書籍・ペーパーバックそれぞれの違いや、誤解しやすいポイントもあわせて押さえておきましょう。
🎥 1分でわかる解説動画はこちら
↓この動画では、この記事のテーマを“1分で理解できるように”まとめています。
実際の流れを映像で確認したあと、詳しい手順や注意点は本文で解説しています。
動画では全体の流れを簡単にまとめています。
さらに実践に役立つ情報や具体的な成功事例は、
下のフォームから無料メルマガでお届けしています。
▶ 制作の具体的な進め方を知りたい方はこちらからチェックできます:
制作ノウハウ の記事一覧
出版作業を「自分で」やる時代は終わりです📘
AI×外注で、時間も労力もかけずにKindle本を量産する仕組みをまとめた
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を無料プレゼント中👇
Kindle出版の「裏表紙」は必要?初心者が最初に知っておくべき基本
目次
Kindle出版で「裏表紙が必要かどうか」は、電子書籍とペーパーバック(紙の本)でルールが異なります。
まずはこの前提をしっかり理解しておくと、余計な作業やトラブルを防げます。
特に電子書籍しか出さない場合は、「裏表紙のことは一旦考えなくていい」ケースも多いのです。
電子書籍では裏表紙は不要|表紙1枚だけでOKな理由
Kindleの電子書籍では、裏表紙という概念がそもそも存在しません。
KDPの仕様上、電子書籍の表紙は1枚の画像(JPEGまたはTIFF形式)をアップロードするだけで完結します。
読者がKindle端末やアプリで本を開くと、その1枚が表紙として表示されます。
紙の本のように裏面や背表紙をつけるスペースはなく、裏表紙を別で作っても使われることはありません。
また、裏表紙に相当する情報(著者紹介やあらすじ)は、KDPの管理画面で入力する「商品説明文」や、A+コンテンツを使って商品ページ上で補うのが一般的です。
ここを勘違いして裏表紙を作ってしまうと、余計な作業になるだけでなく、ファイル形式が違って入稿時にエラーになるケースも見られます。
ペーパーバックでは裏表紙が必須|構成と役割を理解しよう
一方で、ペーパーバック(紙の本)を出版する場合は裏表紙が必須です。
表紙・背表紙・裏表紙を1枚のPDFとしてまとめた「カバー」を作成し、KDPにアップロードする必要があります。
これは印刷用データのため、電子書籍のように1枚画像では対応できません。
裏表紙には、書籍の紹介文や著者プロフィール、QRコードなどを配置することが多く、いわば「本の顔」の裏側として重要な役割を持ちます。
また、裏表紙の一部にはKDPが自動的にバーコードを配置するため、事前にその領域を空けておく必要があります。
この仕様を知らずに裏表紙を作ると、バーコードと内容が重なってしまい、入稿時に差し戻しされることがよくあります。
「裏表紙が必要」と誤解しやすい初心者の落とし穴
初心者の方で特に多いのが、電子書籍だけを出す予定なのに「紙の本と同じように裏表紙も必要」と思い込んでしまうケースです。
私の受講生の中でも、電子書籍の原稿と一緒に裏表紙データまで準備して「どこにアップするんですか?」と聞かれることがよくあります。
これはKDPの公式ヘルプを一度も見ずに、紙の出版と混同してしまうことが原因です。
裏表紙はペーパーバック用であり、電子出版だけの場合は不要です。
逆にペーパーバックを出す場合は、裏表紙の仕様(サイズ・背幅・安全域など)を理解していないと、デザインのやり直しになるリスクがあります。
「電子と紙は別物」と割り切って考えるのが、最初のつまずきを防ぐコツです。
ペーパーバックの裏表紙に必要な要素と基本仕様
ペーパーバックを出版する場合、裏表紙はただの「飾り」ではありません。
KDPでは表表紙・背表紙・裏表紙を1枚のPDFとしてまとめた「カバー」データをアップロードする必要があります。
この仕様を理解していないと、デザインのやり直しや入稿エラーの原因になるため、基本をしっかり押さえておくことが大切です。
裏表紙・背表紙・表表紙を1枚にまとめる「カバーPDF」の基本
ペーパーバックは、表紙・背表紙・裏表紙を1枚のカバーPDFにまとめて入稿します。
KDPのカバーテンプレートを使えば、表・背・裏の配置ガイドやバーコード領域がひと目で分かります。
まずはテンプレをデザインツールに読み込み、上にレイヤーを重ねる形で編集すると失敗が少ないです。
サイズ・背幅・裁ち落とし・安全域などの基本ルール
背幅はページ数×用紙厚で決まり、本文確定後に算出するのが安全です(公式ヘルプ要確認)。
裁ち落としは約3.2mm。背景色・画像は外側まで伸ばし、白フチを防止します。
安全域の外に文字やロゴを置くと欠ける恐れ。文字はガイドの内側に収めましょう。
カバー画像のサイズや形式の詳細は『Kindle出版の画像設定とは?サイズ・形式・解像度を徹底解説』で確認できます。
バーコード位置と注意点|重要情報を重ねない
裏表紙の下部には、KDPが自動でバーコードを配置します。
バーコードの位置は判型によってやや異なりますが、テンプレート上にしっかり示されています。
初心者がよくやってしまうミスは、テンプレートを無視して裏面いっぱいに画像やテキストを配置してしまうことです。
そのまま入稿するとバーコードと重なってしまい、KDPから修正依頼が届きます。
この修正は再入稿扱いになるため、公開スケジュールが遅れる原因にもなります。
バーコード領域には文字・ロゴ・QRを配置しないでください。
ここに重なると審査NG→再入稿になり、公開が遅れます。テンプレ上で最終確認を。
裏表紙に入れる内容例(あらすじ・著者紹介など)と注意点
裏表紙には、書籍の魅力を簡潔に伝える要素を入れるのが一般的です。
代表的なのは「あらすじ」「著者プロフィール」「推薦文」「QRコード(公式サイトやLPへの誘導)」などです。
ただし、ここに詰め込みすぎるとデザインが窮屈になり、かえって読みづらくなります。
特に、あらすじや紹介文は、紙面で細かい文字を並べるよりも、商品ページで丁寧に説明する方が効果的な場合もあります。
また、刺激の強い内容や過激な表現は裏表紙でも審査対象になるため注意が必要です。
Amazonのコンテンツガイドラインに違反するような表現は避け、抽象的で適切な表現に置き換えましょう。
私の経験上、裏表紙は「必要最低限の情報+余白」を意識した方が、見た目もプロっぽく仕上がります。
出版作業に時間をかけたくない方へ⏳
AI+外注で、自分は手を動かさずに出版を進める仕組みを手に入れませんか?
『フル外注AI式Kindle出版 実践マニュアル』を今だけ無料で配布中です👇
よくあるトラブルと差し戻し事例|KDP審査でNGになるパターン
ペーパーバックの裏表紙は、公式のテンプレートに沿って正しく作成すれば問題なく通りますが、ちょっとした配置ミスや勘違いでKDPの審査に引っかかるケースが意外と多いです。
一度差し戻しになると、修正・再入稿・再審査という手間が発生し、出版スケジュールが数日〜1週間単位でズレることもあります。
ここでは、実際に初心者の方がよくつまずく具体的なNGパターンを紹介します。
KDP審査でのNG例や通過のコツは『Kindle出版の審査とは?落ちないための基準と通過ポイントを徹底解説』をご覧ください。
端ギリギリに文字を配置してしまうケース
もっとも多いのが、文字やロゴをカバーの端ギリギリに配置してしまうケースです。
KDPの印刷工程では微妙なズレが発生するため、「安全域」と呼ばれる余白をしっかり確保しないと、印刷時に文字が切れたり、端が見切れたりする可能性があります。
テンプレート上にはこの安全域が明確に線で示されていますが、慣れていないと「大丈夫だろう」と思って配置してしまいがちです。
私も最初の頃、タイトルロゴを裏表紙のギリギリまで広げてしまい、審査で引っかかって修正した経験があります。
安全域は見た目よりも広めに取るくらいがちょうどいいと感じています。
バーコード領域を塞いでしまう配置ミス
バーコードは裏表紙の下部に自動的に配置されます。
この領域にテキストや画像を重ねてしまうと、バーコードが正しく印刷されず審査でNGになります。
バーコード位置はテンプレート上にグレーのボックスで示されているので、ここには絶対に何も配置しないようにしましょう。
初心者の方にありがちなのは、背景画像をそのまま全面に敷いてしまい、重要な文字情報がバーコードと重なってしまうパターンです。
一見、デザイン的には綺麗に見えても、KDP側では機械的にバーコードが乗るため、少しでも被っていると差し戻されます。
テンプレートを重ねた状態でデザインを確認するクセをつけておくと安心です。
刺激の強い内容・表現が裏表紙に含まれているケース
裏表紙も本文や表紙と同様に、Amazonのコンテンツガイドラインの審査対象です。
過激な描写や刺激の強い文言が裏表紙に含まれていると、審査で差し戻される可能性があります。
特に初心者が見落としがちなのは、「裏表紙の紹介文やキャッチコピーの言葉遣い」です。
公式では明確な禁止表現のリストがあるわけではないため、抽象的・一般的な表現に置き換えるのが安全です。
私の経験でも、「本文では問題なかったのに裏表紙のキャッチコピーで引っかかった」というケースがありました。
裏表紙は目立つ位置なので、内容面でも慎重に確認することが大切です。
電子書籍でも裏表紙を作成してしまう勘違い
意外と多いのが、電子書籍の出版だけなのに裏表紙をわざわざ作ってしまうケースです。
Kindleの電子書籍には裏表紙という概念がなく、表紙1枚の画像をアップロードするだけで完結します。
裏表紙を作っても使われる場所はなく、アップロード時に形式が違うとエラーになることもあります。
この勘違いは「紙の出版のイメージ」に引っ張られている人に多い印象です。
電子書籍だけを出す場合は、裏表紙のデザインは不要と割り切る方が、余計な作業やトラブルを防げます。
もし将来的にペーパーバックも出す予定がある場合は、そのときに改めて仕様に沿って裏表紙を作れば十分です。
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。
裏表紙を作成する流れ|初心者でも失敗しない基本ステップ
ペーパーバックの裏表紙は、一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、正しい手順で進めれば初心者でも問題なく作成できます。
ここでは、最もシンプルで実践的な3つの方法を紹介します。
私自身も最初は独学で試行錯誤しましたが、テンプレートをうまく活用することでスムーズに仕上げられるようになりました。
出版全体の登録フローは『Kindle出版の登録手順とは?KDPアカウントから税務設定まで徹底解説』で詳しく紹介しています。
KDP公式のカバーテンプレートを使う方法
まずおすすめなのは、KDP公式の「カバーテンプレート」を使う方法です。
KDPのヘルプページにあるテンプレート作成ツールに、判型とページ数を入力すると、自動で背幅や裁ち落としを計算したテンプレートをダウンロードできます。
このテンプレートには、表・背・裏のレイアウトや安全域、バーコード領域などがガイドとして描かれており、初心者でも迷わず進められるのがメリットです。
テンプレートはPDFとPNGの両方が用意されています。
私はPNGをデザインツールに読み込んで、その上からレイヤーを重ねるようにデザインする方法をよく使っています。
これなら、どこに何を配置していいか一目でわかるので、余計なズレや配置ミスを防げます。
公式ツールは一見シンプルですが、精度は非常に高く、KDPの審査にもスムーズに通りやすいです。
画像編集ソフト・デザインツールで作る際の基本手順
次に、テンプレートを使ってデザインツールで実際に作業する流れを簡単に紹介します。
まずテンプレートを背景レイヤーとして配置し、表紙・背表紙・裏表紙の各エリアに要素を乗せていきます。
背景はカバー全体に広がるように設定し、文字やロゴは安全域の内側に収めるのが基本です。
裏表紙には紹介文や著者情報を入れることが多いですが、詰め込みすぎると見栄えが悪くなるため、余白を活かした配置を意識しましょう。
完成したらテンプレートのガイド部分を非表示にし、KDPの指定通りPDF形式で書き出します。
このとき、余白設定やカラープロファイル(CMYK/RGB)なども確認し、KDPの仕様に合わせることを忘れずに行いましょう。
テンプレートを使わず自作する場合の注意点
テンプレートを使わずに完全自作することも不可能ではありませんが、初心者にはおすすめしません。
というのも、背幅や裁ち落とし、安全域をすべて自分で計算・設定する必要があるからです。
特に背幅の誤差は数ミリでもズレると、印刷時に背の位置がずれて見栄えが崩れることがあります。
それでも自作する場合は、KDP公式ヘルプに記載されている数式(ページ数×用紙の厚さ)を参考に、背幅を正確に計算してください。
また、バーコード領域の確保や安全域の設定も必須です。
テンプレートを使うよりもチェック項目が多く、ミスのリスクも高くなるため、経験者向けの方法といえます。
まとめ|電子は不要、紙は正確な仕様に沿って裏表紙を作成しよう
Kindle電子書籍では裏表紙は不要ですが、ペーパーバックでは欠かせない要素です。
裏表紙の作成は「テンプレートを使う→ツールでデザイン→PDFで書き出す」という基本の流れを押さえれば、初心者でも十分対応できます。
特に、KDP公式テンプレートを活用することが差し戻し防止と時短のポイントです。
独自にデザインすることも可能ですが、まずは基本を正確に踏まえたうえで応用するのがおすすめです。
電子と紙の仕様の違いを理解し、無理なく進めていきましょう。
裏表紙で伝えきれない魅力を補うには『Kindle出版のA+コンテンツとは?作成手順・活用法・注意点を初心者向けに徹底解説』が参考になります。
【著者:石黒秀樹のプロフィール】
Kindle出版サポート歴5年。
これまでに、のべ600名以上の出版をサポートし、
サポートメンバー全体で累計5,000冊以上の出版実績があります。(2025年時点)
フル外注とAI活用により、初心者でも安心して出版できる再現性の高いステップをお伝えしています。
───
【出版サポートを希望される方へ】
・「フル外注AI式Kindle出版実践マニュアル」の無料プレゼント
・Kindle出版をゼロから学べる動画を公式LINEで配信中
・悩み相談・最新アップデートも随時シェア
AI×外注で出版したい方向けに、限定動画や実践マニュアルも公開しています。